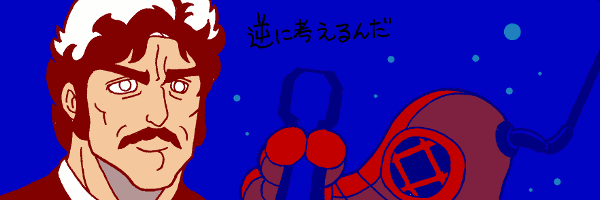|
買い物箱を引いて泳いでいる。 |
 |
様々な形のジェムを術式に当てはめながら作業を続ける。 武器を解体する特殊なもの等も含まれた、いつもより大きく複雑な術式。 |
 |
煩雑な作業に緊張しているようだ。 |
 |
「フォームチェンジ買うぞー」 |
 |
「バルキリーフォース」 |
 |
「メデューサフォース」 |
 |
「シルフィードフォース」 |
 |
「アルテミスフォース」 |
 |
「セイレーンフォース」 |
 |
「楓さんだー!」 |
 |
さらに新しい石を魔法陣に乗せるが |
 |
ふっと横を見て、もくずに石をごちゃっと渡した。 |
 |
「あたらしい仲間を紹介する」 |
 |
「マシナリーシルエットのえちぜんっち!」 |
 |
「ロボで子供とクラゲを連れている頼もしいやつだー」 |
 |
「つまり彼がいればロボと子供とクラゲは足りている!」 |
 |
「…なんか今お前ものすごくサラっと酷いこと言ったな?もずこ?」 |
 |
「だいいちだな。この時節はいろいろ調整めんどくさいんだぞ? ただでさえ暑いんだから精密機器にはよくないんだからな。 おかげさんでここ最近コイツの調子も…」 |
 |
(『設定ミスってましたよ』的エラー報告を提出) |
 |
「はいすいません、マジすいませんでしたッ!」 |
 |
時折、水面に反射する光を覗き込むように浮上してくる。 |
 |
何かが焼ける臭いに反応すると、水中へ潜る。 |
 |
「テリメイン海まつりー!」 |
 |
「海屋台で海イカと海やきそばを買う」 |
 |
「海屋台で海とうもろこしと海わたあめも買う」 |
 |
「海ゆかたを着て海ぼんおどりを踊る」 |
 |
「そして海花火を見るぞー!」 |
 |
「…お前、『海』ってつければなんでもアリだと思ってねえか?」 |
 |
「でもまあせっかくお祭りってんなら俺もまぜてくれよ。 それこそ浴衣は手持ちもあるしよ、あとは海うちわと、せっかくだから海タコ焼き…」 |
 |
(びくっと震えている) |
 |
「…ってどうしたタコ!?お前じゃねえ…って、逃げんなーっ」 |
 |
水面に、広めの間隔に的のようにビンをいくつか浮かべて距離を取る。 |
 |
軽く鐘を振るうと、ゆっくりと波紋が広がり全てのビンが同時にくるくると揺れている。 |
 |
何か満足したようだ。 |
 |
「アトランドの奥にレッサードラゴンが出るらしいぞー」 |
 |
「外見はアライグマに似てしっぽがふさふさで帯模様がある」 |
 |
「主に竹林や樹上で暮らしていてタケやササを食べるが雑食性」 |
 |
「たまに二本足で立つこともあるらしいが理由は不明」 |
 |
「もちろんこれはレッサードラゴンでなくてレッサーパンダの話だ!」 |
 |
「だからレッサーがいるならグレーターパンダもいるにちがいない!」 |
 |
「…その方向性でいくといずれここにもグレータードラゴンも出るってことじゃねえか…」 |
 |
(その方向性でいくとグレータードラゴンは同族をどんどん呼ぶので経験値稼ぎに、などと書き出す) |
 |
「タコおまえもか!!」 |
 |
「なんというか、俺たちほんとこれから何と戦うんだろうか…」 |
 |
(がんばろうね、とジェスチャー) |
 |
空を見ている。 |
 |
潜って戻ってくると、両手をはたはたと羽ばたく真似をする。 |
 |
首をかしげる。 |
 |
「いよいよレッサードラゴン戦だー!」 |
 |
「東南アジアに生息する夜行性のサルで体長は20cm程度」 |
 |
「外見はオレンジがかった毛皮と大きな目が特徴」 |
 |
「とてもゆっくり動くからナマケモノの仲間に分類されたこともある」 |
 |
「体から分泌される毒を毛皮にぬって身を守る世界で唯一の毒を持つサルだ」 |
 |
「ちなみにこれはレッサードラゴンでなくてレッサースローロリスの話だ!」 |
 |
「もういちいちツッコむ気力もねえんだけどよ。お前そのテの微妙な希少動物好きだよな、もずこ」 |
 |
(そっとうなずいている) |
 |
「それで思い出したけど俺さ、スローロリスって、ずっとリスの一種だと思ってたんだけど正しくは『ロリス』なのな。そも、リスどころか全然別物なのな。」 |
 |
(ツッコみ所に困っている) |
 |
「しかも動作がノロいからってことで『スローなロリス』。なのな…」 |
 |
「…ってなんだよ、だ、誰だって勘違いくらいあるだろッ!?」 |

 |
ぐいぐいと手首や肩や腰をほぐしている。 |
 |
ぶんぶんと鐘の素振りをしている。 |
 |
「前回のおさらいー」 |
 |
「レッサーパンダを退治したら白パンダと女の子が現れた」 |
 |
「白パンダにまたがっていた女の子は好き嫌いなくなんでも食べるらしい」 |
 |
「等々力の塩ちゃんこ」 |
 |
「アルウィンの山賊焼き」 |
 |
「喜作のソーセージ盛り」 |
 |
「おいおおぞらいわし、タッパーを用意しておけー!」 |
 |
「(呆然と、ただ成り行きを見守っている)」 |
 |
「…ツッコミ所が多すぎてどこから手をつければいいんだよ!!」 |
 |
(その横で各種オリジナルタッパー販売はまだかしらとかいう顔してる) |
 |
「…」 |
 |
「…なんかさ?男子だ女子だ昔草食系だ肉食系だってカテゴライズするアレあったっていうじゃん?」 |
 |
「…雑食系女子って、要するにもずこみてえな奴の事を言うんだなって、今思い知ってるんだ俺…」 |
 |
(肩をぽんぽん叩き) |
 |
「…ま、どんな時でも、なんでもかんでも楽しめる才能ってのは、本当に大事なんじゃねえかなって気も正直あるんだよ」 |
 |
(しんみりうなずいている) |
 |
「…(もずこを見て)」 |
 |
「…なんかこう…俺も凡人というか、まだまだだよなって、思うぜ、うん」 |
 |
ぐねぐねとうねっている。 |
 |
魔力を循環して傷を再生しているようだ。 |
 |
「前回のおさらいー」 |
 |
「コシロノツエとサメ野郎をたおせなかったぞこんちくしょう」 |
 |
「だがおかげでいろいろと勉強することができた!」 |
 |
「カリフラワーはブロッコリーが突然変異してできた」 |
 |
「ブロッコリーはキャベツが突然変異してできた」 |
 |
「キャベツは古代地中海世界で薬草から品種改良されて生まれている」 |
 |
「そしてキャベツ野郎というとドイツ人へのスラングになるのだ!」 |
 |
「おいおおぞらかける、今日はキャベツごはんを炊くぞー」 |
 |
「…俺が炊くんだよな?それ…(キャベツをざくざく切りながら)」 |
 |
(傍でせっせとゴマを炒っている) |
 |
「でも、確かに勉強になったよな。やっぱなんというか、いろんな人からの情報収集は大事だよな」 |
 |
「聞くは一生の恥、聞かぬは一生の恥、って言うしな。 知らないことは別に悪いことじゃねえさ、知らないことがあって、それを聞いて、自分で理解できればそれは恥でもなんでもねえ、学習って言うんだ」 |
 |
「…とは、わかっちゃいるけど… 大抵の場合、本来知ってたはずのことの再確認、だったりするんだよな…」 |
 |
「いやはや、使えねえ知識はないも同じってやつかー。 ほんとに日々精進だぜ、…もずこ、おい、聞いてるかー?」 |
 |
柔らかい身体と長い首をよじるようにして、身体の傷を一つ一つ確かめている。 |
 |
尾を抱えて深く静かに潜る。 |
 |
「聞いた話ではジュエルビーストがとても強いらしい」 |
 |
「だがまずはコシロノツエを今度こそぽきりと折ってやらなければならない」 |
 |
「クジラはクジラのベーコンにしてやる!」 |
 |
「ツエはメシ炊き用の竹づつにしてやる!」 |
 |
「カリュブディスはたぶんすすぎ洗いに便利だー!」 |
 |
「(テリメインネットに接続して画像検索しつつ) あーなるほどな。カリュブディスってのはなるほど、こういう怪物なのか…」 |
 |
「ってもずこ、お前なんか全然別の事連想してねえか!?」 |
 |
「…でも、この海ってけっこう明らかに『ズラしてる』生物が出るしなあ。 なんだろうな、意表をついてきてるのか、むしろもっと…例えば…」 |
 |
(それ以上はいけないというハンドサイン) |
 |
「…そ、そうだな…」 |
 |
「だからそっちのジュエルじゃねえっての!!もずこ!! そら俺も連想したけどな!!」 |
 |
戦いに使う術式を確かめるように魔方陣を練っている。 |
 |
・・・。 |
 |
もう一度指差ししながら確かめている。 |
 |
何かに気付いた顔。 |
 |
「いよいよジュエルビースト戦だー」 |
 |
「宿題やったか?」 |
 |
「お風呂入れよ」 |
 |
「歯ぁみがけよ」 |
 |
「風邪ひくなよ」 |
 |
「また来週ぅー!」 |
 |
せわしなく魔方陣を動かし、何かを整理している。 |
 |
一息ついている。 |
 |
さらに新しい術式を書き込みはじめた。 |
 |
「ジュエルビースト2連戦ー」 |
 |
「決戦を前にあらためてうちのパーティの役割を確認する」 |
 |
「ゾーラはやわらか大砲で敵をやっつける!」 |
 |
「私は威嚇係で敵をひるませる!」 |
 |
「あとはおおぞらかけるに任せたぞー!」 |
 |
「…(無言)」 |
 |
「要するに、『よきにはからえ』ってヤツだよな?それ」 |
 |
(神妙な面持ち?でうつむく) |
 |
「いいか、どんなドラクエにもそんな作戦名はないんだ!もずこ!! もうちょっとおまえ、その、人権的配慮を考慮した作戦立案をだな!?」 |
 |
(でも要約するとそれがいちばん通じるよねってジェスチャー) |
 |
「…いやまあ、しょーがねえから、やるんだけどな? 頼られてるって思うことにはするけど、なーんかこう…ああ見えて 思慮遠望あんのかなって思わせるそぶりもあるからなあ、もずこ。」 |
 |
「いや、…ないかな…」 |
 |
(やわらか大砲、って単語になんか反応してる) |