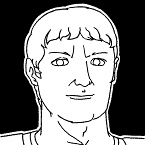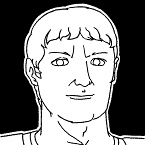
将軍ゲルマニクス(Germanicus Julius Caesar)
生没紀元前15年5月24日〜紀元19年10月10日
私的評価
統率B
知謀C
武勇B
政治C
魅力A
ゲルマニクス・ユリウス・カエサルは本来であれば彼こそが第三代ローマ皇帝となるべき人物でした。当時、帝政ローマを創設した初代皇帝アウグストゥスは直系の後継者に恵まれず、妻リヴィアの連れ子であるティベリウスをしぶしぶ養子にしていましたが、同時に養孫として次代の後継者候補に迎えたのが姉の孫にあたる少年ゲルマニクスです。少年の父ドゥルースス・ゲルマニクスはリヴィアがアウグストゥスと再婚する以前に身ごもっていた子でしたが、長じて勇敢な軍人となりゲルマニアの最前線で国境防衛に活躍すると「ゲルマニアを制した者」を意味するゲルマニクスの称号を与えられていた人物であり、その後若くして亡くなった父の称号を個人の名前として受け継いだのがゲルマニクス・ユリウス・カエサルでした。
幼いゲルマニクスにかかる周囲の期待や重圧は相当なものだったに違いありませんが、父ドゥルーススを敬愛する少年は父に負けじと快活で勇敢な青年として成長します。いささか直情的なところはありましたが生真面目かつ正直な性格で、将軍として馬にまたがるには足が細すぎると揶揄されたときには一念発起して鍛え上げるとたくましい足を披露してみせたこともありました。
当時においても後代においても、統治者として賞讃されるアウグストゥスが自らの後継者選びでは執拗に血縁にこだわり続けた事情に対しては批判あるいは苦笑する声もありますが、一世紀にもおよぶ内乱が終結してようやく訪れた平和を維持するには元老院と民衆の分裂をつなぎとめる存在を欠かすことができません。アウグストゥスは神君カエサルの息子になることで元老院の第一人者かつ民衆の指導者としての権威を得ていた人物でしたが、後継者となるティベリウスは名門クラウディウス家の一族とはいえ陰気な性格が人々には嫌われていましたから、アグリッパ以来の重鎮としての実績と力量はともかく新皇帝として人々に受け入れられるに不安なしとはしませんでした。優れた嫌われ者のティベリウスを養子に、優れた人気者のゲルマニクスを養孫に迎えることは当時の事情を鑑みれば他に選択の余地はなかったでしょう。
† † †
紀元14年、アウグストゥスが逝去すると元老院はその権限をすべてティベリウスに委譲する決議を下します。それは形式的なものとはいえティベリウスが皇帝として認められたことを意味しますが、ローマの主権者はあくまで元老院と民衆の双方であり、元老院の承認を得た新皇帝は民衆すなわち兵士からも支持を得なければなりません。
ある程度予想されていた事態のようですが、ここで最前線ゲルマニアに駐屯する軍団兵たちの間で総司令官ティベリウスへの忠誠宣誓を拒否しようとする動きが起こります。それは反乱というよりも待遇の向上や延期されていた満期除隊の実施を求めた労使交渉、ストライキに近いものでしたが、新皇帝の権威に傷をつける行為には違いなく放置すれば不満が暴動に結びつかないとも限りません。ティベリウスの実子ドゥルーススと若いゲルマニクスの二人が皇帝の名代としてそれぞれ現地に赴くと、ドゥルーススは巧妙に時間稼ぎをして軍団を押さえ込むことに成功しますが、声望のあるゲルマニクスを迎えた軍団ではいっそ彼を新しい皇帝として迎え入れる準備があると若者を煽動したのです。
生真面目な正義漢であるゲルマニクスは憤慨すると軍団兵の提案を真っ向から拒否、激昂した兵士たちが騒ぎだすと自らの不名誉と不面目を恥じたゲルマニクスが剣を抜き自殺しようとして人々に止められる騒ぎにすらなりました。ゲルマニクスは最前線にも家族を帯同する習慣があり、このときも例外ではありませんでしたがこの状況はあまりに危険であるとして退去を薦められると妻アグリッピナと息子ガイウスの二人を陣営から逃がそうと試みます。これが知られると当然のように兵士たちが押しかけますがゲルマニクスは悪びれる様子もなくむしろ堂々として言い放ちました。
「妻と息子に流れるアウグストゥスの血を危険に晒したままにしておくことはできない。だが妻と息子を自分の兵士から逃がさなければならない、恥知らずな司令官はどうかお前たちの好きにしてくれ」
ゲルマニクスの言行は稚気であっても裏表がなく、アウグストゥスの曾孫にあたる三歳のガイウスまで危険に晒したことに兵士たちは意気消沈すると自分たちから彼を取り上げないでくれと嘆願します。ゲルマニクスはその言葉に従うのではなく、ならばお前たちの働きでお前たちの名誉を取り戻してくれと全軍を率いての出立を宣言、勢いのままにライン川を渡りゲルマニアに侵攻するとマルシ族の集落に襲いかかって壊滅的な打撃を与えました。
マルシ族にしてみれば晴天の霹靂以外のなにものでもなく、ことの次第を聞いた元老院でも宣撫に訪れた筈の将軍が独自の判断で無法な侵略行為を行ったことを問題視するむきもありましたが、最終的に不問にされたのは騒乱が鎮定した結果を重視したこととゲルマニアの地がかつてアウグストゥスの時代にウァルスの軍団が壊滅させられた「不面目を晴らすべき土地」であると見なされていたことによるでしょう。不満の直接の原因である満期除隊の実施もティベリウスの命で厳正に行われるようになりました。
こうして最前線にとどまったゲルマニクスはゲルマニアへの侵攻を継続、かつて自らもこの地を転戦したことがある皇帝ティベリウスは深い森が広がるばかりで統治も防衛も難しいゲルマニアを奪還することに懐疑的でしたがゲルマニクスは翌年以降も積極的な侵攻を試みます。名誉を重んじるローマ人として、父が命を落とした蛮地を制圧すべく各地で蛮族を蹴散らして仇敵アルミニウスの妻を捕らえる戦功も挙げましたが、決定的な勝利が得られたわけではなく国境は依然としてライン川から変わることはありませんでした。結局ゲルマニクスの悲願は果たされることがなく、以降は幾人かの皇帝の手でライン国境が整備されていった事情を思えば無念であれゲルマニアを難地とした皇帝ティベリウスの識見が正しかったと言うしかありません。
とはいえその後もゲルマニクスの軍団は戦闘や水難事故などで多くの犠牲を出したとはいえ、それに見合うだけの戦功を挙げることには成功してケルスキ族に大きな打撃を与え、アルミニウス自身にも手傷を負わせて再起を不可能にし、トイトブルクの戦場跡地では放置されていた軍団兵の遺体を弔い、奪われた軍団旗も三本のうち二本を奪還します。軍団を休めるべく一度ローマに帰還すると盛大な凱旋式を挙行、アグリッピナやガイウスらも参列させた式典はアウグストゥスの血を引く若い英雄の帰還として人々を熱狂させるに充分でした。ですが充分というのであれば、人々が熱狂するだけの戦果が挙がり再起ができないだけの打撃をアルミニウスに与えたこと、皇帝にはそれで充分でもあったのです。翌年の再進撃を望むゲルマニクスを北方に送る意思はティベリウスにはもはやありませんでした。
凱旋式を終えたゲルマニクスに与えられたのはそれまでの任地であるライン軍団の指揮権ではなく、地中海東方の行政視察の任でした。決して軽んじてよい任務ではなく、当時、ローマに匹敵する唯一の大国パルティアに国境を制して遠くインドや中国にも至る交易路を監視する東方属州はローマの経済の要とも呼べる地域であり、小国アルメニアで王位継承問題が起きていた事情もありましたが情勢そのものは安定して必ずしも危急の対処が求められていたわけではありません。
ティベリウスの本意はゲルマニクスに外交と行政の経験を積ませることと、犠牲が多く得るものが少ないゲルマニア侵攻を放棄して国境をライン川に固定することにあったのでしょうが、共和政時代から侵攻と領土拡大を続けてきたローマで国境線を後退させるとなれば人々の非難を避けるには戦勝が派手に宣伝されたこの期を除いてありませんでした。ゲルマニクスの戦功を妬んだ皇帝が辺地に流転させたのだ、という評もありますが少なくとも次期皇帝たるゲルマニクスにこれ以上の戦功は不要と考えてはいたでしょう。
志半ばで最前線から遠ざけられたことが残念ではあったものの、若い当時のティベリウスにも匹敵するゲルマニクスの功績は疑いようもなく、青年が新しい任務を疎かにする理由もありません。出立に際して東方に直行せず、皇帝の私領たるエジプトに無断で立ち寄ったことを叱責こそされたものの、皇帝の息子が父の所有地を訪れただけでしたし元来文化的なゲルマニクスが長い前線暮らしの後で家族を労ってやりたかったのだろうという笑い話で済みました。笑い話で済まなくなったのは、予定よりも数月遅れてシリアに到着したゲルマニクスと現地総督ピソとの間に深刻な対立が生じたことと、ゲルマニクスが急逝したことです。
グナエウス・カルプルニウス・ピソは執政官職の経験もある元老院の有力者で、東方四個師団を従えるシリア総督職は総司令官たる皇帝に次ぐナンバー2と呼べる位階にありましたが、ゲルマニクスはその総司令官ティベリウスの名代であり蔑ろにできる相手ではありません。アルメニア王家の調停に成功してシリア入りしたゲルマニクスとピソの間にどのような軋轢があったのかは不明ですが、対立がたびたび口論を呼ぶとある日、ピソが任地であるシリアを離れたとほぼ同時に急な高熱を発したゲルマニクスが病に倒れるという事態が起こります。人々の願いと献身的な看護も空しくゲルマニクスの容態は悪化の一途を辿り、遂には彼らしくもない呪詛と復讐の言葉を残して若い英雄は息を引き取ってしまいました。
現在ではゲルマニクスの死の原因はマラリアによるものとされていますが、当時は多くの人がピソによる毒殺を疑い、両者が対立した原因やピソが任地を離れた理由も不明のままでは誰が納得できようはずもありません。ピソ自身もシリアに戻り、ゲルマニクスの訃報を聞くと手を叩いて喜んだという軽挙のせいで更に人々の怒りと反感を買っていました。遠くローマで事件を伝え聞いたティベリウスは動揺した素振りすらも見せず、まずは真相を明らかにすべきだとピソを元老院に召喚しますが当時六十歳を過ぎていたピソが家名を守るために自死を選ぶとすべての事情は闇に葬られてしまいます。愛想がなく家族の訃報にも動じずに公人として振る舞うティベリウスの態度は以前から人々に嫌われていましたが、養子とはいえ期待されていた息子の死にも微動だにしない皇帝に、実は彼がピソに命じてゲルマニクスを殺させたのだという噂がまことしやかに流れました。寡婦となったアグリッピナは毒殺の噂を最後まで信じていたらしく、その後もたびたびティベリウスに食ってかかると皇帝を辟易させています。
若くして早逝した英雄ゲルマニクスは時に直情的で稚気に思える言行がままあったとはいえ、早すぎる死を人に惜しまれるだけの能力と実績を示した人物であったことは疑いありません。若い折にゲルマニアで活躍して後に東方の行政に携わった経歴はそのまま皇帝ティベリウスの事績と重なり、大成すれば前線の軍歴と行政の経験を積んだ統治者が誕生することは充分に期待できたでしょう。共和政の時代よりローマの指導者には才能や血縁よりも軍政の経験そのものが求められ、皇帝もそれを見越して自分と同じ経験をゲルマニクスに与えようとしていました。まずはアウグストゥスとアグリッパ、更にティベリウス、そしてゲルマニクスと続けばどれだけローマの安定に役立ったか、すべては可能性でしかありませんがゲルマニクス・ユリウス・カエサルが生きていれば帝政ローマの歴史はその後の現実とは異なる姿を見せていたことでしょう。
こうして英雄ゲルマニクスは失われ、後の紀元37年にティベリウスも世を去ると残されていた皇太孫ガイウスがわずか二十四歳、父や養祖父のように軍政の経験も実績もなくカエサルの家と皇帝位を継ぐことになりました。彼こそがガイウス・ユリウス・カエサル・ゲルマニクス、後に狂帝カリグラの通称で知られることになる第三代ローマ皇帝です。
>他の記録を見る