二段ベッドの夜
月明かりが差し込んでくる学生寮の一室、さほど大きくも広くもない部屋には二人分の机や小さな家具などのほかに、二段ベッドがひとつ据えられています。青みがかった静謐に包まれた月夜の部屋は思いのほか明るく、夜に目が慣れてしまえば部屋を見渡すにもさしたる苦労はありません。壁にかけられた時計の針がこつ、こつと小さな音を刻んでいました。
氷雨は柔らかな綿の寝巻きを着て長い黒髪をまとめると、彼女の領域であるベッドに身を休めながら頭上を見上げています。上で寝息を立てている筈の、同室の少女は陸上部に在籍していて中距離から長距離までこなす、今年は全国大会すら狙えるかというほどの俊英でした。文武両道という言葉が似合いそうな、学年上位の常連で模範的な優等生。早朝から目を覚まして走り込みに出かけるために早々に眠りの世界に身を投じている、そんな彼女はですが決して堅苦しい存在でもありませんでした。
誰にでも親しげで男友達が相手でも遠慮なく喧嘩をするし、放課後になれば女の子たちと騒々しく甘味処に足を運ぶこともある。何でもできすぎると敬遠されるむきもありましたが、その彼女は超人でもスーパーマンでもなければ天才といった類でもない、氷雨の誇らしい友人でした。
「お日様が月の夜に眠るなら、私は彼女を見上げよう」
誰にも聞こえない声で呟く、夜は更けて窓の形に切り取られた月明かりがベッドにまで差し込んでいます。頭上にいる少女が生命力にあふれた陽光を思わせる存在ならば、自分はこの月明かりになることができるだろうか。こつこつと時計の針が奏でる音に、窓外のずっと遠くで響いている小さな風の音。耳を凝らせば彼女の息づかいすら聞こえてきそうな、穏やかな静謐の中で妖精の粉を瞼に感じた氷雨はようやく訪れた夢を受け入れることにしました。
山間を吹き抜ける空気は肌に冷たく、今でも少女に新鮮な世界を感じさせています。もともと東京で生まれ育った氷雨が長野県の郊外にある、この町で一人暮らすことになった理由は大仰に運命と呼ぶよりも単なる偶然でしかありません。老舗の料亭の娘として生まれた氷雨は、実家の都合や両親の薦めもあって親戚がいるこの町で高校生の時間を過ごすことになりました。その彼女が入学する先くらいは自分で選びますと、決めたのはこの地域では珍しい学生寮を備えてスポーツ特待制度まで設けられている周囲でも有名な学園です。私立校らしく学業にもスポーツにも力を入れている進学校で、学業には自信があっても運動と名のつくことは苦手な氷雨がとても敵わない同級生たちがいる、なんて素敵なことだろうと考えたのが少女がその学園を選んだ理由でした。
遅めの新緑がまだ訪れてもいなかった頃、寮に荷物を運び込んだ氷雨を出迎えた友人は陽光を思わせる生命力を持つ快活な少女でした。一足早く部屋の主となっていた彼女は地元の生まれということですが、早朝の練習をしたいから無理を言って寮に入れてもらったとは当人の言です。ではスポーツ特待生かと問えば一般入学で、しかも理由を聞けばどうせなら入学試験を受けたかったからという頼もしい返事が返ってきました。
新しくも慌しい生活に、順応性の高い少女たちはすぐに慣れましたし家を思い出して懐かしむ暇もありません。初の試験では氷雨は学内でも一、二を争う成績を残してみせましたが、陸上部に入部したという同室の少女の名が自分からさして離れていない、後ろに挙がっていたことに驚きます。彼女とは同じクラスで確かに勉強もしているようでしたが、感心する氷雨に対して当人は喜ぶよりも同室の友人に負けたことを心から悔しがってこう言いました。
「次は負けないんだから!」
いつでも全力で走り回っている、彼女に氷雨が興味を持つようになったのはこの言葉がきっかけです。スポーツ特待生の制度があるこの学園で、試験でこそ壊滅的な成績でもいざグラウンドや道場に出れば全国大会にも挑もうかという友人は何人もいましたが、自分の得意分野を外れてまで競争心を燃やす生徒は決して多くはありませんでした。
友人の言葉を心に反響させるように、氷雨は軽く目を閉じます。思い出すのは昔のこと。学力至上主義は子供の感性に悪影響を与える、人はもっとゆとりをもって育てられるべきだという教育者の都合が子供たちに押し付けられていた時代。落ちこぼれを出さないという名目で、実際には出る杭を打とうとするだけの時代がありました。
今よりももっと子供だったあの頃のことを、氷雨は思い出します。大人たちには大義名分も理由もあったに違いないでしょうが、いつの時代でも唐突に変更された世界を受け入れるのは子供たちでした。競争社会に疑問を持つのはけっこうだが、では単純に競争を止めようという短絡的な思考に振り回されるのは子供たちなのです。
学校の徒競走で全員が並んでテープを切ろうというとき、たまたま足を躓かせた少女が一人、皆から遅れてゴールしてしまいました。校庭はちょっとした騒ぎになり、それでも全員が一着の旗を持たされてそのときは何もなかったかのように終わります。どのみち、一着以外の旗は用意すらされていませんでしたから。
その少女が無邪気ないじめの標的になったのはそれからのことです。一人で目立った彼女が、自分だけ遅れたくせに皆と同じ一着にしてもらえたことは子供たちにとって度を超した優遇でしかありません。いつの間にか少女は、わざと転んで人目をひこうとしたずるい奴になっていたのです。わざと転ぶ少女は、わざと転ばされる少女になりました。
今でも氷雨は覚えています。無邪気ないじめはそれほど長くは続きませんでしたし、飽きっぽい子供たちがいつまでも同じいじめを続けるような退屈なことはしません。新しい理由でも相手でも、移り変わっていくだけですが数ヶ月、半年、一年もすればやがて誰もが忘れてしまいました。幼さが産み落とした記憶。
ですが今でも一つだけ、彼女は後悔していることがあります。少女がいじめられたことを氷雨は仕方がないと思っていました。だって、彼女は確かに遅れてゴールに着いたのに一着の旗を受け取ってしまったのですから。それがわざとであってもなくても、少女の徒競走は一番びりっけつだった筈です。大人がどう言おうが、誰にいじめられようが自分の中にある「正しいこと」に嘘をつかないこと。あんな旗を受け取るべきではなかった。誰も喜ばない旗よりも、少女にはずっと大切なことがあった筈なのです。
それ以来、氷雨には心の底から嫌いなものができました。頑張ったら誉めてもらえるものは何だろうかと考えて、少女は習い事に励むようになったり学業にもそれまで以上に真摯に打ち込みます。幸い彼女の家はそうした習い事に積極的でしたから華道や書道に至るまで氷雨は得意になりましたし、もとから秀でていた成績も更に群を抜いたものになっていきます。いくら平等で落ちこぼれを出さないと大人が言ったところでコンクールに入賞すればそれを認めない訳にはいかず、成績がよければ他の子に合わせなさいとも言われません。せいぜい、他の子にも教えてあげてねというしごくまっとうなお願いをされる程度で、おかげで氷雨はそこらの教師よりも勉強を教えるのが上手いと言われて一部の先生に難しい目で見られるようになる程度でした。
「ん、どーしたの氷雨?」
「え・・・ああ、いえなんでもありませんよ」
机に向かっていた同室の少女が、不審げに氷雨を見る様子はあのときの教師の目とも友人たちの目とも違っています。彼女は自分を正当に評価してもらいたかっただけですが、目の前の少女はそれだけではなく、その自分に負けないぞと言ってくれるのです。並んでゴールに入ろう、そんな発想は陽光を思わせる少女にはありませんでした。
それ以来、氷雨は彼女の友人になることに決めました。そして体育も徒競走も苦手なままだった彼女は陸上部の友人に走って勝てるはずもありませんが、学業では存分に返り討ちにしてやることを誓ったのです。そして、実際それから何回かの試験で氷雨が友人に負けたことはただの一度もありません。そのたびに本気で悔しがっている友人を、氷雨は心の底から愛しく感じてこう言いました。
「だって、次の試験も私が勝ちますからね」
新緑の季節が過ぎて短い夏、高地の涼やかな夏が訪れても同室の少女はいつでも全力で、忙しそうに走り回っています。氷雨はといえばいくら友人であっても四六時中傍らにいる訳ではなく、教室でも男友達と騒々しく口喧嘩をしている少女を横目に窓外に目を向けたり好きな本を読みふけっていました。とはいえ陽光を思わせる少女はとりとめのない本の話題にも当然のように参加してくるし、互いに薦める本を読み合うことも行っています。呑気な存在に思わせておいて、時間と財布に限りがある寮生にとって本を薦めるということは、それが相手の気に入るであろうことを確信した上で行う真剣な行為であることをどの程度の人が知っているでしょうか。
「でもわたしの趣味は片寄ってると思うよ」
「そんなことありませんよ。でなければ、私もお互い様です」
小さな笑みがこぼれます。もしも少女らしい趣味が詩とか文学だというのであれば、彼女の趣味は確かに片寄っているのかもしれません。氷雨自身はそうした文学でもより古典が好きでしたが、友人が薦める本には時に科学雑誌や専門誌が平気で混じっていることもありました。もちろん、彼女はその中でも氷雨が気に入るだろう内容を選んで薦めていましたし、彼女の見立てがなければ氷雨は古代の哲学者が挑んでいた数学の命題など考えることもなかったでしょう。
貴重な休み時間はあっという間に流れてしまい、放課後になれば少女は陸上部で汗を流して、たいていは日が落ちた遅くに帰ります。閉門の時間は決まっていましたから、同じように部活動をしている同級生と連れ立って帰ることが多かったし時には寄り道をすることもありました。生徒会の書記をしていた氷雨は忙しい時期には遅くなることも珍しくありませんが、早く終われば陸上部を見学に行ったり一足先に寮に帰ってお茶の用意をしています。何とはなく、同室の少女がどちらを欲しがっているかによってお茶には甘いお菓子が添えられることもありました。
毎週、疲れをためないように部活動には休みが設けられていますが、そんな日に彼女は当然のように氷雨がいる生徒会室を訪れます。遊びに来るだけではなく、有志で募集している手伝いをするために。元気だねー、という周囲の声は半ば感心して半ば呆れているのかもしれませんが、少なくとも彼女の友人たちが彼女を評する声には棘がありません。その声に氷雨は苦笑ともつかぬ笑みを漏らしますが、よくまあ体力というか勢いが続くものだと本気で感心します。少なくとも、ひたすら元気な少女を見ているのは気分が悪いものではありませんでした。
氷雨は彼女をことのほか気に入っていましたし、同じクラスで、生徒会室で、それに寮の部屋で会えることを幸運だと思っています。これは恋みたいなものですね、と冗談めかして言ってみたこともありました。
「これは聞きずてなりませんなー」
無邪気に笑いながら、氷雨と彼女を揶揄する声も聞こえます。とはいえその彼女はあまりに奔放でひとところに留まらず、性別は置いても氷雨の恋愛というには片想いに過ぎるかもしれません。それでも彼女を振り向かせることならかんたんでした。真正直に、全力で戦えば彼女は必ずそれを迎え撃ってくれるのですから。
「今日の家政科の課題、もう終わりましたか?」
「もちろん!」
陸上部の練習が始まる時間、日差しは少しだけ傾いて濃い影が生徒会室の一角をななめに横切っています。その日の活動はなるべく早く終わらせようと、氷雨の目の前には並べられた紙束が手際よく片付けられていました。会議の予定があれば議事から時間単位の進行まで用意する、事務手続きであれば先に記載できる箇所はすべて完成させて記入箇所に付箋を貼っておく、書類は扱う順番まで考えて並べておく。
今年の生徒会は例年にないほど効率的で、早く活動を終えることができるとはちょっとした評判になっています。一足早く寮に帰ったらお茶の用意とフルーツケーキを焼いておこう。ちょうど話したい話題もある。氷雨はごく私的な理由で彼女の仕事を片付けていましたが、彼女は別に自分のことを献身的な美徳に満ちた人間とは思っていませんでしたから、自分の満足のために人の役に立とうとしても何も問題はないでしょう。何しろ彼女の同室の友人は、何をしていても油断すれば全力で追いついてくるし読み進めている頁をいつの間にか繰り終えているような少女でした。
いつの間にか。人は不思議に思っているかもしれません、いつ、どこで彼女はあれだけのことをやっているのか。早朝の走り込みを含めて陸上部の練習に没頭し、学業にも滞りはなく、友人とも当然のように遊びに行くし寮に帰れば氷雨とお茶をはさんで他愛ない話題に興じる。毎日彼女と暮らしている氷雨はそのことを知っていますが、別に彼女は特別なことをしている訳ではありませんし寝る時間や休む時間を削っている訳でもありません。
もしも人と違うのかもしれないとすれば、それは彼女がごくふつうの暮しでさえも時間を作ってから行うことでした。時間ができたから休む、暇だから遊ぶということを彼女はしていません。最初から練習する時間や勉強する時間、生徒会を手伝う時間を決めているように休む時間や本を読む時間、お茶を飲む時間や遊ぶ時間を決めているだけです。
「だってもったいないじゃない」
彼女本人に聞いてみたら、そういう答えが返ってきました。人がどう思うかは氷雨には関係ありません。彼女はその言葉をごく当然に言う、そんな友人が好きでした。
同じ陸上部で、彼女と昔なじみという男の子がいます。男の子は短距離走の選手をしていましたが、その彼に少女は自分の専門の中距離でも勝てないんだと漏らしたことがありました。勝てないよと、言いようのない言葉で呟いたことがありました。男の子と女の子の成長が違うこと、例え専門でなくとも、男子の陸上記録に女子の記録が及ぶべくもないこと。それは当たり前のことだと思われていますが、自分が及ばない事実を突きつけられてなお記録に挑み続ける女性がいます。
それは単純に男の子に勝てないとか、昔なじみの友人に勝てないといった理由ではありません。なぜ勝てないのか、それは彼女自身の記録がなかなか伸びないから。成長に合わせて伸び続けていた彼女の記録は、どこかで限界に達します。世界の記録を見れば、全国の記録を見ればハードルがずっと先にあることが分かっていても、自分の記録はそれまでのようにかんたんには伸びなくなる。
一日、陸上部を訪れて話を聞いたことがあります。氷雨が陸上部を見学するのは頻繁ではなくても珍しいことでもなく、友人を気軽に応援しながら時を過ごすのも悪い気分ではありません。グラウンドを走る部員たちは一線に横並びになることもなく、少しでも記録に挑むべく躍動する姿が氷雨の目には眩しく映っていました。
そんな表現を使っていいのであれば、トラックを走る彼女が愚直なほど正直に走っていることは競技に疎い氷雨にも分かります。彼女のコーチ役を兼ねている、同級の男の子に話を聞いてみればはたしてその通りという返答が返ってきました。ペース配分とか、駆け引きとかそうした類のものは重要で、特に中長距離走には欠かせないが彼女はほとんどそうした駆け引きを使わないと。
「確かに、あいつの性格もあるけどな」
例えば序盤はペースを抑えて相手がつられたところで加速する。色々な方法はあるだろうし、競技に勝つためには効果だってあるでしょう。全力で単純で真正直な彼女の性格を考えれば似合わないかもしれませんし、得意ではないかもしれませんが苦手を克服するのも立派な練習でした。
ただ競技に勝とうとするだけならそれでもいいでしょう。ですがペースを落とせば記録が抑えられてしまうことも間違いありませんし、それは他の選手に挑むには良くても自分の記録に挑むには必ずしも向いていません。勝てないと悔しがる彼女の姿はやるだけやって、考えられることをやって、それでも自分の記録が伸びなくなることへの恐怖も含まれているのですから。
軽い風が氷雨の髪を揺らします。高校生のクラブ活動の練習がどういうものか、それは場所によって違いはあるでしょうが思いのほか近代的になっている例も珍しくはありません。特に中学生の頃からすでに本格的な練習を始めていたとあれば、単に死ぬほど練習したからといって速くなるとか強くなる訳ではありませんでした。
「最初に理想の姿を作る、後はそれに近付けるんだ」
人によって異なる、体格や能力を含めて彼女に向いた理想のフォームやリズムがあってそれが実現できれば到達できる記録が存在します。完璧な動作によってそれを実現すること、それに耐えられる身体を作ること。その二つが彼らにとっての練習でした。言うは易くとも脚や腕を振る角度から呼吸の一つまでを理想的に再現することは尋常な労苦ではありません。もちろんそのすべてをゴールにたどり着くまでの一分、二分の間、力を抜かず全力で出し続けなければならないのです。
だからこそ目標タイムという考え方ができますし、彼女の理想が再現できるようになればそれは明確なものになります。もしもそれが容易に確実に実現できる理想というのであれば、そのとき彼らは次の理想の姿を描くことができるでしょう。
やるだけやって、考えられることをやって、自分が描いた理想の姿に挑み続けるつもりなら、ただひたすら時間を費やして練習をしたところで決して足りることはありません。決められた時間でより正しくより効果的に、最大の成果を出すしかないのです。頑張るだけではなく正しい方法を探してしかも頑張り続けること。だから彼女は全力で走り、全力で学びながら、全力で遊んでそして全力で身を休めます。
友人が寝入った静かな部屋。氷雨は彼女のことを知ってから、頑張ったら誉めてもらえるから、見返りがあるから励むだけではない努力があることを学びました。手を抜かず、報われるかどうか自信がない理想に挑むこと。そんな生活をしているからこそ彼女は喜怒哀楽まで全力で表現します。競争が当たり前に存在する、勝ち負けが当たり前にある世界で彼女は記録に挑むことで自分を誇らしく思うことができますし、自分にも他人にも負ければ心の底から悔しがって涙すら流してしまう。そんな彼女を氷雨は心の底から愛しく思うことができました。
頭をなでてあげたくなる。こっそり、彼女が寝ているときに何回かやったことがあります。
勝てないよお。勝てないよお。
二段ベッドの上からかすかに聞こえてくる、その言葉が最近多くなりました。まくらに顔を埋めて、声が漏れないようにしていることが氷雨には分かりましたから、彼女もその言葉に気が付かないようにしています。彼女だって別に強い人じゃない、人と同じようにため息をついても悪いことなんて何もない。
氷雨はそれを慰めてやろうとは思いません。しばらくして寝入った友人の目の下に心を傷つけた跡があったとしても、それで友人に慰められることを彼女は望んでいないでしょう。氷雨にできることはいつものお茶を温かいチョコレートに変えてみたり、活けた花を友人の机の脇にそっと立ててみる程度でした。そんなとき彼女は少しだけ奇妙な、どこか恥ずかしそうな顔をします。
勝てなくてもいいじゃないか、全力で頑張っているんだから。結果じゃなくて、その過程にあなたは嘘をついてはいないんだから。それは正しい言葉かもしれませんが、それを言ってはいけないような気がします。正しいからといってそれを伝えることが正しいとは限らない。窓から差し込んでいる淡い月の光を目に、少女は大人たちが思うよりもずっと難しいことで悩んでいました。
勝てないよお。
それがあまりにも辛そうなとき、氷雨は友人に怒られることを覚悟してゆっくりと梯子を上りました。二段ベッドの上は友人の領域で、そこに踏み込むことは彼女の心に踏み込むことです。眠りの園に立ち入ることができずにいた、彼女は梯子を上る気配にすぐに気が付くと布団から目だけを覗かせるようにして向き直っています。暗がりに判然としない瞳は非難するようにも、救いを求めるようにも見えました。少し、考えるように視線を下ろした氷雨は小さな友人にもう一度顔を向けると穏やかな笑みを浮かべます。
「今日は一緒に寝ませんか?」
どうしてという説明はしませんでしたし、できるとも思えません。少女たちは二人とも全力で、必死で今はどうしたらいいかだけを考えて、見つからない答えを彼女たちなりに探しているのです。氷雨の声に、少女は無言のまま視線を外すとそれでも恥ずかしそうに布団をめくります。その夜の月は格別満月でもありませんし、新月だった訳でもありません。
どこにでもある九日ほどの月が、やわらかい光を少女たちに投げ与えていました。こういうとき、氷雨は自分が女の子で良かったと心から思います。男の子だったら、女の子を抱いて寝るなんてできなかったでしょうから。
勝ち負けは大事だ。全員平等に、並んでゴールするなんておぞましいとさえ思うし、手を抜かずに報われるかどうか自信のないことにも挑む。それが尊いのは勝ち負けが自分の理想に対する勝負だからこそで、少女は他人だけではなく自分とも勝負をしなければなりません。それを捨てたら、全力でいることを止めたら彼女は彼女ではなくなってしまいます。
そうだ、私たちは同じなんだ。
最初は、頑張ったらそれが認められるものを探していました。それは結果が欲しいというのとはちょっと違います。無駄な努力にだって意味はあるし、心から挑戦する過程が結果だけを求める姿勢よりも正しいことくらい分かっています。だけど、心から挑戦するからこそ容赦のない結果も見えてしまいますし、たどり着けない現実に辛さが漏れてしまうことだってあるでしょう。いつだってまじめに生きていることを非難する権利が、いったい誰にあるというのでしょうか。
人は彼女たちの悩みを思春期の不安定さとか、スランプといったありきたりな言葉に置き換えてしまうかもしれません。子供たちが理想を求めすぎる、ですがそれを捨てることは自分を失ってしまうことです。人はそれを大人になったと言うかもしれませんが、そうだとすれば、歳をとったら大人にならなきゃいけないなんて誰が決めたというのでしょうか。永遠に続く理想への憧れを、どうして捨てなければいけないのでしょうか。自分の理想の自分に近づこうとすること、それを忘れることが大人になるということなのでしょうか。
「大丈夫ですよ。望んで手に入らないものなんてないんですから」
根拠のない言葉が、今は必要でしたが氷雨は心からその言葉を信じています。明日になれば、彼女はいつものように走り回っているでしょうし氷雨もそれに負けじと振る舞うでしょう。次の試験が近付いていましたが、カレンダーに沿って行われるだけの試験がこれほど自分たちを奮い立たせることを、氷雨は彼女と出会ってから知りました。
結局、何も解決しないかもしれません。きっと答えなんて出ないことは多くあるでしょう。だってその問いかけは、彼女たちが彼女たちである限りはいつまでも続くものですから。だから氷雨は友人を放っておくことができませんし、今夜だけは腕の中にある温かさと息づかいが少女たちを穏やかな夜に包み込んでくれています。月の光はやわらかく、夜があたたかいことを氷雨は知っていました。
公園に行こう。少し歩いた先にある、池のある地元の大きな公園。寮の女の子たちを誘って、バスケットを手に気まぐれに歩く公園では風が水の上をすべり木々の間を抜けていきます。広々とした穏やかな公園は決して音に満たされていない訳ではなく、多くもない人々が交わす声を除いたとしても風や葉が奏でる音や水の流れ、鳥や虫たちがそこらを跳ね回る音が心地よく耳朶を打っていました。
駅に向かう繁華街に行けばもう少し、最近の女の子らしく遊ぶことだってできるでしょうが氷雨には町よりも公園の喧騒の方が貴重なものに思えます。その通りだねーと言うのは氷雨と同じく東京から越してきていた少女で、地元の友人たちはそんなものかなと言っていましたが彼女たちも持っていないものに憧れながら自分が手にしているものの価値を知っています。少なくとも、彼女たちの頭上を覆う心地よい空気に嘘はありません。
「荷物持ちがいないのは残念だねー」
友人の言葉が素直な本音なのか、男の子がいないことを本気で残念がっているのかは分かりません。荷物持ちだったり、差し入れ付きだったり、付加価値のある同行者をありがたがる思いは確かにあったでしょう。だからといって、この小さなピクニック自体が残念だと思う者は彼女たちの中には一人もいませんでした。
特に何をするかと決めている訳でもなく、本を開く子もいれば池を覗き込んでいる子、大きく伸びをして肺の空気を入れ替えたり木の葉を透かす日を見上げている子もいます。池を巡る柵に腰掛けて、足元に生えていた小さなシダの葉の裏に胞子が実っていることに奇妙に感心している子もいました。
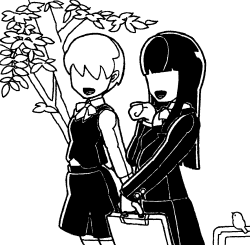 ベンチに腰掛けていた氷雨に、全身に日を浴びている彼女は笑みを向けています。この時間、この瞬間だって少女たちは全力で生きていることを証明するかのように、この他愛のない時間を心から楽しんでいました。手を抜く必要は少しもないし、誰もが同じ体験を横並びに共有することもありません。今は呑気に公園の空気を楽しみながら、友人と同じ時間を過ごしています。自分を見ている氷雨の視線に気が付いて、少女は少しだけ気恥ずかしそうな顔を見せました。
ベンチに腰掛けていた氷雨に、全身に日を浴びている彼女は笑みを向けています。この時間、この瞬間だって少女たちは全力で生きていることを証明するかのように、この他愛のない時間を心から楽しんでいました。手を抜く必要は少しもないし、誰もが同じ体験を横並びに共有することもありません。今は呑気に公園の空気を楽しみながら、友人と同じ時間を過ごしています。自分を見ている氷雨の視線に気が付いて、少女は少しだけ気恥ずかしそうな顔を見せました。「ありがとーね」
望んで手に入らないものなんてありません。たった今、心の底から暖かくなるようなひなたの笑みを見つけた氷雨はそのことを知っています。東京から遠くやってきて、この町が好きでこの町で暮らしている友人たちが好きだから。私はあなたたちが大好きですと、氷雨は堂々と言うことができますが口をついたのは別の言葉でした。
「神は天にいまし、世はすべてこともなし」
自分たちが女の子であることを、こういうときは感謝してもいいでしょう。ひなたに過ごしている彼女は、氷雨の目の前で踊るようにくるりと回ってみせました。
おしまい
>他のお話を聞く