未来はいつも僕らがヒーロー 第5話
県道を走るバス。石川県にある国立能登少年自然の家に向かう、私立樫宮学園高等学校の学生たち。長野県は古坂町を出発して四時間、臨海学校のバスは幸運なことに混雑に見舞われることもなく、少年少女は長い旅路を解放感と期待感とで満たすことができました。
「あーっ!海が見えてきたよ遥」
「綺麗ね」
窓際の座席から見える日本海に、セミロングの髪を揺らして双海蓉子ははしゃいだ声をあげていました。隣りで感激しているのかしていないのか、よく分からない発言をしているのは水木遥。この二人が昔から馴染みの友人であるということは良く知られていましたが、小さな古坂の町内で生まれ育ち地元の高校に進学をした、彼女たちのような知り合いは決して珍しくはありません。蓉子は世話焼きで気の強い遥をよく助けてくれましたし、遥はそんな蓉子をいつでも守ってくれました。それは、ごく普通であたりまえのこと。
日本の海がきれいかどうかということになるとこれは何とも言えないのですが、海を見る機会の少ない長野県出身の学生にとってその海は広くて大きい、そしてすばらしく綺麗なものでした。それこそ長時間、バスに揺られてきた苦労など忘れてしまうかのように。
揺れている、といえば。窓外の風景から視線をはずした遥は軽く首をかしげると、ふと思い出したように蓉子に話しかけました。
「そういえば体育祭の準備はどう?」
「うーん?順調よ、それに恵太君まじめだし」
「そうね…田中…君なら真面目よね」
時は1995年の8月。ほとんどの学生たちにとっては長くて短い夏休みの期間が続いていましたが、部活動に勤しんでいる者や秋に開催される文化祭や体育祭の準備に駆り出されている者は休み中でも学園に行く機会はいくらでもあったでしょう。その年、体育祭の実行委員として選ばれていた蓉子は隣りのクラスの田中恵太と一緒に体育祭の手伝いをしていました。企画の必要が多い文化祭などに比べて体育祭で生徒がやらなければならないことは決して多くはないのですが、各クラスの種目や参加者をまとめたりと事務雑務的な仕事はいくらでもありますし、仕事を苦に思わない性格であればそれは友人と会う絶好の機会でもある筈です。
(私も実行委員やればよかったかな…)
今も後ろのバスで揺れているであろう、恵太の一本縛りの髪の毛を思い出して遥は視線を海に戻しました。その様子を見ている蓉子は何も言いませんでしたが、ガラスに映る友人の顔に自然と笑みが浮かんできます。蓉子の覚えているかぎり、友人の顔は小さいころ雨で遠足に行けなくなった、そんな表情に近かったのかもしれません。遠足に行く、そのバスの中で。
小学生の遠足ではなく高校生の臨海学校。海を臨む自然の家の建物は思った以上に広々としており、学生の旅行で泊まるのであればむしろ豪華ですらあるかもしれません。普通は研修やオリエンテーリング、合宿に使われる施設でキャンプ場の他にも体育館やプールやテニスコート、カヌー用の池まで揃っています。
バスを降りると広い研修室に集められ、ありがたくも退屈なオリエンテーションを長々と拝聴したあとで部屋に移動。旅先の空気にすぐになじんだ少年少女たちは待ちわびていた自由時間、早速目の前に広がる海へと足を運びます。
「石川県にも猫はいるのねえ」
美術部に在籍している綾瀬瑞乃は、眼下の海に続いている遊歩道の入り口で、海に行くでもなく溢れる自然に絵筆を取り出すでもなくただぼんやりとしていました。視線の先にいるのは一匹の猫。建物の周囲を徘徊しているらしい、どこにでもいるような普通の猫でした。
ゆるくウェーブのかかった髪を樹間を抜ける海風に揺らせつつ、貴重な時間をぼんやりと過ごすこと、あるいはそれこそが贅沢な時であるということを猫も少女も心のどこかで知っていたのかもしれません。
「あれ?綾瀬さん、海に行かないの?」
「え?あ、はい、行きます」
絵筆もスケッチブックも持たず、白い水着にパーカーを羽織り大きな帽子をかぶっている瑞乃に柾木小太郎は声をかけました。単に風景と足下の猫に見とれていて海に行くはずの時間をぼんやりと過ごしてしまった、瑞乃がそんな性格だということを小太郎やクラスの友人たちは知っていました。放っておけば日が暮れるまで海に行くことを忘れているかもしれない、声をかけてあげるくらいは親切心というものだったでしょう。
「せっかく来たんだから泳がなきゃ」
「でもそうでない人もいますよ」
小太郎に言って瑞乃が指さした先、海辺につきだした岩の突端には、やはり水着に大きなTシャツ姿でぼんやり腰かけて景色を眺めている恵太の姿が見えました。長野県の山中で見る空と、石川県の海辺で見る空とでは同じ空でも違いがあるのだろう、小太郎にはその区別はつきませんでしたが、あれはあれで旅先の空を楽しんでいるにちがいありません。頭の上で一本縛った髪の毛を風になびかせている友人のいつもの性癖に苦笑すると、少年は少女を誘って海へと歩き出しました。
「そういえば、いつものスケッチブックは持ってないんだ?」
「…ええ」
「?」
「濡れたらまずいのでお部屋にあります」
なんとなく、まずいことを聞いてしまったのだろうか。元来女性と話をするのが得意ではない小太郎としては、話題になりそうなことを探して不器用な知恵をめぐらせていたつもりでした。好意の有無以前に友人との会話は楽しいものにしたいですし、相手が可愛らしい女の子であれば健全な少年としてはなおさらです。少年の得意なボクシングやトレーニングの話をしても、普通の女の子はあまり喜んではくれないでしょう。
小太郎の雰囲気を察したのか、瑞乃は微笑むように言いました。
「海の中の景色って見てみたいですよね」
それが絵に残すために見たいのか、心に残すために見たいのかまでは小太郎は聞きませんでした。ただ、海岸に行ってさて何をしようかと悩んでいた少年の行動は、どうやら大きな水中メガネを用意しての磯歩きになりそうです。先に海岸に行っている筈の同じ班の人たちを探しに、二人は海辺へと向かいました。
足場の悪い、しかも水中を歩くのはボクシングに重要なフットワークの運動にもなる、とはもちろん小太郎の自己弁護でした。
「へー。美術部は夏休みの提出課題があるんだ」
そう言いつつ、蓉子は目の前の美城咲音が課題でなくとも好きな絵を描こうとしているに違いないだろうなと思っていました。小太郎や瑞乃、そして咲音と蓉子も同じ班分けにされており、せっかくなら一緒に遊んだ方が楽しいに違いありませんが相手はなかなかの難物です。
同級生が旅先でも意欲満々に芸術に打ち込む少女であることを蓉子は知っていましたし、荷物のほとんどが絵描きの道具ばかりである咲音の方にもそれを否定する材料はありません。ただ、蓉子のおせっかいも充分正当な理由によるものではある筈です。
「それで何を描くかはもう決めてるの?」
「描くものは決めるんじゃなく決まるものなの」
感性を絵筆に乗せて描きつづる、咲音のことばは芸術家の卵らしいものでした。蓉子はそんな級友にいたずらっぽい笑みを浮かべると、芸術のことは良くわからないんだけどとつぶやきました。さきほど瑞乃と小太郎から聞いていたことばを思いだしつつ。
「海の中って絵にするのは難しいのかしら」
「…」
とても珍しい水着姿の咲音を連れて、蓉子は海岸に足をおろします。色気のない水着の上に何故か白衣を羽織り、担いでいた荷物を岩場におくと咲音はさっそく海に入ります。
「だめだよ、準備運動くらいしないと」
「流れる海が芸術を呼んでいるのよ?」
「海は流れても逃げはしないよ」
やれやれ、という顔で咲音をひっぱりだす小太郎。考えてみれば女性の手をとって、というのは少年はあまり得意ではない筈でしたが、あまりに意識がなければ気づかないものです。どんなに浅い水でも冷えて足をつることはありえましたから、体育会系の少年としては見逃すわけにはいきません。
ようやく解き放たれた咲音はざぶざぶと海に入り、ずいぶん大きな水中メガネをつけた頭をざぶりと海中に沈めます。施設から木枠を借りてきて、覗き箱にするためにビニールを張っていた小太郎が不安になるくらいの時間がたったころに少女はざぱりと顔をあげました。そしてまたざぶりを頭を沈めます。
「一応、これ使えば海の中も見れるけど…」
「わたしが使ってもいいかな?」
小太郎から箱を受け取ると、瑞乃は咲音を追って海に入りました。このあたりは同じ美術部ならではかもしれず、一時も惜しく海に入りたがった少女の気持ちも瑞乃にはわからないでもありません。
海の中というと魚や珍しい生き物の姿をたいていの人々は思い起こすでしょうし、それは間違いではありませんけれど、ただ流れる海の水に削れた砂や石、黒々とした岩肌や貝殻の破片がどれほど魅力的に見えるかはあまり知られていませんでした。蓉子や小太郎もサンダルを履いた足を海水に浸し、しばらく磯の流れを見つめています。蓉子は中学生のとき、交通事故に遭って少し足が不自由になっていましたが、たいした起伏のない磯に入るくらいであればあまり問題はないようでした。やがて咲音が顔をあげると、その目はすっかり芸術家のものになっています。
「流れる水に一時も同じものはない…流れる水に流される砂に一時すら同じ姿があろうか!」
映像とその本質とを脳裏に焼き付けることなど天才咲音には造作もないことですが、直感を覚えたその熱が冷めぬうちに描きたいという衝動を抑えることは容易にはできません。少女はざばざばと岸辺にもどると、おもむろに荷物からスケッチブックを取り出しました。
彼女にしてみれば施設の研修棟にでもこもって、より本格的に絵を描きたいところだったのかもしれません。そうしなかったのは、そして、スケッチブックに描かれた風景に瑞乃や小太郎、蓉子らしき姿が乗せられていたことは咲音が年頃の高校生でもあるということだったのでしょう。
一時も同じもののない、流れる水に戯れる友人の姿を。
尾崎一文はその咲音や瑞乃たちと同じ班で、しかも同じ美術部でしたが流石に車椅子に乗っている身としては海辺まで行くわけにはいきませんでした。一文本人が気にせずとも他の人は気にするでしょうし、自然の家の施設自体にはあちこち車椅子向けの対応がされていましたから置いてけぼりで退屈な気分を味わうこともありません。起伏の少ない遊歩道からキャンプ場の方に行くメンバーに合流して見える景色は、後で車椅子についた潮風を拭く必要があることを除けば充分にきれいなものでした。
「あれー?尾崎さん海行かなかったんだ?」
やや無神経にも聞こえる声。言った瞬間、隣りにいた遥にこづかれていた鰈伽レイには、もちろんなんの害意も悪意もありません。さきほどまで遥や他の人たちと海で遊んできて、少し休もうかと戻ってきたレイとしてはあくまで海がきれいなんで見に行ったらどうかな、と言いたかっただけなのですが、思ったことをうまく伝えられるかどうかはまた別の問題となります。
「海ならさっき高台から見てましたよ。見晴らしはあちらの方が良いですしね」
「えーっホント?水木さん行こうよ行こうよ」
一文の話にレイをフォローするつもりはあったとしても、その話は嘘ではありませんでした。美術部といっても彫刻専門の一文としては、狭い部屋にこもっての創作活動が多い分、広い風景の中での開放感に価値を見いだしても不思議ではなかったでしょう。高台の話に無邪気に遥を誘おうとしているレイに、小柄な身体で一文の膝に座っていた玲飛燕が気をつけるようにと言いました。
「あのへんは鳶が出るから気をつけてね」
「え?なんでとんびが怖いの?」
「鳶は魚を捕るのが苦手だから、海辺の鳶は人でも獣でも襲うのよ」
「えーっ!ほんと!?」
「うそよ」
飛燕は外見だけは小学生くらいの幼い少女に見えましたが、立派にレイたちと同年の高校生です。一文の昔馴染みであるらしくよく一緒にいるところを見かけられますが、長身で大人びた一文と小柄で嘘といたずらが好きな飛燕の組み合わせは保護者と娘のようにも見えました。もっとも、他愛のない少女の嘘を真に受ける者は決して多くはないのですが。
「単純ね」
「単純なのよね」
「玲さんも水木さんもひどいー」
抗議の声をあげるレイ。他愛のない嘘を真に受ける、決して多くはない者のひとりである少女は確かに単純な性格だったかもしれません。遥にしてみれば、そんな友人の性格は頼りなくも不快なものではありませんでしたが。
「でも、単純なのも美徳かもしれないわよ?」
単純なのも美徳かもしれない。石川県の空も夜の星空に変わり、長野の山中に比べて夏の海沿いの空は充分に見上げる価値がありました。少なくとも恵太はそう思っていたに違いありません。夏空に見える星といえばカシオペアに大ぐまに小ぐまといったわりと有名な星座群。そして西に目をこらせばヘラクレスや蛇つかいの星も見ることができたでしょうか。
天体観測の時間、キャンプ場から少しはなれた高台。柵に腰かけて夜空を見上げている恵太がぶらさげたバッグに入っているカメラがこの夜の間、思い出したときにほんの数回しか使われることがないだろうことを遥は知っていました。空を見るのに夢中で自分がカメラを持っていることを忘れてしまう、写真には残っていないフィルムが少年の脳裏にはたくさん焼き付けられているのでしょう。
遥がいるのは恵太がいる高台への、遊歩道に向かう入り口の近く。ここからでも夜空の星は充分に見えましたし、視界の隅に見える恵太のいる場所に向かうには遊歩道は些か暗すぎました。あえて少年の邪魔をする必要もなく、遥は友人たちと夜空を見上げています。
(夜空がこんなにきれいなのは、地上の営みが汚いから…)
などと、ずいぶん皮肉っぽいことをさすがに口には出さないでいた遥は、それでも見上げている空の姿に心を惹かれていました。この空を、この空の遥か向こうをいつも見ている少年の気持ちがなんとなくわかるような気もしてきます。夜空の知識に決して詳しいわけではない彼女でも、視界に入るカシオペアの形や大ぐまの北斗七星は説明されずとも見分けることができました。
星に名をつける、昔の人はなんと空に夢を抱いていたのだろう。そして、その夢を今でも抱いている者はきっと今でも空を見上げているに違いないのです。
「どーしたの遥?ぼーっとして」
「昔っから夢見るロマンチストは多いのよね」
遠慮がちに声をかけた蓉子の問いに対する遥の返答は、あまりまっとうなものではなかったかもしれません。ただ昔からの友人には、少女が星空に何を想っているのか充分わかっているつもりでした。
「こないだ恵太君が読んでいた本を見せてもらったんだけど…」
「それ、私も見たことがあるわ」
それは荒唐無稽なお話。空から落ちてきた星が人に育てられる、そして星は人を連れて空へ行く船となる、そんなお話でした。他愛のない幻想小説の、そのお話がひどく心に残ったとすればそれを読む人にまさしく空を想う心があったからかもしれません。長野県の小さな古坂の町内で生まれ育った少女たちは、空を想う同年の少年のロマンチストぶりに多少呆れつつもその真摯さをうらやましくも思っていました。
いつの時代でも、少年は夢見る子供のままでしたから。
「This is just a little samba
Built upon a single note...」
ふと心づいて口ずさむ、少女のことばは静かな曲。星空に心地よいリズム、ロマンチストは蓉子の隣りにもいるようです。それとも、もしかしたら星空には人をロマンチストにさせる何かがあるのかもしれません。しばらく遥のささやく調べに目をとじて、それから蓉子はふと手首にある時計を見ると、ややわざとらしく遥に言いました。
「そろそろ恵太君呼んできたほうがいいんじゃない?」
「…そうね。でも私に迎えに行ってね、てのは無しよ」
「あれ?そうなの」
「変な気をまわさないように」
口調とは裏腹に口元に笑みを浮かべて遥がいうと、蓉子の手をとって高台へと向かいます。そのままにしておけば恵太は夜が更けても空を見上げているに違いない、夜露に風邪でもひかれたらたしかに可哀想かと思いますが、それは友人を置いていっても構わないという理由にはなりません。
それに、と思いつつ遥が見上げた視線の先で、近づいてくる女の子たちに今更のように気づいた恵太は、振り返ると星明かりで笑顔を照らしています。屈託のないいつもの笑顔に遥も蓉子も直前までの会話を忘れて表情をくずし、ことばをかけました。
「もうすぐ集合時間よ」
「え?ああ、ありがとう」
何やら機嫌の良い顔をしている恵太。もっともこの少年の機嫌が悪かったときなんて、遥も蓉子も数えるほどしか覚えがありませんでしたが、それでも何かあったのだろうかと遥は聞いてみます。
「何か見えたの?」
「うん。空には星が、ね」
ちょっと笑顔がいたずらっぽくなる恵太。不審に思った遥に少年は眼下の海辺を指さしました。柵から少し身を乗り出した二人の少女、そこでは岩かげの波打ち際が緑色に光っており、海岸にぶつかりはじけた水が砕けた星のようにきらきらと舞っています。
それはあたかも星明かりと波とが削り出した翠石の欠片のように。星は夜空に光るだけではなく、海の上でもまたたくもののようでした。
「うわあ…」
「綺麗ね…」
それが何であるか、たぶん恵太は知っているのでしょうが遥も蓉子もあえてそれを尋ねようとはしませんでした。光る海辺の星々、もしかしたら空に輝く星のどれかひとつくらいには目の前にあるものと同じような海があって、その光が数千年のときをかけて今この夜空に届いているのかもしれません。
やっぱり蓉子を連れてきて良かった。恵太が自分たちにこれを見せてくれたかったのだとすれば、遥も蓉子にはこれを一緒に見てほしいと思うでしょう。そしてそれに恵太が反対する筈もないということは、少年の笑顔を見ていれば遥には充分に分かりました。
星空に心地よいリズムを刻む波。さきほどの曲、その最後の一節を少女は口ずさみました。
「...He will find himself no show
That will play the notes you know!」
県道を走るバス。打ち寄せる日本海の波と石川県の山々にはさまれて、二泊三日の臨海学校を終えて長野県は古坂町を目指して走る車内には疲れと満足感にひたってうたた寝をしている学生たちの姿が目立ちます。その日の昼間も大型カヌーをこいだり地引き網を引いたりと、存分に動きまわった少年少女は潮と日差しに焼けた肌をエアコンの風にあずけています。三日間の記憶を窓外に思い返しているか、ただ疲れて寝ているか、どちらであっても車中は静かな雰囲気に満たされていて、バスのエンジンやエアコンの動く音くらいしか聞こえません。
隣り同士の座席に座り、肩を寄せてすうすうと眠っている蓉子と遥。彼女たちがどんな夢を見ていたか、想像はできても知ることは誰にもできないのでしょう。
去っていくバスを見送るきれいな海のこと。
その海を覆っていた星空の天蓋のこと。
一緒に星空を眺めた友人のこと。
それから、と思い出されていく記憶が泡のように夢の中に浮かんでは消えて、少女たちの乗ったバスは臨海学校の地を後にしました。
ごく普通であたりまえで、とても大切な親友のこと。
おしまい
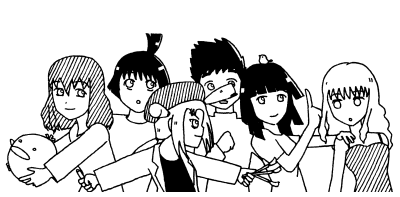
>他のお話を聞く