ぱられるわーるど.番外
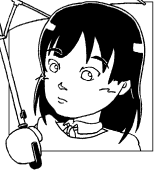 俊足で跳ぶと同時に、すでに技の構えに入っていてそのスピードと動きのすべてが乗せられた一撃が目の前にある目標を両断する。低い踏み込みから脚力と腹筋の力を総動員して、深くかがみ込んで相手の視界から消えた次の瞬間にはすでに振り下ろされた刃が弧を描いていました。当人は一回だけであればと韜晦する、冬真吹雪の斬撃は彼の同僚たちと比べてもその迅さと重さに抜きん出ており、異形の妖であれ容易に防ぐことのできるものではありません。妖怪や異形、化け物と呼ばれる存在は彼らの意味に忠実なままに存在している、その意味を断ち切るのが討魔士としての吹雪の技でした。
俊足で跳ぶと同時に、すでに技の構えに入っていてそのスピードと動きのすべてが乗せられた一撃が目の前にある目標を両断する。低い踏み込みから脚力と腹筋の力を総動員して、深くかがみ込んで相手の視界から消えた次の瞬間にはすでに振り下ろされた刃が弧を描いていました。当人は一回だけであればと韜晦する、冬真吹雪の斬撃は彼の同僚たちと比べてもその迅さと重さに抜きん出ており、異形の妖であれ容易に防ぐことのできるものではありません。妖怪や異形、化け物と呼ばれる存在は彼らの意味に忠実なままに存在している、その意味を断ち切るのが討魔士としての吹雪の技でした。東京都汝鳥市。丘陵から関東平野を見下ろすちょうど境にあるその町では、神々や異形が集う地として妖怪バスターと呼ばれる者たちが人の知らぬ危難を収めるべく術や技を振るっています。汝鳥の学園にはそうした人々の予備軍が集められている二つの倶楽部活動があり、一方を剣術研究会、一方をオカルト・ミステリー倶楽部と称していました。吹雪が所属しているのはその一方である剣術研究会、通称剣術研となります。
「まあ、こんなもんだろ」
「お疲れ様、吹雪くん」
軽く首を回して息をつく吹雪の後ろに、控えていた高槻春菜がどこか安堵したような声をかけてきます。一足跳びに踏み込む斬撃は吹雪の自信の太刀筋のひとつですが、そのとき彼の背に立っていた春菜の存在を少年は一瞬さえ忘れたことはありません。彼女が背後にいることがどれほど心強いか、それを承知した上で吹雪は彼の技を放っています。そして同時に、彼の背後にいる者をその技で守るために。
異形や妖といった存在は意味さえ見つけてしまえばどこからでもどんなものからでも生まれてくるもので、汝鳥のようにふさわしい「力」が集まる場所でそれをかんたんに予測することはできません。劣悪なマンションの屋上に無理やり植えられた植樹、放置された汚水溝、増えすぎた猫、鬱屈した一人暮らしの男、世情に攻撃的な老人。そうした不満や歪みが意味となって力を与えられたとき、それは異形として生み出されます。たいていは、歪みにふさわしく歪められた姿で。
ぞんざいに後ろで一本しばった髪を振って、ごく軽く息を弾ませながら刀を収めた吹雪は春菜から渡されたタオルを手に取ると太めの眉が印象的な細面の顔に浮かぶ汗を拭いました。彼女がわざわざ用意してくれていた好意に、満足感を大声で叫びたくなる稚拙な衝動を懸命にこらえると当然の感謝を示すように、せいぜい紳士的な礼を述べながらタオルを返します。その様子に、春菜もどこかやわらかい笑みを浮かべていました。
人の世に反する異形や妖の存在に対するに、あくまで彼らの世界に帰すことを是とするのか融和と妥協の道を探ることを由とするのか。その意思が衝突する吹雪と春菜の対立は以前から続いていましたし、今でも続いています。その彼らが互いに言い争いながらも協調して繋いだ手を離さずにいることを、事情を知らない者であれば奇妙に思うこともあるでしょう。彼らは自分たちの目指す道が同じところにあることを知っていましたし、ときに傷つけあったとしても決して互いに嘘をつかないことも知っています。以前に比べて変わったことは二つだけで、一つはそれまでたいてい春菜が異形に手を下していた、その代わりに吹雪がそれを行うようになったということ、もう一つは常は黒髪を二本に縛っていた春菜が、異形と対するときを除けばふだんは髪を下ろすようになったということでした。
(ああ、なんていう菩薩の慈愛だと思うよ)
力を振るうことの恐ろしさ、愚かしさを知りながらもそれを少女に任せていたことを知った吹雪は、今では彼女を背に自ら太刀を振るおうとしています。ためらいのない斬撃が異形の妖を断ち切るたびに吹雪は心の底に流れる血を自覚しますが、誰かがやらねばならぬことであれば菩薩の思いを捨てぬままに自分が斬るのがいいでしょう。なにより、少しでも春菜の心に血を流さずにすむのであればと吹雪は少年らしい心で考えます。それが少年の慈愛であるか、それとも傲慢であるかはたいした問題ではありません。
汝鳥の風景は以前よりもどことなく変わっているように感じられることがありますが、その原因としては進級して三年生になった先輩たちの多くが倶楽部を去っていたこともあるでしょう。学生として進学するための準備に忙しい者、倶楽部の運営を後進に委ねて一線を引く者、そして学園や汝鳥そのものを離れる者。
吹雪が常々信頼している半鬼の先輩が汝鳥を離れることになったと聞いたとき、少年は彼が思いもしなかったほどに動揺して落ち込む様を自覚しましたが、頼りになる先達を失って消沈したまま立ち寄った妖の里、マンション・メイヤに足を向けたときに当の先輩がなにごともないような顔で隣人や妖怪たちと一緒にカレーライスを胃袋に放り込んでいる様子を見て全身の力が抜けたものです。
「な、なんでいるんすか先輩。汝鳥を離れたんじゃ?」
「何いってんだ?迷い家には場所の概念はねーからな、俺がどこに住んでいても帰る家はここさ」
その時の自分はどんな顔をしていたろうかと、思い出すだけで吹雪の顔には今でも苦笑が浮かびます。メイヤにいる半鬼の先輩はもう汝鳥学園の生徒ではなく剣術研にも顔を出すことはありませんが、優れた技と肉体、そして意思を持つ鬼が近くにいることはいまだ未熟を自覚している吹雪の助けとなっていました。
去っていたといえば、幼い頃に力を失いながら後進を育てるために知恵を尽くしてくれたオカルト・ミステリー倶楽部の先輩も学園に籍を残してはいましたが、しばらく前から妖怪バスターの活動から身を引くようになっていました。学園での二年ほどの生活は彼女の心身に想像もできないほどの負担をかけていたらしく、二月ほど保養所にいなければいけなかったほどでしたが今はごく普通の学生の一人として復学しており、ときおり部室にも顔を見せています。
「元気だったか?まあ、私よりは元気かな」
「無理はしないで下さい、先輩」
上級生が姿を消して、残された剣術研の部長の立場を継いだのは汝鳥の旧家のお嬢様で、剣の心得すらない少女がその立場にあることを奇妙に思う者もいたようです。同じように旧家の生まれである春菜はといえば副部長として友人の部長を支えており、彼女たちが指導する今年の剣術研究会には、不埒な動機や好奇心を持つ者を含めたとしても新入生が増えたことは確かでした。
「部長と副部長が二人ともお嬢様ってのは強いよな」
「あら?お嬢様って認めてくれるのね」
「いやいやもちろんですとも」
おどけて言いながら、吹雪はそうした不埒者の目が春菜を見ていることにはふざけるなという思いとざまあみろという優越感の二つが混じっていることを自覚しています。もっとも彼以外の誰が彼以上に彼女のことを知っているかという、そんな幼い自信も吹雪にはありました。そしてうちの部長も副部長も、伊達に剣術研の猛者どもを率いる者ではないのです。
ですがそうした気楽な思いとは別に、新入生を預かる身として上級生の気苦労を忘れる訳にはいきません。昨年、大厄をはじめとする多くの災いに対した倶楽部の活動実績が見直されたせいか、今年の新入生は剣術研にオカミスともども例年よりも人数が多く、他県から越境して汝鳥に入学している者も少なくありませんでした。もともと異形や妖に対する技や術を営む者の存在は珍しく、それを運営する学園となれば更に珍しかったからありえない話ではないでしょう。いずれにせよ人数が増えることはありがたい一方で、それが質を保証する訳ではないことは自分たちが新入生だった頃の例を思い出しても理解できます。
新入生たちは当時の自分たちがそうであったように、他愛ない化け物が相手でも四苦八苦しながらつたない剣や術を振って、あるいは振り回されていました。上級生としては実践する場に若者たちを放り込む中で、さして危険のない相手であれば基本的に放置したまま任せておきますが手に負えなくなる寸前になれば自分たちが手を出すことにしています。斬るべき一点を斬る、ためらわずに斬る。こんなものは基本ですらない当たり前のことですが、素人に毛も生えていない連中にとってこれこそが最も難しいことは吹雪も春菜も知っていました。
あの事件以来、吹雪と春菜の仲が周囲に揶揄されるようになったことは今更でしたが、当人たちはさほど今までと変わる様子もなく対立してときに言い争い、傍目には険悪に見えることすらありました。それでも二人がごく自然に並んで汝鳥を歩く姿を見かけられていることも事実で、やわらかく暖かい日差しが差し込むようになった季節の帰り道、自転車を押している少年とその横に並んで歩く制服姿の少女の姿は、汝鳥の町並みに冬が過ぎて春が芽吹く風の音律を感じさせます。
「後ろに乗った方が早いぜ?」
「自転車の二人乗りは禁止です」
冗談めいた口調に思わず吹雪も春菜も笑いますが、心地よい春の空気に並んで歩く彼らが急ぐ理由はありません。重いコートやマフラーも必要なく、春菜の黒髪は少しだけ伸びて背に届くようになっていました。その先が季節に流れる様子を目で追いながら、吹雪は風が彼女に呼びかける声を聞いています。
討魔士としての意見の衝突、学業への興味と好奇心、他愛ない日々の話題、意味のない冗談や友人たちの噂話。そうした話題は言葉の源泉から尽きるものではなく、その中には剣術研究会の上級生として、頼りない後輩たちを導く苦労談らしきものも混じっています。深刻ではない話を交わす喜びがどれほど貴重であるか、誰もがそれを知っている訳ではありませんでした。
「それにしても、お前さんは教えるのが上手いよな」
「吹雪くんが教えるのが下手なのよ」
「だってよう、よく忍耐と辛抱が続くと思うぜ」
言いながらも、吹雪は春菜の指摘を否定はできません。間違っても吹雪は自分がやさしい先輩だとは思っていませんでしたし、他人に剣を教える面倒は昨年でもう懲りていました。一方で充分な知識と理性的な判断力を持っている春菜は下級生を教えるのも慣れたもので、実際に今年の剣術研究会は部長と副部長のお嬢様二人で持っているようなものだと言われているほどです。暴君顧問といえば新たな従僕が集まったことに満足しているだけでしたし、個人主義者を自認する吹雪のような上級生は面倒なことはお嬢様がたに任せて、自分は事件が起きた折りの実力だけで上級生であることを示しています。
春菜も学園に来た当事のように、猫をかぶって人に技を見せることを惜しむようなことはなく細身の彼女が力強い技を繰り出す様は確かに壮観で、その面倒見のよさと相まって下級生に好かれているのも納得できます。吹雪はといえばよく言っても下級生に怖がられているという程度で、事件でもなければ部室に現れず、現れたと思えばたびたび春菜と言い争っていることを思えばそれも無理はないでしょう。さぞ自分を嫌っているお坊ちゃんお嬢ちゃんも多いことだろうと自覚しながら、吹雪にはそれを正そうとする理由はありませんでした。
「まったく相性の悪いタイプというのはいるもんでね」
「そうね。いつもありがとう」
その言葉にどこか奇妙さを感じて、吹雪はおやという顔をします。これまでも春菜の言葉はときおり会話の先を見越したような返答をすることがあって、傍から聞くと会話がつながらないように感じることがありました。実際、吹雪がいう相性の悪いタイプとやらは下級生の中にも幾人かいるようでしたが、その中には女性二人が部長副部長であることを軽んじる者がいないともいえず、ときとして吹雪がそれを戒めていることを春菜は知っていました。それこそ無思慮な力に溺れる輩を無言で殴り倒すような荒っぽい「指導」を含めて、手っ取り早く権威を示すにはやはり恐怖は必要なのでしょう。吹雪があえて部室に頻繁には立ち寄らないようにしていることを含めて、彼らしい我侭な方法で剣術研を助けようと気を使っていることを春菜は知っていました。
神様の道具、すべてを見透かす雲外鏡の力などを使わなかったとしても、まったく自分が彼女を知っている以上に自分は彼女に知られているのです。それは少年にとって決して不愉快な感覚ではありませんでした。
「あらー?知らなかったの吹雪さま。春菜さまってば感応の才があるのよ」
いつだったか、忌々しい豊穣神からそう言われたことがありました。吹雪も気がついてはいましたが、春菜は異形や妖、自然霊や神様といった類に対する感性が鋭く人の心情にも鋭敏でそれこそ神様を祀る巫女にでも向いた才能を持っています。だからとっても感じやすいのよと余計な言葉を続けられて、そのときは怒りながらも吹雪の頭をとんでもない妄想がよぎったことも否定はできません。
卑猥な冗談は別にして春菜の才は生まれながらの才能といったものではなく生活と訓練の賜物であり、彼女が人より少しだけ、自然の気配や人のそぶりに慣れているというだけのことです。本来、人に備わっている筈のそれは幼いころから道場で修練を積み、書道や茶道を含めて意識を集中する術を学び、神木をはじめとする汝鳥の大いなる存在に囲われて育った春菜にとってごく自然なことでした。目で見ずとも葉ずれを聞いて風を肌に感じ、人ならぬ生き物の気配を知ることができる。
「そう言わても別に超能力じゃないし、それに・・・」
春菜自身が述懐していた、その後に続ける言葉は吹雪にも分かります。雲外鏡で見たように人の心を覗いたり、覗かれるように思われる力は御免だということでしょう。本来聴覚は視覚にすぐれ、あるいは五感を使わずとも背後に人が立つ気配を感じることはできるものです。
ですが豊穣神が冗談に紛らせながらも告げていた言葉に吹雪が聞き逃さなかったことは、彼女が人ならぬものを敏感に感じとることができるのであれば、人ならぬものも彼女に影響を与えることができるということでした。だからこそ汝鳥の神々は彼女を祝福することができましたが、それは彼女が祝福だけではなく呪詛を受けることもありうるということでした。豊穣神の言葉を重ねて吹雪は思い出します。
「だから、吹雪さまが守ってあげなさいね」
「へいへい。言われずとも彼女を守るのは俺です」
その言葉には嘘もいつわりも込めることがない。神様に言われたからではなく、彼女が汝鳥に愛されているからでもなく、吹雪は春菜の前で身を賭して守り決して顧みることがないでしょう。春菜が背に立っていることが吹雪には心強く、彼女の前に立つことが吹雪の誇りか、でなければ少年らしい虚栄心を満たすものであったとしても。
時に異形や妖に対することがあろうとも、ふだんの彼らは学生であって人が思うほどに特異な生活をしている訳ではありません。春菜は日課として学園隅にある浅間神社を祀ることはありましたし、剣術研で後輩たちを指導することもありましたがそれを除けば学業にも余暇にもふつうに励む学生でした。
「よぉ。帰るなら送るぜ」
「あら、ありがとう吹雪くん」
日が暮れた人気の少ない学園。春菜の暮らしている高槻の家は学園から汝鳥の端まで歩いた向こうにあり、吹雪の下宿先が近いこともあって送ることには不思議はなかったものの、そのときはわざとらしく待っていたことがさすがに気づかれていたかもしれません。感応がどうというものではなく、自分の行動の底が浅いことは吹雪も知っていました。ときに手をとり、ときに荷物を持って隣を歩く時間が少年には千金よりも貴重で、わざとらしく待つ理由などそれだけで充分です。
「まったく、忙しいのか知らんが娘さんが遅くまで残っているもんじゃないぜ」
「そうね。でも今日は吹雪くんがいるから」
唐突な言葉に思わず息が止まりそうになりますが、自分でも意識していなかったのか春菜も気恥ずかしそうに視線をそらしている様子を見ると、吹雪はかえって少年らしい鼓動を高めます。その時間が吹雪に貴重なものであれば、春菜にとってもそうだと思っていいのでしょうか。空気を隔てて温かさが伝わらないだろうかとでもいうように、少年は少しだけ少女の傍に肩を近づけて寄り添うように歩きました。汝鳥の境内の前を通って、木々が立つ丘を上る道。暗がりに彼らをからかうような葉ずれの音が聞こえています。
まったく彼女は汝鳥に愛されている、そう吹雪は思います。町を見はるかす古い神木の立ち姿や、ほうぼうで人に慕われている桜の木々、流れる音律の風や世俗に慣れた豊穣神、ついでに人の弱さを持つ新しき神さえも彼女には祝福を与えようとしている。
そこまで思って、ふと吹雪は気がつきます。春菜はそんな特別な存在ではない、ごくふつうに人や自然の存在に親しい少女であるというだけでした。それが好かれているのであれば、いつか話に聞いたように汝鳥の神様は彼ら自身が存在する汝鳥を助けるために、それを為そうとしている者に手を貸しているにすぎません。まったく彼女が汝鳥を愛しているからこそ、汝鳥もその彼女に応えているだけなのでしょう。祝福は一方向ではなく、神様たちはただ彼女に礼を尽くしているだけなのです。
「なあ、今度写真を撮らせてくれないか?」
「何を撮るつもりなの?」
自分も唐突に話題を持ち出していると思いながら、吹雪は日の暮れた汝鳥の月に視線を伸ばします。聞いているのが神様とお月様だけというなら、少しは恥ずかしい言葉を並べてもいいでしょう。
「汝鳥の姿を撮りたいんだ。その中に、春菜がいる姿を」
春菜を背に控えて吹雪が踏み込む、その型は必ずしも決まっているものではなくときには春菜が錫杖を手に吹雪がその背を守ることもありました。彼女がためらわずに前に出るのであれば吹雪はそれを止めるつもりはなく、吹雪に誇りがあるように春菜にも矜持があります。そして、自分が背に立つのであれば自分は必ず目の前にいる彼女を守り、傷ひとつつけぬ思いで太刀を構えます。
「吹雪くん、出ます」
「ああ、頼む」
しゃん、と音を立てて。錫杖の響きに続いて春菜が身を沈めます。彼女が手にしていた神木の杖はもとの持ち主に奉還されており、当の神木様はたいそう残念がったようですが今の春菜は樫の柄に銅環のついた杖を持っていました。柔軟な身体で彼女の意思そのままにまっすぐ伸びる、錫杖の軌跡は吹雪の踏み込み以上に迅く、それが必要なときに春菜はためらわずに彼女の技を使います。俊足の踏み込みに続いて、そのスピードと動きのすべてが乗せられた一撃が目の前の相手を貫く。深くかがみ込んでの踏み込みは春菜の技の真髄であり、吹雪の踏み込みも彼女に学んだものでした。
目の前で打ち砕かれる異形。春菜の冷徹さは完璧に近い守りと攻めを繰り出し、ためらいのない一撃が異形の妖を貫くことが彼女の手を血泥に汚していたとしても、彼女は後悔することはなく吹雪もそれを慰めようとはしません。まったく、誰かがやらねばならないことであるならば愚かな修羅と菩薩がその責を負ってやるのもいいでしょう。一撃に周囲が静まるのを待って、その心ではなく、あえてその技を称賛するように吹雪は春菜にねぎらいの声をかけました。
「それにしても流石だよ。あの冷静さは俺には真似できない」
その言葉に春菜もどこか疲れたような、ですが彼にだけ見せるやさしげな顔を向けて小さな笑みを浮かべます。
「だって、あなたが背中にいると心強いもの。いつも目の前であなたが傷つかないように、後ろで見ているのは疲れるのよ」
「・・・ああ、そうか。そうだよな」
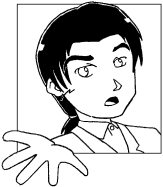
苦笑して頭をかいてみせる吹雪。つくづく、自分たちは似た者同士であるらしい。泥に浸されたぬかるみに敷くレンガの道、彼らの道は同じ場所にたどりつこうとしている。その思いは吹雪にも春菜にも今更のものでしたが、心が通うというのであれば自分だって春菜の考えていることであれば、言われずともそれを知ることができると思いました。
今日は寄り道をして帰ろう。春菜の家は汝鳥の旧家だけあって門限だって厳しいが、少しくらいなら夜道の散歩もいいだろうか。あの忌々しい豊穣神が祝福するような、胸の薄い新しい神様がどこかで覗き見ていそうな、今日が明るい月夜になるらしいことにいささか気が引けなくもありませんが、春菜も同じ気分でいるだろうことを吹雪は心の底から知っていました。
>他のお話を聞く