続あしながおじさん(新潮文庫)
ジーン・ウェブスター著 松本恵子訳
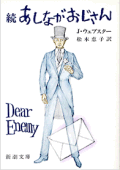 名作「あしながおじさん」に続編があるというのは聞いたことがありましたが、まさかそれがジュディ・アボットの親友サリーを主人公にしたその後のお話だったとは想像したこともありませんでした。原題を「Dear Enemy」、わたしの敵さま、とでも呼ぶべき物語は前作の主人公であるジュディが幸福な結婚をし、夫のジャーヴィスからクリスマスのプレゼントとして彼女が育ったジョン・グリア孤児院を改革する資金を受け取ったことから始まります。
名作「あしながおじさん」に続編があるというのは聞いたことがありましたが、まさかそれがジュディ・アボットの親友サリーを主人公にしたその後のお話だったとは想像したこともありませんでした。原題を「Dear Enemy」、わたしの敵さま、とでも呼ぶべき物語は前作の主人公であるジュディが幸福な結婚をし、夫のジャーヴィスからクリスマスのプレゼントとして彼女が育ったジョン・グリア孤児院を改革する資金を受け取ったことから始まります。
ジュディが白羽の矢を立てたのは彼女の大学時代の親友サリー・マクブライドで、リペット院長に替わり彼女を新しい院長として孤児院の改革を頼むことにしました。サリーは驚きあきれながらもジュディへの手紙に記します。ペンデルトンの家族会議であなたたちが何を言っていたか目に浮かぶようだ、サリー・マクブライドはもっと有意義なことに時間を使うべきで若い政治家なんかにうつつを抜かしている場合ではない、どうか私を招待するなら孤児院ではなくニューヨークの劇場やオペラや晩餐会にしてほしい、と。
前作と同様、サリーの書簡集として綴られる作品では結局院長を引き受けることになった彼女が100人を数える孤児たちの母親として、陽気に彼女らしく改革を進めていく様が描かれます。裕福な家庭で何不自由なく育ったと自認するサリーはだからこそ普通の子供が普通に与えられるべきものを充分に心得ていて、女の子には陰気なギンガムの服ではなく魅力的な服やリボンを与え、男の子は紳士らしくしつけながらも枕投げで遊ぶ元気さに喜ぶといった、どこか孤児院の院長らしくない姿に魅力と共感を覚えるでしょう。
作者自身の問題提起でもある、当時の孤児院に対する指摘に鋭さを感じさせるのも前作同様ですが、新しい生活に戸惑うジュディの姿を通して映し出されていたそれが今作ではそれを改善するためのサリーのアイデアとして提示されているのはこの二作品の面白いつながりとなっています。サリーがジュディに宛てた手紙にときおり現れる「ジルーシャ・アボットのようにみじめな子供時代を孤児たちに送らせるべきではない」という言葉が実に生々しく感じられますが、同時にジュディが自分の前半生をサリーに語ったのだろうことを思わせて彼女たちがどれほど互いを信頼しているかを窺わせてもくれます。これだけのことを言い切れる仲であるからこそ、ジュディは彼女に孤児院を託したのでしょうしサリーもそれを承知したのでしょう。
タイトルにある「敵さま」とはジョン・グリア孤児院を改革するにあたり、サリーを助けるべくペンデルトン夫妻が紹介したスコットランド人の若い医者のことで、名前はロビン・マックレイ。気難しく頑固で無口、ささいな事で気分を害する怒りんぼうのドクトルに宛てて、サリーはたびたび彼に宛てた手紙を「敵さま」と書き出してからかいます。このたくましいユーモアのセンスと行動力、たまには揺らいでしまう孤児たちへの愛情と、ドクトル以上に頑固で力強いサリーの改善活動によって孤児院は日々様相を変えていくことになりました。
院長室を住みよく模様替えすることから始めて食堂は明るい色にぬりつぶして陰気な標語はウサギの絵に替えてしまい、庭に出ても遊ぶ方法すら知らない子供たちに野外の遊びやキャンプを覚えさせる。彼らが社会に出て迷わないように家庭の暮らしや仕事を体験させたり、買い物からお金のやりくりまで学ばせる。その発想は堅苦しい更正プログラムなどではなく、ふつうの子供が大人になるまでに学ぶことをすべて体験させてやろうというものです。その彼女を助けるスコットランド人のドクトルは、たびたびサリーを辟易させますがどれほどの医療の手を孤児院が必要としているかを教えてくれると同時に医者にとって必要な子供たちへの献身も見せてくれます。どうにも遺伝や精神的な疾患に対して口やかましいドクトルですが、その背景には意外な理由があることをサリーは知ることになりました。
物語は孤児院を中心にしながら評議員や村の周囲の人たち、国会議員でサリーの恋人である青年ゴルドン、大学時代の友人たちといった様々な人々が現れてはサリーに感化をもたらしていきます。ジョン・グリアを模範的な孤児院にすべく奮闘していく中で、院長として多くを学ぶだけではなく人生を過ごしていく目的や楽しさを見出した彼女が替えがたい愛情を見つける、最後が暖かく甘いエピソードで終わるのもまた「あしながおじさん」の続編らしいかもしれません。
おそらく当時の知識や認識なのでしょうが、遺伝や精神疾患に対する誤解が一般的な学術的常識として描かれているためにどうしても差別表現を思わせてしまい、改訂も新訳もしづらい事情になっているようです。とはいえ当時の時代の中で孤児たちの暮らしを改善してよりよく感化していこうとするサリーやドクトルの正義感に偽りはなく、では現今の児童福祉は差別が横行した当時よりもマシになっているのかと問えば比較するものでもないでしょう。子供に対する愛情が本来、同じものであるならば手法や表現はその時代の文化に向いたものでしかない筈です。
当時の孤児たちを取り巻く環境に対する問題提起と人生そのものに対する愛情。その二つがテーマである点でこのお話はやはり「あしながおじさん」の続編と言えるのだと思います。ジュディ・アボットの場合、彼女の愛情はごくありきたりな生活を送ることができることにどれほどの価値があるか、家族の存在がどれほど人を支えるかを考えさせてくれましたが、サリー・マクブライドの場合はどうだったでしょうか。意義のある人生とそれを共有する理解者の存在、青年ゴルドンには気の毒ですが、愛情に最も必要なものは理解をすることなのでしょう。
恋愛物語というにはサリー・マクブライドの愛情は何より孤児院に注がれていますから、その後も彼女たちのにぎやかな生活が続くのだろうと思わせますが、それにしても頑固で気難しいスコットランド気質と思わせるドクトル・ロビン・マックレイ、たぶん彼自身は自分で気がついてもいないでしょうが、ほぼ全編を通じてサリー・マクブライドにいいようにあしらわれ続けているのを見ると男性というものが実にほほえましくも気の毒な生き物に思えてきます。
>他の本を見る

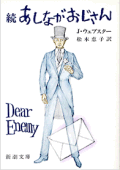 名作「あしながおじさん」に続編があるというのは聞いたことがありましたが、まさかそれがジュディ・アボットの親友サリーを主人公にしたその後のお話だったとは想像したこともありませんでした。原題を「Dear Enemy」、わたしの敵さま、とでも呼ぶべき物語は前作の主人公であるジュディが幸福な結婚をし、夫のジャーヴィスからクリスマスのプレゼントとして彼女が育ったジョン・グリア孤児院を改革する資金を受け取ったことから始まります。
名作「あしながおじさん」に続編があるというのは聞いたことがありましたが、まさかそれがジュディ・アボットの親友サリーを主人公にしたその後のお話だったとは想像したこともありませんでした。原題を「Dear Enemy」、わたしの敵さま、とでも呼ぶべき物語は前作の主人公であるジュディが幸福な結婚をし、夫のジャーヴィスからクリスマスのプレゼントとして彼女が育ったジョン・グリア孤児院を改革する資金を受け取ったことから始まります。