炉辺荘のアン(新潮文庫)
ルーシイ・モード・モンゴメリ著 村岡花子訳
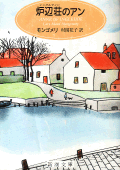 原題はアン・オブ・イングルサイド。新潮文庫の邦訳版では第七作目とされていますが、アンの幸福から三年後の1939年に出帆されておりアン・シリーズでは最後に書かれた作品でもあります。物語はアン・ブライス夫人が新婚生活を過ごした彼女たちの夢の家を後にして、炉辺荘に引っ越して数年がした後のお話。アンとダイアナの語りからはじまるあたりがいかにもシリーズらしさを窺わせますが、内容はブライス家の子供たちと女中のスーザン・ベーカーを中心にした「アンと彼女の家族たち」が主体になっています。
原題はアン・オブ・イングルサイド。新潮文庫の邦訳版では第七作目とされていますが、アンの幸福から三年後の1939年に出帆されておりアン・シリーズでは最後に書かれた作品でもあります。物語はアン・ブライス夫人が新婚生活を過ごした彼女たちの夢の家を後にして、炉辺荘に引っ越して数年がした後のお話。アンとダイアナの語りからはじまるあたりがいかにもシリーズらしさを窺わせますが、内容はブライス家の子供たちと女中のスーザン・ベーカーを中心にした「アンと彼女の家族たち」が主体になっています。
夢の家で産まれたジェイムズ・マシュウ以外は炉辺荘で産まれた子になる訳ですが、ウォルターに双子の姉妹ナンとダイ、スーザンの愛情やまないシャーリーと末娘のバーサ・マリラまで、繊弱なアンがこれだけたくさんの子供たちを抱えていることに驚かされました。もちろん原版の発行順を考えれば「虹の谷のアン」が出版されてから二十年後になる訳ですから、アンの子供たちの存在も当時は知られていて当然ではだったのでしょう。子供たちの名前がアン夫人にまつわるものばかりで、ギルバートの親族の名前がどうにも見当たらないのは彼らの性格でしょうか。この年齢になっても想像力では人後に落ちない夫人とそれを崇拝する夫を思えば無理もないとも思えます。
男の子らしい冒険心に恵まれているジェム、母親すら認める生まれながらの詩人であるウォルター、想像力たくましい美人のナンに父親お気に入りの赤毛のダイ、幼いシャーリーに小さなリラ。にぎやかで愛情と想像力にあふれている炉辺荘の生活はいかにもアンらしい、アンの理想の生活を思わせてくれます。自分が幼い頃の記憶を貴重なものと考えているアンは子供たちにとって理解のある母親で、傍目には滑稽にしか見えない子供たちの事件や真摯な悩みを決して笑うこともなく受け止めててくれる、彼女がいるからこそ危なっかしい子供たちを安心して見ていられることができるという微笑ましい暖かさが作品の魅力でしょうか。
とはいえアン夫人はどうにも子供たちに理解がありすぎるので、マシュウやマリラのように完璧ではなく誤解を受けることがあっても変わらない愛情、を窺わせることができないのはちょっと気の毒かもしれません。そのせいかアン自身の存在感は彼女が悩むエピソードでどうしても強くなってしまいますが、長い結婚生活に行き詰まりを感じる最後のエピソード、が強く印象に残る一方で物語の流れとしては唐突に感じられたのも正直なところです。
穿った見方かもしれませんが、「虹の谷のアン」で子供たちにとって理想の母親になりすぎてしまっているせいで子供たちの生活でも必ず最後には母が助けてくれる、母が話を聞いてくれると感じてしまいスリルに欠けるところがなくもありません。個人的にはアン・ブライスも子供たちの求めていることを理解できない、もどかしさを感じさせてくれた方が決して完全でなくとも愛情には疑いがない、グリン・ゲイブルスの心地よさを感じさせてくれたのではなかったでしょうか。もちろん作者の十八番である日常の素朴な描写、中年や老年の婦人たちの語らいや子供たちのいきいきとした生活感は健在で、ウォルターが婦人会での井戸端会議を延々と聞かされるエピソードなどは作中でも逸品となる愉快な楽しさを感じさせてくれます。
全体の構成では作中の時間の流れと、それを実感するアンの様子が軸になっているようですが「虹の谷のアン」ほどには物語の中心が時を経て移っていく流れにはなっていないのはちょっと残念なところです。それでもジェムやウォルターの生活に始まり、季節の巡りを思わせるクックロビンのエピソードなどを挟みながらごく自然にナンやダイが中心に移っていく様は子供たちの成長の早さと、男の子がより早く母親の手を離れていく時の流れを感じさせてくれました。作中で生まれる小さなリラが、もうすぐ学校へ行くようになる頃には子供たちがいつまでも自分のものではないことを嘆いてみせるアンの思いに、共感すると同時に留まらないからこそ愛しいものも思わせてくれるのではないでしょうか。
もちろんファンであれば薦めるに迷う作品ではありませんが、時間軸ではこの前後になる「夢の家のアン」や「虹の谷のアン」に比べると物語の中心がアンなのか子供たちなのか些か分かり難く、シリーズを読んだことのない人には伝わり難いかもしれません。あるいはこの作品も「アンの愛情」以上にブライス夫人や子供たちではなくギルバート医師の視点を中心にして書いてくれたらより新鮮な面白さを味わうことができたのではないでしょうか。グレン村で多くの住民や患者たちを助け、ギルバートやギルバティーンと名付けられた子供が増えたというほど慕われているギルバート医師は家の中でも夫人や家族の愛情に支えられながら、こと仕事に関する悩みだけは当人が先鋭的な人であるだけに打ち明ける相手が少ないのはいかにも気の毒に思えます。
とはいえ、家族相手にまで仕事の話をしたくないという感情だってもしかしたらあるかもしれません。グレン村ではいつでも彼を呼ぶ電話が鳴り止まず、当人やアンまで肺炎で倒れることがあったりと休まる暇がなさそうなギルバートにとっては炉辺荘の家族たちは何よりの支えになっているでしょう。メラリー・マライアおばさんの一件ではちょっと頼りないところを見せてくれますが、親族を身びいきしながらも辟易して、思わぬ原因でおばさんが帰ることになって安堵する姿にはかえってよく出来た父である筈のギルバートに人間らしい親しみを感じなくもありません。息子に対して僕の奥さんは素敵だろう、と言うときの誇らしそうな顔を思えばアン・ブライスが変わらないようにギルバート・ブライスも年を重ねても変わらない魅力を持ち続けているのだと思います。この人の視点で見た作品を読んでみたいと思わせたのは、先述したとおり「アンの愛情」とこの作品ですね。
でも一番印象に残っている科白は「芥子をとってくれ」です。
>他の本を見る

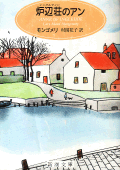 原題はアン・オブ・イングルサイド。新潮文庫の邦訳版では第七作目とされていますが、アンの幸福から三年後の1939年に出帆されておりアン・シリーズでは最後に書かれた作品でもあります。物語はアン・ブライス夫人が新婚生活を過ごした彼女たちの夢の家を後にして、炉辺荘に引っ越して数年がした後のお話。アンとダイアナの語りからはじまるあたりがいかにもシリーズらしさを窺わせますが、内容はブライス家の子供たちと女中のスーザン・ベーカーを中心にした「アンと彼女の家族たち」が主体になっています。
原題はアン・オブ・イングルサイド。新潮文庫の邦訳版では第七作目とされていますが、アンの幸福から三年後の1939年に出帆されておりアン・シリーズでは最後に書かれた作品でもあります。物語はアン・ブライス夫人が新婚生活を過ごした彼女たちの夢の家を後にして、炉辺荘に引っ越して数年がした後のお話。アンとダイアナの語りからはじまるあたりがいかにもシリーズらしさを窺わせますが、内容はブライス家の子供たちと女中のスーザン・ベーカーを中心にした「アンと彼女の家族たち」が主体になっています。