** Call of Cthulhu! Scenario#2:The Fire and Collapse **
『昨今の我が国の科学技術の進歩と社会の興隆には目を見張るものがあり、1927年には我らアメリカの英雄チャールズ・A・リンドバーク氏がニューヨーク市からパリまでの無着陸単独飛行に成功した。この歴史的大事件がいかにセンセーションと熱狂を巻き起こしたかは未だに諸君の記憶に新しいところである。
また1921年のファンダメンダリストの誕生、そしてその数年後の、テネシー州デイトンの高校教師であるジョン・T・スコープス氏の、進化論の授業にまつわる所謂モンキー裁判も、もはや人々が盲目的で素朴な信仰の世界には決して生きてはいない事、それが自明であるにも関わらず、いやそうした世界がすでに崩壊しつつあるからこそか、そのような古く非科学的な世界にに固執する側からの反撃と抵抗が、いかに苛烈なものなのかをまざまざと示すものである。
繰り返し言うが、我々の生きる社会の発展はこの数十年前では夢想だに出来なかった程である。今や街中の通りという通り、道路という道路がフォード氏の起こした奇蹟により、さながら大河の流れの如く、この輝かしいフォードの新型車で埋めつくされているのである。そして街中を見渡せば未だ世間は厳格な禁酒法の法化にあるにも関わらず、人々は科学と工業がもたらす新しい社会からの風にからに浮かれ、騒ぎ、酔いしれている。
このような時世において、私がこれから諸君に語ることはいささかの合理性も持たず、単なる夢遊病者の戯言のように受け止められるかもしれない。人々は言うだろう、私があの古き佳き時代のイギリスの血流を汲むチャップマン邸へのごく僅かな滞在時間に体験した出来事 ー天災による突然の屋敷の崩壊と、それに伴う火災により著しく精神に混乱をきたしたー の為、このような荒唐無稽な幻覚を、あたかも現実の出来事であるかのように認識したのだ、と。
しかし、私があの不幸なイギリス貴族の末裔と、そのもっと不幸な、彼の忠実な執事が引き起こした悲劇 ーそう、あれは紛れもない悲劇であったー は、決して空想の夢物語などではなく、私が悟ったこの世界の根源的な深淵はまさしく真実の事である。どうか、勇気ある読者の諸兄は恐れを抱くことなくこれから語る物語を、実際の事として、そして、未だ公開されざる脅威に対する私からの警告として受け止めて欲しい。
この物語を、昔も今も変わらず、私に親愛なる愛情を捧げてくれる、E・フェイタルズに捧ぐ。
エドワード・B・ヘイズ【炎上と崩壊の狭間で】 1928年アメリカ』
とある夕刻、森をまっすぐに突っ切っている街道を一台の車が走っていた。フォード・モデルAは世界的に普及した黒塗りのモデルTに比べるとより近代的で洗練された車体をしていたが、残念なことに社運を賭けたフォードの後継機としては成功したとはいえず近年はゼネラル・モータースの攻勢に押されている。
若いエドワード・ヘイズは職業的な視点で、彼を同道させてくれた二人に好奇と憶測の視線を向けていた。売れない小説家をしている彼はニューイングランドの辺地にあるインスマウスの漁港に取材旅行に赴いていたが、この町は余所者に極めて排他的でろくな成果も得られないうちにボストンに帰るバスの時間を逃してしまうと、町に引き返すつもりにもなれず途方に暮れかけていたところで街道を走る赤い車体から声をかけられた。後日、この時のエドワードが極めて強力な守護聖人に助けられたことを知るのは彼が再びインスマウスを訪れたその時のことである。
車は海岸線を離れて内地に入ると背の高い杉の古木に挟まれた街道をひたすらまっすぐに進んでいる。運転席でハンドルを握っているキャサリン・ブルックは落ち着いた年齢の独立した女性で、最近まで遠縁の伯父の秘書をしていたが今は休暇と称して友人との気ままな旅を楽しんでいるらしい。なんでも「悪霊の家」と呼ばれる奇怪な屋敷の調査に赴くと散々な目に遭わされたというが、仕事を離れて静養することに決めたというのだからよほどひどい目に遭ったのだろう。広い後部座席には彼女の友人というヘンリー・マグワイア氏が背もたれに身を預けているが、その件については彼も口が重いままで詳しくを語ろうとはしなかった。
「それにしてもずいぶん霧が出てきましたね」
窓ガラスがあることを感謝するかのようにエドワードが呟く。起伏の多いバス通りとは違い、街道はまっすぐで見通しも良かったがそれにしてもまっすぐに過ぎて見えるのは彼らの視界を遮るようになった濃い霧のせいだろうか。エドワードが近年執筆するも評価を得たとは言い難い掌編「黒い霧」とは違って彼らの足を止めているそれは深いミルク色をしている。とうとうたった10フィート先も見えなくなってしまうと、これで対向車でも来たらたまらないと車を脇に停車させる。どうしようかと思案したところで、道の脇にある木々の向こうに小さな明かりがぼんやり灯っているのが見えた。家でもあるのであれば、このまま車中で夜を明かさなくても済むかもしれない。
三人で車を降りるとひやりとした霧が肌と服を濡らす。明かりが見える方角に向けて杉の葉の地面を踏んでいくが、霧はますます深くなってどの程度進んだのかも分からない。視界の向こうにある明かりも小さく見えるままで、さすがに不安になったところで動物がうなるようなぐるるという声が聞こえてきた。エドワードはちょうど彼の怪奇小説の冒頭が霧深い林に聞こえてくる狼のうなり声であったことを思い出す。
「なんだ、黒い霧の冒頭そのままじゃあないか」
行幸というべきであろうか、エドワードの本を読んでいたらしいヘンリーの軽口にやめなさいよ、とキャサリンが窘める声が聞こえるがすぐに小さな悲鳴に変わる。危ないと言う間もなくとびかかったのは霧中から現れた狼ならぬ飢えた黒っぽい痩せ犬で、首輪もなくあばらが浮いて、そしてよだれをだらだらと垂らしていた。ヘンリーがキャサリンをかばおうと身を乗り出して、霧深い中で彼女の手を引くと咬みそこなった牙が霧の向こうに落ちていく。唐突に怪奇小説の一場面に放り込まれたエドワードも、女性を前にして紳士たろうと痩せ犬の前に立つが武器にならないかとバッグから取り出した重たい辞書ではあまり役に立ちそうもない。男たちの背に隠れたキャサリンは一歩二歩と後ずさるが、その背後からもうなり声が聞こえると霧の中からもう一頭の痩せ犬がとびかかって、とっさにかばった腕に牙が突き立てられた。
「きゃああっ!」
「キャシー!」
向き直ったヘンリーの右手には拾ったらしい石が握られていて痩せ犬に思い切り投げつけられる。固い石が驚くほど正確に犬の眉間に命中すると、ごつという音と奇妙な悲鳴が聞こえてどさりと倒れた犬がそのまま動かなくなった。驚いたもう一頭は文字通りしっぽを巻いて霧の中に消えてしまうと、エドワードが呆気にとられている間に唐突に起きた立ち回りは唐突に終わっていた。記録者である彼自身はこの場面で何もすることができなかったが、ヘンリーのような小説の登場人物に足る人物が世の中に存在することを知らされる。
キャサリンは思ったよりも深く咬まれたらしく腕を抱えていた。霧中で襲われると車も明かりも見失ったことに気がつくがうなり声や遠吠えはまだそこらから聞こえていて、どのくらい近くにいるのか遠くにいるのかも分からない。霧はますます深くなり、お互いの姿も見えなくなりそうに思えるとエドワードはしぜんに二人に身を寄せるが、そのような自分がずいぶん頼りない存在に感じられて鼓動と息づかいばかりが荒くなっているのが分かる。これではいけないと思い、婚約者の姿を思って自らを奮い立たせたエドワードが虚勢でも胸をそらせてみせると、視界の向こうにぼんやりとした明かりを灯している一軒の古めかしい洋館の姿を見つけることができた。
野犬の襲撃から洋館を見つけるまでの流れはシナリオの導入として、まずは戦闘と正気度判定の双方を体験してもらうことを目的にしている。そのため痩せ犬のデータはルールブックの犬よりも弱くしているが、探索者の戦闘能力が高い場合は狼にしてもいいだろう。ヘンリーへの咬みつきがいきなり避けられたのも投石一撃で倒されたのも想定外で、エドワードならずとも感心するしかないが、実はこの戦闘のもう一つの目的としてCoCでは探索者の耐久力がとにかく少ないことを知ってもらうことと、後で救急箱を渡すために誰かに怪我をしてもらうことが前提になっている。そのため一頭で探索者を傷つけられないときはもう一頭が背後から襲ってきて、しかも不意打ちになる初回の攻撃は必ず命中することになっている。犬たちは探索者が一人でも怪我をして、仲間が一頭でも倒されるとすべて逃げていく。
野犬が逃げて行ったあと、霧の中で明かりも車も見失った探索者は不安になり正気度判定(0/1)を行う。その後で目星や聞き耳の判定で明かりを探すことができるが、失敗した場合はもう一度正気度判定からやり直すこと。
痩せた野犬
STR06 CON08 SIZ04 DEX12 POW04
咬みつき:20%ダメージ1d3(ただし初回攻撃のみ自動的に成功)
洋館はニューイングランドらしい英国風の伝統的な様式で建てられている二階建ての建物だが、見上げてみるとすべての窓に鉄格子がはめられていて奇異に思えてしまう。両開きの玄関にはノックをするための金属製の輪がぶら下がっていて、重い銅製の輪を握って扉を数度たたくとしばらくしてから「お待ちください」という声が聞こえて扉の向こうでがしゃがしゃと鎖を外す音が聞こえてくる。重くきしみながら扉が開き、隙間からやたらと背が高い初老の男が現れると開口一番こう言った。
「おや、これは珍しい」
男はこの館で執事を務めているクリーズと名乗るといきなりの非礼を詫びる。何しろこのような辺鄙な場所に暮らしているから人が来るなど滅多にないが、霧のせいか数刻ほど前にも別の客人が訪れていたこともあって思わず珍しいなどと呟いてしまったらしい。エドワードが正直に事情を話すと、すぐに救急箱を用意する旨と館にはまだ空いている部屋があるから朝まで泊まっていってはどうかと勧められた。チャップマン様も喜ぶでしょう、とはどうやら館の主の名前らしく、あとはペリンが案内しますと、長身の老人の傍らに影のように控えていた召使いの小男に任せると自分は客人が来たことを主人に伝えてきましょうと一礼して背を向ける。
ペリンは丸まった背が更に小柄に見える陰気そうな小男で、ねめあげるような視線は彼の癖らしい。彼に従って二階への階段を上り、部屋が二つ空いているから男性は一人部屋を、女性は一人部屋をお使い下さいと案内される。手前にある部屋には先ほど執事に聞かされた先客の男がいて、ペリンがノックするとくたびれた背広を着た中年男が顔を出す。ギリアムと無愛想に名乗った男はすぐに部屋に戻ってしまい、そのまま奥の部屋にキャサリンを案内すると、いったん階段の近くまで戻ってからエドワードとヘンリーも二人部屋まで案内される。二十時頃に軽い食事を用意するのであまり部屋を離れないで欲しいと伝えると、ペリンは救急箱を取りに階下へ下りて行ってしまった。
客室は掃除も整頓も行き届いていて、ベッドにタンスにテーブル、引き出しのついたサイドボードや帽子掛けなど古めかしいが伝統的な家具が揃っている。棚の上には燭台が置かれているが、明かりは電灯が灯されているのでろうそくに火はついていない。壁面には洗面台が据えられていて、窓にはやはり鉄格子がはめられている。重々しいマホガニーの柱時計を見ると針は十九時を指していて、古い美術品に興味のあるエドワードが幾つかの家具を感心して見てまわるとどれも三十年以上は昔の伝統品らしい。前世紀の工芸品に触れる感傷に身を浸していたエドワードの耳に、ふとヘンリーが呟く声が届いた。
「エド、何か聞こえなかったか」
耳をそばだててみるとヘンリーの気のせいではなく、確かに何かこつこつと窓を叩くような音が聞こえてくる。だが二階の窓をいったい誰が叩くのだと、気味が悪く思いながら窓枠に近付いてみると夜霧の中に浮いている白っぽい姿が目に入った。それは金髪を長く伸ばした若い女のようで、シーツのような薄布の裾がはたはたとなびいていて、そして宙に浮いた彼女の姿は透き通って後ろの木々が見えていた!思わずあっと声を上げたエドワードだが、霧中で痩せ犬に襲われたときはあれほど恐ろしかったのに目の前の女からは奇妙に怖さも嫌悪感も感じない。女は窓の向こうからかすかに届いてくる声で、明かりを消してくれとひたすら繰り返しているようだった。
背中からヘンリーがどうしたと声をかけてくるが、説明するよりも一見した方が早いとエドワードが部屋に戻って明かりを消すと暗くなった室内に女がうっすらと姿を現した。幽霊としか思えない女を見てヘンリーが思わず口を開く。
「ああ、ノックはしてほしかったかな」
「ヘンリーさん!冗談を言っている場合ではありません」
二人のやり取りには構わず、幽霊はとりとめもなく話し出す。こちらの声はあまり聞こえていないらしく、ただ延々と言葉を綴るがエドワードが携えていた万年筆と手帳を手に、達筆とは言い難い筆致で言葉の断片を書き留めると彼女がコニーという名前であることと、彼女の身に起きたらしいおぞましい出来事が記されていく。私は殺された、この館から逃げなければならない、血の色をした液体を干してはいけない、二時には恐ろしいことが起きた、三時にはもっと恐ろしいことが起きた、ナイフ、本、触手、死・・・意味の分からない言葉も多く、詳しい話を聞きたかったが扉を叩く音がすると幽霊は掻き消えるように姿を消してしまう。ノックをする音が何度か続き、エドワードが扉を開けると救急箱を手に奇妙な顔をしたキャサリンが立っていた。
何かあったの、と言われて慌てて明かりをつけるがこんな話をいったいどう説明したものかと口ごもる。どうも幽霊に出くわしたらしいと、背後からヘンリーの正直過ぎる説明が聞こえると思わず振り返るエドワードだが、平然としているヘンリーと、気味が悪そうな顔をしながら友人を疑っている様子もないキャサリンを見て彼らがこのような事件に遭うことが初めてでないことに気づく。作家が知らない、お伽噺や怪奇小説めいた事件が本当に存在すると知ってエドワードはそれまでの恐怖に勝ってがぜん好奇心がわいてきたことを自覚する。彼が執筆する怪奇小説の世界では、たいてい彼のような好奇心が過ぎる人物は犠牲の祭壇に乗せられるのが常だった。
客室は三部屋あって一つはギリアムが、残る二つが男女別に探索者に割り振られる。部屋を調べると置かれている家具が一様に古く三十年以上前の伝統品であること、窓にはすべて鉄格子がはめられていて外に出ることはできないことが知れる。窓に鉄格子がはめられていたり玄関に鎖がかけられている理由は単に防犯用で古い屋敷に後から取り付けたものだからだが、シナリオ的には逃亡阻止のためで鍵開けによる脱出をほぼ不可能にするため。
幽霊はかつてこの館で殺された女性で、警告するために現れて明かりを消すと部屋の中で話を聞くことができるが一方的に話すだけなので会話はできないし、それほど大した情報を得ることもできない。会話は1d6で聞くことができて同じ目が続くと部屋に人がやってきて終了になる。ほとんどはとりとめもない内容だが6が出たときには血の色をしたグラスには口をつけないようにとの警告が、5が出ると館に地下室があるらしい情報が手に入る。1が出たときには言葉とともに彼女の姿が血まみれになって正気度判定(0/1)が必要になる。ちなみにリプレイ中には236の目が出ていた。
1:私は殺された、血だらけになって殺された
2:この館から逃げなさい
3:二時には恐ろしいことが、三時にはもっと恐ろしいことが起きる
4:私は殺された、霧深い夜に殺された
5:私は殺された、縛られて地下で殺された
6:血の色をしたグラスには口をつけないで
キャサリンを部屋に入れるとヘンリーが救急箱を開き、慣れた手つきで野犬に咬まれた腕を消毒して包帯を巻きつける。破れた袖は台無しになってしまったが着替えは彼女の車の中にあるからどうしようもない。それでも痛みは引いたらしく、息をついたところで再び扉を叩く音がするが部屋の外に立っていたのは召使いのペリンではなく中年男のギリアムだった。ギリアムは世間話を装っているが、大学で心理学を学んだエドワードならずとも不自然な様子が隠せずにいる。先方にも思うところがあったのか、自分から帽子を脱ぐことにすると誰にも言わないでくれと念を押した上で自分が刑事であることを明かす。なんでもこの近くで旅行者が三人も行方不明になる事件が起きていて、ギリアムはその捜査に当たっているらしい。
いなくなった三人は時期も出身も年齢もまちまちだが、エリックとジョーンズとコニーという名前を聞くと思わずエドワードの表情が変わる。見とがめたギリアムが眉を上げるがまさか幽霊の名前だなどと言うわけにもいかず、何か分かったことがあれば伝えますと約束したところでちょうど階段を上ってくるペリンの足音が聞こえてきた。どうやら食事の用意ができたらしい。
全員が階下に案内される。食堂にはやはり豪華で伝統的な家具が並んでいて中央にはクロスのかけられたテーブルと椅子、壁際には大きな暖炉があって壁には何枚かの肖像画が、部屋の隅には立派な甲冑がひとそろえ置かれていた。客室にあったものと同様にこれらの品々も三十年以上は昔の前世紀の品であることがエドワードには分かる。上席には口髭を生やした上品そうな男が腰を下ろしていて、傍らには若い主人に仕えるかのようにクリーズが控えている。この男が館の主のチャップマンであるのだろうが、開かれた唇から洩れる言葉が不自然なほど抑揚も感情もない人形めいていて心中驚かされる。
「ようこそおこしくださた。ゆくりしていてください」
テーブルに並べられている食事はごくかんたんなもので、パンとチーズとサラミとクラッカー、それから人数分のグラスが並んでいる。主のチャップマンは年齢が三十歳ほどの口髭を生やした紳士だが、やけに無表情で原稿でも読み上げるような口調も気味が悪い。会話を引き継いだクリーズの説明によると、チャップマン家は英国で騎士の称号を得た名士で入植初期の時代に米国に移住したらしい。壁にかかっている肖像画は代々の当主のもので、一番右にある一枚が確かに目の前の男によく似ていた。クリーズが話している間もチャップマンは人形のように無表情でいるが、執事の言葉に時折うなずいたりしているので聞こえていないわけではないようだ。
皆様はどのようなお仕事をなさっているのですかと尋ねられると、ギリアムは返答を用意していたらしく日用品のセールスマンをしていると答えていた。エドワードは別に素性を隠すつもりもなく、正直に答えるとクリーズは興味を持ったようで自分も怪奇小説の類が好きで、何冊か図書室に置いてあるのでよければ見ていくとよろしいと薦められる。エドワードやキャサリンは一も二もなく快諾していたが、ヘンリーなどは怖がりのくせに怪奇小説に目のない友人に心中呆れている様子が窺えた。
ひとしきり話題の花が咲いたところで、食事が始められてもいないことに気づいたクリーズが慌てて謝罪をすると年代物らしいワインの瓶が用意されるのを見てエドワードはおやと思う。禁酒法が通達されたこの時代でも、酒を違法に扱う者たちは後を絶たなかったがこれだけ堂々と客人に振る舞う例は珍しい。
主のグラスに赤い液体が注がれると、ギリアムは彼が刑事であることを隠すためか彼の職業倫理が薄れたためかはわからないが同じ酒を注いでもらう。幽霊の話を思い出していた三人は思わず目配せをすると、血の色をした液体を見て大丈夫だろうかと思うがまさか幽霊に警告されたなどと言えるわけがない。適当にごまかした彼らの前にはもう一本用意されていた白ワインや珈琲のカップが並べられた。
「我々の一夜の出会いに」
グラスが傾けられる様子を思わず注視するが、のどに緋色の液体を流し込んだチャップマンもギリアムもとりたてて奇異な様子は見られず安心したような拍子抜けしたような気分にさせられる。チャップマンは早々に席を立つと無表情のまま自室に引き上げてしまったが、クリーズはしばらく歓談に付き合って老人に夜は堪えますなと言い出した頃には時計の針も二十二時を指していた。
まずプレイ中にはすっかり失念していたが、シナリオの舞台は1928年に設定されているので当時は禁酒法の真っ盛りである。ただし主と執事の二人は三十年以上前にここで暮らすようになって以来、外界とは殆ど接していない生活を送っていたのでいずれにしても禁酒法のことは知らないままでいる。ワインは法律が決まる以前に作られた逸品で、たとえ禁酒法のことを知らされたとしてもここだけの話にしましょうといって彼らはワインを振る舞おうとする。探索者が遠慮した場合は白ワインか珈琲を頼むことができるが、よほど説得しない限りギリアムは赤ワインを飲もうとする。ちなみにシナリオとしては彼は足手まといとして登場しているので、ギリアムが赤ワインを飲むのを阻止してもあまり助けにはならない。
実は赤ワインには睡眠薬が入っていて、チャップマン以外の者がこれを飲むと二十四時頃から猛烈な眠気に襲われてそのまま目が覚めなくなってしまう(チャップマンには睡眠薬の効果がない)。また赤白を問わずワインを飲んだ者は耐久力x5判定に失敗すると酔いが回ってしまい、すべての判定に−10%のペナルティを負うことになるので注意(ここではキャサリンが判定に失敗している)。
ギリアム 50歳男・刑事
STR10 CON10 SIZ10 DEX10 APP10 INT14 POW04/SAN20 EDU10
目星50・聞き耳50・応急手当50
食堂の壁にかけられている肖像画は調べてみると生年が書かれていることに気づくことができて、チャップマンのものと思われていた肖像には1868年、六十年前の日付が書き込まれている。この記述が正しければ彼は執事とさして変わらない年齢の老人ということになるが、このことについてクリーズに正した場合は肖像が亡くなった先代のものであると説明する。他には立てかけられている甲冑が手にしている剣は武器として持っていくことができるが、このシナリオではおそらくほとんど役に立たないだろう。
ちなみに本シナリオはFFゲームブック「恐怖の館」を原案にしているが、内容やイベントはほぼオリジナルに書き直しているので挿絵以外はあまり参考にならないだろう。登場人物の名前はいわずと知れたモンティ・パイソンの各メンバーから拝借しているが、幽霊の名前は当初キャロルにしようとしたもののキャサリンと被るかと思いコニーにしているのはわりとどうでもいい余談である。
軽い食事と歓談を終えると、薦められた通り二階の図書室に案内してもらったエドワードたちは立派な本棚に並べられている物語や記録の数々に目を奪われてしまう。零時には明かりを消すのでそれまでには部屋に戻って下さいと言ったペリンが階下に引き上げると、エドワードもこの時ばかりは深い霧のことも幽霊のことも忘れて並んでいる旅行記や事典の物色を始めてしまう。キャサリンが嬉しそうな声で怪奇譚「地を穿つもの」の初版を見つけたとはしゃいでいる声が耳に入り、かの本は今夜彼女のベッドに同伴する栄誉に浴することができるらしい。彼女の趣味はともかく、本棚を眺めていて奇妙に思ったのは収められている本がどれも古いもので少なくとも三十年は昔のものばかりであることだった。新しい本は自室にでも置いているのだろうかと思い、数冊をめくっているとヘンリーの呟いた声が耳に入る。
「栞?いや、何かのメモか」
彼が手にしているのは旅行記に挟まれていた書き付けで、紹介されている西岸のソルトバレーという町を訪れたときに手に入れた丸い石のようなものについて子細なスケッチが描かれていた。何かの卵のようにも見えるがそれにしては大きいし描かれている模様も奇怪なものに見える。
気がつけば時計の針が進んでいることに気づいて図書室を後にするが、幽霊の警告が気にならないわけではない。せめて夜中の二時三時までは起きていたほうがよいのではないか、その提案をキャサリンが快諾したのは間違いなく手に入れた戦利品をしばらく読み耽るつもりでいるからだろう。エドワードはヘンリーと顔を見合わせて苦笑すると部屋に戻ることにするが、幸いなことに、あるいは残念なことに彼らは退屈な時を過ごす必要がなかった。零時が近くなると部屋の外で召使いが明かりを消しに来たらしい足音が聞こえてきて、やがて遠ざかっていくと気味が悪いほど静かになって周囲から音が消える。こつ、こつと再び窓を叩く音が聞こえると、身構えていたにも関わらずエドワードは心臓が跳ね起きたような気分になってすぐに部屋の明かりを消すと透き通った女の幽霊の姿が現れた。今夜も恐ろしいことが起きる、地下に急いでと言うコニーの姿が嘆願しているかのように真摯なものに見えた。彼女の姿はすぐにかき消えてしまい、暗いままの部屋でエドワードはヘンリーに向き直ると意を決したように口を開く。
「探しましょう。地下を」
見ず知らずの幽霊の言葉を信じて疑う素振りもない、奇妙な言動の筈だがエドワードの言葉にヘンリーが感心しているような顔をしていることには彼は気がつかなかった。棚の上に置かれていた燭台を手にして明かりを灯すと、サイドボードの引き出しに入っていた頑丈そうなペーパーナイフを護身用にはなるかと懐に忍ばせる。音を立てないよう静かに廊下に出て、キャサリンの部屋の扉を叩くとすぐに彼女も現れた。荷物もスーツケースも車の中だから夜着に着替えられるわけでもなく、今まで起きていたのも彼女が大事そうに抱えている本を見れば分かる。隣室のギリアム氏は起きているだろうかと、扉の前で耳をそばだてると大きないびきの声が聞こえてくるだけで起きてくる様子はなかった。
とはいえ幽霊の言葉だけで見も知らぬ館で地下室を見つけるのが簡単にできるとは思えず、エドワードがキャサリンと一緒に召使いを訪ねている間にヘンリーが一階の部屋を探してまわろうということに決まる。それぞれが二つあった燭台の一方を手にすると、ヘンリーは先程訪れた食堂のほかに音楽室や厨房にも足を踏み入れるが地下に通じていそうな階段も扉も見つからない。エドワードはキャサリンが具合が悪くなったというシナリオを考えると召使いの部屋の扉を叩き、いぶかるペリンを相手にたどたどしい会話を試みる。仮に近くに病院があったとしてこんな夜中に何ができるはずもなく、不自然極まりないのだが、焦りばかりが募っていたせいか不自然な自分と同じくらいペリンが不自然な様子でいることに気づく。急にエドワードは自分の頭が冷えてくるのを覚えると、不自然を承知でかまをかけてみることにした。
「彼女を休ませたいんだ。そうだな、地下室とか涼しい場所はないかな」
「ち!地下室でございますか、いえ、地下はありますがございません」
急に様子の変わった召使いは慌てた口調で取り繕おうとして更におかしなことを口走る。目の前で小男が狼狽している姿を見てエドワードは完全に我に返ると、彼らの唐突で不自然な訪問そのものがペリンの後ろ暗さを刺激しているのだということに気がついた。ギリアムに聞いた話を脳裏に思い出しながら、表情だけは平静を装ってみせる。
「そうだね、本当は誤摩化すつもりでいたのだがこの際はっきりと言ってしまおう。この館には捜査の手が伸びているんだ。理由は君も知っていると思うけどね」
効果はてきめんで、俯いたままのペリンは視線を合わせようともせずしどろもどろな調子で聞かれてもいないことまで喋り出した。自分は何も知らないが主と執事の二人がときどき地下室を訪れていること、過去にこの館に止まった人たちが連れていかれたのかもしれないということ、もしかしたら主と執事の二人は恐ろしいことをしているのかもしれないと思ったことがあるが、自分は雇われているだけなので何も見ていないし何も知らないのだということ。もしもチャップマン様やクリーズ様がそのようなことをされていたと思うと恐ろしくてたまらないと、ペリンは自己弁護に必死な様子でひたすら口走る。
エドワードは助け舟を出すように、君がこの家に仕えているだけなのは知っている。だから捜査に手を貸してくれれば君に何かをする理由はない、地下室はいったいどこにあるのだいと優しく声をかけた。召使いはエドワードの言葉に飛びつくように、ロビーにある階段の裏がそのまま地下への階段室の入口になっていることを教えてくれる。ただ自分はただの召使いだから地下に何があるかは知らないし鍵を渡すこともできないと言うと、わざとらしく振り向いて壁にかかっている鍵束をひっかけると床に落としてしまう。そうだ明日も早いのだからとベッドに潜り込んでしまった忠実な召使いに、エドワードは感謝の言葉をひとりごとのようにつぶやくと、鍵束を拾って部屋を出たところでちょうどヘンリーと出くわした。
図書室はシナリオの進行には関係がないイベントで、オカルト判定に成功した人数の分だけ怪奇小説が入手できるが、リプレイではキャサリン一人が成功している。本の題名はてきとうに考えたものだが内容は魔導書「妖蛆の秘密」を元にした創作で、十六世紀に焚刑にされた錬金術師ルドヴィッヒ・プリンが十字軍参加時に遭遇したときの異端信仰との接触について語られている。読んだ者は正気度判定(0/1)を行いオカルト技能が+1%上昇する。
地下室に入る方法はいくつか考えていたが、自力で発見して鍵開けを試みる方法やペリンに白状させる方法以外では、深夜二時になると睡眠薬で眠らされていたギリアムが地下に連れていかれるので追跡する方法もあり、その場合は生贄に捧げられる中年刑事の救出がシナリオのクライマックスになる。ただしギリアム以外の人間が赤ワインを飲んでいた場合には、目を覚ますことができずギリアムの代わりに生贄に連れて行かれてしまうので注意。
召使いのペリンは小心者の小悪党で、連続失踪事件のこともすべて承知しているが自分は何も知らないという態度を貫こうとする。彼が動揺するキーワードは事前に定められていて、地下室、刑事や警察や捜査、事件の犠牲者の名前など幾つか用意をしていた。エドワードはこれらを上手く使った上で、君の悪いようにはしないという逃げ道も用意してくれたので積極的に鍵束を落としてくれている。
ペリン 50歳男・館の召使い
STR08 CON08 SIZ08 DEX08 APP08 INT12 POW08/SAN40 EDU10
言いくるめ50・隠す50・忍び歩き50
鍵の一本がかちりと音を立てて、扉が開かれると明かり一つない真っ暗な階段が続いている。地下にはあまりよい思い出がないと躊躇しているキャサリンに後ろから燭台を掲げてもらい、足を踏み外さないように慎重に下りていくと突き当りにもう一枚の扉があった。きしむ音を立ててゆっくりと開いた扉の向こうからひどい悪臭がただよってくる。地下室は真っ暗で、ヘンリーと遅れて下りてきたキャサリンが掲げている燭台の火だけが頼りなく周囲を照らしていた。殺風景な四角い部屋の正面には両開きの扉が、左手には先ほど降りてきた階段があって右手は一面が鉄格子で遮られている。鉄格子の向こうに転がっているものが燭台の明かりに照らされると悪臭の正体が誰の目にも判別できた。
「ひっ」
キャサリンが小さく悲鳴を上げると燭台の明かりが激しく揺れる。鉄格子の向こうには一人、二人、三人の人間が倒れているが、彼らはとうに死んでいて、どれほどおぞましい殺され方をしたのだろうかと思わせるほどにその表情も姿勢も苦痛と恐怖に歪められていた。石造りの床も壁もあちこちに黒ずんだ血の跡がこびりついていて、衰弱しきった死体は落ちくぼんだような干からびたような姿をしている。エドワードとヘンリーの背に隠れながら、吐き気と悲鳴を堪えたキャサリンが口元を手で覆いながら燭台を高く掲げるとそれで更に知りたくもない事実を知ることができる。死体は目の前の三つだけではなく、奥の方に、朽ちて原型すら留めていないもっと多くの人間の残骸が積み上げられているのが見えた。あまり凄惨な状態に、キャサリンが腰が抜けたようにその場にへたり込む。
エドワードは後ろを向いて逃げ出したい衝動を辛うじて堪えると、ジーザス、と呟いてから震える手で十字を切る。鉄格子越しに目の前に横たわっている死体がコニーであることに気づき、このような姿になってまで警告をしてくれた彼女の声を聞き届けないわけにはいかないと自らを奮い立たせた。急いでくれと彼女は言っていたのだ。
「行きましょう。ヘンリーさん、キャサリンさん」
表面に赤黒い錆が浮いている両開きの扉には鍵がかかっておらず、滑るように開いた隙間から細い明かりが漏れてきた。そこは壁も床も天井もひびわれたコンクリートに囲われた飾りも何もない部屋で、奥には祭壇めいた台があって手前の床には魔法陣めいた模様が描かれている。もとは倉庫に使われていた場所らしく、部屋のまわりにはいろいろな物が乱雑に積まれたり置かれていて、薪木や油缶、農具などがある中に犠牲者の私物なのだろう旅行用のスーツケースや荷物がまとめられてほこりをかぶっていた。壁や床はところどころが崩れてむき出しの土や岩肌が見えている。
床の模様は何度も描きなおした跡があり、今は一部がかすれてあまりはっきりとはしていない。祭壇はべっとりと赤黒いもので汚れてしみになっており、上には一冊の本と錆びた短剣、右と左にはかがり火が灯された背の高い台があり、油が満たされた皿と炉心には火がつけられていてあたりを気味悪く照らしていた。ヘンリーが入口を見張るように祭壇の手前に立つと、キャサリンが不気味な装丁の本をめくりながらエドワードも傍らで目を通す。
本は二つ折りの大きなもので、厚紙の表紙は手ずれでぼろぼろになっており中身は誰かが手書きで記述した手記のように見える。英語で書かれてはいるがでたらめに文字があちこちに飛んでいたり隙間まで小さな書き込みで埋められていて読みにくいことこの上なく、それでも断片的に内容を追っていくと館の執事をしているクリーズが数十年をかけて書き残していった記述であることが分かる。内容は荒唐無稽にしか思えないが、それはおぞましいほどに迫真的で情熱的なものだった。
クリーズの主であるグレアム・チャップマンが急死したのは三十年前のことである。人生に絶望したクリーズはかつて主と訪れたことがあるソルトバレーで手に入れた石から「天啓」を授かるとその言葉に従っておぞましい儀式に没頭し、チャップマンが黄泉の国から帰還したことで彼の狂気は揺るがぬものとなった。手記には彼に天啓を与えた存在とクトーニアンという呼び名が記されていて、儀式の詳細な手順も説明されていたがそれは死体の唇に人の血液を塗りつけてから生命を吹き込むというおぞましいもので、蘇った死人は人の生き血を与え続けることで生命を保つことができるが、唯一、血液を得るために用いた刃に触れると生命の絆が断ち切られてしまうらしい。
「グレアムは永遠に生き続ける。私の生涯を彼に捧げることができる・・・」
あまりにも冒涜的な内容にキャサリンは怖気を覚えながらも、クリーズの手記から目を放すことができずにいた。人が生涯に渡り人に忠誠を尽くすとはどのようなものであるのか、彼らが主従や友人を超えた関係であることに気味の悪さとは別に憧憬にも似た感情を覚えずにはいられないが、一方で彼女の理性はそれが決して人の抱いてはならない悪徳であると警告もしている。もしも神が無力だとしても、それでも人は神の理を逸脱してはならなかった。
ヘンリーは部屋の入口にときおり目を配りながら、祭壇にある短剣を手に取ってみるがそれはナイフよりも少し長い代物で刀身が錆びて曲がりくねっている。波打った刃は鋭い切れ味を発揮するものだが、これだけ錆びているとクリーズの記述にある力を発揮してくれるものか疑わしく思えてくる。キャサリンの後ろで手記に目を通していたエドワードが、ヘンリーと視線が合うと現実的な提案をしてみせた。
「少なくとも、この本と短剣が無ければ今日明日の儀式とやらは防ぐことができるのではないでしょうか」
「そうだな。これで盗むなかれとは神様も仰らないだろう」
冗談に紛らわせながらヘンリーが短剣を、エドワードが本を抱えたところで扉の向こうから階段がきしみを立てる音が聞こえてくる。よほど慌てているらしく、剣呑な様子が足音だけで伝わってきた。勢いよく、左右に開かれた扉の向こうにはこのおぞましい館の主とすべての元凶である忠実な執事の姿がある。一方はまったく無表情で感情すら窺えず、他方は対照的にたがの外れた激情に支配されていて、焦点の定まらない目でこちらを睨みつけながら手にした角灯の明かりを振るわせていた。
「やはり貴方たちも私の主人、敬愛するチャップマン様の永遠の命を奪おうとする輩というわけですか。ならば貴方たちをここから帰すことはできません。貴方たちはチャップマン様のために喜んで命を捧げてくださる、それでチャップマン様は死んでなどおらず、生きているではありませんか。しになさい」
自分が明らかに正気を失っていることに忠実な執事は気がついてもいない。クリーズの言葉にチャップマンがバネ仕掛けの人形のように両腕を広げると、ぎくしゃくとした昆虫めいた動きで一歩ずつ近づいてくる。部屋の入り口は一つだけで逃げる場所はなく、本を持ったエドワードとキャサリンは祭壇の近くにいるが、ヘンリーは扉が開く前に壁際に身を隠すと、懐にしのばせた短剣の柄を握り締めていた。
このように窮した場面では、彼の小説の主人公はたいてい絶望的な恐怖を前に愚かな振る舞いにおよんでしまうのだが、エドワードはヘンリーの意図を無言で察すると狂人の注意を自分に引きつけるために上着の影にペーパーナイフを構えて自分が本と短剣を持っているかのように振る舞ってみせる。キャサリンは護身用に携えているリボルバーを構えるとホールド・アップを要求するが、クリーズが扉の後ろに下がっただけでチャップマンは表情の一つも変えぬまま部屋に踏み込んでくる。
「ヘンリーさん!」
がら空きの背に短剣で切りつけようとするヘンリーだが、幸運の女神もそこまでの祝福を彼に授けてはくれず切っ先がむなしく空を切る。感情のない肉人形は見た目よりもずっと俊敏に動くと、腕だけが獲物を狙う蛇のようにまっすぐ伸びてきてヘンリーを捕まえようとした。危険を察したわけではないが、壁際によろけるように身をひねったヘンリーを掴みそこねたチャップマンはそのままバランスを崩して手近にあったスーツケースを掴むとスチール製のケースがまるで紙でできているかのようにくしゃりと潰れてしまう。まともに捕まれば骨の一本や二本では済まず、肝を冷やしたヘンリーの耳にエドワードが狂人たちを挑発する声が届く。
「本は僕が持っている!火にくべてやるぞ!」
「いけない!グレアム、あの男を!」
エドワードの言葉に動揺したクリーズがチャプマンをけしかけると、ヘンリーに背を向けてぎくしゃくとした動きで足を踏み出した。無防備にさらされた肉人形の背中を見て、ヘンリーは手にしていた短剣を思いきり振り上げる。
「誰でもいい、俺のかわりに祈ってくれ!」
外すかもしれない、などと考える暇もなくヘンリーが思い切って短剣を投げつけると錆びた切っ先が化け物の背に深々と突き刺さった。何人もの血を流した刃を突き立てられた瞬間、かつてチャップマンだったおぞましい人形の身体からしゅうしゅうと空気が漏れるような音がして、煙のようなものが抜けていくとみるみる老人の姿に変わっていく。そのまま彼が不当に消費した生命を使い尽くしたように朽ちていくと骨すらも崩れて塵か灰のようになってしまった。
クリーズの手記にある通り、館の主と執事は同年の幼なじみで友人以上の関係だったが、三十年前にチャップマンが急逝したことでクリーズは正気を失うとおぞましい儀式を試みるようになった。儀式はルールブックにある「ゾンビの創造」をアレンジしたもので、彼はこの方法を旅先で手に入れた石のようなものから生まれた存在に教わっている。クリーズは他にも幾つかの儀式や呪文を教わっていて、館の周囲が深い霧で覆われていたのも彼が教わった儀式が原因だった。この接触と蘇生の成功でクリーズは完全に狂気に陥っている。
生き返ったゾンビは通常のゾンビよりもはるかに強く、人格は生前のチャップマンとは別のものだが多少の知能があってあらかじめ教えられた会話を機械的に交わすことができる。食堂での会話はすべてクリーズに教えられた通りのものだが、狂気に陥っている彼は自分が主に教えたことをすべて忘れている。
ゾンビは数ヶ月から数年に一度、人間の血を与えないと身体が腐敗してしまうのでクリーズはこれまでも訪れた客人を薬で眠らせると生け贄に捧げていた。探索者たちが何もしなかった場合は夜中の二時になるとクリーズとチャップマンの二人がギリアムを地下に連れていってしまい、夜中の三時に儀式を行って彼を殺してしまう。翌朝、探索者たちはそのまま解放されるが後日になってギリアムが行方不明になっていることが知れるとシナリオ終了となる(この場合は真エンディング条件が消滅する)。
チャップマンのゾンビは傷をほぼ無効にしてしまう上に再生能力まで持っているので、ふつうに倒すことは難しいが、儀式に用いた短剣の刃で傷をつけるとおぞましい力を失ってただちに朽ちてしまう。もしも儀式の最中に部屋を訪れた場合は、クリーズの手記を読む時間がなくこれらの事情を知ることができないが、オカルト技能判定に成功すれば祭壇の上に置かれている短剣から不思議な力を感じることができる筈であった。
リプレイでヘンリーは執事たちがやってきたことに気づくと扉の影に隠れてやり過ごそうとしたが、扉を外開きにしていたので隠れる場所がなかったとして失敗させてしまっており、ここは隠れる技能判定を行ってもらうべきだったと反省。結果的にはヘンリーが見事に回避を成功させた上に、機転を利かせたエドワードがおとりになってゾンビに背を向けさせる工夫をしてゾンビを倒しているがよいマスタリングではなかったのでごめんなさい。
クリーズ 60歳男・館の執事
STR04 CON10 SIZ18 DEX04 APP10 INT10 POW10/SAN00 EDU16
隠す80・説得80・図書館80・薬学80
呪文:ゾンビの創造、霧の召喚
チャップマン 60歳男・館の主
STR18 CON18 SIZ14 DEX14 APP10 INT00 POW00/SAN00 EDU00
すべての被ダメージ1
耐久力再生1/ターン
崩れ去ったチャップマンの姿を全員がただ呆然として見守っていたが、最初に我に返って絶望の叫びをあげたのはクリーズだった。絶叫は長く長く尾を引いて、老人は彼の生涯の友人がいた場所に駆け寄るとかすれた魔法陣の上に屈み込み、気の狂った身振りで祈るような歌うような文言を唱えはじめる。
「シュド=メルの仔!冥府にすむもの!地の底でうごめくもの!あとたったの一度だけでいい、私の願いをかなえてくれ!」
途端、立っていられないほどの激しい地震が起こるとクリーズ以外の全員が部屋の隅に投げ出される。壁が崩れて天井が剥げ落ち、床が割れると露わになった地面の底からぶよぶよとした巨大なかたまり、人の背丈の倍ほどもある歪んだ烏賊のような蟲のような化け物が姿を現した。それは揺れ動く触手と、灰色がかった、黒い色をした汁気の多い長く伸びた袋のような図体をしていて、うようよと伸びる触手があたりをまさぐっている。どのようにして発しているのか、呪文を詠唱するような讃美歌を囁いているような音がその生き物からは絶えず聞こえてきた。全員が化け物の触手に心臓をわしづかみにされたような恐怖にとらわれると、かろうじて残っていた理性のかけらを吹き飛ばされたキャサリンが正気を失って泣き叫ぶ。
「嫌!?嫌!嫌ああああああ!」
化け物は目の前にいるクリーズに向けて触手を伸ばすとからみついた先が耳や口から老人の体内に入り込んで、ずるずるという音に続いて身体の中のものをすすり出した。クリーズはたちまち干からびて皮だけになると、くしゃくしゃと丸めて呑み込まれてしまう。このような状況で、冒涜的な恐怖は彼らに気を失うことすら許してはくれなかった。
かがり火が倒れ、先程までクリーズだったものの手から角灯が落ちて、油がまわりの品々に燃え移ると地下室に火と煙が立ち込めてくる。熱に怯んだ化け物の動きが止まると、ヘンリーとエドワードが考えたのは友人を逃がすなら今しかないということだった。
「エド!頼む!」
「キャサリンさん!早く!」
ヘンリーの声に、エドワードはキャサリンの手をむりやり引いて立ち上がらせる。非力な彼の言うことを彼女が聞いてくれたのは幸いで、その間にヘンリーは万が一の可能性に賭けて、転がっていた短剣を拾うともう一度投げつけたが、短剣の加護は失われてしまったのかぶよぶよとした皮膚に弾かれただけで化け物は怯んだ様子も見せていない。
「ヘンリーさん!逃げましょう!」
「当たり前だ!」
言いながら、ヘンリーはその場にとどまって二人を待つとエドワードはキャサリンを突き飛ばすように部屋の外に放り出す。クリーズを食い尽くしても満足した様子もない化け物の触手が伸びてきたが、このような時に人には能力を超えた力が宿るのかもしれずエドワードは紙一重で避けてみせた。その間も部屋にとどまっているヘンリーはキャサリンが放り出していた銃を拾い上げると、威嚇のつもりで構えるがこんなものが効くとは思ってもおらず、彼らが部屋を出たら脱兎よりも速く逃げるつもりでいる。銃を構えた腕に細い触手の先が届くと、ずぶりずぶりと刺さって信じられない痛みに思わず悲鳴を上げる。これ以上は耐えられない、というよりもこんなものに耐えて最後まで部屋に残っていた自分をヘンリーは褒めてくれとさえ思う。
腕から血を流しながら、触手を振り払ってヘンリーが部屋を出るとキャサリンも少しずつ正気に戻っているらしく、三人が這うように階段を昇ると再び地面が激しく揺れた。かろうじて一階まで逃げると先ほどの地震で歪んだ玄関にわずかに隙間が空いていて、無理矢理身体をねじ込めば逃げられるかもしれない。階段と回廊はすでに崩れていて、二階のギリアムがどうなったかは分からないがペリンは部屋から現れると何事かという顔をする。彼の疑問に答える必要はなく、床を突き破って、火と煙に悶絶している化け物が現れるとのたうちまわった。
「ペリン!ギリアムは・・・」
ヘンリーの言葉など聞こうともせず、賢明な小悪党は甲高い叫び声を上げると玄関の隙間から我先に姿をくらましてしまう。危険を前にした動物としては間違った行為ではないし、崩れた階段は瓦礫に姿を変えていてとても昇れそうにない。
「ヘンリーさん、早く!崩れます!」
「ちっ!」
ヘンリーがキャサリンを抱えるようにして、その後ろからエドワードが続いて玄関の隙間から外に出ると館の天井が今度こそ崩れてきて怪物の頭上に降り注ぐように埋めてしまった。幸い階上の火はそれで消えたらしく、地下ではまだくすぶっているのかもしれないが化け物は地下深くに潜ることを決めたのか再び現れる様子もない。吹き抜けになっている館の中央と回廊は完全に崩れて瓦礫に埋もれていたが、周囲の部屋は残っていて無事なように見えた。目を凝らした客室のあたりに曙光が差し込んでくると、崩落を免れたのはささやかな加護がもたらされたのではないかと思えてくる。
気がつけば霧は消えていて、三人で少し歩いた先に街道も車も見つけることができた。人を呼ぶとしてもまずはこの場を離れるしかなく、ヘンリーが運転席でハンドルを握ると後ろの座席にはエドワードがキャサリンと座ってともすれば怯えそうになる彼女をなだめている。キーを回して、フォードの赤い車体が走り出すと正面から差し込んで来る朝日にエドワードが目を細めて思わず振り返ると、遠ざかっていく館の残骸から感謝をする女性の言葉が聞こえてきたように思えた。
今回のシナリオは「悪霊の家」のような館探索ものにしつつ調べる必要がある部屋数は少なくしてプレイ時間を適度に短くすること、館の主と執事が登場するなら黒幕は執事という基本?を踏襲すること、そして最後が地下でゾンビと対決ではひねりがないのですべての元凶として神話生物を登場させることなどを意識して書いている。内容はあくまで初心者向きにしたけれど、初プレイの方がいらっしゃるシナリオでいきなりクトーニアンを出しますか!と言われればもちろん出します。
そのクトーニアンは第二から第三脱皮後の個体で成虫ほどの力は持っていないが、それでも人間が相手をしてどうにかなる相手ではないので無謀にも倒すつもりで戦闘を試みたらもちろん全滅して即バッドエンドになるだろう。クトーニアンは地震を起こす力とテレパシーによる人間との交信はできるが、熱には弱く一千度ほどの火で死んでしまうので、探索者が地上に逃げることができればあとは火事を嫌って地中に姿を消してしまう。
クトーニアン
STR25・CON25・SIZ25・DEX08・POW10
装甲3、耐久力再生3/ターン
触手:75%ダメージ1d6
正気度判定(1/1d10)
リプレイではキャサリンが一時的狂気に陥るとヒステリーを起こして泣き出してしまったので、エドワードが彼女を連れ出している間にヘンリーが留まって二人を逃がそうとしている。耐久力ではわずかな差だが、触手で攻撃を受けた際にショック判定で気絶する可能性を考えるとヘンリーはエドワードやキャサリンの倍近く耐えることができるので、彼らの判断は妥当だっただろう。もちろん彼らは最初から神話生物を倒そうなどという無謀なことは考えずに逃げる行動をとってくれていた。
ちなみに各NPCの顛末だが、ギリアムが眠らされていた場合、彼は儀式で生け贄にされない限り生き延びることになっている。目が覚めれば館が崩れているのだからさぞ呆然としたには違いない。ペリンはクトーニアンを目にしたときの正気度判定に失敗した場合は助からない予定で、この時は逃げおおせているが猟奇殺人事件の協力者として手配された後は完全に行方不明となっている。
シナリオのクリア条件は探索者とギリアムの双方が生き残ることで真エンディングの扱いになるので、極端な方法であれば全員が寝ずに朝を迎えれば何も起こらずに終わらせることもできる。ギリアムが犠牲になった場合や探索者に死者または永久的狂気が出た場合はバッドエンドになるが、シナリオの難易度としては低いといえるだろう。なおギリアムが犠牲になった場合のエンディングは、後日ニュースで見つけた記事で街道周辺で起きている連続失踪事件と捜査中の刑事ギリアム氏が行方不明になっている顛末を知らされることになる。
後日、エドワード・ヘイズはデイリー・ニュース紙に州境の街道で起きた局地的な地震と倒壊事故のニュースが載っている記事を見つけることができる。倒壊した館の主であるチャップマン氏は三十年も前に死亡、館を管理していた執事のクリーズと召使いのペリンは行方不明になっていて、建物では州警察のギリアム警部が発見されると病院に収容されたが心神喪失の状態で具体的なことは何も聞けていないらしい。警部は近隣で発生していた連続失踪事件の捜査を担当しており州警察では行方不明の両氏を手配するとともに関連性を調査中である。エドワードは深く息をついて、ニュースペーパーを閉じるとおもむろに時計を見てから立ち上がって上着を羽織る。出版社の印が押されている包みを取り上げて、近所の郵便局に行くついでに肺の中の空気を入れ替えることにした。酷評されることになった「黒い霧」とは違う、新しい作品は作家としての彼の評価を大いに高めてくれることだろう。
エドワードから送られてきたペーパーバックの一冊をキャサリンは自室のサイドテーブルに放り置く。しばらくこの本が彼女のベッドの伴になるだろうと思い、同封されていたもう一冊は彼女の友人に渡すために封筒に入れ直した。「炎上と崩壊の狭間で」とある表題に快いとは言い難い記憶を思い出すと少しだけ背筋に怖気を覚えてしまう。彼女の部屋にあるライティング・デスクはふだんは機能的に整頓されているが、今は二つ折りの手記が広げられていて、傍らにはインク壷とキャサリンが自筆で記したメモが置かれている。そのメモには彼女らしい流麗な筆跡で「私の生涯を彼に捧げることができる」の一文が残されていた。
(Scenario1:TRUE END)
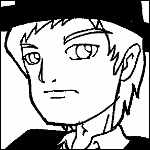 エドワード・B・ヘイズ 24歳男・売れない小説家
エドワード・B・ヘイズ 24歳男・売れない小説家
STR04 CON11 SIZ09 DEX13 APP08
INT12 POW12/SAN60 EDU13
主な技能(%)
オカルト55・心理学60・説得45・図書館65・ラテン語61・目星80・歴史50
精神分析51・天文学31・美術品/骨董品知識31・乗馬25
回避26・英語80
 ヘンリー・マグワイヤ 34歳男・無気力の会代表
ヘンリー・マグワイヤ 34歳男・無気力の会代表
STR10 CON12 SIZ13 DEX07 APP08
INT14 POW18/SAN90 EDU17
主な技能(%)
オカルト35・隠れる40・聞き耳90・水泳35・投擲75・値切り25・博物学50・目星95
応急手当70・機械修理40・信用35・説得25・天文学11・薬学21・歴史40
回避14・英語85
 キャサリン・ブルック(NPC) 40歳女・もと教師
キャサリン・ブルック(NPC) 40歳女・もと教師
STR08 CON07 SIZ11 DEX05 APP12
INT14 POW08/SAN40 EDU20
主な技能(%)
信用85・心理学10・説得50・図書館85・値切り10・法律85・ラテン語81・歴史85
運転25・オカルト25・芸術/ピアノ演奏20・フランス語61・拳銃60
回避10・英語99
>CoCリプレイの最初に戻る

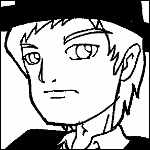 エドワード・B・ヘイズ 24歳男・売れない小説家
エドワード・B・ヘイズ 24歳男・売れない小説家 ヘンリー・マグワイヤ 34歳男・無気力の会代表
ヘンリー・マグワイヤ 34歳男・無気力の会代表 キャサリン・ブルック(NPC) 40歳女・もと教師
キャサリン・ブルック(NPC) 40歳女・もと教師