** Call of Cthulhu! Scenario#3:Hounds of Blue Crystal **
『それまでの苦労はあったがそれなりに平穏で、希望もあった私の人生に何の前触れもなく訪れた恐ろしく狂気に満ちた出来事。そこから、辛くも生還した私は、その発端となった宇宙的かつ、冒涜的な存在、その接触から得た経験と知識を元に、今後の私の人生を決定付けることになった拙著【炎上と崩壊の狭間で】を上梓した。そして、この事件を通じて、優美にして知的なC・ブルック女史と、未だ公には知られざるものの真にアメリカの英雄と呼ぶに相応しいH・マグワイア氏との知己を得たことは、私にとって、天への尽きる事のない感謝を捧げるに足る僥倖であったのは言うまでもない。幸運にも、この二名との交際は現在まで継続しており、特にマグワイア氏から教わることは非常に多く、その異界の化け物どものを相手取った英雄的な活躍の数々に、毎回私は蒙を啓かれる心持である。
そのブルック女史からの要請、そして、私がかつて青春の一時期に籍を置いていた、マサチューセッツ州はアーカムにある、ミスカトニック大学の名物教授、シンプソン氏のちょっとした伝手もあり、私はかのアンダーソン副知事の異様な怪死事件への、作家としての好奇心を抑えることの出来ないまま、ブルック女史、マグワイア氏らと再会し、三人でケープタウンへと赴いた。かの地では、神秘的で、魔術的な文化を色濃く残す、先住者たるナイ族と、そこに入植して来た開拓者たちが、様々な対立と軋轢を経ながらも、最終的には和解し、共存と街の更なる発展に手を携えようとしていた。その矢先に、原因不明の猟奇的な怪死事件が発生し、私たちは、真相の究明と更なる悲劇を阻止する為に、奔走する事になったのである。
最後に、正直にここで述べるなら、口を出すのも憚られるような、異界の追跡者の襲撃を受けながら、私とブルック女史がこうして、変わらずこの美しい世界で息をする事が出来るのは、ひとえに、前述した英雄マグワイア氏のお陰である。氏はその高潔な人格から、決してその功績を表立って口に出したりはしないが、私は勿論、氏が影に日向に、どれだけ人類にとって偉大な行いを果たしているのか、正確に認識している、恐らくは世界でただ一人の人間である。私のささやかな著作によって、氏の知られざる勲が、広く人々に感銘を与え、長く記憶に留まる事を、私は願ってやまない。
エドワード・ヘイズ【青水晶の猟犬】序文より』
キャサリン・ブルックが運転するフォード・モデルAの赤い車体が街道を南に走っている。大西洋に面しているマサチューセッツはアメリカでも特に早い時期に人々が入植して栄えてきた州のひとつだが、開発と発展の裏では例えば十七世紀の有名な魔女裁判に代表される、さまざまな事件が暗い影を投げかけたこともあった。車はアーカムから南へキングスポートを抜けて、更にその南東にあるケープタウンに向かう。ハンドルを手にしているキャサリンの隣にはエドワード・B・ヘイズが腰かけていて、後部座席にはヘンリー・マグワイヤがそこが彼の居場所であるかのように悠然と座っていた。取材旅行と称して彼らを誘ったのはキャサリンで、隣りにいる、十以上も年下の青年に視線だけを向けると口元を軽くほころばせる。
「正直なところ、エドワードは取材よりも事件の方に興味がありそうに見えるわ」
「ええ。僕の方こそ、まさかこの事件で仕事のお話を頂くなんて思ってもいませんでしたから」
センチュリー・フィールド灌漑工事は工事そのものよりも、開発を推進したA・アンダーソン副知事の変死事件で世間には知られている。話を聞くよりも以前に、事件にことのほか興味を持ったエドワードはそこらの雑誌記者よりもよほど詳しい事情を調べ上げていた。先日、ウエイアド・テイルズ誌に怪奇小説にしか見えないルポルタージュを寄稿すると、エドワード・ヘイズは彼の婚約者の両親を激怒させたらしいが生来の性分はそう変えられるものではない。心中の記憶を整理するかのように事件のあらましを諳んじてみせる。
かつて合衆国を席巻したフォードが新しく導入したモデルAを浸透させることができなかったように、開発と発展の最前線であり続けたマサチューセッツも近年は西部の発展に後れを取るようになっていた。むろん人々がそれで未来を手放すことはなく、新しい工業技術の発信基地として着手されたのがセンチュリー・フィールドの開発計画である。キングスポートの湾に面した低地を灌漑して得られる敷地は充分に広く、新しい工場街を設置して将来的には鉄道を敷くこともできる筈だった。開発用地は近隣にわずかに残されていたインディアンの一族、ナイ族の所有地が選ばれたが、アンダーソン副知事は特に重要な保護区域を残すという条件で土地の売買を彼らに合意させたという。ナイ族は売却費用を受け取るかわりに新しい街に彼らの家と土地と仕事を用意してもらうと、先住民と入植者が手を取り合った例として広く報道されたこともあった。
「かつて『最も興味をそそらない土地』と呼ばれた場所がマサチューセッツの希望になる、そんな記事でした」
ナイ族はマサチューセッツ南東にある半島部に暮らしていた小さな部族で、一般的なインディアンの印象とは異なり漁業を中心にして細々と生計を立てていた。とはいえ産業としての漁業はすぐ北のインスマウスがよほど栄えていて、開発計画がなければ今も寂れた漁村であり続けたに違いない。灌漑は数年がかりで行われて竣工したのが一月ほど前、事件はその落成式の日に起きた。
その日、造成地の一画に設けられた会場では長々とした演説が続いていて、人々は欠伸を噛み殺すのに苦労していたが式典そのものは友好的な雰囲気に包まれていたし穏やかに終わるだろうと思われていた。演壇に立っていたのはアンダーソン副知事で、彼の様子もいつもと変わるところはなかった。
突然、衆目の前でアンダーソンの首から上が演壇からごろりと落ちた。少し遅れて、ゆっくりと揺れた身体が倒れるとようやく人々も自分たちの目の前で何が起きたかを理解する。もちろん会場は大騒ぎになり、警察や救急車もやってくるがとうに手遅れだった。アンダーソンの首は斧か鉈のようなもので切り落とされたように見えて、無責任なマスコミにはインディアンがトマホークを投げたのだと吹聴して反発を買うものもいた。
「話だけならとても信じられる事件じゃないものね」
「ですが数十人の目撃証言はすべて同じ、もちろん犯人らしき者の影すら誰も見なかったそうですよ」
キャサリンに仕事を頼んだのは以前彼女が秘書をしていた議員だが、ありていにいえば事件が事件なので、手助けをして妙な醜聞が立たないか調べて欲しいという話だった。副知事の下で開発を進めていたブロンソンという人物に話を聞き、その後でインディアンの文化を研究しているサイモン・シンプソン教授に会うことになっている。教授はエドワードが学生だった当時に講義を受けたミスカトニック大学の人物で、旧知でもあるらしく彼が誘われた理由でもあった。ちなみに後部座席を温めているヘンリー・マグワイヤが誘われた理由は「どうせ暇なのでしょう」というキャサリンの一言によるが、その言葉に彼は重々しく答えたものである。
「返す言葉もございません」
舞台は前回シナリオでチャップマン邸を脱出してから数ヶ月後。少しずつアーカムに近付いているのは少しずつ日常から遠ざかっているという意味を暗示してもいる。ちなみにエドワードのつてで彼とキャサリンは心理療法の医者にかかり、正気度が初期値に回復している(でないとキャサリンあたりが壊れてしまいかねないので)。
不完全なエイボンの書をキャサリンが、クリーズの手記はエドワードとキャサリンが読んだことで二人は幾つかの呪文とクトゥルフ神話の知識を身につけている。ヘンリーは魔道書には目を通さず、投擲の腕を磨いたが、壁を相手に一人でキャッチボールをしていたところをキャサリンに目撃されている。
名家の娘であるエレンと婚約しているエドワードだが、清教徒も多いだろうこの時代にT島やMU誌に記事を掲載したと思えば彼女の両親が激怒したのも無理はないだろう。いずれ彼の口から、この事件が解決したら彼女と駆け落ちするんですなどと聞かされたらそれが彼を見た最後になるだろう。
一日目:The First Day
ケープタウンに到着したのは昼ごろで、そのままセンチュリー・フィールドまで車を走らせると広々とした土地の只中にまとまった宅地や工場の姿が見えてくる。変死事件のせいで企業の誘致が遅れていて、活気のある雰囲気と言い難いのは仕方のないところだろう。役場は機能的な建物で、受付にいる女性に要件を伝えるとやはり機能的なソファやテーブルが置かれた応接室に案内される。しばらくして現れた開発担当者のB・ブロンソンは年齢が45歳、死んだアンダーソン副知事とは学生時代からの友人であり彼の懐刀として知られている人物だった。型どおりの弔辞や選挙に関する話に続いて、話題はすぐに開発計画と変死事件の話になる。ブロンソンは積極的に現場に赴く人間らしく、よく日に焼けた首すじをさすりながら口を開いた。
「センチュリー・フィールドはこの町にも、インディアンにも多くの利益をもたらすだろう。もちろん反対する声はゼロではなかったが、それで人が殺されるなんて莫迦げている。そうは思わないか」
現場では犯人の姿も凶器も見つかってはいないが、人間の首がはねられる病気や事故があるとは思えない。ブロンソンも副知事が殺されたと思っているが、アンダーソンが誰かに殺されるほど恨まれていたのかといえば思い当たることなどなかった。確かにインディアンの中には先祖伝来の土地を売ることに不満の声を上げる者も存在したが、だからこそ故人は彼らが「聖域」と呼ぶ場所を保護区域にして残している。州政府が買ったのはそれ以外の土地だった。
「ここではないけれど、移民が始まった当時は二束三文の年金だけ渡して土地を巻き上げた例もあるし、町が発展すれば家や土地の価値は上がるのだからよほど穏当な交渉だったというべきよ」
「その通りだ。お嬢さんは道理というものが分かっていらっしゃる」
お嬢さんという年齢ではないが、議員秘書をしていた職業柄、過去にインディアンの土地が購入された例のいくつかをキャサリンは知っていた。話を聞いている限りではセンチュリー・フィールドの開発計画に不穏なところはなく、友人に説明するキャサリンの言葉にブロンソンは頷くがそれで故人が戻ってくるわけでもなかった。これ以上のことは警察か検死をした病院で聞くといいと言われるが、先方にすれば友人が死んで以来さんざん聞かれた話に辟易しているのだろう。約束もあり、腰を浮かしかけるがふと「あとは石が・・・」と漏らしたブロンソンの言葉をエドワードが聞きとがめる。
「石が、どうかなさいましたか?」
「いや、こちらの話だ。何でもない」
扉を叩く音がして、空になったカップを入れ替えようと女性の事務員が四人分のアメリカン・コーヒーを運んでくる。浅く煎られた豆の香りが部屋に立ちこめて、一息をつこうとしたエドワードの鼻孔にふと刺激を伴う不快な臭いが混じって何事かと思う。
皆の目の前で突然、ブロンソンの首がごろりと床に落ちる。首のない身体がびくんと動いて真っ赤な血が噴き出ると鮮血がテーブルを染めた。前かがみになった身体がゆっくりとかしぎ、たった今テーブルにできたばかりの血だまりの上に倒れ込む。二人の女性の金切り声が響いてにわかに周囲が騒然とする。
「きゃああああああ!」
「嫌ああああっ!」
唐突な事態にエドワードは呆然とするが、ヘンリーが右に左に周囲を見ている姿を見て理性を取り戻す。これが殺人であれば目にも見えない加害者がまだ近くにいるのではないか、ヘンリー自身は否定するし、先日のエドワードの寄稿にも不本意でいるらしかったが、エドワードは彼が英雄的な精神を持つ人物であると信じて疑っておらず彼の振る舞いを見習おうと努めていた。気を落ち着かせて、周囲を見るが何者の気配も感じることはできなかった。先ほどの異臭もすっかり消えていることに今更のように気付く。
哀れなブロンソンの身体はテーブルの傍らに倒れていて、驚いた表情のまま凍り付いた首が転がっていた。触れないように、死体を探ってみるが傷口は斧か鉈のような、鋭利というよりも力強い一撃で落とされたように見える。傷口のまわりにはいつの間についたのか、緑色に光る液体のようなものが付着していた。更に死体の懐から転がったのか、ヘンリーは足下に水晶のような青い石が落ちているのを見つける。ハンケチ越しに掴んで拾い上げたところで、数人の警備員が部屋に駆け込んでくると思わず身を離した。いったい何がありましたか、と、体格だけはいい警備員が訊ねる言葉がずいぶん間が抜けて聞こえる。見れば分かるだろうとも分かるものかとも言いたくなるが、目の前にある死体が何よりも雄弁に事態を説明してくれるだろう。すぐに警察もやってきて、事情を聞かれるが目にした以上のことは話しようもない。
「まったく何て事件でしょうね。大昔のまじないの時代じゃあるまいし」
若い警官の言葉が奇妙に説得力を持って耳に残る。普通ならとても考えられない事件だが、アンダーソン事件があったばかりで、ブロンソンが死んだ瞬間を皆が目撃していたから聴取も形式的なもので終わる。警官は捜査への協力を頼みながら、むしろこれ以上風評を立てられてはたまらないと、事件についてなるべく内密にして欲しいと仄めかしたほどだった。滞在する予定でいるホテルの連絡先を伝えて、若い警官の名前と先のアンダーソン事件の担当警部の名前まで聞くと、先方も何かあればこちらからも連絡をしますと丁寧に頭を下げていた。
青い石はヘンリーとエドワードが目星判定をするが正体はまるで分からなかった。その形状から、元は大きな結晶がきれいに割られたものであるらしい。
ここまで変死事件の犠牲者は以下の二人。
A・アンダーソン副知事 45歳男
マサチューセッツ副知事で落成式の日に死亡。
B・ブロンソン 45歳男
アンダーソンの同僚で取材中に目の前で死亡。
役場を出たところで、少し遅くなったが約束をしていた教授に会うために彼が滞在しているホテルへと足を向ける。センチュリー・フィールドは町そのものが建てられたばかりだから、どこも新しく機能的に分けられていて、教授のホテルも町の入り口近くにありどこにも行きやすい理想的な場所に建てられていた。
「『炎上と崩壊の狭間で』は実に良かったよ。これからはヘイズ先生と呼ぶべきかな」
「学生時代と同じエドワードで構いませんよ、教授」
人好きのする笑顔と握手で出迎えた、シンプソン教授はミスカトニック大学の人類学部で教鞭をとっている人物で、インディアンの文化にも詳しく今回キャサリンの取材旅行への協力を頼まれている。年齢は五十歳を超えていて、いささか恰幅のよすぎる身体に白く見える銀髪と赤らんだ肌がいかにも白人めいていた。専門である人類学とは別にオカルト的な分野にも強い嗜好を持っていて、エドワードが教授を見知ったのも惑星の運行にまつわる趣味的な会合がきっかけである。年齢と外見のわりに気さくで行動力がある人物だった。
シンプソン教授はミスカトニック大学の教授らしく?超心理学者として作成している。このシナリオではキャサリン同様便利なアイテムとして登場。
S・シンプソン 51歳男 ミスカトニック大学教授
STR06 CON17 SIZ12 DEX11 APP06
INT14 POW12/SAN60 EDU18
主な技能(%)
オカルト65・人類学81・写真術15・ラテン語81・精神分析61・図書館55・心理学10・歴史60
応急手当40・天文学61・考古学51・拳銃40
ホテルの格式にふさわしく、教授が借りている部屋は客人を迎えて談話をするためのスペースも充分に設けられていたが、荷物と資料がところ狭しと散乱して彼の研究室の様子を容易に想像することができる。握手と挨拶を済ませると、遅れたことを謝罪してから変死事件と青い石について説明する。ヘンリーがハンケチを広げると丁寧な様子で石を取り上げるが、教授も鉱石の専門家ではなく石の正体までは分からないと言いながらも、もとの結晶は正八面体に似た形をしてそれが四つに割れたのであろうと言う。
「正八面体というと、ピラミッドを二つ合わせた?」
古今東西、所有者を破滅させる呪われた石の伝説というものは枚挙に暇がない。有名なものでは「マクリーン夫人のホープ・ダイヤモンド」があるが、こうした伝説の大部分は脚色か誇張されたものだ。だが人類学的に考えるならばこうした呪いには禁忌に対する警告の意味合いが強いから、調べてみれば意外な事実が明らかにならないとも限らない。青い石についてもインディアンの文化や伝承の中に記録があるかもしれなかった。
「興味深いね。いや実に興味深い」
教授はよほど好奇心を刺激されたらしく、すぐにでも石について調べたいから貸して欲しいと頼まれる。つまりこれから大学までとんぼ返りをして調べると宣言しているわけで、なるほど行動力のある人物らしかった。明後日の夕方には戻るからそれまで警察や病院で事件のことを調べるといいなどと話しながら、すでに教授はトランクに荷物を詰め始めている。研究室の連絡先を書き残して、車のキーをポケットに放り込むころにはもうコートと帽子を手にしていた。この勢いなら制限速度ぎりぎりで車を走らせて、そのまま研究所で夜を過ごすつもりでいるのだろう。
年齢に似合わぬシンプソンの勢いに唖然とさせられるが、まさかこのまま居座るわけにもいかず教授と一緒にホテルを後にする。これがケープタウンでの初日だと思うとなんとも慌ただしい一日だった。走り去った教授のシボレー・スーペリアを目で追うとセンチュリー・フィールドの町並みに立ち尽くす。新しい家を手に入れたナイ族が暮らしているこの町で、人が集まるのはこれからだから今の住民はインディアンが多くを占めている。彼らは自分たちの居住区で暮らしているらしくこの時間、目抜き通りの周辺はむしろ閑散として人影もほとんど見かけない。
「ねえ、何か聞こえなかった?」
人気のない路地にキャサリンが目を向ける。彼女たちは教授のように値段と格式の高いホテルではなく、ごくありきたりな宿を手配していてヘンリーとエドワードもそこに泊まる予定でいた。車は役場に預けていたからそのまま歩いて宿に向うが、周囲は閑散としてまるで異世界に迷い込んだような違和感を感じさせていた。キャサリンが聞きとがめたのは路地裏の向こうから誰かが呼んでいるような声だったが、不用心に足を踏み入れたところに小柄な影が駆けてくる。すぐに気がついたヘンリーが慌ててキャサリンの腕を掴んだ。
「キャシー、待て!」
「きゃ!?」
よろけながら、ヘンリーの胸に引き寄せられるがそのまま乱暴に突き放されて、何ごとかと抗議しようとしたキャサリンの前で浅黒い肌に鋭角的な顔立ちをしたインディアンが二人、殴りかかってくる姿が目に入った。人気がないとはいえ町中で昼ひなかに暴漢に襲われるなどふつうは考えない。
「ヘンリー!」
このような場面でときおり英雄的な姿を見せることがあるヘンリーだが、彼の守護天使もそこまで暇ではないらしく、問答無用に殴りかかってきた拳が頬骨のあたりに命中する。それでヘンリーが勇敢に殴り返そうとしたか、献身的に友人を守ろうとしたか、それとも退散しようとしたかは結局誰にも分からなかった。この場に六人目の人影が現れると暴漢に向けて一喝したのである。
「お前たち!何をしている!」
「タシュンケ!?また白人の味方をするつもりか!」
新たな闖入者は若々しいインディアンの青年で、暴漢の二人には見知った顔であるらしく慌ててきびすを返すと駆け去っていく。何やら捨て台詞らしき言葉をわめいていて、インディアンの言葉らしく意味は分からないが下品なことを言っているのは間違いないだろう。窮地を救ってくれた青年は怪我はなかったかと言おうとして、ヘンリーが殴られていることに気づくと大丈夫かと言い直す。
「すまなかった。あいつらは白人嫌いのはねあがりどもだ。インディアンがあんな連中ばかりだと思われたら困るから見回りをしている。もう少し早く駆けつけることができればよかった」
青年はインディアンの言葉で暴れ馬を意味するタシュンケ・ウイトコと名乗ると、クレイジー・ホースと呼んでくれという。彼が言うにはインディアンは決して白人を好きではないが、開発計画のおかげで彼らはいい服を着てうまい飯を食えるようになり、ナイ族の多くの者は白人と未来を生きることを望んでいるということだ。
クレイジー・ホースことタシュンケ・ウイトコの主な技能は以下の通り。某無気力の会代表もそうだが、トライブメンバーというのはなかなか優れた人物の集まりに思えてしまわなくもない。
クレイジー・ホース 30歳男 インディアンの青年
STR08 CON12 SIZ10 DEX15 APP13
INT12 POW14 EDU12
主な技能(%)
オカルト85・投擲85・水泳55・ナイフ95・乗馬95・跳躍35・追跡20・登攀50
インディアンの青年と別れて、その日はそれでようやく宿に向かう。エドワードとヘンリーが同室で、キャサリンが隣の部屋を借りるが、先ほど殴られたヘンリーの頬をエドワードが手当てしたのは英雄の名誉の負傷を治療する行為を彼が神聖なものと思っていたなどという大げさなものではなく、相変わらず不器用なキャサリンの手当てを見かねた彼がこっそりと部屋でやりなおしたためだった。
「なぜキャシーは包帯を巻くのが苦手なのか?」
「その答えは大学でも学びませんでした」
二日目:The Second Day
取材旅行のはずが気がつけば捜査の真似事に携わることになったが、シンプソン教授がそうであるように世の中には好奇心を抑えることが難しい人間が存在する。夜が明けると三人はいかにも規格品で揃えられた朝食を済ませ、これだけはましな珈琲で気分を新たにすると、宿を出てさほど離れていない警察署を訪れた。昨日役場であった若い警官、トンプソンを呼ぶと先にアンダーソン変死事件の捜査資料を見せてもらうが報告書によれば死因は不明、事件性は不明、犠牲者の所持品はなしと、あまりに不誠実な記録が残されているだけだった。トンプソンは苦笑いをして、とにかく彼に会えば分かると言いたげな顔をしていたが、青年の無言の声が事実を伝えていたことはほどなく証明された。
「俺がガリクソンだ。民間人が何の用だ?」
アンダーソン事件を担当するガリクソン警部は年齢は50歳を超えているが、時間が彼に与えたものは残念ながら経験ではなく偏狭や怠惰といった好ましからざる概念であるらしい。どうやら厄介な事件だから厄介な彼に押し付けたらしい、警察の事情が透けて見えて彼らの目的が事件を解決することではなく事件を風化させることにあるのは明らかだった。人の印象は初対面の瞬間に半ば決まると言われているが、初対面から不快な印象を与えたガリクソンは印象に違わぬ内面を持つ人物だった。このような人物を相手にしてエドワードは情熱が通用しない相手の難攻不落を実感し、仕事柄辛抱強い交渉に慣れているキャサリンも彼の方針が「民間人に話すことはない」であることを確認できただけである。最初から匙を投げて掴もうともしていなかったヘンリーが、まだ紫煙に汚れていない窓を見上げながらわざとらしく呟いてみせる。
「被害者の遺留品があった筈なんだがなあ、奇妙な青い石とか」
わざとらしい物言いに明らかにガリクソンの様子が変わる。何を言いたいんだとがなりたててくるが、発言者はあえてそっぽを向いたままで茶すら出てこないのを不満に思っているような態度を見せていた。明らかに訊ねられたくない話題なのだということは心理学を学んでいたエドワードならずとも窺えて、ガリクソンは激昂するが結局不愉快そうに立ち上がるとそのまま無言で部屋を去ってしまった。相手の権幕に多少押されたキャサリンが不平を言う。
「あまり挑発するものではないわ。あれでも相手は警察の人なのだから」
「まあ議員秘書様に手は出さんだろう。あの手の輩は」
入れ替わりに入ってきたトンプソン青年が、退出者の権幕を見て事情を察したらしく頭を下げてくる。ガリクソンがきわめて非協力的なことを彼は申し訳なく思っているらしく、いっそブロンソン事件を追う名目で自分の名前を使って構わないということと、捜査に進展があれば連絡をするとも申し出てくれた。
以下警察の二人。実は青年警官の名前は決めるのを忘れていたため急遽命名しています。
G・ガリクソン警部 51歳男
アンダーソン事件の担当。非協力的で挙動不審。
T・トンプソン警部補 30歳男
ブロンソン事件で知り合った警官で協力的。
センチュリー・フィールドでは公共の施設はどれも目抜き通りの近くに置かれているが、警察署から病院まで多少距離があるのは緊急車両の出入りを考慮して互いに邪魔をしない場所にあるからだろう。キャサリンからそのような話を聞くと、彼女が議員秘書だったことを今更のように思い出して感心させられる。あくまで大義名分でしかないが、公的な立場で町を訪れたキャサリンが警察の捜査に協力するという名目だからこそ、彼らはふつうなら入ることができない場所に立ち入ることができた。ガリクソン警部の言いぐさではないが、そうでなければ民間人が変死事件を調べるなどそうできるものではないだろう。
「どうぞ、市警から話は聞いています」
「有難うございます。ご協力に感謝いたしますわ」
病院でのキャサリンの態度も堂々としたものだが、検死室に案内されながら内心は怯えていることもヘンリーには分かっている。これから首をはねられた死体と対面しようというのだから無理もないが、もともと怖がりなんだからよせばいいのにと思わなくもなかった。奇妙なほど冷え冷えとした部屋の中央に、寝台が据えられていてシーツを被された犠牲者の身体が横たえられている。口元をハンケチで抑えながら、こわごわと覗き込んだキャサリンがあっと声を上げると、どうしたと近寄ったヘンリーも彼女に劣らぬ頓狂な声を上げた。
「おい、誰だ、これ?」
遺体に対してずいぶん無礼な言葉になってしまったが横たわっている男は昨日のブロンソンではなく、もちろん一月ほど前に死んだアンダーソンの筈もない。医師に聞くと先ほど運び込まれたばかりの被害者でカールソンという人物だと知れる。C・カールソンはセンチュリー・フィールドの灌漑工事を請け負った建設会社の現場監督で、身元が判明しているのは今日の朝、出勤前に首をはねられた遺体を同僚が会社の前で見つけたからである。病院にすればこちらに首をはねられた死体が運ばれたと聞いていますが、などと聞けば間違えて案内したのも無理はない。
これで変死事件の犠牲者は以下の三人となった。
A・アンダーソン副知事 45歳男
マサチューセッツ副知事で落成式の日に死亡。
B・ブロンソン 45歳男
アンダーソンの同僚で取材中に目の前で死亡。
C・カールソン 45歳男
建設会社の現場監督で出勤中に死亡。
改めてカールソンの遺体を見ると昨日のブロンソンと同様に強い力で首がはねられていることと、やはり傷口のまわりが緑色の液体で汚れていることに気づく。病院でも調べたらしく、液体は生き物の体液と思えるが該当する生物の特定はできていなかった。記録を持ってきてもらうと一月前に死んだアンダーソンの遺体にも同じ液体がついていたらしい。遺留品にはシガレットの箱とライター、手帳の他に教授に預けたのと同じ青い石が残されていた。手帳はごくありきたりなもので、仕事のスケジュールが書き込まれていたが後ろの頁に奇妙なメモがあるのを見つける。
「アンダーソン、
ブロンソン、
カールソン、
デビッドソン・・・?」
そこには変死事件の犠牲者が三人と、もう一人知らない名前が書かれていて上の二人の名前は棒線で消されていた。遺留品を預かりたい旨を伝えるのもあって、警察に連絡をするとトンプソンを呼び出してもらう。カールソンの件はすでに通報があったらしく先方の署内は大わらわで、むしろそちらで調査を進めて情報を提供して欲しいと頼まれるほどだった。
デビッドソンについては警察が事件の関係者を洗った名前の中に挙がっていて、やはり開発計画に関連して契約をした保険会社の部長ということである。四人は学生時代からの友人で、警察としても気になるが派遣できる人がいないのが現状らしい。さすがに個人宅の所在を教えることはできないが、警察から保険会社に話を通すことはできるから明日の朝にでも彼を訪ねて欲しいが、異常や危険があれば深追いはせず警察に急報して欲しいと頼まれる。捜査の協力者として立場を保証してもらえたというわけだが、煩雑な手続きは後にしましょうと言われて受話器を置くと三人三様に顔を見合わせた。
「いくらなんでも慌ただし過ぎませんか?向こうで何かあったんでしょうか」
「すぐにでも先方を訪ねたいんだがなあ、仕方ないか」
犠牲者の手帳に名前が書いてあったからといって、警察でもない人間が夜遅くに自宅を訪ねるのは確かに大げさに思われるだろう。ヘンリーが気にしたのは青い石が四つあって、それを持っているらしい四人のうち三人がすでに殺されているということだった。できることなら四人目の犠牲者など出ない方がいい、ただ巻き込まれただけの事件であっても彼は心からそう思っている。日が落ちるまでにはもう少し時間があったから、病院を出るとインディアンたちの居住区まで足を延ばしてみるが、昨日会ったクレイジー・ホースを見かけることはできず、そこらにいた若者に訊ねると今日はいないが明日ならいる筈だという答えが返ってくる。
ついでにインディアンの伝承に詳しい人がいないかも訊ねてみると、語り部の婆さんだろうと言う。ホースと会うなら彼に頼めば紹介してくれる筈だと請け負ってもらい、この日はこれで引き上げることにした。宿に戻ると部屋に入ろうとするが、扉を開けたキャサリンが絹を割くような悲鳴を上げたのを聞いて慌てて隣の部屋に走り寄る。彼女が叫んだ理由は一目見れば分かり、室内が派手に荒らされた上に赤い液体のようなものがぶちまけられて、壁には血のようような真っ赤な文字でMASSACRE(殺しちゃいますよ)と書かれていた。ヘンリーはキャサリンをなだめながら、努めて平静なふりをして呟いてみせる。
「やれやれ、下着泥棒にしては鼻血を出しすぎだな」
「・・・莫迦」
その様子を見ながら、エドワードはヘンリーが決して動揺しないからこそキャサリンはもちろん彼自身も冷静でいられるのだと思う。冗談のセンスはともかく、目の前の恐ろしい惨状を見て軽口を叩くなどエドワードにはとてもできることではなかった。ヘンリーの意図が通じたように、キャサリンは自分を落ち着かせるかのように大きく息をつくと部屋を調べるが荷物が持ち去られた様子はなく、着替えのいくつかが台無しになったことがむしろ腹立たしくなってくる。エドワードは宿の従業員を呼びに行き、ヘンリーは赤い液体を調べるが血ではなく油の臭いがしてペンキであることが知れた。
ふむという素振りでヘンリーは無精髭が残るあご先に手を当てる。目的はこれ以上事件に関わるなという警告か、あるいは青い石を持っていることそのものへの警告か、たぶん後者だろう。
「おい、明日はなるべく早く出るぞ」
「ヘンリー?ええ・・・そうね」
ヘンリーの呟きに、この状況で彼がまだ会ったことすらないデビッドソンの身を案じていることが感じ取れてキャサリンは今更のように彼を誘ったことが正しかったことに表情を和らげる。エドワードに連れられた宿の支配人は平身低頭すると別の部屋を用意してくれて、そこは二人の部屋から少し離れていたがその夜のキャサリンはこんな出来事の後にも関わらず不思議と落ち着いて眠ることができた。
三日目:The Third Day
あまり美味とはいえない朝食を平らげながら、早朝のラウンジで事件を整理すると思ったよりも手をつけられる箇所がありそうなことに気づく。保険会社でデビッドソンの安否と青い石の所在を訊ねること、アンダーソンが青い石を持っていなかったか調べること、改めてインディアンの居住区で話を聞くこと、夕方にはシンプソン教授も大学から戻ってくるだろう。時計の針を見ながら早々に保険会社を訪れると、幸いデビッドソン当人が現れて応対をしてくれる。警察からの紹介であることは先方も知っていて、ヘンリーが事件と青い石のことを仄めかすとそのまま人払いができる部屋に案内してくれた。
不安げな彼の表情を見れば、デビッドソンが事件のあらましについて知っていることはすぐに分かる。表情は重く言葉は歯切れが悪く、躊躇している様子も見てとれるがすでに何人もの犠牲が出ている事件で無為な時を過ごす理由はない。このような時に交渉ではなく率直な訴えを試みるのは本人もあまり自覚していないエドワードの美徳だった。
「ご友人が亡くなられたことは存じています。ですが事件は何も解決していません。青い石と貴方たちの関わりについて教えて頂けますね?」
「ああ。だがまさかこのようなことになるとは誰も考えていなかったのだ」
デビッドソンは自分が四人目の犠牲者になることを明らかに恐れている。エドワードに促された彼は自分たち四人が学生時代から考古学サークルの友人であったことと、インディアンの聖域から青い石を盗掘したことを今更のように白状した。センチュリー・フィールドの開発そのものは健全な計画で、保護区域を定めて土地を売却することもナイ族は快く承知してくれていた。だが区域を定めたからには調査をする必要があって、インディアンが聖域と呼んでいた場所に遺跡があることを発見した彼らは祭壇らしき場所に収められていた青い石を持ち出してしまう。
「言い訳をしても仕方がない。確かに石は高価なものには見えなかったが、考古学的に貴重で珍しいものであることは疑いようもない。宝石商ではなく、博物館であれば高値で買い取ってくれるだろうとも思ったよ」
「正直なのは良いことですが、できれば貴方たちが石を持ち出す前に正直であるべきでした」
エドワードの言葉は辛辣だが、自覚のあるデビッドソンは頷きながら、これこそが大事であるかのように深々と頭を下げる。
「君たちは石のことを調べているのだな。こんなことを頼んでよいものか分からないが、戻せるなら石を遺跡に戻してしまいたいのだ。もちろんこれも君たちが持っていって構わない」
そういうとデビッドソンは懐から石を出してテーブルの上に置く。彼らの行いは正義に反するが、法的にはインディアンの土地に不法に侵入しただけで命で購うべき過ちにも思えない。彼らが悪いことをしたとして、これは殺されるほどの所業だったろうか?エドワードは石を受け取ると懐にしまう。これが危険な代物であれば、預かることは危険に身を置くことだが彼はそれを自覚して当然のように振る舞っていた。それはエドワードだけではなくヘンリーやキャサリンも同様で、デビッドソンは彼の目の前にいる者たちの振る舞いに今度は心から頭を下げる。
「私はその石を君たちに押しつけようと思っている。そして君が石を受け取ってくれたことに安堵している。だがそれでも私は君たちのように気高く振る舞えない、本当にすまない」
「いえ、そのお言葉だけで充分ですよ」
自分は気高いのではなく、ただこれ以上人が死ぬことはないと、そう願いたいだけなのだ。それにしても保険会社の部長に何度も頭を下げられるなど、彼らにはこれまでもこれからも縁がないことだろう。エドワードの感想をヘンリーが冗談に紛らわせて代弁してみせる。
「まあ将来、俺たちが保険に入るときには充分な便宜を図ってもらうことにするさ」
実はデビッドソンの名前を役場で調べると会社ではなく自宅を直接訪れることができた。その場合は彼の娘が玄関に出て、彼女の首には父親からもらったペンダントがかけられている予定だった。
D・デビッドソン 45歳男
工事の契約を進めた保険会社の部長。
用事を終えて保険会社を出ようとしたところで、受付で呼び止められると警察から伝言が届いていることを教えられる。電話を借りて、トンプソンに連絡するとすぐに当人が出てガリクソン警部が昨日、何者かに殺されたことを知らされる。
「警部には以前、別の事件で被害者の遺留品を着服した前科がありました。昨日は彼は非番で自宅にいたところを襲われたらしく、胸を鋭利な刃物で一突きされていたそうです」
おそらく彼が青い石を着服したのではないかと、内部調査が進められていたが、ガリクソンが殺された現場には石は見つからなかったらしい。ことが殺人事件であるからには、捜査への民間人の協力は危険だと判断されて今後は調査を控えて欲しいと忠告される。情報は教えるし、必要なら警備の人間も手配するとトンプソンは伝えてきた。彼らが襲われたことや宿が荒らされたことを警察も知っている。
「お気をつけて」
だが忠告しながら、彼らが調査を止めるつもりがないことをトンプソンも承知しているのだろう。保険会社を出た彼らはガリクソンが殺されたことで、むしろ石を預けた教授の身が気がかりになって彼が借りていたホテルに足を向ける。
ロビーで訊ねるとシンプソン教授はまだ大学から戻っていなかったが、今朝方奇妙な荷物が届いていたことを知らされる。宛先がサイモン・シンプソン教授とキャサリン・ブルック女史になっていて、つまりどちらかに渡して欲しいという訳だ。ラウンジの一画を占拠して、ずしりと重い荷物を解いてみると中から現れたものに唖然とさせられる。
「ちょっと、これって・・・」
「まったく。とんでもない人だな、あの教授」
キャサリンが驚いてヘンリーが呆れたのは束ねられた資料の内容ではなく、分厚く綴じられたその膨大な量であった。青い石と一緒に同封されていた走り書きの言葉を信じるなら、車を走らせたシンプソン教授は彼の研究室に直行すると、まる二十四時間以上一睡もせず調査に没頭したらしい。メモには汚らしい字で「運転の前に寝なければならない私よりも、この荷物が先に到着するだろう」と書かれていた。ミスカトニック大学には偉人と奇人が多いとは聞いたことがあるが、どうやらシンプソン教授はその双方であるようだ。端書きや注釈がこれでもかと書き込まれた資料を断片的に辿ってみる。
この地域では十八世紀の末頃にもインディアンの部族と対立していた入植者が、首をはねられて死んだという事件があった。ナイ族はナイアラトホテプに祝福された部族の名で、この如何わしい神と従姉妹でもある双性神マイノグラフとの間に「猟犬」とも「狩人」とも呼ばれる存在がもうけられている。猟犬は獲物を見つけると何億年もの時間を超えて追いかけてくる。北極星がひと巡りする時間、二万六千年を一秒で超えると獲物を殺して去っていく。時間と星々の彼方にある猟犬の姿を星図に写した壁画があり、計算をすれば猟犬がいる時代からおよそ一ヶ月で現代に到達できるだろう。資料には猟犬を呼ぶまじないや過去の伝承が記されているが、すべて読もうと思ったら一日二日で終わる量ではない。端書の中に、現代においてもナイ族には彼らの伝承が残されていて、語り部であれば更に詳しい伝承を知っているだろうと書かれていた。
教授のメモは魔道書の扱いで、書かれている内容は大地の謎の七書の抜粋に注釈を書き加えたもの。ちなみにナイアーラトテップとマイノグーラの発音が独特なのはインディアンの語圏を意識してのもの。
センチュリー・フィールドの他の地域とは違い、インディアンの居住区はすでに移住した人々が暮らしていてあまり閑散とした様子はない。建物は新しいが肝心の工場が操業を始めておらず、仕事が限られていたから活況には遠く雰囲気がよいとは言えなかった。居住区の入り口は広場めいていて、住民が集会やイベントを行えるようになっている。すぐに分かるところにクレイジー・ホースがうろついていたのは、昨日訪れた話を聞いて待っていてくれたかららしい。先方から手を上げると気さくに近寄ってくる。
「話は聞いている。語り部に会いたいのだろう、案内するから来い」
居住区の建物はありきたりなもので、インディアンの文化や風習に合わせた造りになっているわけではないがちらほらと見える飾りや伝統的な織り布に入植者とは違う文化を感じさせる。一軒の建物に案内されるとここがそうだと示されるが、店子作りの入口に雑然と並べられた品々が土産物屋か骨董品屋のようにも見えた。礼を言って中を覗き、がらくたにしか見えない品の幾つかに目を止める。エドワードの目を惹いたのは三本足のかぎ十字のような奇妙な模様が刻まれたブロンズ製の円盤で、何やら説明しがたい力を感じていたところに奥の部屋からゆったりした織り布の衣裳を羽織った老婆が現れた。老婆は開口一番、猟犬と青い石のことが聞きたいのだろうと言うと、あんたらが来ることは分かっていたと続ける。
エドワードは芸術ではなくオカルト判定でこれを発見。円盤の正体は後述するが、ナイアラトホテプはこの部族に青い石と円盤の両方を与えていたことになる。ちなみにナイ族はこの神格を崇めてはいるがそれはインディアンの信仰らしく、大いなる自然への畏怖と崇敬であり盲目的に従っているわけではない。
「青い石は白人には呪いの石、インディアンには私らを守る石だと思われている。だがインディアンも間違った伝承を残すことはある。あれはただの人を殺す石さ」
語り部の言葉は穏やかにも聞こえたし忌々しいものを吐き捨てるようにも聞こえた。
「猟犬にして狩人の話は知っているね?それは時間のはるか向こうにいて、鏡のような[窓]を通じて獲物を見つけると[鋭角]から煙のような姿を現してすみやかに獲物を殺してから時間の向こうに帰っていく。大昔、私らのご先祖は窓であり鋭角でもある青い石を授けられたが、猟犬はあまりにも人を殺したから恐ろしくなったご先祖は石を四つに割ってしまった。割れた石は小さいから猟犬は窓からすべてを見ることができなくなり、鋭角からすべての身体をさらけ出すこともできなくなったがそれでもまだ人を殺した。ご先祖は祭壇をつくると四つの石を置いて誰も近づけないようにした。それが聖域のはじまりさ」
そこまで言うと語り部は節くれだった指を伸ばす。
「あんたらの石にはまだ猟犬が追いかけているのがあるね?猟犬は金星が天狼を遮る夜に訪れるよ、もう時間は残っていない」
「天狼?シリウスのことか」
天文学に造詣が深いわけではないヘンリーだが、おおいぬ座のシリウスが魔狼として多くの伝承に現れることは知っていた。金星の運行図はシンプソン教授の資料にも書かれていて、両者は明日には交叉する。つまり明日には猟犬が現れて四人目の犠牲者が出る、それが親しい友人でも、見知らぬ人であってもこれ以上犠牲を出してはならない。
「どうすればいい?あんたには知識があるのだろう」
「猟犬が現れるのを遮ることはできないよ。だがあんたらには助かる可能性がある」
老婆はヘンリーの問いにゆっくりと手を伸ばすと先ほどのブロンズの円盤を掴む。刻まれている模様に一瞥をくれてから、それが当然であるかのようにキャサリンに手渡した。
「娘さん、あんたはこれを使えるね?大昔に顔のない者がこの[車輪]を造った。車輪はナイアラトホテプの眷属である猟犬からあんたらの姿を隠すことができる。あんたが知っている呪文を唱えれば車輪は力を宿す、あとは猟犬が現れたらこいつを床に置けばいい」
「私が、ですか?でも・・・」
戸惑いながら、キャサリンは老婆の手から車輪を渡される。かつて不死なる者の館で手に入れた「エイボンの書」には老婆が言う儀式の文言が書かれていて、それをキャサリンが読んでいたことも、彼女がそれを諳んじることができることも老婆は知っていて何らの不思議もないのだという奇妙な気分にさせられる。
「ン・ガイの森に降りるもの、黒い翼と三つの目、
盲人(めくら)の招きと膝行(いざり)の歩み、
我は命じる、車輪よ我が顔を隠せ」
文言を唱え終わると同時に、円盤が不思議な力を増すとキャサリンはその重みに耐えかねたように床にくずおれて膝をついてしまう。友人たちに助け起こされている彼女を見て、語り部の老婆は満足そうに頷いたがその表情はむしろ引き下がれぬ道に踏み入れた者への警告と憐憫をにじませていた。
「これでいい、車輪はあんたらを必ず守ってくれる。だが娘の友人たちよ、猟犬が現れたらあんたらは絶対に彼女を守らなくてはいけない。車輪から外に出たらすべておしまいなんだ。いいかい、絶対に出たらいけないよ」
円盤は<エイボンの霧の車輪>を唱えるのに必要な道具だが、この円盤はナイアラトホテプが用意した特別なもので、先に呪文を唱えておけば好きなときに術を使うことができてすぐに効果が出る。とはいえこの呪文はMPが7も必要で、キャサリンのMPは8しかないから彼女はこれだけで意識不明寸前になってしまうので注意。
聖域:Ruins
語り部の家を辞した三人だが、キャサリンは相変わらず具合が悪そうでヘンリーに支えられて立つのがやっとに見える。聖域の場所はデビッドソンから聞いていたがセンチュリー・フィールドからは離れた場所にあって車道も通じておらず、彼女がこの状態で辿り着けるかいささか心もとなく思えた。仮に近くまで行ってもそこから歩かなければならないのだ。
「遅かったな。聖域に行くのだろう、案内するぞ」
さも当然のように現れたホースが、それまでどこかに行っていた理由はすぐに分かった。斑毛と赤毛、二頭の立派な馬が引かれていて斑毛の鞍には彼自身が跨がっている。馬であれば道なき道をまっすぐに抜けることもできて、車で大きく迂回するより早いかもしれない。断る理由はなく礼を言うとホースが乗る斑毛の後ろにキャサリンが、赤毛の手綱はエドワードが握って後ろにヘンリーが乗る。上流階級の出自であるエドワードは辛うじて馬を扱ったことがあるものの、二人乗りで道なき道を行くとなれば容易な話ではない。若い相棒の背に身を預けたヘンリーが口を開く。
「あれだな。こういうとき小説の主人公なら勇ましい掛け声を言うものだぞ」
「ハイヨー・レッド、とでも言っておきましょうか」
馬は決して全速で駆けるわけではないが、慣れない馬に二人で乗って、ときおり木立を避けて右に左によれるからどうしても手綱さばきが狂ってバランスを崩しそうになる。むろん先導するホースの馬はそのようなこともなく、走りやすい道を誘導してくれてもいるが、後にして思えばよくついていけたものだとエドワードは自分ながら感心する。保護区域に入ると木立はますます増えて、荒野の中ではなく木々と茂みの間をぬって走るようになる。張り出した枝を一本、ホースが避けたのを見て慌てて真似をするが思いきり顔を打つと鞍から落ちてしまう。幸いというべきか不幸というべきか、茂みに落ちたエドワードは全身を切り傷と枝葉に覆われるだけで済み、彼の目の前でヘンリーがひらりと着地をすると危なげない様子で助け起こしにくる。
「大丈夫か?」
「いえ。僕が二枚目になれないことを思い知りました」
ここでの乗馬判定は二人乗りだがそれほど難しくはない操作、として二倍で行っている。結局失敗して落馬したが、更に跳躍判定に失敗して怪我を負ったのがエドワードだけなのは更に気の毒に思わせる。
切り傷よりも自尊心に負った傷のほうが深そうに見えるが、馬でなければその日のうちに聖域を訪れることはできなかったろう。日が落ちて夜が訪れたがその日は月も明るく馬に任せれば道を進めることができた。夜通し歩く必要はなく、やがて盛り土に面した石造りの入り口が目の前に現れる。
「ここだ、ここが聖域だ」
石で組まれた入り口の脇に、蓋に使われていたらしい大きな平石が倒されている。馬を繋いでからホースが用意していた松明に火を灯すが、平石の具合や地面の様子を見るに荒らされたのはここ最近で、アンダーソンたちの仕業で間違いなさそうだった。松明を掲げて足を踏み入れると、ひんやりとした石室はそれなりの広さがある。壁や天井はエスキモーの氷の家のように丸く組み上げられて奥には祭壇らしい石の台座が置かれていた。丸い石壁にホースの声が反響する。
「知っているか?祭壇に石は四つ置かれていた。石は白人たちが持ち去った。だが聖域には五人の男がいた。石を持ち去った白人が四人と、彼らを案内したやつが一人いた」
その言葉にキャサリンの小さな悲鳴が続き、二人が振り返るとインディアンの青年が彼女を後ろ手に捕まえてのどもとにナイフを突きつける。クレイジー・ホースは彼の演説と要求を続けた。
「俺が白人を聖域に案内するのはこれで二度目だ。お前たちが持っている青い石を渡せ。石を渡せば女は放してやる。インディアンは白人とは違う。約束は守る」
クレイジー・ホースは彼自身が言った「白人嫌いのはねあがり」の頭目で、暴漢が襲ってきたのも宿が荒らされたのも狂言であり警告だった。猟犬の存在を知った彼は青い石を手に入れようとするが、石を見つけた者は猟犬に襲われるから白人を犠牲にして四つの石を手に入れようとしている。もちろんアンダーソンの石はガリクソンが着服して、彼を殺したホースの手に今は渡っている。
ホースの要求にヘンリーは視線で促すとエドワードから石を受け取り、キャサリンもナイフを突きつけられたまま石を差し出した。彼女の安全のためにこんなものを差し出すのは惜しくないが、ヘンリーが逡巡したのは奇妙なことに他の誰でもないインディアンの青年の身を案じたためである。たぶん彼は四つ目の石がまだ猟犬を呼んでいないことも、語り部から預かった円盤のことも知らない。彼の次の行動は予想できる、だがそれでもヘンリーは忠告しないわけにはいかなかった。
「石は渡す。だが石は祭壇に戻すんだ」
ヘンリーが掌にある二つの石を放り投げると、放物線を描いてホースの目の前の床に正確に転がる。青年は頷いてからキャサリンを突き飛ばして、エドワードが助け起こしているあいだに石を拾うと四つの石が彼の掌に収まった。インディアンの青年は再び演説を始めるが、それは自らの正しさを信じるあまり自らの過ちを忘れた愚者の言葉だった。
「ナイアラトホテプの一族は猟犬を従えてインディアンの敵を殺した。女は解放した。俺は約束を守った。だが白人は皆殺しだ。とぅかとのく・どぅ・ふぉ・てぃんだろす!とぅかとのく・どぅ・ふぉ・てぃんだろす!猟犬の最初の犠牲者はお前たちだ!」
クレイジー・ホースが四つの石を合わせて、聞きなれない文言を唱えると「窓」であり「鋭角」でもある石から強い刺激臭と煙が立ち上る。煙は不自然にねじくれてそのまま重いかたまりになると、それまでは割れた小さな窓から獲物を襲うしかできなかった猟犬がついに全身の姿を現した。それは犬とは似ても似つかない姿をしていて、大きさは馬ほどもあり、全身が皮膚をはぎ取られたような姿をして鉤爪のある四本の手足が伸びている。頭とおぼしき場所は目も耳も鼻も判別しがたいが、禍々しく開いた牙だらけの口があって、真っ赤で真っ黒な空洞の奥から太く曲がりくねった舌が垂れ下がっている。しゅうしゅうという音と強い異臭が漏れて、皮膚からは青みがかった緑色の粘液のようなものがしたたっていた。
それがどのようにして人間を殺していたのかはすぐに分かった。猟犬が身をよじり、前足の先にある鋭い鉤爪を振り回すと斧のような鉈のような一撃がインディアンの首をかんたんにはねとばす。クレイジー・ホースは驚いた表情のまま、自分に何が起きたのかも分からず頭だけがキャベツのようにぐしゃりと床に転がった。胴体はまだびくんびくんと動いていて、そのたびに首から赤黒い血がどくどくとあふれている。インディアンの胴体が血だまりの中に倒れると、びしゃりという音がして赤い飛沫が跳ね上がった。
SANcheck HENRY:success
SANcheck EDWORD:failure
SANcheck CATHERINE:success
恐怖を必死にこらえながら、キャサリンが円盤を放ると床の上に落ちる寸前で浮いて止まりひとりでに回りだした。円盤を中心にして青い円筒がゆっくり広がると三人を囲うように伸び上がる。猟犬は先ほどまでそこにいた獲物が急にいなくなったように思えてそこらをうろつき出す。円筒の中に息をひそめて立っていると、すぐ目の前に粘液をたらしながらしゅうしゅう音を立てた怪物が近づいてくる。それが獲物を見失っていることは間違いないが、むき出しの皮膚を覆っている青緑色の粘液のてかりすら判別できるほど近くを歩いていた。
SANcheck HENRY:success
SANcheck EDWORD:failure
SANcheck CATHERINE:failure
猟犬はしばらく鼻先をひくつかせていたが、獲物が見つからないまま部屋の隅に向きなおる。血だまりを踏むたびにびしゃびしゃという不吉な音を立てて、転がっている胴体を忌々しげに食いちぎると引き伸ばされた臓物が床にばらまかれて、すぐ足下にべちゃりと落ちる。
SANcheck HENRY:success
SANcheck EDWORD:success
SANcheck CATHERINE:failure
猟犬はもう一度こちらに近づいてくると、三人のすぐ目の前で鼻づらを伸ばして、吐く息さえ吸い込めそうなほど円筒にぴたりと顔をよせて牙だらけの口からしゅうしゅうという音を漏らしている。食いちぎった肉と臓物の欠片が化け物の牙のすきまから垂れている様がはっきりと見えた。
SANcheck HENRY:success
SANcheck EDWORD:failure...insanity!
SANcheck CATHERINE:failure...insanity!
今回のクライマックスである連続SANチェックは一時間内の1/5減少による一時的狂気を演出してみたかったためのもの(本当)。期待値ではキャサリンは危険だと思っていたがまさか最初のSANチェックでエドワードが最大値の減少を出すとは黒い肌をしたダイスの神様の御業を思わせる。
ティンダロスの猟犬
STR16 CON30 SIZ16 INT18 POW24 DEX10
装甲2自動再生4 武器無効
エドワードは最初に猟犬を目にしたとき、あまりにも強烈な衝撃が恐怖すらも通り越してしまい自分が何を見たのかすら認識できずにいた。だが少しずつ、ゆっくりと、徘徊する猟犬を観察されられた彼は自分の目の前にいるそれが無造作に自分をばらばらにすることができる存在だということをようやく理解する。極限の恐怖を体験したエドワードの肉体はおぞましい現実を受け入れることを拒否すると、彼の精神が崩壊するのを防ぐために慈悲深き失神という手段を選んだ。
一方で目の前を徘徊する恐怖に涙を流しながら必死に耐えていたキャサリンも、それで遂に堪え切れなくなり堰を切ったように泣き叫び出してしまう。これで円筒から逃げ出せば彼女は恐怖からもこの世からも永遠に解放されていた筈だが、華奢な身体を抱えているヘンリーの腕だけが正気を失った彼女を繋ぎ止めていた。
ヘンリーはこんな事態でもなお正気を保つ自分の目が時として恨めしく思えている。キャサリンは泣き叫びながら彼の腕から逃げようとせず、倒れたエドワードも円筒の中にいて猟犬はこちらに気づいていない。このままやり過ごせば猟犬もいずれ諦めていなくなるに違いないが、それが十秒後か、一分後か、もっと先かは分からなかった。心なしか、円筒の青い光が薄らいできたがこれが消えるとはヘンリーは思っておらず、腕の中のキャサリンに視線を降ろす。
「大丈夫だ。お前さんが俺たちを守ってくれるまじないが消えるはずがないさ」
キャサリンが正気でいれば恥ずかしくて口にできないような言葉をぽつりと呟く。強がりではなく、本気でそう思っていたから彼には猟犬が恐ろしいものには見えなかったのかもしれない。
エイボンの霧の車輪の呪文は誰かが円筒の外に出たら消えてしまう。その場合は転がっている石が割れかかっていることに気付いて、DEX順で先に石を割れば猟犬も苦悶の声を上げて四つに割れてしまう。
という救済策を用意していたのだが猟犬のDEXをうっかりヘンリーよりも速く設定してしまったので、狂気表で2(パニックで逃げ出す)を振っていたらと思うとすみません。
とうとう獲物を殺し尽くしたと信じた猟犬は、煙の姿に戻ると石に吸い込まれるように消えていく。数億年の時間を超えた彼の世界に帰って行くと、後には血だまりに転がった青い石だけが残されていた。猟犬が消えるとまもなく、円筒も消えて浮いていた円盤がからりと音を立てて床に落ちる。抱えているキャサリンをなだめながら、ヘンリーが青い石を拾い上げるとそれは不思議な力でぴったりと合わさっていたが、少しだけ力をこめるとかんたんに四つに割れてしまった。やれやれと呟いて、一つずつ、祭壇に石を収めたところでエドワードのうめくような声が聞こえる。
恐怖のあまり自制を失ったエドワードが円筒を壊していたら彼らはたぶん助かってはいなかったから、寸でのところで彼が最後の一線を越えずにいてくれたことにもヘンリーは感謝している。だが、ふと彼は困った現実に気が付いた。エドワードが意識を失って、気が付いたら猟犬は姿を消していてキャサリンを抱えた自分が石を祭壇に戻している。これは作家としての彼にたいへんな誤解を含んだインスピレーションを与えてしまうのではないだろうか、と考えたところで目を覚ましたエドワードと視線が合った。
「いや、俺は何もしてないからな」
エドワードの瞳に映っている自分の姿を見ると、どうやら彼の意図が伝わっていないことは明白だった。小説家エドワード・ヘイズの作品に登場するヘンリーとよく似た人物は、本物とは似ても似つかないのだという説明を彼はいったい誰にすればいいのだろうか。
ちなみに今回のシナリオでTRUE END消失の条件はシンプソン教授とデビッドソンの娘のどちらかが犠牲になること。ガリクソンの捜査に固執してクレイジー・ホースが二日目の標的をシンプソン教授にする場合と、四日目まで青い石Dを入手しないと猟犬がデビッドソンの娘を殺してしまう可能性があった。
もちろんBAD ENDは猟犬に殺されるパターン。
三人が三様にくたびれた表情で、聖域の外に出ると陽光が差し込み始めていて長い夜もようやく終わったらしい。眩しさに目を細めると、そこには穏やかな顔をした語り部が待っていて彼女の後ろにはインディアンの青年たちが並んでいる。
「タシュンケ・ウイトコは言っていたよ。青い石は私らを守る石だ、とね。だがこれからの世界でインディアンが自分を守りたければ白人と手を握るしかないのさ」
そう言って首を振る。
「白人は聖域を保護区域にして、誰も立ち入ることができないと決めた。残念ながらそれは守られなかった。自ら決めた法を犯した白人と、自ら残した伝承を忘れたインディアンがまた青い石を持ち去ってしまうかもしれない。だが、あんたらを見ていると人は賢くなることもできるかもしれない、そう思うよ」
そう言って語り部は控えていた青年たちに声をかけると、入り口に横倒しになっていた大きな石を持ち上げて聖域に蓋をさせる。別の若者たちが御輿のような担ぎ棒のついた板を持ってくると、エドとヘンリーとキャサリンの三人を無理矢理乗せて担ぎ上げた。年老いた語り部がどこか悪戯げな顔で笑う。
「うちの部族の風習でね、英雄はそれを讃える祭りでもてなすのさ。これもインディアンの文化だ、あんたらには付き合ってもらうよ」
そういうと語り部が朗々と歌う声に合わせて青年たちが唱和して、御輿が上に下にと揺られて三人の白人はしがみつくので精いっぱいだった。人が死んだ、だがこれ以上人が死なずにすむなら祝いではなく祈りのために騒ぐことにしようではないか。
その日の記録はエドワード・B・ヘイズの作品に見ることができて、インディアンの文化の記録として貴重な資料的価値があるとされている。
(Scenario2:TRUE END)
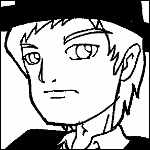 エドワード・B・ヘイズ 24歳男・売れない小説家
エドワード・B・ヘイズ 24歳男・売れない小説家
STR04 CON11 SIZ09 DEX13 APP08
INT12 POW12/SAN60 EDU13
主な技能(%)
オカルト55・心理学60・説得45・図書館65・ラテン語61・目星80・歴史50
精神分析51・天文学31・美術品/骨董品知識31・乗馬25
回避26・英語80
 ヘンリー・マグワイヤ 34歳男・無気力の会代表
ヘンリー・マグワイヤ 34歳男・無気力の会代表
STR10 CON12 SIZ13 DEX07 APP08
INT14 POW18/SAN90 EDU17
主な技能(%)
オカルト35・隠れる40・聞き耳90・水泳35・投擲75・値切り25・博物学50・目星95
応急手当70・機械修理40・信用35・説得25・天文学11・薬学21・歴史40
回避14・英語85
 キャサリン・ブルック(NPC) 40歳女・もと教師
キャサリン・ブルック(NPC) 40歳女・もと教師
STR08 CON07 SIZ11 DEX05 APP12
INT14 POW08/SAN40 EDU20
主な技能(%)
信用85・心理学10・説得50・図書館85・値切り10・法律85・ラテン語81・歴史85
運転25・オカルト25・芸術/ピアノ演奏20・フランス語61・拳銃60
回避10・英語99
>CoCリプレイの最初に戻る

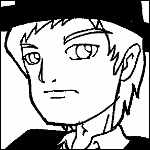 エドワード・B・ヘイズ 24歳男・売れない小説家
エドワード・B・ヘイズ 24歳男・売れない小説家 ヘンリー・マグワイヤ 34歳男・無気力の会代表
ヘンリー・マグワイヤ 34歳男・無気力の会代表 キャサリン・ブルック(NPC) 40歳女・もと教師
キャサリン・ブルック(NPC) 40歳女・もと教師