人物史−ウイリアム・ルスカ
ウイリアム・ルスカは王国暦201年、神聖王国クオス王都にある寺院の寝台の上で生を受けた。下級貴族の家に生まれ、父親は徴税官吏の職責を持ち、母親も傍流貴族の家系であったとされているが、その他に家族に関する記載はほとんど残っておらず、せいぜい裕福な平民程度の生活水準を持っていたとされている。
神聖王国の義務過程である寺院での一般教育と宗教教育を修了して後、彼はそのまま寺院には残らずに王国軍立の幼年学校を経てそのまま軍仕官学校に転じる事になる。神聖王国であるクオスにおいては、軍人や役人もまた寺院から排出される事が多く、軍部が主導するこれらの機関は大きなものではなかったが、軍事に限定しない学識を修めることができる場所として知られていた。当時からクオスの宮廷及び貴族階級や寺院と司法裁判所、軍部の各派閥はそれぞれが対立しており、軍部が独自の教育を執り行う端緒となったのであろうが、より専門的な政治、歴史、経済、語学、組織管理学など、これらの学問の習得を目指すのであれば、寺院や貴族学校よりも軍仕官学校が向いていた事は間違いない。彼がその選択をできたのは下級ながらも貴族階級であったこと、それなりに裕福な家庭であったこと、官吏としての父親が軍部となんらかのつながりを持っていたとされることが考えられている。ルスカ少年の進路選択は、この国における一般の基準から言えば特異なものであったとは言えるだろう。
「軍政、経済の専門的な知識は信仰や伝統から手に入るものではありえない」
後にルスカ自身がそう語っている。軍士官学校での彼の成績は他生徒と比べれば優秀なものではあったが、常に主席の座を外す事がなかったとか、若くしてその存在に後の活躍を感じさせたとか、いわゆる英雄史的な要素は見当たらない。当時の数少ない記録を見ても、例えば特定の分野における突出した成績や論文の類も見当たらず、ごく平凡な優等生というあたりがせいぜいのようである。考査票の一欄に、彼に関する記述として「学業に対して真摯且つ冷静。知識や情報を妄信せず猜疑する傾向がある」と記されており、彼の性格の一端をここに窺う事ができる。
「当時、信仰によって地位を得るつもりであれば寺院に入るのが常であった。資産によって地位を得るつもりであれば一財を用いて共益を成すことで後援者を得る方法もあった。信仰に薄く、充分といえるほどの資産を持たぬウイリアム・ルスカであれば、彼の選択は順当なものであり上等でもあったと言える(歴史学者マリオ・カンパーニ)」
そのように評価する歴史家も存在する。ウイリアム・ルスカが当時から将来の野心と展望を胸に抱いて周到な活動を行っていたとする言はどこにも無いのだが、後代、彼の足跡を知る者の多くは彼の過去にその一因を求めようとして、あるいは彼の野心が顕在化した時期を推定しようとして少なからぬ苦労を強いられる事になる。ルスカが士官学校を志願した理由についても単純な知識に対する欲求の故であったかもしれず、下級貴族出身のごくまっとうな学徒、という以上の存在を彼の過去から窺い知る事は難しいようだ。同時に下級貴族出身のごくまっとうな学徒、という事実そのものが、彼の価値判断と行動基準、及びそれらがもたらした歴史における結果の源泉となっているのである。
軍仕官学校を比較的優秀な成績で卒業したウイリアム・ルスカは、本人の意向もあって神聖王国軍情報部付きの武官補として配属される事になる。一般に軍情報部というと陰謀や策謀の中心部といった印象が強い組織だが、実際には軍需用の食料や物資、武器の手配や管理など数字との格闘、また通信網や伝令設備の配備や運用など事務的な仕事が主な任務となる。無論情報部管轄の任務の中には近隣諸国への情報工作員、ありていに言えばスパイとしての活動も含まれているが、通常スパイ網の構築とは一般人すらも含まれる末端のさほど優秀でない人員多数と、それを統括する優秀な人員の少数によって行われている事が多く、その全容は当の情報部ですら把握されていないことも多い。いずれにしても士官学校を卒業したばかりの人間に割り当てられるような任務で無かった事だけは確かだろう。
ルスカは本人の希望によって軍政官としての道を歩み、事務処理能力と組織管理能力において非凡な才腕を発揮した。だが、組織の通例としてこういった能力を持つ者は優秀な人間としてよりも便利な人間として認識されるのが普通であり、ルスカもまた例外ではなかった。彼はいくつかの成果を上げたがそれはあくまで成果であって功績ではなく、軍人あるいは司祭としての道を歩んだ者たちに比べて、その出世は特に早いというものではなかったようだ。
後世、ウイリアム・ルスカに特に断定的な見解を示す歴史家の中には、彼の歴史上の存在意義と将来への予見力を認める一方で彼を挫折した野心家として扱い、その行動に対しても形式的な出世ではなく、実質的な権力の奪取を目的としたものであったとする意見も多い。だがルスカが軍政官としての道を歩んだ背景もまた彼の野心の現れであり、神聖王国クオスの現状における具体的な国情を把握する事によって、将来の大望への足がかりとする為であったというのは過剰あるいな過大な評価であると言えるだろう。
そしてそれから数年。軍政官の一員として地味な任務を堅実にこなしてきた彼が、成果ではなく、小さいながらも一つの軍事的な功績を立てる事になる。それは彼が有能な軍政官としてではなく、辛辣な軍略家、策略家として知られる事になる最初の契機であった。ウイリアム・ルスカ少尉、当時22歳の時節である。
 ウイリアム・ルスカ
ウイリアム・ルスカ
クオス王国軍における少尉という階級自体は、軍士官学校を卒業したものであれば順当に与えられるものである。当時のウイリアム・ルスカ少尉は財務検査官待遇で各地の食料物資や武器装備の備蓄調査の為に、街道を外れた山間の小さな砦を訪れていた。砦は王都北東部に位置し、隣接する山岳地周辺の危険を監視する為の設備であったが本来は野盗や野獣の出没に備えてのものであり、自然、規模も設備もごく小さな砦である。50人を切る程度の兵士数は、それでも同様の設備に比べれば多い方であったと言えるだろう。
雨と霞が視界を奪う夜。異変に気がついたのは、当直の若い警備兵である。一本の矢が砦にけたたましい警報を鳴らし、同時に警備兵の命を奪った。砦の指揮官であったウイリアム・シーレン大尉は狼狽し、突然の敵襲にただうろたえるばかりであった。彼はこれまで40年以上の人生をごく尋常に過ごしており、物資にも部下の兵士にも充分な視線と配慮を行き届かせる事のできる人物であったが、危急における対処能力はそれとはまた別の問題である。狼狽する指揮官がようやく状況を確認した時、砦は100人を越える野盗の一団に囲まれていたのだ。
神聖王国クオスでは王都周辺に特に厳しい統治が行き届いている分、野盗や犯罪者は辺境や地方に流れる傾向にある。その中には政争や派閥抗争の敗者となった貴族や司祭階級の者が混じることもあれば、それ自体を政争や抗争、あるいは資金調達の道具とするために後援する者も存在した。彼らは非合法が黙殺される範疇をよく心得ていた者たちであり、大規模な野盗の一団がクオスに出没する例は本来稀であったが皆無であった訳ではない。数にして二倍、そして実際の戦闘に耐えうる人間の数であれば三倍の相手に包囲された砦の兵士たちは、自分達のごく近い将来を悲観的に展望する事しかできなかった。
雨と霞に覆われた山間の砦では狼煙の効果も大きくは期待できず、また既に包囲された状況で伝令を出すのは困難であり、まして正面から戦うには兵が足りない。それでもシーレン大尉は専守防衛を決断し、全員で砦に堅く篭ると来援が来るまでの堅守を命じた。無論それ自体は正当な判断であるが、砦の兵たちが急ぎ防衛の準備を整えている中でそれまで資材と兵士の確認を行っていた、指揮官と同名の若い軍政官が別の対応策を提案したのである。来援を待つまでの間、他の防衛策も打ち立てるべきではないかという彼の提案は受諾され、提案者であるウイリアム・ルスカ少尉自身がその指揮にあたる事になった。あるいは彼に責任を押し付ける意図もあったのかもしれないが、無為な防衛策に耐えられない思いがあったことも事実であろう。十人程の血気盛んな兵士が選ばれると、作戦は実行された。
ここでルスカ少尉が選択した作戦は先制攻撃である。門を破るべく、砦を囲うように接近する野盗たちの目の前で正門が開き、砦にいるほぼ全員とも思われる数の兵士が一斉に突撃すると正面からの突破を図った。堅守すると見えた相手からの、思わぬ突撃を受けた野盗は砦の包囲を目的として拡散していた事もあり、大きな被害を受けつつ即時後退するが、無論それだけで崩壊には到らず砦の兵士もすぐに撤退すると今度は門を閉じて堅く引き篭もってしまった。
相手の必死の攻勢が失敗に終わり、戦意を刺激された野盗たちも砦への攻撃を開始するが、さすがに守勢に回った砦を一日一晩で陥落させる事はできない。半日ほどの攻防が続いた後で一度下がろうとする野盗の後方から、突然鬨の声が上がると今度は後背から少数の兵士の一団が襲い掛かってきた。最初の突撃時、突破を図った兵を陽動にして別働隊が砦の外に潜伏し、野盗の後方に回ってこれを撹乱したのである。ことさらにけたたましく騒ぎ立てての奇襲を受けて、一瞬、早すぎる援軍の到着かと驚いた野盗は混乱するが、これが少数の兵士による陽動であると知ると直ぐに体勢を立て直した。潜伏した兵士を発見する事ができないでいる内に翌々日の夜、野盗は再び後方から襲撃を受ける事になるが、今度は陽動である事を知って警戒網を張っており、これを簡単に撃退する。
さらにその翌日、後方からの襲撃に野盗の一団は後衛に割り当てていた部下を回して対応しようとするが、これがクオス本国からの本当の援軍であり、対応の遅れた野盗の一団は大兵力を相手に、呼応した砦の兵との挟撃も受けて壊滅的な打撃を受ける事になる。ルスカ少尉は最初に兵を城外に潜伏させた時点で、援軍の伝令をクオス本国に送っていたのだが、その意図を隠す為に後方撹乱を行い、更にそれ自体を砦への攻勢を鈍らせる為の陽動としたのであった。野盗は撃退され、来援の軍は無事砦に入城した。
若い少尉の大胆な作戦指揮は賞賛され、伝令と陽動を行った決死隊の兵士らはその勇敢さを称えられた。だが、後にルスカ自身が述懐する通りこの成功自体は奇策の要素が強く、内容よりも結果をもって評価される類のものである。それでもこの功績によってルスカは中尉に昇進し、以後、作戦参謀としても軍事に参画する機会を得て多くの功績を立てる事になる。彼の個人史において外す事のできない戦闘であった事は間違い無いであろう。
「この戦闘自体はウイリアム・ルスカの指揮の内でも最悪の部類に属するものであった。が、彼の真に評価されるべきはこの戦闘指揮が最悪に部類されるものである事を自ら認識し、以降の局面においてその教訓を役立てた事にこそあると言える(軍事学者イヴァン・セルゲイノフ)」
軍略家としてのウイリアム・ルスカの基本思想は敵に倍する兵を用意し、敵を分断してかつその逃亡路を押さえ、圧倒的多数をもって分断した敵の一部を殲滅するというものである。それは用兵学の根本を重視したごく当たり前の思考であるが、それに伴う的確な状況の把握、明確な目的の設定、目的を達成するまでの迅速さとそして何よりも辛辣なまでの手段の選択と徹底した実施が後の世に広く知られる事になる。また、常に基本を重視するためにその策が大きく失敗をする事も無く、それが彼の軍部における信頼度を高め、やがて発言力を強めていく事になった。
「ウイリアム・ルスカは天才では無かった。だが、天才よりも恐るべき存在ではあった(マリオ・カンパーニ)」
そして『軍神』ウイリアム・ルスカの評価を決定づける事になったのがそれから2年後、王国歴225年に行われたイルバードの遭遇戦である。
トラッドノア帝国と神聖王国クオスの国境線に位置するユーベル砦、その北方にあるイルバードと呼ばれている小さな平原で発生した戦いは、当初完全な遭遇戦として行われた。対立する両国が国境を接する、不定の中間地点においてクオス国のコーア砦と、当時大陸の三分の一を支配していたトラッドノア帝国のユーベル砦から出されていた軍事訓練中の一部隊同士が偶然遭遇したのが事の発端である。これ自体は完全な偶発事であったが、当事者にとっては戦意を刺激されたのであろう、高圧的な威嚇から始まった小競り合いが乱闘に、更には数百人規模の本格的な戦闘に発展するまでに長い時間はかからなかった。
結局の所両軍の指揮統率能力の不全が混乱をもたらした原因ではあったのだが、死傷者が出るに至って如何な理想や常識論も影を潜めてしまう。事態は直ぐに両軍司令部の知る所となり、混乱を収集する為、詰まるところは軍の名誉と威信を守る為に双方が兵団を投入した。その時、増援部隊を指揮したのが当時コーア砦の法務官付き参謀を務めていたウイリアム・ルスカ少佐であった。
法務官自体はクオス国内法でも軍規程においても部隊を指揮統括することを正式に認められている職責である。その参謀であり、本来は軍政官であるウイリアム・ルスカが部隊指揮官に選ばれた点については、コーア砦の防御指揮官であるラルフ・ロイトリンゲン将軍の部隊動員が間に合わなかった事や、当時の比較的安定した情勢において将軍の下位にあたる人物がルスカ少佐以外に存在しなかった点が挙げられる。従軍参謀として前線の軍政と部隊管理の任に当たっていたルスカ少佐が指名されると、ロイトリンゲン本隊が到着するまでの間、戦線を維持する事を命じられたのである。兵力の逐次投入が戦線の混乱と拡大を助長する可能性についてルスカ少佐は指摘したが受け入れられず、早期動員が可能であった500人の兵士を連れ、イルバードに急行した。
「混乱する前線に兵力を逐次投入すれば、余計な混乱が拡大して犠牲が増えるだけである。であれば方法は二つ、前線の混乱を傍観して本隊の合流を待つか、与えられた兵力のみで早期に混乱を収拾し解決するか。後者は無論賭けであるが、成功すれば際立った華麗さを人々に印象づける事になる。そしてウイリアム・ルスカはその賭けに成功した(イヴァン・セルゲイノフ)」
ウイリアム・ルスカ少佐の指揮する増援部隊がイルバードに到着した時、当初の混乱は既に収束に向かいつつあったが、視界の先、トラッドノア帝国方面からは新たな増援軍が砂埃を上げつつ急行して来ていた。数はほぼ同数。ルスカ少佐は前線で起こっていた戦闘を無視すると、事前に指示を与えていた通りに部隊を敵増援部隊に差し向けた。戦意に溢れるトラッドノア増援部隊は、これに正面から対抗する。両軍まとまった縦隊のままで接近し、互いの距離が接近して戦端が開かれるかと見えた直前、ルスカ少佐は機先を制し弓兵による一斉射撃を行った。
僧兵を中心とするクオス軍において、弓兵の絶対数は必ずしも多くは無いのだが、ルスカは全弓兵を陣の最前部に配置するという大胆な方法で充分な火力を確保し、射程距離ぎりぎりに入った時点で保有する弓を全て用いた一斉射撃を行った。弓兵の存在を相手に警戒させる暇を与えない為の速攻は見事に成功し、トラッドノア軍の最前部は一時的な混乱を来す。そしてこの一斉射撃自体が相手を混乱させることを目的にした陽動作戦に過ぎなかった。
帝国軍の混乱を利用して、ルスカは自軍後衛の軽歩兵隊を両翼に広げ、本隊を迂回させて両側面からの挟撃を指令した。同時に弓兵を後方に下げ、入れ替わるように本隊を前進させる。トラッドノア指揮官であったユイメンは混乱を回避し、指揮系統を回復する為に後退を指示したが、それによってルスカ隊の前進に弾みを付ける形になってしまった。ルスカ隊の前衛は急速前進して突撃を図り、突破は果たせなかったものの両翼の挟撃部隊と呼応して包囲陣を完成させる。更にルスカは本隊を右方向に向け、敵の左半分を完全包囲して攻撃を集中させた。左側の挟撃部隊が敵右翼部隊を牽制し、混乱する半数の敵をごく短時間で撃滅したルスカ隊は、残る半数を余裕を持って「処理」しにかかった。ロイトリンゲンの本隊が到着した時、戦闘は既に集結しており、ルスカ少佐は当初の訓練部隊同士の戦闘の収拾と負傷者の救出にあたっていた。
この戦闘でルスカ少佐の用いた戦法は基本的な両翼展開による半包囲戦である。だが、奇襲となる弓兵による一斉射撃とそれによる戦闘主導権の確保、迅速な部隊展開と戦局への対応は基本的と言える範疇を大きく越えていた。増援部隊がコーア砦からイルバードに到着するまでの間、ウイリアム・ルスカ少佐は信号と合図による数種類の命令のみを配下に伝えていたとされており、兵士は予め定められた部隊展開のパターンに従うだけで多大の戦果を上げる事に成功してしまったのである。
イルバード遭遇戦で当初動員された兵力はクオス訓練部隊104名に対してトラッドノア訓練部隊128名であり、うちクオス側の犠牲者数は37、トラッドノアは34であった。更にウイリアム・ルスカの増援部隊の兵数513名に対してトラッドノア軍ユイメン隊は607名、しかしルスカ隊の犠牲者28に対してユイメン隊の犠牲者及び捕虜の数は450を数えた。これはクオス軍のパーフェクト・ゲームと言ってよい内容であり、戦果である。ウイリアム・ルスカ少佐の功績は讃えられ、中佐への昇進が確定した。
「最も基本的な戦術を最も迅速に、効果的に用いる術は正に神速としか表しようがない。しかもそれはウイリアム・ルスカの天才によってもたらされた効果では無く、彼が事前に周到に用意した予定表の上の結果に過ぎなかったのだ。既に何をするか決めている相手の行動速度を上回る事は、如何な天才にも不可能であろう(イヴァン・セルゲイノフ)」
この後トラッドノア帝国と神聖王国クオスの間では一時的な修好関係が築かれ、ウイリアム・ルスカは本国に戻ると軍政官として神聖王国軍の再編や管理の任にあたる事になる。それから数年、平時に於いて有能な人材であり、非常時に於いて希有な人物であるウイリアム・ルスカが再び歴史の舞台に顔を出すのは、大陸の情勢に大きな変動が起こる正にその時であった。
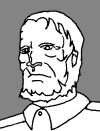 アレクサンデル・バルギルボル
アレクサンデル・バルギルボル
王国暦229年、それまでの沈黙を破りトラッドノア帝国大将軍アレクサンデル・バルギルボルが全大陸に向けて突如宣戦を布告した。後に帝国戦争と呼ばれることになるこの戦争は当時、国内勢力の分裂と解体が著しかったトラッドノアで宮廷と貴族勢力に反発した軍部が暴走した結果であると言われており、一説ではそれを示唆したのがクオスであったとも言われている。トラッドノアの宣戦自体はクオスもその対象に入っており、将軍の突然の狂行に各国は戸惑いを覚えつつも当時のクオス女王ニーナ、後の大女王は前線であるコーア砦に兵を送る。そして神聖王国軍情報部大佐であったウイリアム・ルスカは、この時自らトラッドノアではなく辺境の都市国家、バスキア国への友好使節を志願していた。クオスの探索隊によって数年前に発見されていた都市国家バスキアは、それまで他国から隔絶されていた鉱山都市であり、古代遺跡からの発掘品を中心とした特異な産業と文化、技術力が注目されていた。いずれの国との国交もほとんど成立しておらず、辛うじてクオスが国として接触した程度である。砂漠と山岳に囲まれた辺境には往来する旅人や商隊も無く、将来はともかくとして当時は慎重な対応が求められている存在であった。
軍事的緊張が増大する中で、大佐級の人間があえて前線から離れた辺境の都市国家に赴く事が承認された理由は彼自身が情報部所属であり、通常武器を持って、あるいは兵を直接指揮して戦う立場に無かった事、そして彼が軍部に提出した使節案の内容自体によるものであったと言われている。
この提出案の原文は今も現存しているが、要約すると帝国の宣戦布告を契機に、小国であり国力に不安のあるバスキアと手を結び、当地でガンナーと呼ばれている銃兵に代表される技術力と特異性とを味方に付け、更に協力体制を他国にも広げて帝国を包囲挟撃する政治的体勢を構築するというものであった。また興味深い事実として、これらの提出案においてルスカ大佐はトラッドノアの動向を脅威には思わず、寧ろ彼らが大義名分を失う行動を取った契機を利用して最大限の利益を上げる案を進言していた点が上げられる。そしてこれ以降も、彼はトラッドノアに対しては常に脅威を感じず、そこから生じる自信が他者に強い印象を与えずにはいられなかったようだ。
「歴史上、外交策を無視して軍事的先制や侵略活動を行った勢力は大勢の支持を失い、反動によって衰退或いは滅亡する例が多い。ウイリアム・ルスカはその事実を知っていた。だからこそ彼は帝国に対して常に脅威を感じる事が無かった(マリオ・カンパーニ)」
当時28歳であったウイリアム・ルスカ大佐について、外見的特徴に関する記述は意外な程に少ない。中肉中背で眼鏡を着用していた、などという記述は特筆に値する程のものではなく、眼鏡の下の目つきが鋭く、あるいは険しく、あえて言うなら精悍と言えなくもない顔つきであったという記述が残っている程度である。むしろ他者から見た彼に関する記述としては、彼の行動や印象に起因しているものが圧倒的に多い。常に冷徹で冷静であったとか、その視線から野心を窺う事ができたとか、眼鏡を直す仕草が印象的であったとかいう類のものである。いずれにせよ、彼はその外見によって自らを主張する者ではなかったようだ。
特使としてバスキア国に赴いたウイリアム・ルスカ神聖王国軍情報部大佐は、できすぎた偶然ながら重大な事件に巻き込まれる事になる。当時のバスキアの発掘産業の成果であり、基盤にもなっていた黒柱石の盗難事件がそれであった。その名の示す通り黒い水晶体を思わせる巨大な鉱石は、加工をせずして自ら熱を発するという極めて珍しい特性を有する鉱物であり、当時のバスキアの重要なエネルギー源の一つとなっていた。そしてトラッドノア帝国の工作員が潜入し、この黒柱石を盗み出した事件は当時のバスキアの政府と民衆に大きな衝撃を与えたのである。閉鎖されていた社会に対する唐突なまでの帝国の敵対行動に対する困惑と、黒柱石の消失によってもたらされたバスキア産業への影響はこの小さな都市国家を震撼させた。
そしてこの時特使としてバスキアに赴いていたウイリアム・ルスカはこの事件を利用し、些か強引な手法によってクオスとバスキア間の軍事同盟を成立させてしまう。後代この事件は「できすぎた偶然」として彼に批判的な人間から懐疑の目で見られ、あるいは幸運を主張されるのであるが、この件に限らずウイリアム・ルスカは状況を利用する術に異常な程に長けており、本来彼の不利に働くと思われる事件でさえも彼は自らの利益になるように変質させてしまうのである。そしてその手腕こそが、当時の彼の二つ名である「軍神」の異名を誕生させたと言っても過言ではないであろう。
いずれにせよ、長きに渡る閉鎖国家であったバスキアを開放させた彼の功績は充分に歴史的な意義を有するものであったが、それを両国間の軍事同盟までこぎつけた手腕、または図々しさは並大抵のものでは無かった。彼はこの時、トラッドノア帝国の諜報工作員がバスキア国内に潜入した事実を受け、これを挙げて帝国の脅威を謳い、クオス及びバスキア間の協力の必要性、それにより得られる両国の利益を主張したのである。帝国の行動はクオスとの修交を窺わせたバスキアに対する挑発的な意味を有していたとも、純粋に黒柱石の工業的な利用価値について着目したためであるとも言われているが、その真意はともかくとして、その行動は完全にクオス及びバスキアを、更に言えばウイリアム・ルスカを利する結果となったのである。軍事同盟受諾の正式な報告を受け、当時の神聖王国軍情報部本部長であるボアルチエは、幕僚会議の席上で
「これで歴史が動いた」
と語ったと言われている。クオスは兵力と資源に不足するバスキアに軍事的経済的な支援を行い、バスキアはガンナーと呼ばれる銃兵の貸与と技術の供与を行う。更に地理的にはクオス及びバスキアは二方面から帝国に対する事になり、帝国に対して軍事的に対応する基盤を確保する事ができる。また、これ以降クオス王国の前線では兵装、運用、士気において飛躍的な発展を遂げる事になり、特に前線での新戦術の開発においては、当時のコーア砦指揮官クリフ・ロネイア将軍と共に数多くの運用を行い、実際の成果を上げている。ロネイアによる銃兵の特性を生かしたゲリラ戦術、またウイリアム・ルスカの考案した火力集中戦術、あるいは機動性縦深陣とのコンビネーション戦術等いくつかの有効な戦術がこの時生み出され、クオスの戦術として後代に伝えられた。
「当時、僧兵を中心にした重装歩兵による密集戦術のみを主としていたクオス軍に、射撃戦や機動戦を組み合わせた柔軟な兵の運用による組織的な一斉攻撃という新戦術を導入したという点で、両者の能力は賞賛に値する(イヴァン・セルゲイノフ)」
またバスキアにおいては閉鎖社会に対して外交を意識させ、それが今後の急速な展開を生み出す事になるのである。
ウイリアム・ルスカが提出した先の使節案について、彼の表向きの名目である学術調査を主体とした一枚の報告書が存在する。それは技術調査、生態系調査、文化及び文献の調査を中心とした内容であったが、それらの多くは軍事的な転用が可能な技術ばかりであった。よって学術調査に真摯にとりくむウイリアム・ルスカの姿勢は彼の野心の現れであったとする向きも多いのだが、実際の所は、本来学徒としての彼が軍政官として他国の調査を行うにあたり、このような調査書を作らなければクオス軍部の了解と協力が得られなかったという事実もまた存在するであろう。古代遺跡の上に建てられた発掘都市であるバスキアは、ウイリアム・ルスカならずとも学徒としての探求心を煽る存在であった事は疑いない。
「技術、生態、歴史、文化、いずれを取っても興味深い。しかしその中で最たるものは組織と政治体系であろうか」
当時のルスカが残したメモの中に、このような一文が発見されている。これにある通り、彼は探求心の赴くままに、公的な要求と私的な欲求とによってバスキアの調査を進めていたが、最終的に、または立場上であったのか彼に興味を抱かせたのがバスキア国がその歴史的背景の上に手に入れていた政治体制の特長と危うさであった。
クオスの歴史にはありえなかった、王制でも神権制でもない政治体制。皇帝や司祭ではなく、国内組織の代表者が集い、議会を設立して行う政治体制はウイリアム・ルスカに新しい興味と将来への展望を抱かせた。だが同時にバスキア国内においてそれが十全に運用されていない事情も彼は見て取っており、その原因が閉鎖社会における内政と産業の停滞にあった事を彼は指摘し、また残念がってもいる。
いずれにせよ、彼はバスキアの持つ可能性に目を付けると同時に、現在のバスキアが近い将来に必ず迎えるであろう衰退への道を理解してもいた。産業の停滞と外交知識や経験の不足という政治的経済的な要因に加えて、人口の減少や出産率の低下など民族としての衰退、そして何よりそれらを積極的に打開する為の国民の意志が致命的なまでに不足している。当時、ルスカの非公式なコメントとして、
「クオスは200年、バスキアは50年で滅びる」
というものがあり、バスキア人医師であるキオ・ルーウェンを始め、幾人かにその事を語っている。同時にこの内容から、当時から彼がクオスの神権体制が持つ限界を示唆していた事も見て取る事ができる。
「彼はクオスとバスキアがいずれ滅びるであろう事を知っていた。しかしクオスとバスキアを救おうとは考えなかった。(マリオ・カンパーニ)」
正確にはルスカはクオスやバスキアを救おうと考えなかったのではない。クオス国とバスキア国を救う算段よりもまず両国の民衆を救い、それによって彼の構想を実現するための味方を得る事を考えていたのである。
そして第一にルスカが行った事は、バスキア国内における政治的基盤の確保である。それが国際的に有効であるにしろそうでなかったにしろ、クオス及びバスキア間の突然の軍事同盟は特に保守的な勢力からの猛反発を受ける事になった。修好するのであっても何故それが軍事同盟でなければならなかったのかという、彼らの主張はもっともであろう。中でもバスキア自警団の団長であったエルス・ビドエニッチなどは反クオス派の急先鋒として知られていたが、ウイリアム・ルスカが彼を徹底的に排斥することによって反対派の行動を制限してしまったこともまた批判の要因となっている。
反対派を排斥するに当たり、ルスカの取った行動が辛辣とまで評される理由はそれが単なる陰謀や物理的な手段に依らなかった事にある。彼は当時のトラッドノア帝国の動向とバスキアの産業の停滞という事実からくる危機を声高に説き、自警団の団員、つまりエルスの部下達を説得して懐柔した。更に当時、反クオス派テロリストによって引き起こされたルスカ自身への襲撃事件をも利用し、バスキア政府と当の自警団にこれらの対処を委任する事で両者に対する優位性を確保。同時に国家としての体面から事件解明に全力で当たらざるを得ない自警団は、エルスら反対派がルスカに対抗する為に行動する時間的余裕をも奪われてしまう事になる。ルスカはこれらの「まっとうな」手段で反対派の行動に制限を加える一方で、自警団の中でも特にクオスに協力的な者を中心に協調関係を築き、反クオス派の最大勢力であったバスキア自警団の内部意思の分裂を図った。
無論彼の取った行動はこれだけにとどまるものではない。クオス北東部の開拓地をバスキアに貸与し、生産力の停滞と外交的な混乱の渦中にあるバスキア国の助けとなり、また最悪の場合避難所ともなりうる拠点を設けた。バスキア人の中でも親クオス派に近いキオ・ルーウェンらの協力を得てこれらの政治的経済的援助を行う事によって、多くの中立派バスキア人を味方に付ける事に成功してしまったのである。
「50人の敵に対抗するに、最上の策はうち1人を敵として49人を味方につける事である」
これもウイリアム・ルスカの発言である。使節として政治的に保護されているとはいえ、数人の護衛を連れただけで混乱期にある異国の地に滞在し続けた事実は彼の胆力を証明するものであっただろうが、同時に彼自身がそれを効果的に利用したふしがあることは疑いない。ルスカは「クオスの者としてクオスの為になり、その上で更にバスキアの利にもなる提案を行う事」を自ら明言し、実行する事でかえって多くの人間を信頼させ、味方につける事に成功した。どんな思惑があるにせよ、当時のバスキアにおける政治や産業の混乱と停滞を解決したのはウイリアム・ルスカであり、バスキアの民衆は彼を支持したのではなく、支持せざるを得なかったのである。
こうして反対派を排斥し、己の政治的地盤も強めると、ウイリアム・ルスカは軍事同盟の成果と、バスキアからの銃兵の供与への返礼を示すべくクオス本国から兵士を招聘した。それは対トラッドノア帝国最前線であるコーア砦より、士気の低下を理由に一部撤退した兵たちであったが、この際ルスカが求めたものは最低限の核となる兵力の数であった。士気が落ちているとはいえ、本来彼らは最前線で戦闘に参加した経験を持つ者たちであり、いずれバスキアの銃兵と合わせて訓練を行う必要がある以上、その質はさほど問題にはならなかったのである。また、800人に達するクオス兵の到着は、それまで少数の護衛しか有さなかったウイリアム・ルスカにとってはそれだけで身辺の安全とさらなる影響力の強化とを約束するものでもあった。
無論、ルスカは政治的な要件からこれらの「援軍」をいきなりバスキア国内に進駐させる事はせず、トラッドノア帝国との国境に向かう郊外に仮設の砦を建築し、貸与を受けた銃兵とともにこちらに駐留させた。それは兵士の進駐によりバスキアの民心を刺激する可能性を考慮したからであるが、さらに実際の行動によってクオス軍がバスキアの守備についた事を宣伝する目的、砦の建築による軍需によって停滞しているバスキアの産業を多少なりとも活性化させる目的、兵士訓練の場を設けて戦略的にもトラッドノアの軍事行動に即時対応できるだけの施設を構築するなど、複数の理由を内包していた。一つの行動により複数の効果を期待し、そのうちの幾つかの結果によって実際の利益を得る。それがウイリアム・ルスカの行動哲学であった。
「ウイリアム・ルスカの策は無論、全てが成功する訳ではない。彼は同時に幾つかの策を立て、そのうちの幾つかを成功させるのだ。そして、それこそが彼の策謀の基本理念なのである(イヴァン・セルゲイノフ)」
だがクオス神聖王国軍情報部大佐ウイリアム・ルスカの急激な台頭に、最も懸念を抱いていたのはおそらく当時のバスキア政府首脳部であったろう。クオスの国力を背景としたバスキアへの援助や実際の効果、そして彼自身の術策の手腕によってバスキアの内実が掌握される過程を見れば彼らが心中穏やかでありえなかったのは当然と言える。何より、少なくとも結果としてバスキアの民衆の為に行動している人間を排斥する事は、バスキア政府首脳部の人間としては不可能であるという深刻なジレンマが彼らには存在しており、ウイリアム・ルスカに対するバスキア政府首脳部の感情は直線的なものではありえなかった。
当時、クオス神聖王国友好使節ウイリアム・ルスカの襲撃事件よりまもなく、不可解な殺人事件が発生している。その内容はバスキア自警団の一員である青年が、人気の無い路地裏で何者かに襲撃を受け殺害されたというものであったのだが、先の襲撃事件同様混乱の中にあるバスキアの警察能力の低下を証明するかのように、この事件の実行犯は後代になっても判明していない。通説ではルスカの失脚もしくはクオスとバスキアの同盟破棄を図った人間の犯行とされており、トラッドノア帝国の工作員か、またはバスキア内過激派集団の犯人説が有力とされている。
この事件では現場でクオス王国の紋章が入った短剣と、同じくクオスの物と思われる衣服の切れ端が発見されており、これをもってウイリアム・ルスカを犯人とする説も存在するのだが、こちらはルスカやその護衛たちに直接的な犯行の動機を見つけることができなかった事、現場に格闘を行った痕跡が無く工作が行われた可能性が窺える事、状況的に剣を持った自警団の人間を短剣で殺害する事が困難であると予想された事もあってこの説はほとんど支持されていない。特にバスキア政府にとっては友好親善使節に対して政治外交的な失点を重ねている事もあり、不充分な状況証拠で追及することもできず、むしろ積極的にウイリアム・ルスカの嫌疑を晴らすべく行動していた。事件の犯人が未だ不明であるのにルスカを擁護する材料だけが揃っているのもその為で、この事からこの事件は、ウイリアム・ルスカとバスキア政府が共謀して国内の過激派勢力を牽制する為に行った、とする説すら存在する。
いずれにしても、これらの事象のことごとくがウイリアム・ルスカの行動範囲をひろげ、逆にバスキア政府や自警団、反クオス派の行動範囲を狭める事につながっていった。そしてウイリアム・ルスカはバスキアの内実を掌握すべく、更に活発な活動を行う事になる。バスキア商工ギルド長、バーネル・ガルフとの協力関係の設立がそれであった。
 バーネル・ガルフ
バーネル・ガルフ
バーネル・ガルフはウイリアム・ルスカより15ほども年長の人物であり、格幅の良い体格と抜け目の無い視線は商人というよりむしろ官僚を思わせるものであった。当時、バスキア自警団員の殺害事件に際してガルフはルスカの嫌疑を晴らす事に最も尽力した人物の一人であるが、事件直後、彼は当のルスカと会談を行っており、記録ではその内容は対トラッドノア前線砦の建築についての協力の要請であったとされているが、ここで何らかの政治的または経済的な交渉が行われた事は想像に難くない。
公的な訪問ではないため、会談の具体的な内容については知られていないが、以降のルスカとバスキア商工ギルドとの間に設けられた協力体制の礎となる内容であった事は疑いないであろう。推測ではあるが、具体的にはそれは交易と金融の為の技術と設備の提供案であったと言われており、クオスの持つ貿易の技術や船舶の供与を提示した上での要求であったとされている。ウイリアム・ルスカの構想はバスキアの地勢を利用してクオスと大陸東方の国家との間に新航路を開発、三角貿易を成立させ、その成果をもってバスキアの経済力と政治力とを強化しようというものであった。それは本来商人であるバーネル・ガルフにとって、この上なく魅力的な商談に聞こえたであろう。
「自分の理想の為に相手に利益を与える。信頼や忠誠では無く、打算と野心によって他者を意のままに操る。そこにこそウイリアム・ルスカの真の恐ろしさがあった(マリオ・カンパーニ)」
バーネル・ガルフは打算と野心によってウイリアム・ルスカと手を結んだ。そしてルスカは自分に協力するバスキア人であるガルフを厚遇し、クオスからバスキア政府に提供していた援助物資のうち、特に技術や知識を与える比率を徐々にバスキア商工ギルドに傾けるようになる。バスキア商工ギルドは自らの野心と打算によって自らの実力を向上させ、そして彼らはウイリアム・ルスカの手を握り、以降協力と発展への道を共に歩んでいくことになる。船舶、海産、開拓、農産、建築、金融、軍事など様々な方面で、バスキア商工ギルドは急速に発展を遂げた。そして、組織の代表が議会を構成しているバスキア国家の中で、バーネル・ガルフの実力と影響力もまた急速に増大していったのである。
この「商談」によってウイリアム・ルスカが要求した見返りはただ一点、会談の表向きの目的でもある対トラッドノア前線砦の建築に関するバスキア人の労働力と資材の提供であった。これは黒柱石の盗難事件に伴い停滞状況にあるバスキア産業に、軍需による一時的なテコ入れをする理由もあって実施されているが、この砦の建築が所詮表面的な事項であって、ウイリアム・ルスカの本来の目的はバーネル・ガルフとバスキア商工ギルドとの協力体制を築くことそれ自体にあった事は周知の事実である。
「彼が築いた物は、ちっぽけな仮設の砦などでは無論なかった(イヴァン・セルゲイフ)」
ウイリアム・ルスカとバーネル・ガルフの接近、及びバスキア商工ギルドの急速な発展に懸念を抱いたのは、誰あろうバスキア政府自身であった。権力機構の内部に生息する者たちの常として、自らの縄張り、勢力範囲が影響を受けるにあたって強い不安と不満を感じるのは当然かつ自然な事である。だが、彼らバスキア政府の要人の多くにとって不幸であったことは、長く他国との国交を絶ち塀の中での安寧に浸かっていた結果として、政治や外交に関する手腕と知識のほとんどを深い泥の中に埋もれさせていたことであろう。
彼らはウイリアム・ルスカがバスキア国内の内実のほとんどを掌握した時点になって、ようやく重過ぎる腰を上げてクオス本国へ使節を派遣したが、重要な職責を帯びて派遣されたウォズニは政治外交におけるバスキア政府の能力の乏しさを証明する事しか成し得なかったのである。ウォズニは名のみで姓を持たず、かつ一部バスキア人の特性でもある突然変異的な異相を持つ人物であり、毛髪の無い頭部と斑模様にも見える皮膚が特徴的であった。いかな異相であってもバスキア国内でそれが必要以上に意識や差別の対象となる事は無い。彼はバスキア政府三大首脳の一人としてクオスに赴いたが、いずれにせよ外見と能力が相関関係を示さない事もまた厳然たる事実である。
彼はクオス王国内の対トラッドノア前線であるコーア砦に赴き、そこで重用されているバスキアの銃兵団を慰労するのではなく、バスキア政府の代表として彼らが前線に置かれている事への不満の意を表明した。自国の人間が危地にある事への不満の念は、国粋主義者や人道主義者としてはおそらく賞賛に値するものであったろうが、危難を共有することによる国際的な貢献に対する配慮の不足は外交においてはもちろん、前線の兵士に対する統治者の感想としても充分以上の非難と批判に値するものであった。
バスキア国家の外交材料として、危険を覚悟して前線に有る兵士。殺す事と殺される事に従事させられる危難を与えられている者に対して、ウォズニの表明は無配慮ありで酷薄なものですらあった。こと今回の軍事同盟に関する限りにおいて、彼らこそがバスキアの国家を代表する者として前線に赴いているのであり、それを非難されたのでは立つ瀬が無いというものであった。また、クオス兵にとってもウォズニの発言は、クオスから多くの援助を受けている立場にある者としては傲慢に過ぎる主張であった。
「本来、外交も商談も取り引きの要素を強く持つものである。その関係は特にリスクに対する認識において対等なものであらねばならず、一方的に与え、一方的に要求するだけでは単なる奴隷と主君の関係に他ならない。長きに渡って他国との外交を絶ってきたバスキア首脳部は、クオスからただ与えられ続ける事に慣れてしまい、自らの立場に疑問を持つ事も無くなっていた。彼らは奴隷としての能力も暴君としての資質も兼ね備えていたが、残念な事に対等の友人を作る思想には欠けていたのである(マリオ・カンパーニ)」
上の辛辣なまでの批評は、バスキア所属とクオス所属であるとを問わず、当時のコーア砦の将兵の意見を代弁したものである。そして、これに前後してクオス政府とバスキア政府との間に意見の相違が見られるようになるのであるが、その間もウイリアム・ルスカとバスキア商工ギルドは精力的な活動によってお互いの協力関係と他者への影響力を強め、時代は主権国家という小さな枠組みを越える方向へと歩みを向けていくのである。
後代、ウイリアム・ルスカは一国の軍政官として軍略的な識見を基にしながらも国家の枠を超えた構想を打ち立て、それを実現した者として歴史上に少なからぬ貢献を果たしながらも、とかく批判的な評価を下される事が多い。その功績は充分に認められつつも、彼の思想と行動が非難される理由は、良いと悪いとに関わらず彼の独善的な行動にあった事は疑い無いだろう。正義と信念は全てを免罪する、などとウイリアム・ルスカは思ってはいなかったが、自らが思考し、判断し、責任を持って行動する限りにおいて、彼が他者の批判や非難を意に介さなかったのは確かである。
「歴史と政治におけるウイリアム・ルスカの基本理念は、おそらく中学校の教科書に記されているような初級の概念から外れるものではなかった。初歩なればこそ真理、という思考は無論尊重すべきものであるが、人は数字と方程式の中においてのみ生きるものではない(歴史家ロバート・マホーニー)」
「現実主義に基づく主張が権力者の自己弁護として利用される時、それはその組織が大きな自己矛盾との衝突を回避し得なかったという事実の存在を意味する。多数の安寧を得る為に少数の犠牲を甘受する、という思想は正当なものではあり、古来より権力者にとって魅力的なものでもあったが、少数派の末路に慄然とした多数派の心中を思えば、少数の敵を徹底的に排斥しつつ、多数の味方を擁護するウイリアム・ルスカの姿勢が批判を受けるのもまたやむを得ぬ事ではあったろう(マリオ・カンパーニ)」
これらはウイリアム・ルスカに対する批判的な意見の中で最も代表的なものであるが、結局の所、彼の辛辣さ、計算高さ、あるいは容赦の無さが他人の忌避を買うものであったのだと言わざるを得ない。そして最も残念な事実は当時、彼に最も批判的、あるいは懐疑的であった人物がバスキア政府三大首脳の面々であったという事であろう。
神聖王国軍情報部大佐ウイリアム・ルスカの政治構想において、バスキア商工ギルドの発展と、それを軸とした国際的な協調関係の構築を目指す事は大前提であったが、その一環としてのクオスからの技術、知識援助に加えて彼が行ったのが山脈と森林を挟んでバスキアの隣国にあったアルカンシェルとの外交交渉である。
アルカンシェルは正確には国家ではなく、当時のクオス、バスキアと敵対していたトラッドノア帝国の辺境に位置する帝国内自治都市であった。もともと同地は古来より文化と学問を修める自治国家であったのだが、或いはそれ故に強力な政治指導力を持ち得ず、設立より数百年以上もの間トラッドノア帝国の属領となっていたものである。アルカンシェル自体は古くよりクオスとの国交があり、また、同政府が常にトラッドノアからの分離独立を志向している事も周知の事実であったから、この会談がクオス、或いはウイリアム・ルスカにとって有益な結果をもたらすものになると一般には予想されていた。
「この会談自体はウイリアム・ルスカにとって極めて不本意な結果を招来した筈であった。しかし、そうなるべく図った人々の思惑をすら、彼の知性と理性は越えていたのである(イヴァン・セルゲイノフ)」
アルカンシェル自治政府代表リン=シアとの会談において、ウイリアム・ルスカの提唱したクオス及びバスキア、アルカンシェル三国間の通商条約締結案は少なくとも表面上は謝絶された。トラッドノア帝国の属領であるアルカンシェルにとって、本国を刺激しかねない条約への参加に難色を示すのはごく自然な反応であったろう。この時期においては将来の政治的状況の変化に伴いアルカンシェルが同条約への参加をする可能性が示されれば、ウイリアム・ルスカにはそれで充分であったが、結果としてこの会談の結末は後にアルカンシェル自体を窮地に陥れることになる。
また、この訪問においてルスカはバスキア政府及び商工ギルドからも同行者を帯同しており、特にバスキア商工ギルドの人間を政治外交に参加させた事は彼らにとって重要な意味を有していた。非公式ながらこの時彼らはアルカンシェルの鉱山長であり首脳部の一人でもあるエルドラドという人物と接触を持ち、現地でスターパールと呼ばれている宝石の流通において協定を持ったとされている。バスキア政府が自国内部で自分達の権力を安定させる為に画策している間、ウイリアム・ルスカに主導されたバスキア商工ギルドは若い商人を中心に積極的な産業の展開を行っていた訳で、バスキア政府の要人が古びた土壁を内部から補修している間、若い世代の人間は、ひび割れた壁の内側に閉じ篭っている老人達を後目に外の世界を体験していたのである。
ウイリアム・ルスカがバスキア国にもたらした政治改革は基本的に現体制に因らずに新秩序を築く事で、無論それは旧来の保守勢力には受け入れ難いものであり、また彼自身もその事を良く理解していた。国家と勢力によらず、彼は改革派、革新派の人物と協調関係を結ぶ事が常であったし、アルカンシェルにおいてもそれは同様であった。ただ、同政府に関しては潜在的にトラッドノア帝国に反発する意志があり、それを利用する為にもルスカは彼らと公的な接触を持つ必要があったのである。そしてその目的は達成されていたのであるが、その間隙を縫っておそらくルスカですら予期していなかった「極めて不本意な結果」が帰還後の彼を待ち受けていた。
バスキア政府から示された軍事同盟破棄の提案である。
神聖王国軍情報部大佐ウイリアム・ルスカが、クオス特使としてトラッドノア帝国自治領アルカンシェルを訪問しているのに前後して、ルスカと自国内商工ギルド長バーネル・ガルフの台頭を忌避したバスキア政府は、特使としてエルス・ビドエニッチをトラッドノア帝国に派遣している。
交渉の内容は不戦条約を目的としたものであり、全大陸に宣戦を布告していたトラッドノア帝国に対して軍事的な保護と安全を求めるというものであった。だがおそらくバスキア政府は気付いていなかったであろうが、第三者から見ればそれはまぎれもなく降伏の申し入れ以外の何物でもなかった。本来大国による宣戦布告の最大の目的は、自国の権威をもって他の小国を従わせる事であり、事は軍事外交における常識である。そして外交における知識と経験を持たないバスキア政府は、最悪の形でそれを露呈してしまったのである。
バスキアの「降伏宣言」を受けたトラッドノアは当然の要求として、バスキア政府にクオスとの軍事同盟の破棄、同国が国境線に築いた仮設の城塞の撤廃と軍事力の撤去、安全保障税としてバスキア産業の成果物の一部を無償で供与する事、以上の三点を提示した。エルス・ビドエニッチはアルカンシェル訪問の為にウイリアム・ルスカらがバスキアを離れていた間にこの提案を持ち帰り、そしてバスキア政府はこれら帝国の要求を受諾する意志を決定したのである。
「民意を無視したクオスとの同盟締結を非難された政府が、民意を無視してクオスとの同盟を破棄しようというのだ。これを愚挙と呼ばずして何を愚挙と呼ぶべきであろう」
これは後のウイリアム・ルスカの述懐であるが、この発言からは彼自身もクオスとバスキアとの軍事同盟の経緯を、些か強引なものであったと思っていたらしい心情を窺う事ができる。いずれにしてもアルカンシェルから帰還した彼らを、ほとんどの人間が予測もできなかったであろう事態が待ち受けていた。辛辣な表現を用いるのならば、誰もがバスキア政府がここまで無能であるとは思ってもいなかったのである。
また、奇妙な事であるかもしれないがこの件に関してバスキア政府特使を務めたエルス・ビドエニッチは、バスキア政府の主張が帝国への事実上の降伏宣言であった事、そして帝国の要求が事実上の降伏勧告であった事を最初から理解していたとされている。後に発見された彼の手記にある述懐により、戦火を避ける為に帝国への降伏もやむを得ないと思ったという彼の心情も判明しており、その行動には同意する声も多いが、より以上に批判と非難の対象ともなっている。結局の所、事態の重大さを理解していなかったのはルスカでもビドエニッチでもなく当のバスキア政府であり、それがさらに急速な事態の変化を招く事になった。だが、多くの人々がその変化がウイリアム・ルスカにとって不幸な結果を招くであろうと思っていたのであるが、これまで彼の辛辣な政治外交能力を実際に目の当たりにしてきた人々でさえ、自分達が単にそう思っていただけに過ぎなかったという事実を思い知らされるのである。
クオス神聖王国軍情報部大佐ウイリアム・ルスカがトラッドノア帝国自治領アルカンシェルから帰還した時、彼を出迎えたのはバスキアからの軍事同盟破棄の提案という凶報だった。狼狽したバスキア商工ギルド長バーネル・ガルフからの報告は、当初に一報を受けてからバスキアに帰還するまでの間、既にルスカが考えていたのであろう提案によって直ちに和らげられる事になる。ウイリアム・ルスカが提唱したのはバスキアからの提案である軍事同盟の破棄を全面的に受け入れる事、そしてそれまでバスキアに対して提供していた物資や技術を、以前からルスカがクオス北方の海岸線に用意していた開拓地に向け、そこにクオス自治領としての新バスキア自由経済主義共和自治領、通称ネオバスキアシティを建造するというものであった。
ネオバスキアシティはクオスの自治領としてクオスの政治的軍事的な保護を受ける権利と、独立した自治体としてバスキア及び他の国家と外交折衝を行う権利を有する。更にアルカンシェル訪問で得たエルドラドの協力によるスターパール貿易の拠点としての活用、アルカンシェル経由で中立国のファグオからカラクリと呼ばれる工業品の製造技術を輸入し、貿易と工業と金融とを産業の中心とする。そしてバスキアからの移民や戦乱による避難民を受け入れる事で量的な増大を図る。これをしてルスカ自身は「シナリオの変更」と称し、現バスキア商工ギルド長バーネル・ガルフを自治領主の座に据える事を提言した。また、この時に交わされた書簡は後に「ルスカ書簡」として後のマクシミアヌス三世に着目され、ウイリアム・ルスカの歴史的な功績を証明する史料とされている。
「古い遺跡の管理は老人に任せて、我々はより広い視野で物事を見るべきでしょう」
ウイリアム・ルスカがバーネル・ガルフにネオバスキアシティの構想を語った時、彼は会談の最後をこのように結んだと言われている。これは他国民に対していっそ堂々と亡命と移民を勧めている行為であるが、無論、バーネル・ガルフに目の前に開かれた権威への扉を放棄する意思が無い事は明白であった。会談の後、更にルスカは医師のキオ・ルーウェン、バスキア民族の中でも先天的に色素が薄く、地下に居住区を設けて生活している異相の部族の代表、ギ・ド・メイらにも非公式の協力を要請し、受諾されている。これはルスカがこれまでの活動によってバスキアの内部にどれだけの協力体制を築いていたかを物語るものであったとも言えるだろう。
この件に関してはバーネル・ガルフとルスカの間に交わされた書簡を除けば詳細な記録は残されていないが、当時バスキアの地下に存在した異変なるものが各国の状況をより複雑なものとしていた。それはバスキアの遥か地下に眠っていた黒柱石の喪失によって引き起こされた事件であり、極めて特異な放射線か、あるいは細菌の類であったのではないかと伝えられているが判然としない。その影響はすさまじく、古来よりバスキアに異形の民族や異様な生態系が存在する理由はその地下に眠るものの影響によるものとさえされていた。黒柱石が元来備えていた、独自でエネルギーを発するという性質はこの影響を最小限に抑えており、それが失われた時に力の暴走が懸念されたのである。
ウイリアム・ルスカがバスキア内部において非公式に行っていたのがこの地下の驚異への対応であり、これは本来学徒であったルスカがバスキアの学術調査中に発見したものであったとされており、バスキア人医師のキオ・ルーウェン、地下居住民族のギ・ド・メイらがルスカに協力したのもそれ故の事であったと言われている。
ネオバスキアシティの設立に伴い、ルスカが提示したのはこの機会を利用したバスキア人のネオバスキアシティへの避難、すなわちバスキアからの移民であった。元来バスキア北方の海外線の開拓地は貴重な物資を提供しうる農地の拡大を目的に、戦乱による避難民の受け入れを名目にしてクオス上層部にルスカが認めさせたものであった。バスキア地下の異変に関連して当地の住民を避難させるに当たり、郷愁や愛着といった感情面の反発を呼ぶであろうその手段と方法が懸念されていたのであるが、バスキア政府の混乱とネオバスキアシティの設立に関わる状況を逆用する事でバスキア人の移民を実現させる。この考えには何ら確証が無いが、後にルスカがこの考えを目的として持っていた事は間違いが無いとされている。
「あらゆる状況を利用する。自分に有利なように。状況の不利に負けて改善を諦める凡人とウイリアム・ルスカとの違いは唯一そこにのみある(マリオ・カンパーニ)」
この後、クオス神聖王国大使ウイリアム・ルスカとバスキア政府首脳部との間で深刻なやり取りが交わされる事になる。それは公式な物と非公式な物と、双方においてであった。
軍事同盟破棄の提案に関して、バスキアの主張は戦乱よりも民を守る事を重視する為、そしてバスキア地下の異変の対応に専念する為というものであった。後代多くの歴史家がこれを自国の利益のみに捕らわれた身勝手な発言であると批判しているが、寧ろ批判されるべきはこれがバスキア政府の意思というよりも自警団団長にして対クオス強硬派の急先鋒、エルス・ビドエニッチの意思そのままであった事にあるだろう。この時点で既にバスキア政府は有名無実化しており、自らの意思で外部との折衝を行う能力も内部の調整を行う能力も失っていたものと思われる。
バスキア政府の申し入れをルスカは意外なほど簡単に受け入れ、会談に先だって彼が予め用意していた条項を読み上げた。それは同盟の破棄に伴いクオスがバスキアに供与或いは貸与した全ての物資を返還する事と、同時にバスキアがクオスに供与或いは貸与した全ての物資を返還する事という物であった。無論、同盟破棄を申し入れた側にあるバスキア政府はこの申し出を受理するしか無かったのであるが、実の所クオスがバスキアから受け取っていた利益は銃兵と銃の貸与のみである。そして、前線コーア砦への銃兵の到着次第、その構造と特に運用技術においては長く解析と研究とを行っており、更にバスキアから輸入された工業技術を基に、銃に比べて火力は劣るが遥かに安価な火薬式ボウガンの製造と実用化が行われる段階に入っていたのである。もともと発掘品を流用して作られた兵器であるバスキア銃はその数が限られており、大規模な実戦投入に耐える事は出来ないとルスカは考えていた。性能が劣っても安価で大量に製造出来る飛び道具としての火薬式ボウガンの存在は、クオスにとって銃よりも遥かに貴重で重要な戦力となっていたのである。
これに対してバスキアはこれまでクオスから受けていた援助物資の返還に加え、後にネオバスキアシティとなるクオスから貸与されていた開拓地の返還とそこで得られていた権益の放棄も加わり、今後は不戦条約を結んだトラッドノア帝国への安全保障税をも負担しなければならず、形式だけの独立と引き替えに将来の展望の殆どを失う事になった。
「形の無い技術を返還し、形の有る物資の返還を要求する。これだけ悪辣で単純な詐欺を仕掛ける方も仕掛けられる方も常識を疑う(ロバート・マホーニー)」
いずれにせよ同盟破棄の会談は短時間で終わり、ウイリアム・ルスカは前線砦の撤収後ネオバスキアまで退去する事になった。この時、バスキア前線砦に所属していたバスキア人兵士の内のかなりの数が傭兵としてルスカに帯同しており、この事実も前線の兵士の心理を明確に代弁していたと言えるであろう。
しかし、これに対抗する立場であるバスキア政府の行動もウイリアム・ルスカの退去後、迅速に行われた。商工ギルド長バーネル・ガルフを以前発生したウイリアム・ルスカ襲撃事件の主犯として逮捕拘禁したのである。その理由としてバスキア自警団に残された記録には、ルスカ襲撃事件後に起こったバスキア自警団員の殺害事件に際して、現場に残されていた短剣と衣類の一部が商工ギルド内で発見された為であると記している。しかし前記においてこの事件の真相が未だ不明であるとされている通り、この記録の真実性は甚だ疑われており、殆どの史書に於ける見解では犯人不明とされているのが通常である。ただし、一般的な解釈ではトラッドノア帝国の工作員、商工ギルド長バーネル・ガルフ本人、そしてエルス・ビドエニッチらが何らかの形で事件に関っており、それらが意思統一を見ずに対立した結果では無いかという解釈が定説となっている。これに続いて後に帝国工作員の仕業として知られる商工ギルド幹部の襲撃、殺害事件が多発しており、バスキア国内は一挙に治安の低下と混迷の度合いを深める事になるのである。
「しかし、あくまで混迷の度合いを深めたのはバスキア国内のみであった(マリオ・カンパーニ)」
バーネル・ガルフ逮捕拘禁の報は無論直ぐにルスカの下に届けられた。彼は直ぐに自ら記した書状をバスキア政府に送付した。ところがバスキア政府はこの書状をガルフが拘禁されている自警団に回したのであるが、これを受け取った自警団副団長が事件の管理責任はバスキアにあるとしてこの書状を破棄してしまったのである。
その為書状の内容は現在に伝わっておらず、恐らくはバーネル・ガルフの身柄解放とクオスへの引き渡しを要求する物であったろうと推測するしか無いのであるが、いずれにしても他国の外交官からの書状の内容を政府がろくに確かめもせず、しかも送付した担当者が手紙を破棄してしまった事実は重大な過失である。正当な手続きに依らない手段はその内実を問われる以前にその正当なる資格を失い、それは充分な批判と非難を受けるに値した。ウイリアム・ルスカがこの幼稚な失敗を見逃す筈も無く、公式文書の破棄という外交の常識からは信じられないような無礼を働いたバスキア政府に対して手厳しい勧告が為されるに到った。こうなってはバスキア政府にも反論の余地が無く、正式な謝罪と当の自警団副団長の解任と更迭、更にクオスの希望に沿うという形でバーネル・ガルフの身柄解放とクオスへの引き渡しの要求とを受諾せざるを得なかったのである。また、余談ではあるがこの対応もバスキア政府が自警団副団長にのみ全責任を押しつけて自己の保身を図ったとして、後世の非難を受けるに到っている。
ネオバスキアシティにおいて新自治領主、バーネル・ガルフを受け入れたウイリアム・ルスカはそこを中心とした新体制の拡大に急速に取り組んでいった。同地ではバスキア人の出入国に一切の制限を設けず、それがバスキア人を中心とした交易に大きく寄与する事になったのである。混迷の深まるバスキア国内で生活するよりも、出稼ぎとしてでも交易、製造、開拓等の産業に溢れているネオバスキアシティを訪れる方が余程生活を補償出来るのは間違いが無い。民衆が生きていく為には日々の糧が必要であり、それを与えてくれる政治組織を支持するのは自然というより当然であったろう。
また、ここに至って南方のイトリエールからの使者、又、クオス本国から女王ニーナ自身がネオバスキアシティを訪れウイリアム・ルスカとの会談を行っている。ルスカがネオバスキアシティを中心に構築しつつある通商産業を主体としたトラッドノア包囲体制はその内実を強化すると共にその効果を各国に期待されつつあり、南方で手を結んで帝国に対抗しているイトリエール国及び孤月国が同盟締結と首脳会談の意思を提示してきたのである。ニーナ女王の訪問はネオバスキアシティの視察とこれらの状況を伝える事であったが、同時にニーナ女王自らが密使としてイトリエール国と極秘の同盟締結を行った事、トラッドノア首脳部がバスキア地下の異変を利用して大陸北部に混乱を招こうと画策している事、また、幾つかの内部確執からトラッドノア方面クオス前線のコーア砦指揮官、クリフ・ロネイア将軍がクオスを出奔した裏事情等が明らかにされた。
ただし、これは後代になって知られる事であるが、事実は先のクオス及びイトリエール同盟締結に代表されるクオス首脳部の独走と秘密主義に不満を持ったロネイアが軍部内で不穏な動きを見せつつあった事に対して、女王とその周辺が先手を打ち彼女を追放したものだとされている。同時に将軍としてのロネイアの影響力が増大していた事実を忌避したクオス首脳部が、彼女を排除する為に行ったという一面も存在し、同様の視線がウイリアム・ルスカにも向けられていた事は後に明らかとなる。
大陸北部でのネオバスキアシティの発展とバスキアの混迷、その利用を図るトラッドノア帝国の策謀、南部でのイトリエール孤月同盟の設立とトラッドノアへの進攻、そしてそれらに対抗する帝国の思惑。それまで大陸の一隅、バスキアという小さな都市国家の周辺でのみ繰り広げられていたウイリアム・ルスカの活動はここに至って大陸全体への影響を持ち得る一要素としての資格を得て、その後の歴史に名を連ねる事となる。だがその舞台として用いられたのはバスキア国ではなく、ネオバスキアシティであった。
混迷の時代は若い軍政官を翻弄すべく数多くの策謀を施してきたが、そのことごとくを美酒の如く飲み干した若い俳優は遂に大陸全体に視界の届く歴史舞台にその姿を現す。対トラッドノアを大義名分とした同盟国間首脳会談が実施されたのは王国歴230年、ウイリアム・ルスカ29歳の時である。
王国暦230年。クオス、イトリエール、孤月三国間首脳会談が開催されたとき、各国首脳は後に帝国戦争と呼ばれる戦乱における勝利を既に確信していた。その名目はトラッドノアの軍事的脅威に対抗する為の協力体制の確立を掲げてはいたが、実際には後に「勝者の分割統治」と呼ばれる事になるように、敗勢の確定していたトラッドノア帝国に対する各国の軍事行動の調整、帝都エストリル攻略の時期の確認とが簡潔に行われた後、主題であるその後の帝国分割案における意見の調整が行われていた。
「通常、戦争の帰結は戦争が終結する遥か以前に定められる(イヴァン・セルゲイノフ)」
積極的な外交施策を自ら打ち出していたクオスは女王ニーナに同行する形で外交使節のうち武官代表としてウイリアム・ルスカを、またバーネル・ガルフを新バスキア自由経済主義共和自治領主として帯同し、当時クオスが大陸北部に確立しつつあった通商航路の確保を目的として、その為の主張を行う必要があった。また民族として差別の対象となりかねず、更に外交に関する知識と経験を有していないバスキア民族の人物を対外的な場に紹介する効果も無論考慮されていた。彼等の目的がネオバスキアを中心とした各国間の交易路の確保にある以上、民族融合型の国際体制の確立には注力されて然るべきであり、その為の地道な活動の一貫は以降僅かな血統としてではあっても、バスキア民族の滅亡を防ぐ事に繋がっていく事になる。一部の民俗学者達はウイリアム・ルスカの最大の歴史的な功績は国家の枠を超えた協力関係を構築したことではなく、バスキア民族を解放し、その血統を保全した点にあるとする主張を繰り返している。
 クオス女王ニーナ(大女王)
クオス女王ニーナ(大女王)
トラッドノア侵攻については南方のイトリエールと孤月との連携により、当時の時点で既に充分な戦果が上げられており、帝国都市オワセから北方、沿岸航路を主とした大陸北部の陸路と海路とをクオスが確保する事、アルカンシェル及びファグオとの交易と海産物を主とした大陸東部海域の権益を孤月が取得する事、そして帝国南部から森林地帯に至る広大な資源域とトラッドノア帝国の主都市を主とした大陸南部をイトリエールが統治する事で三者間の合意に達した。また各国間で情報開示を行い、この時期既に著しく戦力が衰微していたトラッドノア帝国が工作員によるテロや破壊活動しか行えない状態にまで追い込まれていた事もあって、その活動に対する警戒と軍備の増強とに務める事で会談は終了した。三国が協調している限りにおいて各国はトラッドノア帝国に対して圧倒的に優位な立場にある事、それを再確認する事が会談の究極的な目的であったといえる。以下は会談における同盟案の条文の抜粋である。
*同盟はトラッドノアの大陸侵攻及びその宣言に対して一致団結して協力し、これに対抗するものである。
*同盟はトラッドノア政府の消滅又は降伏を最終的な目的とする。
*軍事的、政治的対応については各国協議の上、同盟の利益と目的とを優先するものとする。
*同盟により得られた利益の配分については各国協議の上、公正で公平であるものとする。
・
・
・
*同盟は目的が達成後解除され、軍事力による長期的な束縛を避けるものとする。
*上記に替わる秩序としては、軍事力によらぬ方策を指向するものとする。
これらを見るに、会談が強者の論理をもってトラッドノア帝国の解体とその後の分割に対して各国の足並みを揃える事が目的であったという意思が示されている。また、この時ウイリアム・ルスカよりクオスの意見として発言された内容の中には、相互利益を期待出来るだけの産業通商の仕組みを構築する事が望ましいとの要件が挙げられており、この基本姿勢は彼がバスキアの地を始めて訪れた時から変わっていない。敵と味方とを明確に区別し、敵には弾圧を味方には援助を与えるという明快で極端な姿勢は当時においても後世においても批判の対象となる事が多い反面、当の味方となる人々にとって頼もしく有り難いものであった事は間違いがないであろう。
ウイリアム・ルスカが予てより推進していたクオスの船舶工業技術の向上に関しては、ネオバスキアを中心とした積極的な運用と技術開発とによって充分に他国に提示し得る商品となっており、開拓地の拡大に伴う農産物と合わせてイトリエールの森林資源、孤月の海産資源との交易を約束する事で各国の生産性は飛躍的な向上が期待出来ていた。対して大陸中央部において広大な領土のみ保持し、戦乱で疲弊した農地と農民、そこからの搾取による金融資本のみで経済が成り立っていたトラッドノア帝国が瓦解するに至ったのも当然の帰結であったと言える。
「結局の所、無理な外征と内圧とによって滅びる典型的な亡国のパターンをトラッドノアも辿る事になった(イヴァン・セルゲイノフ)」
戦略においては南部から侵攻を行っているイトリエール孤月連合軍に呼応する形で、北方からクオス軍が侵攻する。都市国家の集合体であるトラッドノア帝国を個別に攻略し、橋頭堡を確保しつつ帝都に侵攻する為の方策について確認が行われ、各国は戦乱終結後の優位な外交的立場を確保する為の手段として、帝国侵攻の為の最終準備に取り掛かる事になる。無論クオスもその為の準備に取り掛かる事になり軍事会議が開かれる事になる訳だが、実の所『軍神』ウイリアム・ルスカ主導による大規模な軍事活動が行われるのはこれが初であるであると同時に唯一のことであり、そして後世の歴史において彼の二つ名が確定するのもこの侵攻作戦によってであった。
平地が多く、小規模の都市が街道によって繋がっている大陸内の文化では、それまで歩兵を中心とする重装陸戦兵団が常に戦争の中心となっていた。特にトラッドノア帝国ではその傾向が強く、中核となる軍隊に加えて非常時には農民が収集され構成される民間の騎士団が戦力の絶対数の中心となっており、この方法は国力がそのまま兵力に繁栄できる反面で、軍事教練が必ずしも行き届いてはおらず、指揮能力において不安が大きかった。また、これらの事情から戦争とは歩兵或いは騎兵の大軍同士による衝突と決戦の繰り返しとなり、それは英雄的な将軍の台頭と大陸の中央に威を構える帝国の利ともなっていたが、その他の方策を用いる余地がなくまたその発想に彼等が至る事もなかったのである。
僧兵を中心とするクオスもまたトラッドノア帝国と同様の重装歩兵を主力としており、神聖王国軍大将軍であるラデューを中心に編成されていた。姓を持たないこの人物もかつての戦乱期に前線で活躍したいわゆる英雄的な人物であり、トラッドノア帝国と同様に伝統的な大陸文化に従った存在であるとも言える。ウイリアム・ルスカがバスキア方面に作り上げた部隊は小規模なものであったが、それは個人の能力に頼らず重装歩兵とボウガン兵との連携による機動能力を備え、運用パターンの信号伝達による緻密な戦術能力を有する極めて組織的なものであった。そしてこれにネオバスキアを中心に展開されていた船舶運用技術が合わさった時、驚くべき化学反応を生じるに至ったのである。その策は沿岸航路を高速船舶によって移動し、大軍を直接帝都周辺へ送り込むというものであった。
クオスを迂回し西方海域の大渦島を経由する航路の安全を確保する事、大陸を横断する河上を登り、帝都エストリルに近い工業都市オワセへ到る経路に関する地理的な情報を得る事、充分な船舶の数と運用技術を確保する事、水上戦闘に有効となる強力な飛び道具の使用と信号による迅速な陣形展開能力を持つ事。大陸中央部の都市はその地勢から河川の周辺に発達しており、容易に橋頭堡を確保できる上に、水上輸送は大軍を高速で移動出来る上に将兵の疲労度を抑える事が可能である為、前線を飛び越えて帝国軍の中核を直接攻略する事が可能となる。ウイリアム・ルスカが創出した作戦案は大陸沿岸航路を高速船舶によって移動し、トラッドノア帝都エストリルに到る河川を溯上、橋頭堡として河川の北岸にあるオワセの街を南方から、つまり城壁の後方から急襲して陥落させるというものであった。奇術的な策略を支える幾つかの不可欠となる要因において、これまで神聖王国軍情報部大佐ウイリアム・ルスカはバスキア及びネオバスキアでの活動によってその全てを満たす事に既に成功していたのである。
三国首脳会談によるクオスに与えられた戦略的な目的は、帝国北部戦線への出兵とそれによる南部イトリエール孤月戦線への援護である。そこで明確な侵攻ルートが開示されていた訳では無かったし、その兵力等についても同様であった。これは戦略的な要件があるとはいえ無論ウイリアム・ルスカが意図的に秘匿していた為でもあり、会談に臨んでいた時点で彼の中には既にこの構想が完成していた様子が窺える。北部戦線に出兵する事と南部戦線を援護する事。それら連合軍としての戦略目的の他に、クオスとしての政略的な目的としてはトラッドノア帝国に対する画期的な軍事的勝利を治める必要があり、後の「勝者の分割統治」の為にも対外的な効果を持つ充分な戦果を上げる必要があったのである。
また、この時期アルカンシェルで勃発した鉱山長エルドラドの反乱について、これはウイリアム・ルスカ等による先のネオバスキア訪問時に非公式の協力体制を築いていたエルドラドが、その実力と影響力の増加に伴って現政権に反旗を翻したものであったが、少なからずクオスとウイリアム・ルスカの方針に影響を与えるものと思われた。だがその行動は、帝国攻略に専念したクオス側が静観した事で掲げる火も続かずに早期に鎮圧される事となったのである。
アルカンシェル現政権が帝国属領であり、その当主であるリン=シア自身がかつてクオスからの同盟の申し出を正式に謝絶し、公的には友好関係が築かれていなかった事、エルドラドのネオバスキア商工ギルドとの協力体制もまた非公式なものであった事、エルドラドの反乱自体が成功せず、しかもそれがアルカンシェル警備隊では無くトラッドノア帝国からの援軍によって早期鎮圧された事、更にアルカンシェルに居残った帝国軍がそのまま武力行使によって現政権を更迭し、親帝国勢力としての新アルカンシェル政権を立ち上げた事など、複数の要素によって混乱を極めた情勢は、寧ろクオスが新たに介入する余地を狭めてしまい、アルカンシェルにとっては大いなる禍根となったもののそれがクオスの外交政策や戦略にこの時点で影響を与える事は無かったのである。
無論、事態を静観した事実に対してクオスやウイリアム・ルスカに非難の声が上がったのは事実ではあるが、無謀な武力反乱の挙に出たエルドラドを見殺しにした事に対する感情的な意を除けば、その判断は決して不当なものとは言えないであろう。また混乱に際して海上からの少数の逃亡者は孤月やネオバスキアへ非難する事になるが、それらの受け入れを行った事が彼等に対する消極的な肯定ともなっている。そしてこの挿話自体はこの時点では余談にしか過ぎなかったのであるが、アルカンシェルの新政権は後のトラッドノア帝国の残存勢力として大陸東部に居を構える事となり、孤月を中心とする東部海域の交易に関する情勢について大きな影響を与える事になるのである。
「或いはこれにトラッドノア帝国を生き残らせる為の方策としての要素が存在していた(イヴァン・セルゲイノフ)」
これについては先の会談内容による三国間の協定がトラッドノア帝国の消滅または降伏まで、としている点が問題とされており、トラッドノア帝国を生き延びさせる事によって国内の軍事力を整備する時間を設ける為の口実となり得た。混乱期において軍備を増強する為の口実を確保する事は各国にとって重要であったし、トラッドノア帝国自体は既にその程度の存在でしかなかった。
多分に政治的な思惑の中で、クオス軍の進軍は北部戦線、アップファル及びヴィジランスの東西両域に向けて開始されていた。重装歩兵を主力とする本隊の指揮はラデューによって行われ、国力の低下による本国の不動と補給の停滞によって士気の下がっていた帝国軍の抵抗を爆砕する事に成功する。この主力戦力の進軍自体は陽動であるのだが、大兵力の運用によって恒久的な拠点の確保を行うという正統的な目的も有していた。仮にウイリアム・ルスカの策が失敗した場合でもクオスの対トラッドノア帝国への戦略目的は充分に達成される訳であるが、対イトリエールや孤月に対する政略目的を達成する為にはルスカの別働隊の存在は不可欠であった。
本体の進発と同時にネオバスキアより出港した神聖王国軍情報部大佐ウイリアム・ルスカ自身が指揮する船団は、かねてより確保していた沿岸航路を通って大渦島を迂回、帝都エストリルへ繋がる河川で高速船に移乗すると一路オワセの城へと急行した。オワセは帝都エストリルへ繋がる拠点となり得る都市であり、防衛の為に築かれた城壁が河川側から見ると後背に当たる事が今回の作戦では重視されていた。この時、船団を更に二分し片方を輸送船団に見せて更に陽動としたのはウイリアム・ルスカの芸の細かい所である反面、計画に固執し過ぎる面であったかもしれない。
夜間の船舶による進軍を高速で行うだけの部隊運用技術があった事が、この作戦を成功させた最大の要因であるとして指摘されているが、パターン化された予定表の中の行動を信号伝達によって伝える事で、彼等は通常陸路の進軍では考えられない速度でトラッドノア帝国の中枢近くに突如出現したのである。これにはかつてバスキアからトラッドノアに潜入していた民間協力者である、カールソン兄妹から入手したとされる現地周辺の地図情報による所も大きいとされており、情報部としてその扱いと重要性を特に認識していたウイリアム・ルスカの性格を窺う事が出来る。
襲撃は速やかに行われ、弓による衛兵の狙撃と城門の封鎖を行い、領主官邸、兵団駐留地、治安管理本部、物資集積所、工場設備、交通通信情報拠点など制圧目標の迅速な攻略が達成された。衰微した帝国の兵力はより前線に配備されていた事もあり、軍事力が空洞化していたオワセは夜が明ける前に陥落した。散発的な抵抗を鎮圧すると民衆を宣撫し、オワセをクオス支配化としてトラッドノア帝都エストリル攻略の為の拠点とする事を宣言したのである。この後、元々工業都市として機能していたオワセに一時的な産業の凍結を行い、その生産力を帝都攻略の為の物資調達に回した事はウイリアム・ルスカの悪い意味での軍人らしさであったとして指摘されている。
「占領地住民の協力者を明確にする目的があったとはいえ、軍人による経済統制は軍事力による国家統一主義への第一歩と成り得る。(ロバート・マホーニー)」
またウイリアム・ルスカの支配化にある都市、という名目は後に彼の所属するクオス本国から糾弾される材料とされる事になる。それまでネオバスキアではバーネル・ガルフを自治領主に据えるなど文民支配の形式を守って来たウイリアム・ルスカが戦時における前線拠点での対応を理由に後の禍根を残す事になった。彼自身はオワセを前線の野営地であるという名目で指揮官による一時的な管理を行うというつもりでいたようであるが、理由を見付ける事に注力している人間にとって、大切なのは形式のみであったのである。ウイリアム・ルスカがオワセ民衆に対して布告した文面の内容は以下の通りである。
「本日をもってオワセ砦はクオス神聖王国軍の管理下に入った事をここに宣告するものである。当地の管理権限はクオス神聖王国軍ウイリアム・ルスカ大佐に委譲され、また、これに伴いオワセの民衆に期限付き戒厳令を布告し、一時的な外出の禁止を通達する。尚、この戒厳令については当地の混乱、被害を収集後直ちに解除されるものとする」
当地の管理権限がウイリアム・ルスカに委譲され、という一文が独裁化、軍閥化の証拠だとして後にウイリアム・ルスカはクオス本国との確執を余儀なくされる事になる。アップファルとオワセの陥落により大陸北部に強固な地盤を築く事に成功したクオスはこの時点で既に戦略的にも政略的にも一定の目的を達成していたとされ、戦乱の終結が至近の未来に見えるようになるとルスカのような危険人物は有害な存在となる。コーア砦指揮官クリフ・ロネイアの出奔も同様の事情によるものであり、クオス首脳部の発表では帝国に亡命していたとされていた彼女の遺骸も、後にクオス郊外の洞窟内で無残な惨殺体として発見される事になるのである。
オワセを橋頭堡として補給及び製造拠点としたウイリアム・ルスカは即時帝都エストリル侵攻の為の準備を開始した。クオスの僧兵は彼等の言う所の邪悪な帝国軍の手先に対して強硬な姿勢を取る事が多かったが、これを制御し当地の生産を運用し得たのはウイリアム・ルスカの非凡な面であった。またアルカンシェルの混乱によりファグオ及びアルカンシェルからネオバスキアを経てクオスと結ばれていた産業航路はネオバスキアからクオス、オワセへと繋がれる事となり、そして南方のイトリエールでも孤月との同盟によりファグオへと到る貿易航路が形成され、これが北方のネオバスキア産業航路と繋がる事となる。これらの結果、大陸北部ネオバスキアから西部を廻り、内陸のオワセに拠点を設けた後に南部を迂回して東方の孤月へと到る新経済体制が実現する事になり、旧バスキアそこから阻害される形となる。クオスの大陸北部制圧とアルカンシェルの混乱による東部海域の閉鎖は旧バスキアにとって外交及び通商の致命傷となり、トラッドノア帝国と不戦条約を結んだ彼等は将来に向かって掛け渡されるべき橋を失う事になるのである。
「バスキア民族を救ったのは、結局の所ウイリアム・ルスカの融合政策であった(マリオ・カンパーニ)」
しかし連合軍の帝都攻略に先立ち、トラッドノア帝国は最後の絶望的な抵抗に出る事になる。帝国指揮官「魔導師」ヴィーアによる魂血の方陣の解放がそれであった。
 「魔導師」ヴィーア(本名不明)
「魔導師」ヴィーア(本名不明)
魔導師ヴィーアとはクオスの伝承に伝わる災厄の具現化した存在であり、いわば物語上の人物である。その名を称する人間によって引き起こされた魂血の方陣の解放について信頼できる詳細な記録は残っていないのだが、残っている文献によればバスキアを中心に数箇所で起こった異変に人民が倒れ、軍勢は動きを止められ、帝都への侵攻軍は本国との連絡路を絶たれたとされている。これは一部の伝承には結界という言葉でも記されているが、強い酸化性ガスか何らかの細菌か、或いは地域によってその双方を使い分けたかによって各地に混乱を図ったテロ行為であったとされている。三国会談で懸念されていた、追いつめられた帝国が起こし得るテロ活動が最も派手な形で実現されたのである。ヴィーアの名は信仰のあるクオス兵に対して精神的な圧力を掛ける為のものであったと推測されているが、何れにせよ前線にある各国連合軍が本国との連絡と補給を遮断された事は事実であった。彼等は本国との連絡を回復するか、早急に帝都エストリルを陥落させ、混乱と策謀の根を絶つかを選択する必要に迫られる事になったのである。
もっとも、この戦いが既に掃討戦になっている事は関係者には既に承知の事であった。事がトラッドノア帝国首脳部がアルカンシェル新政府に亡命するまでの時間を稼ぐ為に弄した奇策であった事は自明であり、魔導師ヴィーアもまた燃やされる為に用意された人形に過ぎなかった。連合軍は帝都エストリルを攻囲すべく迅速な行動を開始した。この時、ウイリアム・ルスカ自身も本国との連絡の確保を後事にして早期出陣し、連合他国の軍と合流、帝国内都市からユーベル砦の領主兼指揮官であり、降伏していたタジカ・トキオイらの協力によって各軍は歩みを並べて帝都エストリルへと進軍を行ったのである。大将軍バルギルボルを討ち取り、魔導師ヴィーアを倒したのは言わば演出であり、帝国に対しても連合軍に対しても、トラッドノア帝国が壊滅した事を示す為の宣伝であったに過ぎない。伝承にある悪の魔導師の出現に苦笑しつつも、混乱するクオス軍の僧兵達に向かってウイリアム・ルスカが演説した内容は一つだけである。
「伝説の魔導師などという存在を恐れはしない。人間の力は人間たちの力には遠く及ばないのであるのだから」
事実、孤月の軽歩兵、軽騎兵軍、イトリエールの弓兵軍、クオスの重装歩兵とボウガン隊、そして孤月とクオスの海軍による連携は、一連の戦乱においてトラッドノア帝国軍将兵達の多くを祭壇の供物として捧げてきたのである。陸戦兵力の単純な数と力において勝っている筈の帝国軍は、遂に純軍事的な展開において連合軍から優勢を勝ち取る事は叶わなかった。帝都エストリルが陥落した時、多くの民衆も政府高官も既に郊外や他国に避難しており、バルギルボル将軍の狂熱的な暴走とそれに野合した策謀家達のテロリズムによって引き起こされた大陸の混乱は、あっけない形で幕を下ろすかに見えたのである。三国間協定が正式に結ばれ、大陸北部をクオスが、南部をイトリエールが、東部を孤月が支配する事になったが、大陸東部に残る小勢力の存在がこの時の最後の課題とされた。以前より自由交易を謳っていたファグオは孤月の協力国としての立場を与えられ、独立した自治都市としての存在を許され北方のネオバスキアと共に工業と貿易の中心地となるが帝国属領となっていたバスキアとアルカンシェルには強硬な弾圧の手が伸びる事になる。
辺境に位置し、既に資源も資本も枯渇していたバスキアは小さいが故に無害な勢力として各国監視下で経済封鎖された状態での存続を辛うじて認められていたが、森林資源、鉱山資源、東部海域への影響力を持つアルカンシェルは孤月からの出兵によってその二年後に滅亡させられる事になる。私掠船戦術とゲリラ戦術を中心にしたアルカンシェルの抵抗は頑迷を極めたが、アルカンシェルの地が無ければ孤月の「取り分」はクオスやイトリエールに比べて格段に少なくなってしまう訳であるから、彼等の侵攻もまた真摯で強力なものであった。前述のトラッドノア帝国が滅びるまでという三国間協定を理由にクオスとイトリエールからの援兵も送られ、海上では粘性の燃料による火炎投擲器、森林では魂血の方陣で利用されたものを転用したといわれる酸化性ガスによる敵兵の燻り出しが行われ、「邪悪の残党」に対する苛烈で容赦の無い攻撃の終幕は、新アルカンシェル政権首脳部を中心にリン=シア等旧首脳部を含む政府高官三百余人を戦争犯罪人として大量処刑した事でようやく終結したのである。また、更にこの翌年には国家としてのバスキアが正式に解体され、戦乱期当時の三大首脳であったノイマン、ハンコック、ウォズニの追放を条件にバスキア政府は形式的な存続のみを許され、同地は孤月の植民市となった。
孤月は産業的価値の薄いバスキアをその民族文化を残す為の地として位置づけ、残された少数の人民によって古いバスキア流の生活様式が営まれる事になった。結果的にはこれが功を奏し、ネオバスキアに流出していた一部のバスキア人の帰還と外からの血統の流入によって、バスキアはトラッドノアと運命を共有せずに済んだのである。そして旧トラッドノア帝国勢力が地表から一掃されたこの年が正式に新大陸暦1年と改められ、三国鼎立と協力による暫くの平穏な時代が約束されたのであった。その時は誰もがそう思っていた。
そして神聖王国軍情報部大佐ウイリアム・ルスカの人生は新大陸暦8年、帝都エストリルの陥落から10年後、民衆の内にある戦乱の記憶が平安の現実にとって変わられつつあるその年に終焉を迎える事になる。ウイリアム・ルスカの歴史に残されている公的な発言は、10年前の「人間の力は人間たちの力には遠く及ばない」というものが最後である。
帝都エストリルの陥落後、ウイリアム・ルスカの存在を嫌ったクオス首脳部は辺境警備の司令官として彼を軍中枢部より排斥してしまい、かつての部下との接触を断たせ、更に2年後のアルカンシェル討伐戦では彼を戦陣に参加させなかったにも関わらず、そこで使用された火炎投擲器や酸化性ガスを人道に外れる兵器の使用としてその開発者という名目によって処断してしまった。彼は更にクオス辺境の山岳地に左遷され、数年間軟禁状態にあったが新大陸暦8年に山賊の襲撃に遭い不遇の死を遂げている。この当時クオス本国周辺の山賊や海賊が政府や商人と結託していたのは幾つかの史書に語られている通りであり、ウイリアム・ルスカの39年に及ぶ波乱の生涯は彼を重用した味方の手によって実にあっけない形で幕を閉じたのである。
「軍神も自分の最期を支配する事は出来なかったようだ(ロバート・マホーニー)」
もっともこれには異説も存在する。戦乱期よりウイリアム・ルスカが暗殺者から身を護る為に影武者を使用していた事は知られていたが、ルスカの処断はこの影武者を利用して行われた、クオス首脳部が画策した狂言であるとする説である。バーナード・スチュアート著の娯楽小説「神書」では、トラッドノア帝国のバルギルボル将軍の暴走とその後の鎮圧、ウイリアム・ルスカの台頭とその粛正、それによって築かれた以降の神権国家クオスの体制が全て女王ニーナの策謀による壮大な歴史劇として描かれ、それを影で支える悪役としてバルギルボルとルスカの両名が活躍している。これは史実を元にした創作の色彩の濃い作品ではあるが、一面に真実を潜めているのではないかとされる歴史家の視点が存在する事もまた事実である。
一連の戦乱期において、トラッドノア帝国バルギルボル将軍の暴走に到った経緯と、その後の侵攻が南部戦線に限定されクオス方面への出兵が殆ど行われなかった事実は今でも歴史家の考察の種となっている。軍事力を妄信した結果が暴走に到る例は有り得ない訳ではないが、その後もクオス本国は常に平安にあった事、にも関わらず戦乱終結後に最も大きな果実を手に入れた勢力がクオスである事が疑念を誘う要素となる事はやむを得ない。現在ではそれがトラッドノア内部の王家や旧貴族がクオスと結託した結果であるという説や、女王ニーナがその後の援助を約束して起こした策謀であるとする説が有力視されている。これにウイリアム・ルスカに与えられていた謀略家としてのイメージが重なる時、ルスカが裏から糸を引いてクオスに強権を握らせたとする説にまで到る事になるが、いずれにせよ現状では推測の域を出てはいない。
ウイアリアム・ルスカは39歳で世を去り、彼に肯定的な歴史家からは汎国家的な協力体制の礎を、彼に否定的な歴史家からは大陸分割による大規模な戦乱の可能性を築いたまま後の展開を見届ける事なく、その死とクオス国内の体制の確定は後の歴史の流れを決定付ける要因となったのである。
やがて大女王を神格とするようになった神聖クオスが富裕商人の系列である貴族制に国内制度を移行し、民族主義が横行する自体になった事を死後の世界からウイリアム・ルスカはどのような思いで眺めたのであろうか。新大陸暦40年代後半から起こったバスキア民族への弾圧と47年のバスキア政府解散、51年のネオバスキアの虐殺、52年の第一次孤月クオス戦争、55年の第二次、61年の第三次戦争を経て再び大陸に長い混乱期が訪れ、新大陸暦90年にはイトリエールの大火災、100年には最盛期を迎えていたクオス帝都での100年祭が行われたが、その後衰退への道を辿った神聖クオスが崩壊し、流浪の民となっていたバスキア民族とネオバスキア商人が中心となって確立した通産連合体が新しい秩序を構築したのが新大陸暦199年の事であった。
「クオスは200年、バスキアは50年で滅びる」
かつての神聖王国軍情報部大佐ウイリアム・ルスカ大佐の予言はこうして実証される事になったのである。そして彼が保護したバスキアの民と彼が産み落としたネオバスキアの民とが新秩序の旗手となり、世は神と英雄の支配する封建的な時代から、人間たちの統治する開放的な時代へと徐々に移り変わって行くのである。
>他の資料を見る

 ウイリアム・ルスカ
ウイリアム・ルスカ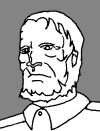 アレクサンデル・バルギルボル
アレクサンデル・バルギルボル バーネル・ガルフ
バーネル・ガルフ クオス女王ニーナ(大女王)
クオス女王ニーナ(大女王) 「魔導師」ヴィーア(本名不明)
「魔導師」ヴィーア(本名不明)