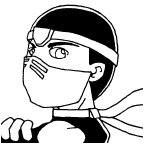4月〜入学式〜
東京コーヤクランドの別名で知られる東京湾埋立地にある、御台場の地に新設された私立バスキア学園高等学校。かつて東京都市博が某知事によって中止となったときに、残された膨大な開発予定地域の一部を第三セクターごと買い上げた、その地に作り上げた学校法人です。千葉県我孫子市の手賀沼周辺にあるいち企業から寄せられるという潤沢な資金によって、最先端の設備と優秀な講師陣が揃っていると言われていました。
そこでは絶対実力主義を不必要なほど前面に打ち出す、謎の校長ミスター・ホワイトが掲げる教育方針「強くあれ」のもと、生徒自らが他者に誇れる能力、分野に対する向上心を育てるべく厳しい教育が行われています。そして今年も、その学園に日本中あるいは世界中から新入生が訪れていました。例えば、遠く伊賀の里からでも。
 山をとび谷をこえて、埋立地の河口沿いの道を僕らの学園にやってくるべく走る一人の少女。使い込んだスポーツバッグを担いだ、どことなく猫めいた印象を与える少女は名前を葵若葉(あおい・わかば)といいました。音をたてずに疾駆する、その姿と彼女の生まれを思えば、猫というよりもまるで忍者のようだと評したくなるかもしれません。そして、彼女は忍者なのです。
山をとび谷をこえて、埋立地の河口沿いの道を僕らの学園にやってくるべく走る一人の少女。使い込んだスポーツバッグを担いだ、どことなく猫めいた印象を与える少女は名前を葵若葉(あおい・わかば)といいました。音をたてずに疾駆する、その姿と彼女の生まれを思えば、猫というよりもまるで忍者のようだと評したくなるかもしれません。そして、彼女は忍者なのです。
路上をすべるように走る、若葉の足が突然、止まります。初の登校日、視界の先に見えてきた一見、ふつうの校舎にした見えない私立バスキア学園高等学校。今は通学時刻となって開かれている、その正門の「上」に立つ一人の男を目に止めると、若葉は思わず声をあげました。
「半蔵兄さま?半蔵兄さまではありませんか!」
門の上に立ったままその声に振り向いた、鎖かたびらに黒ずくめの頭巾をかぶっている怪しさ爆発の男は、意外に若々しい声をあげると若葉を見おろします。
「何と、お主もこの学園に入学していたのでござるか」
少年の名前は服足半蔵(はったり・はんぞう)。若葉と同年同郷の、やはり伊賀の里に生まれ育った忍の者でした。里では落ちこぼれで通っていた若葉とは違って、将来を嘱望された優秀な若手忍者でしたが、その分だけ若葉よりもより胡散臭さが抜けなかったかもしれません。もっとも、完全実力主義のサバイバル修学制度を売りにしている私立バスキア学園では、重要なのは能力であって生まれも出自も、忍者かどうかでさえも些細な問題でしかないのです。
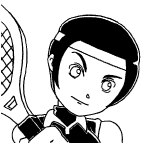 新しい時代の流れに対応できる、新進気鋭の実力を持つ生徒を育てること。それは授業のひとつを取ってもそうであり、限られた枠に定められた単位を修得するためには学生同士が戦って勝たなければなりません。校内規則で定められた範囲の厳格な決闘による勝敗、それによって授業の参加権から購買部の焼きそばパンの所有権、ひいては学内での成績までもが決められていきます。例えば理科の授業をひとつとっても、受講可能な椅子を奪い合う必要がありました。
新しい時代の流れに対応できる、新進気鋭の実力を持つ生徒を育てること。それは授業のひとつを取ってもそうであり、限られた枠に定められた単位を修得するためには学生同士が戦って勝たなければなりません。校内規則で定められた範囲の厳格な決闘による勝敗、それによって授業の参加権から購買部の焼きそばパンの所有権、ひいては学内での成績までもが決められていきます。例えば理科の授業をひとつとっても、受講可能な椅子を奪い合う必要がありました。
「悪いけど、理科の枠はもう最後なんだ。キミに譲ったらボクの受ける授業が無くなっちゃうよ」
そんな理由で勝負は起こります。葵若葉がはじめて、この学園での勝負を受ける相手となったのは藤原マヤ(ふじわら・−)。人外魔境の埼玉県出身、テニス部期待の新入生の少女でした。伊賀の里では落ちこぼれを自覚していた若葉ですが、果たしてテニス部員が忍者に勝てるとでもいうつもりでしょうか。マヤは愛用の重いテニスラケットを手に、ボールを握るとロブ落としで先制攻撃。ですがテニスはやはりテニス、若葉もこんなものでやられる訳にはいきません。すかさず離れて
「食らえ!ダイナマイトサァーブ!」
時速200kmを超えるというマヤの必殺弾丸サーブが襲いかかり、若葉の顔面を直撃すると見事にしとめることに成功します。これがサバイバル修学制度の過酷さですが、勝負というものは過酷なものなのです。
 「あのー、すみません。私も参加させて頂いてよろしいですか?」
「あのー、すみません。私も参加させて頂いてよろしいですか?」
そう言って立っていたのは佐藤愛(さとう・あい)。黒髪黒目、一見したところ優しげで可愛らしい少女ですが、肩にとまっている漆黒のカラスや、とぐろを巻いたヘビを見るにどうにも尋常な少女というには無理がありました。
マヤの返事を待たず、愛の肩からカラスのジョンが飛び上がると空中を二度ほど旋回してから、明らかに殺気を帯びつつひといきに急降下してきます。マヤもすからずサービス、空飛ぶカラスに当てるのは至難の技ですがなんとか追い払います。ですが安心したのもつかの間、今度は毒蛇リリーがするするとマヤの足下に寄ってくるとかぷりとひと咬みで轟沈させました。こうして、理科の授業枠は佐藤愛に渡されることになります。それは莫迦莫迦しいほど過酷な戦いの後に得るちっぽけな単位かもしれません。
「だが、過酷だからこそ芽生えるものがある。それは強さだけでなく強さを支える友情がそうだ(謎の校長ミスター・ホワイト)」
「マヤ、大丈夫?」
どの程度の時間が経ったのでしょうか。毒蛇リリーのひと咬みで轟沈していたマヤに、一人の少女が心配げに近づくと声をかけました。物腰が大人びたやや長身の少女は、茨城県は高萩からやはりこの酔狂な学園に進学している桐生美和(きりゅう・みわ)です。躾の厳しい、名家の一人娘である彼女がこのような場所に通っているのは騙され・・・国際化や情報化といった新しい時代を担うためというこの学園の方針に感銘を受けた故かもしれませんでした。聞き覚えのある声に首を振って、マヤは起きあがると友人の顔を認めて嬉しそうに叫びます。
「桐生先輩!」
「・・・あのね、その呼び方はやめてって言ってるでしょ」
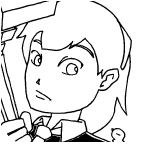 彼女もマヤや若葉と同じく、バスキア学園に今年入学したばかりの新入生です。先輩というのは不幸なほどに常識人かつしっかり者で面倒見のよい、彼女のニックネームでした。それじゃあ私も次の授業があるからと手を振ってその場を立ち去る桐生先輩でしたが、常識人を自負したい彼女にしたところで、この学園のしきたりから無縁でいる訳にはいきません。背後から殺気を感じ、振り向きざまに抜き放った竹の定規を後ろにはらうと、尖端をするどくとがらせた「投げ生け花」が廊下に落ちました。
彼女もマヤや若葉と同じく、バスキア学園に今年入学したばかりの新入生です。先輩というのは不幸なほどに常識人かつしっかり者で面倒見のよい、彼女のニックネームでした。それじゃあ私も次の授業があるからと手を振ってその場を立ち去る桐生先輩でしたが、常識人を自負したい彼女にしたところで、この学園のしきたりから無縁でいる訳にはいきません。背後から殺気を感じ、振り向きざまに抜き放った竹の定規を後ろにはらうと、尖端をするどくとがらせた「投げ生け花」が廊下に落ちました。
「あら、流石ですわ」
穏やかな顔で、動じる風もなく笑みを浮かべているのは広野紫苑(ひろの・しおん)。ごく自然に着物を着こなしたおとなしやかな和服美人ですが、その手には必要以上に鋭く切られた、品の良い色をしたチューリップの茎が握られていました。新入生にして既に生徒会執行部に所属している俊英で、花を扱う手慣れた仕草にもただ者ではない雰囲気が感じられます。
その投げ生け花の正確な軌跡は今も見せてもらったばかりであり、美和としては手に握った1メートル物差しの間合いまで立ち入りたいところでしょう。彼女にしたところで、幼い頃から嗜んでいる剣道の腕前にはちょっとした自信がありましたから。すかさず接近、静かなすり足から流れるような動作で竹の物差しを振り上げます。
とす。
近づいたところに今度は思いきり花を突き立てられる美和。めげずに手首のスナップを効かせて本手打ち、ですが紫苑も穏やかな動きですっと避けると、美和の目の前に鋭い花の切っ先を突きつけて一言。
「花言葉は、思いやり」
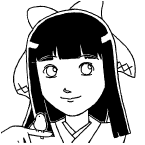 勝利を確信して、軽く髪をかきあげる紫苑。ですが突然、ひゅんと飛んできた鋭い苦無がその手元を通りすぎると、花びらが華麗に舞いました。苦無、クナイとは忍者がクサビなどの用に使う手裏剣に似た道具のことで、こんなものを扱う者は個性的な私立バスキア学園新入生の中でも二人しかいません。
勝利を確信して、軽く髪をかきあげる紫苑。ですが突然、ひゅんと飛んできた鋭い苦無がその手元を通りすぎると、花びらが華麗に舞いました。苦無、クナイとは忍者がクサビなどの用に使う手裏剣に似た道具のことで、こんなものを扱う者は個性的な私立バスキア学園新入生の中でも二人しかいません。
「二人もいれば、たいしたものですね」
不満げにつぶやく、紫苑の前に勝ち誇ったように現れたのは若葉でした。そのまま勝負とするには、不覚にも紫苑は抜き放つ花を丁度使い果たしてしまっていたのです。
「仕方ありません、この場は負けを認めます」
「よっし。これぞ忍法、インターセプトの術!」
「ううむ、若葉も頑張っているようでござるな。拙者もうかうかしてはおれんでござるよ」
時代は国際化、情報化社会に向かっているとは私立バスキア学園謎の校長、ミスター・ホワイトが言うとおりだ。ならば身ひとつで敵陣に忍び込み、重要機密を持ち帰る隠密こそが時代に求められるうってつけの人材ではあるまいか。伊賀の里にある忍者の村で生まれ育った半蔵は、この一見とっぴな学園こそが自分を鍛えるにふさわしい場所であると信じていました。数百年も時代の影に潜んできた、忍びの存在が遂に世に認められるときがくるのです。そして里では若き期待の忍者であった半蔵としては、はっきりと言えば落ちこぼれくのいちであった若葉がどうやら活躍しているらしいということは、忍者の力が認められるようで嬉しくもある反面で負けてはいられないという複雑な気分も抱いていました。
ですが、この学園が一筋縄ではいかないであろうことは彼の野生の本能が告げています。その日も、国際化というなら英語は必要でござろうとばかりに、教室の扉の前に立とうとしていた半蔵の背に甘い声がかけられました。
「フッ・・・そこをどいてくれませんか、美しいボク。美しいボクのために」
振り向いたそこに立っていたのは、薔薇小路綺羅(ばらこうじ・きら)。欧州出身、金髪に白い肌の優男で、世界で一番自分のことを美しいと思っているビジュアル系ポエマーです。
(こやつ・・・できる)
半蔵の野生の勘はそう告げていました。相手はただ者ではない、先手必勝とばかりに半蔵は素早い動きで駆け出すと綺羅のまわりをぐるぐるとまわり始めました。あまりの速さに残った残像が分身を生みだし、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十と次々に増える残像から手裏剣が投げられると綺羅に襲いかかります。これぞ半蔵必殺の石川賢流秘伝の一、服足ビジョンでした。
「しかもただの手裏剣ではござらん、しびれ薬を塗った毒手裏剣(!)でござる」
端正な顔、どころか全身たちまちズタボロになる綺羅ですが、それでも倒れる様子はありません。効いていないのではなく、効いているのに倒れないのです。信じられないほど恐るべき頑丈さでした。予想外に敵が元気なことに思わず動揺する半蔵に、綺羅は流麗な手つきで懐から鏡を取り出すと自分の姿を映しました。
「ああ!この手裏剣がささって血をどくどくと流しているボクですら美しい」
思わず鏡に見ほれてしまう綺羅。この性格が彼の頑丈さの一因なのかもしれません。怯んでいる半蔵に向かうと綺羅はいつも肌身はなさず手にしているゲーテの詩集を取り出し、セクシーボイスで朗読を始めました。
 心よ、わが心よ、どうしたというのか。
心よ、わが心よ、どうしたというのか。
何がお前をそのように圧しつけるのか。
なんという異様の新しいいのち。
今までのお前の面影はもはや見るよしもない。
お前の愛していたものはみな消え失せた。
お前を悲しましていたものも消え失せた。
お前の努力も、お前の安らけさも−−−
ああ、いかなればとて、かく変わり果てたのか。
お前を限りない力でつなぎ留めるのは、
あの若々しい花の姿か、
あのいとおしい人の姿か、
真心とやさしい心に満ちたあのまなざしか。
ひと思いにあの人から離れ、
逃げ去ろうと心を励ましても、
たちまちに私の足は
ああ、あの人の方へともどって行く。
断つによしない
この魔法の細糸で、
愛くるしい快活な娘は
私を否応なしに縛ってしまう。
娘の魔法の環にとらえられ
私のいのちは娘の思いのままだ。
変わりようの、ああ、なんという大きさ!
恋よ、恋よ!私を解放してくれ!
そして半蔵は倒れました。
 私立バスキア学園の誇るサバイバル修学制度がどれほど荒唐無稽なものであったとしても、慣れというのは怖ろしいもので、一週間二週間もすれば人はそんな奇態な生活にもごく自然に慣れてしまうものでした。しかも、それが順応性に優れる学生ともなればなおさらのことであったでしょう。
私立バスキア学園の誇るサバイバル修学制度がどれほど荒唐無稽なものであったとしても、慣れというのは怖ろしいもので、一週間二週間もすれば人はそんな奇態な生活にもごく自然に慣れてしまうものでした。しかも、それが順応性に優れる学生ともなればなおさらのことであったでしょう。
ナンジャ・スルーン・ディスーカは印度の山奥からやってきた、金髪褐色のインド人ハーフの少女です。彼女もまた今年度の新入生の筈でしたが、未だに単位のひとつも取得してはいませんでした。それは弱肉強食の世界では生まれてこざるを得ない、弱き者だったというのでしょうか。
「カレーは嫌いなのだ」
小柄な身体のどこに入るのだろうかという見事な食欲で、ナンジャは学生食堂の親子丼をぱくぱくと食べています。学園ではカバディ戦術同好会に所属、カバディを普及させるためにやってきたと称するナンジャに肝心な問題があるとすれば、彼女はバスキア学園のサバイバル修学制度のことをまるで理解していなかったことであったでしょう。何しろ入学してこの方、新しい学園生活を満喫することに専念していたナンジャは授業なるものが存在することも知らなかったのですから。
「アレは・・・なんなのだー?」
そんなナンジャも時折、決まっているかのような時刻になると他の生徒たちが一様に姿を消すことを不思議に思うようになっています。もちろんそれは授業を受けているか、あるいは授業を受ける枠を手に入れるために勝負を行っているかだったのでしょう。ナンジャの視線の先には、桐生美和と薔薇小路綺羅が言い争いをしていました。
「わかります・・・怖いのでしょう、このボクが。ボクの美しさと争うなんて実に怖ろしいこと。ボク自身ですら怖ろしくなるというのに、ボクと戦う誰もが怖れずにはいられない」
この時点で美和はすでにかなりの精神的ダメージを受けていましたが、時間が合ったからと芸術の単位を選んでしまったのは彼女自身です。ですが、美と称されるものであれば美術であれ美化委員であれ好まずにはいられない綺羅がそれを見逃す筈がありません。美しいもののために綺羅はためらいもなく美和に近づくと、甘く優しいセクシーボイスを耳もとでそっと囁こうとしました。アンデンティティの危機を本能的に感じた美和は思わず飛びすさり、よく手になじんでいる1メートル物差しを抜き放つと容赦なく必殺の本手打ちを叩き込みます。さしもの頑丈な綺羅も、人格を賭けた美和の一撃で美しく倒れると、凄惨なほどに美しく叩きのめされました。
そんなやりとりの一部始終を見て、何やら楽しそうだと思ったのはナンジャです。そしてどうやら勝負をして勝てば何か良いことがあるらしい、というところまでは能天気な彼女にも理解できたようでした。興味本位で歩いてくる同級生に、美和は辛うじて落ち着きを取り戻したような顔で話しかけます。少なくとも、綺羅の相手をするよりは随分ましだろうと彼女は思っていました。
「あなたも新入生?」
「名前はナンジャ。遠くインドの山奥からレインボーマンに会いにキタのだ」
「レンボー・・・?」
どうにも話が通じませんが、国際的な交流では言葉も文化も違う者同士の壁を乗り越えなければなりませんし、何より勝負は勝負です。連戦がきつくないかといえば正直嘘になりますが、学生にとってはそれが試練であり鍛錬でもありました。自分に言い聞かせるように何度か首を振り、すらりと高い背を伸ばして美和が物差しを構えると、ナンジャはおもむろに両腕を広げて不可思議な動きで左右に立ちふさがるように動き始めます。
「カバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディ・・・」
とにかく怒涛のようなカバディ。カバディとは簡単にいえば、狭いコートの中で相手にタッチして戻るという競技ですが、コートにいる間は息つぎをせずにひたすらカバディと言い続けなければなりません。対する守備側はチームプレイを駆使して逃げようとする相手を捕まえるなど独特な戦術が必要になりますが、聞き慣れない奇異な言葉を連呼するナンジャの姿はカバディを知らない美和には脅威以外の何ものでもなかったでしょう。
それでもこんな学園生活に慣れていた分か、振りかざした無礼打ちを動き回るナンジャの額に思いきり当てて、美和は印度娘を撃退します。安堵した瞬間、疾風のようなすばやさで若葉が駆けあらわれると、美和の目の前でぱあんと手を叩きました。古典的な猫だまし、怯んだところに必殺の苦無乱れ打ち。
「芸術の単位はいただくでござるよ、ニンニン」
そう言って樹間?に消えていく若葉。とにかくひとつところに留まってはいられない性格なのかもしれませんが、ひたすら走り回り急襲して去っていく、落ちこぼれなりに頭でも技でもなく足を使いまくる若葉のそれも、やはり戦いであるには違いないのです。サバンナでレイヨウが肉食獣のライオンから逃げ回る、その足も立派な戦いの武器でした。
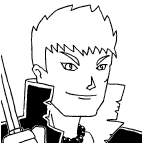 バスキア学園の校訓は「強くあれ」。空手部に所属している龍波吹雪(たつなみ・ふぶき)は強さだったら立派な自信がある好青年でした。ちょっと軽くて女性好き、なところは本人も認めるにやぶさかではありませんが、好きな空手に関してだけは努力と鍛錬を欠かしたことはないのです。あえて聞かれれば、強さを目指す国際的な学園で強い自分にあこがれるような娘がいても不思議はないだろうという、不純な考えだって皆無な訳ではありませんが。
バスキア学園の校訓は「強くあれ」。空手部に所属している龍波吹雪(たつなみ・ふぶき)は強さだったら立派な自信がある好青年でした。ちょっと軽くて女性好き、なところは本人も認めるにやぶさかではありませんが、好きな空手に関してだけは努力と鍛錬を欠かしたことはないのです。あえて聞かれれば、強さを目指す国際的な学園で強い自分にあこがれるような娘がいても不思議はないだろうという、不純な考えだって皆無な訳ではありませんが。
学園での新生活も三週間ほどが過ぎて、それはその日の数学の授業前のこと。吹雪が見かけたのは黒髪で可愛らしげな少女の後ろ姿でした。確か隣のクラスの、なんとかいう女の子だったか。吹雪が声をかけた動機は不純な好奇心からでしたが、この学園では何が純粋で何が不純であるかは実に危ういものなのです。ねぇ君、たしか・・・と吹雪が少女の後ろに立ったとき、
しゃー。
不幸な吹雪は自分がなぜ毒蛇のリリーに咬まれなければいけないのか、まるで理解できませんでした。ちょっと不純な熱血空手少年といえども毒蛇にはかないません。ぱたりと倒れたところにカラスのジョンが急降下をして襲いかかる、その姿はまるでヒッチコックの映画のようでした。
「あらあら、ジョンもリリーも大人しくしないとだめよ」
何ごともなかったかのように、彼女のペットをたしなめる愛。この少女も確かにただものではないのかもしれません。ですが、毒蛇リリーとカラスのジョンが吹雪をかぷかぷぐさぐさとついばんでいる、今こそが彼女の無防備な瞬間でした。
「白土三平流秘伝の一、稲妻落とし!」
がっしと背後から羽交い締めに捕らえると、数学の教室前である筈の風景が一瞬のうちに風吹きすさび枯れ木が立ち並ぶ荒野に変わり、半蔵は高く飛び上がると必殺の脳天逆落とし。
「勝負に情けは無用でござる・・・」
勝者の哀愁にひたる半蔵。そこに黒くて重いラケットがフルスイングされると、半蔵は黒装束ごと豪快に宙に打ち上げられて切りもみ状に回転しながら、自然な放物線を描いて地面という名の現実に落ちました。
コーチから習った自慢のロビングを決めると、マヤは拳をぐっと握って勝ちポーズを決めてみせます。
「なるほど、勝負に情けは無用だね」
それからどれほどの時間が経ったのか、遠くから体育の授業が始まる号令を聞いて、不幸な吹雪はめげずに立ち上がろうとしました。彼はちょっと女の子が好きな程度の基本的には熱血空手少年ですが、リリーの毒は毒蛇の毒というだけあってけっこう強力なのです。ダメージを押してよろよろと立ち上がる吹雪ですが、ひゅるると飛んできた生け花がぷすりと後頭部に突き刺さるとそのままどうと倒れました。紫苑の投げ生けは正確に獲物をしとめましたが、同時に彼女は、すでに背後に立つ殺気にも気がついています。
「見ていらしたんですか?」
「悪いが、この時間は俺様が頂くことにするよ」
北海道出身の自称テキサスカウボーイ、藤野牧男(ふじお・まきの)でした。ポンチョを着た謎のカウボーイスタイルの少年、ですが得意は乗馬でも牛追いでもなく競馬です。カウボーイは指先に挟んだマークシートのカードをくるりと返すと、手首のスナップで弾き飛ばし、鋭いマークシートマシンガンの切っ先が紫苑に襲いかかりました。だが、それは競馬ではありません。
紫苑も得意の投げ生けでマークシート用紙を叩き落としますが、カウボーイはすかさず近づくと容赦なく握り込んでいたダート(砂)を投げつけて目つぶし。ですが重ねて言いますがそれは競馬ではありません。
「俺様は未成年だから馬券は買えないのさ」
それはその通りでした。
私立バスキア学園名物、サバイバル修学制度。望むと望まないとに関わらずそれに慣らされてしまう生徒たちですが、その真の厳しさは常に戦いが続くという、過酷な連戦の厳しさにあります。世の中、自分の思うときにだけ苦労が訪れる訳ではないとは謎の校長ミスター・ホワイトの言でした。例えばリリーの毒牙に倒れた吹雪にしたところで、すぐに復活しなければそのままあらゆる単位を落としてしまうのですから。
ですが、同時にそれは負けた者もそれで終わりではなく雪辱を挑む機会が訪れるということでもあります。まさしく世の中は継続の積み重ねであり、ただ一度の敗北が全てを決することになるなど存外実社会では少ないものでした。大切なことは常に続けることであり、大変なのも常に続けることなのです。
「せっかくの機会ですもの、負けたままではいられませんわ」
「可愛いバンビーナの頼みとあっては断れないな、だが勝負は別だ」
 斜に構えてゆっくりと指を振りながら答えるカウボーイ、それは木曜日の体育の翌日、国語の授業でのことでした。週末を前にしてこれまで続いていた厳しい戦いに、疲労の色が隠せない両者でしたが勝負から逃げる訳にはいきません。そこに賭けられているのは単なる授業の単位ではなく、名誉であり熱い鼓動なのですから。
斜に構えてゆっくりと指を振りながら答えるカウボーイ、それは木曜日の体育の翌日、国語の授業でのことでした。週末を前にしてこれまで続いていた厳しい戦いに、疲労の色が隠せない両者でしたが勝負から逃げる訳にはいきません。そこに賭けられているのは単なる授業の単位ではなく、名誉であり熱い鼓動なのですから。
「勝負の方法はどうなさいますか?」
「お互いに背を向けて一歩、二歩、三歩・・・そうだな、十歩だ」
乾いた風に吹かれて根無し草が転がる、学園の長い廊下で両者は向かい合うと背中向きに立ちます。おそらく、勝負は一瞬で決まるでしょう。足音を響かせながら、一歩、二歩、三歩と歩き出す紫苑とカウボーイ。それが十歩を数えた瞬間、カウボーイの手首がひるがえって、マークシートの切っ先が弧を描いて紫苑に襲いかかります。ですが、紫苑は手にした生け花を投げるでもなく二十歩の間合いをひととびに駆け寄ると、マークシートの軌跡をかわして鋭い献花の切っ先を牧男の額に突き立てました。一陣の風が過ぎ去り、カウボーイはその場にどうとくずおれます。
「見事だぜ、バンビーナ・・・」
「半蔵兄さま」
「おお、若葉ではないか」
こうして、新入生たちの慌ただしい一ヶ月は過ぎていきました。落ちこぼれ忍者であった若葉もこの学園の水が合ったのか、新入生でも上位の成績を存分に発揮して楽しげ、な学園生活を送っているように見えます。半蔵としては知己の同郷人の活躍は嬉しいことでしたが、安穏として喜んでばかりではいられません。
「はっきり言おう、拙者は伊賀の里ではお主のことなど歯牙にもかけていなかった」
「兄さま?」
「だが今度は拙者がお主を目指さねばならぬようだ」
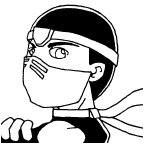
完全実力主義の世界であれば、実力のある相手は認めるべきです。半蔵は、強さは認めても偏見には無縁な少年でした。黒頭巾の結び目から流れる長い布地を風になびかせながら、近い未来を見据える目になると半蔵は誰にともなく呟きます。
「七月には、スパーリングカーニバルがあると申す。地道な鍛錬であるスパーリングをイベントで大々的に行うとは、流石日々の修練の励行を身上とする学園、今から楽しみだ」
その言葉が自分に向けられたものかどうか、若葉には分かりませんでしたが、その目は半蔵と同じ未来に向けられていました。
† つづく †
>私立バスキア学園の案内に戻る

 山をとび谷をこえて、埋立地の河口沿いの道を僕らの学園にやってくるべく走る一人の少女。使い込んだスポーツバッグを担いだ、どことなく猫めいた印象を与える少女は名前を葵若葉(あおい・わかば)といいました。音をたてずに疾駆する、その姿と彼女の生まれを思えば、猫というよりもまるで忍者のようだと評したくなるかもしれません。そして、彼女は忍者なのです。
山をとび谷をこえて、埋立地の河口沿いの道を僕らの学園にやってくるべく走る一人の少女。使い込んだスポーツバッグを担いだ、どことなく猫めいた印象を与える少女は名前を葵若葉(あおい・わかば)といいました。音をたてずに疾駆する、その姿と彼女の生まれを思えば、猫というよりもまるで忍者のようだと評したくなるかもしれません。そして、彼女は忍者なのです。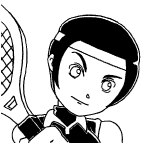 新しい時代の流れに対応できる、新進気鋭の実力を持つ生徒を育てること。それは授業のひとつを取ってもそうであり、限られた枠に定められた単位を修得するためには学生同士が戦って勝たなければなりません。校内規則で定められた範囲の厳格な決闘による勝敗、それによって授業の参加権から購買部の焼きそばパンの所有権、ひいては学内での成績までもが決められていきます。例えば理科の授業をひとつとっても、受講可能な椅子を奪い合う必要がありました。
新しい時代の流れに対応できる、新進気鋭の実力を持つ生徒を育てること。それは授業のひとつを取ってもそうであり、限られた枠に定められた単位を修得するためには学生同士が戦って勝たなければなりません。校内規則で定められた範囲の厳格な決闘による勝敗、それによって授業の参加権から購買部の焼きそばパンの所有権、ひいては学内での成績までもが決められていきます。例えば理科の授業をひとつとっても、受講可能な椅子を奪い合う必要がありました。 「あのー、すみません。私も参加させて頂いてよろしいですか?」
「あのー、すみません。私も参加させて頂いてよろしいですか?」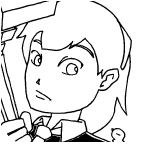 彼女もマヤや若葉と同じく、バスキア学園に今年入学したばかりの新入生です。先輩というのは不幸なほどに常識人かつしっかり者で面倒見のよい、彼女のニックネームでした。それじゃあ私も次の授業があるからと手を振ってその場を立ち去る桐生先輩でしたが、常識人を自負したい彼女にしたところで、この学園のしきたりから無縁でいる訳にはいきません。背後から殺気を感じ、振り向きざまに抜き放った竹の定規を後ろにはらうと、尖端をするどくとがらせた「投げ生け花」が廊下に落ちました。
彼女もマヤや若葉と同じく、バスキア学園に今年入学したばかりの新入生です。先輩というのは不幸なほどに常識人かつしっかり者で面倒見のよい、彼女のニックネームでした。それじゃあ私も次の授業があるからと手を振ってその場を立ち去る桐生先輩でしたが、常識人を自負したい彼女にしたところで、この学園のしきたりから無縁でいる訳にはいきません。背後から殺気を感じ、振り向きざまに抜き放った竹の定規を後ろにはらうと、尖端をするどくとがらせた「投げ生け花」が廊下に落ちました。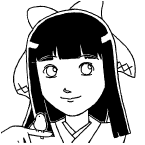 勝利を確信して、軽く髪をかきあげる紫苑。ですが突然、ひゅんと飛んできた鋭い苦無がその手元を通りすぎると、花びらが華麗に舞いました。苦無、クナイとは忍者がクサビなどの用に使う手裏剣に似た道具のことで、こんなものを扱う者は個性的な私立バスキア学園新入生の中でも二人しかいません。
勝利を確信して、軽く髪をかきあげる紫苑。ですが突然、ひゅんと飛んできた鋭い苦無がその手元を通りすぎると、花びらが華麗に舞いました。苦無、クナイとは忍者がクサビなどの用に使う手裏剣に似た道具のことで、こんなものを扱う者は個性的な私立バスキア学園新入生の中でも二人しかいません。 心よ、わが心よ、どうしたというのか。
心よ、わが心よ、どうしたというのか。 私立バスキア学園の誇るサバイバル修学制度がどれほど荒唐無稽なものであったとしても、慣れというのは怖ろしいもので、一週間二週間もすれば人はそんな奇態な生活にもごく自然に慣れてしまうものでした。しかも、それが順応性に優れる学生ともなればなおさらのことであったでしょう。
私立バスキア学園の誇るサバイバル修学制度がどれほど荒唐無稽なものであったとしても、慣れというのは怖ろしいもので、一週間二週間もすれば人はそんな奇態な生活にもごく自然に慣れてしまうものでした。しかも、それが順応性に優れる学生ともなればなおさらのことであったでしょう。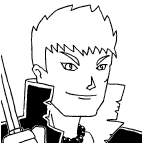 バスキア学園の校訓は「強くあれ」。空手部に所属している龍波吹雪(たつなみ・ふぶき)は強さだったら立派な自信がある好青年でした。ちょっと軽くて女性好き、なところは本人も認めるにやぶさかではありませんが、好きな空手に関してだけは努力と鍛錬を欠かしたことはないのです。あえて聞かれれば、強さを目指す国際的な学園で強い自分にあこがれるような娘がいても不思議はないだろうという、不純な考えだって皆無な訳ではありませんが。
バスキア学園の校訓は「強くあれ」。空手部に所属している龍波吹雪(たつなみ・ふぶき)は強さだったら立派な自信がある好青年でした。ちょっと軽くて女性好き、なところは本人も認めるにやぶさかではありませんが、好きな空手に関してだけは努力と鍛錬を欠かしたことはないのです。あえて聞かれれば、強さを目指す国際的な学園で強い自分にあこがれるような娘がいても不思議はないだろうという、不純な考えだって皆無な訳ではありませんが。 斜に構えてゆっくりと指を振りながら答えるカウボーイ、それは木曜日の体育の翌日、国語の授業でのことでした。週末を前にしてこれまで続いていた厳しい戦いに、疲労の色が隠せない両者でしたが勝負から逃げる訳にはいきません。そこに賭けられているのは単なる授業の単位ではなく、名誉であり熱い鼓動なのですから。
斜に構えてゆっくりと指を振りながら答えるカウボーイ、それは木曜日の体育の翌日、国語の授業でのことでした。週末を前にしてこれまで続いていた厳しい戦いに、疲労の色が隠せない両者でしたが勝負から逃げる訳にはいきません。そこに賭けられているのは単なる授業の単位ではなく、名誉であり熱い鼓動なのですから。