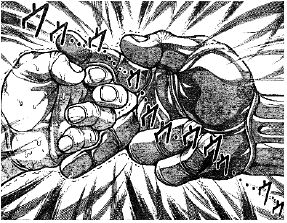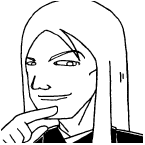2月〜決戦〜
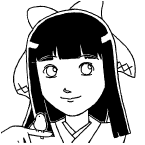 学生にとって年の終わりとは師走ではなく年度の終わり、冬の終わりと春の訪れのことを指しており、寒さの中に忍び込んできた穏やかさが芽吹きを感じさせる感覚はその時が近づいていたことを瑞々しい皮膚にも分かるように示しています。その感覚が地域や時期で微妙に異なるのは四季が存在するこの国で珍しいことではありませんが、広野紫苑(ひろの・しおん)が友人と二人で屈み込んでいた小さな草地はこの時期にも充分な緑色に覆われていて周囲は穏やかな空気に覆われていました。
学生にとって年の終わりとは師走ではなく年度の終わり、冬の終わりと春の訪れのことを指しており、寒さの中に忍び込んできた穏やかさが芽吹きを感じさせる感覚はその時が近づいていたことを瑞々しい皮膚にも分かるように示しています。その感覚が地域や時期で微妙に異なるのは四季が存在するこの国で珍しいことではありませんが、広野紫苑(ひろの・しおん)が友人と二人で屈み込んでいた小さな草地はこの時期にも充分な緑色に覆われていて周囲は穏やかな空気に覆われていました。
「えーと。これで、十三本目?」
「こちらに二本あるから十五本ですね」
頼まれて、という理由もありましたが四つ葉のクローバーを探してまわるのはなかなか大変で、こころよく手助けをしてくれる友人にありがたさを感じます。牧草に使われている草地を順番にめぐり、小さな集まりで使うための小さな飾りを用意する。土と緑に囲まれた作業は一度気に入ってしまえばなかなか楽しく、友人の存在がそれを補ってもくれましたが、土があればもちろん小さな虫や生き物もいましたから、紫苑の友人にすればまずそれに慣れるのが先ではあったようです。
「足が多い形態や足がない形態は環境に適応した訳ではなく最初からそうである生き物が住み着いている訳ですから彼らには本来の姿であって・・・」
ことさらにそう言っていたのは動揺をおさえるためだったのでしょう。四条此花(しじょう・このはな)はどちらかといえば土よりも数字の世界に生きている娘でしたから、最初は小さな虫の一匹にも人並みに騒いではいましたが、自分で四つ葉のひとつを見つけてからはむしろ紫苑よりも熱中しているように見えます。たまにはきゃあきゃあと言う姿を見てみたいと思うのは紫苑のいたずら心というものでしょう。
「終わったらホットチョコレートでも飲みましょうか」
「ハーブティーという手もありますよ」
そう言われればあちらの草地にはミントの葉が茂っていただろうか。案外、ハーブというものが街角に自生していることを知らない人は多いものです。アイドルワイルドのようにこの場にテーブルを置く訳にはいきませんが、草花の声を聞く生活というものは人が思うほどむずかしくはありません。
とはいえこのままでは私立バスキア学園高等学校がアヴォンリー年代記になってしまいますから、時代は強引にこの場所から十年以上も遡ってしまいます。それはまだ学園が建てられてもいなかった頃の話、かつて大規模な都市博覧会が企画されながら、博覧会どころかそれをきっかけとした土地開発まで放棄されていた東京コーヤクランドの広大な荒れ地にその男は一人立っていました。税金の浪費を戒めるとして、時のアオシマユキオーがほんの数百億円ほどの経済効果をふいにすると工事業者には知らぬ顔を決め込んでしまったのも今は昔です。
塩気を含んだ風が吹きすさびシーガ%アのように根無し草が転がる風景、立てられたままの柵や建設予定地とだけ記された看板、遺棄された重機をぐるりと見渡しながら、男はまるでマンダムのテレビコマーシャルを収録しているかのように指先であごをなでてみせます。これで「切レテナーイ」などと言えばまだこの時代には放映されていなかったでしょうから、やはりマンダムが無難でありふさわしくもあるでしょう。
そこまで考えて、男はセピア色の回想シーンが何ひとつ進んでいないことに気がつきます。誰もいない荒野で小さく苦笑した男は懐からマイルドセブンを一本取り出すと、口先にくわえたそれを風から守るように手で覆いながらチルチルミチルで火をつけました。寒さの中に忍び込んできた穏やかさが芽吹きを感じさせる筈の季節、ですがこの荒れ果てた大地には探すべきクローバーの一本もなく穏やかさは冷たく乾いた風に吹き飛ばされて根を下ろすことができません。
ともすれば頼りないライターの炎すら消してしまおうとする風に、負けてなるものかとガスのつまみを動かして火の勢いを強くします。さあどうしたいフリント。お前はまだまだ老いぼれちゃいない、飛べない訳はないんだ。まだまだ、お前は飛べるんだ。風に耐えて立つ炎を見やりながら、ひとりごちていた男の脳裏に天啓が閃きます。
「ここに巨大な学園を建てたらおもしろそうだ」
ささやかな問題があるとすれば彼がシルバーでもなんでもない単なるホワイトだったことでしょう。これが私立バスキア学園高等学校が誕生した瞬間でした。
その教育方針に堂々と「強くあれ」の言葉を掲げている私立バスキア学園高等学校ですが、それは別にモヒカンでバイクに乗って火炎放射器を手にヒャッハーというのではなく、分野を問わず他人に誇ることができるものを手に入れようという姿勢と向上心を指しています。
古代ギリシアにて貧しさは罪ではないが貧しさに安住することは罪であると言われたように、マリオブラザーズもやりこめばジャンプせずファイアボールをくぐり抜けることができるようになるのです。二番を目指すなどという妄言は所詮上等な料理にハチミツをブチまけるがごとき思想でしかありません。
その日、登校した学生たちはいつもと異ならないように見える風景にどこか違和感があるのを感じて、どことなく落ち着かない様子で一様に首をかしげていました。
学年度も終わりに近づいた二月半ばの一日、周囲には残された課題を片づけようとする忙しなさや、あるいはすでにやるべきことを終えた安堵感を伴う空虚さ、またはそれらの一切を放逐して現実から楽しく目を背けている陽気さに満たされていましたがおいおい最後のはまずいだろうと思いつつ、いずれにしても彼らが感じている違和感はそれらと異なるものです。
 「先輩、この塔なんなのだー?」
「先輩、この塔なんなのだー?」
「うーん。何かしらねえ」
呑気に指さしながら見上げているナンジャさん(なんじゃさん)に、桐生美和こと桐生先輩(きりゅうせんぱい)もムーミンママなみに動じた様子もなくあらあらどうしたのかしらといった風情で視線を上に向けています。
外見を見ると五階建てくらいでしょうか、地上十メートルをゆうに超える石造りの塔が校門をくぐった正面に建てられていてその入り口にはわざとらしい鋼鉄の扉が構えられており、脇には当然のように「ここより入る者すべての希望を捨てよ」の文字が書き殴られています。どうして一晩でこんなものが建てられるのだろうといえばそれは企業秘密でした。
「ぬう」
その言葉は塔を見上げながら首をかしげているナンジャや先輩のものではなく、尖塔の更に屋上、襟巻を風になびかせながら突端に立っている服足半蔵(はったり・はんぞう)のものです。両腕は二の腕を水平に肩の高さで組むことによって、胸板がたくましく見えることはメキシコでルチャドールがポーズを取る際には常識でした。
伊賀の里を出てまもなく一年、半蔵は感慨にふけっていました。それは毎年恒例となっているバレンタインなる舶来の行事で受け取ったチョコレートが原因ではありません。
里で暮らしていた当時から意外とイケメンで好人物の半蔵兄様はけっこう皆に慕われていましたがそれはそれとして、しかも同郷の娘からつい先程けっこう本気っぽいチョコレートまで受け取ってしまうと妹のように思っていた彼女も成長したものだと思っていましたがそれもそれとして、生真面目な半蔵はやっぱり生真面目に学園生活を振り返ってはいたのです。
「人も宝石も磨かれて輝くものでござる。だが・・・」
分野を問わず「強くあれ」を標榜する学園は確かに一芸に秀でた生徒が多く、私立樫宮学園高等学校なみに県大会や高校総体レベルの選手がごろごろしているとは世間の評判でした。生徒数が少ないこともあり、特に団体競技ができるだけの人数が集まらないことはネックとされていましたが、他校からスカウトが来て転校した生徒すらいる程であり少なくとも学園の教育方針が相応の成果を上げていることは疑いありません。
そして強さとは個性であって戦いや競技、あるいは勉学にすら限定されるものではなくつい先日も「北千住商店会世界一美男子コンテスト」に優勝した生徒が学内でもその活動と成果を表彰されており、ナンバーワンとオンリーワンの双方を容認する教育方針には半蔵も異論はありませんでした。
とはいえ半蔵自身は将来的には里のエリートたちと同様、立派な諜報機関に勤めて間諜や捜査官として活躍することを目標にしていましたし、日々気張りながら生きていくマッハな人生にも納得していましたが他の生徒たちはどうであるのか。あるいは平和に学園生活を送りたいだけで、朝から晩まで命を賭ける生活に理不尽さを抱いている生徒もいるのではないでしょうか。そうした疑問を彼が抱くようになったことも確かです。
自らは校長打倒を目指しながら、もしも勝利することが叶えばそうした平穏を望む生徒たちに対する選択肢を設けることを検討して欲しい、半蔵はそう考えています。問題はその校長を打倒することが難題であることだけでしょう。
「拙者のマッハがどこまで通用するか」
強くあれを標榜する学園を率いるだけのことはあり、校長は口だけではなく強くあることを自らにも課していました。半蔵が在校生や学園の卒業生から聞き出した話では勉強スポーツ趣味から遊びにいたるまで、過去にも幾人かが校長に挑んでは返り討ちにあったとされており未だ勝利した者は誰もいないとすら言われています。
走ればサンドマンに勝り、鉛筆を握れば轟一番に勝り、腕ずもうをすればシルベスタ・スタローンに勝り、連射をすれば高橋名人にも勝る。ミスター・ホワイトはただ偉ぶりながら騒動を欲しているだけの人物ではなく、にらめっこで幼児を笑わせるときですら本気で行うのが彼の流儀でした。
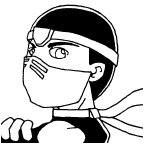
学生たちに試練を課して自らもそれを体現してみせる。先のハルミの事件でも結果だけを見れば機械仕掛けの友人は救われていましたし、であれば過程に口うるさく言わずとも良いではないかと強弁することはできるでしょう。もしも校長が手段のためには目的を選ばない人物でなかったならば、その理屈も説得力があるかもしれません。
彼自身の性格にふさわしく、ものすごく生真面目に考え込んでいる半蔵はひょっとしたら校長は単なるにぎやかしの愉快犯ではないかという疑念を抱かなくもありませんでしたが、まさか学園の長がそんなことはあるまいという常識が高い壁となって真実に至る門を閉ざしています。
「だってまがりなりにも拙者たちの校長じゃん!」
狂人は自分が狂人であることに気がつくことができませんが常識人は他人が狂人であることになかなか気がつくことができない。それがごく常識的な人間というものです。
時は一日ほど遡ります。私立バスキア学園高等学校地下六階にある廊下を、来るべき戦いにそなえてぷらぷらと歩いている学生の姿がありました。龍波吹雪(たつなみ・ふぶき)はやや唐突に自分を呼び止める声に足を止めるとゆっくりと振り向きます。人気のない通路に一人、どこか神妙な面持ちで立っていたのはあろうことか彼が打倒すべきミスター・ホワイトその人でした。
いずれ自分が倒すべき相手が何の用だろうかと、いぶかる吹雪に対していつもよりやけに体格がよくてアゴが長い校長は唐突に床に這いつくばると叫びます。
「わたしに勝たせてくれッッッ!」
いくら戦いの世界に長く身を置いてきた校長であっても、確実に忍び寄る老いの影響をぬぐい去ることはできず、若く体力にも生命力にもあふれる学生たちを相手に勝ち続けることは容易ではありません。ですがバスキア学園を率いる校長がここで負けてしまえば自分を目指している他の学生たちが目標を失ってしまうことになりかねない、だから勝ちを譲ってくれないかと言うのです。
老齢の自分に残されている時間はそう多くないし、八百長なんて大相模協会(だいさがみきょうかい)でもやっていることではないか。自分にはしょせん吹雪のような若くて強い戦士に勝てる実力はないし、君たちにはまだ幾らでも機会がある。土下座したまま最後には涙まで流してみせる校長の姿にさすがの吹雪も怯んでたじろぎますが、彼とても生まれながらの戦士でしたからはいそうですかと受けられる話ではありません。むしろ怒りを込めた若い叫びが狭い廊下の壁と天井に響きます。
「冗談じゃないッ!あんた自分が何を言っているか分かってるのかッ!」
「ひ、ひいい!」
ともすれば情に流されそうになる自らの心を厳しく戒めるように、あえて背を向けた吹雪ですがその表情は決して迷いを断ち切ったものではありません。無様に這いつくばったままでいる男の姿が、立ち去る吹雪の背後で少しずつ小さくなっていきました。
こうして幾つかの感情やわだかまりが拭えずにいる中で、校庭に屹立する塔という現実は霧消することがありません。やがて他の生徒たちも登校してくるとまっすぐ教室へと向かう者たちと足を止める者に少しずつ分かれていき、とうとう予鈴が鳴りましたがどうせ塔に向かっても出席扱いになるだろうことは誰もが心得ていました。
これがないと学園ものであることが分からなくなることを防ぐためとしか思えない、鐘の音が最後の余韻を消し去って周囲に静謐が訪れると、塔の入り口に据えられていた旧式のスピーカからざらざらとした声が流れ出します。それが私立バスキア学園校長、ミスター・ホワイトその人の言葉であることを学生たちはすぐに理解しました。
「それでは特別授業を始めよう。私に挑むつもりがある生徒たちはこの扉をくぐりたまえ」
「何を今更。俺様がいなければレースが始まらないさ」
愛馬エ%シンホワイティの鞍上で言い放つミスター・バスキアこと藤野牧男(ふじの・まっけんおー)の目の前で、鋼鉄の扉がきしむ音を立てながらゆっくりと左右に開きます。学生たちは互いに視線を交わし、うなずくと一人また一人と暗がりに足を踏み入れていきました。幸いここはゴットサイド最寄りの天空の塔ではありませんから、チンドン屋みたいな武器防具を身につけずとも追い返されることはありません。
塔の頂上に待っているであろうマスタードラゴンならぬマスターホワイトを討伐すべく石造りの塔に挑む、その校長はといえば呑気にスピーカから流れる声で彼の遊びを盛り上げるべくナレーションを続けていました。
「こうして無謀だが勇敢でもある生徒たちは邪悪な校長が待つ塔へ足を踏み入れてゆくのであった。ジャジャーン!一人また一人と若者たちの姿が暗闇へと消えていく・・・だが幾人かが入ったところで、門はそれ以上の戦士を拒むかのごとくゆっくりと閉まりだしたのだ」
「・・・やばいッ!」
とっさに駆け込んだ生徒たちの背後で、ものすごい勢いで扉が閉まるとバターン!という音を響かせます。ぜんぜんゆっくりじゃないだろうという常識的な文句に耳を貸す者がいる筈もなく、派手に落馬したミスター・バスキアは尻を突き出してうつ伏せに倒れていましたし、よそ見をして思いきりはねとばされたらしいナンジャさんは頭の上にぴよぴよとヒヨコを巡らせていました。
 再び静寂が訪れると周囲は暗いままで今のところは何かが現れたような様子もなく、危難に挑む友人たちの気配しかありません。この機を狙って襲いかかるといった類の卑劣さは校長の流儀ではなく、彼ならばもっと悪辣な方法で生徒たちを陥れようとするでしょう。それを知っている皆は校長の罠を感じて一瞬ごとに緊張を強くしていましたが、それが悪寒に変わったとき彼らは暗闇に潜む危険の存在を理解しました。
再び静寂が訪れると周囲は暗いままで今のところは何かが現れたような様子もなく、危難に挑む友人たちの気配しかありません。この機を狙って襲いかかるといった類の卑劣さは校長の流儀ではなく、彼ならばもっと悪辣な方法で生徒たちを陥れようとするでしょう。それを知っている皆は校長の罠を感じて一瞬ごとに緊張を強くしていましたが、それが悪寒に変わったとき彼らは暗闇に潜む危険の存在を理解しました。
「暗闇ッ!ボクが暗闇にまさぐられちゃう!」
どんなシチュエーションでもイクことができる薔薇小路綺羅(ばらこうじ・きら)はたぶん暗闇でひとり揉みしだいていましたが、早いところこれを何とかしないと暗闇が美力(びぢから)に満たされてしまうこと疑いありません。
ごつり、と何かかたいもので叩く音がすると、どさりとやわらかいものが床に倒れる音がして急速に生徒たちの悪寒が消えていきましたが暗いままなので何が起こったのかは分かりません。しばらくしてようやく明かりが灯ると皆がまぶしさに目を細めますが、広々とした部屋の中央には勇敢な一人の美戦士が倒れているだけでした。殺人事件勃発です。
「さあ、行きましょ」
もしかしたら闇の世界の殺し屋がどこかに潜んでいるのかもしれませんが、ちょっとだけ気になることといえば部屋の隅に転がっている鈍器に赤いものがべったりとついていたということと、事件現場から皆を立ち退かせている桐生先輩がいつもの竹刀袋を持たず手ぶらでいることくらいなので何の手がかりもありません。貴重な犠牲(死んでません)はとりあえず放っておいて皆は明かりに慣れてきた視線で部屋を見渡します。
塔の中は外見たよりもずっと広くできていて、少年漫画にありがちなサイズを無視したつくりとなっています。この中であればタルカスや大豪院邪鬼のような巨漢でさえも暴れ回ることができるでしょうし、それらを倒すごとに上の階に進むことになっている様子はどこぞのカンフー映画のようで、誰も黄色いジャージを着ていないことがいっそ惜しまれるほどでした。
「来るのか?」
最初の刺客。それを迎え撃つべく自らを鼓舞するかのように呟いたのは吹雪です。前日の校長の言葉が戦士の心の片隅で尾をひいており、それを断ち切るには熱く激しい戦いに勝るものはないでしょう。卑劣な校長を打倒して、強敵と書いてトモと読む友人新庄ジュンペイを救い出すこと。それが吹雪の目指すところであり友情のために努力をして勝利を得るなんてまるで少年漫画の主人公みたいじゃないかとちょっと自分に酔いながら奮い立っていました。
ここで活躍して迷いを振り払うと同時に、塔に足を踏み入れている女子生徒たちに戦士のかっこいい姿を見せてやろうという男の計算を働かせている吹雪の視線の先で、部屋の向かい側にある扉から学生服を着た見知らぬ人影が現れます。どこか既視感(デジャブby菊池桃子)を刺激されなくもない、ですが吹雪だけではなく誰の記憶にも見出すことができない姿に首をかしげながらも見知らぬ男に誰何の声が投げかけられました。
 「誰だ?お前」
「誰だ?お前」
「何言ってるんだ!?俺だよ、ジュンペイじゃないか!」
心から驚いたような様子を見せている、新庄ジュンペイ(しんじょう・ずんぺい)を名乗る男ですが吹雪が知っているジュンペイはもっと魚みたいな顔立ちをしていたりたまにはヤギだったりダチョウだったりしたことはありますがこんな普通の男子高校生みたいな姿はしていません。友人の名をかたる不埒な男に正義の怒りを感じた吹雪は、のび太を殴るジャイアンのようにまっすぐな拳を顔面にバコーとめりこませました。
問答無用で倒されたニセモノの身体がどさりと崩れ落ちると同時に、地下格納庫に収容されていた鋼鉄巨神奇怪王(きかいおー)の目がぴかりと輝き、唯一の主人を守るために床をせり上がって吹雪たちの前に鋼の身体を現します。かのWDF社が背後についている私立バスキア学園で、校長の手先がロボットを操ったとしても何の不思議もないでしょう。すかさず此花がまるで真田さんかジアニ・メージのように宣言します。
「こんなこともあろうかと、こちらも龍波くんを勇者風に改造しておきました」
「勇気が胸にある限り・・・俺は・・・負けないいっ!」


義理チョコひとつで男の説得をされた吹雪が力強く拳を握ります。身を賭してでも救い出そうと願う強敵(とも)のために怒る鋼のサイボーグは熱いまなざしに銀の腕を握り締めて、口ずさむテーマソングもすでに熱唱から絶唱へと変わりつつありました。眼鏡をきらりと光らせた此花が拳を勢いよく振り上げると、けっこうノリノリな様子でセキュリティカバーを叩き割ります。
「ファイナルフュージョン、承認!」
叫びとともにどこからともなく飛んできた三機のガオーマシンが吹雪と生機融合して勇者王ガオフブキーが地上に降り立ちます。まるで学園がストライク・バックの競技場になったかのように見える鋼鉄の勇者同士の一騎打ち。先手を打って奇怪王の胸のシンボルマークが灼熱色に輝くと、ヒートブレイザーの熱線波が解き放たれて真正面から襲いかかりました。鋼鉄のボディを赤外線ヒーターのように真っ赤に焼かれながら、背に守るべき者を従えているガオフブキーは一歩すら退く訳にはいきません。
「まだだ・・・まだ俺は、立ち上がれる!」
ずっと仁王立ちなので別に倒れてはいませんがその辺はワキゲノヒダリという奴でしょう。襲いかかるエネルギーを正面から受け止めながらやや演出過剰気味にゆっくり両腕を開き、右手には攻撃エネルギーを、左手には防御エネルギーを握り締めて二つを融合させた力ががっしりと握り締められました。
突きだした両の拳が目標をまっすぐに捕らえると、背中の推進機が炎を吹き出して一気に加速するヘル・アンド・ヘブンで突進します。搭乗者というか吹雪自身にも必要以上にダメージを与える特攻が一撃で奇怪王の装甲を突き破り、ファイナルブレイクの声とともに巨大なキノコ雲が巻き起こりました。
爆風が収まり、第一層を勇敢に攻略した学生たちは鋼鉄巨神の残骸を踏み越えて奧にある階段を上ります。意外に長い石段を上り終えた次の階、どこか古めかしい雰囲気を漂わせている第二層ははおよそ百年ほど昔の日本を思わせるモダンな情景の中にあり、行き過ぎる人力車や町の人々も和装と洋装が混在したハイカラな姿をしていました。唐突にタイムスリップをさせられたような感覚に浸っている中で、学生たちの意識を引き戻したのはやはり部屋の向こう側に傲然と現れた三つ編みお下げにセーラー服姿の巨躯を認めたからでしょう。
その名は綾小路静香(あやのこうじ・しずか)。古くは日露戦争時代に遡るといわれる旧家の出自であり、華道の家元であると同時に帝国海軍にも多くの士官を輩出した名門中の名門です。その帝国海軍の秘密兵器と呼ばれる彼女はムキムキピチピチの十七歳、大なたの一本で堅木を倒してみせる腕前は若くしてすでに綾小路流の免許皆伝を得ていました。
「いや、華道はそんなじゃないから」
日舞と剣道をたしなむ桐生先輩が裏手ではたくような素振りを見せますが常識的な指摘に誰も耳を貸してはくれません。もとは大陸北部の河北省に発した門派のひとつである綾小路流は剛猛かつ重厚な技で知られており、虎形熊歩と呼ばれる動きを旨として熊のごとく重厚に攻めよると虎のように剛猛な接近短打の一撃を打ち込むとも言われていて、更に現在ではこれに劈掛拳の手技が組み込まれて懐に飛び込むスタイルを確立させています。
「いやだからそれ華道じゃないから」
この期に及んでつっこみをしても無駄なことと知りつつ常識人の感覚を捨て去ることができません。理性を残したままではデビルマンになれませんが、別に彼女は勇者アモンと合体したりはしないのです。
それまで組んでいた腕をことさらゆっくりとほどき、拳を握り締めて構える綾小路静香と対峙して、竹刀の一本も鈍器の一つもなくては綾小路流の華道に剣道で応えることはできないでしょう。手頃な得物はないだろうかと周囲を見渡すと、ちょうど足下にモンスターハンターでも採用されているすてきなハンマーが転がっていました。
「行きます!」
礼儀正しく構えてから前進。正しい剣の道を見せるべく、すり足による踏み込みからあえてオーソドックスな面打ちを狙う先輩のハンマーが振り下ろされました。襲いかかる一撃を交叉させた両腕でがっちりと止めた綾小路静香の全身に血管が浮き立つと、まるでラオウの剛拳を受け止めたトキのようにバルクアップした肉体は衝撃を正面から受け止めて小揺るぎもしません。誓いの時は来た、今私はあなたを超える。
先手を止められて一歩を下がる先輩に、軽く首を鳴らしてみせた帝国海軍の秘密兵器は礼には礼で返すべく傍らの水盆に活けられていた枝振りのいいヒノキの幹を担ぎます。スレッジハンマーに石柱で対抗するワムウ様のように頭上に抱え上げた幹が振り下ろされて、受け止めた衝撃が火花となって飛び散ると頑丈な幹が砕けますが、弾かれたハンマーの柄も先輩の手を離れて回転しながら背後の床面に突き刺さりました。剣士として武器を手放してしまった先輩は敗北を認めるしかなく、がっくりとひざを下ろします。
「・・・参りました」
激闘に勝ち誇るムキムキピチピチの十七歳は、戦いと勝利の双方に満足すると次なる相手を求めて学生たちに視線を巡らせます。無言の要求に応えて飛び出したのは佐藤愛(さとう・あい)が連れている愛くるしいペットたちと、敬愛する先輩の敵を討つべく(死んでませんけどね)同じく元気よく飛び出したナンジャさんでした。
「ミーコ、ジョン、レオン、ナンジャ?ご飯はちょっとだけお預けね」
「なのだー!」
バスキア学園の流儀として決斗勝負が一対一である必要は必ずしもありませんし、チームワークの意味を思えば強大な相手に力を合わせて挑むことはむしろ純粋な技術の一つとすら言えるでしょう。最近正式にカバディ部の創設を認めてもらったナンジャさんの機動力をもってすれば、一人のナンジャが二人のナンジャ三人のナンジャが四人五人オウオウオウオウヤアと襲いかかることだってできました。
「カバ以下省略ー!」
まるで101匹ワンちゃん発情期のように走り出すペットたち。黄色くにごった目に口からはだらだらとよだれを垂らしているバイオニックな黒犬レオンの背にナンジャさんもまたがると一斉に飛びかかりますが、迎え撃つ綾小路静香も腰を低く落とすと両の掌を前に突き出すように構えます。
「哈ァッ!」
むき出しの牙と伸びた爪が届くと見えた刹那、鍛え上げた硬気功が綾小路静香の強靭な肉体をハガネに変えると気合い一喝動物たちを弾きとばしました。きゃいんきゃいんと地面に落ちる獣たちに続いて猛牛マックがデータイーストの空手道ばりに突進しますが、やはり空手道のボーナスステージばりに沈み込んだ姿勢からしゃがんで逆突きの一撃が眉間に打ち込まれると得点500点とともに巨獣の身体がぐらりと傾いで朽木のように倒れます。
綾小路流免許皆伝の実力は草花はもちろん獣に対しても退くところがありません。ナンジャさんと愛と動物たちがこれを克服するには力を超える友情または熱情パワーが必要でしょう。
「カバ?」
「カバさんですか?」
どこからともなく体重1トンを超えるカバが一頭。
 「カバカバカバ」
「カバカバカバ」
「カバさんですね?」
サバンナの乏しい水辺に集まるカバが数頭、数十頭と現れるとカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバディと連呼するナンジャに合わせて巻き起こる土煙がまるでトルネコが呼ぶ商人の群れのように唐突に過ぎ去って後には残骸しか残されていませんでした。パワープレイにはいつか限界が訪れて、強大で圧倒的な力を最後に倒すのはミスター・サタンの呼び掛けに応えた人々の元気玉だったという言葉に彼女たちが耳を貸してくれる筈もなく、力ずくのアニマル・アタックでケモノになりたい彼女はケモノの俺に逆らえない。
「カバカバカバカバカバカバカバカバカバー!」
「名前をつけないといけませんね」
こうして悪の校長が用意した試練もいよいよ三層目に入りましたが少年漫画を思わせる際限ない力のインフレーションがどこまで続いてしまうのか、容易には判断がつきません。幸いバスキア学園で死人が出る筈はないのでアストロ球団になる心配こそありませんが、収拾がつけられなくなれば追放されてアフリカに行くしかないのです。
「どう思いやすか?」
「ん?」
それまで仲間たちの後ろに控えるように観戦役に徹していたカミソリ斬七朗(にっぽんでにばんめのとこや)が、尻を突き出した後は同じように控えていたミスター・バスキアに声を投げかけます。カミソリを持った渡り鳥と馬に生涯を捧げた男の二人連れは、西部劇でなければ怪傑ズバットの世界を生きているかに思える渡世人たちでしたが基本的に牧男は愛馬エ%シンホワイティにこそ乗っているもののお馬さん同士のレースに興味がある確率研究会の一員でしかないことはあまり人に知られてはいません。
斬七朗が気になっていたのはこれまで用意されていた試練と仲間たちの戦いぶりを見た校長の思惑であり、力を正面からの力で攻略した、その次に現れた試練が更なる強力な力であったという事実でした。校長があれでも教育者を自称する人物であり、際限ない力のインフレーションに異を唱えようとするのであれば、あえて次の試練もまた強力な力を用意してこれを力以外の方法で克服させようとするのではないかというのが斬七朗の意見です。
「あっしが校長さんならそうしやすね」
「ボーイの考えには同意するが・・・」
それでも試練は堂々と正面から乗り越えてこそ克服したと言えるのではないか、学園の皆であればそう考えるに違いないしそれもまた正しいだろうというのが牧男の意見です。
渡世の床屋として生きてきた斬七朗はそれに納得はしながらも、どれほど優れた技、極めた術であってもお客さんが満足しなければ意味がないことも知っていました。戦いには当事者を超える第三者が存在することを彼はかつてニッポンで一番目の床屋から敗北とともに教えられていたのです。もっとも牧男本人は斬七朗への言葉に加えてこうも言っていました。
「まあ俺様の座右の銘は『勝てば官軍』だけどな」
ところで史上最強の生物とは何であるか。唐突な質問ですが地上最強どころではなく生物の長い歴史の中で最強の存在といえばかつて数億年の昔に地表を闊歩していた恐竜の名を挙げることができるでしょう。ミスター・ストライダム曰く、その恐竜に戦いを挑み捕食していたという、考古学上の定説も生物学上の常識も覆してしまう存在こそ太古の地層から発掘された氷漬けの戦士ピクル(作者補正有り)でした。
化石時代の旧人類はベイン博士と科学者アレンくんによる解凍蘇生実験&レックス・ステーキのにおいで二億年の時を超えて蘇ると、厳重な警戒の中で来日していましたが空港に到着する早々女子アナ相手にさかってしまうというハリマオ以上の野生を発揮します。そのピクルが放送倫理上の問題で腰布だけは履かされた状態で、東京ドーム地下格闘場めいた砂地の部屋でつまらなそうに腰を下ろしていましたが、誇り高いこの生き物は自分よりも強大な敵が現れたときにはじめて、それを餌として狩るべく襲いかかるという習性というか性癖がありました。
「つまりこれは拙者のマッハに対する試練でござるな!」
今回はマッハ人生をテーマにしている半蔵であればこそ、天才愚地克己が真マッハ突きを用いてなお倒すことができなかったピクルを攻略しない訳にはいきません。何しろ相手はあのティラノサウルス・レックスやトリケラトプスを捕食していたとさえ言われる、生物を超えた超生物なのです。斬七朗が言っていた通り、際限なく続く力のインフレーションを承知した上でそれに正面から立ち向かうことは半蔵の矜持でもありました。愚直なほどひたすらに鍛錬を繰り返して力を得ること、それは決して無意味な行為ではない筈です。
腰布いっちょうの原始人は黒装束の忍者に興味を覚えると二メートルを超える巨体をゆっくりと立ち上がらせますが、ある意味時代を超越している二人が正面から対峙する姿は一種異様に見えなくもありません。
すでに人類どころかまっとうな生物の範疇すら超えている超生物と向かい合いながら、半蔵はここで自分に求められているものが何であるかを正確に理解していました。あからさまに際限がない力、それに挑むならば彼に必要なものは単純に相手を超える力ではなく自分の限界を超える力であるというのが校長の真意なのでしょう。他人を負かすのはそんなむずかしいことじゃあないが、もっともむずかしいことは自分を乗り越えることだというのはかの岸辺露伴も言っていることです。
「拙者の超電磁神風を超える回転超電磁神風の術、それを真に極めるにはやはりマッハの領域に到達するしかあるまい」
高速のすり足で放電しながら突進する超電磁神風の奥義、これに回転を加えることで必殺技としたのが名づけて回転超電磁神風です。とても強力な技である一方で、空中でいちど回転してしまえばあとは勢いで回り続けるだけですからそれ以上更に速くなることはありません。速度がどれだけ大きくても加速度がゼロなら空気抵抗によりやがて力が衰えていく、それは物理法則からも当然のことでした。
超電磁神風の術が生み出した静電気、これを身にまといつつ回転して電磁力を生み出す技が回転超電磁神風であり、放電する電磁の竜巻が目標を捕らえ、そこに同じく電磁力を帯びた半蔵が突入することによって回転しながら引き合うと目標に正確に命中する。放電する竜巻と引き合う半蔵自らが一本の磁石であり、それが回転すれば右ねじの法則によって電磁力を得ることができますから、回転する竜巻の電磁力に引かれるリニアモーターカーと同じ原理で加速することができましたがマッハを狙うにはこれだけでは足りません。
空中で回転するからこそ半蔵は電磁の力を得ることができましたが、ひとたび空中に飛ぶ以上、加速は初動の一瞬にこそ最大を狙えるのは当然でしょう。であればその一瞬、初動に爆発的な速さを得ることがマッハに至る最短の道でした。全身の関節を完璧に連動させてただ一瞬の加速に費やす、筋肉を脱力させてしなやかな鞭と化し、爪先から足首、ふくらはぎからひざを経て股関節から脊椎といったように回転を繋げていくことによって二十七箇所の関節が完全に連動したときに半蔵の肉体は時速千二百二十五キロメートル、音速を超えることができる筈です。もちろん砂は音に弱いくらい勢いで考えた理論ですから深く検証してはいけません。
「参る!」
それまでにたにたと笑っていた原始時代の戦士を前に、半蔵は自らの肉体を武器とした彼だけのマッハを放つべく深く構えます。太古の野生がただごとではない気配を感じとったのでしょう、ピクルの表情が変わり彼の中で半蔵は遊び相手から全力で捕食すべき餌へと昇格を果たしました。
郭海皇が心臓を止めたくなるような一瞬の後、半蔵の肉体が時速千二百二十五キロメートルで飛ぶと次の瞬間には放電の軌跡だけを残して消え去ります。回転しながら全身の関節を同時に稼働させて加速する、伊賀忍者界のリーサル・ウエポンがティラノサウルス・レクスの尾の一撃にすら耐える強靭な肉体を弾き飛ばし、遅れて到達した衝撃波が奇妙に甲高い音を立てて炸裂しました。
原子の力もマッハの前では分が悪い。恐竜を相手にしても屈服しなかったであろうピクルが膝をつきますが同時に伊賀忍者界の若きリーダーの肉体もどさりと音を立てて倒れます。よく考えずとも音速を超えるスピードでぐしゃりと激突すれば、すさまじい衝撃は半蔵の肉体をも砕かざるを得ません。全身を朱に染めた忍者は力を尽くした結末に満足した表情を見せると崩れ落ちますが、覆面の下なので誰に見られることもありませんでした(死んでませんよ)。
文字通り身を賭した一撃、ですが恐竜時代の戦士は彼が体験したこともない衝撃に驚愕を覚えながらも、存在自体がインチキに等しい肉体はこれに耐えて悠然と立ち上がります。誰かがパワープレイにパワープレイで対抗することにブレーキをかけなければこのまま校長の試練はエスカレートして、遂にはフリーザ様やスーパーサイヤ人3あたりが登場せざるを得なくなるかもしれません。今度こそ誰かがからめ手で勝たなければなりませんが、からむといえばランダン流格闘家を除けばあの男しかいませんでした。
「つまりこれはボクのマッパに対する試練だね!」
薔薇小路綺羅は半蔵のようにマッハではありませんが間違いなく彼はマッパでした。腰布いっちょうの太古の戦士に対してビキニタイツいっちょうで立つ美の化身はけっこう似合いの相手かもしれません。野生の獣そのままの肉体が内包する巨大なエネルギーはある種の美しさを感じさせて、綺羅は愛読するゲーテの詩集を懐にしまうと美しさを競うべく腰をくいとひねって構えます。太古の野生がただごとではない気配を感じとったのでしょう、ピクルの表情が変わり彼の中で綺羅は遊び相手から全力で捕食すべき餌へと昇格を果たしましたがこの際は食べるの意味が変わっていないことを祈ります。
「ああっ!」
まるで烈海王が頬を染めたくなるような一瞬の後、美獣の肉体が時速千二百二十五キロメートで飛ぶと舞い散る花びらだけを残して消え去ります。回転しながら全身の関節をくねらせて加速する、美世界のビューティフル・ウエポンが激突した瞬間に身に着けていたわずかな衣服すらも弾き飛ばし、遅れて到達した布きれの破片がまるで枯れ葉のようにひらひらと舞い落ちました。これが綺羅だけのマッパ、真・マッパ好きです。
「ボクのムチを当てない打撃ッ!」
原始の力もマッパの前では分が悪い。とはいえこのままではパワープレイよりももっと間違えた方向に戦いがエスカレートしてしまうのは時間の問題でしたから、男たちの戦いを見届けていた斬七朗が愛用のカミソリ「耳なし」を抜くと無数にも見える軌跡が飛び交い、閃いた弧線だけが人の目に残像として残りました。
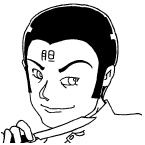 「そろそろこの辺にしておきなせえ」
「そろそろこの辺にしておきなせえ」
どこからともなく石川五右衛門が斬鉄剣を抜いたときのちゃらり〜んというSEが響き、ピクルも綺羅も上から下まできれいに剃られてしまうとさすがに放送コードに触れてしまうので頭上から網が落ちかかり、動けぬ獣たちに向けて麻酔銃が放たれると時空を超えた二人のマッパは捕獲されてしまいました。
「またつまらぬものを切ってしまいやしたぜ」
力に力で対抗する限りそれを超える力が試練として与えられる。底意地が悪いといえばそれまでですが、それは鍛錬による力を望む者にとって超えるべき目標が常に用意され続けるということですし、そうでない者にとっては力では決して及ばぬ相手を覆す工夫が求められるということでもあります。打倒校長は学生たちに与えた目的であると同時に、まがりなりにも教育者のはしくれにかろうじて引っかかっているミスター・ホワイトの思惑ではそれが生徒たちに何らかの向上心を与えなければ彼の大義名分が立ちません。
「ですが力が力以外の方法で克服された。今度こそ異なる相手が用意されるでしょうね」
「じゃんけんとかだといいんですけどね」
それは此花が得意とする知性と理論を駆使した戦いになるでしょうか。少なくとも単純な力によらない試練であれば彼女が挑むのに向いているように思えますが、例えばどこぞのジュテミストが喜ぶような美を競う試練を用意されたらそれはそれでたまったものではないでしょう。どこまで本気か分からないような紫苑の言葉に、軽く苦笑してみせます。
石段を上り、足を踏み入れた第四層もこれまでと同じように広々とした部屋ですが、今度はごくふつうの板張りのフロアで一見したところ何がいる様子もなくいつまで待ってみてもそれらしき相手が現れる気配すらありません。それどころか危険や緊張感、ある種の悪寒といった感覚さえ微塵も感じとることができず、穏やかな空気に耳をすませてみればぴよぴよといった小鳥のさえずりまで聞こえてくる始末です。
もしかして校長が試練を用意するのを忘れたのではないだろうか、そんなことを思った此花ですがふと気がつくと小首を傾げながら唇に指先を当てて考え込みました。どうして塔の中でぴよぴよ鳴く声が聞こえてくるのだろうか。背後でちょっと早めの食事の時間に興じている愛のペットたちに視線を向けてみても、こちらはガウガウギャアギャアシュウシュウといった声が聞こえるだけでぴよぴよの主がいるとは思えません。
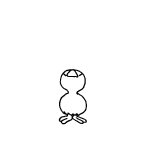
「あこそ、何かいますよ?」
気がついた紫苑が指差した先、あまりにも広すぎる部屋の真ん中に小さな小さな何かがぽつりといる姿を見つけると、もともと視力が弱い此花は眉根を寄せて眼鏡の奥の目をいっそう細めます。彼女たちを通すまいとして決然と立ちはだかっている姿、それはとてもやる気のある一羽のヒヨコでした。
この階を超えるためにはどうしてもこの敵を倒さなければいけません。おそるおそるといった様子で近づく此花を前にしてもヒヨコは怯む様子もなく胸をそらせていましたが、近寄ると足元にとことこやってきてくちばしでえいとつつきました。
いったいどうやってこれを倒せばいいのか、コンピュータのまた従姉と評される彼女の知性は一瞬でオーバーヒートしてしまうととてもまともな判断などできそうにない状態に陥ってしまいますが、とにかく戦ってみようと伸ばした指先で押すようにヒヨコの身体を転がしてみます。
ぴいっ。
かんたんに転がってしまったヒヨコはぴいぴい鳴くと頑張って起き上がりました。ものすごい罪悪感に襲われながら、もう一度指先で転がしてみます。
ぴいっ。
やっぱり頑張って起き上がったヒヨコは負けてなるものかと立ちはだかります。このおそるべき敵を相手にして呆然とする友人を助けるべく、紫苑が助っ人にやってくるとどきどきしながら人差し指でちょっと弾いてみました。やわらかいものが少しだけ宙にういて、ぽてりと落ちるとそれでもやる気のあるヒヨコは一所懸命起き上がって目をうるうるさせています。
「な、なんてことをするんですかっ!」
「ご、ごめんなさいっ」
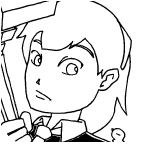 思わず此花が紫苑に詰めよりますが、彼女自身がヒヨコにした仕打ちを思い出すと友人から視線をくっとそらします。懸命に自我を取り戻してから決然と視線を戻しますが、もしもこれで首のまわりをうりうりとしてあげたら一体どうなってしまうことだろうかという邪悪な思いが脳裏に浮かびました。
思わず此花が紫苑に詰めよりますが、彼女自身がヒヨコにした仕打ちを思い出すと友人から視線をくっとそらします。懸命に自我を取り戻してから決然と視線を戻しますが、もしもこれで首のまわりをうりうりとしてあげたら一体どうなってしまうことだろうかという邪悪な思いが脳裏に浮かびました。
小鳥というものはくちばしで自分の顔や首のまわりをかくことができませんから、他の小鳥にかいてもらうことがあるのです。いわば急所みたいなものですから勝つためにはうりうりしてあげないといけないかもしれない!
このときの此花は間違いなく危険な状態に陥っていましたが、彼女たちが心中でものすごい葛藤を続けている間に無言でやってきた桐生先輩が屈みこんで、背中のあたりを押すようにしてなでてあげるとヒヨコはそのまま寝てしまいました。驚いた此花や紫苑、ナンジャさんたちの視線に気がついた先輩はまるで弁明するように叫びます。
「ひ、ひよこは背中を押されると寝てしまうのよ!寝てしまうんだからね!」
「先輩キャラが変わってるのだー?」
とりあえず此花のヤチヨや紫苑のハルミのカメラ機能が存分に駆使されて大量のヒヨコの画像がメモリーに収められたようですがそれはそれとして。鋼鉄の巨神に帝国の秘密兵器、古代の超生物からとてもやる気のあるヒヨコまで数々の試練が設けられていた塔もいよいよ最後の層を残すだけとなり、そこには彼らが目指しているマスターホワイト、天空の高みから下界を睥睨する白い校長が待ち受けているに違いありません。衝撃からなんとか立ち直ったらしい此花が呟きます。
「こうなると校長が何を用意しているか・・・」
私にもちょっと読めないと言ってしまうと海のリハクになってしまうことに気がついた此花は言葉を打ちきります。校長自ら出陣するか、最後の罠を設けているか容易に判断することはできませんが、単に学生たちを驚かせることが目的ならここまで来て塔はニセモノでしたというマンパン砦ばりのどんでん返しを用意する手もあるでしょうか。
とはいえZEDの呪文が使えない彼らにそれを強要するのはゲームマスターとして許される行為ではなく、あくまでルールに則って反則をするのが悪役レスラーというものです。さしもの学生たちもここまで来れば校長がどういう人物であるか何となく理解できていました。
「龍波くん?どうかしましたか」
「ああ、いや・・・何でもないぜ」
本当ならここでプレイボーイ志願者らしく何でもないぜベイベーと返すべきところでしょうが、考えごとにふけっていた吹雪にそこまでの余裕はありません。そもそも彼が深刻めいた顔で考えごとをするなどあまりにも珍しく、此花の奇異を誘ったのも当然ですが戦士はここまで来てもなお心中のわだかまりをぬぐい去ることができずにいたのです。
その卑劣な申し出を受けることなど考えることもできませんが、若き虎の群れを相手にする老いた虎の姿を思えば無心でいることもできません。そういえばこんな心境を現すにふさわしい歌があったと思うと吹雪はおもむろにマイクを握りました。
つかみかけた熱い腕を ふりほどいて君は出てゆく
わずかに震える 白いガウンに君の
年老いた悲しみを見た
リングに向かう長い廊下で 何故だか急に君は立ち止まり
ふりむきざまに 俺にこぶしを見せて
寂しそうに笑った
やがてリングと 拍手の渦が
ひとりの男をのみこんで行った(You're king of kings)
立ち上がれ もう一度その足で
立ち上がれ 命の炎燃やせ
君はついに立ち上がった 血に染まった赤いマットに
わずかに開いた 君の両目に光る
涙が何かを語った
獣のように挑戦者は おそいかかる若い力で
やがて君は 静かに倒れて落ちた
疲れて眠るように
わずかばかりの 意識の中で
君は何を考えたのか(You're king of kings)
立たないで もうそれで充分だ
おお神よ 彼を救いたまえ
ロッカールームの ベンチで君は
切れたくちびるでそっとつぶやいた(You're king of kings)
帰れるんだ これでただの男に
帰れるんだ これで帰れるんだ オー!
ライラライラライラライラライ・・・床を踏みならさんばかりに本日二度目の絶唱を続けている吹雪ですが気がつけば牧男や半蔵といった熱い男たちももちろん床を踏みならして一緒に唱和しています。
若き虎としてせめて吹雪自身の手で老いた虎を介錯してやることが校長に敬意を払うことではないだろうか、戦士の魂は結論に達すると決然として奮い立ちますが心に引っかかることがまるでないといえばそれは嘘になるでしょう。大切なマイクを懐にしまった男たちはいよいよ決戦に臨みます。
石段を上り入場ゲートめいた通路を抜けた先、四方に玄武白虎青竜朱雀の大書が書き殴られた、広々としたフロアの向かいにはただ一人で学生たちを迎え撃とうとする気高い男の姿がありました。すでに下の階でいろんな部下を使っているじゃんとか、そんな指摘はささいな誤差でしかありません。
彼こそはミスター・ホワイト。私立バスキア学園を支配する校長にして権力者であり、またの名をどす黒い白と呼ばれるビンス・マクマホンばりの悪の総帥です。和装を着て悠然または泰然として構えている校長に戦士の総決算をすべく、決意の拳を握り締めたのはもちろん我らが吹雪でした。
「ここは俺に行かせてくれ」
「吹雪殿?」
守るべき友人たちを背に一歩を踏み出した吹雪は、戦いに殉じる戦士の面持ちで校長に対峙します。まず彼が出てくることを予想していたのでしょう、校長は神妙な様子をして先に自分がとった卑劣な言動を恥じているようにも見えましたし、これから裁かれることを覚悟しているようにも見えました。
一方の足取りはまっすぐで迷いがなく、一方の足取りはゆっくりとしていてしぜん、両者が足を止めた場所はフロアのより奧の方になってしまい、背後に控えている学生たちから見れば校長が少しうつむき加減でいることを除けばその表情まで読み取ることはできません。両者がいよいよ向かい合うと、裁かれるべき卑劣な校長が遠慮がちな声を漏らしました。
「龍波くん・・・」
次の瞬間、無防備な吹雪の後頭部にダッシャ!の叫びとともに校長の強烈な延髄斬りが炸裂します。飛び上がっての派手なキック、格闘技の実戦ではまず決まらないだろう大技が空手をたしなんでいる筈の吹雪を一撃で沈めると校長の右拳が天高く突き上げられました。
校長の策略も吹雪の葛藤も知っている筈がない者たちが見れば、真剣な面持ちで一対一を挑んだ吹雪が思わぬ大技一発でダウンさせられたのであり、もしかすると校長はやはりただ者ではないのだろうかと学生たちの間にどよめきが走ります。まさかの奇襲に頭を抑えてうずくまる吹雪に校長の右手が差し伸べられました。
「立ちなさい、龍波くん」
素直に手を握ってしまった吹雪の股間を悪の右足が強烈にかち上げます(良い子は真似をしないでください)。もちろん観客からは完全に死角になる角度から、情け容赦のない男の一撃で完全に動きを封じてから卍固め、カール・ゴッチ直伝のオクトパスホールドががっちりと決まりました。
アントニオ・ホワイト数ある必殺技の中でもベストをひとつ挙げるならこれ!と言われるフェイバリット・ホールドは完璧に決まれば決して抜け出すことができず、無情のレフェリーストップコンテストが宣告されると気の毒すぎる敗者の骸(死んでません)がどさりと地面に倒れ、まさかの秒殺劇にどよめきが走ります。
「勝負ありッッッ!」
ちょっととぼけているけど空手の腕前は一級品、いたずら厳しく一級品、だけど女にゃからっきしだよ三級品のあの吹雪が延髄切り一発からの卍固めというアントンな攻撃で倒されてしまったという事実に動揺が隠せません。言いたいことはいろいろあるけど物言わぬ戦士の屍(死んでませんけどね)を乗り越えて、愛馬エイシ%ホワイティを駆る牧男が蹄の一歩を踏み出しました。
 「では次は俺様だな」
「では次は俺様だな」
ミスター・ホワイトを倒すにはミスター・バスキアが出るしかないだろうと、校長以上に偉そうな牧男は無意味な図々しさで対抗すべく愛馬の首筋を手でなぜてみせます。
馬上から地面にひらりと降り立つと、自分の好きなルールで構わないなら俺様は馬券での勝負を提案したいと言い放つ牧男は切っ先するどいマークシートをまるでキャッツアイ三姉妹のように指先に構えました。「強くあれ」を標榜する校長にもちろん異がある筈もなく、どんなジャンルであれそのすべてを迎え撃とうと宣言する姿は牧男に劣らず必要以上に自信に満ちあふれています。
勝負の方法は単純、互いに背を向けて立ちまっすぐに十歩ずつ歩いたところで振り返って一撃を放つ。東京コーヤクランドの荒野にふさわしい男の決斗勝負でありおそらく勝敗は一瞬でつくことになるでしょう。
一歩、二歩、三歩・・・と歩みを進めていく、二人のガンマンの足音が互いの耳には届いていて、歩調を合わせているそれが勝負のカウントダウンを兼ねています。この場合、あくまで撃ち合いは同時でなければならず、例えば十歩を数える前に振り返って撃つようなことをすればそれは卑怯や卑劣というレベルではなく、単なる不意打ちでありルールそのものを無視する暴挙でしかありません。
先程の吹雪との試合が不意打ちかどうかは置いといて、悪の校長であるからこそ反則はできてもルールを逸脱することはできないだろう。牧男の勝機はそのデッド・ラインを味方につけることにありました。
「制限されたルールであるほど反則が難しい。この勝負、俺様がもらったぜ!」
撃ち合いになれば牧男のマークシートは弧線を描いていかなる防御すらもかいくぐると正確に目標に命中する、それだけの自信がありました。パドックから本馬場入場に至るまでの、出走ぎりぎりの時間まで粘ってシートを提出するために編み出した彼ならではの奥義ですがそもそも学生が馬券を買ってはいけません。七歩、八歩、九歩・・・
ごっ。
同時に十歩を踏んだ瞬間、同時に振り返ると投げつけられたカードをかいくぐって握り心地のいい石が牧男の眉間に命中します(良い子は真似をしないで下さい)。確かに何を投げるとも何を撃つとも誰も言ってはおらず、せっかくルールを制限したのに肝心の投げる道具を制限し忘れた牧男のマークシートがむなしく空を切ると石壁に突き立って、カウボーイの身体がどさりと倒れました。白い長髪をばさりと風になぶらせて、大人げない連勝記録を伸ばしたミスター・ホワイトが勝ち誇る声を上げます。
「さあ、次は誰かな?」
「あっしが行きやしょう」
荒野の決斗勝負に倒れた骸(死んでませんってば)を乗り越えて、校長の挑発に足を踏み出したのは斬七朗です。ニッポンを巡り、技を磨きながらも常にお客さんの要求に応えてきた彼は灰色のバーバー・ブレインを駆使して考えます。純粋な格闘の舞台を望んだ吹雪はまるでプロレスのように派手な大技の前に沈み、戦いをデザインすべくルールを提案した牧男はそのルールに足を取られて敗北、であれば校長自身にルールを提案させたらどうであろうか。
何をもって強さを競うか、その方法は校長さんが決めて構いやせんぜと言い放つ斬七朗。挑発を挑発で返されたことにおもしろそうな表情を浮かべたミスター・ホワイトはさほど長くもない時間、考えるような表情を浮かべると勝負の方法を提示しました。
そのルールはジャンケン勝負、奇しくも紫苑が此花に答えた冗談が冗談ではなくなってしまいましたが、それは古く超人オリンピック予選でも採用されている伝統の競技であり先に三本を先取した側が勝利、途中棄権は敗退というルールはかの岸辺露伴対ジャンケン小僧でも用いられた格式ある戦いです。相手をしのぐ強運が求められると同時に相手の心理を読み、更にはプレッシャーをかける駆け引きが要求されるという単純に見えて奧が深い競技でした。
この方法でも勝ってみせるという校長の自信を感じながらも確かにジャンケンであれば斬七朗がこれまで磨き上げてきた床屋の秘術や裏技術を使う余地はありません。それでも人を切る世界に長く従事していた彼であれば、人の心理を読む経験にも長けていてそれは完璧とまで断言はできずとも三本先取の長期戦で必ず活きてくるでしょう。
「覚悟はいいかね」
「いつでも来なせえ」
校長は右、斬七朗は左に構えます。向かい合って立つ両者の間を一陣の風が吹き抜けると、先程に続いて荒野の決斗勝負にふさわしい緊張感が男たちのうなじのあたりをぴりぴりと刺激していました。両足は肩幅に開き、最高の速度で抜いた手を放てるように、力みを抜いてだらりと伸ばした腕は両脇を少し開いて構えられている、斬七朗の姿は奇しくも両手撃ちのガンマンが構えるそれに酷似しており極められた技が同じ山の頂に到達するという事実を証明しているようにも見えました。
互いに大きく振り被ってから、じゃんけんほいのかけ声とともに抜き放たれる二つの手、突き出されたそれは校長の手がチョキを、斬七朗の手がグーを示しておりニッポンで二番目の床屋が先んじて一勝を得ることに成功しますが、初戦を落としたにも関わらず不敵な笑みが消えずにいる校長の手がゆっくりと斬七朗の拳に迫ります。

斬七朗の右手から破滅の音がすると、星飛雄馬のように使いものにならなくなった腕ががっくりと垂れ下がりました。そのおそるべき思惑に気がついたときにはすでに手遅れであり、残された左手がじゃんけんほいのかけ声を聞いて反射的に抜き放たれるとやはり校長の手がチョキを、斬七朗の手はグーを示しています。やられたという表情としてやったりの表情が好対照を描く二人。
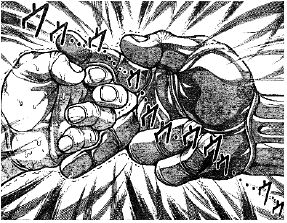
俺のチョキは石をも砕く。じゃんけん自体は確かに斬七朗が二勝をしましたが、二つの石を砕かれた彼には文字どおり打つ手がなく後は敗北の辛酸をなめるしかありません。どんなジャンルであれそのすべてを迎え撃ち、そのすべてに勝ってみせるという男の本領がここにありました。ホラティウス家の三人は最初の二人が倒されても最後の一人でクリアティウス家の三人を撃破することでローマに勝利をもたらしたのです(良い子は真似をしないで下さいね)。
「さてそろそろ終業のチャイムが鳴る時間かな」
「では拙者が相手をさせて頂こう」
戦場をともにしてきた男たちが一人ずつ倒されてしまい、半蔵は決然として彼を待つ戦いに身を投じます。この期に及んで奇をてらう理由はなく選ぶルールは自由格闘、武器の使用だけは禁止として最後まで立っていた者が勝利というシンプルな方式を選びました。
強くあることを目指して精進する、その考えは貴重ですがそれだけが正しいと考えることはできない。悩み抜いた半蔵だからこそ自分が悩みすぎていたことに気づき、ただ勝ち負けにこだわるのではなく普通に暮らしている生徒たちへの選択肢も与えられること、それを勝ち取るべく彼は校長に挑みます。
それは弱きに安住することを肯定するのではなく、千尋の谷に落とされた獅子であっても谷を登る途中でつまづく子がいるだろうことを慮ってのものであり、谷の途中に身を休める場があっても悪くあるまいという考えでした。あえて足を止めることで思索を巡らせることも、仲間を助けようとすることも、更なる強さを身につけることもできる筈なのです。
「よかろう。ならばその更なる強さを私に証明してみたまえ」
「無論!そのつもりでござる」
半蔵が選ぶ技は回転超電磁神風。彼の思いが正しいのであればあえて新しい技を探さずとも、彼が信じて鍛え上げた技を更なる高みに到達させることがふさわしい筈でした。二十七箇所の関節を同時に稼働させる、それがマッハの理論ですがイメージの力は無限であり肉体に備わっている関節の数を無限に増やすことで限界を超えた動きを獲得することができる筈です。
もろい中身を守るために卵は固い殻を持ち、キリンは高いところにある草を食べるために首を伸ばした。ゾウが鼻を伸ばしてシマウマや虎が縞模様になり、ヒョウが柄を手に入れて昆虫は擬態し鳥は翼を持ちヘビが毒を備えたようにすべては生き残らんが為、彼ら生物たちの「生」に対しての執念がもたらした進化の大きさです。
「拙者自身が・・・驚いているッ」
そもそも進化の基本は突然変異と適者生存なんですがそれはそれとして、イメージの力で進化した伊賀忍者の肉体が完全に脱力した瞬間、再び音速を超えたマッハが放電の軌跡だけを残して消え去ると遅れて到達した衝撃波が周囲に炸裂しました。
閃光に続く衝撃と音、それが去って巻き起こる砂煙の中に残されていたのは壁面にぐしゃりと激突して崩れ落ちている半蔵の姿と、全身全霊の一撃に敬意を表するように、傷つきながらもゆっくりと立ち上がっている校長の姿でした。
「・・・見事な一撃だった。あるいは君が連戦をしていなければ勝敗はところを変えていたかもしれないが、君自身の身を犠牲にした結末が今こうして立っている私であるならば、やはりこの勝負は私の勝ちというべきだろうな」
「いや、そうじゃないさ」
勝ち名乗りを上げようとしたところにかけられた、思わぬ声に校長は振り向きます。そこに立っていたのは眉間から赤いひとしずくを垂らしている牧男であり、先に荒野のガンマン対決で命を落としていた筈の彼はホル・ホースの「皇帝」の餌食になったモハメド・アブドゥルのように命中した瞬間、身をそらしたためにちょっぴり頭蓋骨の表面を削られると意識を失っていただけだったのです。つまり彼が挑んだ校長との戦い、馬券での勝負は未だ続いているということでした。
「壁に刺さっているものをよく見るんだな」
半蔵が崩れ落ちている石壁に突き立ったままのマークシートを抜き取ると、校長の手に握られたそれには黒のマジックインキで「校長の勝ち:万馬券」と殴り書かれていたのです。つまり半蔵との勝負に校長が勝てばそれは馬券が当たった牧男の勝利であり、そうでなければ校長は半蔵に敗れるしかありません。とても卑劣な気がしますがそもそも校長が卑劣ですから何も問題はありませんでした。勝利を確信したカウボーイが校長に問いかけます。
「ひとつだけ聞かせてもらおう、あんたなんでこんな学園をつくる気になったんだ?」
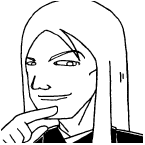
国際時代に対応できる生徒の育成、放棄された東京コーヤクランドの敷地を利用しての巨大学園都市の建設、ですがその根底に何があったか、単なる興味であっても校長が何を考えてこのような制度を考えたのか牧男ならずとも聞きたいことです。
「そんなことに興味があるのかね。ならば年寄りの昔話を教えてやってもよかろう・・・」
もともとミスター・ホワイトは若くして名を知られた天才的な人物であり、小学生のときに灘高の入試問題を解いて中学生の感想文ではデカルトを構造主義で批判し、高校生では体育で幅とび8メートルを飛ぶような子供でした。若きホワイトは各国の文化や知識を貪欲に追い求めてそれにふさわしい博学強記を得ると、今から数年以上も前に海を越えた東洋のちっぽけな島国に渡ることになり初めて訪れるこの国の文化を身につけるためにやはり多くの知識をかき集めようとします。
彼はフィールド・ワークを軽んじる訳ではけっしてなくその重要性を知悉していた一方で、文明の所産である文献や記録の価値に対してもごく正当な評価を与えていましたからまずは多量の書物や映像からこの国を知ろうと努めました。そして玉石混交清濁併飲といった言葉はこの場合、彼の知識に対する貪欲さにも完全に当てはまったのです。
「私はこの国の文化を知るためにうわさの天海やトイレット博士、かぼちゃワインに名探偵カゲマンといった書物の数々を読み、更にはかげろう忍法帳やテレビジョッキーに刑事くん、目方でドン!や西部警察といった映像資料を調査した。その結果、私は無宗教とされている筈のこの国の人々が六百万人も信奉している、友情努力勝利という哲学が存在していることを知ったのだ」
なまじむつかしい書物や文献がすでに目を通したものばかりであったために、彼が知らない新しい知識を意図的に求めたらこのような悪魔が完成してしまいました。おそらくこの男には日本の神様とは空からブランコで降りてきてとんでもない私ゃ神様だよと言う存在に思えているのでしょうし、警察が凶悪犯を逮捕するためにヘリコプターからショットガンを撃つものだと考えているのでしょう。しかもその知識は現在進行形で更新されていましたから、日本でトラストミーと言えば約束を破ることを意味していますがこれは事実だから問題ありません。
「君たちは見事だったがまだ青いな。勝利を確信したときそいつはすでに負けている、これは私がこの国の文献で学んだ勝利の哲学だが私のミスに最大限につけこむのであれば私が自ら勝利を宣言して勝ち誇る、そのときにすべきであったのだ」
そう言うと校長は壁を背に崩れ落ちている半蔵の手をとってむりやり立ち上がらせると、健闘を称え合うキン肉大王と委員長のように互いの両腕を上げました。同時に終業を告げるチャイムの音が鳴り響き、それは戦い終えてノーサイドの彼らを労るかのように快い音を残します。
「残念ながら服足くんとの勝負は時間切れで引き分けだな。つまり君の馬券は払い戻しという訳だ」
記録上は半蔵と牧男はあのミスター・ホワイトを相手に引き分けた二人の生徒としてバスキア学園史に名を残すことになります。ですが誰がこの戦いの真の勝者であったのか、当事者にはよく分かっていたことでしょう。とりあえずナンジャさんの提案でみんなでなかよく焼き芋を食べて帰ろうということになり、傾いた夕日が学園に赤い光を投げかけていました。
「なぜ焼き芋にマヨネーズをつけるでござるか!」
「何だ、これが美味いのを知らないのかね?」
「納得できねえぜ!勝負しろ校長!」
そんなやりとりがあったかどうかは知りませんが、今日も私立バスキア学園高等学校では戦いの声が絶えることはなく、屋台を離れた隅っこでは子カラスを見つけた娘たちが屈み込んでじっと見ていたら親カラスに頭を蹴られていたりもしていましたが、そんな生活こそいつもと変わらない、ごく普通の彼らの日常なのでしょう。
† つづく †
>私立バスキア学園の案内に戻る


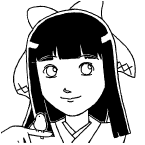 学生にとって年の終わりとは師走ではなく年度の終わり、冬の終わりと春の訪れのことを指しており、寒さの中に忍び込んできた穏やかさが芽吹きを感じさせる感覚はその時が近づいていたことを瑞々しい皮膚にも分かるように示しています。その感覚が地域や時期で微妙に異なるのは四季が存在するこの国で珍しいことではありませんが、広野紫苑(ひろの・しおん)が友人と二人で屈み込んでいた小さな草地はこの時期にも充分な緑色に覆われていて周囲は穏やかな空気に覆われていました。
学生にとって年の終わりとは師走ではなく年度の終わり、冬の終わりと春の訪れのことを指しており、寒さの中に忍び込んできた穏やかさが芽吹きを感じさせる感覚はその時が近づいていたことを瑞々しい皮膚にも分かるように示しています。その感覚が地域や時期で微妙に異なるのは四季が存在するこの国で珍しいことではありませんが、広野紫苑(ひろの・しおん)が友人と二人で屈み込んでいた小さな草地はこの時期にも充分な緑色に覆われていて周囲は穏やかな空気に覆われていました。 「先輩、この塔なんなのだー?」
「先輩、この塔なんなのだー?」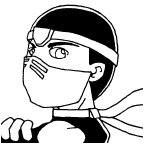
 再び静寂が訪れると周囲は暗いままで今のところは何かが現れたような様子もなく、危難に挑む友人たちの気配しかありません。この機を狙って襲いかかるといった類の卑劣さは校長の流儀ではなく、彼ならばもっと悪辣な方法で生徒たちを陥れようとするでしょう。それを知っている皆は校長の罠を感じて一瞬ごとに緊張を強くしていましたが、それが悪寒に変わったとき彼らは暗闇に潜む危険の存在を理解しました。
再び静寂が訪れると周囲は暗いままで今のところは何かが現れたような様子もなく、危難に挑む友人たちの気配しかありません。この機を狙って襲いかかるといった類の卑劣さは校長の流儀ではなく、彼ならばもっと悪辣な方法で生徒たちを陥れようとするでしょう。それを知っている皆は校長の罠を感じて一瞬ごとに緊張を強くしていましたが、それが悪寒に変わったとき彼らは暗闇に潜む危険の存在を理解しました。 「誰だ?お前」
「誰だ?お前」

 「カバカバカバ」
「カバカバカバ」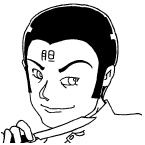 「そろそろこの辺にしておきなせえ」
「そろそろこの辺にしておきなせえ」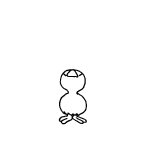
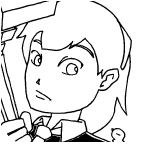 思わず此花が紫苑に詰めよりますが、彼女自身がヒヨコにした仕打ちを思い出すと友人から視線をくっとそらします。懸命に自我を取り戻してから決然と視線を戻しますが、もしもこれで首のまわりをうりうりとしてあげたら一体どうなってしまうことだろうかという邪悪な思いが脳裏に浮かびました。
思わず此花が紫苑に詰めよりますが、彼女自身がヒヨコにした仕打ちを思い出すと友人から視線をくっとそらします。懸命に自我を取り戻してから決然と視線を戻しますが、もしもこれで首のまわりをうりうりとしてあげたら一体どうなってしまうことだろうかという邪悪な思いが脳裏に浮かびました。 「では次は俺様だな」
「では次は俺様だな」