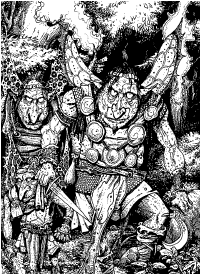SCENARIO#1
大陸から西の海を越えたところにあるミッドランドの島国では、未だ無秩序が善と混沌を押しのけて世界に猛威を振るっていた。『白い魔女』アルガラドが治めているアーガイルの国では、王が死んで以降は各地の村や町の往来が滞ることが多くなり、領土を守る騎士団の姿も見かけなくなって久しく、ことに辺境には野盗や凶暴な亜人のたぐいが住み着いていて不定期の襲撃を繰り返している。
そうした無秩序の中で旅人や商人の往来が著しく減っていたとはいえ、比較的大きな街道に面していたその村は、訪れた者に一泊の宿と一杯かそれ以上の杯を提供する場所として周辺の者には知られていた。だが、今そこではちょっとした騒動が持ち上がっている。先ほどまでエール酒が満たされていた木製の杯をテーブルに置くと、男は皮肉な笑みを浮かべた。
「なかなか威勢のいい坊主だ。だが、血の気が多くとも良いことは何もあるまいて」
「ボクは坊主じゃない!それに悪事を切らずして何の剣があるというんだ?」
一見して少年としか呼べぬほどに若い、銀髪の剣士の放つ威勢のいい言葉にガルド・ミラは白狼の毛皮で作った頭巾の下で髭をふるわせた。「白の狩人」の異名を持ち、ミッドランドの山地や森を定住もせずに五十年ほどの歳月を過ごしてきた彼にとって、目の前の小柄な剣士は若いというよるもあまりに幼く見える。年齢の差も、その外見も、そして言動もだ。髭に隠れたガルドの口元がわずかに上がり、壮年期を過ぎた狩人は隣りに立つ女に顔を向ける。
「のうベレトや、お前さんならどちらがいいと思うかね」
「さてねえ。たださらわれた娘とやらを助けたいんなら、受けたふりだけでもしないといかんだろうさ」
ベレト・エカリムはガルドと数年来旅を伴にしている、癒し手の女である。呪い師の家に生まれ、成人して出奔してから長く野に生きてその技を学ぶうちに、彼女は白の狩人と知り合うようになった。元来が好戦的な質ではないが、荒事の近くにいれば薬師であり治療師でもある彼女を必要とする事態には事欠かない。そして彼女の後ろには屈強な体躯をして、背には大剣を下げた半裸の蛮人が無言で立っていた。ウェイ・ラスローというその蛮人は無口で無愛想な様子を見せながら、村人の好奇と小さな恐怖の混じった視線を受けていたが、より人を見る者であれば蛮人の下げている道具や留め金が存外原始的なものではなく、例え彼が未開地の出身であるとしても文明化された生活にもなじんでいることに気づいただろう。
彼ら三人がこの村に立ち寄ったのは、蒼白な顔をした商隊の使いが酒場に面する広場でわめきたてている丁度その時であった。数台の荷馬車を率いて村に停泊していたとある商隊の娘が、ここから北方にある森を根城にしている山賊によってさらわれたというのである。娘の親である商人は村に人を送り、自分は身代金を払ってでも山賊の要求に従うつもりであるからそれを賊に届けてもらいたいと吹聴して人を集めていたが、村長は村のためにもこれをなんとかして退治して欲しいと呼びかけていた。
そこで酒場で演説めいたことをして「悪党を退治するために共に行く勇士」とやらを集めていたのが先の若い剣士である。エア・トゥーレという小柄な剣士の言葉は純粋な正義に満ちたものではあったが、ガルドやベレトから見ればそれは世間ずれをしていない剣士の幼さの現れにしか見えていない。エアの考えであれば邪な悪党と交渉するなどありえる話ではなく、約束を破るやも知れぬ相手に屈服するかのような仕業は著しく剣と名誉を損ねる行為であったろう。だがガルドやベレトにとっては山賊と交渉するということは娘を救う機会を探すということであり、むろん成功すれば商人に恩を売ることになってより多くの報奨が望めるだろうという打算もあった。
「まあせいぜい英雄の剣とやらを振り回してみるんだな」
「くっ・・・山賊ごときを恐れる奴に要はない!」
吐き捨てると、エアは村長に会うべく荒々しい音を立てて酒場を出ていった。あまりにも無鉄砲なその様子に、ガルドは仲間たちに顔を向けると軽く苦笑をしてみせる。その表情はあの坊主と生きて再会する機会があれば良いが、とでも言いたげであった。正義感の強いエアにしてみれば人質がいるのであればことは一刻を争うように思えるし、街道を往く人々から恩恵を受けているこの小さな村で、それが途絶えるような事態が死活問題であることも理解していた。むろん商人の心配も分かっているつもりだし、ようは急襲して山賊につけいる隙など与えずに退治してしまえば良いのである。
若い剣士は粗末だが広さは充分にある木造りの屋敷を訪れると、響きのよい声で山賊退治を申し出るために現れたと用件だけを簡潔に告げた。これあるを期待していた、格幅のよい初老の村長が駆け出してくるが、あまりに幼げな剣士の姿に一瞬、不安げな顔を見せるとすぐにその表情を打ち消すように話しはじめる。エアにしてみればこれまで幾度となく見せられている顔であり、今さら気分を害するたぐいのものではない。
「酒場で話を聞いてきたというのであれば、すでに剣士様も事情はご承知のことでしょう。山賊共も明後日までは返答を待つと言っております。当の商人は全財産を差し出してでも娘を助けてくれとは言っておりますが、それで山賊が約束を守る保証などはございませんし、味をしめて今後も似たようなことをしでかすことでしょう。私共は何も人質の安全を省みないという訳ではないのですが、このようなことをしでかす悪党は何としてでも退治してしまいたい。北の森にある、彼らが根城にしている古い砦の跡まで半日はかかりますし、こんな街道の村に王国まで助けを呼ぶような余裕もありません。なにとぞ剣士様にお助けを」
村長の言葉にエアは頷くと相手を安心させるべく、自信ありげに剣の柄を手で叩いてみせる。他人に言われるまでもなく、いまだ若く武者修行中の身ではあろうとも、その剣はこれまでも幾度かの悪事を裁いて正義を見せてきたのである。善は急げであろう、旅の剣士は村長から北の森に通じる道筋を聞き出すと、愛用の剣を携えて勇躍村を駆け出した。若い、あるいは幼い英雄に対する村人の好奇と期待の視線を浴びながら、エアは街道を外れた森へと足を踏み入れてしばらくするとその姿も見えなくなったのである。
† † †
山賊の根城は森に入ってから北にまっすぐ進んだ先に設けられている、もとは森林と街道の双方を見張る場所に設けられた駐屯所跡ということであった。森の道は今でも周辺の村人や猟師によって使われているのであろう、頼りない幾筋かの踏み跡が見受けられるが実際には道というほどしっかりしたものではない。勇んで森に入り、迷子にでもなれば一生の恥辱であろうが、それほど視界の悪い場所ではないし、幾らエアが無謀で無鉄砲であったとしても森の中で方角を心得る程度の知識と経験くらいは持っていた。頭上からときおり見える太陽の場所や、多少なりとも開けた場所に出れば葉の茂る向きを見て方角を知ることはできるのである。
だが板金を当てた軽い皮製の鎧を旅装束の上に着て、一人森中を進んでいる剣士の姿はとうに相手によって見つけられていた。もとより剣士の側に身を隠して進むという考えもないのであれば当然だが、村の様子を見るべく山賊が送り出していた斥候が慌てて丈の低い木の茂みに姿を隠していたことにエアは気づいていない。斥候の男は土に汚れたあご髭を一度しごいてから、足取りも早く近づいてくる幼げな剣士の様子を窺う。
相手は一人、どこから見ても話し合いに来ましたという風ではなく、囮にも自分のような斥候にも見えず後ろから仲間が近づいてくる素振りもない。育ちの良い子供が一人、こちらの人質になるべく勇んで登場したようにしか彼には見えていなかった。男は音を立てないように小弓を構えると、短いが鋭い矢をつがえて引き絞った。矢にはこの近くの猟師が狩りに用いる、毒枝を煮詰めた樹液が塗られていて命中すれば相手を弱らせることができる。うまく捕まえれば人質が増えるし、うっかり殺したところでそう困ることはないであろう。自分の手柄に気をよくした男がまさに矢を放とうとしたとき、彼らの頭上から涼やかな声が降ってきた。
「ふふっ。人間には風の声が聞こえないのねえ?」
瞬間、奇妙な笑い声とともに森の中に一陣の風が吹くと、男の手から放たれた矢は不自然に曲げられてエアの足もとに突き立った。驚いて立ち止まった剣士の目に、今度は喉もとに細い投げ短剣を突き立てられている山賊らしい男の姿が目に入る。山賊は首から空気の漏れるひゅうという音を立ててその場にどさりと倒れると、エアの頭上からは美しいエルフ(elf)−森に暮らし風を友とする妖精−の女性が姿を現した。
「私は快風(かぜ)のフィアリア。でもあなたの名前は必要ないわ、のろまな人間の名前を覚えても仕方がないものね?」
突然現れた命の恩人による侮辱めいた言葉に、エアは礼の言葉を言うことも忘れて剣の柄に手をかけて強くにらみ返すと、フィアリアと名乗ったエルフはにこやかな笑みを消さずに頭上に姿を消してしまった。あるいはこの森に暮らしている妖精だろうが、やはり妖精などという輩にはろくな連中がいない!だが今は助けられた自分の幸運に感謝するべきだろう。
思い直して周囲を見まわしたエアの視線の向こう、村の方角から武器を持った一団の人々がゆっくりと近づいてくる様子が見えた。一瞬、腰の剣に手を伸ばし直すが、その中に先ほどの酒場で見た幾人かの顔が混じっていることに気づくとエアは力を抜いて手を放す。どうやら彼らなりに話がついて山賊退治なり娘の救出なりに向かうことになったのだろう、たったいま襲撃を受けたこともあり、エア自身もここに来てまで一人で先に進む理由は見いだせなかった。ガルドは先ほどの剣士がどうやら無事でいたらしいことに軽く安堵すると、やや皮肉な口調のままで同道を申し出る。幼い坊やが無為に命を落とす無謀を救ってやる義理まではないにしても、見殺しにするのはやはり気分のよいものではなかった。
† † †
「ふん、確かにエルフというのは気に入らない連中さ」
結局その日は先を急ぎつつも、一度夜営をして早朝に山賊の根城に向かうべく彼らは話を決めた。火を起こす小さなかまどを掘ると、背負っていた巨大な方盾を地面に突き立てて腰を下ろしたのは、いかめしい鎧姿をした小柄なドワーフ(dwarf)、山を住処として黄金と酒と煙草を愛する大地の小人族である。よくそれを着て休めるものだという重い金属鎧を身につけた彼女は立派な女性であり、フールフール・パトギスタンと名乗っていた。ドワーフにしては大仰な名前だと幾人かは思ったであろう、エア・トゥーレが出会った山賊の斥候とそれを倒したというエルフの話を聞きながら、彼女は悪態をついていた。干した肉を火にあぶりながら、細身の男がその様子を見て小人と妖精が仲が悪いと言われている、その実例を楽しんでいる。
「それにしてもドワーフというのは大足とか鉄の指とか、大抵そんな名前がついているものだとばかり思っていた」
「それは異名を名前にしている連中さね。もっとも、あたしの名前は確かに少しばかり長いがね」
風来坊のバリィ・ウォーグに尋ねられると、小人の女性は豪放な笑みを見せた。バリィもそれを見て鋭い目に胸襟を開く笑顔を見せるが、ふと、その表情が怪訝なものに変わったことを彼女は見逃さない。あんたは何か言いたいことがあるのかね、という彼女の問いをバリィは制すると、今度は周囲に耳をそばだてる様子を見せる。その頃には、他の者たちにも森の静けさに混じった生き物の足音とうなり声が聞こえ、彼らの手は近くに置かれている武器の柄に伸びていった。

うぉん、と咆吼とも風を切る音ともつかない音を立てて黒い塊が飛び上がると夜営している者たちに襲いかかる。周囲にはもう一匹の獣の姿、それは狼によく似ていたがそれよりも二まわりほど大きい、魔狼(warg)と呼ばれる生き物であった。その体格と無分別な凶暴さがこの生き物が魔狼と呼ばれる所以であったが、ドワーフの女は手近の盾を地面から引き抜くとそれを力強く振って獣に叩きつける。ぎゃうんと鳴いて飛び退いたところで、すかさず剣を抜いたバリィが獣の背に一撃を振り下ろすと、ごきんと音を立てるが魔狼は猛り狂うままに牙からよだれを飛ばして暴れまわる。更にバリィは強引に下から振り上げると、今度は柔らかい腹部に剣が叩き込まれて大柄な獣の身体は吹き飛ばされた。
「獣であっても牙を抜けば容赦はしない」
首をめぐらせるバリィの目に、治療師の女性をかばって立つ蛮人の姿が入る。ウェイ・ラスローは背負っていた大剣の包みを解く暇もなく、半裸の肌に幾度か爪を立てられて幾筋かの血を流しながら、献身的な蛮人はベレトの前に立ちはだかると彼女に傷一つ負わせようとはしない。治療師のベレトには巨大な獣を相手に立ち回るような膂力はなく、彼女自身もそれを知っていた。
すかさず滑り込んできた「白の狩人」ガルドが飛び上がった獣の腹部に正確な刃を突き刺し、離れたところで矢継ぎ早に足を切ると動きの鈍った魔狼に、二本の短いが幅の広い剣でつぎつぎと突いてようやくこれをしとめる。短い騒動が終わると途端に周囲には先ほどまでの静けさが蘇り、ベレトが一息をつくと小さな騒々しさが生まれていた。
「咬まれなかったようだが病がないとも限らん、すぐに治療しよう」
「なに、これも傭兵の仕事だ」
互いに感謝の言葉を出さないのは、今さらそれを告げるまでもないからであろう。手早い動きでベレトは腰の袋から出した葉をもむと、ウェイの傷跡に麻紐で貼り付ける。あとは起こしていた火で水と薬草を煮て、一度傷口を洗えばすぐにふさがるであろう。蛮人の頑健さはその外見のみではなく、彼らは伴に旅をしていただけあって各々の役割を充分に心得ているようであった。
† † †
森の奥に据えられていた、山賊の根城ではすでに襲撃を警戒する体制が整っている。彼らにすれば斥候として出していた仲間が帰っていないのだから当然だが、夜を徹した警戒に多少の疲労の色は隠せない。顔のいぼをぼりぼりと掻きながら、粗暴で不機嫌な目をして周囲をうかがっていた見張りが叫び声を上げると同時に、山賊たちの視界に数人の武器を持った一団が近づいてきた。六人ほどの先頭に立っているのは半裸の蛮人と厳めしい鎧に身を包んだ小柄で頑健な姿の二人である。構えていた方盾をどっかと地面に突き立てると、空気を割るような声を張り上げたのは小柄な鎧の姿であった。
「山賊共を退治に来た!山を恐れる貴様らが、生きてここを出られるとは思うなよ!?」
強硬で強圧的な恫喝はあまりに危険ではないだろうか。背後に控えていたエアは自身も強硬な性格を持っているつもりではいたが、まるで人質の存在など知らないとでも言いたげなドワーフの様子に一瞬、不安を覚えた。相手もそう思ったのであろう、石造りに丸木であちこちを補修した砦の奥から、後ろ手に縛られた娘を連れ出すと、その首を押さえつけるようにして前に出る。だが、連れ出された娘の姿を見てもドワーフの女と蛮人は武器を手に直立した姿勢を変えず、眉一つすら動かす素振りを見せない。その様子を不愉快に思いながらも、山賊は訛りのある、ざらざらした耳障りな声で恫喝した。
「おおがた村に雇われた命知らづだろうが、こっぢには人質がいるぞ!大人じく武器と金目の物を置いて帰るんだな!」
「山賊共を退治に来た!生きて出られるとは思うなよ!?」
「うおおおおーっ!」
聞く耳も持たぬとばかりに、ドワーフと蛮人が声を張り上げる。あまりの状況に人質の娘は気も狂わんばかりの様子だが、彼らの粗野な外見と言葉すら通じぬのではと思わせる態度が山賊の不安に拍車をかけた。相手は単純で交渉ができる相手に見えぬ、しかも人質を殺せば替わりはいないのである。元来気が長い向きでもない山賊たちは、たまりかねて武器を抜くと手下に呼びかけた。
「・・・ええい!やっぢまいな手前ら!」
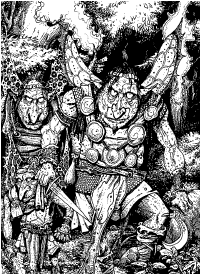
ウェイにとっては願ったりである。自分の外見を最大限に利用してのハッタリだが、これで人質の居場所を探す必要もなくなった。後は山賊を一人でも多く引き寄せて迎え討つことだとばかりに、蛮人は威嚇するために大剣を派手に振ると肩の上に担ぐと、隣りに立っていたフールフール・パトギスタンも自分の背より巨大な剛弓を立てて長い矢をつがえる。たくましい筋肉が盛り上がり、引き絞った弓が放たれると弓というよりも弩の勢いで飛んだ矢が山賊の胸板を一撃で貫いた。
どさりと倒れる仲間の姿に怯んだ山賊にすかさず、他の者たちも武器を手に左右に広がる。風来坊のバリィは長い剣を抜き放ち、エア・トゥーレも鋭い刃を振りまわしているが山賊も数が多く戦意は旺盛であって、容易に打ち倒すという訳にはいきそうにない。
「だが、最早語ることなどない。往生せい!」
そう言って長く固い棒を突き出したのは、ウンスイと名乗っていた異国の男であった。奇妙な黒い僧衣をまとい、頭には草の篭か笠のような帽子をかぶっている。重い鎧も鋭い武器も持っていないが、重い棍棒を軽々と振りまわして俊敏に動きまわると、力強い一撃で相手を殴り倒していく様が周囲の目を引いた。
その異国の僧の隣に立っているのは大木を思わせる丈高い剣士、ハインツ・シュタインである。抜かれた平剣を地面に垂らすように立っているが、目の前に手斧と丸盾を構えた山賊が近寄ってくるやその剣先がゆっくりと動き出した。大きな動作で一息に振り上げる、次の瞬間には先ほどまでとは比べものにならぬ俊速で剣が振り下ろされて、どかんと地面を砕く音に続いて山賊の左肩から先が地面に落ちていた。
「眠れ・・・永遠に」
自身も眠っているかのような細い目で、長身の剣士は呟くと次の獲物に身体ごと向け直す。ドワーフの女はすさまじい一撃で賊の一人を倒していたものの、その後は囲まれて苦戦しているが頑強な鎧と隣りに立つ蛮人が守っているおかげで充分に耐えているように見える。更に目を凝らすと、砦の近くでは山賊に組み伏せられて武器を取り落とし、今にも鎧をはぎとられようとしている剣士の姿が目に入った。
「くっ・・・この!ボクは・・・」
「伏せてろ!」
鋭く叫びながら大股に駆け出すと、伸び上がるようにハインツの大振りの刃が水平に打ち出されて賊の首から上を吹き飛ばす。見おろした視線の下では、激しく飛び散る赤いしぶきと衝撃に目を見開いていたエアが取り落とした剣に手をかけようとしていた。ハインツは細い目で一瞥をくれただけで、次の相手を捜して立ち去ってしまう。わずかの間に二度も命を救われた情けなさに、エアは屈辱にまみれた顔をして一度首を振ると、ただ自分が頼るべき剣を握りなおしていた。
† † †
賊の首領は争いが始まるとすぐに、人質を連れて根城の奥に逃げ込もうとしていた。裏手から逃れることができれば、人質を盾に姿をくらませることも無理な話ではないだろう。だがこれあるを予想して幾人かの仲間と裏にまわっていたベレトは、護身用の短い槍を抜いて潜んではいたが、相手の足を止めることができるかどうかは心許ない思いである。何しろ、彼女自身は一介の治療師にすぎないのだ。
「まあ、やるだけやってみるか」
彼女は自分の目的が足止めと時間稼ぎにあることを承知していた。治療ではなくまじないに用いる薬草や鉱石の中には、迷信深い者には魔法にすら見えるほどの不可思議な効果をもたらすものもあるのだ。ベレトは腰の袋から出した黄色い粉を一息吸うと、気を奮い立たせてから人質を連れて逃げる首領の前に立ちはだかり、あえて高圧的に娘を放すように告げる。もちろん、相手がそんな脅しを聞くとは最初から思っていないが時間を稼ぐのが彼女の役目であった。
「どきな!娘とお前ざんを殺じて逃げる時間ならあるぞ!」
その言葉に嘘はないだろう、相手は少なくとも自分より腕が立つように見えた。だがベレトにはここで誰を殺すつもりも殺されるつもりもない、彼女はおもむろに腰の薬袋から茶色の粉をにぎりしめると、それを周囲にばらまいたのである。それは激しく胞子を飛ばすことで知られている、茶苔の粉であった。せき込んだ山賊の首領が屈み込んだ瞬間に、ベレトは人質の手を取り強く引き寄せる。しばらく、呼吸を弱くする薬を嗅いでいた彼女は周囲を飛び交う胞子の中で多少とも早く動くことができた。だが男は人質を奪われるくらいならと、闇雲に蛮刀を振るとベレトの背に向けて振り下ろす。逃げられないかと彼女が娘に覆いかぶさったとき、白い影が躍り上がって山賊の刀を弾くと続けて一撃、鳩尾に剣を打ち込んでから右手のもう一撃を左あごの下に突き上げた。ごきりと音がして、首を折られた山賊の首領はその場にくずおれる。
「・・・危うかったとはいえ、やれやれ上手くいったようだ」
「まあ、娘には災難だが無事なだけよしとしよう」
胞子を吸わないように顔に巻きつけていた布を外して、ガルド・ミラが言うとベレトは倒れている娘を介抱すべく、薬草や治療の道具を並べはじめている。いつの間にか、一陣の風が流れると周囲に立ちこめていた胞子は吹き払われていた。その頭上、丈高い木々の高くに美しいエルフの女性の姿があることに彼らは気づいていない。
「ふぅん・・・」
わずか一日程度の間に、ある者は争いある者は恫喝し、またある者は人を救う。野蛮そうな人間や下品でちびたドワーフも混じっていたが、好奇心に満ちた視線を向けながらフィアリアはその騒々しさに興味を覚えていた。
† † †
山賊にさらわれた娘を救い出して、意気揚々と村に帰還した彼らを村人は総出で迎え入れた。中には不本意な戦果に不満げな顔をしている者もいたが、山賊は退治され娘も救い出されて村長も商人も機嫌がよいのは当然であろう。当の娘にとってはあまり思い出したくもない救出劇だったらしく、それでも命の恩人たちへの感謝が否定されることはない。
即席の英雄たちを祭るささやかな宴の中で、豪放なドワーフの女が混じっているのを見た一人の商人が声をかけた。
「貴女はドワーフの方ですな。そういえば、どくろ沼の近くに<豚と盃>という店がありましてね、そこの店主がやはりドワーフの女性なのですがご存知でしょうか?」
どくろ沼といえば恐ろしい怪物共の住処であり、足を踏み入れれば方角すら見失う暗黒の沼地として知られているが、ここを通り抜けることができる腕の立つ者を探しているらしい。気がつけば、この恐ろしい沼地の話を聞こうと集まる者の数が、一人また一人と増えていった。
...TO BE CONTIUNUED
>第四の石版の最初に戻る