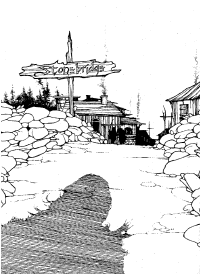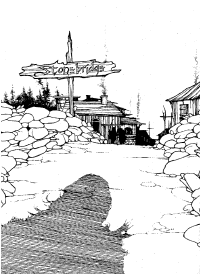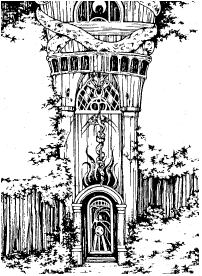SCENARIO#3
王国アーガイルの北につながる要路を遮っている、どくろ沼を抜けてウィロウベンドの町に入る。不気味な霧に覆われた危険な沼地を初めて踏破した彼らを迎えて、町は沸き返っていた。貧窮するアーガイルにとって交易を助ける道の発見は喜ばしいことであり、それはウィロウベンドにとっても発展への足がかりを意味している。白の狩人ガルド・ミラが手にする羊皮紙に描き込まれた道筋はやがて広がってそれが沼地を覆う霧を晴らしていくのであろう。
ウィロウベンドに滞在した彼らはアーガイルから遣わされた急使に会うと報酬を受け、引き替えに沼地の道筋を描き込んだ地図を渡す。どくろ沼の南にある<豚と盃>亭を訪れる者もこれからは増えることになりそうだ。ドワーフ(Dwarf)の銘酒「脳喰らい」も手に入れやすくなるわい、とはある女ドワーフの言葉である。
「それで、あたしの話なんだけどさ・・・」
料理と煙草から上る煙に曇る酒場の一角で、串焼きにした炙り肉を頬張りながらアン・ラッキーは声を落とす。猫のような耳と尾を持つ、キャットテイル(CatTail)の妖精族である彼女は沼の北岸で化け物に襲われていたところを助けられていたが、彼女の話によれば東にあるドワーフの町ストーンブリッジで、高名な王ジリブランの持つ魔法のハンマーが盗まれたというのである。ストーンブリッジのドワーフはグランドピアンの山脈につながる、山岳地帯に住むトロール族(Troll)とは伝統的に仲が悪く、ために野蛮な彼らの進攻からミッドランドを守る重要な拠点とも見なされていた。
十日ほど前の満月の夜のことである。ダークウッドと呼ばれる暗い森の近くで焚き火を起こし、シープスキンの毛布にくるまろうとしていたアン・ラッキーの心に緑色の顔をして叫んでいるトロールたちの姿がちらつく。突然、左側の茂みにぎこちない足音がして、小枝がパチンと折れるような音が聞こえた。うめき声と地面になにかが叩きつけられる鈍い音が続き、やがて苦痛で顔を歪めた髭もじゃの年老いた小男が姿を現す。
(絶対に手に入れるぞ!絶対にだ。あー!ハンマー。ジリブラン様よ、このビッグレッグが御前にハンマーを運び届けますぞ、きっと・・・)
年老いたドワーフの腹部には二本の石弓の矢が刺さっており、矢に塗られた毒のせいで頭がおかしくなっているようだ。猫妖精の娘は倒れた男の耳元で彼の名前を呟くと、まばたきもせずに目が見開かれて激しく叫び始めた。やがて苦痛が少しやわらいだのか、うわごとがおさまると小声で話し始める。
(友よ、我々を助けたまえ。ジリブラン様にハンマーを・・・ハンマーだけが我々をトロールから救ってくれるのだ。我々はハンマーを求めてダークウッドへと行く途中だった。しかし、トロールに待ち伏せされてしまった。他の連中はみんな殺された。どうかお願いだから、ハンマーを見つけ、我がストーンブリッジの領主、ジリブラン様のもとに届けてくれまいか。必ずや報われること大であるから・・・)
ビッグレッグは言葉を続けようと口を開けるが、最後の息しか漏れてこない。アン・ラッキーは彼女の名に劣らぬ不運なドワーフの腰から金貨の入った袋を取り上げると考えを巡らせた。享楽的なキャットテイルにドワーフの町を救う義理などある筈もないが、うまく立ち回れば儲け話になるかもしれない。
話を聞いて木製のジョッキをテーブルに置いたのはバリィ・ウォーグである。眼光が鋭く人を寄せつけない雰囲気があるが、妖精の娘は自分を助けてくれた細身の男に興味を持ったのか、あるいは護衛にでもするつもりかウィロウベンドでも彼の側を離れようとはしなかった。
「だがストーンブリッジの王ジリブランといえば、アーガイルの最も賢き魔女アルガラドに仕える剣士シグルドソンとも親しい仲であると聞く。この際にかの地に行くのも悪いことではあるまい」
荒事に身を投じる者は自分を取り巻く状勢に敏感でなければならない。一度アーガイルに手を貸したのであれば、その益になる行動は彼ら自身にとっても益になるであろう。
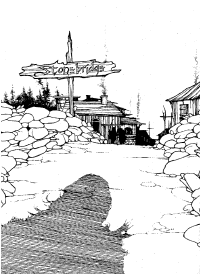
道は野原を抜けて、きれいな川にかかっている石の橋まで続いている。橋の向こう側に小さな屋敷と木造の小屋がいくつかあり、道標には「ストーンブリッジ」とある。橋を渡ったガルドは真っ白な髭を長く伸ばした二人のドワーフに会うと、ジリブランのもとに連れていってくれるように頼んだ。ガルドの後ろを歩いていたエア・トゥーレは周囲に目をやりつつ、小さな落胆の息をつく。少年めいた小柄な剣士はいずれどこかの王家に召し抱えられて正騎士になるのが夢であり、ガルドに従ってストーンブリッジを訪れていたが、素朴な町に暮らすドワーフに仕える騎士というのはあまり様にはならなそうだった。
石造りの館に続く石段の上り口に到着すると、館の外にしつらえられた飾りのついた木の玉座に座っている、長い髭をたくわえた老人を目にする。王冠こそいただいているものの、すこぶる苦しそうで、両手で頭を支えていなければならないほどだ。野蛮なトロールに鉄槌を振るうドワーフの王、ジリブランの名は遠くアーガイルの地にも届いていたが、目の前の老人がそのジリブランであるとは一見して信じ難い。王はその姿に似合う、弱々しい口調で来訪者に向けて語り出した。
「客人よ・・・白の狩人の名はこの石橋の町にも聞こえておる。丘に住み国を脅かすトロール族と戦うために、我が民を守る象徴であった戦いのハンマーが奪われてしまった。暗い森に住む闇エルフ(DarkElf)の飛ばした鷲が我らからハンマーを奪ったのだ。だが鷲は死の鷹に襲われて暗い森に落ちると、ハンマーの行方も失われたと聞く。白の狩人よ!その鷲鷹の如き目に助けを求めたい、暗い森に落ちたハンマーを見つけ出して、我らの戦いの心を取り戻して欲しいのだ」
王の懇願にガルドは丁重に傅く。アーガイルのみならず、ドワーフは人間の友邦でもあるのだ。だが戦いの士気をただ一つのハンマーに求めるドワーフの考えがエアには理解できなかったらしく、同道していたマキという小柄な女戦士もそれに同調する。偉い人に話を聞いた方が早いと思い、ストーンブリッジを訪れていたものの目の前の弱々しげな老人は彼女の期待に反する存在であった。ドワーフの持つ武器への信仰を彼女たちは理解しておらず、賢明にもその思いを口に出すことは自重するが態度から伝わるものがあったのであろうか。ジリブランは不機嫌な面持ちのままで客人をもてなすように告げると館の中に姿を消してしまった。ともあれ、彼らはドワーフの魔法のハンマーを探し出さねばならない。
† † †
ダークウッドと呼ばれる森は、ストーンブリッジの南に川を挟んで広がっている。賢人によればかつては一の森と呼ばれた古代から残る森林の一部であって、木々は高く茂り、周囲は深い沈黙に満ちていて鳥や動物たちの鳴き声はまったく聞こえてこない。失われたハンマーを探すのであればそれが落ちた森の住民を探したほうが早いであろうと、幾人かはガルドたちよりも一足早く、昼なお暗い森へと足を踏み入れようとしている。
「なんて邪な気配に満ちた森・・・」
不機嫌そうな声でエルフ(Elf)の女性が呟く。森の妖精族である快風(かぜ)のフィアリアの目には、ダークウッドと呼ばれるに相応しい木々の様子が忌まわしく感じられて仕方がなかった。この森には彼女の信じる森の神エリリア、人間の言葉でガラナと呼ばれる女神の祝福はもたらされてはいないようだ。
だが、フィアリアの不機嫌の理由は他にあったかもしれない。本気かどうかは分からないが、ドワーフの王になど会いたくないという彼女はストーンブリッジには赴かず、森へと足を向けていたが、その彼女に同行していたのがよりにもよって彼女の嫌う蛮人やドワーフたちであったのだ。もう一人、ウィロウベンドから連れだっているサヴァンという男にしたところで彼女の好む類とは言い難い。
「ご不快な様子ですが、私で良ければ君の・・・」
皆まで言わせず、フィアリアは森へと足を進める。胡散臭い髭をはやして片眼鏡をかけた怪しげな男は小さく肩をすくめると、いささかわざとらしく厚いマントを翻した。エルフほどではなくとも森の中で足取りは軽く、尋常な者ではないように見えるがそれと好みは別の問題である。だが本来荒事が得意ではないフィアリアとしては、このような場所に一人だけで入り込めるとは思っていなかった。
狭い道を歩いていると、先頭を歩くフィアリアの耳に小枝がパリパリと鋭く折れる音と低くささやいている声が聞こえてくる。細い剣を静かに抜き、後ろに続いていたサヴァンたちも集まると大きな樫の木を背に注意深く身構えた。向かい側の木の背後から四人の男と緑のうわっぱりを身につけた女の一味が出てくる。五人とも手に斧と剣を持ち、兇悪な表情を浮かべている。若い女が一歩前に進みでて彼らの領地に侵入していることを告げると、通行料として所持しているものを全て置いて行かないとどんな結果になるかわからない、と脅迫した。
返事のかわりにつばを地面に吐いて、無言のままで長い弓を引きしぼったのはフールフールである。ウィロウベンドを訪れていた東方の商人から買ったワキューという、上下非対称の剛弓から放たれた矢は、ドワーフ女の力でまっすぐに飛ぶと盗賊の一人の胸に突き立つ。すかさず雄叫びを上げて、ウェイ・ラスローが大剣を振り上げた。半裸の戦士は自分がどのように人に見られているかを充分に心得ており、板金に身を固めたフールフールと野卑な蛮人がどれだけの威圧感を与えるかを知っている。大薙ぎの剣が二人目の盗賊を地面に叩き潰すと、蛮人は大きく叫んだ。
「恨むのはなしにしてくれよ!」
仲間の野卑な戦い方に嫌悪感を感じつつ、フィアリアは一歩下がると森に強風を呼び込もうとする。だが、盗賊の女は腰に吊していた投げ網を放ると風との交信を試みていたエルフに頭から被せてしまう。森の戦いでエルフが恐れられることは自明であり、すかさず男の一人が剣を構えると動けぬ彼女の金髪を血と脳漿で赤黒く染めるべく振り下ろした。鈍い音が響き、エルフの娘はあっけない死を覚悟したが彼女の頭に叩きつけられた剣はゴムのように曲がると弾かれてしまい、そのまま垂れ下がる。驚いている盗賊に向かい、大仰にマントを翻すと見栄を切ったのはサヴァンであった。
「棒を、ゴムに!」
魔法使いの力はそれを知らぬ者には人智を越えた脅威となる。怯んだ盗賊をウェイの大剣が叩き潰すと、生き残った盗賊たちは恐慌を来して逃げ出してしまった。フィアリアはようやく網を抜け出すと、屈辱に耐える思いで唇を咬む。人間と会うようになって以来、自分が不機嫌に顔を歪める機会が増えていたことも彼女には不快だった。
† † †
森の外縁に近い場所を歩いていたバリィは、道から外れたところに目立たぬように立つ石造りの塔の家を見つける。彼の後ろには相変わらずキャットテイルの娘が親しげな様子でつき従っていた。巨大な樫の木の扉を構える石造りのアーチには大きな真鍮の鐘が吊り下げられており、バリィが鐘を鳴らすと大きなボーンという音がダークウッドの深い沈黙を破る。風来坊の剣士と猫妖精の娘の後ろに控えていた、ベレト・エカリムがびくりと肩をふるわせた。
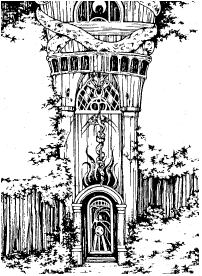
扉のところで不安な気持ちで待っていると、塔の上から降りてくるゆっくりとした足音が聞こえる。扉についている木製の小窓が開いて、二つの目が覗いた。おまえさんたちは誰だという尊大な声が聞こえると、ベレトはドワーフの戦いのハンマーの行方を探していると告げる。興味を持ったのか、きしむ音を立てて扉が開くとボロ服をまとった老人が姿を現し、らせん階段を上がるように促した。
「へえ・・・」
思わず感嘆の声が漏れる。老人に続いて足を踏み入れた、塔のてっぺんにある大部屋には戸棚や食器棚、ガラス棚が壁にびっしりとならび、ビンや壺、武器に防具、そのほかあらゆる種類の奇妙な骨董品がつまっている。偉大な魔法使いヤズトロモと名乗る老人はバリィから不運なビッグレッグのいきさつを聞くと、顎髭をなでながらゆっくりとしゃべりだした。
「ストーンブリッジに住むドワーフが、古くから伝わる戦いのハンマーをなくしてしまったことは聞いている。投げれば持ち主の手に戻ってくる魔法のハンマーだが、ドワーフというものは武器に対する信仰をことのほか大切にするものだ。あれがないと、あの国の王は民を奮い立たせることができないのだよ。
噂では暗い森に落ちたハンマーは二人のゴブリン(Goblin)に拾われたらしい。どちらが持っていくか決められずに何時間も取っ組み合いをした挙げ句、二人はハンマーの頭の部分から柄の部分がはずれてしまっているのに気がついた。もめ事は解決して、一人が頭、一人が柄の部分を持っていくことにした。だからおまえさんたちは、ハンマーの頭と柄と両方を手に入れなきゃならん。つまり、厄介事は二倍ということになるな」
そう言いながらも、ヤズトロモはストーンブリッジのドワーフを案じているのか彼の持ち物から何かひとつだけ好きなものを持っていってよいと伝える。アン・ラッキーは投げ上手の手袋を、バリィは鼻用フィルターを受け取った。ベレトは植物封じの薬と書かれているビンを手に取るが、手を滑らせると床に落としてビンを割ってしまう。ヤズトロモは眉をしかめてから別のものを選ぶとよい、というがベレトは薬師として落とした薬の価値を知っており、謝辞を言いつつもそれを辞退することにした。
塔を離れて暗い森に分け入ったバリィたちは、やがて狭い道を抜けて大きな樫の木が立つ空き地へと足を踏み入れる。そこでは乱戦があったらしく、地面には血で汚れた跡がありウェイやそれに合流したらしいガルドたちが集まっていた。互いにジリブランやヤズトロモからの話を聞くと、ハンマーを手に入れた二人のゴブリンやそれを奪おうとした闇エルフの後をそれぞれが追うことに決める。分かれたハンマーを追うのであれば捜索の手も分けた方が良いであろう。森に親しいガルドやフィアリアが見るには森はあちこちが狭く、大人数で動くことはかえって待ち伏せの餌食になりやすく危険であった。
「エルフを追うならエルフ娘がいた方が良いかもしれんな!」
フールフールのその一言で、フィアリアはハンマー探しの一行に加わることに決める。闇エルフと一緒にされることはエルフにとっては最大の侮蔑であり、先の失態がなければその場で無礼な酒樽女に矢の一本でも突き立てていたかもしれない。ハンマー探しの者たちは更に二手に分かれて二人のゴブリンを追う。バリィとそれに従うアン・ラッキー、それにハインツ・シュタインを連れた三人はまっすぐに北へ向かう道を選んだ。道の両側に太陽の光が何本もの筋となって、木々の間から降りそそいでいる。木々がまばらになってきて、道幅も広がり、右手の奥まったところに洞穴の入り口が大きく見えてきた。
慎重に洞穴の中を覗き込むと、水を入れたかめを手に持ち、材木を縦横に組み合わせてつくったオリに向かってゆっくりと歩いているオーガー(Ogre)の巨大な姿が目に入る。彼は毛皮に身をつつみ、ベルトに石の棒をさしている。オリの中では小さな怪物がとび跳ねているようだ。
気付かれないように足音を忍ばせながら、アン・ラッキーはザックに手を入れると、紫色の絹の手袋を引っぱり出す。ヤズトロモからもらっていた投げ上手の手袋をはめてから、かがんで大きめの岩石を拾い上げると、あらん限りの力を込めて、オーガーに向かって投げつけた。岩石は矢のように飛んで側頭部をとらえ、化け物は意識を失ってひっくり返ってしまう。オリの中の怪物が前よりもいっそう狂ったように跳ねまわった。
「やったあ!」
喜びをあらわにして猫妖精が声を上げる。すばやく化け物を縛り上げて、オリに目を向けると囚われているのは小さくてがっしりした人型の怪物、ゴブリンであることが分かった。その首のまわりに、黒光りする棒が皮ひもでぶら下がっているのを見て、もしやと思いオリの鍵を壊して開けると怪物は飛び出して、金切り声を上げて突進する。
この狭い場所で大剣が使いづらいことを承知していたハインツは、長身をかがめるようにして手早く短刀を抜くと、細い目をいっそう細めてからひととびに怪物を組み伏せてしまった。
「無用な殺しは好まんが・・・」
そう呟きつつ、ためらわずに怪物ののどを裂くと気の狂ったゴブリンの亡きがらにかがみこんで、首にぶら下がった棒を調べてみる。一方のはしにGの文字が刻印されており、失われた戦いのハンマーの柄に違いなかった。他にめぼしいものは見つからなかったが、それでも彼らは勇んで洞穴を外に出る。
† † †
戦いのハンマーの行方を探している間、それを奪うべく鷲を飛ばした闇エルフを探すためにウェイやフールフールたちは暗い森の下生えを踏み分けている。闇エルフは暗黒の魔人マイユールを信奉した挙げ句に追放された古代のエルフ族の末裔であり、今では森を離れて地底に潜む間に別の種族と化してしまっている。広大な地下帝国の出口の一つがダークウッドの周辺にあるらしく、善なるストーンブリッジが野蛮な丘トロールの手で陥落すれば彼らにとって都合がよかった。
「だが、闇エルフとは恐るべき者どもであっても数は決して多くない。実働は数人もいないだろう」
闇エルフの力は数にはなく、エルフと起源を等しくする弓の技と歪められた暗黒の魔法の力である。獣を操り、姿を隠して毒の矢を放つ、闇エルフの襲撃部隊は奴隷や財宝を奪うためにときおり地上に現れては、誰もが気づかぬうちに目的を果たして地底に消えてゆくのだ。
彼らが人数を分けたのには理由がある。ストーンブリッジにハンマーを取り戻す試みを闇エルフは望まぬであろうし、人数が減ればそれだけ襲撃もしやすくなるのだ。当然、ハンマーを捜索に出た者が襲われる危険も増すことになるが、正直なところそこは賭けであった。闇エルフはドワーフやふつうのエルフをことのほか嫌う、フィアリアがこちらにいれば確実に彼らの標的になっていたであろうが、このときは鈍重なドワーフを的にすることを選んだようだ。ひゅうんという音が聞こえると飛んできた矢がフールフールの肩に突き立つが、分厚い鎧はドワーフの命を奪うにはいたらない。

道は大きな丸石や岩のあいだを抜けて、丘を下って北に走っている。丸石のかげから姿を現した数人の闇エルフたちは毛皮を身につけており、髭も髪も伸び放題だ。彼らは獲物の命を奪えなかったので、怒り狂ってとんだり跳ねたりする。だが互いの距離は遠く、続けて矢をつがえると弓を引き絞った。剛毅なドワーフ女も東方のワキューを構えるが、エルフに弓で対抗するなどドワーフらしく正気ではない行為だと闇エルフたちは嘲りの表情を浮かべる。
「この弓から逃れられるのなら逃れてみるがいい!それが大地の裁きだ!」
放たれたフールフールの剛弓は一本を放てば一人が、二本を放てば二人の闇エルフが倒れる。今更ながら相手が尋常な弓の使い手ではないことを悟った闇エルフは岩かげに身を隠すが、すぐにエアとマキの二人の剣士が駆け出した。エアはウィロウベンドで手に入れていた幅広の剣を振りまわして切りかかる。
「臥薪嘗胆!捲土重来!」
「くらえ、今考えたあたしの必殺技!」
続いて切り込んだマキも巨大な斬馬刀を振り回すが、動きが早く身を隠しながら手早く弓をつがえてくる闇エルフをうまく捕まえることができずにいる。一歩下がっているベレトは自分の身を守るのに手一杯という様子だが、彼女はそれが自分の役目であることを知っていた。ウェイが控えてフールフールとベレトの盾になっている間に、ドワーフ女の弓から放たれる矢が闇エルフを追い出すとエアの剣がとどめを刺す。暗黒に潜む妖精が全て倒されると、周囲にはダークウッドの静けさが戻ってきた。ベレトはいつものように荷物から薬草を出すと、もみほぐしてからフールフールの肩の傷に貼りつける。この森から邪な混沌の気配を断ち切ることはできずとも、これでしばらくは平穏になるかもしれない。
† † †
暗い森の中を北に進んでいたフィアリアは、ダークウッドの様子にここは浄化しなくてはいけないと呟く。妖精は自然をもたらす者であり、精霊と交信することによって自然に反するものを癒す力を持っているのだ。
「ドワーフはそれを忘れてしまっているけれどね?」
ようやく彼女らしい高慢な軽口が戻ってきたようだとガルドは苦笑する。しばらく進むと木々の合間にツタがからまる苔むした石造りの建物が見えた。窓のない、小さな建物には石の階段が口を開けており、暗黒の深みに向かって続いている。だがガルドやフィアリアの目は、地面を引きずり何者かがここに出入りした痕跡があることを見つけていた。
一歩一歩踏みしめるようにして注意深く階段を降りはじめる。だんだん暗闇に目が慣れてきたので、階段のいちばん下にあるものの形がはっきり見えてきた。天上の低い真四角の小さい部屋の床にはほこりが一面に積もっており、どこもかしこもクモの巣だらけだ。部屋の真ん中に石でできている箱のようなものがあり、その箱の上には大きな平べったい石板が置かれている。ざらざらした石の壁の一つに小さなくぼみがあって、そこに立てられているろうそくに火をつけると部屋じゅうに不気味な影が投げかけられた。
その黄色い光の中で、箱は石棺でありのせられた石板には年老いた男の顔が彫られているのが分かる。周囲に目を巡らせると、ほの暗い影から骸骨の足がとびだしていた。
散乱している骸骨は小さく、頭蓋骨からは鋭い歯が突き出している様子を見ると、ゴブリンのような小さな怪物の骨であるに違いない。いくつもの傷がある骸骨の様子を見て、顔をしかめたサヴァンがかなりまずい状況ですな、と呟くとガルドが同意した。
「納骨堂・・・だがあれはここに納められた骨である訳がない。何かに襲われた犠牲者だ、それもここに連れ込んだ誰かの手によってな」
その言葉が終わるより早く、ゆっくりと石棺のふたが持ち上がると、恐ろしいことに腐りかけた死体が棺桶から起きあがり、侵入者の姿を認めて両腕を広げにじりよってくる。はるかむかしに暗黒の使徒たちが築いた不潔な納骨堂にある、まだ死にきっていない呪われた化け物の棺桶のふたが開いたのだ。
不死の化け物が足を踏み出す姿を見て、とっさにとびすさったガルドの目に、石棺の中に転がっているGの文字が刻印された黒っぽいかたまりが目に入る。
「やれやれ、これでは引く訳にもいかぬか」
転がっている哀れな骸骨の正体こそが、ドワーフのハンマーを手に入れたゴブリンであったのだろう。屍鬼(Ghoul)は汚れた歯をむきだしにして、黄色く鋭い爪を立てると緩慢な動きでガルドたちに襲いかかってきた。不死の化け物がもつ毒の爪と歯は、傷つけたものをしびれさせる力を持っている。そうして動けなくした犠牲者をゆっくりとむさぼるのだ。
屍鬼の動きは緩慢だが、化け物は切っても叩いても死なぬから不死なのである。短い剣を二本抜くと手早く切りつけるが、屍鬼の腐りかけた身体には堪えたふうもない。地下にある狭い納骨堂の中ではサヴァンやフィアリアも自由には動けず、目指すハンマーは化け物の背中にあった。
フィアリアはドワーフのように下品な行為であるのを承知で、小さく舌打ちをする。彼女の親しむ自然の力も地下の石室には届かないのだ。ゆっくりと振り上げた化け物の爪がサヴァンに襲いかかり、マントの上から引き裂く。傷は浅いが毒が多くまわればすぐにも動けなくなってしまうだろう。一刻も無駄にはできそうにない。
不潔な歯をむきだすと、もう一度爪を振り上げた屍鬼に向かってガルドは体当たりをするようにぶつかり、咬みつかれ引っかかれるのを覚悟で腕を伸ばしてハンマーの頭をわしづかみにする。屍鬼の力は強靭だが、堅い皮の胸あてをめりめりと裂かれながらもガルドは化け物を引きはがす。すべてが手遅れになる前に、目的の物を手に入れて逃げ出す必要があった。
「逃げるぞ!娘!」
自然に反するものを嫌うエルフにとって、不死の化け物はその存在自体が許しがたい。フィアリアは歯がみをするが、これ以上ここに留まればサヴァンやガルドの命がないことは明らかであった。
「・・・火に踊るとかげよ、お前の力を貸せ!」
彼女は火の灯るろうそくに潜んでいる小さな炎のトカゲに早口で呼びかけると、炎の舌の一閃を走らせて屍鬼の顔を焼く。植物をも焼く火はフィアリアが軽蔑する力であったが、その時の彼女はためらうことなく傷ついた仲間のためにそれを用いたのである。
石段をかけ上り、森の中に出ると石造りの建物を覆っているツタに呼びかけて、入り口を塞いでしまう。これでしばらくは化け物も外に出ることはできぬであろう。フィアリアたちは安堵すると薬師のベレトに傷を見てもらうために暗い森を後にする。彼らの目的はストーンブリッジのハンマーを手に入れることであり、化け物を倒すことも森を癒すこともできずとも、代えられぬものがあったのだから。
† † †
ストーンブリッジに戻り、石の橋を渡るとそこには真っ白な髭を長く伸ばした二人のドワーフが立っている。森で受けた傷とボロボロになった服や鎧の姿に興味を示し、くわえている陶器の長パイプで身体に刻まれたさまざまの傷をさしながら、先人の経験を学ばない人間はどうしてこんなことをするのか、さっぱり分からないと言う。ドワーフはことのほか慎重な種族で先人の伝統を重んじる者たちであり、性急な人間の生き方を理解できないでいることをフールフールは知っていたが、フィアリアは皮肉っぽく自分は人間ではないがドワーフに分かってもらおうとも思わない、と考えていた。
石造りの館に続く石段の上り口にある、飾りのついた木の玉座には長い髭をたくわえた老人が腰かけている。まわりにいるドワーフたちはみんな何か呟いたり、ささやきあっているのだが、全員の顔に何かを期待する気持ちがあらわれている。
ジリブランの前に立つと姿勢を正したガルドがザックからハンマーの頭と柄を取り出すと、老ドワーフは目を輝かせ、飛び上がるのだった。その様子は先ほどまでの弱々しさを一片も残してはおらず、剛毅さを全身からみなぎらせて彼らの所属する大地を力強く踏みしめると、白の狩人の手から彼らのハンマーを受け取り、居並ぶドワーフの戦士たちに大声で語り始めるのだ。
「我がハンマーだ!我がハンマーが返ってきた!さあ、皆の者、これでトロールどもと戦うことができるのじゃ!」
ドワーフの群衆がそれぞれに斧と剣、槌を空中にかざして喚声を上げる。その様子にエアやマキは圧倒されていたが、これこそがドワーフの信仰の姿であった。鬨の声を上げて、来るべきトロールの襲撃に備えるべく、多くのドワーフが家々や防柵に戻っていく。
力強い余韻を残したままようやく周囲の高揚感が鎮まると、ジリブランは彼らに救いをもたらした恩人たちに向けてゆっくりと語る。それは王にふさわしい、力と威厳に溢れる言葉であった。
「我らが友よ!これでドワーフは蘇る。聞けば汝らはシグルドソンの居るアーガイルより訪れたとのこと、ストーンブリッジはアーガイルとの変わらぬ友誼を特に汝らに伝えよう。アーガイルの北方からグランドピアンに至る、北の要である我が町が力を得ればアーガイルもより安全になる。
だが汝らよ!勇敢なる者たちよ知るがいい。水晶の洞窟と呼ばれる、グランドピアンにある要塞では最も賢き魔女アルガラドを憎む者、雪の魔女シャリーラが居を構えておる。あの者を倒せばグランドピアンは平穏になり、エディンバラにつながるミッドランドの北方は安定するのだ。汝らは勇気ある者であるか!ならば更に北に向かうがよい、ペン・ティ・コーラが正しき者どもを助けるであろう!」
彼らはストーンブリッジの友邦として扱われ、各人には充分な報酬が手渡される。特にガルドには彼の「白の狩人」の呼び名をジリブランからも称号として与え、そして悪しき者どもの多くを殺したフールフールには「猛女の弓」の名が、ウェイにはドワーフの細工になる金の羽根飾りがついた兜が贈られた。
ジリブランは北方への案内役となる、スタブという名のドワーフを一人呼び出すと、グランドピアンへの道を教えるべく彼らに仕えるように命じる。ストーンブリッジの救い手たちは振り返ると、いまだ周囲に居並んで興奮の余韻を残しているドワーフたちに手を振ってから王の前を辞した。
...TO BE CONTIUNUED
>第四の石版の最初に戻る