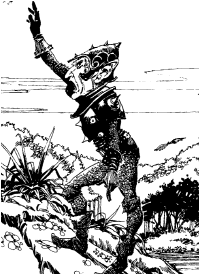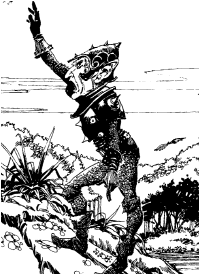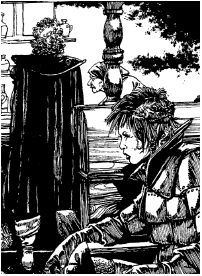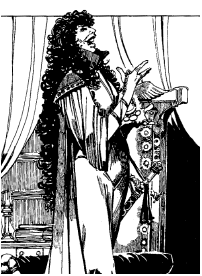SCENARIO#5
グランドピアンの峰を下り、南方へと歩みを進めてウィロウベンドに到る頃には刺すような冷気を肌に感じることもなく、気候もすっかり穏やかになっていた。もはや無用となった重たい毛皮を売り払うとさっそく、ドワーフ(Dwarf)のフールフールはグランドピアンの寒気を吹き飛ばすべく、火と酒を求めて酒場のきしむ門をくぐり抜ける。
ストーンブリッジの王ジリブランのハンマーを奪還し、グランドピアンの雪の魔女を討伐した「猛女の弓」や彼女の仲間たちが立ち寄った頃と比べて、酒場に活況はあるが周囲のささやきにはどこか影があって悲観的にすら見える。その理由は酒場の主人が陰気に語る話によってすぐに理解できた。
「野盗だか何だか知らんが沼の近くに出回っていてね。せっかくあんたらが道を拓いたというのに、最近また旅人の姿が減っちまった。あんたらがアーガイルへ行くなら、以前のようにエディンバラを遠くまわったほうがよほど近いよ」
「なに任せておけ!野盗だろうが化け物だろうが腸詰めのように食ってやるぞ!」
威勢良くエール酒と豚の腸詰めを胃におさめながら、フールフールは声を張り上げている。どくろ沼は王国アーガイルからエディンバラやグランドピアンにつながる要路を遮る危険な沼地として知られていたが、賢明な魔女アルガラドの布告によって「猛女の弓」や「白の狩人」をはじめとする一行が、沼地を抜ける道を発見して以来互いの交易が期待されていた。
英雄の功績が永遠に残る訳ではない。だが拓かれた道がふさがれ、すべては以前と同じに戻るとあれば道を拓いた当人である彼らにとって面白い話ではないだろう。カウンターの丸椅子に腰かけて、「龍殺し」と呼ばれる強い火酒をジョッキに注ぎながらハインツ・シュタインもドワーフ女たちの話に耳を傾けている。他の客たちからは一人離れた場所で、塩気の強い薫製肉をかじりながら酒精に身を委ねていた。耳朶を叩く声でさえ、今の彼には心地よい。
「頼むよ、一昨日も威勢のいい娘さんが何人か連れて沼にいったがどうにも心配でね」
無鉄砲な人間はいつでもどこにでもいるらしいが、彼らにしたところで人のことを言える存在ではないだろう。
ウィロウベンドからどくろ沼を抜ければすぐにアーガイルである。ハインツはフールフールに同調して沼地をもう一度抜ける旨を伝えると、懐から金貨を放り投げる代わりに火酒の一本をしまい込んだ。異境の酒はどこへ行っても好まれるものだろう、アーガイルの酒場での土産になるかもしれない。
† † †
南に向かって伸びる街道は石が退けられて平らにならされており、どくろ沼に向かう道を平坦なものにしている。それはウィロウベンドがこの道にかけている期待を早くも示している姿であり、時をかけてこの道がアーガイルにつながれば沼はよほど安全になるが、今は曲がりくねった細い小径が幾つにも分かれながら沼地を抜けているに過ぎない。旅人が歩くことはできても馬車で抜けることは難しかろう、だが今は、その旅人すら襲われるようになったというのだ。
町を出て二日ほど歩みを進めている、沼の小径は低い場所から霧が立ちこめて数歩先が見えなくなっており、下生えは深く周囲にはガスが瘴気となって立ちこめて水は澱んでいる。数歩を隔てて目に止まる立て札によって、辛うじてアーガイルへの道が判別できる有り様だが一歩を外せばそこに深い穴があったとしても誰も気付かないであろう。ハインツは背の荷物を担ぎなおすと、一度長身を沼地に向けてから細い目をいっそう細めて周囲の様子を窺う。
「さて、強い酒に似合う危難はどこに潜んでいるものやら」
見通しの悪い沼地で手にはたいまつを掲げ、大振りな平剣はいつでも抜けるようにしている。沼地の瘴気だけではない、見通しの悪い霧と肌に感じられる水気を含んだ風が彼らに過剰な警戒感を抱かせていた。
ハインツの隣では、筋骨たくましい蛮人が不機嫌そうな顔で鼻を動かしている。ウェイ・ラスローは野蛮な外見に比べれば文明化された人物とされていたが、これだけは立派な金の羽根兜がかえって彼の外見を粗野なものに見せている。ウェイは長身の背を丸めながら更に鼻を動かし、耳をすませるとかすかな喧噪を感じとる。蛮人が顔を上げた瞬間、彼らに向けて駆け寄ってくる幾人かの人影が目に入った。
逃げる者たちの先頭を駆けている、頭巾のついた外套を頭からかぶっている野馳りめいた姿は小柄な男のようにも見えたが、近付くとそれが女であることが分かる。身を低くして飛ぶように走る、野馳りの足元に短い矢が襲いかかると次々に地面へと突き立った。酒場で話を聞いていた娘とやらであろうか、ウェイは大剣を構えて野馳りを助けるべく前に出るが、鋭い警告はその女の口から発せられた。
「駄目だ!逃げろ!」
すかさず狙いを変えた、霧中を飛ぶ矢が正確に蛮人を捕らえると厚い胸板に突き刺さる。女の声が届いた瞬間、辛うじて眼前に出していた大剣に当たった数本を除く矢がウェイの肩や腕や胸に深々と食い込む。たまらず足を止める蛮人に続けて二射、逃げられぬと悟ったウェイは己の頑健な肉体を信じて身を返すと、背から肩に何本もの矢を受けて針山のようになる。
野馳りの女は自分を救おうとして矢を受けた蛮人をかばうように立ちはだかると、外套を脱いで大きく振り回す。大布で矢をからめて落とすべく、器用に立ち回りながらウェイを守る女の動きは明らかに荒事に慣れているようだ。女に率いられていた者たちも逃げることに懸命で、すでに幾本もの矢を受けて足取りもおぼつかない者も見える。
立ちはだかる女に苛立ちを覚えたか、霧と瘴気に隠れていた小柄な影のひとつが姿を現す。肌の黒い人型の生き物が視界の隅に捕らえられると、フールフールが大声を張り上げた。
「今どきのエルフは森ではなく泥から生えてくるようだな!」
これも大抵のエルフ(Elf)が聞けば激昂する言葉であろう。ドワーフ女が大弓を構えて狙う、黒い姿は闇エルフ(DarkElf)のそれであって遥か古代にエルフの道を踏み外した者たちの末裔である。どくろ沼からは北方に離れた暗い森に見られる闇エルフが、住処を離れたこのような場所にいる理由が分からない。襲い来る矢の数を見ればその人数も一人とは思えず、まとまった数がいるに違いなかった。
襲撃者を返り討ちにすべく東方は八幡に伝わるワキューを構えるフールフールだが、「猛女の弓」と恐れられるドワーフ女の一撃も霧に姿を隠す相手を射抜くことは容易ではない。一人を狙う間に他の矢が襲いかかると、フールフールが着込んでいる厚い綿入れに突き立った。
「加勢しますぞ、ご婦人方!」
片眼鏡に光を返して、フールフールや走りよる野馳りの女と入れ替わるようにサヴァンも前に出ると呪文を用いようとするが、姿の見えない至近から襲う矢をそらすことはできずに、たちまち全身に矢を受けて外套のそこらから血煙を上げる。ほとんどの者たちが傷つき、いずれこのままでは全員が沼地に沈められて化け物の餌になりかねない。状況はあまりに悪く、一歩離れて下がっていたハインツは、しまい込んでいた火酒の瓶を空けると燃える松明をねじ込み放り投げる。
「死にたくない奴は死ぬんじゃないぞ!」
逃げる者たちに遠慮もせず投げられた火酒がエルフたちの足元に落ちると、強い酒が瞬く間に広がり燃え上がった。同時に重い平剣を構えて切り込むと大きく伸び上がって、地面すら割る勢いで振り下ろす。ハインツの一撃が先頭の闇エルフを両断すると威嚇するように剣を大きく横にないでから、ためらわずに振り返って自分も逃げ出した。他の者たちも後を続くようにどくろ沼を北方へと引き返す。
思わぬ反撃を受けたエルフたちは勢いをそがれると、その場にとどまって隊長らしき男の周囲に集まる。風に乗る声がハインツの耳に届く、その言葉は「我らマイユールが信、イシュトラが増すことを望まぬ。マルボルダスが願いを叶えん」というものであった。
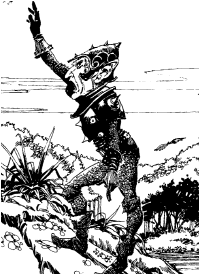
ほうほうの体でウィロウベンドへと帰る。いずれにせよ、どくろ沼の道は闇エルフの手でふさがれてしまいそれを解放することはできなかった。ウェイやサヴァンといった傷の重い者たちが運ばれると、野馳りの女はハインツに礼を告げてから名を告げる。ニン・ガラという女はストーンブリッジよりも更に東方の山野に生きる狩人の部族に暮らしていたが、どくろ沼に道が拓いたことを知って最近、訪れていたものである。
「どうしてあんな所にエルフがいたかって?知らないよ、こっちが聞きたいくらい」
部族でも人を率いる質であったらしいガラは腕っぷしの強い男たちを連れて沼に赴いたが、まさか沼地でエルフに襲われるとは考えてもいない。傷つきながら仲間を逃がすことが精一杯であったし、ハインツたちが現れなければそれすらも危うかったろう。
だが常であれば暗い森の地下に暮らしているか、その周辺に現れることがせいぜいと言われている闇エルフがなぜ一団を組んでこのような場所にいるのか。ハインツが聞いたという闇エルフの言葉を聞いてガラは眉をひそめた。
「イシュトラとマイユールってのは化け物どもが信奉する魔王子の名前、奴らにとっちゃ神様みたいなもんさ。だがマルボルダスってのは知らないね」
† † †
暗い森、ダークウッドに立ち並ぶ木々は傍らを走っている街道にすら、その不吉な影を長く投げかけている。かつて一の森と呼ばれたこの地には遥か古代、エルフの王国に叛旗をひるがえした者たちの末裔が潜んでおり、夜の僕となって戻ることのできぬ地上への憎しみを抱きながら今も地上への襲撃を繰り返している。
堕落したエルフ、夜の僕である闇エルフの襲撃を避けて森に立ち入ることはせずに、その周囲を迂回する街道に身を預けていた一行は、人間にも知られている古いエルフの伝承を思い返している。
「アル・アンワール・ゲリサンを奉じるエルフの王子、邪なケリスリオンが逃げ込んだこの地に闇エルフの帝国が作られたんだよね」
「・・・ふん、そうね」
少年めいた容貌をしている剣士、エア・トゥーレは暗い森にまつわる伝承を思い返しながら、不機嫌そうな顔で同行している快風のフィアリアに気を使うような素振りを見せている。傭兵の生まれであると自称しているエアはその振る舞いに奇妙な品位を感じることも多く、力を重んじても知識をなおざりにすることはない。いずれ事情があるのだろうと言われている娘である。
追放されたエルフの王子が信奉するアル・アンワール・ゲリサンはエルフの言葉で「影の灰色のささやき」と呼ばれ、人間には悪意の神スラングとして知られている神である。ケリスリオン王子は人間や短命の生き物を知るために彼らの神のひとつを知ることによって、彼らの幼稚さを蔑み優れたエルフが世界を統治する専制の夢を抱いたのだ。
「やがて奴らの信仰はアル・アンワール・ゲリサンから今では魔王子マイユールとなった。エルフの伝承は古すぎて人間程度ではどこまでが本当なのか知る由もないとはいえ・・・」
エアの言葉とフィアリアの様子を受けて、肩をすくめるように言うのは今や彼自身が「魔人殺し」と呼ばれるバリィ・ウォーグだが、魔王子とは神話や伝承に現れる存在であって定命の存在が触れることを許されたものではなかった。
いずれにせよ、不機嫌を通り越してそろそろ地面につばを吐きたそうな顔にも見える、フィアリアの様子が何よりも雄弁にエルフの伝承を物語っているのであろう。このエルフ娘もずいぶんと人間に馴染んだものだと、やや苦笑しながらバリィは考えている。以前であれば、姿を現してともに歩くことすらしなかったであろうに。
「だがそれにしても・・・やけに静かだ。前にここに来たときも静かではあったが」
どこか不吉を覚えて、バリィは右手に広がる暗い森を一望する。昼なお暗いダークウッドは沈黙に満ちて鳥や動物の声もまったく聞こえてこなかったが、今はこの森に巣くう邪な者ですら息をひそめているように感じられた。森の生き物が土を踏む音や息づかいの音ですら、耳に届きそうに思えるが生あるものの存在を今はまるで窺うことができない。
静寂を通り越して沈黙に包まれた、ダークウッドに沿ってしばらく街道を歩いた一行はやがて日が暮れると森にほど近い空き地に陣をとって、その日の夜を過ごそうと荷を下ろし始める。できることならば森を離れた場所が望ましいのかもしれないが、無闇に街道を離れることはよほど危険であろう。
空き地はこれまでにも多くの旅人や商隊が夜を明かした場所でそこらには踏み消された燃えさしの残骸が見受けられる。野盗や蛮人であれば火を見て獲物がいることを理解するが、獣であればそれを追い払う役に立つ。
そして人間は火があろうがあるまいが襲いかかってくるのであれば、このような場所で野営をすることに何らの問題もあるまい。穴が掘られて火が起こされると、気の早い者はさっそく携行する固いパンや干し肉を火にくべている。
「ねえ、何か聞こえなかった?」
不気味なほどに静まり返った、ダークウッドの沈黙が耳を鋭くしている。荷を開いていたマキが森の端に目をやると、ゆっくりと姿を現したのは毛並みのよい一頭の狼(GrayWolf)であった。
本来であれば警戒すべきところかもしれない。だが剣士の少女は何を思ったか、懐から取り出した干し肉をひとつまみ目の前の獣に放り投げる。頭を垂れた狼が贈り物を受け取ると、突然森をかきわける音がして緑色のローブを身にまとった男が姿を現した。老人めいて見える男は片手に樫の木の杖を持ち、もう一方の手には銀の斧を持っている。ヤドリギでできた冠が頭上に乗っている。男は横柄というよりも礼儀に無関心といったふうに話し出した。
「人が獣に食を与えるならば人は人ではなく、獣でなければならぬ。とはいえ娘よ、人の流儀であればわしは狼に代わって礼を言わねばならぬのであろう。わしの名はウォードマン、暗い森にもドルイドは存在する」
「あ、ええと・・・」
無愛想で無礼な言葉にマキはあっけにとられるが、すぐに男は相好を崩すと礼を告げた。ドルイドとは自然崇拝をこととする原始的な僧たちであり、たいていは森や山岳で文明から離れた偏狭な暮らしを営んでいる。
火を用いず、文明を批判しているが妖精のように森を育てることもなければ狩りや肉食も平然と行う「動物の王宮の中立」に従って本能のままに生きることを由とする。人間にもエルフにもドルイドの暮らしは奇妙なものに映っていたが、彼ら自身はそうした動物をも含めた、森の世俗にもっとも通じている者たちとして知られていた。
「古くからこの地には森を育てるエルフがおり、樹人がいたものだ。だが地下に暮らすエルフもいる。昔むかしのことだ。この森で彼らはひとつの首飾りをつくった。この首飾りがあると邪な使徒たちはいつの日か、彼らの主人をこの世界へとまねき出すことができるというものだ。だがエルフにはその力がなかった。彼らにはもうケリスリオンはいなかったからだ。だがあるとき、彼らのもとを一人の天才が訪れた。その者の名はエーレン、嵐の子エーレンだ」
熱っぽい視線でドルイドは語る。かつてはこの暗い森でさえドルイドが暮らす動物の中立は保たれていた、だが今のダークウッドは彼に警鐘を鳴らす充分な理由を与えている。
「エーレンは幼い子だった。その子は森の中を半リーグほど入った雪の吹きだまりの中に捨てられていた。その夜は何百年に一度というひどい冬の真っ最中だった。その夜、地面の下に隠された呪われた都市から黒い頭巾の者たちが満月を崇拝し、血の生け贄を始めとするおぞましい儀式を行うために外に出てきていた」
暗い森の地下にある闇エルフの都市、ティランデュイル・ケルサスの一行が雪に跡も残さず、静かに進んでいるさいに子供の叫びを聞いた。見ると、凍った布に包まれて、哀れな人間の子供が声を限りと泣いている。
「彼らはその子を儀式の場に連れていき、空にかかる<沈黙の守護者>に祝福を求めて捧げた。その結果、この子は天からの贈り物ということになり、永遠に満月の加護を受けられることになった。嵐の子と名づけられたエーレンは闇エルフの社会に受け入れられている。彼は今では闇の子供であるマルボルダスと名乗り、禁じられたエルフの秘儀の研究を終えようとしている。そのとき彼の手によって首飾りの力は解き放たれるだろう、だが、暗闇の愚かなエルフたちはケリスリオンがいなくなってからアル・アンワール・ゲリサン、彼らの首飾りが失われていたことに気が付いていたのだ」
首飾りを探して、多くのエルフたちが森を発った。行き先は分かっている、ケリスリオンが信奉したアル・アンワール・ゲリサン。エルフの王子が彼の首飾りを委ねるのであれば、「影の灰色のささやき」の手をおいて他にないだろう。
「アル・アンワール・ゲリサン・・・スラングの寺院にその首飾りがあるってこと?」
マキの問いにドルイドはゆっくりとした面持ちで頷いた。ダークウッドの闇エルフたちは闇の子供マルボルダスの望みを叶えるべく、森を出てスラングの寺院を目指している。話を聞いていたバリィが半ばひとりごとのように答えた。
「スラングは悪意と暴力を容認するが競争の神でもある。ダークウッドの近くであれば、ラーヴングラスにもスラングの寺院があった筈だ」
ラーヴングラスはすでにアーガイルの領土に入る、雑然とした港湾都市である。ダークウッドを迂回してアーガイルを目指している、マキやバリィたちが立ち寄る地は港町ラーヴングラスに決まった。ウォードマンは来たときと同様に唐突に姿を消すと、周囲にはダークウッドの不吉な沈黙が訪れていた。
† † †
ラーヴングラスはミッドランド西方にあるソルウェイ湾に面した、雑多な混沌と活気に溢れている港湾都市である。漁船と商船が日々、往来しているこの町はしばらく前に冥府魔術師団の手で解き放たれた悪魔魚によって荒らされていたが、勇気ある人物の手で退治されて今は活況をていしている。
「まずは強い酒、あとはそれに合う料理を一品」
「同感だな、少しでも探している話が聞けるといいが」
ハインツの提案にバリィが賛意を示す。路地を少し外れたところにある、目に入った看板にはうまくもない文字で「赤竜酒場」と書き殴られていた。地下に続く階段があり、もうもうと立ちこめる煙でうす暗くなっている地下室から、しわがれた笑い声がひびいてくる。
ハインツとバリィ、それにフールフールとウェイは中へ入ると、この安酒場で唯一光があってものが見える場所まで歩く。テーブルや丸椅子を通り抜けてカウンターまでたどり着く、その後ろにはこの酒場の主人らしい、太った男が立っている。
「親父、この店で一番強い酒をもらおうか!その次にもらうのは二番目に強い酒だ!」
ドワーフの嗜好と鯨飲ぶりは今更のことであり、フールフールの言葉は驚くに値しない。長身の戦士と風来坊めいた男、頑丈な鎧に身を固めたドワーフ女に派手な羽根兜をかぶった蛮人。四人は酒を注文すると酒場の主人がエール酒をついでいる間に、暗さに目が慣れるのを待ってこの店の客たちを見渡す。
店は思っていたよりも人が多く、様々なうわさ話が流れている。耳を傾けると北のどくろ沼を抜ける道がふさがれたという話が聞こえ、フールフールやウェイは苦々しさを覚えると木のジョッキをあおるように強いエール酒を飲み干してしまう。近隣の旅人がウィロウベンドに来る途中で幾度もエルフらしい姿を見かけたという噂もちらほらと聞こえて、バリィとハインツは無言で視線を交わす。
幾つかの噂が流れている中で、ハインツやバリィが興味を覚えたのはカスパーで起きているという騒乱の話であった。カスパーはアーガイルの南西に位置する国で、アーガイルの前王ソーステインを暗殺したターグ男爵が治めている。
西の離島から渡ってくるトカゲ兵団のおかげでカスパーが陥落するかもしれない、いい気味だといった話が聞こえる。更に耳をそばだてていると「赤竜酒場」に二人の新しい客が入ってきた。最初に入ってきたのは、のっぽで針金のようにやせ、黒の外套を着た男だ。トウモロコシのような明るい黄色に染められたちぢれた髪だけが目立っている。二番目は美しい女で、鉄板をはりあわせた奇妙な鎧を身につけている。
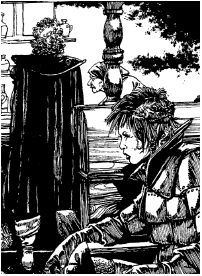
二人の姿に酒場の主人は息をのむと、むりやり笑みをとりつくろって「テュテュフ様、カサンドラ様、ようこそおいでくださいました」とこびへつらう。テュテュフがカウンターまで歩みより、飲み物を注文する。バリィたちが座るテーブルの真向かいにカサンドラが腰をおろすと酒場の中に不穏な空気が流れ、ジョッキを手に戻ってきたテュテュフがバリィをにらみつけて言う。
「お前の顔は気に入らないな」
バリィが答えるよりも早く、勢いよく立ち上がったのはフールフールとウェイである。彼らは侮蔑を黙ってやり過ごすような性格をしてはいない。狭い酒場で大弓を抜くわけにもいかないフールフールは手近な椅子を手に持つと、お前の顔をもっと気に入らなくしてやろうと叫んでから殴りかかった。
テュテュフはひととびしてそれを避けると、うすら笑いを浮かべながら人の背丈ほどもある長い剣を抜いて、片手でかるがると振り回す。フールフールの手にしていた椅子が長剣の一撃で砕かれると、加勢に出たウェイも瞬く間に剣ごと弾かれ倒されてしまう。
混乱で満たされている酒場で、バリィもハインツも慌てて剣を抜くが、今度はカサンドラがヒョウのような優美な身のこなしで動き、剣を抜く。その剣は冷たく輝き、刃先に霜がついて一目で魔力を帯びていることが分かる。
ウェイは闇エルフに受けていた傷もあって俊敏には動けず、フールフールはテュテュフの剣から身を守るので手一杯でありバリィとハインツもカサンドラの剣を止めることができない。騒動を聞きつけたのであろう、にわかに酒場の入り口に慌ただしい声が聞こえるとテュテュフとカサンドラは視線を合わせ、野次馬と衛視に出口がふさがれるより早く地上へ駆け出すとラーヴングラスに姿を消してしまった。
「臆病者め!平たく潰してやるから戻って来い!」
怒り狂うフールフールは力こぶを盛り上げた両手に椅子を下げ、逃げた二人を追って階段を駆け上がろうとしている。ハインツは置き去りにされたドワーフの弓や荷物をひったくり、バリィも倒れているウェイを抱えると急ぎその後を追った。
この状況で、衛視に捕まればめんどう事になるのは目に見えている。酒場の主人には気の毒だが今は見失ったテュテュフやカサンドラと同様に、身を隠すしかあるまい。
† † †
港湾都市ラーヴングラスにある悪意の神スラングを信奉する寺院は、表通りを外れた路地裏の一角に建てられている。悪意と暴力を容認するスラングは邪な神とされる一方で、人間の本質と競争を司るとも言われており、おおやけに崇めてよい神であるとはされていないがその教えを聞く者も決して少なくない。
スラングの教えでは他者を貶めることで他者に勝利することは悪ではない。この教えから武器を持つことを認められたスラングの僧は競争を保証する神として、商人に崇められていることも多く港を守る役目を果たしていることもあった。
「理解できぬことではない。欲得を是とする教えは八幡にも存在する」
「なるほど、信仰っても多いしね」
小声で語る、東方の黒衣を着たウンスイは彼自身が奉じる信仰を持っているが、異教を知り検分を深めることも修行の一つであると考えている。
だが信仰はすべてが他の神を認めるとは限らない、ウンスイの話に耳を傾けているエアはスラングの教義が異教を廃することで至高を得ることができると解いていることを知っていた。今は彼らの教義を深く探求すべきときではないが、異教の僧であるウンスイがスラングの寺院を訪れることにエアは心配を抱かないでもない。
「だがこちらには目的がある。今はそれをこそ優先すべきであろうな」
寺院には外套を目深に被り素性を隠しているウンスイとエア、それに「白の狩人」ガルド・ミラの三人が足を踏み入れている。異教の徒をこころよく思わないスラングの寺院に異教の僧が立ち入ることは危険かもしれないが、見聞の広いガルドや信仰を心得ているウンスイがいたほうが都合はよいかもしれない。
スラングの司祭はホーカナという最高位の巫女である。背が高く目もさめるような黒髪の女で、黒の外套を着ているがその裾の間からは長剣の柄がのぞいている。争いを承認するスラングの司祭らしい姿だが、スラングの剣は競争を守る武器の象徴でもあった。
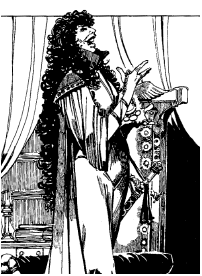
礼拝堂でエアたちが見るホーカナは信仰を統べる者らしく、威厳のある姿を信徒たちの前に現している。悪意の神を信奉するその顔は昂揚し、残酷に見える笑みすら浮かべていた。
寺院に入り込んだはいいがどのようにして首飾りの件を調べるべきであろうか、そう考えていたエアはホーカナの手に黒曜石の飾りがついた不吉な首飾りが握られているのを見て声を上げそうになる。エアの隣でガルドもウンスイも、彼らが求めている物がこの場にあることに気が付いていた。ホーカナの昂揚はエアたちが考えていたそれとは異なる理由によっていた。
「皆も知っておろう!数日来このラーヴングラスで見かけられた邪なエルフどもの一味が私の寺院を訪れたことを。だが寺院はスラングに守られている、ホーカナが下す炎が彼らを灼き滅ぼした。これじゃ!これが彼らの求める『首飾り』じゃ!」
どくろ沼はすでに闇エルフの手に落ちており、エルフたちがエアたちに先んじてラーヴングラスに入っていても不思議ではない。ホーカナはすでにその襲撃を退けたのだ。礼拝堂に深いどよめきが起こる。
これなら急いで来る必要もなかったかなと、聞こえないようにエアがつぶやく。大勢で押し入るわけにも行かぬと、他の者たちは寺院の外に隠れて周囲の様子を窺っている。ことが終わっていることを伝えれば彼らはどんな顔をするであろうか、やや気の抜けたエアはそんなことを考えたが、ラーヴングラスの港町は彼女が考えているほど平穏ではなかった。
スラングの寺院は、表通りを外れた路地裏に面して建てられている。路地の影に身を隠していたガラとサヴァンはにわかに周囲が慌ただしくなる声を聞いた。大通りに相次いで人斬りが出た、門の近くで商人の馬が暴れ出して手がつけられないでいる、昼日中の酒場で火が上がった。どれもスラングの寺院からは場所が離れた場所で起こっている。
「こいつはまずいね、来るよ」
次の瞬間、頭上から下りてきた黒い影が刃を閃かせてガラに襲いかかる。野馳りの女はとっさに身をかわしたが、隣りに立っていたサヴァンはかわしきれずに短刀が脇腹に突き刺さるとその場にうずくまった。
細い路地の一角から新たな喧噪が続き、そこではすでに剣を抜いて打ち合っているエルフのフィアリアが闇エルフの剣撃を弾き返していた。フィアリアとともに身を隠していたマキも重い斬馬刀を振っているが、狭い場所で俊敏な影を捕らえきれずに手傷を負っている。勢いのまま寺院になだれ込む闇エルフの一団を追って、フィアリアとガラが続いた。エルフ娘の顔は怒りと侮蔑に満ちている。
「呪われた同胞よ!貴様らの汚れた血を流せぇ!」
エルフの言葉で激しく罵る、フィアリアの姿は常の彼女を知るものに驚きを与えるだろう。エルフの抱いている闇エルフへの憎悪は人間の理解を超えており、互いが目にすれば何れかが死ぬまで争いを止めないとすら言われている。闇エルフもフィアリアにだけは一度に三人が切りかかって無数の傷を負わせていたが、フィアリアはそれすらも意に介するふうを見せていない。
やがてエルフの細い剣先が闇エルフの咽を貫いて寺院の壁まで突き通すと、石片を弾いて壁に縫いつける。追いついたガラはやや気圧されながらも短い棍を振り回し、加勢する闇エルフの刃を弾いていた。混戦に慣れている彼女はこの状態では味方を傷つけぬことが重要であると気が付いていた。だが、フィアリアとガラが数人の闇エルフを止めている間に他の者たちが次々と寺院に入り込む。
正面から、裏口から、窓から幾人もの闇エルフたちが押し入ると寺院は恐慌を来す。信徒らが押し合い、ホーカナも壇上で剣を抜くとスラングを汚す者たちに怒りの声を上げているが一人を切り伏せたところで邪な刃が降り立つと、深々と巫女の鳩尾に突き刺さる。
ガルドは二本の短剣を抜くと入り口付近に入り込んできたエルフに応戦するが、足を止められて動くことができずにいる。すかさず壇上に駆け上がったのはエアだが、礼拝のために殆どの武器は手元になく懐に忍ばせていた短剣の一本で闇エルフに切りかかった。今ここで「首飾り」を奪われる訳にはいかない、苦戦しながら勇敢に戦うエアにウンスイの声が飛ぶ。
「行くぞ!娘よ!」
「任せるよ!」
黒衣の僧が力一杯、投げつけたのはグランドピアンで手に入れたルーンの刻まれた棒である。投げると同時に、エアは背後の出来事が見えているかのように身を屈めると、魔力を帯びた棒が正確に闇エルフの心臓に突き立った。
目の前の敵が倒れる様子を見たエアはすぐに背後を振り向くと、新たに切りかかってくる闇エルフに対峙する。混乱の中で二人、三人と壇上のエルフの数が増えてくると剣士の娘は圧倒されるが、それでもエアは背を向けようとはしない。
「何人でも来るならこい!全員ボクが倒してやるぞ!」
決死の覚悟で虚勢を張るエアに、四人目のエルフが頭上から落ちかかる。だがその姿は全身に傷を負ったフィアリアであり、激昂するエルフの剣が壇上にいた闇エルフの一人を貫くと、身体をぶつけるようにもう一人を押し倒してから手近に落ちていた短剣を左目に突き刺した。遅れて壇上に上がったウンスイが最後の一人を組み伏せ、エアがとどめを刺したところでようやく周囲は鎮まったのである。
† † †
騒乱の規模はあまりにも大きく、ラーヴングラスの衛視たちも方々で起きた事件に駆り出されていたがやがてスラングの寺院に集められる。エアやウンスイは混乱に乗じて逃げることもできたろうが、むしろ事態が事態だけにこの場は衛視たちに引き立てられることを選んだ。
首飾りの話は捨て置くわけには行かず、アーガイルの王都にことの次第を知らせなければならぬ。闇エルフがアーガイルへの襲撃を図ったことを告げれば、ストーンブリッジで認められた「白の狩人」ガルド・ミラやグランドピアンの「魔人殺し」バリィ・ウォーグの一行が賢明な魔女アルガラドに会うことも無理ではあるまい。
ホーカナの手を離れた首飾りは今はフィアリアが手にしている。どくろを象った黒曜石の首飾りは手にしているだけで不吉な邪悪が重くのしかかる。闇エルフを撃退した後でエルフの娘はいつもの様子に戻っていたが、エルフが闇エルフを相手に生命を賭すことはフィアリアにとって何ら奇妙なことではない。一行の中でそれを理解している者がいるとすれば、皮肉にも同じ妖精族であるフールフールであったろうか。
「ドワーフがトロールを嫌うようにエルフにも許せないものはある。一族の誇りに気恥ずかしさを感じる者はいない」
「あら。あれをトロールと一緒に語るのはいいけど、エルフをドワーフと同じように語ることはないのよ?」
久々の軽口に、救われた気分になったのはむしろフィアリアであったろうか。衛視たちに囲まれて護衛と監視を受けながらも、一行は「首飾り」を手に王都アーガイルへと向かっている。カスパーの相談と闇の子供マルボルダス、そして闇エルフと首飾り。彼らが問いたださなければならないことは数多くあり、賢明な魔女アルガラドが助けになることを望まずにはいられなかった。
...TO BE CONTIUNUED
>第四の石版の最初に戻る