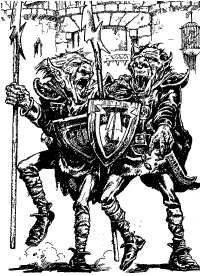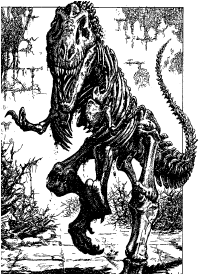SCENARIO#7
賢人アラコール・ニカデマスが住んでいるあばら屋は、ミッドランド西方にあるソルウェイ湾に面した港町ラーヴングラスの橋通りの先にある、<歌う橋>と呼ばれるおんぼろな木造りの橋の下に据え付けられていた。闇のマルボルダスの這いまわる遣いを倒した一行に、遅まきながら訪れたアーガイルの使者が伝えてくれた情報による。
下卑た港町をさんざ歩き回されての探索のほとんどが無駄足であったことを知るや、猛女の弓フールフールなどは使者に掴みかからんばかりの勢いで憤慨してみせたが、今はようやくにしてもその所在が知れたニカデマスに言葉を乞うべく、あばら屋に向かうことが先決であろう。
腐臭のただよう汚い川にかけられている、木造りの橋が見えてくると、汚れた川の黒い水面にはさまざまな塵あくたが浮かんで海へとただよい流れていく。見間違いであろうか、ごみに混じって人間の片手らしいものが流れさるのを見てゾッとする。橋の欄干から柱が高くのびていて、そこに人間や動物めいた生き物たちの頭蓋骨が取りつけてある。風が不気味な音を立てて橋げたを吹き抜けると、さながら拷問にあった魂が助けを求めているかのように不気味なうなり声を響かせていた。
「なるほど、それで歌う橋という訳ですか」
「どちらにしても魔法使いというのはろくな連中ではない!」
どこか嬉しそうな調子でサヴァンが呟く声に、フールフールがどら声を張り上げる。ドワーフならずともこのような場所で不平を上げない者がいるとすれば、不潔なトロールやオークを除けば気の触れた魔法使い程度のものであろう。
ほとんど人目につかないところに小さな階段があるのを見つけ、ぎしぎしと音を立てるそれを踏みつけながら橋の下へ降りていくと水辺の臭気はいっそうすさまじくなる。頭上を渡る足音が聞こえており、橋の基部にはめ込んだ形で木の小屋が立っている。カーテンがさがって小屋の内部はよく見えないが、扉に大きな赤い字で「立入禁止」と書いてあるので、歓迎されないのはたしかだ。
数人が顔を見合わせてから意を決して扉をたたくと、しばらくは誰も何にも答える様子がない。もう一度、ドワーフの女が今度は強く扉をたたくと、ぶつぶついう声とかすかな足音がしてからふいに扉が開く。目の前に長いローブ姿の、白髪に長いひげの老人が立っている。老人の声は不機嫌そうな顔にふさわしい、不機嫌そうなものであった。
「あんた方は何様のつもりじゃね?この哀れな老人を困らせおって。まるでわしが耄碌して手持ち無沙汰で客もなく、この汚い川の水が床板を通してしみ込んでこないようにするしかやることがないとでも思っとるのか?それにしても、お前さんらはこの川の水ほど臭くはないのう。さあさっさと用件を述べてみよ。わしを煩わせるだけの理由がないとなれば、お前さんらをひとまとめにトゲウオに変えてしまって樽に詰め込み、この川に叩き込んでくれるぞ!この川でどの程度生きていられるものか、ちょうど試してみたかったからな!」
「賢人アラコール・ニカデマス殿とお見受けします。我らは白い魔女アルガラドの導きによって、闇のマルボルダスと彼奴めが追う首飾りについてご助言をうかがいたく参りました。ここに来るまでにいささか寄り道をしてしまった故、突然の来訪による無礼は平にご容赦願いたい」
仰々しいサヴァンの物言いに、白髪の老人はじろりと一行に目を向けるがその視線がマキの姿に一度向けられてから、ニン・ガラの肩にとまっていたアルガラドのオウムに止まるとやにわに表情が変わり、ひどく急いで中に通すと扉の掛け金を下ろしてしまう。老人の部屋は想像していたよりもはるかに整頓されており、賢人や魔法使いといった類が使いそうな杖やしなびた首、生きたカエルの詰まった瓶のようなものはどこにも置かれていなかった。

殺風景にも思える部屋は中央に腰掛けが一つあるきりだったが、一行が首を巡らせている間に気がつくと人数だけの椅子が用意されている。アラコール・ニカデマスが小道具など必要としない人間であることを一行が理解すると、白髪の老人は先んじて口を開いた。
「やれやれ、昨今の空の暗さには辟易していたがよもや首飾りがスラングの手を離れておったとはな。この町に暮らしておきながら気がつかなんだとは、確かにわしも耄碌したかもしれん。だがお前さんたちが立方体を持つ身であれば、第四の石板に描かれた者をアルガラドが探しているということか」
賢人の言葉はくどくて長たらしいが一行の目的は言わずとも理解しているようだ。闇の首飾りの邪悪に顔色を悪くしている、快風のフィアリアとその傍らにいる小柄なマキの二人に目を向けるとニカデマスは語を継いだ。
「首飾りが邪な存在を甦らせること、そしてそれを求める者どもがこのラーヴングラスにいることをお前さん方はとうに理解しておろう、それを封じるのに手っ取り早い方法は他の神に捧げてしまうことだ。だから首飾りはスラングに捧げられておったが、それが襲われたとあればスラングの加護も充分とはいえまい。だがもっと力の強い神もこのラーヴングラスには祀られておる。地下の下水溝、魚人たちが暮らす古代王国の遺構にある水神ハイダナの寺院であれば、邪な者にもそうでない者にも容易に手を出すことはできん」
「ふん、黒い連中よりも鱗の生えた連中がましという訳ね」
いかにもエルフらしい、フィアリアの物言いにニカデマスはひげを振るわせる。どこか他種族を突き放していながらも、棘のない口調は彼女がエルフとしては珍しく他者と接することに慣れていることを示していた。ニカデマスの言う魚人とは混沌に類する者ではないがミッドランドに相応しく無秩序な種族であり、海エルフや人魚たちとは異なり決して善に与する存在という訳ではない。
「そう嫌わずともよい。何もトロールに会えという訳ではないのだし、そうであればそこの酒樽のような女が収まらぬであろう。ハイダナの水底に捧げれば誰であれ容易に訪れることはできなくなるが、確かにラーヴングラスには邪な手が伸びているようだ。この騒々しい町の地下にはかつて埋もれた古代王国の遺構に海水が入り込んで下水溝とされておる。港の下のどこかに魚人たちの集落があるが、お前さんらにとっての最善の策は波止場近くの古い水門を幾つか試してみることじゃろう。しかし、日暮れまで待たねばならん!昼の間はこの町の警備兵どもが、取り立てを逃れようとする商人どもをひどく追いかけまわしておるからな」
「邪な手というと、カスパーの者か?或いは闇エルフか、それともマルボルダスという輩か」
くどくどと長たらしい言葉は賢人であるためではなく、ニカデマスの性格らしい。逸れた話題を戻そうとするように、ハインツ・シュタインは彼が最も聞きたかったことを尋ねる。細い目を剣呑に歪めているハインツの並べた言葉の順番に、カスパーの傭兵に遅れを取った彼の思いが現れていた。顔をほころばせているニカデマスは剣士の言葉を窘めるようにも、さして気にとめていないようにも見える。
「戦士には戦士の軽重があろう。だが間違えるではないぞ!本当に首飾りを欲している者は嵐の子エーレン、闇のマルボルダスであるということだ。彼を取り巻く闇エルフですら、マルボルダスには利用すべきものでしかない。カスパーのターグはこれに乗じることを望んでいるが、本当に邪な存在のことなどまるで理解してはいないのだ。まあこの町でならず者を追うのであれば、ならず者に聞くしかない。有名な<黒海老亭>がある港通りよりも、入り組んだ塔通りの方がそうした連中が集まっているかもしれん。なにしろあそこにはろくでもないならず者が集まっているからのう」
賢人はその後もしゃべり通すと、一行がいささか辟易とした頃になってようやく解放する。日は暮れかけており、波止場を歩きやすくなる時間を待っていたのかもしれずニカデマス自身がしゃべりたかっただけかもしれない。一行はフィアリアを囲うように波止場へと向かうが、ハインツら幾人かは通りを外れてラーヴングラスの横丁や路地へと姿を消してしまった。
† † †
住民には<海老波止場>と呼ばれている、ラーヴングラスの船着き場は昼の間はたくさんの船が商品と客を乗せて世界の隅々から到着し、活気に満ちた騒々しい場所となっている。だがひとたび日が暮れてしまうと人々は自分たちのねぐらや酒場に姿を消すか、路地裏の隅で丸くなって眠ってしまい人気のない港は平穏そのものだ。暗くなってからも行き交っているのはよからぬことを企む者か、町の警備兵か、あるいは魚人の寺院を追って下水溝へ降りるための道を捜す者たちくらいであろう。
「魚人って人魚とは違うのかい?」
「小柄、といっても人の半分くらいの背丈をした魚に手足が生えたような連中よ。小さい種族だと思えばドワーフみたいなものかしらね」
「ふーむ、拙僧の国では聞いたことがないな」
多少の偏見を含めて説明をしているフィアリアの言葉に、エア・トゥーレとウンスイが純朴そうな顔で頷いている。年齢も傭兵としての経歴も浅いエアはまだしも、東国の修験者であるウンスイはこれまでも諸国を多く行脚していたが、彼の知らない珍しい種族も未だ幾らでもいるようだ。もっとも黒衣の僧が生まれた国はこのミッドランドとはよほど異なる種族が闊歩していることもあって、見も知らぬ生き物と出会うことに新鮮な興味を覚えている。
下水溝に繋がる水門はすぐに見つけることができた。水門の周囲は静かで幸いにして巡視や衛兵の姿もないが、雑多で治安が良いとはいえぬラーヴングラスはもともと警備にも熱心ではないのであろう。仮に見とがめられたとしても穏当に切り抜ける術は幾らでもあるが、面倒を避けるにしくはない。
崩れかけた足下や天上に気を配りながら、間に合わせの階段を降りていくと一行の目の前には町の地下に張り巡らされた下水溝が広がっている。たちこめる臭いはいよいよ酷くなり、世界中のあらゆる悪臭を混ぜ合わせたようなすさまじい臭気となっている。ガラの肩にはアルガラドのオウムが止まっていた筈だが、臭いに耐えかねたのかどこかへ飛んでいってしまった。野馳りの娘は角灯に火を入れながら、噂に聞いた地下世界の姿に目を見張っている。
「すごいね・・・」
驚き、圧倒されていたのは悪臭のためばかりではない。ラーヴングラスの下水溝は元来、そのために作られたものではなく古代の町が一つ地下にすっぽりと収まっており、そこに地上の汚水やごみが流し込まれていた。
地上では踏み固められた地面の上に木と泥でできた建物が今日にも崩れそうな増築や改築を繰り返されているが、地下の街路は石畳で舗装されて側溝まで掘られており石造りの壁は頑丈で地下に埋もれてなおかつての威容を窺わせている。これだけの遺構が土と汚物に埋もれている、そのことがラーヴングラスの混沌と無秩序を象徴しているかのように思われた。
「何故こんなふうになったんだろうね」
「ラーヴングラスは河口の町だ。川を流れる泥土がやがて積まれていく。放っておけば埋もれもするし、洪水でも起きればそれはより広がっていくだろう」
野馳りの女の言葉に、白の狩人ガルド・ミラが語る。無秩序が町を頽廃させると時とともに累積する土砂の下に埋めてしまい、町は新たな無秩序を呼び込む。ミッドランドが善でも悪でもない無秩序によって支配されていることを彼らは苦々しく認めざるを得ないが、今必要なことは止められぬ無秩序の侵攻を嘆くことではなく邪悪の策動を抑えることであった。
問題は魚人たちの集落を捜す方法であろうかと考えていたが、手にした灯火を頼りにしてじわじわと下水溝を進む彼らが悩むより早く頭上から大きな網が降ってくると一行をくるんでしまい、慌てているところに汚水の中から大勢の魚人(Fishman)たちが姿を現す。
三つ又の槍を構えている、手足の生えた魚めいた生き物たちは一見して十人は超えているが水中にまだどれほど隠れているかは判然としない。魔人殺しのバリィは先の天幕での戦いに続けて頭上から網を被せられることになったことに悪態をつく。軍団旗を手にするエアや大きな斬馬刀を持つマキなどは絡まった網の下でもがいているが、網を切るにしても争うにしても今は長い剣を振りまわせる状態ではないだろう。だが恐る恐るという体で、槍先を向けている魚人たちもこちらを囲いながらすぐに襲いかかってくる様子はない。
「ぐぉのカサカサ野郎ども!俺だぢのねぐらに何の用だ!」
ごぼごぼと水音を立てるような声で、魚人の一人が三つ又の槍を突き出す。その様子と言葉におやという顔をした魔人殺しがすばやく目配せをすると、その意図を承知したガラやウンスイが心得たように表情を改めて手早く水袋の中身を頭から被る。もとより丸い目を更に丸くしている魚人たちに、せいぜい敬虔そうな様子で頭を下げてみせた。
「水に浸されたハイダナのお遣いであらせられますか。我ら乾いた肌を持つ身でありますが、大いなる海に囲われた地に暮らす者として、この世界の祖たる水神に供物を献じたくこのじめじめした場所にやって参りました。なにとぞお取り次ぎを頂きたい」
「本来であればこの身を水に浸して敬虔を表すべきところ、この程度の礼でお許し頂けますか」
「拙僧異境の身なれど、水に濡れる畏敬を有り難く存ず者」
奇態な受け答えに聞こえるが、カサカサと乾いていることが魚人にとって侮蔑を現しているのであれば水に濡れているという言葉はおそらくその逆だろう。エアやフィアリアなどは聞いたこともない即興の礼節に目を丸くしているが、魚人たちは彼らが思うカサカサした連中が下手に出ていることに悪い気はしていないようだ。だが水神ハイダナに供物という言葉に対しては、どこか困惑したように互いを見合わせている。
「寺院はカサカサ野郎の酒場から近いが、黒い子供が入り口に化げ物を置いぢまっだ。あそごには行げねぇ」
黒い子供、という言葉にフィアリアは小さく肩を振るわせてバリィやウンスイも背筋に戦慄を覚える。遂に嵐の子エーレン、闇のマルボルダスが自ら首飾りに近づきラーヴングラスに邪な手を伸ばしてきたということであろう。
ガラは魚人たちに化け物を排する約束をすると<人魚酒場>と呼ばれる店から繋がっている、古代の遺構の奥に設けられた寺院の場所と魚人たちの案内を取り付けてから一度ラーヴングラスの地上へと戻る。悪臭を避けていたオウムがいつの間にか戻ってくるが、調子のいい鳥を一瞥するガラの目にも緊張の色が消えることはなかった。
† † †
ハイダナの寺院を捜す者たちが未だ波止場の周囲で人気が消えるのを待っていた頃、野馳りの女の肩に止まっていたアルガラドのオウムが飛んできた様子にサヴァンは陽気な顔を向けていた。
「おや下水溝はお気に召しませんか?」
片眼鏡をした奇態な風体の魔法使いの肩に止まっているオウムの姿は一層奇妙であって、蛮人ながら多少は文明に慣れているつもりであったウェイ・ラスローの目にもやはり不可思議に映っている。大柄な蛮人の傍らで、彼の胸までしかない背丈の酒樽のような女が不機嫌そうな様子を見せているが、フールフールがそうした素振りを見せているのはこのラーヴングラスに来て以来とくに珍しいことではない。
魔法使いに蛮人に酒樽女、そして大きな平剣を背に吊しているハインツの四人は、カスパーの傭兵であるテュテュフとカサンドラの二人を追って町の裏路地へと足を踏み入れている。
ラーヴングラスは遠くから見ればそれなりに大きな、他の多くの海岸近くの町と同じように見える。高い市壁の後ろでごちゃごちゃとした屋根と塔の雑多な集まりが空を背景に散っているのが分かる。彼らがいる<塔通り>はそうした雑多な塔の中でもひときわ大きな、だが古びて今にも崩れそうな塔の周囲に繋がる路地のような通りであり、長い歳月の間に継ぎ足されていった建物や壁が入り組んでいて暮れかけた空を覆い隠そうとしていた。
港に続く大通りを外れたこの周辺では無精な住民たちが汚物を下水や川に持っていかず、通りに投げ捨てる習慣があるせいでそこらに悪臭が漂っており、こうした場所に慣れている筈のウェイやフールフールでさえも鼻を曲げている。どれだけひいき目に見ても住民もろくなものではなく、人通りの多い時間であればすりやかっぱらいに宿なしといった輩に悩まされていたであろう。
日が落ちようとしている今は人影こそそこらに見えているが、多くは港や大通りにある酒場へ足を向けているのかもしれない。彼らが追う者たちもそうした酒場にいるであろうか、そう考えていた矢先に前方の路地から大柄な一組の生き物が姿を現す。黒っぽい服に矛と盾を持つ醜いトロール(Troll)の姿にフールフールの顔色が一瞬で変わる。
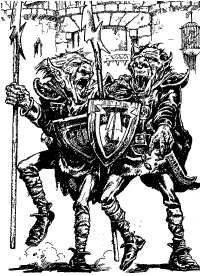
無様な生き物たちは一見してラーヴングラスの衛兵めいた風体をしているが、言われるまでもなく彼らが従うのは彼らが勝手に決めた規則でしかないだろう。トロールはこちらの姿を認めるといぼだらけの顔ににやにやした笑いを浮かべながら近付いてきて、大盾と長弓を担いでいる小柄な酒樽女の頭上からことさら臭い息を吐きかける。
「なぁブラックボイル?俺の足下にちっぽけなドワーフがいるかも知れねぇが小さくて見えねぇぜ。へっ、へっ」
「そいつは大変だ、楽しく踏みつけたら靴の裏にへばりついたガムになっちまう。ガムは食えるけどドワーフは胃にもたれるから始末に悪いじゃねぇか」
「へっ、へっ。その通りさ、お前もそう思うだろう?なぁ、ドワーフゥ?」
もしもフールフールの全身に毛が生えていれば、たちまちそのすべてが逆立っていたであろう。ラーヴングラス中に響くのではないかと思われるほどの、意味不明な雄叫びを上げたドワーフ女がトロールの一人に掴みかかる。トロールの背はドワーフの倍ほどもあるが、フールフールは力ずくで無様な生き物を押し倒してもみ合うと、あごや胸を殴りつけた。倒れたトロールも激しく暴れて腹や頭に拳を叩きつける。
「うばぁああぐぁああ!」
最早どちらの叫びかも分からない、激しい乱闘に<塔通り>の周囲には人が集まってはやし立てはじめており、ブラックボイルと呼ばれていたもう一人のトロールも加勢しようと矛を構えている。おそらくトロールであれば仲間を傷つけても気にしないであろう様子にすかさずサヴァンが一喝する。
「髭を!鋼に・・・わ、わたしの髭が!」
「何やってんだ魔法使い!」
すかさずウェイとハインツが突進するが、ブラックボイルもしきりにあごのあたりを気にしており確かにサヴァンの魔法はトロールの気をそらしているようだ。ハインツはこの程度の相手にと思いながらも平剣を大きく振ってトロールの矛を叩き落とし、ウェイは乱闘に向いた短いイスパニア剣を抜くとひといきに咽を刺してしまう。倒れたトロールの身体をひとつ蹴ると、いまだトロールと殴り合うフールフールを見るがごろごろともみ合ったままで手を出すことができそうにない。
いつまでも乱闘を続けていれば興奮した周囲の人々が参加していずれ手がつけられなくなるであろう。ウェイとサヴァンが目を見交わすと、心得たとばかりに魔法使いが蛮人に向けて奇妙な仕草で両手を振り回してみせた。
「男に!火酒の力を!」
「任せておけ!おおおおおおおおっ!」
燃えるように力をみなぎらせた蛮人がもみ合うトロールとドワーフにどかどかと近付くと、その二人ともを持ち上げて放り投げてしまう。トロールが頭から落ちてぐしゃりと音がするが、受け身を取ったフールフールは動かなくなった生き物の頭を気が晴れるまでさんざ殴りつけた。暴れる酒樽女をウェイが後ろから抱えて、軽々と肩の上に担ぐと驚く人々に向けて大仰な勝鬨を上げる。
「ぬおおおおおおおお!」
「げああぁはああ!」
信じられぬ怪力を見せた蛮人に<塔通り>の人々も感嘆して歓声を上げる。派手な見せ物にハインツは呆れながらもこれで多少は動きやすくなるかと思い、それらしい数人を捕まえてテュテュフとカサンドラのことを少しでも知る者がいないかと尋ねた。長身に黒い外套を来たのっぽの男と、奇妙な鎧を着た美しい女だ。
「俺たちは火の蛮人とその一行だ。魚人の話で彼らと会うことになっている」
聴衆の一人がそれはおそらく<人魚酒場>のことだろうと言う。酒場はこの<塔通り>で酔いつぶれた客を魚人に売りさばくという堅実な商売を営んでおり、魚人が迷路のような下水溝を抜けてハイダナの寺院に行くための入り口に繋がっていることも教えてくれた。思わぬ情報を得るとサヴァンの肩にいたアルガラドのオウムがどこかへ飛び立つ。おそらく、他の仲間たちに知らせにいったのであろう。
† † †
カスパーの思惑は自領を脅かしているトカゲ兵団に対抗するために闇エルフに恩を売って彼らの力を借りること、そのために彼らが探している闇の首飾りを欲している。その闇エルフは彼らに授けられた嵐の子エーレン、闇のマルボルダスに従って首飾りの所在を探していた。だがマルボルダスはそのようなことは気にもしておらず、ただ自分が魔王子マイユールの力を得るために首飾りを求めているのだ。そしてテュテュフやカサンドラはカスパーのターグ男爵に雇われた傭兵であり、彼らもまた首飾りを探していることは疑いない。
ハイダナの寺院に繋がるという<人魚酒場>は、奇妙なほどに閑散として客の姿が見えない。一行が訪れると禿げ頭のふとった主人はどこか怯えたような様子で、火酒の蛮人ウェイや魔人殺しのバリィらが来ることをすでに承知していたように首をすくめると寺院へと続く地下室の隠し扉に指を向ける。手際の良すぎる待遇にエアは奇妙な顔になって傍らのバリィに尋ねた。
「どういうことかな?」
「誘われているのさ。寺院への道を遮る化け物とやらが俺たちを襲う、ならば後ろから挟み撃ちだ」
闇エルフやマルボルダスが暗躍する中で、おそらくテュテュフやカサンドラも自分たちだけで首飾りを奪えると考えてはいないのだろう。石造りの地下室はそれ自体が古い建物の一室となっており、酒蔵に用いられているぞんざいな棚の脇には不似合いなアーチ状の門が据えられている。ラーヴングラスが地下に埋もれた遺跡の上に立つ都市であることを、今更のように思わずにはいられない。
首飾りを持つフィアリアとそれを守るマキ、白の狩人ガルドにサヴァン、そしてウンスイの五人がハイダナの寺院へと向かい、魔人殺しや火酒の蛮人らが酒場でカスパーの傭兵団を迎え撃つ。首にかけた邪悪に押し潰されそうになりながら思い詰めたような顔を見せているフィアリアだが、視線を向けられると蛮人とドワーフには酒場がお似合いねと悪意のない口調でおどけてみせる。たいまつや角灯を手に、エルフの娘たちが地底の暗がりに姿を消すと、酒場は静寂に包まれてしまう。
向こうが誘うのであればこちらも準備ができると、待ち構えるハインツたちは<人魚酒場>の入り口近くでそれぞれの武器を携える。酒場の主人は半ばあきらめたような素振りで、いつでも逃げ出せるようにして注文すら聞こうとはしない。衛視や官憲を呼ぶ様子もないのは<塔通り>の住人であるためか、彼自身にやましいことがあるためであろうか。
日はすでに落ちており、通りに繋がる路地に人気がほとんど無くなるとようやく暗がりから人影が現れる。ひときわ目立つ長身に黒い外套を着た男と鉄板をはりあわせたような奇妙な鎧を着た美しい女、見紛うことのないテュテュフとカサンドラである。荒くれの水夫らしい、数人の男を従えている。酒場の中に待ち構える者たちの姿があることを認めると、テュテュフがやや無個性な様子で口を開く。
「やはり分かれたか。ハイダナの寺院へ向かってもマルボルダスの番犬を倒すことはできない、首飾りは失われるだろう。闇エルフが台頭すればカスパーは息をつくことができるが、首飾りを手にすれば世界に混沌が解き放たれる」
テュテュフの言葉はどこか無責任に突き放したような素振りを感じさせる。闇の首飾りは魔王子マイユールの力であり、それを知ってなお騒乱を望む黒い戦士にガラが問いただす。
「あんたは首飾りの正体を知っているんだろう?魔王子を信奉する奴なんかを助ければ、カスパーやアーガイルどころかミッドランドに災いが訪れるかもしれない」
「知ったことではないな。傭兵はどんな世界でも生きる」
ガラの声に聞く耳を持たぬ風で、足を踏み出したテュテュフが人の背丈ほどもある剣を構えるとその後ろにいるカサンドラも無言のまま冷たく光る剣を抜き放つ。<人魚酒場>の主人には気の毒だと思いながらバリィとハインツが入り口の正面に並び、左右にはエアとウェイが構えて四人で囲う位置に立つ。後ろには背丈より長い弓を手にしたフールフールと、弩を構えたガラが陣取ってそれぞれ矢をつがえる準備をしている。
黒い戦士と魔剣の女の技は身に染みて分かっている。少しでも優位に戦うべく建物に踏み込んでくる相手を迎え撃とうとするが、大股に歩み寄ってきたテュテュフが酒場の入り口で足を止めると、変わらぬ無個性な口調のままで呟くように言う。
「残念だ。ここを選んだのは俺たちだというのに」
その声と同時に酒場の窓が破られて男たちがなだれ込む。短い剣や斧を手に踏み込んできた連中にフールフールが手早くつがえた矢を放ち、一人の胸を貫くが続けて三人ほどが狭い酒場におどり込んでくる。ガラは構えていた弩が間に合わぬことを知るとそれを投げ捨てて右手に短い剣を、左手には転がっていた木の腰掛けを持つ。まずは相手を倒すよりも、使える物を使って身を守らなければならない。
テュテュフが長剣を大きく振って酒場に飛び込むとカサンドラが続く。すかさずウェイとハインツが前に立つが黒い戦士は二人を相手に一歩も引かず、見かけからは想像もつかぬ大力でハインツの平剣を弾いて平然としている横で、獣が地を跳ねるようにカサンドラがおどり込む。加勢するバリィが濡れたように冷たく光る刃を弾くが、カサンドラの魔剣は刃こぼれする素振りすら見せない。悪態をつきながらも、魔人殺しは背後を任せるつもりで酒樽女に呼びかける。
「背中は娘さんがたに任せた!」
「では俺の弓技を見せてやろう!」
娘さんと呼ぶには豪快すぎる雄叫びを上げたフールフールが手斧の男に肩口からぶつかると、勢いよく転がった相手を踏みつけた上からすばやく猛女の弓を放つ。エルフが見ればその野蛮さを非難せずにはおかないであろう一撃で男が死ぬと、他の襲撃者たちもその苛烈さに怯みの色を見せる。身を守る一方であったガラがすかさず酒場の隅に下がると、軍団旗を預けたエアが入れ替わるように広刃の剣を抜く。
「アーガイル騎士団の名誉にかけて!ボクの剣を食らえ!」
その言葉に騒乱を騎士団のせいにされないだろうかとも思うが、次の瞬間には激しい剣の音が周囲に飛び散る。小柄な身を巻き込むように沈ませてから外に振り上げる剣で一人の短剣を弾きとばすと、身をひねってもう一人の剣をかわす。バランスを崩した男のあごを剣の柄で打ち、転がったところに刃を突きつけると戦意を失った相手を手早く組み伏せる。
「ふん、お優しいのう」
「騎士の名誉と言ってよ」
男たちを片付けたとはいえ、その間もテュテュフとカサンドラの剣は嵐のように荒れ狂って留まるところを知らない。尋常ではないテュテュフの膂力に、ハインツは致命の一撃を腕甲で避けるのが手一杯でウェイと二人がかりでも押されている有り様であった。常の平静さを忘れたように激しく平剣を振るう。
「命を尽くせ!力と技を尽くせ!愛するが如く!」
打ち合い、わずかに押し返した間隙をぬってカサンドラの刃が伸びるが、バリィが割り込んでこれを弾くと再びテュテュフの剣が暴れまわる。カスパーの傭兵二人の連携は完璧に見えて隙がない。魔人殺しの剣が縦に振り下ろされて<人魚酒場>の床を穿つが、一瞬前にカサンドラはヒョウのような身ごなしで飛びすさっている。暴風のように荒ぶるテュテュフの剣が開いた場所にカサンドラがおどり込むと、板張りの鎧で身を守りながら冷たい魔剣の一撃を狙う。
ハインツもウエイも全身に傷を増していき、広刃の剣を構えたエアや手頃な棍棒に持ち替えたフールフールが加勢するが黒い戦士の剣は更に勢いを増して建物ごと砕くかのように振り回される。大盾に身を隠したフールフールが雄叫びをひとつ上げると、正面からテュテュフの剣を遮るように激しく受けて剣の嵐を止める。脇を潜るようにエアが切り込むが、黒い戦士は信じられぬ力で剣を引き戻して斬撃を弾き返した。フールフールとエアが広げた空間にすばやく魔人殺しが切り込む素振りを見せると、一歩早くカサンドラがおどり込むがその足が先ほどバリィに穿たれていた床の穴に踏み込むと一瞬身体が傾ぐ。誘われたことを理解したカサンドラが悪罵の叫びを放った。
「謀られたか!」
「地獄へ行っても!忘れるなよ!」
魔人殺しの剣の一閃が容赦なくカサンドラの首筋に打ち込まれた。鎧が鳴る激しい音とともに膝をついたカサンドラはわずかに視線を動かして、自分を叩きのめした相手に小さく笑うとそのまま彼女の魔剣とともに崩れ落ちる。がしゃりという音に続いて、冷たく光る刃が床に転がった。
仲間が倒れたことにテュテュフは叫ぶでもなく動じるでもなく、だがすべての思惑が崩れさったことを悟ると大きく剣を振ってから跳びすさり、無言のまま魔人殺したちを一瞥して身を翻した。バリィは転がったカサンドラの剣を拾うとテュテュフの視線が憎悪でも冷酷でもなく、だが言い様のない奈落に捕らわれていたことに気をかけたが、今はハイダナの寺院に向かう仲間を追わなければならないだろう。アンセリカを煎じた薬を手にしたガラが歩み寄り、倒れている鎧の女の様子に決断をつけかねるといった顔でバリィに問いかける。
「・・・助けるかい?」
「寺院に向かった連中が心配だな。追いかけた方がいい」
† † †
ラーヴングラスの下水溝は元来地下に埋没した古代王国の遺構であり、ハイダナの寺院に繋がるという通廊も方々に柱を配した出入口が開いていて、別の通路へと繋がっている。かつてはそれぞれが古代の家や建物であった様子がうかがえる。
角灯の火をかざして<人魚酒場>の地下室から寺院に至る通廊を照らしながら、魚人に聞いていた話を思い返す。全身を鱗とぬめりに覆われている、彼らが祭壇を設けて寺院とした建物は古くは古代の兵舎か何かであったらしい。中庭を抜けたその奥がハイダナの寺院となっているが、その中庭に彼らの言う「黒い子供が置いていった化け物」が陣取ってすでに多くの魚人たちが犠牲になっていた。
「礼拝もできぬとあれば気の毒ではあるな」
「だが異境の神が拙僧の助けを受け入れてくれると良いが」
ガルドの言葉にウンスイが珍しく冗談めいて言うが、案外当人は本気でいるのかもしれない。化け物を恐れてか、魚人たちは寺院までの最低限の道を教えた後は姿を隠している。目的の場所は幾度か曲がりくねった通廊を抜けた先にあって、入り口の左右は装飾の凝らされた円柱に支えられていた。
石造りの通廊から続いている頑丈そうな門を潜ると、寺院へと通じる中庭までまっすぐに続いており、床は丁寧に磨かれた跡があるものの方々が固いもので引っかかれたように傷つけられて、中央には巨大な残骸のようなものが積まれている。奥まった先の建物が寺院のようだ。
かつての庭園は植えられていた草木が枯れて久しく、周囲の石壁や床につけられた傷は新しいものに見える。その理由はすぐに明らかになった。積まれていた残骸のような姿がぎくしゃくと動き出すと、ゆっくりと立ち上がって巨体をもたげる。骸骨暴竜(Dinosaur Skeletons)は巨大な頭に、一本が短剣ほどもある牙をむき出してその巨大な足を踏み出した。これこそ嵐の子エーレン、闇のマルボルダスが配した番犬であろう。
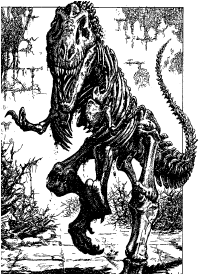
暴竜の背には寺院へと続く扉が見えているが、傍らをすり抜けるほどの余裕はない。見かけよりも遥かに俊敏に迫る巨体とマルボルダスの力に怖気を振るいつつ、サヴァンとフィアリアを後ろに控えさせてガルドとウンスイ、マキの三人が前に出る。暴竜が足下に転がっていた魚人の骸を踏み砕いて頭を下げると、ガルドは懐から短い棍棒を抜いて手早く殴りつけた。
「おそらく剣は効かぬ。だが・・・」
骨でできた身に刀傷を及ぼせるとは思えないが、それが棍棒であっても全力で殴りつけてどれほど傷を負わせることができるか心許ない。危うく身を屈めた、白い狩人の頭上を暴竜の尾が横なぎに振り抜けると、少しでも気を引くために動き回ることしかできなかった。すかさず跳び上がって、全身の力を乗せた斬馬刀を振り下ろしたのはマキである。
「これが必殺!力押しだ!」
骨と刃が弾ける、がぎんという音が響くが暴竜はわずかに表面が欠けた程度にすぎない。着地してもう一度、今度は脚に切りつけるが骸骨暴竜は見た目以上に重く頑丈で転ばせることも容易ではなさそうだ。戦士たちを助けるべくサヴァンが呪文の言葉を唱えて、フィアリアも地下の遺構でわずかに漂う精霊に語りかけては角灯から炎の舌を伸ばす。
「武器だって折れぬさ、棒だって折れぬさ!」
「火に踊るとかげよ、お前の力を貸せ!」
炎が骸骨を焼き、続けてガルドやマキが暴竜の足を叩くとわずかに動きが止まる様子に、錫杖についた輪をしゃん、と鳴らしてからウンスイが跳ぶ。巨体を相手に地をすべるように低く、脚を払うように打ち据えた。
「転!」
骨を削る不快な音が響き、怪物が揺らぐがそれでも倒れない。突然、邪な気配を感じたサヴァンは彼らの背後で中庭に入る門がゆっくりと閉じる様子に背筋を寒くする。中庭の中央には底のない黒い穴が現れて、その向こうには純粋な邪悪が渦巻いていることが分かる。慌てたようにサヴァンは奇態な身振りをすると背後の門に手のひらをかざすが、もはや動かぬ扉が魔法の力で閉ざされたことを知るだけであった。
(首飾りを渡せ)
嵐の子エーレン、マルボルダスの抗いがたい意思が閉ざされた中庭に響く。巨大な牙が迫り、突き出したウンスイの錫杖が暴竜に咬みつぶされるとまるで小枝のようにくしゃりと曲げられてしまう。短剣のような鉤爪が黒衣の僧を袈裟切りになぐと同時に、尾が叩きつけられてウンスイの身が宙に舞う。
更に巨体に似合わぬ動きで、もう一度振り回した尾が続けてガルドをも弾きとばすと石壁にしたたか背を打ちつけた。息を吐き出して膝をついた白の狩人は身を起こそうとするが立ち上がることができず、ウンスイも傷を押さえたまま動くことができない。
(首飾りを渡せ)
首を振って邪な声を振り払い、仲間を守るべく勇んだマキが真正面から切り込むと、暗闇の中で見えない道を切り開くように重い斬馬刀に全身の力をこめて打ち下ろした。
「あたしの!あたしの力とパワーは無敵の筈だ!」
頭蓋に叩きつけられる、その一撃が暴竜をわずかでもよろめかせたように見えたが渾身の一撃に着地を損ねたマキが動きを止めたところに、牙がずらりと並んだ巨大な顎が覆い被さる。誰もが目を背けそうになる一瞬、マキが懐に入れていた立方体からきぃんと音がすると、崩れた床石に足を取られた暴竜が躓いてマホウ剣士の娘を危うく咬み損ねた。それがアルガラドの立方体の助けであることは明白であったが、だからこそ友人が咬み砕かれる未来が寸でで変えられたことにフィアリアは顔面まで蒼白になると耐えきれずに叫ぶ。
「止めてぇ!望むなら・・・首飾りを。だから、もう」
その声にすべての動きが止まる。エルフの娘は自分が心から邪悪に屈した恥辱と恐怖に耐える顔で首飾りを外すと、震える手をゆっくりと前に差し出す。暴竜の足下に開いている黒い穴からは邪悪な意思が立ち上り、一瞬、フィアリアはためらうがその手から首飾りが放られると、それは吸い込まれるようにして黒い穴の底に消えていく。
同時に骸骨暴竜はがらがらと音を立てて崩れると、もとの瓦礫の山に戻り中庭を閉ざしていた門がきしむ音を立てて開かれた。首飾りさえ手に入れれば嵐の子エーレン、闇のマルボルダスにとって他は瑣末な事柄でしかないのであろう。
「私は・・・私は・・・」
それ以上の言葉を続けることはできない。闇のマルボルダスに首飾りを自ら差し出した、誰もエルフの娘を咎めようとはせずフィアリアは嘆くことすらできずに立ち尽くしている。傷は癒す。危難は克服すれば良い。だがすべてが手遅れになればミッドランドは魔王子の望む地に変わるであろう。背後から仲間たちが駆ける音が聞こえると、遂にこらえきれずくずおれたフィアリアが両手で顔を覆い嗚咽の声を上げる。倒れた者たちは傷よりも恥辱に懸命に耐えながら、辛うじて残された意思を支えていた。
...TO BE CONTIUNUED
>第四の石版の最初に戻る