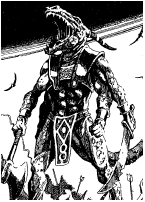SCENARIO#9
トカゲ兵帝国軍が、またもや怒涛のごとく城の防壁に押し寄せてきて、カスパーの篭城軍は震えあがった…が、なんとかもちこたえた。男も女も、歩く死体といったも過言ではないほど疲れきっているにもかかわらず、崩れ落ちた防壁を背に、必死で戦ったのだ。長きにわたる飢えと疲労で衰弱し、やつれ果てた兵士たちを支えているのは、意志の力以外になかった。
トカゲ兵軍は一歩前進するごとに百匹のトカゲ兵を失っていると、見張りは確信をもって言った。だがそれが気休めにすぎぬことを口を開いた当人が誰よりも心得ている。強大な勢力をもつトカゲ兵帝国軍は、失った数以上の兵力を投入してくるのだった。この邪悪な亜人類たちが防壁の石組みをひとつひとつ取り外して、最後の防衛線が突破されるのはもはや時間の問題だろう。

賢人の言葉を信じるとすれば世界は現界と多くの異界に分かれている。神々によってつくられた、この世界が虚空に浮かぶ球体の姿をしていることはほとんどの人々によって認められてはいたが、ではどれだけの異界が存在して球体とどのように接しているかは議論がまとまる様子を見せていない。夢と呼ばれて、妖精が自由に行き来することのできる異界は最も人に親しみがあるが、夢がどこにあるかと問われて答えることのできる者は少ないだろう。
そうした異界の中で、人が最もおそれて警鐘を鳴らしているのが奈落(PIT)と呼ばれている世界である。そこにはあらゆる邪悪と混沌がうごめいており、罪業に汚れたものどもが死んでから、あるいは生きながら落とされる場所とされている。奈落は鋼鉄や黒曜石、血や胆汁といった合計すれば七つの地域に分かれていてそれぞれを統べる七つの城が建てられている。七つの城には四体の魔人と三体の魔王子が座していて、彼らこそが奈落の支配者という訳だ。
神々の中でもっとも危険なものである「死」が選んだしもべの長が彼ら奈落の王者であり、狂気、堕落、真の混沌などで邪悪と混沌の軍勢を完璧に掌握している。奈落ではしばしば残酷な酒宴がもよおされており、生皮のクロスで覆われたテーブルを不死の怪物どもが囲み、生きたものや死んだもの、半分死んでいるものをつまんではちぎりとって貪っている。床は膝までが血と粘液に満ちて空気は死にゆくものの叫びと生きたものをすする音で満ちている。人にとって幸い、あるいは嘆かわしいことに、人は天上よりも奈落に詳しく詩人や賢人が多くの知識を残しているようだ。
「皆さんの労にアーガイルの、ミッドランドの者として感謝の意を表します。よくぞ闇のマルボルダスの企てを封じ、魔王子マイユールが世界に干渉する術を打ち砕きました」
奈落の酒宴とは異なる、人の王宮でもよおされる式典は遥かに健全で威厳に満たされており、ずっと堅苦しい。暗殺された王ソーステインに代わり、アーガイルを統べている白い魔女アルガラドは彼女が立っている階から深々と頭を垂れた。魔女が常の庭園ではなく、謁見の間にいる理由は英雄たちに敬意を表してのことである。広間の左右に個性のない表情を並べている高官や貴族たちも、王が頭を下げるのでなければ口うるさく言う必要もないらしい。
目を見交わしひそひそとささやいている姿を横目に見て、やはりこのような場所は性に合わぬと白の狩人ガルド・ミラはやや気圧されたようにかしこまっていた。邪な野心がくじかれたとはいえミッドランドの騒乱は今だ収まってはおらず、最近では火山島のトカゲ兵団が海峡を越えて上陸すると、南方のカスパーを襲っているという噂も聞いている。
情勢と、この状況でアーガイルがどう動くかを問うことができればありがたいと考えて、白の狩人は堅苦しい宮廷に足を運んでいたがこのまま堅苦しい式典が続くのであればいっそ長居せずに辞したほうがよいだろうか。
そのガルドの心情を慮った訳でもないだろうが、場違いな鳥の鳴き声が上がる。人々が首を巡らせるとアルガラドの伝令であるオウムがガルドの傍らにいる娘から飛び上がり、元来の主人の肩に降りる。それまでかしこまっていた娘は短い旅をともにした仲間が離れたことにどこか残念そうに見える顔をしながら、魔女にも宮廷にも臆した様子もなく口を開いた。
「白い魔女アルガラドよ、不作法の野馳りに宮廷は窮屈でかないません。我らが意義はミッドランドに流れる言葉を交わすことにありますれば、尋ねたき言葉は私へのものではなく、私が人に伝えるべき言葉でございます」
そう言って頭を下げる、ニン・ガラは若いながらガルドと同じようにミッドランドの空を天井にし木々を枕にして暮らしている娘である。仰々しく示された敬意を大人しく受けるくらいの分別は持っていたが、堅苦しい礼節を苦手とすることは皆と同じであったし、何よりも彼女が望むことは騒乱止まぬミッドランドの情勢であった。
白い魔女もそれは承知しているのであろう、わずかに表情を崩すと和らいだ口調で言葉を紡ぐ。それがどこか曖昧で分かりづらいのは宮廷にいるからではなく、賢人アラコール・ニカデマスと同様魔法使いと呼ばれている輩に共通する欠点であるのかもしれない。
「主なきアーガイルは国を統べる者を求めており、それは力と知恵と技が記された三枚の石板を手に難題を克服しようとしています。ですがミッドランドを混沌と無秩序から守る者はもう一枚の石板に示されている、それが何であるかを以前私はあなたがたに問いましたね」
白い魔女の言葉に、すかさず声が上がる。
「前から考えてたんだ。答えは勇気だね!」
「いや、拙僧には理解できた。答えは『仲間』であろう」
勢いよく声を上げたのはマホウ剣士を自称するマキであったが、語を継いだのは東方の修験者たるウンスイである。闇のマルボルダスの野心をくじき、解き放たれようとする魔王子の力を彼らが未然に防ぐことができたのは何によってであるか。
龍の封印を打ち砕いたエルフの娘は中立ではなく、己が信じる世界を律する力を用いればいいと言って彼らの神であるエリリアに祈りを捧げた。そして自らの信仰を持つ者が邪悪を打ち砕くのであれば、必要なものは信仰の種類ではなくそれを持つ者が互いに手を握ることそのものであろう。
海の彼方に正しき思想が根付いていることに満足した白い魔女は、口元をいっそう和らげると頷きを返す。
「第四の石板に示されている言葉は『仲間』。それはありきたりな言葉に思えるでしょうか。ですが一人では克服できない試練が、二人いれば克服できるようになるものです。そして覚えていてください。ミッドランドには未だそれだけの試練が訪れようとしているのだということを」
雪の魔女はアイス・デーモンの囁きに耳を傾けたが、打倒されて氷指山脈は厳寒の静謐を取り戻している。ダークウッドの闇エルフはケリスリオンの首飾りが失われたことで森へ戻っていたし、どくろ沼も解放されて未だ安全とは言えぬが少しずつ人の往来が増えてもいた。ラーヴングラスは無秩序が支配しているが賢人ニカデマスが腰を据えて煮こぼれた泥が鍋の外へ吹き出さぬよう努めている。そして失われた砂漠のヴァトスにはエリリアの娘が植えた菩提樹を礎として、長い時をかけた森の営みが始まろうとしている。
英雄たちの手でミッドランドを窺う野心は一つずつくじかれており、アーガイルの難題と称される危難の数々も内湾を震撼させた悪魔魚は退治されていたし、グランドピアンの財宝や怪物ミノタウロスが守るシャントスの珠は取り戻されている。
一つずつではあるが、国を立て直しつつあるアーガイルに比べてカスパーは危難のただ中にある。西の海峡を越えて上陸したトカゲ兵(Lizard Man)の軍勢がカスパーを襲い、おぞましい怪物どもによる包囲が数月も続くと遂に王の息子が重囲を抜け出してアーガイルにたどり着いたばかりだとアルガラドの口から聞かされる。門には巨大な破城槌や恐竜(Dinosaur)の角がたたきつけられ、頭上からは石や火のついたたいまつが昼夜を問わず降り注いでいる。
城は陥落寸前であり、援軍が間に合うか分からないが助けない訳にはいかぬ。貴族や高官の中にはアーガイルの王ソーステインを殺したターグを救うことに反対する声が根強いが、宮廷魔術師として主なき国を治めるアルガラドはカスパーを救うことを明言していた。
「王が暗殺されたにも関わらず、なぜアーガイルはカスパーを救おうとするのか。それはアーガイルが正義だからではありませんし、白い魔女が賢明であるからでもありません。カスパーを救わねばこのミッドランドが滅ぶのです」
アルガラドの啓示魔法は未だミッドランドに警鐘を鳴らして止まず、それは強くなる一方であり彼女の憂慮は消えることがなかった。肩にとまっていたオウムが白い魔女を離れると彼女の意志を託すかのように石板の英雄たちに向い、ニン・ガラが差し出した腕に再び足を下ろす。何としても、トカゲ兵の帝国がミッドランドに侵攻の足がかりをつくる事態は避けられねばならない。
野馳りの娘が姿勢を正して会釈すると、白の狩人もそれに倣いマホウ剣士は大布を巻いたままの巨大な剣を宣誓するかのように前に掲げてみせた。彼らはアーガイルのためではなく、カスパーのためでもなくミッドランドのために武器を握るが、黒衣の僧は元来アーガイルの者でもなければミッドランドの出自ですらない。八幡の礼節に忠実に従った作法で手を合わせて頭を垂れると、ウンスイは遠慮のない口を開く。
「アーガイルの意思は承知した。だが魔王子とやらについて白い魔女は如何ほどのことを御存知か。ミッドランドが滅ぶというのであれば、言葉を曖昧にして濁す必要もあるまい」
宮廷にどよめきが起こる。平穏に慣れて安定だけを望む人々にとって、それは目を背け耳を塞ぎたい言葉であったろう。マルボルダスが魔王子マイユールの首飾りを望んでいると告げたときもそうであったが、白い魔女の言葉はそれにも増して曖昧に過ぎる。ウンスイにはその理由が一つしか思いあたらない。
「我らが挑み、打ち倒したのは魔人に唆された娘であった。あるいは奈落の王が力を望んだ魔法使いであった。魔王子イシュトラの名を口の端に乗せることを今になってためらうか」
黒衣の僧が追求する相手は白い魔女アルガラドではなく、宮廷の周囲に居並ぶ人々に向けてであった。奈落の王が自らミッドランドを訪れようとしているのであれば、いつまでも国の恨みなど抱えている場合ではないだろう。
奈落は七体の主によって統べられている。夜を象徴する四体の魔人カリン、シャコール、レレムそしてヴラドナは奈落の軍勢を率いている指揮官であり、世界が最も寒くそして暗い夜にうごめくものどもを連れて奈落の淵から湧き出してくる。
真の支配者は魔王子シスとマイユール、そしてイシュトラの三体である。伝承によればシスは最も邪悪な存在であり、蛇の姿をした巨人の女で四本の腕を持っている。マイユールは最も賢く美しい妖精の男に似ているが、その正体はカエルに呑み込まれたような姿をしている。そしてイシュトラは最も強い魔王子であり、ヤギとワニを組み合わせた怪物が炎に包まれた姿をしていると語られていた。
奈落の主は互いに争って自らの影響力を強めようとしているが、シスは最も強大な勢力を誇っている一方で現界に及ぼしている力は少なく、邪な蛇人を創造した後は奈落における彼女の地位を保つことに忙しい。マイユールは自ら力を及ぼすよりも闇エルフを導いたり、あるいはマルボルダスがそうであったように邪悪な人間を唆しておぞましい叡智を授けることを好む。
イシュトラは遥かに精力的であり、沼地で怠惰に暮らしていた大トカゲを立ち上がらせると武器を手にすることを教え、彼らをミッドランドに君臨させると共に自らも降臨することを望んでいるとされていた。
伝えによればミッドランドの何処かには奈落へと通じる深い巣穴(PIT)があり、トカゲ兵は彼らが巣の父と呼んで信奉する魔王子を迎えるためにこの地への上陸を企図しているのである。その時こそ、人間でも蛇人でも闇エルフでもないトカゲ兵の帝国がこの世界を統べることになるであろう。
「賢人ニカデマスや癒し手ペン・ティ・コーラ、そして魔術師ヤズトロモらが懸命になって巣穴を探していますが未だその存在は明らかになっていません。その間もトカゲ兵団はミッドランドを窺っている。彼らの足を留める者が必要なのです」
白い魔女はいっそう深々と頭を下げる。文明の曙と呼ばれる時代より、魔法を統べる者が自ら世界に力を及ぼすことは禁忌とされており、彼らは神々と同じく人を見守り英雄を助けることしかできぬのだ。導く者や教えを示す者ではなく、導かれる者こそ最も尊いことを彼らは知っているのである。
† † †
敵の襲撃と城壁警護の任務の合間をぬって、城の大広間に列をなして横たわる病院や負傷者たちの世話をおこなう。多数の負傷した戦士ばかりではなく、そこには流れ矢で傷ついたり栄養失調で倒れた女や子供も大勢いた。わずかに残った食料は厳重に統制されており、優れた計画性がなかったら、これほど長く食いつなぐことはできなかっただろう。
食料不足以上に悪いのは、慢性的な睡眠不足だった。石の砲撃と硫黄弾の破裂によって、どのみち充分に眠れないうえに敵は夜ごとに亡霊や悪魔を魔法で呼び出し、城のまわりで夜明けまでわめかせている。しばしばそれに襲撃が加わって、ほとんど絶望的なほどに眠りがさまたげられているのだ。
それでも今夜は、彼は眠った。夜更けまで、城の南塔で起きた大火事の消火を手伝っていたのだ。敵が防壁の射程距離外に設置した巨大な石弓のひとつから、燃えさかる薪の束が射こまれ、大火事になったのだった。火が消えると、彼は主塔の自分の部屋に戻る手間をはぶいて、空いた場所を見つけ、汚れたマントをひっかぶって眠りこんでしまった。
「断は下されたのです。すべての吉兆がそなたの上にありますように」
翌日、彼の母は厳格そうな顔を見せていたが、その目に不安が消えることはなかった。部屋の中の誰もが困惑と決意の混ざりあった複雑な気持ちをわかちあっていたが、この決定には全員がうなずいていた。
† † †
白い魔女アルガラドとの会談が王城の謁見の間で行われると聞いて、堅苦しさを嫌い近衛騎士団の兵舎に足を向けていた者たちがいる。火の蛮人ウェイ・ラスローは人が思うほどに野蛮でも未開人でもなかったが、そう思われていれば気楽なことが多く、豪放な振る舞い自体は彼の好みにも合っていた。
「それにしても、同じ魔法使いでも違うものだ」
「私は奇術師のようなものですからな。世界を導くのではなく世界に彩りを添えるが役目」
半分は皮肉のつもりで言ったのだが、サヴァンは気にした様子もなくおどけている。伝説の時代、魔法使いは互いに力を振るい争った挙句に多くの国を滅ぼしたとして、神々の伝承に倣い自らが人の世界に力を及ぼすことを禁忌とするようになっていた。死と破壊をもたらす炎は禁忌を恐れぬ邪な者だけが扱う、それが彼らの論理だがもともとサヴァンは魔法を彼の美学に沿う使い方をすることに意義を感じている。世界を導くことも世界を支配することも彼の好みではなかった。
兵舎には騎士団長シグルドソンが常の親しげな様子で、数名の兵士や戦士に声をかけている姿が見える。もともと白い魔女の護衛をしていたという剣士であり、堅苦しい宮廷どころか陣営の床几に座していることすら性に合わぬらしく、一見して彼自身も戦士の一人にしか見えなかった。
その騎士団長が数名を伴って客人たちに歩み寄る。カスパーを攻囲するトカゲ兵団の話は彼らの耳にも届いており、しぜん話題はミッドランドへの上陸を図る軍勢へと傾いていた。
「連中は人間よりも統率された兵団を率いる。カスパーは善戦していると聞くがそう長くは保つまい」
トカゲ兵は西にある火山島ロクスから海峡を越えてミッドランドへの上陸を企図している。彼らはカスパーを襲っているのではなく、温暖な気候と湿地帯を好む彼らがたまたま暖流に乗って上陸した場所にカスパーがあったというだけだ。
これまでもトカゲ兵が海を越えたことは幾度もあったが、大規模な軍勢を率いてのことではなく、突然の襲来に城壁は破壊されて人々は城の奥へと立てこもり、絶望的な状況で雇い入れた傭兵すら逃亡を図るようになっていた。放置すれば陥落は時間の問題であり、アーガイルはすでに救援の軍勢を送ることを決めてはいたが、それすらも間に合うとは限らない。
カスパーへの援軍は宮廷でも反対する意見があるが、貴族や高官は不平を言うだけで自ら行動することはないから即日の出立は間違いないだろうとシグルドソンは確約する。彼が求めたのは軍勢の出立に合わせて先発し、包囲網の攪乱を図る者と突破してカスパーに援軍の到着を知らせる任を図る者である。
アーガイルが兵を出したことを知れば孤立したカスパーの士気も上がり、呼応してトカゲ兵を挟み撃ちにすることも不可能ではない。シグルドソンの言葉にハインツ・シュタインは淡々とした様子でうなずいてみせる。
「戦士は勝利ではなく戦いを約束するものだ。戦いがあるならば戦場に身を捧げることを誓うことは容易い」
ハインツの言葉に、自分と同じ戦士の匂いを感じたのであろう。シグルドソンは面白そうな顔をすると、それまで傍らに控えていた若い戦士に視線を向けた。
「如何かな。彼の言葉は戦の神の恩寵にふさわしかろう」
「まことに。叶うならばテラクの信仰を抱く者として、戦士の腕を見せて頂ければありがたいですな」
貴族の子弟であるのだろうか、どこか気品を隠せないでいる若い戦士は背に下げていた長い剣を外すと、刀身を軽く手で叩いてみせた。その様子に私は戦士ではありませぬぞとおどけて言うサヴァンを押しのけるように進み出たのはウェイである。
楽しげな顔をした様子は明らかにハインツに先んじて遊ばせてもらうという意思の表れであったろう。火の蛮人は腰に吊るしていた短いイスパニア剣を抜き、傍らに立てかけてあった軍団兵用の大盾を構える。堅牢な守りから鋭い致命の一撃を狙う、それは未開の蛮人ではなく鍛えられた兵士が用いる伝統の技術だ。
若い戦士は蛮人の構えに応えるように、背に吊していた奇妙に長い剣の覆いを外すと両手で構える。波打つように見える刀身は飾りや儀礼のためではなく、戦場で兜を断ち割るために鍛えられた逸品であることを示していた。
互いが戦士の作法に則った挨拶の構えを取ると、火の蛮人は大盾に身を隠すようにして前進する。大力を活かして盾で押し込み、崩れた相手を剣で突く算段だがこれに構わず若い戦士も豪快に振り上げた剣を正面から打ち下ろすと、打ちつけられた刃先が盾の表面で弾かれて表面に深い亀裂を穿つ。遠慮の無い一撃に蛮人が押し込まれるが、下がることはなく雄叫びを上げると身体ごと押し返すように力を込めた。
「恨むのはなしにしてくれよお!」
押し込んだ盾の勢いで、互いに弾かれると同時に戦士は横なぎに二撃目を振るう姿勢を取り蛮人は右腕を突き込もうとする構えを見せる。だが次の一撃でどちらかが倒れることを知った彼らの動きが申し合わせたように止まり、武器を下ろすと互いの力量をたたえるように剣を正面に掲げてみせた。彼らは戦の神に戦士の技を捧げているのであり、殺し合いをしているのではない。
打ち合いが互角に終わったことに満足にも残念にも見える様子を見せて、一礼した下がったウェイに替わり今度はハインツが大振りの平剣を担ぐようにして進み出る。左肩から腕に腕甲をしているが盾は持っておらず、両手で握る剣だけで打ち合う構えを見せていた。若い戦士もこれに答えるように、長い剣をもう一度剣を構えると正面から対峙する。
戦士の打ち合いは儀式であるから小細工を用いず、互いの武器や盾を正面から全力でぶつけ合うのが作法である。力が及ばない者は弾き飛ばされて戦士にふさわしくない姿を見せることになるという訳だ。
「いざ、参ろう」
構えがそのまま合図となり、双方が前に進みながら大きく振り上げた剣を、全身の力で振り下ろすと剣と剣、刃と刃というよりも金属の塊同士が正面からぶつかり合う音が兵舎に響き渡る。耳ざわりな音がして、力こぶが大きく盛り上がるがどちらも一歩も引かず互いの剣が相手の剣を押し返そうとする。
力は双方が互角、だが波打つ刃の鍛えられた刀身はハインツの頑丈な平剣にすら勝り、刀身がわずかに曲げられたところに刃が食い込んでいる。そのまま押し合うが互いに一歩も引くことがなく、やがてどちらからともなく剣先が下ろされると満足げに息をつく。若い戦士が賛辞の声を上げた。
「成程。彼らであればカスパーを託すことができる」
戦士は頭を下げると自分はカスパーの王子テラク、戦神の名を授かった父王ターグの息子であると告げる。トカゲ兵団の攻囲は厳しく、ターグは城壁を挟み応戦しているが早々に二の門まで破られると傭兵団も崩壊してしまい、今やカスパーでは市民まで駆り出されて昼夜の抵抗を試みていた。
王子は使者としてアーガイルを訪れていたのではなく、城が陥落した際に王統を絶えさせぬため恥を忍んでアーガイルへと逃がされたのだ。ターグも彼の側近も王子が包囲を抜けることに成功したならば、戦いが終わるまで決して国に戻らぬようにと厳命している。
「他国の王を殺しておいて身勝手とお思いになって結構。父王の野心は性急であったとは思うが、私は野心そのものを否定する気にはなれない。負けて倒れればただの肉だが、戦わねば負けることすら叶わぬのだから」
テラクは戦いの神にあやかって授けられる名前であり、ウェイやハインツと打ち合った腕前を見ても王子がすぐれた戦士の技と力を備えていることが分かる。その戦士が王統を絶えさせぬために戦場から逃がされて、自らの国を救うために武器を振るうことが許されぬとあれば無念であったろう。
だからといって無責任に戦場に戻ることをすすめることができないことを、ウェイもハインツも各国を渡り歩いた経験から知っている。もしもカスパーが陥落し、ターグが倒れたときに王子がいなければ国が滅ぶのだ。カスパーの王子はカスパーを救う役目を彼が認める者に託さなければならない。
「これが我が城に伝わる宝剣フレイムストライクだ。私が戦場に赴くことができないのであれば、これを振るい我が国を救って欲しい」
テラクはそう言うとハインツの曲がった平剣に替えて自らの剣を差し出す。フレイムストライクはハインツの平剣よりも細いが長さでは勝り、見た目よりも遙かに重く振り回すには相当な力が必要である。炎を模した波打つ刃と、この重さであれば鎧でも兜でも易々と叩き割ることができるだろう。
テラクは戦士の作法として自分の剣に替えてハインツの平剣を受け取ると、捧げるように正面に掲げてみせた。ハインツも無言で受け取った宝剣を正面に掲げると、誓うように空へ突き立ててみせる。
「汝らに戦神テラクの加護があらんことを」
† † †
トカゲ兵はもともと温暖な湿地帯で、日光と泥水に皮膚を洗いながら怠惰な暮らしを営んでいた。ある時、彼らの前に燃え盛る炎の剣を持つ巨大なオオトカゲが現れて以来、トカゲ兵は二本の足で立つことを覚えて世界を彼らの文明に従えることが義務であると考えるようになった。
その燃え盛るトカゲこそが魔王子イシュトラの変身した姿であったと言われており、それまで沼地に草木を積み上げた巣に暮らしていたトカゲ兵が今では石造りの都市を設ける術を覚えている。カスパーを囲う陣営地すら小規模な町に等しく、天幕や柵、塹壕や見張り台が規則正しく並べられているだけではなく堅牢な石造りの建物がいくつも設けられていた。
巨体に頑丈な体躯、分厚い皮膚を持つトカゲ兵は優秀な戦士である。外見は手足が伸びたオオトカゲがそのまま二本の足で立ち上がっているかのように見えて、巨体を支えている足や尾は特に力強く見える。決して俊敏とは言えないが鈍重でも不器用でもなく、武器と盾を構えて襲いかかってくるが軽装でも厚い皮膚が鎧の代わりを果たすことができる。徒歩だけではなく騎乗用のオオトカゲ(Lizard)や恐竜(Dinosaur)にまたがっている例もある。
だが戦士としての優秀さよりも統率された軍団そのものがトカゲ兵の力であるとされており、彼らは常であれば障壁となる密林や沼地、塹壕といった地勢をものともせずに進軍すると城や町にも勝る陣営地を築き、いざ戦いになれば死を恐れず与えられた命令のままに戦う。
「戦争のことは分らないけどさ。アーガイルの援軍が到着したらトカゲ兵を倒せるの?」
「まともに戦えば無理だろうな。ドワーフやエルフの軍団は確かに強いが、人間は彼らに遠く及ばない」
ガラの素朴な問いにウェイは正直に答える。だがトカゲ兵の軍団は全員がトカゲ兵ではなく、実際にはほとんどが無様なオーク(Orc)の傭兵やオーガ(Ogre)の戦士で固められており、彼らは無秩序な雑兵でしかなく動揺すれば戦場を離れて逃げ出す公算が強かった。
奇襲か急襲をして混乱させることができれば、アーガイルやカスパーにも充分に勝機があるだろう。だからこそ先行する部隊が求められたのであり、彼らの任は重大だがやみくもに潜入を試みたところで成功する筈もない。トカゲ兵は誰も逃がさぬように厳重な包囲を敷いているし、カスパーは誰も通さぬように城壁を懸命に守っている、彼らはその中を突破せねばならなかった。
低く身を屈めるような姿勢で、滑るように駆けているガラをウェイとハインツが守るように従い彼らはトカゲ兵の陣営地に近い一角を横切っていた。騒ぎを起こして彼らを引きつけ、隙をつくる間に他の者たちが潜入を試みる算段である。
ガラたちの目論見は陣営から見えるところに火と煙を焚いてそちらに注意を向けようというものであり、少しでもトカゲ兵を誘うと同時に、城内でも煙に気がつけばそれが援軍の合図であると知らせることができるかもしれない。囮になる彼女たちと、包囲網を突破する者たちのどちらが危険であるかは容易に判断し難かった。
「周りには気をつけてね。ヒトとトカゲの感覚は違うから」
カスパーは海峡を流れている暖流の影響でミッドランドでも比較的気候が温暖な地域にあり、湾に面している城の周囲にも低い灌木や湿地が多く、本来であれば市壁や城壁の守りは堅牢と言うことができたがトカゲ兵にとってぬかるんだ地は彼らの庭である。灌木越しに見えている広大な陣営や、おぞましい軍勢の姿は情勢を危うく思わせるに充分なものだった。
彼女たちを辟易させたのは足下のぬかるみであり、トカゲ兵が陣営にわざと水を流し込んでいたことである。ぬかるみはトカゲ兵の障害にはならないが、人間であれば動きにくいことこの上なく足を取られるだけではなく足音も足跡も消すことが難しくなってくる。
ことにガラは火を焚くための薪わらを背に担いでおり、武器を持つ二人に荷を持たせる訳にもいかず、野馳りの生活に慣れているとはいえ若い娘に楽な仕事ではなかったろう。これではオークやオーガも苦労しているだろうにと不平を言うが、混沌の軍勢が雑兵の待遇をさほど気にするとも思えなかった。
苦労してようやく、固く乾いた地面を見つけると薪を積んで砕いた石の粉をかけてから手早く火種を移す。悠長に火をつけている暇はないから、あらかじめ火口箱に起こしていた火を使う。石の粉とわらがはぜる音がして、それが薪に燃え移ると濃い赤色をした煙が立ち上った。
「急いだ方がいいな。すぐに見張りが来るぞ」
細い目をいっそう細めたハインツが常と変らぬ様子で、それでも急かすように言う。入り組んだ戦場で方角は定めにくいが野馳りの方向感覚と戦士たちの嗅覚が頼りになる筈だ。ここまでは彼らの目論見通りことが運んでおり、陣営の奧へ突入を図るか、あるいは城壁にたどりついて状況を覆すきっかけとしたいところであった。
トカゲ兵は勇猛な兵士であり、雑兵には正面から無謀な突貫をさせながら彼ら自身も安穏としてはおらず最前線で塹壕を進み城壁にとりつこうとしている。攻防は日を置いて断続的に行われていたが、地下道を掘ったり水を流し込んで城壁を崩そうとする試みは途絶えることがなく、城内に休まる暇はないが軍勢は前線に集まっているから背後で小細工を試みて逃げるだけの算段はつけられる筈だ。
遠く城壁を囲っているおぞましい軍勢の姿を見やり、ガラは気があせるのを感じたがわずかに首を振ると塹壕の影に飛び込み、護衛の戦士たちを案内するように身を低くして駆け出そうとする。途端、黒々とした塊が視界の外から襲いかかると、小柄な身体の横腹に思いきり打ちつけられた。
「ぐっ・・・!?」
叩き飛ばされて、宙を舞う娘の体がぬかるみに落ちる。塹壕の影から鈍重に現れた巨体はふつうのトカゲ兵よりもさらに大きく、四本の腕を持つ変異種(Mutant)の姿をしていた。
イシュトラの混沌に身を捧げた代償として、トカゲ兵には生まれつき優れた能力や知性を持つ上位種が生まれやすい一方で劣悪な変異種も多く生まれていた。そうした変異種のたいていは奴隷や雑兵として扱われるか、それすら適わないものは気まぐれに叩いたり蹴飛ばされたりする存在にしかならないが、変異種であるからにはふつうのトカゲ兵より並外れた力を持つものもいてやはり地位は低いものの凶悪な戦士とされていた。
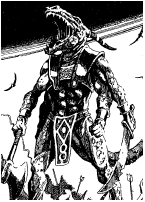
野馳りの娘は必死に起き上がろうとして成功せず、口からは赤黒い塊を吐きだしている。騒々しくわめき立てているオウムに警告されるまでもなく、このままでは変異種がゆっくりと振り上げた斧に両断されるのを待つだけだろう。
ハインツとウェイは同時に動き、腕甲の戦士がフレイムストライクで怪物に打ちかかると火の蛮人は小柄な娘を拾い上げて肩に担ぐ。乱暴な扱いに再び血を吐くがそこまではウェイの知ったことではない。ハインツの叫びが塹壕に響く。
「先に行け!」
「言われるまでもないな」
ウェイのイスパニア剣は短いが驚くほど鋭く、突き刺してひねるだけでたいていの生き物に致命的な傷を負わせることができる。蛮人にふさわしい大力と合わせれば娘を担いだまま戦うことも不可能ではないが今は少しでも早くこの場を離れることが先決だろう。
頭上でわめきたてているオウムの声を聞き流しながら、ぬかるんだ塹壕を走り抜ける。幸い、見張りのほとんどは立ち上る煙に向っているようであり、時折現れる無様なオークの兵士はウェイの相手にもならなかった。一日で六体のオークを殺したことは彼の記録となる。もっといればもっと記録を増やすことができたろうが、オーク・スレイヤーなど名乗ったところで名誉とは言えない。火の蛮人は娘を助けるために戦場を走り抜けたが、命を救われた当人は後に、生きていたことは幸運だが担がれている間は最も不幸だったと言っている。
変異トカゲ兵と対峙するハインツは仲間が無事に逃げることを知っていたが、彼自身もここで犠牲になるつもりはない。目の前の怪物は一体しかいないが戦いの喧騒が長く続けばすぐに他の見張りや兵士が集まってくるだろう。早々に勝負をつける必要があるが、一方でハインツは宝剣フレイムストライクを振るう機会が訪れたことに喜びを感じてもいる。
「愛するが如く戦う、この剣はそれに値する」
仰々しく構えると身体を大きく回転させるように、横なぎに宝剣を振るう。変異種は厳格に鍛えられた兵士ではなく、巨体と怪力で敵を蹂躙するだけの怪物であり、戦いの作法や技術を心得ているとは考えづらい。
ハインツは闘技場で熟達した剣闘士を相手にするときの感覚ではなく、猛々しい獣を相手にする感覚で打ちかかりながら素早く移動する。乱暴な斧や鉈の一撃はむなしく地面を穿つと穴を開けているが、すべての攻撃をかわしてみせるハインツにも外見ほど余裕がある訳ではない。一撃を受ければ怪力で吹き飛ばされてしまうだろう。
「どうした。こちらはまだまだ戦えるぞ」
言いながら波打つ刃を振るい、重い刀身そのものを叩きつける。変異トカゲ兵のばかばかしいほどの怪力はハインツのそれを遙かにしのいでいるが、渾身の力を乗せて振り回されるフレイムストライクは怪物の一撃に劣らない。
三撃目で受け続けていた斧の柄が折れると、四撃目が腕の一本を切り飛ばす。斧の次は腕、腕の次は脇腹に宝剣が叩き込まれて怪物は絶鳴を上げると巨体が大きな木のように揺らぎ、ゆっくりと崩れるように倒れた。
すでに方々から喧騒が近づいており、ハインツは彼らしくもなく慌てたように剣をひと振りしてこびりついた血を払うと塹壕の影に姿を消す。立ち上る赤い煙と何者かによる襲撃は、巨大な軍団にとってささやかな異変でしかないがカスパーを包囲するトカゲ兵の注意を引くことには成功したようだ。
† † †
堅牢な城壁に囲われているカスパーはトカゲ兵の海に浮かぶ小さな岩となっている。トカゲ兵はおぞましい怪物たちの中でもっとも統制が取れた集団であるとされており、混沌と無秩序の軍勢であるにも関わらず厳格な秩序と規律は人間の兵団をはるかに勝っていた。彼らの集団はアリの集落に似た性質を持っていて、集団を統べる一体に従い、他のトカゲ兵はすべて忠実な手足として行動する。
アーガイルから送られる援軍は先行する幾つかの部隊がトカゲ兵の包囲をかく乱して混乱を誘いながら、好機を見て攻めかかるという算段でいる。相手は多勢で統率がとれており、まともに戦えば勝てるものではない。
だがトカゲ兵が統制された集団であったとしても、彼らが雇い入れたオークやオーガの無様な集団はそうではない。アーガイルの動きをカスパーが知ることができれば、城の外と中から挟み撃ちにして怪物どもを混乱させることは充分に可能だろう。そのために潜入することが彼らの目的である。
「ロクスのトカゲ兵はノーブルと呼ばれる王に率いられているが、上陸した軍勢にそれはおるまい。別のトカゲ兵が指揮官を務めているだろうな」
「じゃあそれを倒せばいいんだね」
正直すぎるマキの物言いにガルドは苦笑する。彼女の言う通りではあるのだが、陣営の奥にいるだろう長をかんたんに討てるとは思えない。
だが笑いながら、粗雑な作戦に案外価値があるかもしれぬと考え直してガルドは表情を改める。トカゲ兵の軍勢を突破するという彼らの任務がそもそも危険なものであり、どうせ危険ならば大きさ重さを区別する必要はないかもしれない。
「いかがかな。ウンスイ殿はどう思われるか」
「拙僧の国では尊き結末は尊き振る舞いが成すとは申す」
英雄にふさわしい行いをしようとした者だけが英雄になることができると、黒衣の僧がしかめつらしい顔で答える。彼らはすでにカスパーを包囲する陣営地の外側にまでたどり着いており、別の部隊が周囲をかく乱するのに合わせて侵入を試みるつもりでいた。
トカゲ兵もオークやオーガの雑兵たちも含めて、兵士のほとんどは城壁にとりつこうとしており思いのほか陣営地に残っている兵は少ない。アーガイルの援軍を知れば怪物どもは後方にも兵を向けるであろうが、彼らの好機はその狭間にあるのではないかと思える。
塹壕の影を利用して、ぬかるんだ地面を踏みながら駆けるように進んでいたガルドの足が止まる。哨戒の兵らしい、トカゲ兵の姿が現れてこちらを見ると激しくわめき立てて手にしている鞭を振り上げた。とっさにサヴァンが被っていた帽子を脱ぐと、奇妙な緑色のかつらを被る。
「俺たちは怠けていたんじゃねえ!これから城を攻めるところだ!本当だぞ!」
その言葉にトカゲ兵はさらに憤慨した様子になるが、振り回した鞭を彼らではなく地面に何度も打ちつける。サヴァンの言葉がトカゲ兵には通じているらしく、怠け者の雑兵にさっさと城に向かえと怒鳴り散らしているらしかった。
軽装に外套を羽織っているガルド、鉄塊のような大剣を背負っているマキ、異境の黒装束に編み笠を被っているウンスイ、そして片眼鏡に緑色のかつらを被ったサヴァンという一行は一見して奇妙にしか見えないが、実のところトカゲ兵は尻尾がない者の外見などほとんど区別することができないのだ。かつらの上に帽子を乗せて、サヴァンが仲間たちを急かすように追い立てると哨戒のトカゲ兵は相変わらず何かがなり立ててはいたが、こちらを追ってくる様子はない。
姿が見えなくなる程度まで走り続ける。なんとか逃げられそうですなと、やれやれといった風情でおどけてみせる魔法使いにマキが尋ねるように口を開いた。
「トカゲ兵ってあんなものなの?」
「いえ。ですが皆様にもオークの顔の区別はつきますまい?」
「ふーん。なら伝令だって言えば好きなところに行けるよね」
何気ない言葉に全員が足を止める。マキがかんたんに言ってのけるほどに、雑兵が陣営を好きに歩きまわって咎められることがないとは思えない。現実的な話だとは思えないが、だがトカゲ兵に連れられた雑兵であれば話は違ってくる。先ほどトカゲ兵と言葉を交わしていた魔法使いが哨戒のトカゲ兵に化けることはできないだろうか。
「魔法使いはそこまで万能ではありませんぞ。残念ながら私の姿をトカゲ兵だと思い込ませるのがせいぜいですな」
それが化けることとどう異なるのか、サヴァンの言葉は他の三人には理解し難い。
トカゲ兵の陣営地は人間のそれに似ているが、単に天幕を並べているだけではなく堅牢な石造りの建物がいくつも建てられていて小さな集落よりもよほど立派なつくりをしている。水に満たされた塹壕があちこちに掘られているが、それが守りになると同時にぬかるみを好む彼らが移動するためのすぐれた手段にもなっていた。
だがすべての塹壕を水で満たしてしまえばオークやオーガといった雑兵の移動にも不都合を生じるから、トカゲ兵たちは尻尾がない連中の鈍重さを軽蔑しながらしぶしぶ水を浅くした箇所を設けている。
「トカゲ兵は統制された軍団だからこそ指揮官がいる場所も決まっている。探すこと自体は難しくないだろう」
「問題はたどりつけるか否かであるな」
先頭をどかどかと歩いているサヴァンの後ろ姿に目を向けながら、ガルドとウンスイが言葉を交わす。先ほどのかつらを被ったままで、尾のつもりらしい、杖を腰の後ろに下げていることを除けば魔法使いの姿は常と変らなかった。
化けるのではなく見た者にトカゲ兵だと思わせるとはこういうことかと納得するが、これで本当にごまかせるのか、そこは任せるしかないであろう。
「ですがトカゲ兵の言語は身振りと、何よりも尻尾の位置で細かい意味を現します。私の術でもそこまでは難しい」
海に暮らす者は魚を種類や大きさで分けて呼ぶが、山に暮らす者にはどの魚も魚である。トカゲ兵であれば沼やぬかるみの状態をいくつもの言葉で呼び、しかも水音の多い場所で身振りを含めて表現する。だからこそ彼らは尾や四肢が不充分な変異種や、尾を持たぬ生き物を心から蔑んでいる。
ぬかるんだ塹壕をびしゃびしゃと音を立てながら進む。小細工のためにわざわざマキの首にひとくくりの縄を巻いて、引っ立てるように連れているがこれはやりすぎだったろう。
本陣とおぼしき建物はすぐに見つけることができて、陣営地の中央に設けられている石造りの正面には衛視らしいトカゲ兵が立っている。ここからは賭けである。飛び込んだ本陣に目的の相手がいないか、またはあまりに多くの護衛が詰めていれば助かる術はないだろう。
「さあ!ここからがカーテンコールだぜ!」
「承知!」
雑兵を連れた哨戒の兵がどかどかと本陣に近づいてくる、衛視は当然のように騒ぎ立てているが無視をして駆け出すと、先んじたウンスイが一方の懐に飛び込んでルーンの棒を突き立てた。厚い皮膚を一撃で貫くことはできなかったが、怪力で振り回される長槍もこの近さでは扱うことができない。
黒衣の僧は足の裏で思い切り蹴りつけると、今度は脇に回り込んで柔らかい場所を狙う。大きく振り回される尾が横なぎに襲いかかるが、これを下がるのではなく屈みこんで避けてみせた。マルボルダスの骸骨暴竜に襲われたときを思えば、はるかに楽なものだろう。無礼な侵入者にもう一匹のトカゲ兵も長槍を振り上げると、皮膚が厚いトカゲ兵は相討ちを恐れず、仲間ごとウンスイを切るつもりでいることが分かる。
「棒を!ゴムに!」
サヴァンが叫ぶと同時に長槍がだらりと垂れ下がって用をなさなくなる。驚いているトカゲ兵の間を抜けるように、マキとガルドの二人が建物に駆け込むと入口をふさぐようにウンスイとサヴァンが立ちはだかった。彼らが時間を稼ぐ間に、ことを済ませなければならない。
マホウ剣士を自称する娘は走りながら大剣に巻きつけていた布をほどくと、迷うそぶりもなくただまっすぐに駆けて奥へと向かう。表の騒動を聞きつけたのであろう、奥の暗がりから二匹のトカゲ兵が姿を現した。いや、二匹かと思った頭は一つの胴体につながっており、それが双頭の司祭(Bishop)であることに気付く。

トカゲ兵の社会で変異種はほとんどが蔑まれていたが、例外として双頭のトカゲ兵は生まれつきすぐれた知能を持ち司祭として高い地位を約束されていた。片手には曲がりくねった短い剣を、片手には鎖につながれたドワーフを引きずっており、この司祭がカスパーを陥落させる軍勢の指揮官として「儀式」を行う最中であったことをうかがわせる。
駆けこんだ勢いを弱めることすらなく、マキは大きく振り上げていた大剣を真正面から振り下ろした。トカゲ兵の怪力とはいえ、容易に防がれるとは思えなかったが双頭の司祭は短い剣の一本でこれを受け止めると刀身から吹き上げるような炎が巻き起こる。
火はイシュトラの象徴であり、怪物どもが信奉する魔王子の力である。すかさずガルドがマキの背後から変異種の脇腹に回り込むと、二本の短剣を突き立てるがドワーフごと振り回された鎖で弾かれてしまう。二つの頭を持つ司祭は二人の斬撃を別々に認識して戦うことができる上に、マキはドワーフに当たることを恐れて思い切って切りかかることができずにいる。
「これじゃあ二対二じゃなくて二対三じゃないか!」
ザンバと呼ばれる大剣を、ドワーフの逆側から横なぎに振るが双頭の司祭は炎の剣で受け止めてしまう。巻き起こる火にもマホウ剣士はひるまないが、少しずつ肌が焼かれて腕がしびれを覚えていくのが分かる。
大剣の一撃を受けながら、司祭のもう一方の頭はガルドに向けて鎖を振り回すと、小柄なドワーフの身体を武器として叩きつける。白の狩人は飛ぶようにしてこれを避けるが、地面に打ちつけた身体から骨がくだける音がひびき、思わずマキが顔をしかめるがガルドは平然として叫んだ。
「ドワーフよ!お前の力を貸せ!」
彼らの忍耐と頑健さには並ぶ者がない。誇り高い大地の妖精はくだけた身体で地面にしがみつくと、双頭の司祭が振り上げようとした鎖が止まり左腕ががらあきになった。
すかさずガルドが無防備な左側から飛び込み、突き出された二本の短剣がすり抜けると一本はトカゲ兵の分厚い皮膚に阻まれるが一本があばら骨の隙間を貫いて心臓まで達する。二つの頭が二つの悲鳴を上げて、耳まで避けている口から音が途絶えると火の消えた剣が落ちてから怪物の身体がゆっくりと倒れ込んだ。
周囲が急に静かになり、しばらく無言のまま息をついていたが白の狩人は古い文字が刻まれた短剣を拾い上げる。振り返るとドワーフの身体に歩み寄るが、すでに動かない大地の妖精は彼が生まれた地面から今も手を放そうとはせず、その顔には勝利を確信した者が浮かべる会心の笑みが見えた。
「助からぬことは分かっていた。だがドワーフは満足したであろう。人はそうかんたんに割り切ることができないが、大地の妖精が身を賭して怪物を倒したことは疑いない」
陣営の外ではわずかだがそれまでとは異なる喧騒が聞こえはじめている。ただ一匹の指揮官によって強力に統率されているトカゲ兵はそれが倒れれば混乱して解体するしかない。軍勢は崩壊して包囲は解け、アーガイルの援軍が合流してカスパーは救われるであろう。
ミッドランドへの上陸を企図していたトカゲ兵はその足がかりを失い、人間は彼らの野心をくじくためにロクスの火山島を探ることができるようになる。戦いで失われた魂が戻ることはもはやないが、彼らの犠牲は決して無駄になることがない。
英雄は一人ではなく、尊き行いをした者はその資格を得ることができる。白い狩人と、大剣を担いだ娘はカスパーを救った英雄の小さな身体にそれぞれの作法で祈りを捧げると、丁重に抱え上げてから陽光が照らすミッドランドの大地へと視線を向けなおした。
...TO BE CONTIUNUED
>第四の石版の最初に戻る