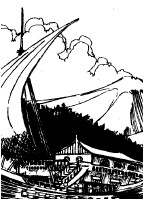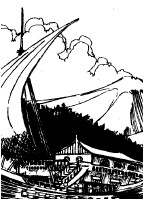SCENARIO#10
海峡を渡り、長くにおよびカスパーへの攻囲を続けていた爬虫類の軍勢が唐突に混乱の渦中にたたきこまれていた。トカゲ兵(LizardMan)の指揮官が軍団を従える方法は多くの賢人が試みて未だ明らかにされていなかったが、双頭の主が英雄たちの手で倒されると同時にすべての支配が解けたかのように統率が失われてしまっていた。
最前線で塁壁を突きくずしていた兵士は丸木を何本も並べた巨大な攻城器をひきながら呆然と立ちつくし、陸でも空でも恐竜(Dinosaur)の背にまたがる兵士は一散に戦場を逃げだそうとしている。雑兵として使役されていた、無様なオーク(Orc)やオーガ(Ogre)の兵士だけが猛りくるう無秩序のままに武器を振るっていたが、彼らも彼ら自身を率いるトカゲ兵が混乱するさまを見てやがて事態の急変をさとる。
たびかさなる襲撃に耐えた堅牢な砦をのぞむ戦場に、鬨の声がひびきアーガイルの援軍を連れたカスパーの王子テラクが馬上に剣を閃かせる。曙光を照り返している、折れた平剣は王子が戦士から譲られた武器であり、決死の使者となり傷つきながらもなお戦う姿にふさわしかった。勝敗が決して邪な軍勢が追いはらわれると、疲労すら忘れた人々が城壁や城門の上に駆け上がって空をふるわせる歓声がわきおこる。馬を駆る騎士たちが次々と城に迎えられた。
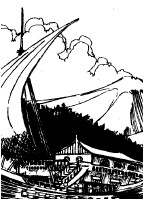
カスパーの救援にこたえて兵を出したアーガイルと両国の間で修好が確認される。アーガイルの王ソーステインを暗殺したカスパーの王ターグが既にトカゲ兵団の矢に倒れ、命を失っていたことが皮肉ながら事態を円滑に進める役に立っていた。
ターグは愚かであったかもしれないが、野心にふさわしく勇敢で危難にあっても恐れを知らず、トカゲ兵団から国を守ろうとした姿に民の信頼も厚い。アーガイルの貴族や重臣には修好に不満を示す者も少なくなかったが、白い魔女アルガラドと騎士団長シグルドソンの決定に渋々ながら従っている。
カスパーを襲った災厄と王の死を受けて、それでもなお邪悪の軍勢に対抗したカスパーを鞭うつことは邪悪に加担すると思われかねないとの打算が説得に力を貸した事情もあるが、のこされた王妃と王子に従いカスパーを守り抜いた人々に示された敬意に嘘はなかった。
「でももう少し暴れたかったよねー」
「そう言うあんたはそもそもどこにいたんだよ」
城内はあちこちが補修されており、方々には人が詰めていた気配や戦いの喧騒がいまだ残されているように思われる。騒々しく飛びまわりながら陽気に笑っているホーリィ・スプリングはいかにも無責任な妖精(Pixie)らしく、カスパーを攻囲から救う重要な任務ではどこかに姿を消していたにも関わらず、すべてが解決するといつの間にか現れて騒ぎに加わっていた。
大剣を横たえて腰をおろしていたマキが呆れた視線を向けているが、妖精に固いことを言っても仕方がないよとホーリィ自身が堂々と言ってのける様子にあいた口がふさがらない。だが妖精が笑いながら陽気に飛びまわっている事実そのものが、この国が救われた証拠であり、むずかしく考えるのは確かに彼女の性に合わなかった。
「まあ、何よりだね」
一行は城内に設けられている陣幕で身を休めていたが、広間ではカスパーを守りつづけた女王と王子テラクがアーガイルの騎士団長シグルドソンと謁見をしているはずである。周囲の喧騒は戦勝に沸きかえっているためばかりではなく、傷ついた者を救い底をついた食料を運びこまなければならず平穏とはほどとおい。撃退されたとはいえトカゲ兵団の残党はいまも周囲に徘徊しており、式典も略式でおこなわれていたが互いに過去の経緯を忘れてミッドランドを襲う危難に対抗することが確認されていた。
トカゲ兵の指揮官を打ち倒して城を救った英雄たちの名は知られることがなく、カスパーではあくまで決死の囲いを破った王子テラクがアーガイルの助けを得て軍勢を追い払ったのでなければならない。その事情を彼らは充分に心得ていたが、ひとつだけ主張して譲らなかったのは双頭の神官と相打ちになって果てたドワーフ(Dwarf)の勲を讃えることであった。
「死者を讃えるに国の思惑はいらぬからな」
「左様。真に讃えられるべき勇気を人は忘れてはならぬ」
数日前までは落ちかかる矢と飛来する怪物の姿に悩まされていたであろう空に視線を向けながら、白の狩人ガルド・ミラが呟くと目深にかぶっている編み笠に視線を隠していたウンスイがうなずいてみせる。彼らの目的は人々の歓呼を受けることではないが、彼らが崇敬する行為に人々は歓呼を与えるべきであろう。
カスパーを救うことはミッドランドへの上陸を企図するトカゲ兵の目論見をはばむことであり、魔王子イシュトラの到来を阻むことである。かつて沼地に暮らす大トカゲでしかない彼らに文明を与えたのはイシュトラだが、侵攻と征服を望むトカゲ兵の帝国は海峡と寒冷地の気候によってのみ隔てられているのが実状だった。
ミッドランドから海峡をこえた西にある火山島ロクス。海流の影響により温暖な気候につつまれている孤島はトカゲ兵の世界であり、本来、人間があえて乗り込むべき理由はない。だがトカゲ兵がミッドランドへの上陸を試みて、魔王子イシュトラが訪れるのであれば無視できる話ではなく、その手がかりを突きとめなければならなかった。
「連中の目的がカスパーをおとすことじゃないなら、城攻めに参加していないトカゲ兵もいるんじゃないかな」
野馳の娘がガルドたちの会話にわりこんでくる。ニン・ガラは若い娘ながら屋根をもたぬ生活を続けて長く、その時間は白の狩人にくらべればとるに足りないが空と大地に日々を捧げていることではいささかの違いもない。トカゲ兵の残党を追うための出立を彼らが遅らせていた理由は、王子テラクの入城を待っていたことと先の戦いで傷を負った彼女が癒えるのを待っていたためであった。
どくろ沼で見つけたアンセリカの実は、治癒の力をもつ白魔術の材料として珍重されているが、これがなければ今しばらくは寝台から起きあがることもできなかっただろう。治ったというには遠く、ときおりむずかしい顔を見せているが、ただでさえ戦乱で傷ついた者が多いカスパーで呑気に仲間たちの出立を見送るつもりはガラにもなかった。
† † †
上陸したトカゲ兵の軍勢はカスパーを囲う陣営地をもうけると攻城戦をつづけながら、そこを橋頭保として内地への進出を試みていたらしく斥候と思わしき集団の姿がたびたび確認されている。彼らを追跡してその目的を探ることはガラやガルドら野馳りが得意とする分野であった。
先行する二人に魔法使いのサヴァンが従い、少しはなれてマキやウンスイがこれを追う。トカゲ兵の軍勢はふつう彼らがひそむに適した水壕を掘りながら侵攻するが、陸地であれば荷役用の獣を連れて移動することも多い。相手が集団であれば機先を制するため魔法使いの機知に頼りたいところである。
カスパーで聞いていたうわさに従い、数日も追跡すると荷車を曳いたわだちの跡を地面に見つけることができる。方々にはトカゲ兵に特有の尾をひきずった跡も残されていて、更に二日ほども追った視線の先に巨大な黄土色の鈍重そうな獣を駆る一団を見つけることができた。
荷物をいっぱい積んだ荷役獣のむれを、十二人ほどのトカゲ兵たちが警備している。トカゲ兵は木の鞍の上から用心深くあたりを見まわしている。ガラたちは見つからないように身を伏せると、ここはわたくしの出番とばかり魔法使いが大げさな身ぶりをまじえて近づいていく。
緑色のかつらをかぶると腕をふり足で地面をびしゃびしゃと叩き、尾のあたりに吊した杖を動かしている姿は一見して滑稽にしか見えないが、沼地に暮らすトカゲ兵の言語は身ぶりと音が様々な意味をあらわしている。トカゲ兵を相手にサヴァンがどのような話をもちかけているか、まるで見当もつかないが荷役獣の背にいる小柄なトカゲ兵がなにやら騒ぎたてると、明らかに雲行きがあやしくなっていく様子にたまらずガルドが声をかけた。
「大丈夫なのか?連中、いきり立っておるようだぞ」
「これは迂闊。わたくし、南方のトカゲ兵をよそおっておりましたが彼らの中に当の南トカゲがおりました」
「来るよ!」
ガラが叫ぶと同時にトカゲ兵のひとりが手にした鞭を振りあげる。ただごとではない様子に、隠れていたウンスイやマキが駆けだすと、トカゲ兵も荷獣の背に鞭をおとして激しくあおりたてた。
振りまわされる尾に巻きこまれてはたまらないと、ガルドとガラがすばやく飛びすさると入れ替わりに斬馬刀を担いだマキらがあらわれる。トカゲ兵たちは獣の背でいっせいに長弓を引くと、一メートルもある矢をはなってくる。
「考えるな!感じるんだ!」
豪快に振りおろされた鉄のかたまりが荷役獣の分厚い皮膚に叩きつけられた。鈍重な獣がどれだけ痛みを感じているか疑わしいが、咆吼をあげると暴れまわり背中のトカゲ兵を振り落とそうとする。あわてて手綱を引くが、獣の首につながれていた皮ひもが奇妙に結ばれていて狼狽する。妖精がしてやったりの笑いを浮かべる。
「妖精は結ぶのとほどくのが得意なんだよ」
「好機!」
すかさず荷役獣の背を軽快に駆けあがったウンスイが、ルーンの棒を獣の頭に突きたてるとハッソウトビと呼ばれる八幡の技で別の獣へと飛びうつる。いくら鈍重な獣とはいえ、胴を打たれて気づかずとも顔を打たれて怯えぬものはいない。ふだん顔を打たれることがない巨獣であればなおのこと、いきり立って暴れまわり背中にトカゲ兵を乗せていることなどとうに忘れていた。
数頭の巨大な獣が立ちあがり転げまわって、黒衣の僧だけが羽根のように飛んでいる。手綱がからみついたまま振りおとされたトカゲ兵は無惨にもほとんどがつぶされてしまった。厚すぎる皮膚に守られた荷役獣が、鞍と乗り手の残骸を引きずりながら逃げていくと、かろうじて生きていた数体のトカゲ兵も戦意など失われてしまう。かつて沼地で暮らしていた当時のように四つ足で地面に這いつくばる生き物を器用にしばりあげながら、サヴァンが感心した顔をしてみせた。
「さすがですな。黒衣の影をトカゲ兵が恐れておりますぞ」
「爬虫類に讃えられても喜んでよいか分からぬ」
冗談めかして言うが、いずれにせよ上陸したトカゲ兵の残党を追ってこれを撃退すると同時に、生き残りを捕らえることもできたのだから上出来というべきであろう。黒衣の僧を迷信的に恐れるトカゲ兵への尋問もたやすく、彼らの目的を容易に聞き出すことができた。
海峡を西にこえた火山島ロクスにある、トカゲ兵の帝国からミッドランドに上陸した彼らの目的がダークウッドの森にあること、海を渡るために殺し屋アブダルひきいる海賊の助けを得ていることを知らされる。南トカゲはもともと海賊の一味であり、南方の海を荒らしまわっていたが縄張りを広げることを餌に内海に呼ばれていたらしい。トカゲ兵はあくまでミッドランドに兵を送り、ダークウッドにたどりつけばそれでよいのだという。
「魔王子の巣穴は暗い森にありか」
「でもあそこはヤズトロモもなにも言ってなかったよ」
ウンスイの呟きに、ホーリィがダークウッドを見張る魔術師の名をあげる。魔術師はダークウッドの端に塔を立てると森を世話するエルフや、ストーンブリッジのドワーフらの助けを得て邪な勢力があふれ出ぬようにしていたが、それは主に地下に暮らす闇エルフ(Dark Elf)に備えてのことと思われていた。
奈落につづく巣穴の存在にはヤズトロモですら気がついていないのかもしれない。妖精の言葉に悩んだ一行はまずはアルガラドに借りたオウムを飛ばして警告を伝えることに決める。気がつけば長く旅に同行していた友人と別れることに、ガラなどはいたく残念がったがこのさいは仕方なかった。
足輪に書状を入れたオウムが空に消えていく姿を見送りながら、火山島に渡る船を借りるために港町ラーヴングラスへと足を向ける。アーガイルが用意した船を受けとるために、先んじて幾人かが無秩序と混沌の町に向かっているはずであった。
† † †
ソルウェイ湾に面した港町ラーヴングラスは名目上はアーガイルに属しているが、誰もそのように考えてはおらず独立した都市と思われている。だが無秩序な町を統治、または支配する者はおらず悪意の神スラングの寺院が勝手に自治を行っていたり、船乗りや商人の組合がたがいを守るために協定をむすんでいたり、地下の水路では魚人(Fish Man)が集落をつくり裏通りに入れば衛兵と称するトロール(Troll)がその日の気分で護衛料を巻きあげているようなありさまだった。
皆に先んじてハインツ・シュタインがこの町に向かっていたのは、アーガイルが用意した船を受けとるためだったが傭兵として長く暮らしてきた身としてはにぎやかなカスパーの式典を嫌って早々に出立していたという事情もある。
そのハインツよりも更に早く、猛女の弓フールフールが酒場にいりびたって酒樽のようなドワーフの身体にエール酒を流しこんでいた理由は、彼女なりに海賊の様子について探ろうとしていたのかもしれないが、あるいは単にラーヴングラスのトロールと派手ないさかいを起こそうとしていただけかもしれなかった。何しろドワーフとトロールが仇敵の間柄にあることは今更である。
「うわさではアブなんとかいう海賊がソルウェイ湾の近くまで出ばってきているらしい。わざわざ南からご苦労なことだ」
木製の大ジョッキを、まるで小さな杯のように無造作にあおりながら酒樽女が笑ってみせる。海賊のうわさを耳にしたフールフールはもっと詳しい話を聞こうと、この酒場で待ち合わせをしているが、ちょっとした問題があるので手を貸してくれるとありがたいとのことである。
とうとつな頼みにハインツには何のことやら見当もつかないが、人相の悪い用心棒を何人も連れてあらわれた、ジアミル・エル−ファズークと名乗る男を見るにどうもまっとうな事情とは思えない。たくましい男たちが主人を守るように後ろにならんでいる。

良心的な商人を自称するエル−ファズークはミッドランドの港から港をめぐり、手に入れるものは何でも手に入れるし売れるものは何でも売ってやろうと豪語している。もちろんお前たちが欲しい情報も売ってやるという、尊大な態度にハインツは心の中で腹をたてるが、ドワーフ女ではあるまいしこの程度でなぐりあいをする理由にはならなかった。
商人がいうには殺し屋アブダルの呼び名で知られているミッドランド南方の海賊が、火山島のトカゲ兵たちにそそのかされてソルウェイ湾の近隣にはびこっているらしい。この湾は最近まで悪魔魚と呼ばれる怪物が跳梁して、船そのものが減っていたから海賊も身をひそめていたが、アルガラドの難題を解決した英雄の働きで平穏になってからは船の往来が増えていた。自分もそうした船の持ち主のひとりだとは、尊大なエル−ファズークの言葉である。
ここまでは単なるうわさ話でしかないが、殺し屋アブダルに襲われた船と売りさばかれた奴隷のゆくえを知って、海賊の根城と船の居場所をつきとめることができたという。命がけで手に入れた情報だというが、エル−ファズーク自身が船荷と奴隷の取り引き相手であったことは疑いない。海賊と商売をしてその海賊を売るのだからかなりの悪党である。
貴重な情報だからかんたんに教えるわけにはいかないと商人の目つきが変わる。金貨二百枚が相場だと、あきれる値段を持ちかけるがフールフールは取り合うそぶりも見せず豪快に笑ってみせた。
「貴様などに金貨一枚も払うつもりはないぞ!いいから知っていることを全部話せ」
どうやらこれは交渉ではないらしいと、理解したハインツはフールフールにすべてを任せることにする。問題があるので手を貸してくれ、ではなく問題を起こすから手を貸してくれというつもりなのだ。
面白いことをいうドワーフだと、エル−ファズークの口調が険悪になるが面白いなら大声で笑えと酒樽女は気にした風もない。商人の背後にひかえている男たちの中から筋肉のかたまりが身を乗りだしてくるが、どう見ても人間ではなくオーガの血がまざっていた。ハインツよりも頭ふたつ、小柄なフールフールに比べれば倍程度は大きくみえる。
時ならぬ見世物の気配に周囲の耳目があつまり、酒場の主はすでにカウンターの後ろに避難して負けたほうから損害額を巻きあげるつもりでいる様子がわかる。ハインツは腰を浮かしかけるが、ここはまだ自分が出るべき幕ではないだろう。トロールを心の底から嫌っているドワーフだが、どうせオーガのことも嫌っているに違いなく、無責任な賭けに参加してひともうけしたいところだが今はおとなしくしておく必要があった。
「さあこい、ばかものめ!」
血管を浮きあがらせて、オーガのチャンピオンが無造作に振りおろした拳をドワーフは両手でがっちりと受けとめた。もりあがった力こぶが腕というよりもまるで脚のようで、酔客がどよめく声が響く。
オーガは空いた左腕でなぐりかかろうとするが、フールフールは掴んだ拳を思いきり押しこむと相手がよろけたところで腹に頭突きを入れる。身をかがめたオーガを持ちあげて、天井をふるわせるどら声を張りあげると商人がいるテーブルにほうり投げた。オーガの下敷きにされたエル−ファズークの顔は赤を通りこして紫色になっているが、ドワーフ女はこれで金貨百枚にはなったろうと笑ってみせる。
テーブルと筋肉のかたまりに潰されてもがいている主人を助けるべく用心棒が一斉に立ちあがり、酒場の外にひかえていた護衛たちも踏みこんでくる。人相の悪い男たちが五人、六人と酒樽女に近づこうとする前に重い剣の一撃が床に打ちつけられた。ゆっくりと立ちあがったハインツが、鞘にしまいこんだままの大剣フレイムストライクを威圧するように担いでみせる。
「お前たちの顔は気に入らないな」
かつてそのような挑発をする戦士がいたことを思い出していたハインツは、鞘のままの大剣を竜巻のように軽々と振りまわす。当てるつもりはなく、恐れさせるために幾つかのテーブルを粉みじんにすると、その間にフールフールが転がっていた商人を抱えて酒場から運び出してしまった。
あまり英雄らしい行為とはいえそうにないが、面白かったことは否定できず堅苦しい式典に参加せずによかったと思いながら裏路地を幾度かまわってドワーフ女と合流する。すっかり観念したエル−ファズークから貴重な情報を絞りだすと、謝礼に三枚ほどの金貨を握らせた。フールフールが百枚で自分が九十七枚、あわせて金貨二百枚というわけだ。
† † †
悪名高い殺し屋アブダルは極悪非道で知られる海賊で、相手が船でも港でも海沿いの街道にいてもためらわずに襲いかかると荷物はすべて奪いさって人間は皆殺しにしてしまうが、もしも抵抗する者がいれば活きがよいからと捕まえて奴隷に売りさばいてしまうような人物だった。
あくどく稼ぎまわっているが船は一隻しか持っていない。船員はミッドランド南方の出身者を中心とした数十人ほどで、海賊としては決して大きい集団とはいえないが神出鬼没で身を隠されると追跡がことのほか難しかった。
その海賊の船と根拠地の情報をいったいどうやって手にいれたのか、ハインツは黙っていたしフールフールは親切な商人に聞いたのだと言うだけだがおよそ想像はできる。
アーガイルの軍船は二隻用意されて、一隻がアブダルを追いながらもう一隻が根拠地を襲撃することに決めるとソルウェイ湾から数日をはなれた小島へと舳先を向ける。接近する船の存在を知られて海賊に逃げられては意味がないから、風も波もない夜を選んで小舟にうつると海流を使って島に近づく。夜明けとともに軍船を上陸させる算段で、それまでに海賊の根拠地を制圧するか逃げられないように港を焼かなければならない。
「・・・はずだったのにねえ」
呑気なほどに陽気な声で笑っている、ホーリィの小柄な身体が麻ひもで幾重にも巻かれていた。土壁の地下牢に押しこめられている、ウンスイやガルドも似たような状態でマキにいたっては縛りあげられた挙げ句に暴れまわったのが災いしてかえって絡まった縄が二度とほどけそうにないありさまだった。
彼らは夜陰に乗じて上陸すると、身をひそめて海賊が根拠地にしている小島の様子をさぐり、船が近づく頃合いをはかって火を放つ手はずでいたが、砂浜を数百メートルも進んだところでだしぬけに足下の砂がくずれると、地面の穴からあらわれた凶暴なオオヤシガニ(Giant Cococrab)に襲われてしまう。
ハサミをのばしてつかみかかろうとする怪物と打ちあっている間に、騒ぎを聞きつけた海賊が駆けつけると数十人に囲まれてしまう。こうなれば多勢に無勢であり、ひとくくりにされると牢に放りこまれてしまったが、首領がおらず、怪物がうろつく夜だからこそ捕まるだけで済んだものの夜が明ければあまり考えたくはない結末が待っているだろう。
「しかし一生の不覚である」
「不覚は皆が同じであろう。とにかく夜が明ける前に逃げ出さねば無事に済むまい」
ウンスイとガルドはそういいながらも縄を抜けだす術がないかと苦闘を続けていた。彼らが放りこまれた牢は切り立った土壁に口をあけている天然の洞窟で、明かりもなく入り口は頑丈な格子戸でふさがれている。全員が縛られて武器も取り上げられており、外には数人の見張りの姿が見えるが手足さえ自由になれば妙策が浮かぶかもしれなかった。
結ぶのとほどくのが得意だといっていたホーリィだが、妖精にかぎらず魔法には複雑な身ぶり手ぶりが必要であり縛られたまま呪文を唱えることは難しい。自分のひもをほどくのは苦手なんだよと、この期におよんで笑っている性格はいっそ大したものだが事態の解決には何の役にも立っていなかった。大したものというのであれば、動くこともできない様で未だもがいているマキも同様だがさすがにそろそろあきらめたような素振りも見える。
「お願い・・・うまくいってよね」
時間は限られており機会は一度きりである。洞窟の入り口が見える茂みに音もなく一人ひそんでいたガラは、投石器を握ると風をきる音すらも立てぬように石のかたまりを投げつけるが、見張りに当たることもなく格子戸すらすりぬけて洞窟に吸い込まれてしまった。
不審な動きに気がついた見張りが顔を向けると、茂みの中から今度は正確に投げられた石がこめかみに当たるがこれも倒すにはいたらない。あわてて逃げだした娘の姿を、いきり立った二人ほどが追いかける。孤島では逃げ場もなく日がのぼれば狩りだされるしかないだろう。
外の騒ぎは土壁にひびいて聞きとりにくいが、見張りの数人が離れたらしく格子戸の向こうに海賊は一人しか見えない。洞窟に投げこまれた石は不運なマキに当たると地面に転がっていたが、身体をひきずりながらガルドが手で探ってみると割られた石の角がするどく欠けているのが分かる。
野馳の娘の意図を理解した白の狩人が後ろ手に握った石を立てると、心得たウンスイが身をひねりながら手首の縄を何度もこすりつける。あちこちを傷だらけにしながら、ようやく縄が切れると手早くひとりひとりを自由にするが本命は結ぶのとほどくのが得意だと豪語してみせた妖精である。がんじがらめにされていたマキの縄をほどき、それが蛇のように地面をつたうと残っていた見張りの足下からはいあがって瞬く間に縛りあげてしまった。
「急げ!」
それは脱走に気がつかれる危険への心配ではなく、ガラの姿を追った海賊どもが戻らないことへの焦慮だった。茂みに飛びこみ、数人がかりでのしかかられていた娘をあやうく助けだすことに成功する。
夜が明けてアーガイルの軍船が姿をあらわすと、狼狽した海賊は人質を放りこんでいた洞窟に向かうが、入り口に縛られた仲間が転がっているだけで他には誰もいない。上陸する兵士たちとの間に剣が交わされ、海賊が次々と捕らえられるが幾人かは小舟で逃げられてしまう。一行はいささか気まずいながらも助けられるが、海賊の根拠地を押さえることはできたし奪われていた武器も取りもどすことができた。あとは仲間たちが殺し屋アブダルの船を捕らえることを祈るだけである。
† † †
海に親しみがない者にとっては、船といえば水にさえ浮かべばどれも同じものに見えるかもしれないが、大げさな船乗りの言葉を借りれば海の数だけ異なる種類の船が海上にその姿をならべている。
ミッドランド沿岸を往来する船であれば、ごく小さな漁船の類をのぞけばたいていは図体の大きい帆船で、風や海流を利用して進むが港では櫂を用いることもあった。小回りはきかないが船員が少なくて済み、荷を多く積むことができたから商船や客船に多く使われている。
海賊があつかう船は小さな帆をかかげて左右に櫂をならべており、何人ものこぎ手が必要だが動きが軽快で船を襲うのに適している。このような船は遠い航海を乗りきることは難しいから、根拠地をもうけて度々出港しては港に戻らなければならなかった。
アーガイルの軍船は船にいきおいをつけるためだけに用いられる、四角い帆が申し訳ていどについているが、左右にならんでいる櫂の長さも数も海賊の船とはくらべものにならない。装甲が厚く船底は浅く、海賊船以上に遠距離の航海には向いていないが、たくさんの櫂でこぐから海上を自在に動くことができた。ひとたび見つかれば殺し屋アブダルのバンシー号が逃げきることは難しいだろう。
「進め進め!船を沈めたら好きなだけ酒をふるまうぞ!」
軍船ヘイベルダール号の舳先に立ち、はるか前方に見える船影を指すフールフールの姿が勇ましい。穴ぐらに暮らすドワーフはもともと海が好きではないが、生まれながらの職人である彼らは人が建造した乗り物をことのほか好んでもいた。威勢のいい酒樽女にこたえて櫂をこいでいる男たちの様子を見て、これではどちらが海賊か分かりませんなとサヴァンがおどけてみせる。
一刻がすぎるごとに船影は大きくなり海賊船が近づいていることが分かる。やがて甲板でわめきたてている姿が視界に入るが、あれが殺し屋アブダルに間違いないだろう。トカゲ兵にそそのかされて、海峡を荒らしてまわった海賊もこうなればもはや逃げ場もないが、アーガイルにかぎらずどの国でも海賊は捕まれば縛り首だから必死になるのも当然だった。
「捕まえた南トカゲの話によれば、トカゲ兵は海賊に守護者なるものを与えたとのことですぞ。護衛の一体二体がいるやもしれません」
「船ごとぶつければ楽だがそうもいくまい。せいぜい気をつけるとしようか」
サヴァンの警告にこたえてハインツが大剣の柄を強くにぎってみせる。装甲でも船の大きさでも勝っているアーガイルの軍船であれば、ぶつけてしまえばバンシー号を沈めることもできるだろうがこちらも傷つかないとはいえない。何より船を沈めれば勝ったときの実入りが少なくなってしまう道理で、船上の戦いでは船も船員も略奪品にされることは海賊ならずとも同じだった。アーガイルでもその事情は変わらない。
ヘイベルダール号はぶつけるためではなく、剣を持った船員たちが乗りうつるために全速で櫂をこぎ船を近づける。海賊船のほうが多少の小回りがきくとはいえ、軍船から逃れられるほどではなく、こぎ手の数がまるで異なるから速度でも戦力でも比べるべくもなかった。海賊に数倍する船乗りたちが乗りこんでくれば、あとは一網打尽にされるしかない。バンシー号の甲板では殺し屋アブダルが奇妙な管をくわえて、思いきり吹くと低く長い音が海峡にひびきわたった。
「落とされるなよ!」
フールフールのどら声がひびき、船と船が近づいて波が高くなる。舳先にしがみついた酒樽女は大弓だけを背にかついでおり、甲板にいるハインツやサヴァンも軽装で武器だけを手にしていた。
ヘイベルダール号が大きく揺れて、かぎのついた縄が何本も投げられると海賊船のあちこちにひっかかる。甲板には乗りうつるための板が立てられて接舷するのを待っていた。狼狽する海賊どもの中には海に飛びこもうとする姿も見える。
なんの前触れもなく、船がだしぬけに止まり全員が甲板に投げだされる。海賊も船乗りもごろごろと甲板に転がって、水に落ちた者もいるがいったい何ごとが起きたのか、その理由はすぐに明らかになった。
船のまわりの海面が激しく泡立ったかと思うと、蛇のような長い首がいくつも波間からでてくる。ふくれあがった黒い胴体から、何本もの首がでているのだ。この怪物はおそろしいヒドラ(Hydra)だ!トカゲ兵の守護者は不気味な口をあけて船の上にのしかかり、おびえあがった海賊も兵士もみさかいなくくわえこんでいる。その中には殺し屋アブダルの身体もあり、あわれな海賊はぐったりして動かない。

おそろしいヒドラは船乗りのうわさ話や伝説で耳にする姿よりも更に大きく、二隻の船を相手にしてもおびえるどころか甲板にずらりとならんでいる餌の多さをよろこんでいるようにすら見えた。一本の首が人間をくわえこんだまま頭をもちあげると、まるのみにされた身体がのどにおちて船乗りたちが悲鳴をあげる。
バンシー号の海賊もヘイベルダール号の船乗りたちも怪物から逃れようとするか、あるいは海に落ちぬようにしがみつくことしかできずにいるが、船の揺れがおさまると舳先から飛びおりたフールフールがひるむ素振りすらみせず背中にかついでいた大弓を構えてみせる。酒樽女の力こぶがもりあがる様子を見て魔法使いがすかさず声をかけた。
「伝説では不死身のヒドラを倒した英雄は、生き返らぬように 首を焼いてから土にうめたそうですぞ」
「ここは海の上だ!」
どこに火と土があるのかとドワーフが怒鳴りかえす。一本が矢というよりも槍のような大弓がひきしぼられて放たれると、怪物の首に深々と突きたった。ヒドラの胴体は倒すには強すぎるが、首をすべて失えば怪物は死んでしまうから何本かを倒せば逃げていくだろうとサヴァンが言う。
二本目、三本目の矢が次々と放たれては突きささり、怪物は天をやぶるような声をあげると振りまわした首があやうくフールフールを弾きとばす。甲板を転がった酒樽女はすぐに立ちあがると四本目の矢をつがえて撃ち放つ。眉間に矢をはやした首がついに絶命の声をあげると力つきて甲板に横たわった。
「土はないが火はここにあるぞ」
大剣フレイムストライクを構えたハインツが、両足で強く甲板を踏みしめる。首の一本を倒されて怒りくるうヒドラの目の前に立つと、戦神テラクに捧げる剣を空にかざしてみせた。閃いた陽光が大剣に照りかえされる。
船の上での戦いであり、重い鎧どころか短衣を着ているだけで腕甲すらつけていないが、怪物にひとのみにされてしまえば鎧などあってもなくても同じだろう。大きく開かれた顎にはいやらしい牙がずらりとならんでおり、ハインツをくわえこもうとしている。
牙をかいくぐって怪物のふところに入りこむと、首の根元に大剣が叩きつけられる。ヒドラに絡みつかれている船は甲板の揺れこそおさまっているが、ときおり傾いてきしむ音がする上に海水に濡れた足場は不安定で力をこめることが難しい。
分厚い怪物の皮膚は船乗りの弓や短刀であればかんたんに弾いてしまうが、フールフールの矢が貫いたように波打つフレイムストライクの刃はヒドラの皮膚にくいこんで深く傷をうがつことができた。
「さあテラクよ、戦士の戦いを照覧あれ!」
ハインツは思いきり大剣を振りまわすと、斧で大木を倒す勢いで刃を打ちつける。怪物はけっして鈍重ではないが巨大なだけに動きも大きく、襲いかかる剣先をよけることができない。うがたれた傷から体液が吹きだし、濡れた甲板に足をとられた戦士が船べりにしがみつく。
傷ついた首を助けるべく別の首が伸びあがると、洞窟のような口が開かれるがその中にフールフールの太矢が撃ちこまれた。のけぞった怪物ののどに、すかさず立ちあがったハインツのフレイムストライクが叩きこまれると柔らかい感触がして力を失った首が海に落ちる。先にハインツが傷つけていた首もしばらくもがいていたが、やがて甲板からずり落ちると海中へと沈んでいった。
怪物の首は半分ほどが倒されて残りが海上にうごめいていたが、ごちそうを相手に思わぬ怪我をおわされることになったヒドラは困惑しながらも船に絡みつくのをやめていない。きしみをあげるヘイベルダール号の甲板で、魔法使いが彼らしく大げさに見栄を切ってみせる。
「さて上手くいったら御喝采、ここはわたくしが久々に魔法らしい魔法を披露いたしましょう」
そういうと懐から奇妙に赤い石をだして、何やら意味のわからぬ文言をとなえながら海の上にほうり投げる。とたんに海が激しく泡立つと、本物とそっくりなヒドラの長い首が伸びてきた。石とおなじ色をした首は、とまどう怪物に牙をむいて深々と咬みつこうとする。
更にもう一つ、赤い石をほうり投げると二本目の首が伸びて、二つの首が二つの首に襲いかかると食いやぶろうとした。懐をさぐりながらサヴァンがおどけてみせる。
「これは残念、怪物が大きすぎて化け物うつしが二つでも足りません」
何本もの獰猛な叫びが甲板を叩き、くいこんだ牙が抜けなくなると別の牙が食らいついた。残された首が仲間を助けるために加勢して、ヘイベルダール号もバンシー号も激しい揺れと波に襲われる。魔法の首が二つとも、とうとう食いやぶられて倒れると化け物うつしの効果も消えるが咬みつかれていた二つも裂かれたのどくびからひゅうひゅうと空気をもらしていた。
あわせて五本もの首を倒されたヒドラはそれでも残っていた首がくわえこんだ餌にしぶしぶ満足すると、忌々しい船からとうとう逃げはじめる。絡みついていた首がはなれて、胴体が海に沈むと二隻の船はもう一度揺れるが傷ついていたものの沈没することはなく、船乗りも海賊も幾人か消えていたが無事に生きている者も多い。
海賊船バンシー号は甲板や船体の方々が歪み、櫂は何本か流されて帆柱が折れている。殺し屋アブダルは怪物にくわえられて水中に消えていたし、その怪物を倒した英雄の船を相手にして海賊たちはもはや戦うつもりも逃げるつもりもなく、せいぜい這いつくばって命ごいをするしかできずにいた。
† † †
海賊船を曳いたヘイベルダール号がラーヴングラスの港に入る。殺し屋アブダルは討伐されてソルウェイ湾の危険は減り、トカゲ兵の帝国も火山島ロクスから海峡をこえて軍勢を送ることが難しくなった。何本もの首をもつおそろしい怪物ヒドラは退治されて、逃げていったがよほどのことがなければ二度と人間の船になど近づこうとはしないだろう。首を失うくらいであれば、サメでもクジラでもひと呑みにしていたほうがよほど安全というものである。
三人の英雄は酒場をひきまわされて、海の男たちは詩人がうらやむ冒険譚をいささか誇張して語るのに忙しい。
「一人につき酒樽ひとつで許してやろうじゃないか」
片手に一つずつ掲げた大ジョッキを交互に飲みほしながらフールフールが豪語しているが、用意された酒樽の半分はドワーフ女の胃袋に収まってしまいそうである。景気のいい冗談話に聞こえる一方で、首謀者がいなくなった海賊を縛り首ではなく身代金で許してやってはどうかという意味に聞こえなくもない。もしもそれが酒樽女の言葉でなければ、英雄の慈悲に人々は感嘆したことだろう。
カスパーを襲う危難は去り、海峡を覆う雲は吹きはらわれていたがトカゲ帝国の脅威が失われたわけではなく魔王子イシュトラの脅威も消えてはいない。アルガラドのオウムの伝言を受けて魔術師ヤズトロモはダークウッドの上空に使い魔のカラスを飛ばしていたが、奈落の巣穴につながる手がかりはいまだ得られていなかった。白い魔女も啓示魔法をくりかえしながら、森を調べるに森のドルイドやエルフ(Elf)の助けが得られないかと使いを送っている。
ついに賢人たちは気のすすまぬ結論を決めた。こちらから火山島ロクスに渡り、トカゲ兵の帝国に忍びこんで彼らが崇拝する魔王子のたくらみを探るのだ。ミッドランドを脅かす三人の魔王子のうち、マイユールは彼が力を与えようとした闇のマルボルダスを失っていたし、女王シスは地上での代理者を持たず奈落を掌握するのに忙しい。イシュトラの侵攻を阻むことができれば、災厄は去って世界にひとときの平穏が訪れるだろう。
英雄たちが選ばれて火山島に渡るために考えられるだけの助けが用意される。強力なトカゲ王が治める帝国にあえて渡るほど愚かな行為はなく、相手がたとえ邪悪だとしてもアーガイルから攻める行為には疑問の声もあった。
彼らの目的はトカゲ兵の帝国に侵攻することでも侵略することでもなく、海峡を境にして互いの領分を侵さぬことでありその妨げとなる魔王子の到来を阻むことである。野心を持ちながらも彼らなりの秩序と文明で国を治めているのであれば、それはカスパーもトカゲ兵の帝国も、おそらくアーガイルも大きく変わるものではない。
「国が変われば肌の色が変わり、或いは鱗があったとして何の不都合があろうか。いさかいが起きぬ世界などないが好んで争えばそれは邪悪と変わらぬ」
東方からきた黒衣の影がミッドランドの空を見あげながら呟く。流れる風が変わり東から西へ、火山島に向かっているが空を覆う厚く暗い雲はいまだ散らされることも晴れることもなかった。
...TO BE CONTIUNUED
>第四の石版の最初に戻る