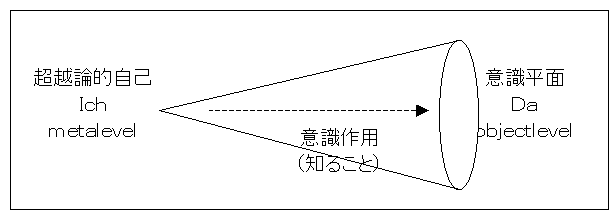
Antipsychiatry帋榑仈侾
仈侾丏侾丏丂嶨帍側偳傪撉傓尷傝丄惛恄堛妛偵娭偡傞媍榑偼暣媻偟偰偄傞偲偄偆報徾傪怈偄嫀傞偙偲偼弌棃側偄丅偦傟偧傟偺榑幰払偺庡挘偡傞棫応丄偦偙偵偍偗傞旝柇側曃嵎傪姼偊偰偛偔戝嶨攃偵惍棟偡傞側傜丄偦偙偵偼擇偮偺棫応偑偁傞偲偄偊傞偩傠偆丅懄偪丄乽惗暔妛揑惛恄堛妛乿偲乽惛恄昦棟妛乿偱偁傞丅惛恄幘姵傪惗暔妛揑庤朄偵偟偨偑偭偰帯椕偡傞偙偲傪婇恾偡傞慜幰偲丄惛恄幘姵偲偄偆姵幰偵偲偭偰偺僋儔僀僔僗傪暘愅揑丒椆夝揑偵懆偊傛偆偲偡傞屻幰偲丅偙偺棫応偺堘偄偼丄棫榑偺堘偄偵寛掕揑偱偁傝丄偙偺椉幰偼墲乆偵偟偰媍榑偺慜採偑堎側傞偨傔偵懳榖偼暯峴慄傪偨偳傞偙偲偑懡偄丅崱偲傝偁偊偢俀偮偺棫応傪庢傝弌偟偨偑丄栜榑偙偺僌儖乕僾撪偱傕媍榑偼偡傟堘偄偮偯偗傞偙偲傕傑傟偱偼側偄丅偍偦傜偔丄尰戙偵偍偄偰偙傟傎偳傑偱偵棫応偑憡堘偟偰丄弌夛偄偦偙偹偺榑憟傪懕偗偰偄傞暘栰偼惛恄堛妛傪慬偄偰懠偼側偄偱偁傠偆丅
丂偟偐偟丄偙偺媍榑偵偼丄扨偵懡條側棫応偑懚嵼偟丄偒傢傔偰榑憟揑側忬嫷偑堐帩偝傟偰偄傞丄偲偄偆偩偗偱偼側偄丅偦偙偱偼丄偦偆尵偄偒傞偙偲偺弌棃側偄揰丄偦傟偩偗偱偼岅傞偙偲偺弌棃側偄揰偑偁傞丅傓偟傠巹偑娭怱傪書偔偺偼偦偙偱偁傞丅傕偼傗惛恄幘姵傪傔偖偭偰偼丄偦偺媍榑偑惛恄堛椕撪晹偵偲偳傑傜偢丄忢偵幮夛揑儊僨傿傾傪捠偠偰暿偺椞堟傊偲奼戝丒奼嶶偟偰偄偒丄杮棃幘姵偵娭偟偰偼摿尃揑側埵抲晅偗傪偝傟偰偄傞偼偢偺堛椕幰偑丄偙偺栤戣偵娭偟偰偼偦偺摿尃惈傪幐偆偲偄偆揰偩偗傪偲偭偰傕丄偙偺栤戣偺摿庩惈偼昞傟偰偄傞丅儊僨傿傾傪捠偠偰桿婲偝傟偨彅栤戣偑丄傆偨偨傃堛椕撪偵夞婣偟偰丄怴偨側傞媍榑傪姫偒婲偙偡偲偄偆忣曬宱楬偼丄捠忢堛椕奅傊撍偒偮偗傜傟傞摟柧惈偺梫媮偲偼慡偔堘偭偨條憡傪掓偟偰偍傝丄撈帺偺暘愅偑昁梫側偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅偦偟偰偦偆偟偨暥專偼寛偟偰懡偔偼側偄丅
丂偩偑偟偐偟丄側偍岅傜傟偰偄側偄栤戣寳偼懚嵼偡傞丅巹偑偙偙偱暘愅偟偰傒偨偄偲巚偆偺偼丄偦偙偱偁傞丅椺偊偽偳偆偟偰偙傟傎偳傑偱偵惛恄幘姵偼幮夛揑側媍榑傪姫偒婲偙偡偺偩傠偆偐丠丂惛恄幘姵偼杮摉偵乽惗暔妛揑乿偵丄偁傞偄偼乽惛恄昦棟妛揑乿偵榑偠愗傞偙偲偺弌棃傞傕偺側偺偱偁傠偆偐丠丂偙偆偟偨暣媻偟偨帠懺偼丄壗偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟偰偄傞偺偐丠丂偦傕偦傕乽惛恄堛妛乿偲偼壗傪堄枴偟偰偄傞偺偐丠丂乧乧偙偆偟偨栤偄偐偗偼丄傓偟傠傎偲傫偳峴傢傟偰偄側偄偲偄偭偰傕椙偄丅崱栤傢傟傞傋偒偙偲偑偁傞偲偡傞側傜丄偙偆偟偨媍榑偑峴傢傟偰偄側偄偺偼偳偆偟偰側偺偐丄偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅
丂偙偙偱丄傑偢堦偮丄媍榑偺偨傔偺曗彆慄傪堷偔偙偲偵偟傛偆丅偦傕偦傕乽惛恄堛妛乿偺乽堛妛乿偲偼壗偐丠丂堦斒揑偵偼丄惛恄堛妛偺楌巎偼僋儗儁儕儞偵偦偺抂傪晧偆傕偺偲偝傟偰偄偄傞丅僋儗儁儕儞偼乽惛恄乿偵娭偡傞乽堛妛乿傪懪偪棫偰偨偺偩偲丅偟偐偟丄偦傕偦傕偙偺乽堛妛乿偲偼壗偱偁傠偆偐丠丂偦傟偼乽堛椕乿偲偼堘偆傕偺側偺偱偁傠偆偐丠丂惛恄堛妛偲惛恄堛椕丅偙偙偱丄杮棃巹偼惛恄堛妛偲惛恄堛椕偺偦傟偧傟偺宯晥傪楌巎揑偵偨偳偭偰峴偔傋偒偱偁傠偆丅偦偺忋偱椉幰偺嵎堎傪摨掕偟偰偄偔傋偒偱偁傠偆丅偟偐偟丄偙偺擇偮偺娫偵偁傞偹偠傟偨娭學偼丄変乆偑捠忢偙偺椉幰傪摨堦偺傕偺偲偟偰尒丄偦傟偵娭偟偰夰媈傪嵎偟嫴傑側偄偑屘偵偁傑傝偵傕塀暳偝傟偰偟傑偭偰偄傞丅偦傕偦傕扨弮偵偼偙偆偟偨宯晥傪偨偳傞偙偲偑弌棃側偄偺偩丅偦偺偨傔偵偼偁傞庬偺愴棯偑昁梫偲偝傟傞丅変乆偼偦傟備偊丄僋儗儁儕儞偺亀惛恄堛妛亁偱偺婰弎偵傑偱熻傜側偔偰偼側傜側偄丅偦偙偐傜乽堛妛乿偲偼壗偐偲偄偆栤偄傪丄偄傢偽愭庢傝偟偨宍偱峫嶡偣偞傞傪偊側偄丅
丂惛恄堛妛偼惛恄揑側幘姵偲偦偺帯椕偵娭偡傞妛偱偁傞丅偦偺弌敪揰傪堊偡偺偼惛恄忈奞偺杮幙偺壢妛揑擣幆偱偁傞丅枹奐柉懓偱偼惛恄幘姵偼揋堄偁傞埆婼偺塭嬁偵偝傟傞偺偑忢偱丄搶梞偱偼崱擔偱傕惛恄幘姵偼恄偵鄝報傪撴偝傟偨恖偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞丅偦傟偵斀偟偰屆戙僊儕僔傾偺堛巘払偼偡偱偵丄嫸婥偺嵗偵擼傪抲偒丄惛恄幘姵傪偁傞庬偺恎懱揑忈奞丄摿偵擬傗懱塼偺曄壔偲寢傃晅偗傞傎偳偵恑曕偟偰偄偨丅崱擔偺柦柤偺擇丄嶰偺傕偺乮乽儊儔儞僐儕乕乿丄乽僸億僐儞僪儕乕乿側偳乯偼偦傟偵抂傪敪偟偰偄傞丅巆擮側偑傜丄偡偱偵懱宯妛偵敪払偟偨偙偆偟偨帇揰偼丄屆戙暥壔偺姠夝偲嫟偵傎偲傫偳姰慡側傑偱偵幐傢傟偰偟傑偭偨丅偦傟偵懳偟偰拞悽偼惛恄幘姵偺尒曽偵偮偄偰丄堦曽偱偼僗僐儔揘妛揑丄懠曽偱偼廆嫵揑丒柪怣揑側悇應傪墴偟晅偗丄帺慠壢妛揑棟夝偺婛懚偺夎傪媫懍偵攔彍偟偨丅惛恄幘姵偼傕偼傗幘姵偱偼側偔丄埆杺偺巇嬈丄揤孻丄傑偨帪偵偼恄揑湌崨偱傕桳偭偨丅惛恄忈奞幰偺尋媶傗帯椕偵実傢傞偺偼傕偼傗堛巘偱偼側偔丄憁椀偑埆杺傪戅嶶偝偣傞偨傔偵偦偆偟偨傕偺傪捛媮偟偨丅柉廜偼嫸恖傪惞幰偲偟偰悞傔丄杺彈嵸敾偺敾帠偼悇應忋偺栂憐揑側嵾偺偨傔偵丄嫸恖傪崏栤幒偺拞傗壩孻戜偺慜偱敱偝偣偨丅
丂壢妛偺暅嫽偲摿偵堛妛偺敪揥偲嫟偵丄師戞偵堛巘払偺嫽枴偼傑偨惛恄幘姵幰偵岦偗傜傟巒傔偨丅偨偩丄惛恄忈奞偼堛妛揑尒抧偐傜偺傒惓偟偔捛媮偝傟擣幆偝傟摼傞偺偩偲偄偆柧傜偐側抦幆偑堦斒偵捠梡偵払偡傞偙偲偑弌棃傞傑偱偵堦悽婭傪梫偟偨丅僇儞僩偼傑偩丄昦揑側惛恄忬懺偺恌抐偵偼堛巘傛傝傕揘妛幰傪屇傇傋偒偱偁傞偲偄偆尒夝傪巟帩偟偰偄偨丅惛恄幘姵幰偺偨傔偺堛巘偺娔撀壓偱偺婔偮偐偺摿掕偺巤愝偺寶愝偑傗偭偲師戞偵丄惛恄幘姵偺壢妛揑娤嶡朄偺敪揥偺摴傪戱偒巒傔偨丅彮悢偺愭嬱揑嬈愌傪搙奜帇偡傟偽丄幚嵺偺惛恄壢堛偼傗偭偲廫敧悽婭偐傜懚嵼偡傞偙偲偵側傞丅惛恄堛妛偼偦偺帪偐傜丄撪揑偍傛傃奜揑側崲擄偵傕偐偐傢傜偢丄堛妛偺堦偮偺椡嫮偄暘婒偵傑偱栚偞傑偟偔媫懍偵敪揥偟偰偒偨丅
丂偲偼尵偆傕偺偺丄摿偵僪僀僣偱偼丄傑偩崲擄側摤偄傪傑偢崕暈偣偹偽側傜側偐偭偨丅側傞傎偳惞彂偺尃埿偵巟偊傜傟偨溸偒傕偺柪怣偼丄崱擔偱傕枾偐偵暚偒弌偡傛偆偱偁傞偑丄婛偵椡傪幐偭偨丅偦傟偵斀偟丄傑偝偵僄僗僉儘乕儖偵傛偭偰摉帪朙偐側椪彴宱尡偺庤偵埾偹傜傟偨庒偄惛恄堛妛揑抦幆偼丄惛恄幘姵偺偁傞庬偺摴摽恄妛揑攃埇偵懚偡傞婋尟側揋偲摤偄懕偗偨丅偦傟偼慜悽婭偺嵟弶偺廫擭娫偵僴僀儞儘乕傗儀僱働側偳偵傛偭偰惛恄幘姵偺妛愢偺拞偵帩偪崬傑傟偨傕偺偱丄偙偆偟偨尒夝偵傛傟偽惛恄忈奞偺庡側惈幙偼帺屓偺嵾偺寢壥丄偙傟偑恖娫偵懳偟朶椡傪壛偊傞傛偆偵側偭偰丄寢嬊怱恎傪懯栚偵偡傞偺偱偁傞偲偄偆丅偙偆偟偨丄傑偨椶帡偺丄旕忢偵偆傑偔傂偹傝弌偝傟偨尒夝偵懳偟偰偼丄僫僢僙傗僐乕價傪愭曯偲偡傞丄惛恄幘姵傪恎懱揑忈奞偺昞傢傟偲偟偰愢柧偡傞乽恎懱榑幰乿払偑丄帺慠壢妛揑尋媶偺晲婍偱摤偭偨丅
丂斵傜偼彑幰偱偁傝懕偗傞偺偵惉岟偟偰偄傞丅幍廫擭慜偵偼傑偩嬯楯偟偰榑憟偟摤偄庢傜偹偽側傜側偐偭偨偙偲偑丄偙傫偵偪偱偼丄偟偽偟偽堎側偭偨宍偱偱偼偁傞偑丄惛恄堛妛偺帺柧偺婎斦偲側偭偰偄傞丅傕偼傗扤傕丄惛恄忈奞偑堛巘偺帯椕偡傋偒幘姵偱偁傞偙偲傪姼偊偰媈傢側偄丅崱偱偼変乆偼丄惛恄幘姵偵偍偄偰偼惛恄尰徾偺宍偑懡偐傟彮側偐傟丄擼丄摿偵戝擼旂幙偺惛嵶側曄壔傪掓帵偡傞偺偩偲偄偆偙偲傪抦偭偰偄傞丅偙偆偟偨抦幆偵傛偭偰惛恄堛妛偼丄帺慠壢妛揑側庤抜偲尨懃偵婎偯偄偰绨恑偡傞妋屌偨傞柧傜偐側栚昗傪妉摼偟偨偺偱偁傞丅乮亀惛恄堛妛亁戞堦姫弿榑乯
侾丏傑偢丄惛恄堛妛偼丄壢妛揑擣幆偵婎偯偔丄惛恄幘姵偲偦偺帯椕偵娭偡傞妛偱偁傞丄偲偄偆庡挘偑暘偐傞丅
俀丏偲偙傠偱偙偺乽壢妛揑擣幆乿偵偮偄偰丄僋儗儁儕儞偼傕偭偲偼偭偒傝丄乽恎懱揑忈奞乿偵婎偯偔丄偲偄偆尵梩傪巊偭偰偄傞丅偲偄偆偙偲偼丄惛恄堛妛偲偼丄惛恄忈奞傪恎懱揑側忈奞偐傜棟夝偡傞妛偱偁傞丄偲偄偆偙偲偑敾傞丅
俁丏師偵丄僋儗儁儕儞偼丄廬偭偰乽惛恄忈奞乿偼乽堛巘偑帯椕偡傋偒幘姵偱偁傞乿偲偄偆偙偲傪庡挘偡傞丅懄偪丄惛恄偵娭偡傞幘姵偼丄堛巘偑帯椕偡傋偒幘姵丄堛妛偺斖埻偵偁傞偲偄偆偙偲傪庡挘偡傞偺偱偁傞丅
係丏偦偺嬶懱揑側曽嶔偼丄僋儗儁儕儞偵偡傟偽丄乽擼丄摿偵戝擼旂幙偺惛嵶側曄壔乿偺尋媶偵婎偯偄偰丄昦忬傪掓偡傞晹暘傪夵慞偡傞偲偄偆偙偲偵媮傔傜傟傞偩傠偆丅僋儗儁儕儞偺帪戙偵偼傑偩弌棃側偄偑丄惛恄堛妛偺栚昗偼堦偮偱偁傝丄擼偺尋媶偵婎偯偄偰堎忢傪惓忢偵栠偡偨傔偺曽朄傪捛媮偡傞偙偲偵偁傞丄偲偄偆偙偲偵側傞丅
丂偝偰丄偙偙偐傜僋儗儁儕儞偺乽堛妛乿娤偵偮偄偰傕偍偍傛偦偺偙偲偑暘偐傞丅僋儗儁儕儞偵傛傟偽丄偦傕偦傕堛妛偲偼丄乽壢妛揑擣幆乿偵婎偯偄偰丄壗偑堎忢偐尋媶偟丄堎忢晹暘傪惓忢偵栠偡傋偔帯椕偡傞丄偦偺偨傔偺乽妛乿偱偁傞偺偱偁傞丅廬偭偰僋儗儁儕儞偼丄偙偺帇揰偵棫偮埲忋丄惓忢偲堎忢偺嬫暿丄峏偵偦偺暘椶傪揙掙偝偣傞昁梫偵敆傜傟傞丅帠幚僋儗儁儕儞偺巇帠偼偦偺傛偆偵梫栺壜擻偱偁傞丅僋儗儁儕儞偼偦偺惗奤傪偐偗偰丄朿戝側徢椺傪丄屌掕偟丄暘椶偟丄婰嵹偟偨丅偦偺暘椶偼丄擭寧傪捛偆偛偲偵嵶暘壔偟丄壗搙傕壗搙傕彂偒姺偊傜傟丄傑偝偵廔傢傝偑柍偄丅偁偨偐傕昐壢帠揟傪嶌傞偐偺傛偆側嶌嬈丅尰嵼偺堛妛傕偙偺曽朄榑傪婎杮揑偵摜廝偟丄偦偺堦晹栧偱偁傞惛恄堛妛傕偍偍傛偦偙偺墑挿忋偵偁傞丅
丂偲偙傠偱偙偙偱拲堄偟側偔偰偼側傜側偄偙偲偑偁傞丅偙偺傛偆偵彂偔偲丄偁偨偐傕乽堛妛乿偼乽堛椕乿偲偄偆幚慔偺偨傔偺朿戝側儅僯儏傾儖傪嶌惉偡傞傕偺偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞丅妋偐偵偦偆偄偆堦柺傕偁傞丅偩偑僋儗儁儕儞偺亀惛恄堛妛亁傪偼偠傔偲偟偰丄朿戝側乽堛妛乿尋媶傪慜偵偟偨帪偵丄偦偆偟偨娤揰偼幚偼桳岠偱偼側偄丅妋偐偵堛妛偼乽堛椕乿偵偦偺抂傪晧偆丅偟偐偟偦偺傑傑偦傟傪婰嵹偡傞偺偱偼扨偵宱尡榑偵廔傢傞丅堛妛偺栶栚偲偼丄夁嫀偺宱尡傪暘愅偟丄拪徾壔偡傞偙偲偱丄彨棃偵懳偟偰偁傞庬偺價僕儑儞傪掓帵偡傞偙偲偱偼側偄偩傠偆偐丠
丂偙偺偙偲偼堛妛偵尷傜側偄丅偄偐側傞妛傕丄偦偺栚揑偼扨偵宱尡榑偵廔傢傞偙偲偱偼側偐偭偨丅偨偲偊偦偺妛偑敪惗偟偨帪偵偼偦偆偟偨堄恾偼側偐偭偨偲偟偰傕丄慿峴揑偵尒偨帪偵偼忢偵壗傜偐偺搳婇惈偑尒偊偰偟傑偆丅惛恄堛妛偺応崌偵偟偰傕丄偨偲偊嵟弶偼徢椺傪廤傔傞宱尡榑偵夁偓側偄傕偺偱傕丄偦傟偑暘愅偝傟拪徾壔偝傟傞偲丄偦傟偼傕偼傗扨側傞夁嫀傊偺僐儊儞僩亖宱尡榑埲忋偺壗偐偵側傞丅偦傟偼枹棃偵懳偟偰傕僐儊儞僩偡傞偺偩丅壗偑乽徢忬乿偱丄壗偑乽幘姵乿偐丄偦偟偰偦偺乽帯椕乿朄偼壗偐丄摍乆丅偦傟偼夁嫀偺堚嶻偱偁傞偲摨帪偵丄彨棃偵暍偄旐偝傞僼傿儖僞乕偵側傞丅偦偆側偭偰弶傔偰乽妛乿偑惉棫偡傞丅
丂柍榑丄乽妛乿偼忢偵惓偟偄寢榑傪掓帵偡傞偲偼尷傜側偄丅偩偑丄慿峴揑偵尒傞偲偒丄変乆偵偼乽妛乿偺娫堘偄偼乽尒偊側偄乿丅壗屘偐丅変乆偼楌巎傪怳傝曉傞帪偵丄変乆偺帩偮乽妛乿偺拞偱丄偦偺帇揰偵増偭偰乽妛乿偺楌巎傪怳傝曉傞丅偲偙傠偱偦偆偟偰尒傞偲丄乽妛乿偺拞偱丄屄乆偺尋媶幰偑娫堘偄傪斊偡偙偲偼敾傞偗傟偳傕丄偦偺婎斦偱偁傞乽妛乿偦偺傕偺偺娫堘偄傪乽尒傞乿偙偲偑弌棃傞偱偁傠偆偐丅悢妛偵偮偄偰峫偊偰傒傞偲偄偄丅條乆側妛愢偑旘傃岎偭偨丅偦偺拞偵偼変乆偐傜偡傟偽丄姰慡偵揑傪奜傟偨堄尒傕桳偭偨偱偁傠偆丅偟偐偟変乆偼忢偵丄崱変乆偑帩偮乽悢妛乿偲偼堘偆傕偺偱偁傞偐傕偟傟側偔偲傕丄乽悢妛乿偦偺傕偺偺岆傝側偳丄尒偊傞偱偁傠偆偐丅屄乆偺妛愢偺岆傝偱側偔丄偦偺媍榑偺婎斦偱偁傞乽悢妛乿偦偺傕偺偑丄偦偺峫偊曽帺懱偑岆傝偱偁傞側偳偲偄偆丄偦偆偟偨峫偊曽傪変乆偼嫋梕偡傞偱偁傠偆偐丅偦偆峫偊偨帪丄乽堛妛乿偵娫堘偄側偳柍偄偺偱偁傞丅
丂堛妛偵娫堘偄側偳柍偄丅屄乆偺妛愢偵娫堘偄偑偁偭偰傕丄堛妛偦偺傕偺偵岆傝偑偁傞壜擻惈偼側偄丅偦傟偑乽妛乿堦斒偺摿挜偱偁傞丅偙偙偱丄惛恄堛妛偵榖傪栠偦偆丅僋儗儁儕儞偼乽惛恄堛妛乿傪丄偲傕偐偔乽暘椶乿偐傜巒傔偨丅乽帺慠壢妛揑擣幆乿偑偄偐側傞傕偺偱偁傠偆偑丄偙偺揰偼摦偐側偄丅廬偭偰丄屄乆偺妛愢偱偼側偔丄惛恄堛妛偲偄偆搚戜偲偼丄崱偺暥柆偐傜偡傟偽丄乽暘椶偡傞偙偲乿偦偺傕偺偵媮傔傜傟傛偆丅暘椶偺巇曽偵偼岆傝偑偁傞偐傕偟傟側偄偑丄暘椶偡傞偲偄偆偙偲偦偺傕偺偵偼岆傝偼側偄丅偙偺偙偲偼丄彨棃傕寛偟偰曄傢傜側偄丅偟偐偟偙傟偼偳偆偄偆偙偲偐丅
丂偙偙偱丄惛恄堛妛偩偗偱側偔丄傕偭偲峀偄帇栰偵棫偭偰峫偊偰傒傞丅僋儗儁儕儞偺惗偒偨帪戙偼丄幚偼僼僢僒乕儖傗償傿僩僎儞僔儏僞僀儞偲偄偭偨丄榑棟幚徹庡媊偺揘妛偑峀斖偵庴偗擖傟傜傟偰偄偭偨帪戙偱傕偁偭偨丅偲偄偆傛傝傕丄帪戙偺晽挭帺懱偑尦乆榑棟幚徹庡媊偵婎偯偄偰偄偰丄偁傜備傞妛偑偦偺塭嬁壓偵偁偭偨偲偄偭偨曽偑偄偄偐傕偟傟側偄丅偙偺塭嬁偼尰嵼偵偍偄偰傕徚偊偰偄側偄偑丄偲傕偐偔偙偺帪戙偵偦偺巚峫宍懺偼惍旛偝傟偨丅偲偙傠偱偦偺榑棟幚徹庡媊偲偼壗偐丅偙傟偼丄堦偮偺僇儞僩傊偺墳摎偱偁傞偲惍棟偱偒傞偩傠偆丅
丂師偺恾傪尒偰梸偟偄丅榑棟幚徹庡媊偲偼壗偐丅堦尵偱尵偄昞偡側傜偦傟偼倣倕倲倎倢倕倴倕倢偲倧倐倞倕們倲倢倕倴倕倢偲偺揙掙偟偨槰棧傪摿挜偲偡傞榑棟偱偁傞丅偱偼偙偺恾偵増偭偰愢柧偟偰偄偙偆丅
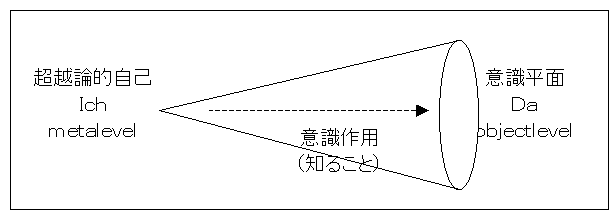
丂挻墇榑揑帺屓偲偼丄娙扨偵尵偊偽丄乽抦妎偡傞乿巹偱偁傞丅巹偼條乆側傕偺傪姶偠傞丅奜奅偺岝丄壒丄壏搙丄條乆側宍徾傕塣摦傕抦妎偡傞丅偦傟偩偗偱偼側偄丅巹偼帺暘帺恎傪抦妎偡傞丅帺恎偺姶忣偺摦偒丄婐偟偄偲偐夨偟偄偲偐丄捝偄偲偐嬯偟偄偲偐丄搃傑偟偄偲偐憺偨傜偟偄偲偐丄帺暘偺拞偺偙偲傪傕抦妎偡傞丅偙傟傜慡偰傪抦妎偡傞庡懱丄偦傟傪挻墇榑揑帺屓偲屇傇丅偦偟偰愭偵嫇偘偨傛偆側丄抦妎偝傟傞傕偺慡偰傪崌傢偣偰丄堄幆暯柺偲屇傇丅償傿僩僎儞僔儏僞僀儞偼丄偙偺挻墇榑揑帺屓傪栚偵丄堄幆暯柺傪帇栰偵歡偊偨丅帇栰偺拞偵栚偼柍偄傛偆偵丄堄幆偺拞偵傕挻墇榑揑帺屓偼側偄丅
丂偙傟傪妛堦斒偵奼挘偟偰峫偊傛偆丅椺偊偽悢妛傪椺偵庢傞丅悢妛偱偼條乆側悢傪寁嶼偡傞丅悢妛偱偼尃棙忋丄偄偐側傞悢傕寁嶼偟摼傞丅廬偭偰偙傟傜偼寁嶼偺懳徾亖倧倐倞倕們倲偵側傞丅偟偐偟寁嶼偺懳徾偵弌棃側偄傕偺偑悢妛偺悽奅偵傕懚嵼偡傞丅偦傟偼丄寁嶼偡傞偙偲丄偦偺曽朄偦偺傕偺偱偁傞丅椺偊偽俆亄俁亖俉丄偙傟偼捠忢偺寁嶼偱偁傞丅偟偐偟偙偺寁嶼偱巊傢傟偰偄傞亄傗亖偼寛偟偰寁嶼偺懳徾偵偼側傜側偄丅俆亄亄亖俉丄偲偄偆寁嶼幃偼丄寁嶼偺寢壥偑偳偆偙偆尵偆慜偵丄偦傕偦傕娫堘偭偰偄傞丅寁嶼偵偲偭偰丄寁嶼偡傞偙偲丄寁嶼偡傞曽朄帺懱偼丄寛偟偰寁嶼偺懳徾偵偼側傜側偄丅偙偙偵嫇偘偨椺偱尵偊偽丄亄傗亖偼倣倕倲倎倢倕倴倕倢側偺偱偁傞丅
丂妛偵偍偄偰偼丄偙偺倣倕倲倎倢倕倴倕倢偲倧倐倞倕們倲倢倕倴倕倢偲偼寛偟偰崿摨偝傟側偄丅偙偺偙偲傪変乆偺暥柆偐傜峫偊偰傒傞丅僋儗儁儕儞偼條乆側偙偲傪暘椶偟偨丅偦偺暘椶懳徾偼峫嶡偺懳徾偲側偭偨丅偟偐偟斵偼丄帺恎偺乽暘椶偡傞偙偲乿偦偺傕偺傪峫嶡偡傞偙偲偼側偐偭偨丅彮側偔偲傕斵偺懱宯偺拞偱偼尃棙忋晄壜擻偱偁偭偨丅尵偄姺偊傛偆丅僋儗儁儕儞偺懱宯偺拞偱偼丄斵偑棫偰偨暘椶偡傞偙偲亖倣倕倲倎倢倕倴倕倢偼丄峫嶡偺懳徾亖倧倐倞倕們倲倢倕倴倕倢偐傜忢偵摝傟傞丅僋儗儁儕儞帺恎傕娷傔丄惛恄堛妛幰偨偪丄堦斒壔偟偰乽暘椶偡傞乿幰偨偪偼丄偦偺暘椶偵曄峏傪壛偊傞偙偲偼偁偭偰傕丄寛偟偰帺恎偺傗傝曽傪丄偁傞偄偼帺暘払傪峫嶡偡傞偙偲偼側偄丅榖傪峀偘傛偆丅暘椶偡傞偙偲乛尰帪揰偱偺暘椶朄丄惛恄壢堛乛姵幰丄惛恄堛妛懱宯乛徢忬丄偙偺擇暘朄帺恎偼丄寛偟偰梙傞偑側偄丅惛恄堛妛偼乽妛乿堦斒偺偙偆偟偨峔憿傪摝傟傜傟側偄丅
丂乽妛乿偺峔憿偵偮偄偰丄傕偆彮偟惍棟偟傛偆丅慜弎偟偨傛偆偵丄乽妛乿偺堦斒峔憿偲偟偰丄偁傞庬偺拪徾壔偑懚嵼偟偰偄傞丅偙偺拪徾壔偲偼壗偱偁傠偆偐丅
丂乽妛乿偼堦斒偵丄妋偐偵夁嫀偵懳偡傞僐儊儞僩偐傜巒傑傞丅偙偺堄枴偱偼捠忢偺宱尡榑偲曄傢傜側偄丅夁嫀偵婲偒偨帠徾傪幏漍偵婰嵹偟懕偗傞偙偲偼丄妋偐偵偦傟側傝偵堄枴偺桳傞偙偲偱偁傞丅偦傕偦傕捠忢乽姷廗乿傗乽揱摑乿偺柤偺壓偵岅傜傟傞傕偺偲偄偆偺偼丄偦偆偟偨懁柺偑嫮偄偱偁傠偆丅妋偐偵朿戝側僲僂僴僂偼偁傞偩傠偆丅婔偮偐偺峴堊偺慖戰偵偮偄偰丄椙偄夞摎傪梡堄偡傞偩偗偺弨旛傕偁傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟偦偙偵偼尨棟偼側偄丅
丂乽妛乿偼偦偙偵棷傑傜側偄丅偄偭偨傫暘椶偝傟丄暘愅偝傟丄拪徾壔傪宱偰偟傑偆偲丄偦傟偼慜偲偼堘偭偨壗偐偵側傞丅懄偪丄乽尨棟乿偑弌尰偡傞丅偦傟偼丄夁嫀偵娭偡傞僐儊儞僩傪丄偦傟帺恎撈棫偝偣丄偄傢偽愜傝曉偡宍偱丄枹棃偵娭偡傞僐儊儞僩偵曄偊偰偟傑偆丅傕偆彮偟尵梩傪曗偆側傜丄偦傟偼夁嫀偺偁傞堦帠徾偑帩偭偰偄偨帪娫惈傪斈帪娫惈偵丄旕帪娫惈偵曄偊偰偟傑偆丅帪娫側偒傕偺偼晛曊揑偱偁傝丄偦傟偼枹棃偵娭偟偰價僕儑儞偲側傞丅
丂夁嫀偺枹棃傊偺憲傝曉偟丄傑偢偼偙偺峔憿傪妋擣偟偰偍偔丅偟偐偟乽妛乿偺峔憿偼丄偙傟偩偗偵棷傑傜側偄丅乽妛乿偼偦傟帺懱婎掙嵽偲偟偰帺恎傪昞弌偡傞丅偳偆偄偆偙偲偐丅乽妛乿偼崱弎傋偨傛偆偵丄枹棃偵娭偟偰傕僐儊儞僩偡傞丅偲偄偆偙偲偼丄妛偼帺傜偺拞偵偁傞庬偺婎弨亖僲儖儉傪帩偮偲偄偆偙偲傪堄枴偡傞丅僲儖儉偲偼捠忢乽尨棟乿偲偟偰岅傜傟丄偙偺乽尨棟乿偺擇廳惈偑丄乽妛乿偵偲偭偰晄壜寚側惈幙傪晅梌偡傞丅
丂傑偢乽妛乿偼丄幮夛揑側梫惪偵墳偠丄偦偺尃埿晅偗偺忦審偲偟偰丄壗傜偐偺僲儖儉傪掓帵偡傞丅僲儖儉偲偼丄偙偺応崌乽婯斖惈乿偺妋掕丄惓忢惈偲堎忢惈偺嬫暘傪掓帵偡傞嵟廔怰媺傪堄枴偡傞丅偙偺堄枴偱偼丄乽妛乿偼摟揙偟偨暘椶丄姰慡偵摟柧側婎弨偺嶌惉傪屓偺忦審偲偡傞丅偙偺庡挘偼丄偟偐偟摨帪偵暿偺栤戣傪姭婲偟偰偟傑偆丅偮傑傝丄偦偆偟偨僲儖儉偵偼廬傢側偄傛偆偵尒偊傞帠徾丄愢柧偱偒偦偆偵傕側偄帠徾傪偳偆懆偊傞偺偐丄偲偄偆栤戣偱偁傞丅偦傟備偊乽妛乿偼丄帺恎偺惓摉惈偺庡挘偺偨傔偵丄摨帪偵偁傜備傞帠徾偵懨摉壜擻側儘僕僢僋丄偁傜備傞尰徾傪愢柧壜擻偲偡傞倣倕倲倎倢倕倴倕倢偺尨棟傪掓帵偡傞偙偲偵側傞丅帠徾偵枾拝偟丄偦偺惓忢乛堎忢傪敾掕偡傞倧倐倞倕們倲倢倕倴倕倢偺尨棟偲丄帠徾偐傜偼棧傟偰丄傓偟傠帠徾偵懳偡傞敾抐帺懱傪敾抐偡傞倣倕倲倎倢倕倴倕倢偺尨棟丅乽妛乿偼偙偺擇廳峔憿傪帩偮丅
丂暿側尵偄曽偱孞傝曉偦偆丅乽妛乿偼妋偐偵幮夛揑側梫惪偐傜敪惗偟偰偄傞丅偦偺堄枴偱偼偁傞庬偺捈愙揑側惌帯惈傪丄懄偪倧倐倞倕們倲倢倕倴倕倢偺敾抐偵偍偗傞怰媺偲偄偆栶栚傪忢偵扴偆丅偟偐偟偦傟偩偗偱偼乽妛乿偼傓偟傠帺恎偺惓摉惈傪庢傝摝偡丅側偤側傜偦偺傑傑偱偼條乆側巚峫僔僗僥儉偺拞偺堦偮偵夁偓側偔側偭偰偟傑偆偐傜偱偁傞丅帺恎偺惓摉惈傪寛掕揑側傕偺偵偡傞偨傔偵乽妛乿偼帺恎偺惌帯惈傪塀暳偟丄旕惌帯揑側傕偺丄旕壙抣敾抐揑側傕偺偵偟傛偆偲偡傞丅婯斖偵廬偭偰偄傞偐斲偐傪慡偔敾抐偟側偄埲忋丄偦偺敾抐偼忢偵惓偟偄丅偮傑傝丄妛偵偍偗傞偙偺倣倕倲倎倢倕倴倕倢偱偺尨棟惈偵偼丄捠忢偺堄枴偱偺斸敾偼晄壜擻側偺偱偁傞丅
丂乽妛乿偼偙偺儗儀儖墶抐惈傪忢偵嵞惗嶻偡傞丅偙偙偵乽妛乿堦斒偺柍昑惈偲旕惌帯惈偑堐帩偝傟傞尨場偑偁傞丅偙偺擇廳惈偺暘愅偙偦偑丄乽妛乿偵娭偡傞斸敾偵拞怱揑側埵抲傪帵偡傕偺偵側傞偩傠偆丅傕偆彮偟晅偗壛偊傛偆丅偙偺擇廳惈偺暘愅偼丄偍偦傜偔偦偺偢傟偐傜峫嶡偱偒傞丅傑偨丄妛偼忢偵偦偺撈帺側懱宯偐傜嵞惗嶻偝傟偰偄偔偲偄偆揰傕丄尒棊偲偟偰偼側傜側偄揰偱偁傠偆丅偦偺懱宯偼丄幮夛揑側梫惪偐傜巒傑偭偨偲偟偰傕丄偦傟撈帺偺懱宯壔傪帩偮丅椺偊偽偦傟偼傾儖僠儏僙乕儖偑暘愅偟偨傛偆偵丄忋晹峔憿偼壓晹峔憿偐傜撈棫偟偰怳傞晳偆偲偄偆傆偆偵掕幃壔傕弌棃傞偩傠偆丅妋偐偵忋晹峔憿偼壓晹峔憿偐傜塭嬁傪庴偗傞丅偟偐偟忋晹峔憿偼撈帺偵乽屇傃偐偗乿丄偦傟帺恎偲偟偰嵞惗嶻偝傟摼傞偺偱偁傞丅
丂堛妛偲偼丄乽妛乿偱偁傞埲忋丄忢偵偁傞庬偺乽尨棟乿惈偵棫偪曉傞偙偲偵側傞丅尨棟惈偲偼壗偐丅偦傟偼丄偁傞庬偺僲儖儉傪掓帵偡傞偙偲偵偁傞丅僲儖儉丄懄偪婯斖惈丄偦偺掓帵偵偍偄偰偙偦丄乽妛乿偼幮夛揑偵尃埿晅偗傜傟傞丅惛恄堛妛偵偍偄偰丄偦偺栶妱偼寛偟偰彫偝偄傕偺偱偼側偐偭偨丅傛偔抦傜傟偰偄傞傛偆偵丄偦傕偦傕楌巎揑偵尒偰丄惛恄堛妛偺敪惗偼惛恄偵娭偡傞乽婯斖惈乿偺妋棫偲偄偆丄嬌傔偰幮夛揑側梫惪偵傛傞傕偺偱偁偭偨偐傜偩丅僋儗儁儕儞偺婰嵹偑丄擛壗偵帺恎偺乽惓摉惈乿傪庡挘偟傛偆偲傕丄偦偺儘僕僢僋偑壗傜偐偺僲儖儉偺採帵傪峴偭偰偄傞偙偲偵曄傢傝偼側偄丅偦傟偼丄堎忢偲惓忢偲傪暘偗傞婯斖偺掓帵偙偦丄戞堦偵峴偆傕偺偱偁偭偨偐傜偩丅偦偺乽旕惌帯揑乿側奜尒偺棤偵塀偝傟偨乽惌帯惈乿偵娭偟偰偼丄傕偼傗媈偄傛偆傕側偄丅
丂惛恄堛妛偼丄偦偺峀斖埻側揱攄偵傛偭偰惛恄偺婯斖揑婯斖傪楙傝忋偘偰偒偨丅暥壔憡懳庡媊傪庡挘偡傞暥壔恖椶妛偵傛偭偰傕偦偺偙偲偼暍偣側偄丅側偤側傜丄傑偝偵條乆側惛恄偺嵼傝曽丄惛恄偺婯斖偺嵼傝曽偑偁傞偲偄偆帠幚偦傟帺懱偑丄惛恄堛妛偵偲偭偰偼帺恎偺惓摉惈傪庡挘偡傞榑嫆偵側偭偰偄傞偐傜偱偁傞丅惛恄堛妛偼帺恎傪寛偟偰倧倐倞倕們倲倢倕倴倕倢偵偼抲偐側偄丅惛恄堛妛偼偁傜備傞暥壔偺惛恄偺婯斖偺嵼傝曽偵懳偟偰丄倣倕倲倎倢倕倴倕倢偱偁傞偙偲傪庡挘偡傞偺偩偐傜丄傑偝偵惛恄偺條乆側嵼傝曽偙偦偑惛恄堛妛偺峀斖側壜擻惈傪栺懇偡傞偙偲偵側偭偰偟傑偆丅惛恄堛妛偲偼丄屓傪姰慡偵摟柧偵偟偮偮丄偁傜備傞帠徾偵娭偟偰偐傇偝偭偰偄偔傛偆側僼傿儖僞乕偲側傞偺偱偁傞丅偦傕偦傕惛恄偵娭偡傞堛椕丄惛恄偵娭偡傞暘椶偲偄偆峫偊曽偦傟帺恎偑惛恄堛妛偐傜敪惗偟偨傕偺偱偼側偐偭偨偐丅偦偆偱偁傞偲偡傟偽丄暥壔恖椶妛偑條乆側惛恄偺嵼傝曽傪掓帵偡傞傑偝偵偦偺偙偲偙偦偑惛恄堛妛偺傗傝曽側偺偱偼側偄偐丅
丂惛恄堛妛偼僲儖儉傪掓帵偡傞丅偦傟偼屄恖暥壔傪敍傝晅偗傞僲儖儉偱偼側偔丄偦傟傪夝庍偡傞僲儖儉丄倣倕倲倎倢倕倴倕倢偵偍偗傞僲儖儉偱偁傞丅廬偭偰丄捠忢偺堄枴偱偺惛恄偺懡條惈偺庡挘偼丄傓偟傠惛恄堛妛偺尃埿傪嫮傔偰偟傑偆丅惛恄堛妛偼丄忢偵偦偺婰弎傪旕惌帯揑側傕偺丄旕壙抣敾抐揑側傕偺偵偟傛偆偲偡傞丅偦偺堄枴偵偍偄偰丄惛恄堛妛偼倣倕倲倎倢倕倴倕倢偵偟偐側偄丅偟偐偟惛恄堛妛偼摨帪偵丄倧倐倞倕們倲倢倕倴倕倢偵偮偄偰傕岅偭偰偟傑偆丅偙偺婏柇偲傕尵偊傞儗償僃儖墶抐惈偼丄惛恄堛妛偺拞怱揑側埵抲傪愯傔傞偙偲偵側傞偩傠偆丅
丂偲偙傠偱丄偙偆偟偨揰偐傜乽惛恄堛妛乿傪峫嶡丒斸敾偟偨暥專偼懚嵼偟側偐偭偨偐丠丂偦傟偼幏漍偵彂偐傟懕偗偨偺偱偼側偐偭偨偐丠丂偦偆偟偨宯晥偼丄偱偼尰嵼偳偆偟偰偦傟偵傆偝傢偟偄拲堄傪庴偗偰偄側偄偺偐丠丂巹偼偙偙偱摿尃揑偵丄僋乕僷乕偺亀斀惛恄堛妛亁傪庢傝忋偘傞丅偙偺杮偺尨戣偼丄乬俹倱倷們倛倝倎倲倰倷丂倎値倓丂俙値倲倝倫倱倷們倛倝倎倲倰倷乭偱偁傝丄惛恄堛妛偲斀惛恄堛妛偲偺娭學偵偮偄偰斵偑彂偙偆偲偟偨偙偲偑偡偱偵僞僀僩儖偐傜柧帵偝傟偰偄傞丅巹偑偙偙偱峴偍偆偲偟偰偄傞乽惛恄堛妛偲偼壗偐乿偲偄偆栤偄偐偗偼丄幚偼偙偺杮偵傛偭偰愭庢傝偟偰峫嶡偝傟偰偄傞丅栜榑僋乕僷乕偼摉帪偺惛恄堛椕偺尰忬偵懳偟偰斸敾偟偰偄傞偺偩傠偆丅偟偐偟偦偙偱斵偼摨帪偵惛恄堛妛偵偮偄偰傕壗帠偐岅偭偰偄傞丅変乆偼偙偙偱丄偙偺杮偺惛撉傪峴傢側偗傟偽側傜側偄丅偦偺忋偱偼偠傔偰丄尰戙偵偍偗傞惛恄堛妛傪傔偖傞媍榑傪暘愅偡傞偙偲偑弌棃傞偱偁傠偆丅