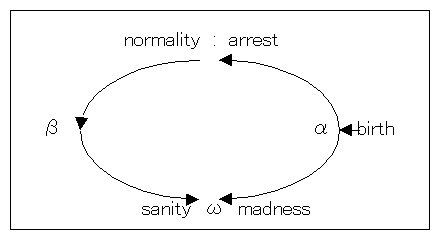
Antipsychiatry試論#2
#2.1. 「[……]精神医学理論を、最も革新的に、かつラディカルに批判していこうとするとき、まずもって提起すべきことは、精神医学と精神分析をその歴史的起源にまで遡って分析することである」(p.49)。クーパーは、“Psychiatry and Antipsychiatry”の中で、こうしたきわめて大胆かつ壮大なプロジェクトを掲げている。しかし、私が見たところ、そうした試みはこの本の中では実質的に一切着手されずにいる。我々がここで行おうとする試み、それはクーパーのこの未完のプロジェクトへのコマンテールである。
ところで直ちに問題となってくるのは、どうしてクーパーがこの試みを掲げつつ行うことができなかったのか、ということである。結論を先取りした形で言ってしまえば、そのことこそクーパー自身の立場の揺らぎ、ある種の曖昧性が如実に現れている点であろう。クーパーが、精神医学に対して、又同時に精神分析に対して示す態度は両義的なものであり、実はそれこそこの本にある種の緊張感を与えている点なのであるが、そのことについては充分な分析がなされているとは言い難い。クーパーの主張の分析は、権利上こうしたクーパーの立場の分析に先行することはできない。我々はしたがって、まずはここで、クーパーの両義的な態度を余すことなく読解しよう。そしてそうした立場を採らざるを得なかった理由について考察を進めていこう。精神医学と精神分析の歴史的起源を分析すること、それは同時に、反精神医学の歴史的起源を分析することでもあるはずだ。
したがって、我々はこの本を、クーパーの指示通りに読むことは必ずしも必要ではない。むしろ、クーパーが示し得なかったことを掴むために、その読解にはある種の戦略性が要請されよう。そうした読解を経てはじめて、今まで注目されてこなかったクーパーの立論の革新性が見えてくるであろう。
クーパーの、通常言われる意味での主張は、序章の冒頭部分にきわめて明確に記されている。「[……]精神分裂病と呼ばれているものに対する接近法は、二通りの一般的範疇に分かれている。すなわち、一方に、精神分裂病と呼ばれるものは一つの疾病分類学上の単位であって因果的に説明されねばならないものだ、と断定する従来の接近法である。[……]また、他方には次の二点を強調する接近法がある。つまり、疾患単位として確立されているような精神分裂病など存在しないという点と、‘モデル’としての疾患とか思考の仕方としての疾患は、‘精神分裂病の分野’への接近法としてはおそらく最も不適切なものか、もしくはこの分野の特質そのものと全面的に矛盾するものでさえあるという点を主張する接近法である」(p.9)。更に後者について、「将来患者にさせられる運命にある者の中には、一時的な欠陥はないのだ、[……]人間同士が関わり合っている微視的社会分野にこそ欠陥があり、しかもそれははっきりと論証できるものである」(p.11)と書いている。
したがって、クーパーが‘精神分裂病’に対する接近法として挙げているのは、
1.個体内に病気を推定する方法
2.個体間に病気を推定する方法
の二つがある、ということになる。前者が従来の(しかもクーパーが後に「精神医学的」と称する)接近法であり、後者こそがクーパー自身が提起しようとする関係論的、「反精神医学的」接近法である。ここでのクーパーの議論はクリアである。
クーパーは、この前者の考え方、「精神医学的」接近法を批判し、後者の考え方、「反精神医学的」接近法を評価しようとする。基本的に彼の論の枠組みはこの点では狂わない、と考えられている。しかし、この結論は、その後の彼の議論の中で、彼自身の言葉の中で、揺れていく。テクストを実際に追って行こう。彼は「狂気の再評価」を行う必要性を強調する(p.50)。「その核心は、おそらく図表を使うと、最も適切かつ簡潔に表現される」(p.51)。ではその図表とは如何なるものであるか。
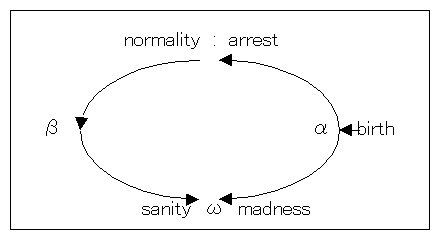
これについてのクーパーの説明は、どのようなものであろう。それは、次のようなものだ。「多くの人間は誕生の瞬間から、社会的な正常性を身につける上で、家庭や学校を社会的な学習の場にして発達していく。多くの人々は、発達上、この正常という状態にとどめられたままでいる。ある人々は、この発達の過程で挫折し、図にある狂気という状態へと後戻りする。また、ある人々は、ごく少数ではあるが、疎外された統計学的正常性とも言うべき惰性あるいは停止の状態をうまくすりぬける。そして、正気への回路にある程度まで進んで行く(β)。これらの人々は社会的正常性の判定基準を熟知しているので、他者による無効化を避けることができる(これは、常に賭けなのである)。正常性というのは狂気からだけではなく、正気からも遠く隔たった対極の位置にあることが判るだろう。正気は狂気に近づくが、最も重要な亀裂、すなわち差異は常に存在する。これがω点である」(p.32)。
クーパーの言う「最も重要な亀裂」であるω点における差異、これは一体如何なるものなのであろう? 正気の者と、狂気の者との差異は(sanityとmadnessとシェーマにはある。しかしここでbirthの語が記され、このシェーマ自体人の発達について書かれたものであるわけだから、むしろクーパーの指示に逆らって、これをthe saneとthe madと読むことは、おそらく正当であろう)、クーパーのこのシェーマから判断する限り、その正常性にしかない。説明しよう。狂気の者は、「この発達の過程で挫折し」て狂気へと「後戻りする」。ところが、正気の者とは、「統計学的正常性」をうまくすりぬけてきたが故に「社会的正常性の判定基準を熟知している」。どちらも正常性からは離れているが、この一点に関してのみ異なる。であるなら、ω点における差異とは、無効化されるかされないかが本質なのではない。正常性を持ち得るか否かが本質なのである。したがって、クーパーは、「最も重要な亀裂」を「正常性」の有無に見ているということになる。このことは何を意味するのであろう。
その問いを先延ばしにしつつ、ふたたびクーパーのテクストを忠実にたどってみよう。クーパーは、「精神医学が正気の人間の利益とか偽りの利益を代表する限り、精神医学それ自身が振るう暴力こそが、実は精神医学における暴力だと我々は悟る」(p.29)と述べているが、この「暴力」とは具体的には何を指すのか。「ある個人の自由が他者の自由を腐食させてしまう作用を及ぼすとき、それを暴力という」(p.34)と述べたあとで、
人間集団は、集団外からのある程度現実的な脅威とか、または幻想的な脅威との関わりの中で形成される。しかし、この外的な脅威がより遠のくにしたがい、その集団はそれ自体の永続性を保証するためにふたたび恐怖を作り出さねばならなくなる。[……]この二次的な恐怖は、集団の内部解体を防ぐためにのみ集団から自由に生み出されたものであり、共同の自由という暴力によって引き起こされた恐怖なのである。この意味における暴力は、精神医学の分野では、精神障害者にさせられる運命にあるものの家族の中から始まってくる、しかし、この暴力はその家族だけにとどまることはない。(p.35)
すなわち、クーパーは、集団にはそれと認められる外部が必要だということ、そして、精神病は集団を維持するために想像上、戦略上生み出された内部の外部であるといっているのだ。であるならば、彼は「精神医学の暴力」という言葉で、ここでは具体的には共同体の暴力の一翼を担うもの、つまり精神病者の創出を意味していることになろう。そしてその方法は、ラベリングによる無効化=normの創出と維持、ありもしない根拠=categolizingを作り出す権威となることに他ならない。しかもそのことは、「主観がどうあろうとも」(p.34)、すなわち無意識的に行われているのだ。
更に、第五章においては、クーパーはむしろ狂気というものを、偏在するものとして語っている(例えばp.153を見よ)。このことは、クーパーが序章において、精神分裂病という狂気を実体としてではなく、人間関係論的に捉えることを提起したこととパラレルである。それはもう一度第一章においても繰り返される。「問題は、いわゆる‘病者’の中にあるのではなく、個人個人が相互に作用し合うネットワークに、とりわけ家族の中にあるといえる。[……]いわば、狂気は個人の‘内に’あるのではなく、‘患者’というラベルを張られた個人が関与している一つの関係システムのうちにあるのだといえる。[……]精神分裂病者などというものは存在しないのである」(p.50)。この主張こそ、おそらくクーパーが最も強調したい点であろう。
「臨床精神医学の基本的分類」(p.30)に対してラディカルな異議申立てをしようとしているクーパー、「正常性」を「正気」から離れた単なる「統計学的概念」であるとして(p.31)退けようとするクーパー。しかし、同じクーパーが、ではどうしてFig.1においてω点における差異を、正気の人間と狂気の人間との間の決定的な「亀裂」を語ったのか? このことは何を意味しているのか?
これほどまでに従来からの精神医学に抵抗を図り、狂気の再評価をしようとするクーパーは、しかし同時に正気との差異を強調せざるを得なかったのだ。それも、「正常性normality」の有無によって。差異を消しつつその差異をふたたび強化しようとするこの運動こそ、クーパー自身のnormへの依存心を示している。
別の箇所から、この読みを補強しよう。それは、第四章の最後で語られていることだ。
実際に狂気になって(解体して)精神病院に入院してくる患者のうち、少数部分ではあるが――それは意味のある少数であるが――次のような精神科医や看護婦を必要としている者がいる。つまり、自分の不安を充分に克服している者、自分自身の狂気に対しても比較的忠実に向かい合っている者、正常よりは正気を選択することによって正気になり得ている者、そのような医者や看護婦が必要とされているのである。新しい形式の精神医学的状況を始めるときに必要なものは、決して種々の技術や計画表なのではない。まさに正気の人間が必要なのである。(p.124)
正常な家族、正常な精神科医は、患者を救うことはできない。正気の人間こそが救い得るのだ。それがクーパーの主張である。正常性とは、normal性ということなのだろう。だが、この主張は、慎重に読み取らねばならない。正気の者を、むしろ狂気に近いが故に狂気を理解でき、かつそこから救い得る、のであるとするなら、やはり狂気は狂気であって正気ではないということになるだろう。狂気の者は「解体」しており、「再統合」のためには正気の者の助けが必要だとクーパーは述べるが、それは何を意味するのだろうか?
クーパーのテクストをふたたび辿ってみよう。「[縦断的複合=患者の家族との関係史と、横断的複合=今ここでの患者と回りの人間との相互関係を理解することによって]患者がそれまでに受けてきた無効化の形態を正確に捉えることが可能になるし、患者がその無効化の餌食になったのは彼自身の生き方のどんな失敗によるのかも正確に理解できるようになる。同時に、患者が自己のある種の復活を願うときに伴う特殊な緊張をも、我々は理解できるようになる。もし、この願望に我々が気付いてその実現のために正当な人間関係を与えることが出来るならば、患者は自分を葬ってしまおうとするマス化された社会の要請に対し、単純に反応することはないであろう」(p.118)。これを、Fig.1の次の部分と比較してみることは、意義深いことである。「ある人々は、この発達の過程で挫折し、図にある狂気という状態へと後戻りする」。「挫折」、「失敗」というタームから、クーパーはここで、明らかに精神病を患者自身の責に帰していることが理解できるだろう。
いや、確かにそのあとでクーパーはこうも述べている。「[我々の社会においては、自己を解体していく時期=挫折や発展の時期に先立って社会的な無効化が起きるが]これらの無効化の過程こそが決定的な破壊をもたらすものなのである。適切な方針さえ与えられれば、精神病的な体験はもっと進んだ人間的な状態になるかもしれない」(p.121)。社会的な無効化=他者からの干渉こそが、精神病的挫折を生む。この主張は、先に挙げた議論とは矛盾している。だが、それでも精神病が、何らかのtombeによるnormalでない状態であるということには変わりはない。それは、「復活」というターム設定から既に明らかだといえよう。精神病的状態は、決してnormalな状態としては語られない。マス化された社会への批判を語りつつも、そこでのノルムの強固性・一貫性故に、クーパーは批判し切ることは出来ない。
更にクーパーの議論を辿ろう。「人は、自分がバラバラになってしまうことを許してもらいたいと願う。そして、ふたたび自分がまとまりを取り戻していくのを、助けてもらいたいとも願う」(p.118)。「[……]存在は、性質とか属性ではありえないし、ましてや性質とか属性として現れることもない。したがってこのことを明確に認知するときに、他の存在の真只中におかれている自己存在からの分離が必要となってくる。[……]この無の淵にたどり着いてはじめて、存在、すなわち私の存在があるといえる」(p.119)。ここで彼は、ドゥルーズの言う「単独性」を主張していることになろう。あらゆる属性・性質を超えた「この私」を主張するというのだから、「この私」とは権利上如何なる性質も属性も主張できない。「この私」を支えるものは何もない、というそのことが逆説的に「この私」を支えるのだ。このロジックそのものは極めて強力であろう。nothingとは一つなのだから、人はここから不可避的にoneであるのだ。しかし、ここでクーパーは自分の提起したロジックに逆に足元を掬われているといえないだろうか。如何なる状態をも超えて人はoneであるとするなら、どうしてクーパーは人がバラバラになってしまうということを想定できるのか?
ここでのクーパーは、ほとんど何かに急き立てられているかのようだ。一体どうしてクーパーはここで人がoneであるということをここまで語らねばならなかったのか? クーパーは人と人との間の関係から精神病を説明しようとした。精神病を患者として実体化するのではなく、微視社会的なネットワークにおいて現れるゆがみとして説こうとした。その説明を忠実にたどるのであれば、むしろ人がoneであるという主張それ自体を批判するべきだったのだ。人とはこの極度なまでに錯綜したネットワークの中で突き動かされるフィクションであると言ったほうが、クーパーの最初の意図からすれば正確な言い方になったのではないか。このクーパーのためらいから、次のように推測することはむしろ妥当である。即ち、クーパーは、そう語ることなく、彼の属する共同体の規範、即ち人はoneであるべきであるという通念を反復してしまっているのだ。まとまりを取り戻したいと言う願いは、共同体の要請を内面化したものであるという視点を、それゆえ彼は採ることが出来ない。
「[……]注目すべきは、解体するためには練り上げられた戦略を生み出す必要があるということである。バラバラになりつつある人々がそのような基本的戦略を独自に生み出そうとするとき、精神医学こそがその糸口を与えてあげるべきなのである」(p.123)。良い精神医学とは、正常ではなく、正気の人間がいるところだ。正気の人間だけが、再統合への助けをすることができる。しかし、ここでいわれている「再統合」とは何か? バラバラからoneへとなることであろう。これは、社会の中で、社会の役割に同一化することと何が違うのか? oneになるべきというのは、そもそも社会的通念である以上、そのように問うことは妥当である。望ましい社会ならよいと、彼は言いたいのか?
それ以上に、正気の人間こそが狂気のものの再統合を助けることができると言う主張の意味は何であろう。正気の人間と狂気の人間の差異は、正常性を保ち得るか否かであった。そしてそのことは、norm即ち共同体の規範に従っていることと読み替えて良いであろう。ならば、次のように読むことは正当なのではないか。狂気の者は、彼らの側には社会のnormが無いが故に、再統合はありえないのだと。「解体」、「再統合」と彼はいうが、結局の所それは社会的規範に従うことを意味するに過ぎないのだ。バラバラな狂気の者よりも、oneである正気の者の方に、明らかに重点がおかれている。狂気madnessは正気sanityに近いと言う理由だけで評価されている。「解体」という「限界状況」(p.122)を、彼は「限界状況」と呼ぶことでその内実を「新たな生」である正気に、normal性の下に、テロスとしてのnormに帰属させてしまうのだ。これがnormへの依存心の表れでなくてなんであろう。彼はたとえ狂気を評価することがあったとしても、狂気の者を評価することはありえないのだ。
クーパーは、精神医学それ自身の暴力を批判しようとした。それは、具体的には精神病の創出に関わるものであった。だが、クーパー自身、そうした共同体のnormを反復している。彼は「精神医学」を批判しようとして、「精神医学」を反復している。
別の点からクーパーの揺らぎについて考察を進めよう。彼は「精神分析」については、更に微妙な、あいまいとしか言いようの無い態度を示している。例えば彼は、多くの箇所で、「精神分析」を「精神医学」と同列に扱っている。「精神分析」を、名前を挙げて批判している箇所を一つずつ上げてみよう。
「還元的分析が、たとえそれが生理学とか学習理論から組み立てられたものであろうと、また精神分析理論から組みたてられたものであろうと、完璧にしかも詳細に提示しているのは、人間と対立するような有機体としての外的及び内的背景である。[……]本能衝動と攻撃衝動といったものに還元されていく。いわば一連の抽象的な理論系列が結び合わされた交点は、人間の持つ(絶対に)還元し得ない現実として措定されているのである。[……]還元的分析の成立基盤となる諸説は、人間実在がその外部にある要因によって構成されていく方法に関したものでしかない」(p.23)「精神医学の歴史の主題は、巧みに公共の便宜を図ることにあって、その結果が、大精神病院、外来診療所、総合病院の精神科、そして時には不幸にも精神分析の寝椅子、といったような形をとって広くゆきわたってきた」(p.30)「人がその身を委ねている医者は、症状(常に、転移させるか、抑圧せねばならないものとしての)という惰性的な非人間的分野や、疾病過程のみを相手にしているのである」(p.47)「我々は相互作用を研究するに当たって、精神分析的方法を排除してきた。[……]‘純粋な’精神分析的研究は決定システムの相互作用を理解する枠組みを欠いているために、常に中心課題からそれたところに停まっていると言えるだろう」(p.110)「精神分析的なグループでは、患者たちの言葉や行為が種種の葛藤の長期的徹底操作という視点に還元されてしまう形で解釈されている。[……]‘入院した急性精神分裂病’と呼ばれるような一つの課題に関しては上に述べたような分析的接近はむしろ不適当であると考えたからである。この精神分析的な状況は基本的にはかなり欺瞞に満ちた状況といえる。そこでは患者にさせられた者とその挿話に関わっている他者との間で起こっている全てのことが、実質的にはこの欺瞞を受けてしまうのである」(p.115)「ある種の精神分析家たちは、一元的な状況の中で研究している。即ち患者を取り巻く人間環境を切り離したところで患者を観察しているのである。従って時にこの点にこそ彼らの致命的な限界があるように思われる」(p.116)
これら多くの箇所で、クーパーは常に精神分析を自身の方法論とは真っ向から対立するものとして論じ、批判している。だが彼自身が提示する反精神医学的立場は、本当に精神分析とは無縁なものであろうか。そもそも「精神分析」とは如何なるものであろうか。私はここで、精神分析の歴史を丁寧にたどって行く余裕はない。例えば一般に精神分析学の創始者と呼ばれるフロイトについてだけでさえ、そのテクストは要約を許すようなものではない。しかし、いくつかの特徴線をそこから取り出すことは、実際にその錯綜したテクストを解きほぐす作業の前作業としてであれば、許されることでもあるし、必要でもあろう。そうした特徴線を、ごく大雑把に素描することをここでは試みよう(尚、フロイトについては、別の機会に丁寧にたどる予定である)。
フロイトの提示した問いとは、簡単に言えば、意識では補足することの出来ない情報経路があるということ、そこでの伝達が主体に対して何らかの影響を与えるということである。この意識では捉えられないものをフロイトは「無意識」と総称した。それは、抵抗という形で、つまりポジティフには語り得ない形で、その存在を示すようなものである。それゆえ、無意識は実体としては取り出すことが出来ず、あくまで分析者-被分析者の関係の中でのみ可知化されるに過ぎない。
この情報伝達は、時として極めてゆっくりとした速度で行われる。過去(例えば幼少時代)の何らかの外傷的経験が現在になって回帰し、主体を脅かす、がしかし主体はその脅かされる原因=発信源を知らない。このような、通常我々が意識の中で経験される時間感覚とは、まるで異なったクロックで伝達される伝達経路の存在が、無意識を構成している。これがフロイトの提示した一つ目の問題圏である。
ところでフロイトの観察したことに因れば、この回帰は現在と関連がある、というよりむしろ現在それ自身である。どういうことか。過去の外傷経験も、現在の状況によって主体を脅かしたりしなかったりする。無意識に備給された情報の行方は、現在の状況によって影響される。時には、外傷経験など実際にはなかったのだとしても、あたかもあったかのように主体に影響を与えてしまうことすらある。無意識という情報経路は、単純な伝達ではなく、それ自身他の情報の影響を受けて混線する。無意識という情報のネットワークは、不完全なものであり、それがいつ発信されたものなのか、何が発信したものなのか、特定できないし、その内容もまた分割されたり混じり合ったりする。こうした不完全なネットワークとしての無意識、これがフロイトの提示した二つ目の問題圏である。
さて、しかしこれだけだと無意識とは個人のものでしかない。フロイトは更に議論を進めて行く。意識と意識との間で伝達がなされるように、自分の無意識と他者の無意識とは連結しうる。それゆえ、人は全く意識することが出来ないまま、他者の無意識的伝達を受け取り、行為してしまう。フロイトは次のようなことを記している。ある女性が夫の性的能力をめぐり不安神経症になった。無論、彼らの意識はともにその原因を知らない。しかし夫は「その妻の不安の意味を告白も説明も無しに理解し」、「彼の方でもまた神経症的に反応した。即ち彼は夫婦交渉を――最初から――拒絶したのである」。他者の無意識的表明を意識を介さずに理解するこの能力の存在こそ、精神分析技法を支える重要な柱でもある。フロイトはここで、人と人との間での、無意識の連結を語っているのだ。精神分析は、この無意識における伝達を主題化する。無意識とは個人の中でとどまることはない、これがフロイトの提示した三つ目の問題圏である。注意しよう、これはユングが言った社会的無意識とは違うものだ。フロイトは、これらをあくまでの情報のネットワークとして捉える。そして、ここから彼の重要な概念である「転移」が理解される。転移とは、他者からの無意識的伝達による症状なのだ(こうした視点は、おそらく彼の娘のアンナ・フロイトのフォーマットからは理解できないものであろう)。
これらを「精神分析」と呼ぶとき、クーパーの議論はどのように読み得るであろう。結論を先取りして言ってしまうなら、そもそもクーパーの議論とは、精神分析の議論そのままなのではないだろうか。
具体的にクーパーのテクストを見てみよう。彼は次のように述べている。「患者の‘精神分裂病的’な自己表現を了解することを目的としなければならない。その時、‘縦断的’複合と‘横断的’複合の両面から、その行動を理解する必要がある。縦断的複合とは、家族の中での患者の発達に関するもので、その発達は彼の両親の家族の起源にまで遡って理解されるべきものである。また、横断的複合とは、今ここでの患者の相互作用に関したものである。その相互作用は、病棟の患者やスタッフとの関係であり、患者に面会に来たときの両親や週末に家に帰ったときの両親との関係である」(p.118)。過去における体験=人間関係と、それが現時点でどのように反復されているか。これは、上で述べたように、精神分析における基本的な枠組みに他ならない。更に、こうした無意識経路は、単純に意識化されることは普通なく、他者との関係の中でのみ可知化されるというクーパーの論の立て方そのものが、きわめてフロイト的なものであることは、疑いようもないであろう。ここでの彼の記述は、フロイトを忠実に反復している。
クーパーの論の立て方は、彼が反精神医学的な議論を提示しようとしていればそれだけ強まっている。詳しくは分析しないが、彼が転移や投影、関係論など精神分析的ツールによって語っている箇所は、実際非常に多いのだ。目に付くところだけでも拾ってみよう。如何に多くの箇所で彼がこの枠組みを使っているか、はっきりと理解できるであろう。また、これまで彼が精神医学批判として語ってきたこと(本論において、前半部で展開した)が、如何に精神分析的なものであるかも、感じられるであろう。
「精神分裂病とは、微視社会的な危機状態である。ある個人の行為や体験は、[……]他者によって無効化されてしまう」(p.11)。「中心課題は、まず、[……]‘急性精神分裂病患者’という診断が下されたものが呈する言語的コミュニケーション及び、非言語的コミュニケーションの総和を取り出すことである。次に、患者とその患者が関わり合っている他者との間で現在起こっていることや、過去に起こっていたことが、どの程度までこの行動図式を可知的なものにしてくれるか明証することである。[……]患者を観察するとき、私は二つの必要事項を決定した。一つは、病棟集団における患者の相互作用を観察することであり、一つは、それと同時に患者各々と家族との相互作用を観察することである。[……]家族集団の作用について得られた理解によって、病棟内の相互作用がもたらす現象に対してどのような光明を投げかけることが出来るのかを確認する目的からである」(p.12)。「相互作用においては、我々各々は、絶えず全体化を脱全体化していく統合体ということになる。一つの行為をするごとに、わたしは自分自身を対象化する、いわば自己自身を世界に刻印する。[……]しかしこの自己自身に対しての対象化は、自己の統制範囲から抜け出して、あなたの統制範囲に入っていく。[……]この自由の行為こそが、私の自由を制限してしまう一つの対象化を生み出すのである」(p.18)。「一つは、説明可能な過程[=生物学的な疾病プロセス・個体内的 ex.脳器質性疾患]として理解するのが極めて適切であるというように表現し得る行動と、一つは、人々が実際に相互に何をし合っているのかという点から見たときに初めて可知的になる行動とを、区別すべきなのである」(p.36)。「もし子供が家族のルールを破るならば、その規則違反が明らかに無害な自律行為から起こっているものにせよ、それは家族集団を決定的に崩壊してしまうことであり、同時に母親の人格やその他の家族の人格をも解体させてしまうことになるのだと教え込まれる」(p.37)。「精神病院においても、人との付き合いが一つの社会構造を巧妙に生み出してきた。それは、患者の家族がもっていた狂気を作り出してしまう特殊性といったものを、多くの点で繰り返している構造といえる。[……][病院のスタッフは]患者が失敗してしまった家族内のゲームと、そのゲームの複雑さという点において極めて似通った対人関係というゲームを演じている」(p.38)。「きわめて広い範囲にわたって言えることだが、精神分裂病者の‘疾病性’とか非論理性は、他者の論理自体の疾病性に端を発しているものである」(p.43)。「患者を疾病過程によって変質させられた存在としてみる考え方に、いわば生物学的・心理学的・社会的な考え方全て、あるいはその一部を含む考え方に疑問を呈していかなければならない」(p.48)。「[……]この過程を段階的に見ていくと、[……]まず他者が一人の人間を無効化するという行為、つまり否定の行為がある。[……]そして次に、この否定の行為は、様々な方法で否定されていく。即ち、その人は自分自身で無効化してしまったのだとか、または生まれつきの弱さや疾病過程によって無効化されてしまったのだと見なされてしまう。[……]閉め出す側の人々は、自分たちを‘善良’で‘正気’の人間であると規定しているのである。つまり彼らは、二重否定というその上塗りをすることによって、安全で居心地の良い集団恒常性を維持しているのである。一方、集団のスケープゴートとして選ばれたものは、しばしばこの過程に迎合してしまう」(p.54)。「[家庭において]両親が重きをおくのは、周囲に受け入れられる社会的役割を提示することであって、子供に対して自分自身を現出することではないのである。[……]家族の中で両親が提示しているのは、実際には不在でしかないということだ。いわば、両親から提示される社会的役割はまず持って対他存在という実存的構造を持つことになり、対自存在は二次的なものになってしまう」(p.61)。「‘精神病的な’構築は、主として自己の行動とか実践を疎外している家族過程を具現化したものなのである」(p.63)。「double binderは相手からの反応を一方では望んだり要求したりするが、同時に他方では望んでもいないし要求してもいないという点において、その論理体系は二重なのである。[……][子供に想起させようという]両親の要求は、社会的に決定されている本当の要求であって、決して‘嘘’の要求ではないのである。しかし、この要求は、もう一方の社会的に決定されている[子供に忘れさせようとする]要求とは相反したものである。実は、double binderはdouble bindさせられている者でもあるのだ」(p.74)。「課題となるのは、まず精神分裂病者にさせられた者の行動を取りだし、その行動が過去と現在における他の人達との間の相互作用の側面からどの程度まで可知的なものと見なせるかを見極めることである」(p.78)。「エリックの将来は、両親の過去の経験と現在の要求に適合するように家族によって明確に厳密に計画されていたといえる。いわば、エリックは異常なまでに媒体となってしまったのである。即ち、両親は自分たちの過去にかなえられなかった希望や満たされなかった欲望を、エリックという媒体を通して、代理的に実現させようとしていたのである。[……]彼にとっては、彼の対他存在が彼の対自存在を越えて、実存的優位を保っていたのである」(p.87)。「このように自己の自律性を主張したために彼は病院に入れられてしまった。何故ならば、彼が自由で人間的な構造を劇的に始めたために、家族の実存構造全体が脅かされてしまったからである。だから、家族は病気を捏造することで、彼の自律行動を無効化してしまわねばならなかった」(p.98)。「実体の明白ではない‘声’が彼のわがままを非難するのを‘聞いた’と彼は言っていたが、その声は、以前家族面接の中で父親によって述べられ記録にも残されている所説が内在化されたものであった。また、‘他の人達’が彼について感じていることに関しても彼はおぼろげながら何かを感じていたが、その彼の感情は、両親が彼について持っていた感情から引き起こされたものであった。[……]エリックには、これらの内在化された所説と感情が自分自身のものではないことはわかったが、それらの真の出所を突き止めることは非常に困難であった」(p.108)。「‘精神分裂病’を疾患単位として理解するのではなく、それは人間同士の相互作用のパターンのある一定の組み合わせであって、その組み合わせが多かれ少なかれ特異なものであると理解することが必要なのであった。いわば、精神分裂病は一人の個人の内に起こってくる何かなのではなくて、人間同士の間に起こってくる何かなのだと理解することである」(p.114)。「転移とか投影といわれるものは常に存在している」(p.116)。「[このvilla21というユニットは]ある程度病院内の‘悪’が投影されて行くスケープゴートになってしまう可能性がある」(p.126)。「もしも患者が病棟の日常的な仕事や様々な作業療法の種目を充分にしなかったり、あるいは病院の庶務部門の手伝いをしなかったりすれば、患者は‘引きこもった’‘収容されたままの’‘慢性患者’になるだろうという幻想が、暗黙のうちに考えられていたり、時には語られたりしているのである。ところが、これらの命令された仕事の全てを黙々とやり通すような患者こそが、とりも直さず、上記のラベルの内実を持った者なのである」(p.134)。「もしも精神科医が、患者から、言いかえれば医者自身の障害を投影した患者から、身を守るための一つの手段として白衣と聴診器を用意しているとすれば、一連の印刷物もまた、そのためのもう一つの手段であるといえよう」(p.139)。「患者は、‘ここ’に、つまり内部にいるのである。これに反して、スタッフはここにいないのである。単に、行ったり来たりしているに過ぎないのである。[……]基本的にスタッフは部外者なのである。[……]人は、‘ここ’と‘そこ’の間にある特有な弁証法について熟考することとなる。[……]ここにいないということは、現在の実際の状況の中に存在していないということである」(p.157)。
長々と様々な箇所を引用してきた。こうしたテクストの箇所から明らかになることは、クーパーの論が、如何に精神分析の方法論を反復しているか、ということである。それと同時に、にもかかわらずクーパーは精神分析を、二箇所を除いて、決して評価しようとはしない。それに、その二箇所も、決して全面的に評価しているのではなく、奇妙な両義性をにじませた形で語っているに過ぎない。「精神医学の大部分の資格取得過程の中においては、[精神療法的技能や、小集団の社会学に関する教育や経験などといった]これらの技能が著しく軽視されているか、もしくはその過程から除外されているのである。選考委員会の委員の中には、正統的な精神分析教育に偏見を持っているものもいる」(p.140)。「精神分析教育は、一つの要素として厳しさというものを教えてはいるものの、社会状況から生じてくる要請がかなり多岐にわたっているために、精神分析教育はこの要請に充分に対応していくことはほとんど出来ないと言って良い」(p.154)。
一体、クーパーの、この精神分析に対する拒絶は何を意味しているのだろうか。どうしようもなく反復しながらも、頑なに自身の中に混じりこむ精神分析を否認しつづけているのは何故なのか。
私は本論の中で、クーパーが、批判しつつも、どうしようもなく反復してしまうものとして、「精神医学」と「精神分析」を、それが彼のテクスト上で如何に現れるかを、辿ってきた。彼の態度は、この両者いずれに対しても、両義的で錯綜している。だがその意味合いは異なる。ごく大雑把に言ってしまうなら、彼の提示しようとする反精神医学とは、精神分析のことであり、そしてそこから精神医学への抵抗を図ろうとしているのだ。したがって、彼の中にその両者が混入していると言っても、その意味は全く違う。
こうしたクーパーの両義性、あるいはためらいは、実はクーパーのテクストから理解され得る。それは本論の中で多少触れてはいるが本格的には取り上げてはいない問題圏である、人間主体のonenessに関する問題圏である。クーパーは、関係論的に精神分裂病を考えようとしている以上、即ち精神分析的にアプローチを試みようとしている以上、人がoneであるということを権利上主張することは出来ないはずである。しかし彼は、この、人というものがoneであるべきだという彼の主張を、結局最後まで捨てようとはしない。
本来この問題は、きわめて慎重にテクストをたどって示すべきであろう。しかしここではごく乱暴に述べておく。クーパーは、このテクスト上で、きわめて頻繁に「自律」「主体」「実存」といった人のone性を示す言葉をポジティフに用い、「解体」「疎外」など人のone性を否定するタームに関しては常にネガティフに用いている。これは、クーパーの中に、彼の属する共同体のnormが混入したためだということは前に述べた。しかし実際にはもう一つ理由があるのではないか。つまり、クーパー自身の、「解体」への恐れからである。
クーパーはおそらく、自身の中に「精神医学」的な概念、「精神分析」的な方法論が混入してきていることを、意識的にも無意識的にも感じていたに違いない。それは彼に、言いようのない不安感、あたかも自分自身が解体させられてしまうような不安を巻き起こしたに違いないのだ。何故か。「精神医学」に関してまず考えよう。彼は「反精神医学」を提起しようとしているのだ。「精神医学」に対して反対しているのに、どうして彼は自分自身の中に精神医学的契機が入り込んでいることなど認められようか? 更には、現在の我々の共同体のnormに対して反論しているのに、どうして自分自身にそのnormが混入していることなど認められようか? もし認めたとしたら、彼は自分の立論が、結局共同体の暴力の反復に過ぎないことを認めることになってしまう。自身が精神医学という暴力に荷担していると認めることになってしまう。そんなことはどうあっても認められるものではなかろう。そうした疑念を、そうした自分自身の不安を振りほどくためにこそ、どうしても彼は「精神医学」を認めることは出来ないのだ。
しかしそのためには、主体を情報の束と見なし、主体のone性を認めない精神分析は、おそらく彼にとっては決定的な脅威でもあったに違いない。もしも主体が一つではなく、分裂を許すようなものであるとすれば、彼が如何に自己の議論の正当性を主張しようとも、語るその端からそうした正当性は突き崩されてしまう。彼がいくら必死になって論じようとも、彼が言おうとすることはそのままの形では決して伝わらないのだ。精神分析を認めてしまうと、精神医学の混入もまた否定できなくなってしまう。彼の主張は精神分析無しにはありえないが、同時に彼は精神分析を恐れていた。
彼が人のone性をあれほどまでに強調するのは、したがって彼の不安の投影によるものだ。彼の議論は、彼自身の怯えによって駆動されている。だが、この怯えとは、一体何であろう。このことは、一人クーパーの問題なのだろうか。そうではあるまい。彼はどうして怯えたのか。彼は何故不安を感じねばならなかったのか。いや、そもそもどうしてそれでもクーパーは書いたのか。それも、我々が見たように、彼自身の不安が目に見えるような形で。このことは、更に別の形で掘り下げられる必要がある。そしてこのことこそ、クーパーを今なお読み直すべき理由でもあるのだ。