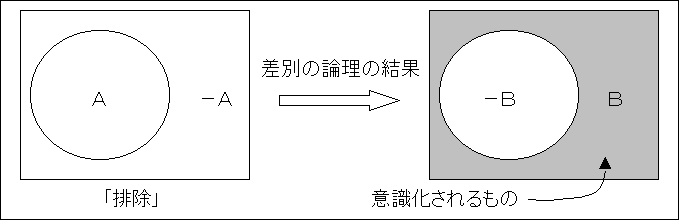
Antipsychiatry試論#3
#3.1. クーパーは、まさに冒頭で、次のように記している。「教育研修病院や精神病院で行われる正規の研修や日常の教化を制度化していく過程がどんどん進行しているが、それにもかかわらずその過程の中で自分がまさに無感覚にさせられたり、飲み込まれてしまいそうになっていることに対して、多くの人々は批判的認識を持とうとしないままで精神医学の分野に関わっている」。批判的認識、即ち自分が今置かれている状況や、今自分が為そうとしていることへの自覚が、多くの人には欠けている。彼はおそらく、「反精神医学」を語ることで、現在への自覚を促そうとしているのだろう。だが、前に見たように、何よりクーパー自身が、自分が受け取っている情報――即ち、精神医学と精神分析――の系譜を知ることが出来ていない。その意味では、クーパーは単に自己矛盾を引き起こしているだけに過ぎない。一方で私は、そのことを確認しておく。だが、クーパーは無自覚なままに、実は様々な種子を、この本の中でちりばめているのだ。それはstaticには見ることは出来ない。そのことを知るには、我々はむしろ、きわめて特殊な読解に進まねばならない。そのことこそ、我々がまさに今、クーパーを読みなおすべきである理由を明らかにするであろう。
この読解のため、私はいくつか補助線を引いておく。
江原由美子は、次のように書いている。長くなるが、必要な議論なので、引用する。
性差別や身体障害者差別の論理はこの意味で二重化されている。女性や障害者はカテゴリーとして「差別」されているのだが、その根拠付けとして「能力」や「業績」、「身体的条件」が利用され、その測定のためにまた、性別や障害の有無などが指標として利用されているのだ。結局女性や「障害者」は、女性であるゆえ、「障害者」であるゆえをもって「差別」されているということができよう。それゆえ、いくら女性が「能力」があることを説明しても「差別」はなかなかなくならないのである。なぜなら女性は女性であるゆえに「差別」されているのではなく、男性でないために「差別」されているからである。
即ち、女性は女性の固有性や特殊性によって「差別」されているのではない。それらはそもそも差別者の考慮の外にある。「差別」において女性は単に「男でない」標識を持つものとして意識されるに過ぎない。そもそも女性はその能力や適性をそれ自体として認識されるべき位置にいないのであり、そのことが「差別」なのだ。
「差別」には二重の方向があるという。一つは縦の軸、即ち差別者=優越、被差別者=劣等と価値づける軸であり、他の一つは横の軸、即ち被差別者を「排除」する軸である。この二つの軸において通常、前者だけが認識されやすいが、どちらがより「差別」の本質を示すかといえば後者の方である。「差別」は社会の中心的な組織形成のための、組織論的必要から生み出されたのであろう。それは組織から特定のカテゴリーに属する者を「排除」することを目的としていると思われる。ある人々を「排除」することで、内集団の結束や凝集力を高めうることができるのかもしれぬ。
だが差別の機能が何であれ、それが被差別者の特性や固有性とほとんど無関係であることは明白である。「差別」は「差異」などに根拠を持ってはいないのである。「差異」の定式化やその評価はむしろ、「差別」の不当性を見えなくさせるための装置である。
それゆえ、「差別」をあたかも「正当なもののごとく」に産出する「差別の論理」のもっとも重要な論点は、被差別者の特殊性、固有性を主張することである。このことこそ、もっとも重要な論理であり、すべての「反差別」の言説を困難にさせる効力を持っている。
それゆえ、「差異」とその評価をめぐる議論においてもっとも重要な論点は、被差別者に帰属させられている属性が否定的なものであるか、その評価が妥当なものであるかといった問題なのではない。それがいかに正確かつ適切なものであろうとも、「差異」とその評価が「差別」問題を解く鍵のようにしくまれている限り、その論は不当である。すなわち「差別」が「差異」に基づくものであるかのように思わせる点において不当である。
(『「差別の論理」とその批判』)
この江原の議論は、現在に至っても反復している問題点を鋭くえぐっている。差別の論理において重要なのは、差異の内容それ自体ではなく、差異の内容を考えるようにしくまれている無意識的権力構造なのだ、という江原の議論は、現在においても光っている。さて、江原はこのあと、この「差別の論理」を図式化して説明している。要約的に述べよう。
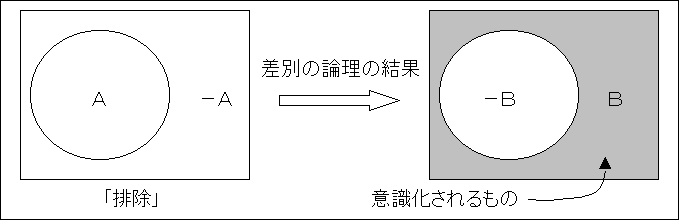
「差別」とは、本来特定に人々を「排除」する論理である。さて、図の左側は、ある組織においてマジョリティである人Aが、特定の人々を排除する論理を示す。この論理は明快だ。つまり、排除される人-Aは、Aでないがゆえに排除されるのである。だが、これは根拠付けを持たないがゆえに意識されない。それゆえ、-Aとカテゴリー化された集団が、Bという属性を持つことだけが強く主張され、それこそがあたかも「排除化」の根拠であるかのように意識されるのである。
言い換えよう。Aは-Aに対し、Aでないという理由でAの成員が持つ基本的権利を否定するのであるが、そのことは-Aの属性(B)が提示され、Aの属性は単にその否定として示される(-B)ことにより、あたかも-Aに帰属させられるBという実体的な「差異」的属性こそが、Aの-Aに対する「差別」的待遇の根拠であるかのように装置の中にしくまれるのだ。たとえば女性が男性から排除されるのは女性が男性ではないために過ぎないのに、あたかもそれが女性に帰属される属性、たとえば女性が子供を産む性であるとか、感情的・感性的であるとかいった属性を持っているためであるかのようにしくまれるのである。このように論理化することで「差別の論理」は「実在的差異」という論の根拠を得、このようにしてその不当性は目からそらされるのだ。
問題は、このようにしくまれた「差別の論理」の効果として、被差別者が「反差別」の論理を立てることが困難にされることだ。どういうことか。「差別の論理」は、現実の差別の正当性を論証することは出来ない。する必要すらないのだ。被差別者が「排除カテゴリー」として位置づいていることを「差別の論理」は隠してしまうので、「差別」を「不当」なこととして論証する責任は被差別者の側にあることになる。だが、「差別の論理」は差別者―被差別者を、被差別者の有徴性と差別者の無徴性として描き出す。すると、差別はあたかも被差別者の側の「実在的な差異」に根拠があるかのように意識されることになる。差別の責任が被差別者自身にあるということにされてしまうのだ。そうすると、「反差別」を訴えるとき、被差別者は結局、自分がそのBという属性を持っていないという主張をせざるを得ない立場に立たされるのだ。これは、結局Aという属性に自分を同一化させることにしかならない。同時に、Bというカテゴリーに置かれた、Bという属性を持った別の人間と自分との差異を主張して、Bというカテゴリーに置かれている人への差別を容認することにしかならない。いずれにせよ、「反差別」の訴えは、そもそも初めから認められない構造があるというわけだ。
ここでの議論を援用しつつ、我々の議論に立ち戻ろう。精神分裂病者とそうでない人間たち。精神分裂病者は、社会的に差別されている。それは通常、精神分裂病者の持つ属性、たとえば妄想であったり、思考の道筋が立てられないことであったり、異常な振る舞いであったりすると考えられている。だが、上述の議論を考えると、それはむしろ逆立ちした議論である。むしろ精神分裂病者とは、「正常者」でないことを示す一カテゴリーに過ぎない。それ故、たとえば精神分裂病者一人を取り上げて、その立ち振る舞いがいかに「正常人」と同様なものであるかを示そうとも、精神分裂病者全体に対する意味づけは変わらない。更に、精神分裂病者の体験や言葉が、いかに「正常人」にとって有用な、崇高な、真理に迫ったものであろうとも、結局のところ差別の論理が機能している「排除」それ自体が変わるのではない。「排除」が変わるのではなく、「排除」された対象、有徴化されている対象即ち精神分裂病者への意味づけを変えるに過ぎない。それは、排除という差別の基本構造を維持したまま、その見た目を変える狡猾な手段に過ぎない。
この排除という構造が維持されている間ならば、むしろ精神分裂病について何だって言えるのだ。それは「正常者」にとっては全く関係のない世界なのだから、どんなに彼らが崇高な、「正常者」には近づくことの出来ない叡智を持ち、人生について本質的な思考をしているかなどと言っても、全く痛くも痒くもないのだ。我々は、現在までのほぼ百年間の間に展開されてきた精神病理学の多くの思想を知っている。そうした思想を展開してきた人々が、実はまさしくもっとも狡猾に、時代の社会的要請を受けてこの排除機械を駆動させてきたかを、我々は問うことが出来る。「狂人たち」のもっとも不幸な点、終わることのない不幸さとは、それは彼らを理解しようとしている人々こそ、最も巧妙に彼らを裏切る者であるということなのだ。
だが、単純化することは止めておこう。今必要なことは、この構造を見極め、いかにして歴史の中で反復され、生き延びてきたかを問うことの方だ。そして、実はそれへの抵抗は、クーパーの中にも素描されている。我々はここで、この構造の基盤を構成しているドイツロマン派の考え方を素描するため、フロイトの時代へと舞い戻らねばならない。
小林敏明は、その柄谷論の中で、フロイトのパラダイムについて述べている(『柄谷とカラタニの間あるいは永続する他性』)。フロイトのパラダイム、それはドイツ・ロマンティークのパラダイムである、と小林は言う。フロイトはロマンティークの素養を備えた人間であった。「カント的啓蒙主義がその反動としてドイツ・ロマンティークを誘発したことは良く知られているが、その代表ともいうべきノヴァーリスが『夢』や『内面への旅』を主題化することに手をつけ、それが哲学を含む文芸のあらゆる領域に亘って席巻していったのが十九世紀だとすれば、フロイトはいわばその運動の一つの集約点に立っている」。フロイトを、このようなヨーロッパ的規模での運動の中に置いて眺めてみることは必要なことだ。たとえば啓蒙的理性に対する批判を行った思想家として我々はアドルノやホルクハイマーを挙げるかもしれない。しかし、「彼らのオリジナリティはそれをナチ批判に結び付けたところにあるのであって、啓蒙的理性批判とそれに相即する同一性批判は必ずしも彼らの専売特許なのではない。それは彼らの最大の標的であったハイデガーの中にさえあるからだ。ニーチェ、キルケゴール、フロイト、ハイデガーを一覧するとき、それぞれに対処に違いはあるものの『不安』『死』『罪』『不気味なもの』『隠されたもの』といったテーマが驚くほど共通し合うという事実は一体何を語っているのか。それは彼ら自身が自覚していた、いなかったに関わりなく、一様に前世紀からの巨大な精神のうねりを受け止めていたということである」。この「精神」を、小林はロマンティークと呼ぶ。フロイトの切り開いたパラダイムとは、従ってロマンティークのパラダイムなのだ。
だが、ロマンティークとは単純にパラダイムだといって、「歴史的なもの」として切り捨てられるのか。「フランクフルト派のようにあっさりと『根源』を見つけようとすること自体が既に一つのイデオロギーだと批判して済むのであれば問題はない。だが彼らはそのことによって彼ら自身が依拠したフロイトの射程を狭めてしまった。[……]またカール・シュミットのように『オッカジオナリスムス』という、いわば結果論でロマンティークの問題が切り捨てられるのなら、これも話が早いのだが、あいにくこれはヒドラの触手のようなもので、いつでもまたいくらでも生えてくる。その点でそれは宗教に似ている。またハイネのように、これに「病い」というレッテルを貼っても、ロマンティークはそのレッテルを喜んで飲み込んでしまうだけだろう」。フロイトが相手にしたロマンティークとは、従って一筋縄ではいかないものだ。「フロイトはこれに言葉を与える道を探した。この道はハイデガーのように最後はただ沈黙の下に待ち望むという態度からはっきりと区別される。それは思考錯誤を伴った永続的な言葉による格闘の道である。ここにフロイトの本質的なジレンマが生まれる。言葉を与えるという作業は、それ自体が多かれ少なかれ啓蒙的理性を共有せざるをえないからだ。それ以外に道はない。それでいてフロイトは自分が格闘する対象によってその理性の側が崩れ無効になることも見ていた。ジレンマとは理性的言語の臨界点のことである。フロイトの著作を読んで様々な自己訂正や記述の矛盾が見出されるのはそのせいである」。
そして、このロマンティークのパラダイムは、現代をも規定しつづけている。柄谷、デリダ、ミシェル・アンリらが提示したデカルト論は、そのことをよくあらわしている。「デリダはデカルトの『コギト』の中に『未聞の独特な過剰さ』『未決定なるものと<無>と<無限>へ向かう過剰さ』『考えうるものの全体性や決まった実存性と意味の全体性や事実の全体性などをはみでる過剰さ』(『エクリチュールと差異』上百十頁)を認め、それをフーコーが言うような理性による『監禁』の世界から区別してみせたのであった」。アンリの主張も、「デカルトの『精神mens』は『知性ratio』や『理性intellectus』と区別されなければならない」というものであり、これは「『純粋理性の対-象化』『存在論的差異としての開けouvertの開性ouverture』であり、まさに語の文字通りの意味での『ek-stasis』である(『精神分析の系譜』二十七頁)。言うまでもなくこれはレヴィナスの『実存』ひいてはハイデガーの『存在』の焼き直しである。このことは多かれ少なかれデリダの解釈にも影を落としている」。
このように読みこまれたデカルトの「コギト」、デリダのいう「差異性・他者性」やアンリのいう「外部へ出ようとする意志」、柄谷の言う「精神」は、しかし、「いわば『自明性』や『同一性』『理性』の否定態として想定されるあらゆるものをぶち込まれたブラックボックス、更に意地悪く言えばごみ箱のような存在にされてしまっていることはもっと注意されていい。好みならばこの中にはまだ『夢』『狂気』『無意識』さえ放り込むことができる。これは構造主義、ポスト構造主義を中心にして展開されてきたこれまでの差異についての論議の最大の盲点である。『差異』『逸脱』『外部』『夢』『狂気』『無意識』『死』『暴力』『性』そして『他者』、もしこれらが事実みな同じところに収まるのだとするならば、それは何のことはない、結局フロイトが切り開いたパラダイムを反復しているに過ぎないのだ」。そして、このパラダイムは、先に見たロマンティークのパラダイムそのままだ。
この小林の議論を導き手として、我々の議論を進めていこう。ロマンティーク、それはごく大雑把に言えば、normalでないなにか、我々が通常生活しているこの共同体の内部とは違ったなにかを「外部」として想定し、それについて思考するある種の思考構造であるといって良いだろう。特に、ロマンティークでは、この『外部』が好んで取り上げられ、かつポジティフに評価される傾向にある。小林が挙げたように、「差異」「逸脱」「外部」「夢」「狂気」「無意識」「死」「暴力」「性」「他者」、これらはすべて、通常我々が触れることのない、normalではないという共通性があり、それらをロマン派は好んで取り上げたのだ。
さて、しかしロマンティークは、思考構造上この外部/内部の境界を設定することが前提として要請されていることになる。つまり、この思考形態以前にはもしかしたら存在しなかったかもしれないものを「外部」として放逐することで、はじめてロマンティークは存在できるのだ。もちろん、共同体は実際、ロマンティーク以前から外部を想定してはいただろう。そして、それ以前には外部はネガティフに放逐されるだけだったのが、ロマンティークはむしろこの境界の意味付けをむしろ逆転させ、外部をポジティフに語るようになったのだとも言えるだろう。しかし問題は、ロマンティークは決してこの境界自体を消し去ったわけではないということなのだ。
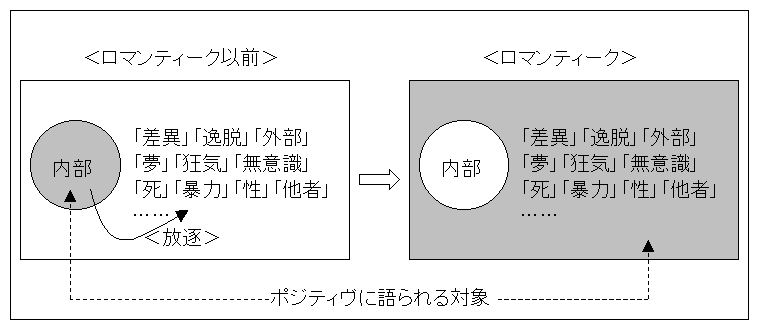
ロマンティークはむしろ、この外部/内部の境界を活性化させたに過ぎない。それ以前においては、この「外部への放逐」こそが逆説的に内部の結束を高めていたのを、ロマンティークは外部を語ることそれ自体によって内部を活性化させ、安定化させたという違いがあるに過ぎない。決してロマンティークは境界を消すことはない。なぜならこの境界こそ、ロマンティークの存在基盤であるからだ。さて、小林はフロイトがこの「外部」に言葉を与えようとしたのだと述べていたのを思い出して欲しい。フロイトは、この境界をそのままにしようとしたのではなかった。「言葉を与えるという作業は、それ自体が多かれ少なかれ啓蒙的理性を共有せざるをえない」が、「それでいてフロイトは自分が格闘する対象によってその理性の側が崩れ無効になることも見ていた。ジレンマとは理性的言語の臨界点のことである」。フロイトは、自身がこの外部に言葉を与えようとすることによって、単にロマンティークと同様それを食いつぶすことで内部を安定化させようとしたのではなかった。フロイトは自身の語る基盤であるはずの啓蒙的理性が、そのことによって崩れ無効になることも意識していた。よく知られているように、フロイトはすべての人間は神経症であると述べている。それは、多くの精神病理学者の述べる狂気、正気に対立する狂気とはまるで違ったものであることに注意しなくてはならない。フロイトは、神経症に対立する「正常さ」を認めていないのだ。いわば、フロイトはここで、まさにこの外部/内部の境界それ自身を問題視している。だがこの問題化は、既にして困難である。もしフロイトが、「内部」において流通している理性を完全に捨ててしまったとすれば、フロイトはこの「外部」を語ることすら出来ないが、しかし語ろうとしている限りこの「内部」に留まるしかない。フロイトのジレンマとは、現代において言語の外部を求めて格闘したラカンやデリダにおいて反復されているように、解決が極度に困難な課題であった。それは従ってある種の「運動」として永続される他はない。
フロイトの課題は、通常思われているのとは違い、きわめて政治的な次元を持ったものだ。たとえばそのことについて、ジジェクはヤコービを引き合いに出しながら的確に整理している(『主体に原因はあるのか』)。
フランクフルト学派と「フロイト-マルクス主義」を結び付ける人々は、ここで最初の驚きに出くわす。最初から、アドルノは「フロイト-マルクス主義」の試みの失敗と、その本質的理論の失敗を糾弾している。この失敗に終わった試みとは、史的唯物論と精神分析に共通の言語を提供しようとする、つまり客観的な社会関係と個人の具体的な苦しみとの間を橋渡しする試みであった。この失敗は何らかの「より大きな総合」を通じて、精神分析と史的唯物論両方の「不完全な」性質を「克服する」という内在的な理論的手続きによって、「失われる」ことはない。というのも、この失敗は「個別と普遍との現実の争い」、個人の自己経験と客観的社会的全体性との争いを記録しているからである。
修正主義の理論的「退行」は、理論と治療の間にある関係の中に最も明白に現れる。理論を治療のために用いることで、修正主義はその弁証法的緊張を失ってしまう。すなわち、疎外化された社会では、治療は結局失敗するようになっており、この失敗の理由は、理論自体がもたらしているのだ。治療の「成功」とは患者を「正常化」すること、つまり患者が現存する社会の「正常な」機能に適応できることである。これに対して、精神分析理論の決定的成功とは、まさに現存する社会秩序の構造そのものから「心の病」がどのように発生しているのかを説明することである。つまり個人の「狂気」は、文明それ自体に固有の「不満」に基づいている。理論が治療に従属することは、このような精神分析の批判的次元を失うことになる。
個人の治療としての精神分析は、必ず社会の不自由の領域内部に関わることになり、一方理論としての精神分析は、この同じ領域を越えたり、批判したりすることができる。その最初からして、治療としての精神分析は、文明批判としての精神分析を個人の調整と断念の道具へと変えることで、矛先を鈍らせることになる。[中略]精神分析とは治療としての精神分析を必要とする不自由な社会の理論である。(Jacoby,“Social amnesia”)
こうして、我々は、精神分析を「不可能な職業」とするフロイトの命題にある、社会批判に相当するものを手に入れるのだ。治療は治療など全く必要としない社会、つまり「精神的疎外感」を生み出さない社会でのみ上手くいくのである。あるいは、フロイトを引用するなら、「精神分析は、その実践が必要とされないような、つまり健康な人々の間であるといった、好ましい最適条件に応ずるものである」。ここに「失敗した遭遇」の特殊なタイプがある。つまり精神分析理論は、その治療が不可能なところで必要であり、不必要なところでのみ可能であるのだ。
ここで問題になっているのは、「転移」という次元である。精神分析はこの「転移」に関わる理論であり、それゆえに批判的次元を持つことが出来る。通常、精神分析の治療的成功は、患者を社会に適応可能にすることであると思われているが、それは精神分析の決定的成功ではない。何故かというと、そもそも精神疾患は現在の高度に疎外された社会から構造的に産出されるものであるから、そうした社会に適応したとしても患者は決して苦痛から解放されないし、患者の置かれる社会構造が変わらない以上再び同じ症状を誘起されることになってしまう。したがって精神分析は、この社会批判の次元にどうしても踏み込まざるを得ない。精神分析における治療と理論の対立とは、結局のところ「個人の自己経験と客観的社会的全体性との争い」の反復に過ぎない。「客観的な社会関係と個人の具体的な苦しみ」との間には、如何なる掛け橋も可能ではないのだ。したがって、個人と社会との間には、永続的な葛藤が存在することになる。
個人の病理と社会の病理とはリンクする。「転移」の次元を問題にするとは、この事実を痛感することにほかならない。個人から社会を説明することも、社会から個人を説明することも、共に拒否されなければならない。だが、別の「より大きな総合」を持ち出すことも出来ない。ジジェクは引用の前の部分で、アドルノを引き合いに出しつつ、自我について、また文化について整理している。そこで問題になっているのは、やはり解消不能な矛盾である。「一方では文明の発展すべてが、支配と搾取という社会的関係のために、欲動の潜在的な力を抑圧していると、少なくとも暗黙のうちに非難されている。他方、欲動の充足を否認する抑圧は、『より高次の』人間活動、すなわち文化の登場のためには、不可欠で打破できない条件であると認識されている。この矛盾からフロイトの理論内に生ずる結果の一つは、理論的に適切な方法で欲動の抑圧と昇華を区別することは出来ないということである。[……]このような理論的失敗は、あらゆる昇華(直接的な欲動の充足を目指さないあらゆる心的活動)が、必ず病理学的な徴候、あるいは少なくとも病原となる抑圧という徴候に襲われてしまう社会的現実のために起こる」。また、自我は二つの作用、つまり意識と抑圧を持ち、その二つは分かちがたく絡み合っていると述べたあとで、「その結果、あらゆる抑圧の障壁を取り壊そうという欲求に促された初期精神分析の『カタルシス』の方法は、必然的に自我そのものを分解することになる。[……]一方、『自我を強化する』といういかなる要求も、一層強い抑圧を必然的に伴ってしまうことになる」。「精神分析の目標と、その矛盾をはらんだ性質は、根元的な社会的対立、つまり個人の欲求と社会の要求の間の緊張関係を再生産してしまう」とジジェクはまとめる。社会的矛盾は、そもそも精神分析理論の中にも入りこむが、そもそもそのことが精神分析の批評性を支えている。「あらゆる『昇華』には、拭い去ることが出来ないほど『野蛮な』暴力的抑圧の面が隠されている」のだ。
自我における葛藤も、文化の暴力的側面も、個人と社会との間に起こる矛盾と同型の構造を持つ。社会構造は、自身の構造的矛盾を転移させることで、そうした諸問題を生成しつづける。我々はここに来て、精神分析における批判的次元を受け取るのだ。
以上の議論を援用しつつ、クーパーのテクストに戻ろう。
テクストの中では、クーパーは精神分裂病を「家族の病」であるとして説明している箇所もある。クーパーは精神分裂病を、人間関係それ自体から説明しようとしている。「‘精神分裂病’を疾患単位として理解するのではなく、それは人間同士の相互作用のパターンのある一定の組み合わせであって、その組み合わせが多かれ少なかれ特異なものであると理解することが必要なのであった。いわば、精神分裂病は一人の個人の内に起こってくる何かなのではなくて、人間同士の間に起こってくる何かなのだと理解することである」(p.114)と述べているが、この箇所以外にも彼はことあるごとに精神分裂病を関係論の立場から説明しようとしてきた。それは、精神分裂病を患者という実体として捉えることに反対する。特に、「スイスの有名な精神科医であるE.Bleulerは、かつてこう言った。入院している精神分裂病患者一人に対し、共同社会の中には十人の精神分裂病患者がいる、と。しかし、このように統計を見ていくならば、既にその時から精神分裂病に偏見を抱くことになるのである。つまり、精神分裂病というものを、ある人が‘もっている’ある種の実体と見なしてしまうことになる」(p.3)という箇所や、「問題は、いわゆる‘病者’の中にあるのではなく、個人個人が相互に作用し合うネットワークに、とりわけ家族の中にあるといえる。[……]いわば、狂気は個人の‘内に’あるのではなく、‘患者’というラベルを張られた個人が関与している一つの関係システムのうちにあるのだといえる。[……]精神分裂病者などというものは存在しないのである」(p.50)という箇所は、彼が示そうとしている理論化のいわば根底を我々に覗かせてくれる。だが、ここで言われる「人間同士の相互作用のパターンのある一定の組み合わせ」が、時としてそう読まれるように「家族」に限定されるものであるとするなら、彼が言っていることは大した問題提起にはならないだろう。それはスティグマの対象を、今までの「患者という実体」から、「家族という実体」へとシフトさせたに過ぎない。つまり、構図としては、この社会それ自体が問われないという意味では、同じことになる。
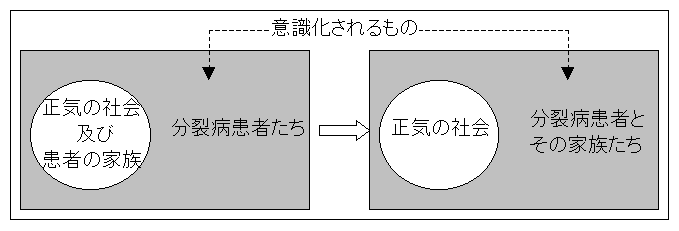
しかし、果たしてクーパーは、このようなことを言いたかったのだろうか。すなわち、彼は新たな分割を、新たな「排除」の構造を作ろうとしていただけだったのだろうか。確かに、テクストを忠実に読む限り、そのようにしか読めない箇所も少なからずある。そのことは一方で確認しておく。たとえば我々は、テクストのそこかしこに明らかなロマンティーク的身振りを見つけることが出来る。オリエンタリズムとでも称した方がいいかもしれない、非西欧、非近代への頻繁な言及がまずその一つである。具体的な記述箇所を挙げよう。「人が禅で言うところの‘疑念’というものを体験する」(p.1)。子供の領域が成立する以前のヨーロッパへの言及(p.51-53)。第二章のエピグラフでの『老子』・『論語』の引用(p.59)。紀元前エジプトにあったとされる治療共同社会テラポイテへのポジティフな言及(P.112)。「すなわち現代では、道教の教えである無為の新の意味が失われていると言えよう」(p.114)。北欧神話に出てくるイッグドシラルや、シャーマニズムへの言及(p.120-121)。これらは、クーパーのテクストにおいて、ほとんど、あるいは全く議論の上で必要がないように思われるがゆえに、ますます奇妙な言及に思われるが、逆にここにおいて彼のロマンティーク性が現れていると見ることも出来る。あるいは精神分裂病へのロマンティーク的と呼ぶにふさわしい記述もまた、挙げておくべきであろう。クリティーク2において大枠は説明したが、それ以外にも、アルトーへの言及(p.56)では「狂気」の「真理」への近接性を主張しているし、「ここで思い出すのは、精神分裂病者とは我々の時代の締めつけられた詩人であるという考えである。我々が癒す者になろうとするならば、彼らの喉を締め付けていた手をそろそろはずす時期に来ていると言えるだろう」(p.163)という記述も同様である。そして、「おそらく我々は、この精神分裂病者の外見上の無意味さの根底に、なにか核心的な意味が存在していることに気が付くだろう。精神分裂病者、この狂人は何処からやってくるのだろうか。何処からやってきて、どうやって我々の中にたどり着いたのだろうか。この狂気の奥に正気が秘められているということはないのであろうか」という記述は、狂気を外部に置いて、かつそれをポジティフに評価し返すという典型的なロマンティークの二分法に寄り掛かった表現である。これらは、クーパーがロマンティークのパラダイムの中で考えたことを示しているといえる。
ほぼ同型の構造で、クーパーが家族研究に携わっていることは注目されて良い。これも具体的にテクスト上で確認可能だ。例えば、彼は第二章において、あたかも家族によって精神分裂病が成立しているかのような論述を展開しているし(「経験を積んだスタッフがしばしば考えていたことは、患者の家族の中にこそ何か異常なものとか、狂気とさえ呼べる何かがあるということであった」p.59――これは第一章p.37の、「患者の家族はそれ以外の家族とはかなり異なったものである」という過程と響きあう――、第一章でも語られた家族というネットワークによる分裂病成立のプロセスをベートソンやウィニーらの家族研究への言及によってより詳細に論証しようという試み)、第三章ではまるまる一章使ってエリックが如何にして家族によって(ラベリングという観点と、エリックの疾病性という観点との両方から)精神分裂病としての自我をもたされるようになったかを説明している。また、序章でも、「精神分裂病とは、微視社会的な危機状況である。この状況においては、ある個人の行為や体験は一定の可知的な文化的理由及び微視社会的理由(通常、家族的な理由)のために、他者によって無効化されてしまい、ついにはその個人は一定の方法で、まず‘精神的に病気’であるものとして選別され、確認される」(p.11)と述べられ(これはインテンドがかけられており、クーパー自身がこの本の中で重要と見ている仮説である)、精神分裂病を生じさせる根拠を(「通常」と断りがあるが)家族に帰しているのが理解できる。こうした説明は、第一章の、「精神分裂病者の‘疾病性’とか非論理性は、他者の論理自体の疾病性に端を発しているものである。したがって、家族が、非本来的な生活様式の中で家族自体を維持するために、病気を捏造しているということになる。[……]家族のうち一人が自律しようとする行動に対して、家族は耐えがたい不安を感じるが、実際にはその耐えがたい不安を起こさせるものすべてを、精神分裂病の症状と呼んでいる」(p.43)「家族の態度と社会的執行者との間に非常に陰険でかつ巧妙な共謀がしばしば成立している」(p.51)という記述によって最も明確に現れる。社会的無効化は、まず何よりも家族によって始められる。こうした論述が、レインらの家族研究を背景として成立している――クーパー自身そう認めている――ことは注目されるに値する。何よりレインこそは、患者の内面に焦点を当てるというアプローチをとることで、結果的にロマンティークを拒む方法を見つけ得なかった精神分析家であったからだ。
このように言うと、クーパーが提示したものは、結局別の分割に過ぎなかったという結論を受け入れざるを得ないように思われてくる。だが、もう少し待ってみよう。テクストの別の箇所を読むことで、この結論は微妙だがしかし確実な形でずらされていく。むしろ注目すべきはそちらである。例えば同じ第二章においても、ダブルバインドに関する説明で、クーパーはベートソンらを批判しつつ、次のように述べている。
人間を対象にしている論理学者は、自己の論理体系の中では、ダブルバインドを次のように考えるべきである。すなわち、ダブルバインドをかけている者(double-binder)は、相手からの反応を一方では望んだり要求したりするが、同時に他方では望んでもいないし要求してもいないという点において、その論理体系の対象は二重なのである。我々の例に見られたように、決定的な出来事を子供に想起させようとする両親の要求は、社会的に決定されている本当の要求であって、決して‘うそ’の要求ではないのである。しかし、この要求は、もう一方の社会的に決定されている要求――子供に向かって忘れさせようとする要求――とは相反したものである。実は、ダブルバインドをかけている者は、同時にダブルバインドさせられている者でもあるのだ。[……]両親が自分たちの立場を守るために、不適当な理性形式に依拠する限り、本当の非論理性とか論理自体の誤謬は両親の中にあるということになる。しかし、実は、一般の社会のほうでも両親と同じ誤りを犯しているのである。(p.74-75)
ここでクーパーは、患者の持つ非論理性を家族由来のものであると述べるだけでなく、そもそもその家族の持つ非論理性を社会由来のものであると述べているのだ。先ほどの図で言うなら、クーパーはここで、まさに正常性を構成している我々の社会自体を問題にしているのだと言うことが出来るだろう。そうであるなら、彼が言う、「生きていくための必要性」(p.2)からの「社会的無効化」「ラベリング」とは、患者の家族に限定される行為では全くなく、この社会に広範に行き渡っているものである、ということになるのではないか。まさにここにおいてこそ、この社会と精神医学との巧妙な連関を問う余地が現れるのではないか。
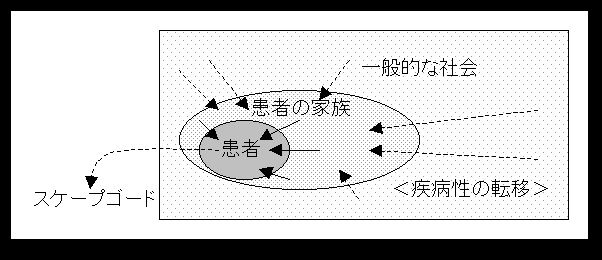
こうしたプロセスを、精神医学が支えている。病気というラベルを貼ることで、組織的に患者の自律性を奪い、社会的に無効化し、社会に遍在する疾病性を集約する形で「患者」として(社会的に見ればスケープゴードとして)社会の外部=精神医学の内部に放逐していくプロセス。「精神医学自体の暴力」としてクーパーが語っているのは、このプロセスに精神医学が根拠付けをしてしまっている事態そのものを指している。したがって彼は次のように述べるのだ。
現代の社会では、狂人というラベルを貼られた者に対して、狂気だけを隔離する小共同体が産み出され、かつ維持されてきたが、社会は今になって、それが罪であることにやっと気がつき始めている。つまり、社会は、一方では、精神障害者を普通の病人という地位に格上げしたり、精神科施設を大幅に許容したりして彼らの身分を改善していこうとし、他方では、患者としての同一化を与えて完全な患者に仕立て上げる擬似医学体系をフルに駆使したり、社会復帰過程における出発点の曖昧さという困難性を楯に取ったりしながら彼らを狂気の役割の中に閉じ込めようとしているが、このような矛盾に満ちた試みこそが罪なのである。(p.55-56)
クーパーは、つまり、狂人の隔離と維持を、精神医学の罪であると述べているのではない。そもそもそうした社会的行為の前提にある、患者を「患者」として仕立て上げ、狂気の役割に閉じ込めること自体を精神医学の罪であると言っているのだ。したがって彼にとって、患者を「患者」として見なしていく社会的過程に加担するあらゆること(例えばこの過程をスムーズにするために精神病院の待遇改善など)は、精神医学の暴力そのものなのだ。
精神医学の暴力の中で何よりキーとなるのは、したがって精神分裂病という区分を作ることそれ自体にあるというべきだ。病気として捉えることで、もしも病気でなかったならばこれこれこのような行動を取るはずである、という形で、一般社会に流布している人間に対するイメージ、更には社会構造自体を維持してしまうからだ。病人は、正常な状況ではないのだから、社会にとっては単純に外部であり、関わる必要のない者、耳を傾ける必要のないもの、たとえ耳を傾けるにしてもそれは対等な存在と考える必要のない者なのだ。
社会は決して自由な者によって構成されているのではない、と、クーパーはことあるごとに注意を呼びかける。彼は、社会というものをいわば一つのメカニズム、一つの機械として捉えているのだ。無自覚なままでは、決してこの巨大な排除機械を止めることは出来ない。彼はそれゆえ、自律、自由、責任、疎外などといった、実存主義的タームを頻用する。それは、彼自身のone性への希求もあったろうが、同時に彼がこの自由な個人に何がしかの希望を賭けていた証でもあるのだろう。彼が、何より自分の立場を「反精神医学」と名づけた理由の一端は、ここにあるように思われる。
彼がこの排除機械への抵抗を測ろうとした足取りを、もう少したどってみよう。それはこれまであまり触れてこなかった、第五章、第六章において示されている。ここで彼は、まさしく狂気/正気、外部/内部の境界を巡って議論している。
精神医学が、たとえ画一的ではあれ、非画一性というものを繰り返し創り出し得ているという注目すべき事実がなかったなら、画一性への要求は際限がないように思われる。
患者を、‘治す’という概念の中にこそ、基本的な困難性を見出し得るのだ、と私は思う。[……]
治すということは、他者が患者をより受け入れやすいようにすること、つまり、他者(医者や看護婦を含んだ)が患者に対してより不安を起こさずにすむようにするということであり、しかも、患者がより苦悩を表さないようにすることである。一方、癒すということは、様々な程度にバラバラになってしまった人々が再びまとまりを取り戻して行くのを援助することである。(p.160-161)
狂気を「治す」べきである、とは彼は言わない。また、そもそも狂気と正気の区別を彼は問題にする。更に、狂気が置かれているコンテクストをも。
看護婦、医者、作業療法士、患者の間にある役割が次第に不明瞭になってきた。[……]私は、一見混乱を招くような逆説的とも思えるいくつかの質問に焦点を絞ってみようと思う。例えば、患者は他の患者を‘治療すること’ができるだろうか。患者はスタッフを治療することまでもできるだろうか。病棟の共同社会の中で、スタッフは、自分たち自身が持っている無能力さや‘病気’や、それに対する‘治療’の必要性の程度を、きわめて素直に理解し認めることができるだろうか。[……]従来の精神医学的研究との訣別が最もラディカルな形で始まったのは、まさにこの時点であった。(p.137)
スタッフと患者をはっきり分けている境界が侵害されるようなユニット内すべての出来事に対して、彼らは極度に脅かされていると感じていたのである。[……]発展は、彼らが持っている自分自身についての概念、つまり患者は狂気で自分たちは正気だという考えを、根底から覆そうとするものであった。(p.146)
実際に、スタッフにとって困難なことは、自分自身に出会うこと、すなわち、自分が抱えている問題とか障害とか狂気といったものに出会うことなのである。[……]精神科医と看護婦(つまり、‘市民’に代わって実行する人間)の側にある暴力を患者へと外化することによって、従来の均衡が支えられてきた。[……]精神衛生機構全体と精神病院とが一体になって、陰険かつ複雑な共謀をしてきたという重大な社会問題が、この均衡の上に成立している。(p.153)
悪は投影によって成立しているというのは、彼が繰り返し述べてきたことでもある。ユダヤ人キャンプの例(p.144)もそうである。また、彼は「役割」についてはこう付け加えている。
精神医学に関する多くの実践は、たとえそれが如何に進歩的な装いを見せていようとも、所詮その目的は、権威を持つ人間が下す厳格で型にはまった命令に強制的に順応させることでしかないのである。[……]社会的な期待と目に見えない要請とを屈折させた形で患者に向かって集約させているのが権威者といわれる人々の実体なのである。[……]権威者の権威とは恣意的な社会的定義によって付与されているものだ。[……][このようなあり方からスタッフが身を移していこうとするときには]患者と規定されている他者の中にも、それと同じ根拠があることに気が付くのである。(p.143)
だが、こうした方向へは向かない。スタッフ自身がまず、制度のなかに絡め取られているからである。スタッフが患者に向かおうとするとき、常にそのまなざしにはスティグマが付きまとう。もしも反精神医学的実践というものに向かおうとするのなら、
患者に何が起こっているのかを理解する前に、我々は少なくとも、スタッフに何が起こっているのかについての基本的な自覚を持つ必要があるということである。[……]精神医学の歴史の中では、障害、分裂、暴力、汚辱を含むと考えられている狂気から身を守るために、精神医学的制度が必要とされてきた。したがって、スタッフの防衛が現実の危機に向かっているというよりも、むしろ想像上の危機に向かっているものであるならば、私はそれらをまとめて制度自体の不合理性と名づけたい。(p.131)
何よりも、反精神医学の実践とは、この現場において生起するものなのだ。無論、クーパーにおける現場とは、精神医療というシステムであり、社会の中における精神医学という機構それ自体である。何よりまずこの現場への分析化ら、自覚から始めなければならない。だが、そのことはきわめて危険である。それはクーパーにも判っていたはずだ。「[このユニットが]ある程度病院内の‘悪’が投影されていくスケープゴードになってしまう可能性があることをも、私は充分に自覚していた」(p.126)。
この時点でのクーパーには、ロマンティーク的議論はもはやない。それは次のように、彼自身の手で、はっきりと記されている。
我々がしてきたことは、‘文明の英雄としての精神分裂病者’といった、安っぽく賛美された地位に彼を祭り上げることではなかった。我々のしてきたことは、彼(‘狂者’)と我々(‘スタッフ’)――つまり、正気の社会の代表者である我々――との間にある隔たりを、少なくとも部分的であれ排除することであった。
だがこうした試みは、決して病院内部、医療内部において完結することはできない。なぜなら、こうした境界を設定してしまう疾病性は、そもそも社会に由来しているからだ。だからこそ彼は次のように述べるのだ。
我々が患者に対して援助してきたことは、退院後彼が独立した生活を営めるように、システム化しない形で適切な準備を整えてあげることだった。ところが、この準備はしばしば失敗に終わってしまった。[……]この間の事情は、我々の統制が直接的に及ばないというはっきりとした理由によるものであるように思われた。つまり、それは、本来、共同社会が組織化していくべき問題なのである。(p.150)
結果としては、制度を変革する際の限界が明らかになっていったということが挙げられる。[……]大きな精神病院施設というものは、家族世界の母体である共同社会の外へと物理的に押し出されてきたが、我々のユニットを更に発展させるためには、この施設の外、つまり共同社会へとその発展を広げていかなければならない。なぜなら、施設の外にこそ、真の問題が生じているのだし、その解答が用意されているからである。(p.154)
彼は第五章の最後を、「我々は、理想的な精神医学的共同社会、というよりもっと正確に言うならば反精神医学的共同社会を創出しようとして、多くのとてつもない夢を見ていたのかもしれない。[……]更に前進するためには、究極的に、精神病院を超えて共同社会へとステップを踏み出さねばならないのである」と結んでいる。彼の実践は、何より共同社会へと向かって進んでいくものだった。社会における転移に注目してしまえば、もはやそれ以外に答えがないことは明らかである。彼はフロイトと同じジレンマに突き動かされたのだ。
我々はここに来て、クーパーの記述が、どうしてあれほどまでにアンヴィヴァレントなものにならざるを得なかったか、理解できるだろう。例えば彼は第二章で、家族研究について、「可知的」というタームを頻用している。たとえば、
精神分裂病に対する従来の見解の中で最も不条理な、最も意味のないものと見なされていた‘症状’は、この種の家族調査と病党内集団での相互作用の観察を併用することによって、可知的なものになるのである。(p.31)
彼は分析的理性を嫌い、弁証法的理性の必要性を訴えた。このことは、我々の言葉で言いかえるなら、現場性を認めるかどうかで分けられる。例えば、彼はベートソンの研究を、分析的理性に過ぎないといって批判している。彼が問題にしたかったのは、ベートソンのように整合的なロジックを組むことではなく、人と人とのこの場での相互作用であった。まさしく精神分析的なこの主張は、クーパーの立場を根本的に規定している。彼は弁証法的理性に結び付けて「可知的」という言葉を使っている。これは、非歴史的に存在するのではない人間関係を、この現場という形で理解可能なものにできるのだという彼の主張に従ったターミノロジーだ。
私は彼が、家族研究という、新たな分割の作業に組しつつ、そこからずれている部分を読むべきだと述べた。それはしかし、彼が家族研究に関与していないということではない。彼はここで、二重の身振りを取っているのだ。彼の全体としてのロジックは、上で述べたようにやはり共同社会に向かったものであるだろう。だが、これは現在ですら同じことなのだが、単純にいきなり個人のレベルを超えた「社会」に議論をシフトしてしまうと、現場性が消えてしまい、読み手はそれを自分の問題として受けとめなくなってしまう。これは社会心理学の最大の盲点である。彼は、現場性を保ち得るぎりぎりのレベルとして、家族研究に目をつけたのだ、と私は思う。だが同時に、家族研究の失敗を、彼は充分に予感していた。家族研究は、結局新たな分割に過ぎず、家族自体をスケープゴードとしていくに違いない社会のメカニズムを彼が理解していなかったとは思われない。彼は家族研究に踏み入れつつ、そこから微妙にずれた立場を採ることで、かろうじて自身の主張を守った、といえるのではないだろうか。
実はこのことは家族研究だけではない。私はクリティーク2において、クーパーのターミノロジーに、精神医学が感染している様を丁寧に分析した。そのことを認めないのは彼の立場上の問題であるとも述べた。だが、我々はここに来て別の捉え方が可能であることに気付くだろう。彼のいた現場は、精神医療である。そこでの言葉は、精神医学の言葉でしかない。もし彼が精神医学の言葉を語らず、自分のタームのみを語ったとしたら、周りの人間は果たして聞こうとしただろうか。おそらく、単純に排除されて終わったに違いない。ここでもフロイト的ジレンマが生じる。あることを主張するためには、その現場の言葉を使わないことはできない。だが、まさにその現場を問題にしたいとすれば、単純にその言葉を使うこともまたできない。彼は従って、フロイトと同じ戦略に出る。その現場の言葉を使いつつ、そこでの意味を微妙にずらしていくという、ウイルスのような戦略に。
彼は自分の実践を、「反精神医学」だと述べた。注目してもらいたいのは、この実践は「反」「精神医学」である以上、精神医学という実体抜きに成立することはできないということなのだ。反精神医学は、精神医学に感染するウイルスのような形で存続するしかない。これは、精神分析に由来する反精神医学の、ほとんど宿命的な立場である。クレペリンによって形成された精神医学は、同年の生まれのフロイトが創始した精神分析に付きまとわれつづけてきた。その過程で、精神医学は確実に変化してきた。しかし精神分析は精神医学から正当性を認知されることはない。ここで私が精神分析というものは、治療的実践というよりは、ある種の運動を指している。従って、狭義の精神分析家たちの活動だけを指すのではない。精神医学に抵抗を図ろうとした者達、例えばサリヴァンやロジャーズのことを私は言いたいのだが、彼らが最終的に精神医学への抵抗を社会的政治的な次元で行わなければならなかったのはどうしてなのか、クーパーはその答えを暗に示しているのだ。
反精神医学とは、従って永続する闘争として存在するしかない。それは、名を変え、形を変え、精神医学が存在する限りとりついて離れないものだ。それは発作的に再来する。「多すぎる光は心を暗くする」。莫大な、洪水のような「常識」という情報の流れの中で、我々が時に感じる自明性の消失。クーパーの実践は、精神医学に生起した理性の発作なのだ。