1.戦場の偶然は歴史上の必然
東西ローマ帝国の関係は極めて微妙なものであり、前年、東ローマ帝国ヴァレンス帝がゴート民族との戦乱で没した時も援軍を用意していた西ローマ帝国グラティアヌス帝は軍を退けてしまっていた。だがヴァレンス帝に代わる皇帝にテオドシウスを推薦し力を貸したのは西ローマ帝国で教会組織を抑えているアンブロシウスなのである。錯綜する歴史こそが混乱の母体となる、そんな時代であった。
「前方未確認艦艇群確認、かなりの規模…2万隻に達します」
黒曜石の盆に満たされている透き通った水面のような宇宙空間を、銀白色に輝く幾何的な外見をした数万の金属の塊が規則正しく配列されている。戦艦ロンデニウムの艦橋で、ガイウス・ヘクトール・アウレリウス准将は覇気にあふれた顔に困惑とも笑みともつかない表情を浮かべていた。遥か過去、帝国に叛意を翻した将軍ヘクトールの末裔であることを公言してはばからない男である。
その当時辺境星系に進発し、騒乱を鎮めるための遠征軍を用意するために東西ローマ帝国の双方では軍備の増強に余念がなかった。彼らが大規模な演習と訓練のために艦隊を率いて東西ローマ国境周辺にまで出向いていた、まさかその時期と場所までもがこれほど重なることがあろうとは双方とも思ってもいなかったのである。演習の目的はあくまでも辺境ゴート民族の鎮定軍の用意であり、或いは最近不穏な気配を見せているというブリタニア星系への遠征用意のためであったろう。それを予め知らせるだけの理由は彼らにはなかったし、出会って仲良く笑顔で挨拶をかわして別れる理由もやはりなかった。
「停船せよ、しからざれば攻撃する」
これが宇宙の軍船乗りの挨拶である、と言ったのは誰であったろうか。ヘクトールと伴に演習に派遣されていたピナル・アルトゥアは神経質な外見の痩せた老人であるが、同僚以上に好戦的でヒステリックなまでの性格をしていた。偶然というのであれば、この時にこの場所で、部隊を率いていたのが彼らであったこともまた偶然であったのだろうか。警告信号を出すと同時に近隣宙域で別の演習に参与している友軍に通信を送り、彼らは艦艇を第一種戦闘体勢へと移行する。
一方の西ローマ艦隊も艦艇数ではほぼ同数であり、やはり近隣宙域にある味方を呼び寄せようと複数の通信波が複数のプロテクトをかけられた状態で送られていた。総指揮官と部隊長との間でも積極的な通信がかわされている。
「今この時期に大規模な戦闘は避けたがよろしいのでは?適当にあしらってお茶を濁すのがいいと思いますがね」
「貴官に意見を聞いた覚えはないぞ、ザリエル准将」
「小官も意見を求められた覚えはありません。総司令艦閣下」
通信スクリーンを通じて、カルレット・ザリエルは戦艦エウリュティオンの艦橋で人を食った笑みを浮かべる。通常であればこのような不遜な発言が認められることは決してなかったであろうが、事態が緊急である上に司令官が演習の査閲のために派遣されていた軍政官であったとすれば、こと非常事態に到り実戦経験の豊富な第一線の指揮官たちが上官を侮るのも無理からぬことではあったろう。
カルレット・ザリエルは一介の兵士からのたたき上げの将官であり、兵士からの信望も厚いまず一等の人物であった。この時期、荒廃したローマ帝国において出自を問わず実力のある者は前線にて勲功を立て、反対に覇気も能力も失っていた者は不平を言いたてながら自分たちの既得権益を守ることにのみ熱中する、そんな存在でしかない。後の立身への足がかりとして軍歴だけを求める者にとって、査閲官という任務は危険が少なく実入りが大きい、きわめて魅力的な任務である筈なのだ。
「それもつい先程までは、だがな」
流石に通信回路を切断してから、カルレットはそう呟く。常は戦場に遠くあり、戦場経験を持たぬ者こそが概して好戦的になりうるという事実を彼は長い軍歴の中で経験として知っていた。相手の行動線を見るに会戦を望むつもりに疑いなく、総司令官閣下も目の前の敵を見て戦わない、という発想など思いもよらない「愛国者」である。どうやら戦闘は避けられないであろう。
戦場における偶然とは歴史における必然でもある、と称したのは後代の戦史家であった。
だが彼らは所詮、その当事者であったに過ぎない。
† † †
カルレット艦隊は後方遊撃の位置に待機、左右両翼から味方が到着し次第包囲戦を図るという方針を決して、西ローマ艦隊もまた第一種戦闘体勢へと移行する。双方が味方の来援を待つ体勢となる以上は、互いに相手の実力のさぐりあいから始めるのが定石であろう。
「正面より敵ミサイル群接近…3時方向に囮を射出、回避可能です」
「こちらも砲撃、相手の反応を見るぞ。深追いはするな」
戦闘自体は静かだが力強い攻防で開始された。西ローマ艦隊から発射された数百のミサイル群はヘクトール艦隊の射出した偽装艦隊に誘われて軌道を変えると、衝突とともにレーザー核融合爆発の輝きに包まれる。西ローマ軍の牽制の砲火もまたエネルギー中和磁場にさえぎられて派手な光彩を散らすだけのことしかできなかった。初手の挨拶を終えると西ローマ艦隊は熟練した艦隊運動を見せて手早く左右に展開、砲撃を一点に集中してヘクトール艦隊の前面部、指揮系統に負荷をかける戦法に移管する。各所に開いた小さな穴を切り拓くかのように的確な砲撃がヘクトール艦隊に出血を強いていった。
友軍の戦況を見やりながらピナル・アルトゥアも戦場の中心に向かって突入を開始する。自ら乗る戦艦ヴァスパシアンを最先頭に、傍若無人の勢いで急進する様はかつてローマ大戦で剛勇を振るったという彼の祖先を思い起こさせるものだった。これを迎え撃ったのはカルレット・ザリエルの部隊である。戦場の後方から敵軍の動向を見ていた彼は指揮下の部隊を巧みに移動させると、急進するピナルの部隊を左側面から急襲する体勢を成立させる。
「捕らえたな…全艦砲撃、ただし艦列を崩さず、遠距離砲撃に専念せよ」
カルレットの目的は味方本隊と同様に遠距離の砲戦で損害を避けつつ、敵の指揮系統に負荷を与えることにあった。体勢としては挟撃、無理な混戦に持ち込まれることさえなければ長期に渡って戦況を優位に保ちつつ友軍の到着を待つことができるであろう。そしてその時期は当初の予想以上に早く訪れることとなった。
「ガリアヌス隊、クレンダス隊到着しました!」
その報告がもたらされたとき、ほぼ同時に東ローマ艦隊にも増援到着の報が届いていた。
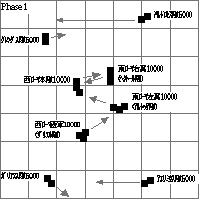 西ローマ帝国艦隊の増援として、まず戦場に到達したのはゼフェル・クレンダス准将である。未だ20代の青年将校は戦艦ケーニギン・ティガーを中心に部隊を横に展開させると、だが積極的な前進は控えるように指示を行う。
西ローマ帝国艦隊の増援として、まず戦場に到達したのはゼフェル・クレンダス准将である。未だ20代の青年将校は戦艦ケーニギン・ティガーを中心に部隊を横に展開させると、だが積極的な前進は控えるように指示を行う。
「敵の動きを見てから、対応する…全軍砲撃体勢のまま距離を保て」
消極的な行動に不満を覚えるものもいたであろうが、ゼフェルとしては左翼から正面前進で敵を押し返し、敵本隊に対して左側面から攻勢をかけたいところであったのだろう。同僚には「気の弱い青年」として知られるゼフェルだが、帝国士官学校戦略研究科を優れた成績で卒業した俊英でもある。そしてゼフェルと同様に西ローマ艦隊の、こちらは右翼側に到着したヨハンナ・ガリアヌスもやはり士官学校の俊才にして建国の良将たるテオドラ・ガリアヌスの直系の家の生まれであった。敵と味方の戦力は同等、より効果的に戦果を狙うのであれば半包囲体勢の確立であろうと判断したのも同様である。
「敵左側面に迂回し、急襲を図るぞ。急げ!」
旗艦アキピテルに従い戦場の外縁を進軍するヨハンナ艦隊。だがその意図は東ローマ帝国コルネリウス・アエミリウス准将によって完全に察知されていた。
「敵は戦場を迂回して味方の左側背に回り込むつもりである。こちらは敵に2時間先行して急襲、そこに戦場を確保できれば逆に戦闘中の敵本隊を囲うことが可能だ」
没落貴族の出自である若い軍人としては、可能な限り積極的に自らの手で戦況に寄与し功績を得たいところでもあったろう。兵は神速を尊ぶ、コルネリウスは迅速な行動によって迂回を図ろうとしたヨハンナ艦隊の機先を制することに成功した。
「撃て!」
戦艦カンパーニアの艦橋で振り下ろされる右腕と伴に複数の光条と砲弾とが発射され、ヨハンナの部隊に先制の打撃を加えた。混乱したところに続けて砲撃、積極的な前進、攻勢によってほぼ一方的に損害を与え続ける。ヨハンナとしては出血が致命的なものとなる前に迂回策を断念し、後手にまわった不利を承知で部隊を再編、相手の正面に向き直るしかなかった。
一方、戦闘の開始されたゼフェル隊も悪戦のさなかにある。東ローマ将校ダリア=ハルトロセスは相手の包囲策に乗らずに戦場外縁部を急進、ゼフェル隊の更に左側面から強襲を図ろうかという構えである。ゼフェルは高速で移動するダリア隊に対応し、独自の戦場を設定することで危険を回避する方策をとらざるを得なかった。
「迎撃用意…撃て!」
「前進、急襲、展開。こちらのペースで構わないわ」
戦艦ハイラントにあるダリアは横列に構える敵陣に戦力を集中して急襲、損害を嫌ったゼフェルが部隊を密集させるタイミングに合わせて今度は自軍を散開させると敵部隊にまとわりつくように展開、砲撃を続けて敵を損耗させることに専念する。機会が得られるまではあくまで慎重策、というのはゼフェルの信条でもあるが敵の巧みな攻勢によって損害は無視できないものとなりつつある。全体として戦況は依然東ローマ優位、西ローマは中央本隊が敵の攻勢を抑えてこそいるものの、着実に敵の包囲策にはまりこみつつある。
「部隊を散開、敵攻勢の限界を誘い反撃に出るぞ」
言いながら、カルレット・ザリエルは違和感をぬぐいきれないでいた。味方の犠牲を抑え敵の指揮系統に負荷を与えつつ消耗を強いる、そのための体勢も充分に確保したというのに、敵に後退あるいは逡巡するむきが見えないのである。ピナル・アルトゥアは老齢の人物とは思えないほどの獰猛な剽悍さと、あわせて老齢の人物らしい頑迷さとをもって不利な戦況にあってなお前進、突撃、攻勢をやめようとはしない。オペレータからの急報がもたらされる。
「前衛部隊の連携が崩れました!敵、突入してきます!」
「…やれやれ、まいったねぇ」
あごをさすりながらカルレットは呟く。新造部隊である味方が敵の圧力に耐えきれなかった、指揮系統に負荷を与えられていたのはこちらであったようだ。だが予想外の展開にカルレットが一瞬、自失していたとしてもまさしく一瞬のことで、味方を集結させて指揮の分散による不利を防ぐと中央を厚く編成し、敵の先頭部一点に集中して反撃の砲火を放つ。
「目標は敵先頭の突端部ではなくその後ろ、敵先頭部と後続との結節点だ」
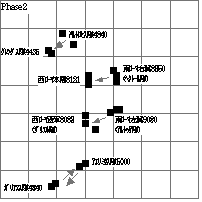 次の瞬間、それまで優勢にあったピナルは劣勢に転じていた。的確で強力な砲撃はピナル隊を前後に二分しようとするかのようであり、先頭部は前進すれば層が薄くなるし後続部は前進すれば集中する砲火に自ら飛び込むこととなる。だが、それでもまだピナルは前進をやめようとはしない。
次の瞬間、それまで優勢にあったピナルは劣勢に転じていた。的確で強力な砲撃はピナル隊を前後に二分しようとするかのようであり、先頭部は前進すれば層が薄くなるし後続部は前進すれば集中する砲火に自ら飛び込むこととなる。だが、それでもまだピナルは前進をやめようとはしない。
その間も戦闘は更に苛烈さを増している。ガイウス・ヘクトール・アウレリウスは柔軟な艦隊運動で部隊を展開、前進、編成、移動を巧みに使いこなし、都度変化する戦況に適宜に対応して常に戦闘を主導しつづけていた。対する西ローマ艦隊は後手にまわりつづけ、当初こそ優勢にあったものの戦場の全面で確実に劣勢に転じつつある。
「次は左だ、凹形陣の中央に敵突出部隊を誘い込むぞ」
「旗艦、前進しすぎています!後退の許可を!」
「いちいちそんな事は…!?」
西ローマ艦隊の総旗艦が突出、瞬間、ヘクトール隊の集中砲火にさらされる。前面の護衛艦隊が一撃で吹き飛ばされ旗艦も被弾、総司令官と首脳部は重傷を負って後退することとなった。ここに至り、戦況はほぼ決したと言って良いであろう。
>2.アドリア会戦を見る
>地中海英雄伝説の最初に戻る

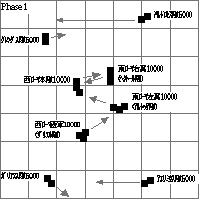 西ローマ帝国艦隊の増援として、まず戦場に到達したのはゼフェル・クレンダス准将である。未だ20代の青年将校は戦艦ケーニギン・ティガーを中心に部隊を横に展開させると、だが積極的な前進は控えるように指示を行う。
西ローマ帝国艦隊の増援として、まず戦場に到達したのはゼフェル・クレンダス准将である。未だ20代の青年将校は戦艦ケーニギン・ティガーを中心に部隊を横に展開させると、だが積極的な前進は控えるように指示を行う。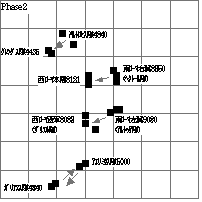 次の瞬間、それまで優勢にあったピナルは劣勢に転じていた。的確で強力な砲撃はピナル隊を前後に二分しようとするかのようであり、先頭部は前進すれば層が薄くなるし後続部は前進すれば集中する砲火に自ら飛び込むこととなる。だが、それでもまだピナルは前進をやめようとはしない。
次の瞬間、それまで優勢にあったピナルは劣勢に転じていた。的確で強力な砲撃はピナル隊を前後に二分しようとするかのようであり、先頭部は前進すれば層が薄くなるし後続部は前進すれば集中する砲火に自ら飛び込むこととなる。だが、それでもまだピナルは前進をやめようとはしない。