3.ブリタニア動乱
銀河ローマ帝国を東西ローマに分割した、皇帝ディオクレチアヌスの没後50年程が経っていた。東ローマ帝国は惑星ニコメディアにある将軍テオドシウスが、西ローマ帝国では首都であるミラノ星に若いグラティアヌス帝が司教アンブロシウスに支えられて人民を統治している。それはアウグストゥスが立ち上げた銀河ローマ帝国がもはやただ一つの力では支えることができなくなっていた、その証明であったのだがこの期に及んでもなお彼らは互いに反目しあっていたのである。しかも、東西に分かれ内憂を抱えるローマ帝国には強力な外患が存在していたというのに。
† † †
辺境星区であるブリタニアでの騒乱は、当地を治める総督マグヌス・マクシムスが軍備増強を始めたことに端を発する。マクシムスの主張は簡潔であり、若輩のグラティアヌスに無用な負担をかけまいと防衛のための常備軍を整備していると言うものであった。聞く者がその言葉を信じないであろうことを承知の上で、ブリタニア総督マグヌス・マクシムスは強気の姿勢に出たのである。これを受けた皇帝派は憤慨、皇帝グラティアヌス自身の出馬により不逞な「辺境の王」に訓戒を与えることを決意する。
「それで皇帝自ら威を示すべし。とはどうにも単純だな」
「相手の意図は明らか。ならば増長してのさばらせる前に陛下自ら威をお示しになることで、他の小マクシムス共をも黙らせるおつもりでしょう」
指揮官の個室に据え付けられていた、通信用の小さなスクリーンを通じてカルレット・ザリエルとヨハンナ・ガリアヌスの二人の准将が言葉を交わしていた。ブリタニア総督マグヌス・マクシムスへの対応は誤れば確かにローマ辺境に叛乱を誘発することになりかねない、故に皇帝グラティアヌス自らが親征に立つことで他属州をも牽制する。もともと属州総督には独立した軍団の編成権と指揮権が与えられており、軍事力が混乱期における重要な力であることは疑いようもない事実である。若年の皇帝が侮られぬためにはその実力を目に見える形で誇示しておく必要があった。
それでも皇帝自ら戦場に赴く親征となれば前線での危難と、本国の安定との双方に不安をもたらす大事である。皇帝とその側近はブリタニアにまでは進まず、その中途にあるガリア星系の惑星リヨンに留まることで前線と後方の双方を監督するつもりであったがそれで不安なしとする訳にもいかなかったろう。
「こちらに思惑があるなら敵さんにも目論見があるだろう。ブリタニアは遠い、いっそ辺境の王でも何でもならせてやればいいのさ。どうせ駄目になれば自滅するだけなんだからな」
「貴官は…」
不遜で人を食った、この男をヨハンナはあまり好いてはいなかった。不逞なブリタニア総督に懲罰を与えるための親征、その下で彼女は一軍を駆る指揮官であり、彼女たちの後ろには若い皇帝自らが控えているのである。軍人としては前線の任務を全うし、同時に主君たる皇帝陛下の威を示すこと。それ意外の余計なことを考えすぎるカルレットは、ヨハンナにすれば任務に対する誠実さに欠けているとしか思えない。
一方カルレットにしてみれば軍人は自分の与えられた任務のみを果たしていれば良い、余計な考えとは越権行為であり軍において最も重要な規律を乱す思考である、とは考えてはいなかった。彼は自分の存在している歴史がどのように流れているかに常に興味があったし、この混沌とした時勢に彼自身と部下達の身を案じるのであれば歴史の潮流の流れる先を無視することはできなかったのである。
だがいずれにせよ彼らは全軍を従える総司令官ではなく、単なる部隊指揮官でしかなかった。戦うにせよ退くにせよ、それを決めるのは彼ら以外の人間の役割だ。いざ戦場に出れば彼らは目の前の戦況にのみ従って戦わねばならず、それまでに彼らの手の届く範囲内でできる限りのことは解決しておく必要があったろう。
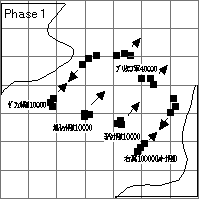 辺境ブリタニア星系は、かつて「国家の父」神君ガイウス・ユリウス・カエサルが制圧してより帝国ローマの属州として長く治められてきた星域である。西ローマ帝国主星ミラノからはガリア星系より更に遠く、航宙の難所を越える必要があることからも星系を統治する総督は現地の有力者によって行われていることが常であった。属州に与えられるものはローマの法を遵守する義務と属州税を治める義務、そしてローマによる星系自治の保証と宙域の安全、統一された通貨等である。帝国とは複数の政体を選ばれた少数の者が指導する体制であり、人民主導の上に公益の代弁者を置くこともできるシステムであったが、同時に公益の保証と平等性に対する不安が容易に不満に転化しやすい欠点も持っていた。この制度下では人民主導の自治国家が帝国の保護を受けるというパラドックスですら成立させうる一方で、帝国に従う利益が保証されなければあえて帝国に従う理由もなくなるのだ。
辺境ブリタニア星系は、かつて「国家の父」神君ガイウス・ユリウス・カエサルが制圧してより帝国ローマの属州として長く治められてきた星域である。西ローマ帝国主星ミラノからはガリア星系より更に遠く、航宙の難所を越える必要があることからも星系を統治する総督は現地の有力者によって行われていることが常であった。属州に与えられるものはローマの法を遵守する義務と属州税を治める義務、そしてローマによる星系自治の保証と宙域の安全、統一された通貨等である。帝国とは複数の政体を選ばれた少数の者が指導する体制であり、人民主導の上に公益の代弁者を置くこともできるシステムであったが、同時に公益の保証と平等性に対する不安が容易に不満に転化しやすい欠点も持っていた。この制度下では人民主導の自治国家が帝国の保護を受けるというパラドックスですら成立させうる一方で、帝国に従う利益が保証されなければあえて帝国に従う理由もなくなるのだ。
ブリタニア総督マグヌス・マクシムスは皇帝グラティアヌスの出陣を受けて直属艦隊を編成、難所の多いブリタニア周辺宙域に大軍を押し出してきているという。横に広く陣を布いている相手の意図が、こちらを誘い込む目的にあることは明白である。属州艦隊が皇帝の軍に弓を引く、その行為を彼らが幾らでもごまかすことができるつもりでいるだろうことが、今のローマ帝国の実状を示していた。
「舐められているわね、気分の悪い」
「中央は突破、左右は抑える。敵さんが侮ってくれているなら幸いじゃないかね」
「相手の意図に乗るつもり?地形を利して包囲されると厄介ではなくて?」
「奥に引っ込まれるほうがもっと厄介さ。即戦で打撃を与えて早々に退く、こんな田舎にいつまでも留まっていたら方言がうつってしまう」
急襲により一撃して離脱、深追いはしない。その考え方はヨハンナも理解できるが、カルレットの言葉を聞くにどこまでが本気でどこからが冗談なのかは判別しがたい。西ローマ軍は中央前衛をヨハンナが、後方をカルレットが束ねており別に両翼が配置されている。その両翼部隊が先行して敵の両翼と接触し、これを抑えたところで中央が急進。重厚な布陣を活かした時差前進戦法である。
危険宙域を背に布陣するブリタニア軍に対して、西ローマ艦隊は堂々たる布陣で前進する。不安があるとすれば総司令官たる皇帝グラティアヌスが自身、戦場になく未だ後方のリヨン周辺に留まっているということであろう。自然、前線指揮は各分艦隊の指揮官に委ねられるしかない。
「といっても相手は貧弱だ、誘い込んで小細工を弄するしかない…決して陣形を乱さず、ひたすら前進。それさえできれば間違いなく勝てる」
左翼司令官であるゼフェル・クレンダス准将が戦艦ケーニギン・ティガーの艦橋でうそぶく。問題は西ローマ軍の質そのものが、決して陣形を乱さないという最も基本で重要なことができるかどうかということであった。ゼフェル自身も自覚していることだが、混迷の状勢の中でローマの国力が落ちていれば兵士の質も下がるのが常だからだ。
「彼我の距離70…敵、砲撃開始しております。まだ射程には達しておりません」
「幸いだな…相手は素人だ、こちらは55まで引き付けろよ」
戦力をぎりぎりまで溜めて一気に解放する、ことは前線における常道である。左翼艦隊が突入を開始、一斉砲撃を行うとブリタニア軍は支えきれずにすぐに戦線を混乱させる。戦場経験の少ない叛乱軍は守勢に弱く、ローマ艦隊の攻勢を支えることができないままに後退を開始していた。
一方で西ローマ軍右翼艦隊は早くも苦境の中にあった。航宙の難所に誘い込んでの迎撃を図る敵に先んじて急襲、そこまでは良かったが勝勢を駆らず艦を展開させている間に敵に建て直す時間を与えてしまい、逆に反撃を受けることになっていたのである。艦列を乱している間に先手先手を取られてしまい、その損害は無視できないものとなっていた。実に艦艇の5割が被弾、損害を受けるに至って攻勢を諦め、後退することになるが後退する味方を先導したのは先のアドリア会戦で奮闘したレオーナ・シロマーサ大佐である。
「こういう仕事ばかり回されてもねぇ…」
前線で援護する司令官に代わり後退指揮、責任感を讃えても良いのかもしれないが、弱敵相手に苦境を招いた自業自得、と思わなくもない。幾つもの不本意の種を抱えながら『海賊女神』は撤退行を率いている。
だが右翼戦線でこそ苦闘を強いられていたものの、全体としては西ローマ軍が優勢を確立しつつあった。カルレットの当初の思惑どおり両翼が充分に相手を釘付けにすることによって敵はこちらを誘い込むことができず、形としては長い一列横隊同士が正面から激突するだけの戦闘となっていた。そしてこのような激突であれば勝敗を決するのは軍隊としての規律である。頽廃の進むローマ、と言われようが未だに彼ら中級指揮官に支えられた軍の品質は優れたものであったのだ。
「艦列を乱すなよ。密集して連携を崩さず味方艦の隙間から長距離砲で砲撃、敵が崩れるのを待つ」
「ケントゥリア発進、制宙権の確保に専念して」
カルレットもヨハンナも相手の弱点を存分に利用するつもりでいた。持続性がなく守勢に弱い、頑健な相手の砲火にさらされつづけ、しかも隙を見せない西ローマ艦隊を相手にブリタニア軍は徐々に艦列を乱し始める。そして隊列に不均衡ができればそこに負荷が集中し、引き続く戦闘の中で自壊を始める。戦場において規律とはまず戦闘から脱落せぬために必要な能力なのだ。
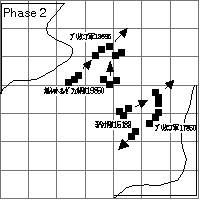 戦況の自然な推移にともなって、左翼側ゼフェルとカルレットの艦隊は前進して敵を押しまくる形となり、ヨハンナは後退する右翼と連携して追撃する敵の右側面を狙い急襲をかける。右翼の損害によって総数ではブリタニア軍に劣ってすらいたのだが、危険宙域を利用して敵を包囲陣形に誘い込むことに成功していた。
戦況の自然な推移にともなって、左翼側ゼフェルとカルレットの艦隊は前進して敵を押しまくる形となり、ヨハンナは後退する右翼と連携して追撃する敵の右側面を狙い急襲をかける。右翼の損害によって総数ではブリタニア軍に劣ってすらいたのだが、危険宙域を利用して敵を包囲陣形に誘い込むことに成功していた。
「砲撃を一点に集中、敵側面を更に分断する…撃てっ!」
号令一下、砲火がブリタニア軍側面の中央部一箇所にたたきつけられると、西ローマ軍右翼艦隊も艦首を転じて攻勢に出る。縦に長く伸びて統制を失っていた敵はこの一撃で崩れ、混乱する中に容赦なく砲撃を撃ち込まれることとなった。これだけの体勢となれば指揮官は味方の状況を気にする必要もなく、前線の各個撃破を見守りながら損害を受けた味方の収容と艦艇の修復、補給に乗り出すことも容易になる。そして疲労や物資弾薬すら回復させながら、より包囲は強固なものとなっていくのだ。
「右翼はこれで終わりそうね。左翼は…」
そう呟くヨハンナだが、むしろ当初苦戦していたのはこちらである。目の前で展開される戦闘を見つつ、彼女は味方左翼の優勢を疑いもしなかった。だが、左翼の戦況は彼女の思ったほどに優位に展開しているとは言えなかったかもしれない。
「敵、反撃来ます!」
「やれやれ、元気なことだ」
苦笑して顎に手を当てるカルレット。追いつめられての絶望的な反撃を招来してしまったか、という自嘲がそこにはあり、正直なところ放置すれば無視できない損害が発生する恐れもあるが、迅速に適切な措置さえ施していれば鼠に病気をうつされることもないだろう。カルレットの指示で艦隊は隊列を維持したまま散開、敵の攻勢を受けとめようとする。無秩序な暴走が長く続くことはない、自壊を始めている相手に付き合うことはないのである。
効果はすぐに現れた。派手な砲撃をがむしゃらに放出し突進していたブリタニア軍はすぐにスタミナ切れとなり、的確に飛んでくる西ローマ軍の砲撃に耐えられず一艦、また一艦と撃ち減らされていくこととなった。攻撃は通用しない、弾薬もエネルギーも欠乏、突進すれば敵砲火に突っ込むことになり方向を転ずれば敵の砲火に横腹をさらして撃ち抜かれるだけである。完全に手詰まりになった相手にカルレットは敢えて一斉攻撃に出ることすらせず、敵の失血死を待つこととした。多少時間はかかるが味方の損失はより少なく済み、右翼状勢もどうやら決した様子で敵の急襲を受ける心配もなさそうだった。
こうしてブリタニア動乱は西ローマ遠征軍によって鎮定されることになる。だが戦場にあって完全勝利を目前にもたらされた報告によって、彼らは叛乱総督マグヌス・マクシムスの撤退を許すこととなってしまった。
惑星リヨンにある皇帝グラティアヌスが暗殺されたのである。
>4.ゴート戦役を見る
>地中海英雄伝説の最初に戻る

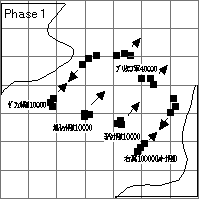 辺境ブリタニア星系は、かつて「国家の父」神君ガイウス・ユリウス・カエサルが制圧してより帝国ローマの属州として長く治められてきた星域である。西ローマ帝国主星ミラノからはガリア星系より更に遠く、航宙の難所を越える必要があることからも星系を統治する総督は現地の有力者によって行われていることが常であった。属州に与えられるものはローマの法を遵守する義務と属州税を治める義務、そしてローマによる星系自治の保証と宙域の安全、統一された通貨等である。帝国とは複数の政体を選ばれた少数の者が指導する体制であり、人民主導の上に公益の代弁者を置くこともできるシステムであったが、同時に公益の保証と平等性に対する不安が容易に不満に転化しやすい欠点も持っていた。この制度下では人民主導の自治国家が帝国の保護を受けるというパラドックスですら成立させうる一方で、帝国に従う利益が保証されなければあえて帝国に従う理由もなくなるのだ。
辺境ブリタニア星系は、かつて「国家の父」神君ガイウス・ユリウス・カエサルが制圧してより帝国ローマの属州として長く治められてきた星域である。西ローマ帝国主星ミラノからはガリア星系より更に遠く、航宙の難所を越える必要があることからも星系を統治する総督は現地の有力者によって行われていることが常であった。属州に与えられるものはローマの法を遵守する義務と属州税を治める義務、そしてローマによる星系自治の保証と宙域の安全、統一された通貨等である。帝国とは複数の政体を選ばれた少数の者が指導する体制であり、人民主導の上に公益の代弁者を置くこともできるシステムであったが、同時に公益の保証と平等性に対する不安が容易に不満に転化しやすい欠点も持っていた。この制度下では人民主導の自治国家が帝国の保護を受けるというパラドックスですら成立させうる一方で、帝国に従う利益が保証されなければあえて帝国に従う理由もなくなるのだ。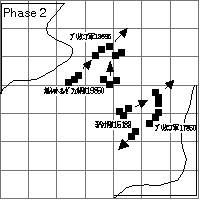 戦況の自然な推移にともなって、左翼側ゼフェルとカルレットの艦隊は前進して敵を押しまくる形となり、ヨハンナは後退する右翼と連携して追撃する敵の右側面を狙い急襲をかける。右翼の損害によって総数ではブリタニア軍に劣ってすらいたのだが、危険宙域を利用して敵を包囲陣形に誘い込むことに成功していた。
戦況の自然な推移にともなって、左翼側ゼフェルとカルレットの艦隊は前進して敵を押しまくる形となり、ヨハンナは後退する右翼と連携して追撃する敵の右側面を狙い急襲をかける。右翼の損害によって総数ではブリタニア軍に劣ってすらいたのだが、危険宙域を利用して敵を包囲陣形に誘い込むことに成功していた。