不定期連載 あの頃、我々は何をやっていたのか
終章・それで、結局我々はなにをやっていたのか(前)
アニメーションの自主活動について振り返ってみたい。
あの頃、というのは、1970年代から80年代、我々の世代がアニメファンとなって、サークルを作ったり、自主上映をやったり、同人誌を発行したり、自主製作アニメを作っていた頃の話である。
我々、というのは、つまり我々の世代、あの頃にファン活動をしていた、中高生から大学生、一部社会人も含んだ、アニメを観るだけではなく、何らかの活動をしていた人たちである。
それは、ファン活動をしていたのだろう、と言われるかもしれないが、そういう風に一言ではすまされない事があの頃には起こっていたのではないかと思える。
この時代のファン活動、というのは、最近(というのは、2000年以降位のここ20年くらいだが)、よく発表されるアニメーションの歴史についての文献・図書においても触れられている事があるが、「この頃からいわゆるアニメーションファンの活動が活発になった」とか、「ファンがセルの収集に夢中になり、盗難事件まで起こった」とか、断片的に触れられているだけで、供給する側の製作現場、興行現場、スポンサーの動き、などについてはそれぞれ関連した動きについて分析されていても、ファンサイドについては、「お金を払って観に来る人たち」「関連グッズを買う人たち」というくくりで処理されているだけであるようだ。
前回までは、あの頃、アニメファンになった私の周辺の事象と、当時の自主制作活動・自主講座活動について書いてきた。今回より完結編。
6.終章・それで、結局我々はなにをやっていたのか」(前)
前回迄は、アニメファン活動が始まったとされる1970年代前半から、ファンの自主活動が衰退に向かっていった1980年代半ば迄に起こった事象を中心に、「自主上映会」「同人誌活動」「自主制作活動」「自主講座活動」などについて、述べて来た。
1970年頃は、中学生頃になったら、「マンガやTVマンガは卒業し、活字の本や、実写のドラマを観るもの」とされていた。ところが、1972年の「海のトリトン」の放送をきっかけに、中学生や高校生で「テレビアニメ」を観ている人が意外と多く居る事が広くこの世代に知れ渡った。「この年(といっても中高生)になって、アニメなんて観ているのは自分くらい」と思っていたアニメファンは「我々はもはや孤独ではない」とばかりに、仲間を求めて各地でサークルを作り、「研究」を始めて研究結果を発表したり、作品への熱い思いを吐露する文章を載せたりした。
この頃は、この世代(中高生)に向けて、その好奇心や知識欲を満たすような商業サービスが十分ではなく、あるのはもっと小さな子ども向けの「TVマガジン」位だったので、満たされない思いを持った彼らは、自分で調べ始めたのである。
ここで、アニメファン活動の始まりとなった「トリトン」ファンクラブ創設当時の状況について、当時の資料を入手・発見したので、再度追ってみる。
消えたトリトンの謎
まず、1972年4月から9月まで、「海のトリトン」放送。そして、翌年始め頃、週刊朝日に小さな記事が載った。

「旗ふりかざして頑張る「トリトン」病患者たち」というタイトルで、「続編を作って放送して」という署名簿を放送局に持ち込んだり、東京で旗を振ってデモ活動をしたり、という行動の紹介と、「ファンクラブ活動は放送中から」「1972年末に最初の再放送」などという記述がみれる。
そして、その後、「SFマガジン 1973年4月号」に、この記事を読んだ熱烈なトリトンファンの投書が載り、同6月号に、この投稿に応える別のトリトンファンの投書が掲載され、翌7月号に4月号に投稿された方の「サークル結成」への呼びかけの投書が載る。
この「SFマガジン」は、当時は毎月購読していたのだが、その後手放していたので、最近、ヤフオクで、「この頃の筈」と、トリトンの放送の終った1972年9月号から、順に1号ずつ買って、手に入れたのである。結構かかった。
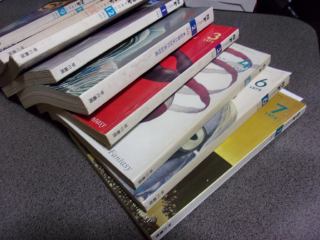
この「投書」が載ったのが「SFマガジン」というのは、当時の状況として「必然」だったのかも知れない。トリトンの視聴者層である中高生が購読する新聞・雑誌で、こういう投書が載りそうなものは、当時「SFマガジン」位だったと思う。ひょっとして、「中三コース」の類いにも載っていたのかもしれないが、「学年誌」でもあるので、他の学年・世代にはアピールしなかっただろう。
さて、記事・投書を調べた結果として判明した意外な事実として、「SFマガジンの投書が、トリトンファンクラブ結成のきっかけではない」「SFマガジンで結成が呼びかけられたのは、「トリトン」という名前のSF・ファンタジーに関する総合研究サークルであって、トリトンファンクラブではない」ということだ。ということは、従来語られて来た「SFマガジンへのファンの投書がきっかけとなって、最初のアニメファンサークルのトリトンファンサークルが出来た」という見方は誤りだったという事である。
考えてみれば、「トリトンの録音スタジオに、ファンが見学に来た」という事は、製作中でないと出来ないから、放送翌年にファンクラブが出来たのでは間に合わないだろう。この方々がどうやって集まったのかについてはわからない。しかし、「海のトリトン」という作品が、当時の若い世代に、それだけの魅力のあった作品であった事は間違いないようである。
なお、以前、「同級生の男子はみんな観ていた。女子については判らない」と書いたが、最近高校美術部のOB展に来られた当時の同級生(という事は、中学当時も同級生)の女性の方に「当時、トリトン観てましたか」と聞いた所、「トリトンは記憶にない。ソランは観ていた」との事でした。考えてみれば、SF少年スーパーヒーローものであるから、元々、男の子向けの番組なので、数からいけば、男子の方がよく観ていて不思議はない。しかし、トリトンについては、「熱狂的な女性ファンが多かった」という事のようなので、普通にテレビ番組として観ていた男子の大半は放送終了後別の番組に興味が移り、残ったファンには女子が多かった、という事なのかもしれない。
スタジオ見学の時代
さて、「トリトン」ファンサークルの結成をきっかけとして、全国で続々とアニメファンサークルが誕生する。なにしろ、「我々はもはや孤独ではない」「この熱い思いを聞いて欲しい」「もっとアニメについて知りたい」というファンは一杯居て、その要望に応える商業的サービス殆ど皆無、という状況なので、アニメファンダムは、戦後焼跡闇市のように、各種サークルが乱立する盛況となった。
この頃のアニメファンの気質として、なにか、「選民意識」のようなものもあった。なにしろ、「アニメーション」というものの価値が判っているのは我々だけだ、という意識が高く、アニメファンを止める事を「社会復帰」と言ったり、アニメファンの人がアニメファンでない人と結婚する事を、「Aさんは「民間」の人と結婚した」と言ったりしていたのである。
また、この頃の熱心なアニメファンは、しばしばアニメスタジオを「見学」と称して訪問していた。当時の雑誌に、「「セル」に群がるアニメファン」として、好みのキャラクターのアニメセル欲しさにスタジオに押し掛けるファンが多い、と書かれていた。それは、そういう人もいたであろう。
当時、研究熱心で、資料だけでは判らない事を調べるのに、現場のスタッフに直に話を聞きに行く、というファンも少なからずいたし、当時すでにアニメファンの憧れの職業になりかけていたアニメーターの「本物」に会いに行った、という人も多かった筈である。私自身は、「スタジオ見学」に行った事はないが、後年、当時、「アニメーターになりたい」と、スタジオを訪問した方の話を伺ったことはあるし、「スタジオ見学の中学生・高校生が来た」という当時プロのアニメーターの話を伺ったこともある。
この、「スタジオ見学」というものも、現在はないようである。80年代以降、しばしばテレビで「アニメスタジオ訪問レポート」等が放送されたり、アニメ情報誌による取材結果が報じられたりしているので、そういう事をする必要が現在はなくなった、という事であろう。
丁度、つい先日、NHKで、「マルコ・ポーロの冒険」というアニメ実写作品の再放送が決まった、という特集番組があり、なにげなく観てみたら、当時のその番組のファンの人たちが出て来た。「マルコ・ポーロの冒険」が放送された当時は、録画用ビデオテープは高価で放送後は再利用されるため、NHKにも残っておらず、映像は元のフィルムのネガが残っていたため再現できたが、音源が発見できなかった所、当時のファンが残していたVHSの録画テープが出て来た、という話である。ところがこの録画テープに一話欠落があったのだが、そこでさらに出て来たのが、べつの方が番組の音だけ録音したカセットテープだった。見ると、懐かしい「ローノイズ」グレードの一番安いテープで、当時の中高生のお小遣いで買えるのはそれ位だったのである。わたしもずいぶん音をとったし、映画館・上映会場のスピーカーの前にラジカセをずらりと並べて音を録音している風景も見た事がある。

(写真は、NHK番組から)
さらに出て来たのが、当時の番組ファンクラブの「同人誌」。手書き文字(当時のワープロは何百万もするものだったのだ)で書かれた多分熱い番組への思い、手描きのファンアートのが伝える主人公への思いが見て取れた。
さらに、当時、アニメーターになった、という人まで出て来た。4年くらいで自分の才能に見切りをつけてあきらめた、との事だったが、結構きれいな絵を描かれる方だった。また、当時は、動画職アニメーターでも、食べて行く事は出来たから、4年間も続けられた、という事でもあると思うし、アニメファンから、アニメーターになった方々のひとりでもあると思う。
このファンの熱狂の勢いは、自主制作や自主講座活動へも向かって行った。なにしろ、「よく判らないが、アニメーションの方向へ向かっていけばなんとかなるだろう」という騎虎の勢いであるから、自主制作は大盛況、自主制作アニメ上映会は満員、自主講座もアマ・プロ・学生生徒が押し掛ける状態となった。
アニメファン、「時代」を動かす
このファンの勢いをうまく使ったのが、「トリトン」のプロデューサーでもあった、「宇宙戦艦ヤマト」制作総指揮・西崎義展氏だったようである。氏の伝記のような本によれば、スタジオ見学にやって来たファンを歓迎して、番組スタッフ(本物)に応対させたり、劇場版長編アニメのポスターを「貼って宣伝してほしい」と渡したり、使用済みのアニメ素材を渡したりしたそうである。効果は抜群だったらしく、劇場版ヤマトの公開前日、「客は来るだろうか」と心配する制作側の面々の前で放送されたのが、「前日夜から、ファンが劇場を取り囲んで行列ができている。」というテレビのニュースだった。
「市場」があるとなれば、「企業」も当然動く。「アニメージュ」を始めとする情報誌の数々が創刊され、アニメファンの知識欲を満たして行った。これら情報誌の当時の投書欄や、ファンサークル・ファンジン紹介コーナーなどには、当時のアニメファンの熱気があふれていた。
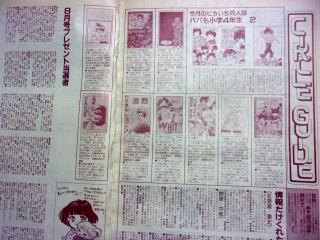
(当時のアニメ情報誌 ファンジン紹介コーナー)
また、ファンの所有欲を満たすビデオソフトなども続々発売された。当時、「アニメものは何を出しても3000本は出る」と言われていた。「アニメのソフトなら何でも買う」という固定ファンが一杯いたということであろう。これは、アニメブーム当初は、まだ良質のアニメーションの供給が不足していて、各地のアニメ上映会には、「アニメでさえあれば何でも観る」というアニメに飢えたファンが大勢詰めかけていたのである。「いま買わなければ、いつまた無くなるかもしれない」という思いも彼らをビデオ販売店に走らせていたのだろう。
こうして、僕らの季節は終った
これらの、企業側のアニメファンへの対応は、アニメファンを満足させる一方で、アニメファンによる自主活動を衰退させていく。なにしろ、「情報誌を買えば、情報は手に入る」のである。また、アニメ情報誌には「投稿」コーナーがあり、番組やキャラクターへの想いや、ファンアートなどが盛んに投稿されていた。わざわざ自主サークルに入って例会に出たり、同人誌を出したり買ったりする必要はなくなっていく。それまで活動していた人はしばらく残っていただろうが、自主サークルに新規に入る人は少なくなっていったはずである。
また、「持っているのに、上映会にわざわざ行く必要はない」のであって、当時某社から出た、アート系アニメーションのラインナップは素晴らしいが、上映会から客を減らす結果になった事は間違いない。
自主制作・自主講座もそうである。70年代後半から80年代初めにかけてのこれらの活動の中では、なんとなく、「アニメーションを作っていれば、なんとかなる」という幻想のようなものがあった。実際、これらの活動の中から、プロの業界に入った方も少なからずいたのであるが、しだいに、「ほとんどの人にとっては、アニメーションとは、実際は、お金を払って楽しむ」ものであって、「アニメーションに関わると収入を得て生活できるようになる」ものではない、という事が明らかになって来たのである。私も、70年代の初めにアニメファンになったが、80年代の初めに大学を卒業して社会人となった。アニメーション自主活動の衰退とともに、自主制作・自主講座に関わる人が減って行った時期である。
こうして、70年代初めに始まった「熱狂的」自主アニメファン活動は、終った。同人誌に替わって、商業情報誌、自主上映会に替わって、ビデオソフトの供給や国際アニメフェスの開催、自主制作・自主講座に替わっては、専門学校・芸術系大学による教育が充実し、「アニメーションを作る側から関わりたい」という若いファンの要望に応えている。
これは、正しい姿である、とは思う。あの70年代の熱狂は、今のような業界側からのサービス提供の欠如により起こったものであり、焼跡闇市や、被災地の仮設店舗のように、復興・正常化が進むと、いつかは無くなるものなのだろう。
では、あの、70年代の熱狂的自主アニメファン活動は、跡形もなく無くなってしまったのであろうか。
(終章・それで、結局我々はなにをやっていたのか(後)に続く)
(1.「トリトン」の頃)
(2.「長編アニメ」を求めて)
(3. ファントーシュとFilm1/24 そして)
(4. PAFと自主アニメの熱狂)
(5. 自主アニメ講座の時代)
(6. 終章・それで、結局我々はなにをやっていたのか(後))
|


