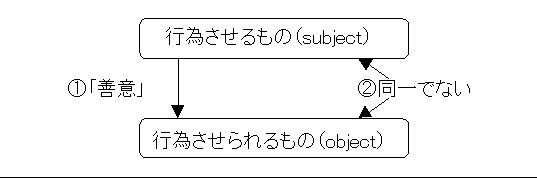
パターナリズムとは、何を意味しているのかについては、これまでも多くの論考が存在していますが、その最大公約数を取れば、次のように図式化できるでしょう。特徴は2点に集約されます。
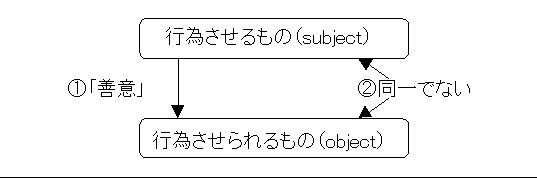
fig.1
「行為させるもの」と、「行為させられるもの」とが存在し、その「させる」ことは「善意」によって裏打ちされ(fig.1内①)、かつその両者は同一でないと見なされる時(fig.1内②)、それをパターナリズムと呼びます。特徴はこの2点、すなわち使役が善意によって裏付けられているということと、使役者と被使役者とが同一でないということで、このどちらが欠けてもパターナリズムとは呼ばれません。
ところで、パターナリズムの対概念であるオートノミー(「自律」という訳語を当てていいかと思います)は、ではどのような特徴を持つのでしょうか。これについても多くの論考が既に存在していますが、上と同様にその最大公約数となる考え方を取れば、次のように図式化できると思われます。やはり特徴は2点に集約されます。
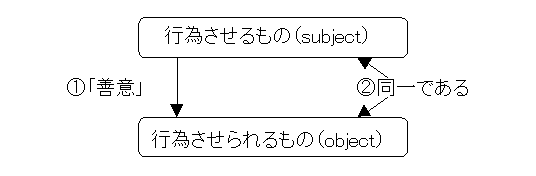
fig.2
「行為させるもの」と、「行為させられるもの」とが存在し、その「させる」ことは「善意」によって裏打ちされ(fig.2内①)、かつその両者は同一であると見なされる時(fig.2内②)、それをオートノミーと呼びます。パターナリズムととてもよく似ていますね。異なっている点は一つだけ、使役者と被使役者とが同一であるということです。このオートノミーの概念はおそらく、カントによって定式化されたsubjectivitat(「主体化」)という概念に由来するものであろうと思われます(自分が自分によって支配されていることをもって、カントは「主体化」と呼びました)。おそらく同一概念と見なしてよいでしょう。
少し判りにくいでしょうか。例を挙げてみましょう。自分に対して、自分を良くしてあげようと考える(=「善意」)こと、及びその考えに基づいて行為することは、オートノミーと呼ばれました。怪我をしたら消毒する(=「自分の」体がそれ以上侵襲を受けないようにする。これは「善意」ですね)、疲れたらゆっくり休む(=「自分の」体を休ませる。使役になっているのが判りますね)、将来のために勉強する、などは、全てこうした形に当てはまりますよね。これらの使役の対象が他の人であった場合に、パターナリズムというのです(相手が怪我をしていたら消毒する、疲れていたらゆっくり休ませる、将来のために勉強させる、となります)。善意の対象が、自分であるか否かが、オートノミーとパターナリズムとの相違点である。この概念は、言われてみればごく日常的なことであろうと思われます。パターナリズムとは元々の語義からすれば、親が子を愛するように面倒を見るという意味で、親が子どもに対して注ぐ愛は基本的には自己愛と同一内容であると言われますから、まさしくこの図式に合致する訳です。
さて、このパターナリズムは、近年医療の領域において、強い批判に晒されています。その背景を簡単に整理しておきます。一言で言うなら、「個人主義」が医療の世界にも波及したことがパターナリズム批判の背景であると言えるかもしれません。患者自身の意志は尊重されるべきであるという考えが、急速に力を持ち、現在その思想的基盤の上に新たな医療システムが構築されようとしている途上であると言っても、分析としてはそう大きく外れてはいないでしょう。
さて、そのことを少し詳しく考えてみます。現在批判に晒されているパターナリズムも、かつては当然なこととされて、批判を受けていなかったのですが、それはどうしてでしょうか。先ほどのパターナリズムの定義を思い出してください。パターナリズムは、使役者と被使役者とが同一でないが故に、パターナリズムだと言われているわけです。かつての医療においては、患者の意志は医療者の意志に一致すると考えられていました。つまり、患者の意志は、単純にその病気を治すことだとされており、その意味では医療者が何をやってもそれが「善意」である限りにおいて患者の意志に背くことには決してならない、そういうものであると考えられていたのです。
患者の意志と、医療者の意志とが、完全に重なり合うと考えられるのであれば、医療者がパターナリスティックに行為したとしても、それがそのまま患者自身の意志でもあるわけですから、それがパターナリズムであるとは見えない。つまり、オートノミーであると見える訳です。ところが現在、ここで隠されていた患者と医療者との間の意志のズレは、目に見える形で現れてきた。そこに個人主義が入りこむ余地があったのです。「個人主義」は、患者が自分の意志を医療者に代理させることを、権利上認めない。この個人主義の波及は、事実問題としては一つには医療者側の「善意」が不完全であったということが、そしてもう一つには患者側が考える「医療者の善意」が、医療者が考える「善意」と必ずしも一致しなくなってきた相対主義の風潮が、背景として存在するといえるでしょう。
繰り返します。医療者側の道徳観念の欠落、そして価値相対化の隆盛、その二つが原理的には医療の領域での「個人主義」を支え、それがパターナリズム批判に繋がっている。ところで面白いのは、この「個人主義」がもたらした別の側面です。それを纏めれば、「患者ではなく、病気を見よ」という考えであると言える。どういうことでしょうか。徐々に議論が込み入ってきたように思います。まず、図式化してみましょう。
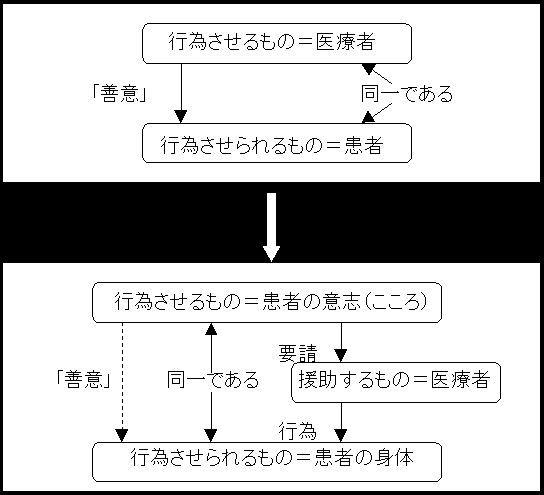
fig.3
患者は自分の中の何ものかが異常であることに気付き、それを「病気」であると認め、それを治療しようとする。ところでここでその病気は、患者自身の一部でもあるわけですが、それを治そうと行為する主体もまた、患者自身であるわけです。このような二重化によって、患者は病気であったとしても、病気ではない自分を「こころ」として保持することが出来る。(少し補足させてください。近代において一般的に流布した考え方である心身二元論とは、自分自身をこのように行為する主体とその対象となる客体に二重化した結果として成立するものと理解すべきもので、その際の主体を意味する「こころ」という語彙もまたそこから考えるべきです。「こころ」はそれゆえ、非常に掴みづらい性質を持っています。)
ただ一方で、患者は必ずしも治療について深い知識や技術があるとは限らない。それ故に、患者本人だけでは成し遂げられない治療を、専門家である医療者に委託するのです。これを治療契約と言いますが、この形式を取ることによって患者は自分自身を主体として保持したまま、治療を行うことが出来るのです。ここで治療対象となるものは患者が治療を要請している客体としての病気だけであって、主体としての患者自身ではありえない。個人主義はいわば権利上、患者自身への治療を拒否する論理であるということが出来るでしょう。
パターナリズム批判が依拠する個人主義の論理は、このように患者自身が医療者にとっての客体となることを拒否するが故に、それが依って立つ医療システムは「病気を対象とする」ものでしかありえない。ここからは、それを超えて患者自身へ治療的介入することは、越権行為であると、そう結論されるべきでしょう。繰り返しになりますが、「医者は病気を治すのではない。患者を治すのだ」という、ヒューマニスティックな主張は、パターナリズム批判と権利上両立できないということ、これは重要なことだと思われます。
単純なパターナリズム批判が陥りやすいのは、果たしてそのことによって自分が何を言おうとしているのか、自覚できていないということなのです。それゆえその主張は往々にして自己矛盾を犯してしまう。だが、たとえ議論を如何に精密に展開したとしても、現在の医療においてパターナリズム批判を貫徹させることは出来ないでしょう。それがよく現れている例として、一つ目に小児医療を取り上げてみましょう。
小児医療においては、患者であるのは子どもであるわけですが、ほとんどの場合その親(もしくは親以外でもその子どもの養育者)との関わりが重要な意味を持ちます。どういうことかと言うと、現在子どもは社会的に権利主体となることが認められていないが故に、子どもに「代理」して行為を決定するのは別の成人(多くの場合はその子どもの親)であって、医療においてもそのことが当てはまるからです。
この「代理」ということは、通常は誰に対しても成立するようなことではないのですが、現在社会的に「家族は一体」であるとする風潮が強く、親と子どもは同一カテゴリーに存在することとされるために、その文字通りのパターナリズムはあまり強烈に意識されない。それだけでなく、家族が同一カテゴリーに存在するということは、家庭内における「代理」はオートノミーとして処理され、家庭外の人間からはその家庭にはアプローチしにくいということを意味しています。
(「自分のことは自分で行う」という個人主義の風潮は、オートノミーである限りにおいて他からの干渉を許さないというロジックを形成したように思います。家庭は勿論「個人」が単位ではないのですが、社会的に「家庭」が一単位として見とめられているが故に、個人におけるオートノミーの類推から家族のオートノミーも認められていて、その家庭が外的な干渉を排除する根拠を形成しています。これがプライベートという空間を形成します。プライベートとはどういうことか、議論を尽くす必要がありますが、それは元々存在していたものではなくて歴史的社会的に形成され、維持されているのだということには、意識的である必要があるでしょう。)
このような「家族」システムの下では、小児医療とはどのようなことを意味しているのでしょうか。繰り返しになりますが、家族は社会的に同一カテゴリーであると認識されていて、かつ子どもは社会的に権利主体であると認められていない。従って、子どもの意志決定は、家庭内の成人(多くの場合はその子どもの親)が代理するという構造をとっているわけです。常に自分の意志決定を、親などの成人に委ねるということは、その意味では子どもは親の所有物であるとさえ言えるでしょう。そうした現状の上に成り立っている小児医療とは、したがって次のような構造をとることになります。
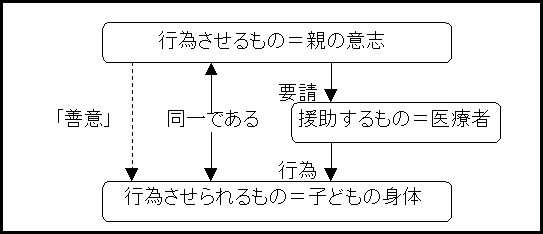
fig.4
子どもは親の所有物であるとされ、その所有者である親が子どもを治療する上で、専門的な技術の提供をを医療者に対して要請する。そしてその要請に応えて医療者は行為する。これは、前に挙げたfig.3の下の図と、全く同一の構造を示していることが理解できるでしょう。そして現在、まさしくこの構造で小児医療は展開されています。唯一、「親が子どもの代理をする」という前提さえ認めるなら、つまりは「家族のオートノミー」という前提を認めるのであれば、前述の議論によってこの図式は全く問題が生じない筈なのです。そう、親が善意の下で子どもに為すことは全て問題がないのだ、とする限りにおいて、この図式は現在の社会的要請に極めて合致したものだと言えるでしょう。ここに、医療者のパターナリズムが入りこむ余地はありえない。
だが、果たしてその前提は正しいのか、と、ここで問うことができる。親が子どもに対して「善意」で行為を為す、と言う場合に、まずその「善意」という語の曖昧さを問うことが出来るし、また、それが「善意」であるか否かを誰がどう判断するのかと問うこともできる。判断など為されているでしょうか。近年話題になっている子どもに対する家庭内虐待は、決して親が子どもに対して常に望ましい存在ではないということを明らかにしているだけではなく、家庭内部の問題に他人が介入することがいかに困難であるかということも示唆しているように思われます。社会的に流布している家庭のイメージは、ある意味親が子どもに対して善意で行動を為すものであるという前提を無批判に植え付けているのではないか。それゆえ実際に親が子どもに対して善意で行為を為しているのかを問わせなくさせているのではないか。まず、そのように疑問符を投げかけることはできるでしょう。
次に、そうしたインパクトのある話題だけでなく、ごくありふれた次元においても、似たような問いを立てることができる。仮に親が善意で行為を為しているからといって、それを受けた子どもが本当にメリットを受けているだろうか。先程よく流布した言い方を借りて、現代は価値観が多様化しつつある時代であると述べました。その意味では、親が良かれと考えていることが、普遍的に良いわけはありえない。親の側の善意が、むしろ子どもを縛り付け、害を為している可能性はないか、我々は問うことができるでしょう。
そう、ここから改めて問わねばなりません。先程の図式は、本当に問題がないのだろうか。家族のオートノミー、言い換えるなら子どもの行為を親が決定してしまう「代理」の構造は、果たして問題がないのであろうか、と。
ここで我々は、非常に大きな問い掛けをしているといわねばなりません。家族のオートノミーという前提を疑ってみる必要性を唱えているわけですから。そしてそのことは、ある意味医療者のパターナリズムを、すなわちここでは家族内部への価値判断的介入を、少なくとも時には必要なものであると、そう主張していることになります。親が自分の子どもを育てる、それについて他人は口出しできないという現状への批判は、従って非常に広い問題圏を抱えていることになります。それら困難な問い掛けについて解決策を出すことが、ここでの目的ではありません。ただし、次のような視点を提出することは、そうした難問を考えていく上で助けになるかもしれません。
子どもが社会的に正式な意味では権利主体とは認められていないということを、社会的に子どもはマイノリティであると整理してみてはどうでしょう。我々は、子どもというマイノリティが持つ権利について、我々は耳を傾ける責任があるのではないか。子どもにも権利があるとした場合、必ずしも親と子どもの両者の権利が両立する場合だけではないでしょう。時に相反することもあるでしょう。しかし、相反した場合、外的に何もしなければ現状では親の権利しか認められようがない。マイノリティである子どもの権利を守るためには、たとえそれがパターナリズムであっても、家庭の外部からの積極的な介入が必要であるのではないだろうか……。
ところがここで、別の問題が浮上してきます。果たしてそこまでして家庭内部に介入する根拠は何であろうか、と。現在医療の問題をお話していますので、その例で言うことにします。先程、「親が子どもに対して善意で行為を為す」という考え方について触れました。そして、善意であるからといって問題がないとは言えないのではないかと述べました。では、親が子どもに対して良くないことをしていると医療者が判断する場合、その医療者が判断する根拠は何でしょうか。また、そこで介入しようとする動機は何でしょうか。やはり、その医療者の「価値観」に基づく「善意」と答えるしかないのではないか。医療者のパターナリズムでしかないのではないか。
問題が少しずつややこしくなってきました。親が子どもに為している「善意」は、「善意」だからといって正しいとは言えないと、ついさっき述べたばかりです。しかしそのように判断している医療者とて、「善意」以上のものを持っているわけではない。言い換えれば、医療者の方も、絶対的な正当性があって判断を下しているわけではない。別の言い方をしましょう。ここには、親や医療者の言葉があっても、子ども自身の言葉は出て来ないのです。
子どもの権利という言い方があります。だが、それを言い出したのが、言葉も知らぬ子どもではなかったことは銘記すべきでしょう。「子どもの権利」もまた、大人によって提出された議論であり、そこに子ども自身の声がどれだけ織り込まれているだろうか、と考えることは、常に必要なことであろうと思われます。今の例で言えば、言葉を語っているのは子どもではなく、親と医療者であって、親と医療者とが子どもを取引材料にして争っているのだと言っても、現状として大きく誤解しているとは言えないのではないでしょうか。
もう一つ別の例を挙げましょう。近年、インターセックスである権利を訴える運動が目に見え始めました。そこで槍玉に挙げられているのは、新生児診察時に、性別を男か女かどちらかに決定してしまうこと、そしてもしそのどちらでもない中間的なものと考えられる場合、治療対象となるという医療の現状です。勿論副腎皮質過形成など、重篤な内分泌疾患の合併が存在する場合には、生命予後に影響がありますからその治療が始められることに異論はないでしょう。ただ、ここで問題となっているのは、社会的にどちらかの性になることを強制されているということなのです。
これは医療者だけの問題ではなくて、親も治療を望む場合が多い。それにもかかわらず、インターセックスであっても良い、そうした権利を守ろうと主張する場合には、親や医療者のパターナリズムに対抗する形での運動とならざるを得ないでしょうが、そしてそれもまたパターナリズムでしかありえまい。たとえ子どもが自分の意志で判断できるまで手術を延期せよという主張であったとしても、絶対的な正当性を持っているとは言えないでしょう。その時点における子どもの声は、決して聞くことが出来ないのだから、やはりこれもまた、子どもを取引材料に争っているに過ぎないのです。
そう、これらで問題となっているのは、複数のパターナリズムであり、それが競い合っているに過ぎないという状況なのです。だが、子ども自身の意志に基づいて、子どもが行為するということを、現状では認めることが出来ない以上、この問題は常に浮上してくるでしょう。そこで単純にパターナリズムを排除することは、決して出来ないでしょう。ここでまず求められているのは、より精緻な分析でしょうが、もはやそれはこの短い論考の範疇を遥かに超えてしまいます。だが、少なくとも問題がどこにあるかについては、明らかになったのではないでしょうか。
医療におけるパターナリズム批判を考えるとき、小児医療以外に困難に突き当たる地点が存在します。それが精神医療です。パターナリズム批判が単純には遂行され得ない分野の二つ目として、精神医療について考えてみることにします。
先程、fig.2で、自分が自分に対して善意で行う行為は、オートノミーであるから批判することは出来ないのだと述べました。それが個人主義であると。だが、他者からそれを「善意による行為」であると認められない場合、突如それはオートノミーではないとされ、他者からの介入が許されるのです。精神医療とは原理的にこの構造を抱えていますが、特に強制入院制度のことを考えると判りやすいと思います。先程、小児医療における医療者のパターナリズムについて触れました。それを、医療者は「親から子どもを守るために」パターナリスティックな行為をすると整理するなら、精神医療では医療者は「本人から本人を守るために」パターナリスティックな行為をするのだと整理できるでしょう。
図式化すれば、次のように表すことができるでしょう。
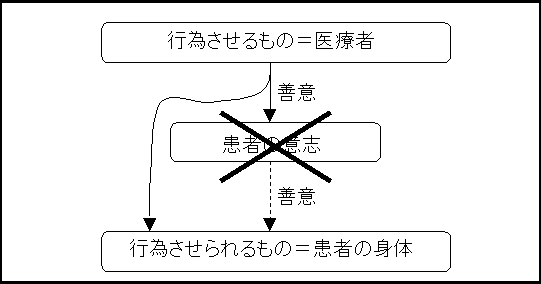
fig.5
ここでやはり考えさせられるのは、「善意」というものがあらかじめ社会的に決められた仕方しか認められないということです。人が自分に対して、ふさわしい仕方で接していない限り、人は社会的に権利主体であると認められることが出来ない。「ふさわしい仕方」とは、「社会的にノーマルな仕方」のことなのです。たとえば未成年者が煙草を吸うのは良くないこと、学校に行かないのは良くないこと、自分の体を傷付けるのは良くないこと、歳相応の興味を持たないのは良くないこと、等など、社会的に「ノーマルである」と見なし得ないものは全て、「ふさわしい仕方」ではないとされ、他者による「善意」の介入が認められる仕掛けになっています。精神病は、その構造が最もドラスティックに現れる場なのです。
時々、こうした精神医療の構造を、精神病者から精神病者以外の人間の身を守るためであるという、社会防衛という観点から根拠付けようとする人がいますが、おそらくそれでは説明がつかないでしょう。例えば、時に精神病者による犯罪が云々されることがありますが、精神分裂病者が犯罪を起こす率は、健常者の犯罪を起こす率と比べて、むしろ低いという統計結果があります。精神病者に対する恐怖感は、時に語られますが、それが自分の身に降りかかるかもしれない身体的な危険のことを言っているのであれば、その根拠は極めて薄いと言うべきでしょう。したがって、精神医療、特に強制入院を「社会秩序の維持のために必要である」と語るのであれば、その「社会秩序」とは何を意味しているのか、明確にしなければならないでしょう。
しかし、おそらく結局は、「精神病者本人のため」以外の理由は挙げようがないのではないか。つまりはそうした社会的なレヴェルにおける「善意」、こう言って良ければ社会に遍在するパターナリズムだけが、現在の精神医療の構造を支えているのではないか。それこそが、重度の精神病者が社会的権利主体になり得ない理論的根拠なのではないのか。人が自分自身に対して為す行為であってさえ、社会的に制約を受けているということ、つまりはオートノミーは社会的にノーマルなあり方でしか認められないのだということは、深く考えるに足る問題でありましょう。
精神医療とはそう考えると、、その目的において、精神病者が再び社会的に「ノーマルな」あり方をとることが出来るようにする社会的装置であると呼んでも良いかと思います。
患者を「ノーマルにする」こと=ノーマライゼーションこそが、精神医療の本質であり、精神医療を根底で支える社会的パターナリズムそのものである。社会に遍在する「善意」とは、では、結局のところ、社会の均一化のために機能しているのでしょうか。医療者がよく口にする「患者のために」という言葉も、結局は患者を他の人と同じように生きていけるようにするためという意味なのでしょうか。そうかもしれません。であるとすれば、医療において倫理とは何を意味するのでしょうか。医療は「多様性」ということについて、どのように答える準備があるのでしょうか。例えば近年、膨大な数の「こころの問題」を扱う書物が出版され続けています。そこに記された膨大な数の「こころのあり方」は、それらを分類し解説していくということによって、実は「こころのあり方」の多様性を守るのではなくて、その均一化をこそ結果しているのではないか。社会的に主体となっている「こころ」の管理こそ、目的としているのではないか。
そこまで考えるとき、社会において無意識的に機能している管理機構の精密さに、驚愕せざるを得ません。個人主義とは、主体が自由に行動することを認める考え方とは、もはや言い切れないでしょう。それはまたかつてとは別の仕方での管理方法なのです。オートノミーという形に隠れて機能している社会的パターナリズム、「こころのノーマライゼーション」に、我々はもっと注意深くあらねばならないでしょう。
もはや、最初に挙げたパターナリズムという問題圏から、非常に遠い所まで思弁を広げてしまったように感じます。だがしかし、医療におけるパターナリズムとは、これだけ広い問題を背景に持っているのだと考えねばなりません。果たしてこのような現状において、パターナリズム批判とは一体何を意味するのでしょう? それによって、我々は何を語ろうとしていることになるのでしょう? だが、この問題こそ、医療とは何であるか、あるいはどのようであるべきか考える上で、不可欠な問い掛けなのです。医療を問い直すとき、この問いを無視することは誰も出来ないでありましょう。
パターナリズム、語られた感すらあるこの問題は、医療の根本に存在する問題を指し示しているのです。その問いはやはり何ごとかを語っている。だが、複雑過ぎて、その困難さは見えないのです。
analyse interminable startpage / preface / profiles / advocacy of gay rights / essays / links / mail