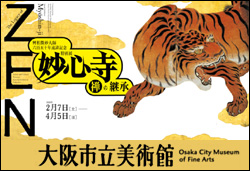
▲展覧会公式サイト |
|
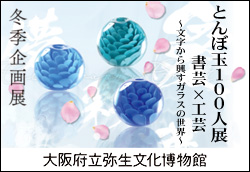
▲展覧会公式サイト |
|
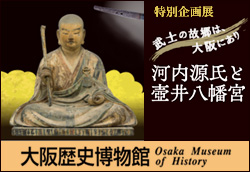
▲展覧会公式サイト |
興祖微妙大師650年遠諱記念
特別展
妙心寺 禅の継承
Myoshin-ji:
The Legacy of Zen
Artistic and Cultural Treasures
from the Myoshin-ji Collection
■2026年
2月7日(土)〜4月5日(日)
※会期中、一部展示替えがあります。
前期:2月7日(土)〜3月8日(日)
後期:3月10日(火)〜4月5日(日)
■大阪市立美術館(天王寺公園内)
Osaka City Museum of Fine Arts
■大阪市天王寺区茶臼山町1-82
■開館時間/9:30〜17:00
※(入館は午後4時30分まで)
■休館日/月曜日(ただし2月23日は開館)、2月24日(火)
※災害などにより、変更となる場合があります。
■入館料:
一 般:2,000円(1,800円)、
高大生:1,300円(1,100円)
小中生:500円(300円)
※( )内は前売および20名以上の団体料金。
※未就学児、障がい者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)は無料(要証明)。障がい者手帳等は、日本の法律に基づき交付されたものに限ります。
※大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。
※本展の当日券で、企画展示もご覧いただけます。
■大阪市立美術館MAP
■美術館公式サイト
主催:大阪市立美術館、臨済宗妙心寺派、日本経済新聞社、テレビ大阪
◎京都の西郊、風光明媚な花園の地に広大な敷地を誇る臨済宗妙心寺派の大本山、妙心寺。大きな山門や仏殿、法堂を中心にして約40もの塔頭寺院が並ぶ境内の光景は圧巻です。かつてこの地は、花園法皇(1297-1348)の離宮御所があり、それを建武4年(1337)に関山慧玄(1277-1360 かんざんえげん 無相大師)を開山として禅寺に改めたのが妙心寺になります。応永6年(1399)には足利義満の不興を買い、寺領を没収されるなどの不遇の時期もありましたが、永享4年(1432)には中興し、さらには戦国武将たちの寄進を受けて多くの塔頭が造営されました。そのため、この時期に描かれた狩野派や長谷川派、海北派などの桃山絵画の宝庫としても著名です。(後略)
(美術館公式サイトより転載)
●展覧会公式サイト→ここから |
|
|
|
令和7年度 冬季企画展
とんぼ玉100人展
書芸×工芸
〜文字から興すガラスの世界〜
■2026年(令和8年)
1月24日(土)〜3月22日(日)
卑弥呼と出会う博物館
■大阪府立弥生文化博物館
Museum of Yayoi Culture
大阪府和泉市池上町4丁目8-27
■TEL.0725-46-2162
■博物館MAP
■博物館公式サイト
■開館時間:9:30〜17:00
(入館は16:30まで)
■休館日:毎週月曜日(ただし2月23日は開館)、2月24日(火)
■入館料:
一般:340円、
65歳以上・高大生:260円
(常設展示室改修中につき、通常の企画展開催時と入館料が異なります)
※(中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名様は無料/20名様以上の団体は団体割引料金)
■主催:大阪府立弥生文化博物館、
とんぼ玉100人展実行委員会(佐竹ガラス株式会社)、日本ランプワーク協会
※展示パネル改修工事のため、下記の期間において展示室の一部を閉室いたします。
[第1展示室]2026年2月3日(火)〜2026年3月末まで
[第2展示室]2026年2月3日(火)〜2026年3月1日(日)まで
◎ガラス工芸の中でも、ひときわ繊細な輝きを放つとんぼ玉。瑞瑞しい感性で表現された現代作家たちの作品は、彩り豊かな珠玉の光を生み出します。 今回は、博物館近隣に所在する高校3校の「書道」部が筆をふるった漢字をテーマとし、全国各地のガラス工芸作家がそこからイメージした世界を表現するコラボレーション企画となっております。ぜひご覧ください。
(博物館公式サイトより転載)
●展覧会公式HP→ここから |
|
|
|
特別企画展
武士の故郷は、大阪にあり
河内源氏と壺井八幡宮
■2026年
1月16日(金)〜3月15日(日)
■大阪歴史博物館
Osaka Museum of History
大阪市中央区大手前4-1-32
■TEL.06-6946-5728
■会場:6階
特別展示室
■休館日:火曜日
■開館時間:9:30〜17:00
※入館は閉館30分前まで
■観覧料:常設展示観覧券でご覧いただけます。
・大 人600円(540円)、
・高校生・大学生400円(360円)
※( )内は20名以上の団体割引料金
※中学生以下・大阪市内在住の65歳以上(要証明証提示)の方、障がい者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料
※高校生・大学生チケットの購入時は証明証をご提示ください。
※大阪市内在住の65歳以上の方は、ツルマークの健康手帳、敬老優待乗車券、運転免許証など証明できるものをご提示ください。
■大阪歴史博物館公式HP
■大阪歴史博物館アクセスマップ
■主催:大阪歴史博物館
■協力:壺井八幡宮
◎「八幡太郎(はちまんたろう)」源義家(みなもとのよしいえ)や、源頼朝(よりとも)・義経(よしつね)兄弟、足利尊氏(あしかがたかうじ)を輩出した「河内源氏」。そのはじまりは、義家の祖父・源頼信(よりのぶ)が河内国壺井(現大阪府羽曳野市壺井)の地に館を建てたことに遡ります。頼信の子・頼義(よりよし)が石清水(いわしみず)八幡宮を勧請して建立した壺井八幡宮は、源氏の守護神として長らく武家の崇敬を受け、現在に至っています。
本展では、「木造僧形八幡神及諸神坐像」「黒韋威胴丸(壺袖付)」(いずれも重要文化財)、「太刀 銘安綱(号 天光丸)」(重要美術品)をはじめとする壺井八幡宮の社宝と、河内源氏に関する館蔵資料等をあわせて展示し、「武士の世」の礎を築いた河内源氏の活躍と伝承、そしてその源流が大阪にあったことをご紹介します。
(公式サイトより転載)
◎展示資料数:約80点
●展覧会公式サイト→ここから |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
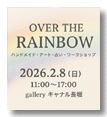
▲クリックで詳細 |
■Gallery
キャナル長堀
▲会場案内頁とリンク
■大阪市中央区東心斎橋1-11-14
TEL.06-6251-6198
■大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅、堺筋線・長堀鶴見緑地線 長堀橋駅
■クリスタ長堀南6番出口前
■開廊時間:
11:00〜17:00
■ギャラリーMAP |
|
 |

▲クリックで詳細 |
■Gallery
キャナル長堀
▲会場案内頁とリンク
■大阪市中央区東心斎橋1-11-14
TEL.06-6251-6198
■大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅、堺筋線・長堀鶴見緑地線 長堀橋駅
■クリスタ長堀南6番出口前
■開廊時間:
11:00〜17:00
■ギャラリーMAP |
|
 |

▲クリックで詳細 |
■Gallery
キャナル長堀
▲会場案内頁とリンク
■大阪市中央区東心斎橋1-11-14
TEL.06-6251-6198
■大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅、堺筋線・長堀鶴見緑地線 長堀橋駅
■クリスタ長堀南6番出口前
■開廊時間:
11:00〜17:00
■ギャラリーMAP |
|
OVER THE
RAINBOW
・ハンドメイド・・アート
・占い・・ワークショップ
主催:橋元カオ里
■2026年
2月8日(日)
※終了しました。
入場無料/どなたでもご参加OK!
●心ときめくハンドメイド作品
●自分だけのアート体験
●癒しの占いブース
◎カラフルでわくわくする一日をあなたに。雨上がりの虹のように、たくさんの出合いが待っています。
●もっと詳しく→ここから |
|
|
|
te to te
つながる マルシェ
貴女のお気に入りを
見つけに来ませんか?
■2026年
3月29日(日)
入場無料/どなたでもご参加OK!
●明日見ひなた
●あめの宇受媛
●北城彩華
●Megmi
Nishi
●moko-house
●LAVANDE
●crystal
kaori
●もっと詳しく→ここから |
|
|
|
te to te
つながる マルシェ
貴女のお気に入りを
見つけに来ませんか?
■2026年
3月29日(日)
入場無料/どなたでもご参加OK!
●明日見ひなた
●あめの宇受媛
●北城彩華
●Megmi
Nishi
●moko-house
●LAVANDE
●crystal
kaori
●もっと詳しく→ここから |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|