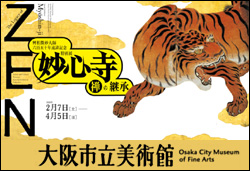
▲展覧会公式サイト |
 |
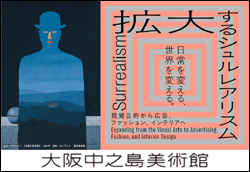
▲展覧会公式サイト |
 |
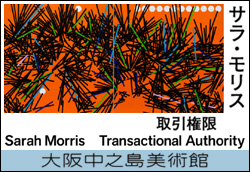
▲展覧会公式サイト |
興祖微妙大師650年遠諱記念
特別展
妙心寺 禅の継承
Myoshin-ji:
The Legacy of Zen
Artistic and Cultural Treasures
from the Myoshin-ji Collection
■2026年
2月7日(土)〜4月5日(日)
※会期中、一部展示替えがあります。
前期:2月7日(土)〜3月8日(日)
後期:3月10日(火)〜4月5日(日)
■大阪市立美術館(天王寺公園内)
Osaka City Museum of Fine Arts
■大阪市天王寺区茶臼山町1-82
■開館時間/9:30〜17:00
※(入館は午後4時30分まで)
■休館日/月曜日(ただし2月23日は開館)、2月24日(火)
※災害などにより、変更となる場合があります。
■入館料:
一 般:2,000円(1,800円)、
高大生:1,300円(1,100円)
小中生:500円(300円)
※( )内は前売および20名以上の団体料金。
※未就学児、障がい者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)は無料(要証明)。障がい者手帳等は、日本の法律に基づき交付されたものに限ります。
※大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。
※本展の当日券で、企画展示もご覧いただけます。
■大阪市立美術館MAP
■美術館公式サイト
主催:大阪市立美術館、臨済宗妙心寺派、日本経済新聞社、テレビ大阪
◎京都の西郊、風光明媚な花園の地に広大な敷地を誇る臨済宗妙心寺派の大本山、妙心寺。大きな山門や仏殿、法堂を中心にして約40もの塔頭寺院が並ぶ境内の光景は圧巻です。かつてこの地は、花園法皇(1297-1348)の離宮御所があり、それを建武4年(1337)に関山慧玄(1277-1360 かんざんえげん 無相大師)を開山として禅寺に改めたのが妙心寺になります。応永6年(1399)には足利義満の不興を買い、寺領を没収されるなどの不遇の時期もありましたが、永享4年(1432)には中興し、さらには戦国武将たちの寄進を受けて多くの塔頭が造営されました。そのため、この時期に描かれた狩野派や長谷川派、海北派などの桃山絵画の宝庫としても著名です。(後略)
(美術館公式サイトより転載)
●展覧会公式サイト→ここから |
|
|
|
Surrealism
拡大するシュルレアリスム
視覚芸術から広告、ファッション、インテリアへ
Expanding from the Visual
Arts to Advertising, Fashion, and Interior Design
■2025年12月13日(土)〜
2026年3月8日(日)
前期:12月13日(土)〜1月25日(日)
後期:1月27日(火)〜3月8日(日)
■大阪中之島美術館
会場:4階展示室
NAKANOSHIMA MUSEUM OF ART,OSAKA
■大阪市北区中之島4-3-1
■開場時間:10:00〜17:00
(入場は16:30まで)
■休館日:月曜日、12/30(火)、12/31(水)、1/1(木・祝)、1/13(火)、2/24(火)
*1/12(月・祝)、2/23(月・祝)は開館
■観覧料:消費税込み
一 般:1,800円(1,600円)
高大生:1,500円(1,300円)
小中生:500円(300円)
※( )内は20名以上の団体料金
※当館メンバーシップ会員の無料鑑賞/会員割引 対象
※障がい者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)は当日料金の半額(要証明)。ご来館当日、2階のチケットカウンターにてお申し出ください。(事前予約不要)
※一般以外の料金でご利用される方は証明できるものを当日ご提示ください。
※本展は、大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。
※災害などにより臨時で休館となる場合があります。
※お問い合わせ:大阪市総合コールセンター(なにわコール) 06-4301-7285
受付時間/8:00〜21:00(年中無休)
■大阪中之島美術館MAP
■美術館公式サイト
■主催:大阪中之島美術館
■特別協力:横浜美術館
◎(前略)
シュルレアリスムが芸術のみならず社会全体に影響をもたらしたことは今日においてもなお特筆に値するものです。シュルレアリスムの発生から約100年を経た今、本展覧会は日本国内に所蔵されている多様なジャンルの優品を一堂に会し、シュルレアリスムの本質に迫ります。圧倒的存在感をもって視覚芸術、ひいては社会全体へと拡大したシュルレアリスムを、表現の媒体をキーワードとして解体し、シュルレアリスム像の再構築をめざします。
(美術館公式サイトより転載)
●美術館公式サイト→ここから |
|
|
|
サラ・モリス
取引権限
Sarah Morris
Transactional Authority
日本初、大規模個展
■2026年
1月31日(土)〜4月5日(日)
■大阪中之島美術館
会場:5階展示室
NAKANOSHIMA MUSEUM OF ART,OSAKA
■大阪市北区中之島4-3-1
■開場時間:10:00〜17:00
(入場は16:30まで)
■休館日:月曜日、2/24(火)
*2/23(月・祝)は開館
■観覧料:消費税込み
一 般:1,800円(1,600円)
高大生:1,200円(1,000円)
中学生以下:無料
※( )内は20名以上の団体料金
※当館メンバーシップ会員の無料鑑賞/会員割引 対象
※障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)をお持ちの方(介護者1名を含む)は当日料金の半額(要証明)。ご来館当日、2階のチケットカウンターにてお買い求めください。(事前予約不要)
※一般以外の料金でご利用される方は証明できるものを当日ご提示ください。
※本展は、大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。
※災害などにより臨時で休館となる場合があります。
※お問い合わせ:大阪市総合コールセンター(なにわコール) 06-4301-7285
受付時間/8:00〜21:00(年中無休)
■大阪中之島美術館MAP
■美術館公式サイト
■主催:大阪中之島美術館
◎サラ・モリス 略歴:
1967年英国出身、現在はニューヨークを拠点に活動。図式的なグリッドを用いた幾何学的な抽象絵画で知られ、国際的に高い評価を受ける。様々な形状を使い視覚的構造物を生み出すモリスが扱うテーマは、多国籍企業や輸送ネットワーク、地図、GPS技術、月の満ち欠けの周期など多岐にわたる。絵画と並行して制作している映像作品は、多層的かつ断片的なナラティブを通した心理地理学的探求であり、変動し続ける都市の性質も探っている。モリスは自身と鑑賞者を映像の中に投じ、社会の階層性を映し出している。
◎主要作品の絵画約40点、映像作品17点を展示
本展では、モリスの初期の作品から最近の作品まで約40点の重要な絵画を展示し、絵画と並行して制作された映像作品も、新作含めてすべて上映します。モリスの創作活動を時系列で総覧する本展では、変わり続ける世界の大都市に対するモリスの関心がうかがえます。都市において複雑に絡み合う文化・政治・経済構造が、美しさや緊張感、不安定さとともに、絵画と映像に表れています。
(美術館公式サイトより転載)
●美術館公式サイト→ここから |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
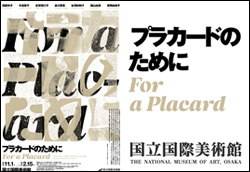
▲展覧会公式サイト |
 |
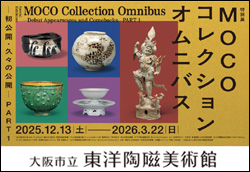
▲展覧会公式サイト |
 |
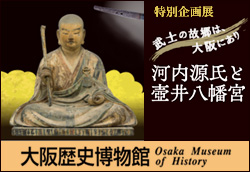
▲展覧会公式サイト |
特別展
プラカードのために
For a Placard
…………………………………
同時開催
「コレクション2」
■2025年 11月1日(土)
〜2026年 2月15日(日)
■国立国際美術館(大阪・中之島)
B3階展示室
THE NATIONAL MUSEUM OF ART. OSAKA
大阪市北区中之島4-2-55
■休館日:月曜日(ただし11月3日、11月24日、1月12日は開館)、11月4日、11月25日、1月13日、年末年始(12月28日-1月5日)
■開館時間:10:00〜17:00
(金曜は20:00まで)
(入場は閉館の30分前まで)
■観覧料:
一般:1,500円(1,300円)
大学生:900円(800円)
※( )内は20名以上の団体料金および夜間割引料金(対象時間:金曜
17:00〜 20:00)
※高校生以下・18歳未満無料(要証明)
※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料(要証明)
※本料金で同時開催の「コレクション2」もご覧いただけます
■美術館公式サイト
■主催:国立国際美術館
◎美術家・田部光子(1933-2024)は1961年に記した短い文章において「大衆のエネルギーを受け止められるだけのプラカードを作」り、その「たった一枚のプラカードの誕生によって」社会を変える可能性を語っています。過酷な現実や社会に対する抵抗の意思や行為、そのなかに田部が見出した希望は、同年発表された作品《プラカード》に結実しました。「プラカードの為に」と題されたこの文章は、作品が生まれるまでの思考の過程を語ったものであると同時に、社会の動きを意識し活動するひとりの美術家の宣言としても読むことができます。「たった一枚のプラカード」とは、行き場のない声をすくいあげ、解放の出発点となるような、生きた表現の象徴でもあるのです。
田部の言葉と作品を出発点とする本展覧会は、それぞれの生活に根ざしながら生きることと尊厳について考察してきた、田部を含む7名の作品で構成します。各作家は、これまで社会に覆い隠されてきた経験や心情に目を凝らし、あるいは自ら実践することで、既存の制度や構造に問いを投げかけます。彼女・彼らの作品を通じて、私たちを取り巻く社会や歴史を見つめ直し、抵抗の方法を探りながら、表現することの意味に立ち返ります。
出品予定作家:田部光子、牛島智子、志賀理江子、金川晋吾、谷澤紗和子、飯山由貴、笹岡由梨子
(美術館公式サイトより転載)
●展覧会公式HP→ここから |
|
|
|
特別展
MOCOコレクション
オムニバス
−初公開・久々の公開−PART1
MOCO Collection Omnibus
Debut Appearances and Comebacks-PART1
■2025年12月13日(土)〜
2026年3月22日(日)
■大阪市立東洋陶磁美術館
THE MUSEUM OF ORIENTAL CERAMICS,
OSAKA
■問い合わせ:
電話:06-6223-0055
■美術館公式サイト
■美術館マップ
■〒530-0005
大阪市北区中之島1-1-26
■開館時間:9:30〜17:00
(入館は16:30まで)
■休館日:月曜日、2025年12/28(日)〜2026年1/5(月)、1/13(火)、2/24(火)※但し、祝日の1/12(月)、2/23(月)は開館
■入館料:
一般1,600円(1,400円)、
高校生・大学生800円(700円)
( )内は20名以上の団体料金
※中学生以下、障がい者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)、大阪市在住の65歳以上の方(要証明)は無料
※上記の料金で館内の展示すべてをご覧いただけます。
■主催:大阪市立東洋陶磁美術館
■共催:毎日新聞社
◎当館は、旧安宅産業株式会社が収集した世界屈指の中国・韓国陶磁コレクションである、「安宅コレクション」965件を住友グループから寄贈されたことを記念して、1982年11月に開館しました。また、1996年から1998年にかけて、李秉昌(イ・ビョンチャン)博士から韓国陶磁を中心とするコレクション351件の寄贈を受けました。実は、これらの核となるコレクション以外にも、開館以来40年余の間に、篤志家(とくしか)の方々から様々なコレクションが当館に寄贈され、収蔵品の質と量が拡充されてきました。
本展では、ほとんどが初公開となる茶道具を中心とした「松惠(しょうけい)コレクション」や、久々の公開となる中国陶磁の酒器を中心とした「入江正信(いりえまさのぶ)コレクション」、中国陶磁を中心とした「白檮廬(はくとうろ)コレクション」、人物・動物・建物をかたどった墓に副葬する中国陶磁を中心とした「海野信義(うみののぶよし)コレクション」、韓国陶磁の魅力を日本に紹介した陶磁研究者の浅川伯教(あさかわのりたか)旧蔵作品や関連資料による「鈴木正男(すずきまさお)コレクション」を、オムニバス方式で紹介します。
(美術館公式サイトより転載)
●美術館公式HP→ここから |
|
|
|
特別企画展
武士の故郷は、大阪にあり
河内源氏と壺井八幡宮
■2026年
1月16日(金)〜3月15日(日)
■大阪歴史博物館
Osaka Museum of History
大阪市中央区大手前4-1-32
■TEL.06-6946-5728
■会場:6階
特別展示室
■休館日:火曜日
■開館時間:9:30〜17:00
※入館は閉館30分前まで
■観覧料:常設展示観覧券でご覧いただけます。
・大 人600円(540円)、
・高校生・大学生400円(360円)
※( )内は20名以上の団体割引料金
※中学生以下・大阪市内在住の65歳以上(要証明証提示)の方、障がい者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料
※高校生・大学生チケットの購入時は証明証をご提示ください。
※大阪市内在住の65歳以上の方は、ツルマークの健康手帳、敬老優待乗車券、運転免許証など証明できるものをご提示ください。
■大阪歴史博物館公式HP
■大阪歴史博物館アクセスマップ
■主催:大阪歴史博物館
■協力:壺井八幡宮
◎「八幡太郎(はちまんたろう)」源義家(みなもとのよしいえ)や、源頼朝(よりとも)・義経(よしつね)兄弟、足利尊氏(あしかがたかうじ)を輩出した「河内源氏」。そのはじまりは、義家の祖父・源頼信(よりのぶ)が河内国壺井(現大阪府羽曳野市壺井)の地に館を建てたことに遡ります。頼信の子・頼義(よりよし)が石清水(いわしみず)八幡宮を勧請して建立した壺井八幡宮は、源氏の守護神として長らく武家の崇敬を受け、現在に至っています。
本展では、「木造僧形八幡神及諸神坐像」「黒韋威胴丸(壺袖付)」(いずれも重要文化財)、「太刀 銘安綱(号 天光丸)」(重要美術品)をはじめとする壺井八幡宮の社宝と、河内源氏に関する館蔵資料等をあわせて展示し、「武士の世」の礎を築いた河内源氏の活躍と伝承、そしてその源流が大阪にあったことをご紹介します。
(公式サイトより転載)
◎展示資料数:約80点
●展覧会公式サイト→ここから |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |

▲展覧会公式サイト |
 |

▲展覧会公式サイト |
 |
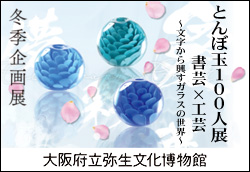
▲展覧会公式サイト |
特別展
日本画
アヴァンギャルド
KYOTO 1948-1970
NIHONGA
AVANT-GARDE:
KYOTO 1948-1970
■2026年
2月7日(土)〜5月6日(水・休)
※会期中、一部に展示替えあり。
前期:2月7日(土)〜3月1日(日)
中期:3月3日(火)〜4月5日(日)
後期:4月7日(火)〜5月6日(水・休)
■京都市京セラ美術館(岡崎公園内)
会場[新館 東山キューブ]
Kyoto City KYOCERA Museum
of Art
■TEL.075-771-4334
■〒606-8344
京都市左京区岡崎円勝寺町124
■開館時間=10:00 〜18:00
(最終入場は17:30まで)
■休館日=月曜日(祝・休日の場合は開館)
■観覧料=
一般:1,800(1,600)円
大学・専門学校生・高校生:1,300(1,100)円
※中学生以下無料
※価格はすべて税込
※すべて前売価格の設定はありません
※( )内は20名以上の団体料金
※障害者手帳等をご提示の方は本人及び介護者1名無料(障害者手帳等確認できるものをご持参ください)
※学生料金でご入場の方は学生証をご提示ください
■美術館公式サイト
■主催=京都市、関西テレビ放送、京都新聞
◎戦後、伝統と革新のはざまで揺れる日本画界において、京都では画家たちによる前衛的な試みが始まりました。本展では、1940年代以降に結成された3つの美術団体である創造美術、パンリアル美術協会、ケラ美術協会を中心に、日本画の枠を問い直し、新たな表現を模索した気鋭の画家とその軌跡を紹介します。
本展を通じて、京都画壇の批評精神と創造性に着目し、現代へと連なる日本画のもうひとつの系譜を紐解きます。本展ではこの戦後京都で生まれた日本画の反骨的創造運動を「日本画アヴァンギャルド」※として総称し紹介します。
※「アヴァンギャルド」という言葉は、フランスにおいて19世紀半ばに文化芸術的な用法として広まり、急進的な芸術家たちを指すようになったものです。その後、過去の伝統を見直し、革新的なものを目指す運動全般を広く示すようになりました。
(美術館公式サイトより転載)
●展覧会公式HP→ここから |
|
|
|
セカイノコトワリ
私たちの時代の美術
#Where Do We Stand ?-
Art in Our Time
■2025年12月20日(土)〜
2026年3月8日(日)
※日時予約制ではございません。
■京都国立近代美術館(岡崎公園内)
The National Museum of Modern Art, Kyoto
■TEL.075-761-4111
■〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町
■開館時間=10:00 〜18:00
◎金曜日は20:00まで開館
※入館は閉館の30分前まで
■休館日=月曜日(ただし、1月12日(月・祝)、2月23日(月・祝)は開館)、 12月30日(火)〜1月3日(土)、1月13日(火)、2月24日(火)
■観覧料:
一 般:1,500円(1,300円)
大学生:700円(600円)
※()内は前売と20名以上の団体及び夜間割引(金曜午後6時以降)
※高校生以下・18歳未満は無料*。
※心身に障がいのある方と付添者1名は無料*。
※ひとり親家庭の世帯員の方は無料*。
*入館の際に学生証、年齢の確認ができるもの、障害者手帳等をご提示ください。
※本料金でコレクション展もご覧いただけます。
■美術館MAP
■美術館公式サイト
■主催=京都国立近代美術館、
メルコグループ
◎本展では、世界のグローバル化が進み、日本人作家の海外での発表の機会が増えた1990年代から現在までの美術表現を中心に、20名の国内作家による作品を紹介します。世界と人間との関係をめぐるアーティストたちの考察や実践を、「アイデンティティ」「身体」「歴史」「グローバル化社会」といったキーワードを手がかりに読み解き、展覧会での鑑賞者の作品体験が、あたかも航海上の潮流やうねり、未知の島との遭遇などを記録した「海図」のような物語として描き出されることを試みます。
本展のタイトル「セカイノコトワリ」には、外来語や新しい概念をカタカナで表記するように、未知のものに対して安易な解釈や意味づけを保留しつつ自らの思考を更新していく態度という意味が込められています。「私たちの現在地はどこ?/Where
Do We Stand?」という問いに対する答えは無数にあり、海に浮かぶ小舟のように常に揺れ動いているとも言えます。それでも、他者と共有可能な拠りどころを探しながら生きていくために、本展が鑑賞者それぞれのセカイノコトワリを見つける機会となれば幸いです。
(近代美術館公式サイトより転載)
●展覧会公式HP→ここから |
|
|
|
令和7年度 冬季企画展
とんぼ玉100人展
書芸×工芸
〜文字から興すガラスの世界〜
■2026年(令和8年)
1月24日(土)〜3月22日(日)
卑弥呼と出会う博物館
■大阪府立弥生文化博物館
Museum of Yayoi Culture
大阪府和泉市池上町4丁目8-27
■TEL.0725-46-2162
■博物館MAP
■博物館公式サイト
■開館時間:9:30〜17:00
(入館は16:30まで)
■休館日:毎週月曜日(ただし2月23日は開館)、2月24日(火)
■入館料:
一般:340円、
65歳以上・高大生:260円
(常設展示室改修中につき、通常の企画展開催時と入館料が異なります)
※(中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名様は無料/20名様以上の団体は団体割引料金)
■主催:大阪府立弥生文化博物館、
とんぼ玉100人展実行委員会(佐竹ガラス株式会社)、日本ランプワーク協会
※展示パネル改修工事のため、下記の期間において展示室の一部を閉室いたします。
[第1展示室]2026年2月3日(火)〜2026年3月末まで
[第2展示室]2026年2月3日(火)〜2026年3月1日(日)まで
◎ガラス工芸の中でも、ひときわ繊細な輝きを放つとんぼ玉。瑞瑞しい感性で表現された現代作家たちの作品は、彩り豊かな珠玉の光を生み出します。 今回は、博物館近隣に所在する高校3校の「書道」部が筆をふるった漢字をテーマとし、全国各地のガラス工芸作家がそこからイメージした世界を表現するコラボレーション企画となっております。ぜひご覧ください。
(博物館公式サイトより転載)
●展覧会公式HP→ここから |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|