|
|
| -- |
|
|
 |
▲重要文化財「関が原合戦図屏風(右隻)」八曲一双、桃山時代(17世紀)、大阪歴史博物館蔵
慶長5年(1600)、徳川家康の東軍と石田三成の西軍の天下分け目の合戦を、前日の両軍の動きと当日の戦闘に分けて一双に描く。合戦図でも最大級の画面に迫真的な戦闘場面が展開する戦勝記念の意味合いの濃い歴史画で、弘前津軽藩に伝来したため「津軽屏風」と称される。
※展示期間:(右隻)10/30(火)〜11/25(日)(左隻)11/27(火)〜12/16(日) |
|
|
|
 |
▲上:「関が原合戦図屏風(右隻)」
大阪歴史博物館蔵 |
|
|
|
|
 |
| ▲上:「関が原合戦図屏風」右隻部分 大阪歴史博物館蔵 |
|
|
|
| 第4章:近世屏風の百花繚乱 |
| ■「桃山百双」という言葉が象徴するように、大城郭や大寺院の建築が相次いだ桃山時代には、襖絵などの障壁画と並んで、絢爛豪華な金屏風も多数制作されました。《豊国祭礼図屏風》の桟敷席の背後には、後世、人気を博し繰り返し描かれた「柳橋水車図」「武蔵野図」といったテーマ性も盛り込まれています。やがて江戸時代になると、狩野派にとどまらない、様々な流派の画家たちによって六曲一双という大画面を存分にいかす工夫や試みが重ねられ、屏風は豊かな展開をみせるとともに、屏風絵は幅広い階層に愛好されました。 |
|
|
|
|
|
|
 |
▲「四天王寺住吉大社図屏風
」六曲一双 江戸時代(17世紀)東京・サントリー美術館蔵
※展示期間:10/30(火)〜11/18(日) |
|
|
|
| ■摂津四天王寺と住吉大社を一対に描く屏風。
本図の特徴は、四天王寺を描写する視点が、通常は南側からうかがうことが多い中、西側から描く点で、南大門、五重塔、金堂、講堂の主要伽藍が一直線上に整然と配置される。住吉大社も、特に祭礼の様子は描かず、もっぱら参詣の人びとの風俗に関心が向いている。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 左:「四天王寺住吉大社図屏風 」六曲一双(右隻/住吉大社の図)江戸時代(17世紀)東京・サントリー美術館蔵 |
|
|
|
|
右:「鶴図屏風(右隻)」
尾形光琳筆 四曲一隻
江戸時代(17世紀)
メトロポリタン美術館蔵
■尾形光琳の息子寿一郎の養子先であった小西家に伝来した光琳関係資料。鶴を主題として六曲一双屏風の画稿。画面中央に水紋を描く渓流を、右岸に松の大樹、左岸に竹林を配置し、両岸に鶴がたたずむ。俵屋宗達に私淑する以前の、狩野派や伝統なやまと絵などを学習していた頃の、光琳の比較的若描きと判断される。
※展示期間:
(右隻)10/30(火)〜11/25(日)
(左隻)11/27(火)〜12/16(日) |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
▲上:秋草浜松図御簾(あきくさはままつずみす)
屏風(部分)
六曲一双 江戸時代 個人蔵 |
|
|
左:秋草浜松図御簾(あきくさはままつずみす) 屏風 六曲一双 江戸時代 個人蔵
■部屋の間仕切りや遮蔽(しゃへい)、室内装飾と、屏風は日常生活のさまざまな場面で使われてきた。「御簾屏風」あるいは「翠簾屏風(すいれんびょうぶ)」は、各扇中央部をくり抜き、そこに御簾をはめ込んだもの。風を通すことから、夏用の屏風として用いられた。また欧米の貴紳たちへの贈答の品の中にも、しばしば「翆簾屏風」の名を見出す。
※展示期間:
10/30(火)〜11/18(日)
(裏面・浜松図)
11/20(火)〜12/2(日) |
|
|
|
|
|
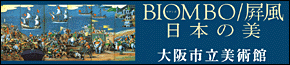 |
|
▲展覧会の詳細は上の画面をクリック。 |
|
|
| ■特別展「BIOMBO(ビオンボ)/屏風
日本の美」 −日本人の誇り 黄金の文化遺産− |
| 会場:大阪市立美術館 会期:2007年10月30日[火]〜12月16日[日] |
| ■ストリート・アートナビ取材:展覧会シーン Top-Page/Page-1/Page-2/Page-3/Page-4/Page-5/Page-6 |
| ■取材日:2007年10月29日 掲載:11月23日 ART SCENE/Street Artnavi |
| ■取材・写真・Webデザイン:ストリート・アートナビ 中田耕志 |
| ※上記の説明、写真キャプションは展覧会報道資料、展覧会図録、同展説明会を参考にしました。 |
 |
| New▲展覧会シーン/2005年〜2008年 画面をクリック |
|
|
|
|
|